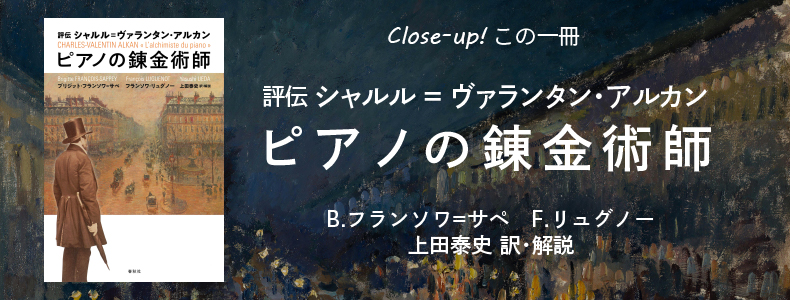異端児ならざるアルカン かげはら史帆(B. フランソワ=サペ、F. リュグノー『評伝 シャルル=ヴァランタン・アルカン ピアノの錬金術師』上田泰史 訳・解説)
アルカンは異端児か?
シャルル=ヴァランタン・アルカン(1813-1888)という音楽家に対して、「異端児」「奇人」というイメージを持つ人は多いだろう。「ピアノの錬金術師」というその怪異な渾名。天才的なピアノの腕前を持ちながら、華やかな社交界を厭い、隠遁生活を送ったという伝説。世間から背を向けたかのような後ろ姿の写真。「鉄道」「イソップの饗宴」「悪魔のスケルツォ」などの──タイトルからしてマニアックな匂いが漂う作品群と、呆れるほどの超絶技巧ぶり。今日「アルカン弾き」として知られるマルカンドレ・アムランや森下唯の個性的な立ち位置も、アルカンの魔性を現代に召喚する効果を生みだしている。
無名とも有名ともいえない絶妙な知名度と、フレデリック・ショパンやフランツ・リストと同世代であるという不幸な偶然が、彼の存在をより「わかりやすく」した。個性的すぎたゆえに王道から外れた、1810年代生まれのロマン派ピアニズムの徒花の1人──シャルル=ヴァランタン・アルカン。決して誤った理解ではない。ただ、その手のアルカン像が、この音楽家の別の側面を見えにくくしてきたのも確かだろう。そんな積年のイメージを刷新してくれるのが、ブリジット・フランソワ=サペとフランソワ・リュグノーの共著による『評伝 シャルル=ヴァランタン・アルカン ピアノの錬金術師』(上田泰史訳、春秋社、2022年[原著: 2013年])である。
ニュー・スタンダードとしての「音楽院出身者」
本書を読んで筆者がもっとも驚いたのは、アルカンが人生の初期からアカデミアの中で生き、その世界でアイデンティティを形成した人であったという点だ。平たくいえば、彼は「一流の音楽学校で一流の師から薫陶を受け一流になった」タイプのピアニストであり、その意味においては、異端とはほど遠い正統なキャリアの持ち主だった。幼時より才能に恵まれた少年であった彼は、6歳でパリ音楽院のソルフェージュ科に入学し、当時の高名な教授であるジョゼフ・ヅィメルマンのもとでピアノを学びはじめる。10歳でピアノの修了選抜試験で一等賞を取り、15歳にして音楽院のソルフェージュの指導者となり、学士院大賞コンクール(いわゆる「ローマ賞」)にも応募する。そんな優等生たる彼の悲願は、音楽院の教授の地位に就くことであった。
アルカンが実は保守的なアカデミシャンであった──といいたいわけではない。むしろ彼のキャリアはこの時代において先進的であったともいえる。パリ国立音楽院の創設は18世紀末である。学校に入り、そこで師に就いて学び、プロフェッショナルを目指すという道は、19世紀生まれの音楽家志望の若者にとってニュー・スタンダードであった。
かつて音楽家にこうした人生のレールを提供したのは宮廷の世界だっただろう。「フランス人ではない」という理由でパリ音楽院への入学を拒否されたリストは、自力でキャリアを切り開いた末にジュネーヴ音楽院で教授職につき、さらにヴァイマールの宮廷楽長の地位を手に入れるという離れ業に及ぶが、生え抜きの秀才であったアルカンは、あくまで音楽院内での出世を夢見続けた。
アルカンの人生2度目の「隠遁」が、この夢が破れた結果であったことも本書で明らかにされている。1848年というフランス2月革命の年を、リュグノーは「政治・芸術界における断絶と同時に、シャルル=ヴァランタン・アルカンの人生における断絶を象徴する年」(p.74)と描写している。この年、師のヅィメルマンがピアノ教授職を電撃辞任し、その後釜をめぐって同門のアントワーヌ=フランソワ・マルモンテルとのポスト争いが勃発した。アルカンは、作家のジョルジュ・サンドやヴィクトル・ユゴー、さらには同業者のマイアベーア、リスト、ショパン、タールベルクらまでをも自身の後ろ盾として掲げ、なりふり構わずマルモンテルに対抗した。結果として勝利をおさめたのはマルモンテルであったが、リュグノーはもしアルカンが勝っていれば、後世のフランスのピアノ音楽史により大きな影響を与え得ただろうと予測する。なぜならアルカンは「音楽的教養、鍵盤楽器についての知識、ピアニスティックな直観、芸術的天分」(p.82)を備えた人物であったからだ。
異端児のイメージは本書の至るところでくつがえされる。同時代のジャーナリストたちは、アルカンが「幻想的な協奏曲や悪魔的な即興曲、メフィストフェレス的なカプリース」に染まらなかったことを称賛し(p.54)、彼がバッハやハイドンやモーツァルトといった「我々の神々しい天才たちの忠実で恭しい代弁者」(p.186)であったと述べる。彼を負かしたマルモンテルでさえも、「受けを狙うために自身の様式を変えることをしなかったピアニスト兼作曲家」(p. 55)として、アルカンの名を肯定的に挙げている。これらは、現代におけるアルカンのイメージとは対照的である。
隠遁者はなぜ隠遁したか
さらに本書では、アルカン若き日の1度目の隠遁の理由が、ある38歳の未婚女性が生んだ子どもにあることも明かされている。同時代人はみなその子どもがアルカンの息子であろうと察知していたが、アルカンはこの子どもの父権を法的に認知せず、しばらく世間から姿を消した。「アルカンにしてみれば、いかがわしい、つまりはスキャンダラスな状況を聴衆や家族に知られることなど、ありえないことだった」(p.60-61)──同時代におけるリストとマリー・ダグー夫人との堂々たる駆け落ちとは正反対の、有り体にいえば小心なふるまいといえようか。アルカンは決して人目を気にせぬ世捨て人ではなかった。少なくともこの1度目の隠遁についていえば、彼は、人目を気にしたからこそ世間から身を隠したように見える。
孤独な隠遁者は、家庭の強い絆に守られて生きた人でもあった。彼は16世紀までルーツを遡ることができるユダヤ系フランス人の家系の一員で、父は五線譜の罫引き工から音楽教師になった人物だった。男女6人いるきょうだいの全員がパリ音楽院に入学し、アルカンは他のきょうだいと区別するため自身を「アルカン長男」と名乗った。父はプロデューサー役をつとめ、コンサートの企画に奔走して子どもたちを売り出そうと尽力した。
この家で宗教がどこまで大きな役割を果たしていたかは、今日の研究においてまだ明らかになってはいない。しかしユダヤ教者としてアルカンが培った宗教への省察が、彼の人生全体に特異な影響をもたらしたのは確かなようだ。彼は2度目の長い隠遁の時期、ユダヤ教に由来する数々の作品を書きながら、一方で新約聖書を訳し(!)、またルター派のプロテスタントであったヨハン・ゼバスティアン・バッハを「神と向き合う」音楽家として「熱烈に信奉」(p.204)してもいる。フランソワ=サペは、こうしたアルカンのアンビバレントな宗教観は、ユダヤ系でありながらキリスト教をモチーフにした画家マルク・シャガールの「エキュメニズム的な世界観」に通じるものであったと分析している。「宗教的な心を持つアルカンは、自身の音楽を通して、人間的博愛や普遍的平和を説いていたのではないだろうか」(p.218)──夢破れた男は、自身の宗教的出自と芸術的出自を融合した独自の精神世界に引きこもり、安らぎと慰めを見出していたのだ。
2人の書き手と1人の訳者によって照射されるアルカン像
本書は、アルカンの人生に比重を置いた第I部(原書の第II部)、作品に比重をおいた第II部(原書の第I部)に分かれており、フランソワ・リュグノーが前者、ブリジット・フランソワ=サペが後者を担当している。しかしこれらは、音楽家の伝記本にしばしば見られる「生涯編」「作品編」の2部構成とはやや性質が異なる。ふたりの著者は、それぞれ包括的かつ年代史順にアルカンの生涯と業績を描いており、役割分担をしているというより、アプローチの異なる2篇の評伝が1冊の本に収まっていると考えるほうが適切だろう。リュグノーが「バルザック風の主人公」の音楽人生をドキュメンタリー風の筆致で追うのに対して、フランソワ=サペは「二面性」という観点をベースに作品と成立背景を音楽学的に追っていく。両氏が着目するポイントは異なり、たとえばリュグノーが作品名を挙げるのみで通過している《大ソナタ「四つの年代」》(作品33)を、同作の研究者であるフランソワ=サペは「ロマン主義という新思潮の先陣を切る」(p.156)重要な作品として取り上げている。
日本語版の訳者であり、巻末に充実した解説を寄せている上田泰史氏は、日本の読者にとって3人目の著者であるといっても過言ではない。同氏は、2人の評伝を「アルカン・コードの解読」「アルカンとキリスト教」「ロマン主義」などの要点に振り分け、自身の解釈や他の研究者の論考を織り交ぜつつ分析している。これを読解の手がかりとして、読者はより多角的な視点でもって本書のアルカン像に接することができる。
2人の書き手と1人の訳者によってアルカンという音楽家が照射される意義は非常に大きく、本書は、さまざまなピアニストによるアルカン演奏を聴くのと同じ喜びと驚きを読者にもたらしてくれるだろう。