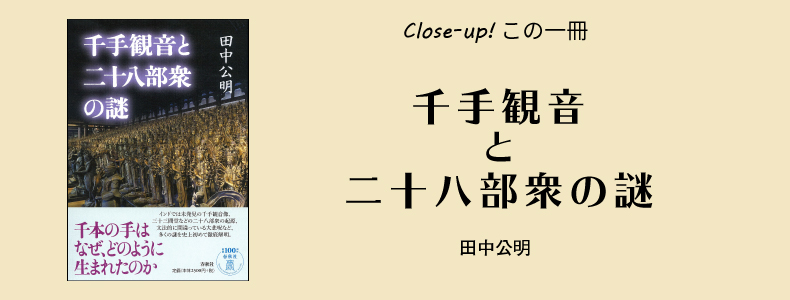千手観音の謎に迫る!/田中公明『千手観音と二十八部衆の謎』
誰もが知っている千手観音は、どこでどのように生まれたのかはよくわかっていない。その他にも、守護する二十八部衆や文法的に間違っている大悲呪など、多くの謎に満ちている。『千手観音と二十八部衆の謎』(田中公明著)は、千手観音にまつわるこれらの謎を徹底的に解明した史上初の解説書である。仏教の故国インドにまでさかのぼる知的冒険の旅は、好奇心を大いに満足させてくれるであろう。
第5章 どうしてインドから確実な作例が発見されていないのか?
これまでの各章では、千手観音研究の序説として、観音信仰の成立や変化観音全般を紹介してきた。本章からは、いよいよ千手観音を取り上げることになるが、千手観音を考える上で最大の問題は、現在(2018年)までのところ、インド(チベット仏教圏を除く)からは千手観音と確実に同定できる作例が、彫刻・絵画を通じて一例も発見されていないことである。
インド亜大陸から出土した変化観音像で、もっとも臂数が多いのは、ナーランダー遺跡から出土し、現地の考古博物館に所蔵される一面十二臂像である。中国には、十一面をもたない一面千手の作例が相当数あるので、一面であっても千手観音に比定することはできるが、千手観音を特徴づける正面の合掌手がないのが問題である。いっぽうバングラデシュ北部のカシプールから出土した観音像(ヴァレンドラ博物館蔵)は、頭部を失っており保存状態が悪いが、やはり合掌手のない一面十二臂像と考えられる。
またケンブリッジ大学図書館に、各地の霊像や仏塔を描いた『八千頌般若経』の装飾写本(Add.1643)があり、その中に「コーンカナのシヴァプラの千手世主」Koṅkane Sivapure Sahasrabhujā Lokanāthaの銘文をもつ挿絵が含まれている。コーンカナはデカン高原の西海岸で、観音の霊場、補陀落山のモデルとされるアガスティア山にも近いが、シヴァプラの正確な位置は不明である。その図像は、正面に合掌手ではなく、転法輪印を結ぶ二手が描かれ、放射状の脇手が無数に伸びているが、細密画のため、一々の持物までは確認できない。
これがインド製なら、インドから発見された唯一の千手観音の作例となったが、ネパールで11世紀に書写された写本であるため、図像がどの程度正確に描かれているのかは分からない。
このようにインドからは、現在までのところ、千手観音の確実な作例は発見されていない。これに対して十一面観音は、すでに確実な作例が複数発見されている。また不空羂索観音も、多くの作例が同定されている。馬頭観音は、日本のものと大きく異なるが、観音像の脇侍や眷属として複数の作例があり、西北インド(現パキスタン)のスワットから、単独の鋳造像(シカゴ博物館蔵)も同定されている。准提観音は、インドでは変化観音ではなく仏母に分類されるが、多数の作例が知られている。これまでインドからは作例が見られなかった如意輪観音も、ナーランダー出土の塼仏の中から、日本のものによく似た六臂像(アストッシュ博物館蔵)が同定された。
このように千手観音は、他の変化観音とは異なり、代表的な変化観音でありながら、確実な作例がインドから発見されていないという問題がある。
それならばインドには、千手観音は存在しなかったのかというと、いくつかの有力な反証がある。インドの仏典を忠実に翻訳した『チベット大蔵経』には、千手観音に関する複数の経典と儀軌類が収められている。その中には、本書第8章で見る『千手経』のチベット訳のように、インドを捜索しても原典が見つからず、吐蕃が占領(8世紀末~9世紀中葉)していた敦煌で、法成というバイリンガルのチベット僧が翻訳したテキストも含まれている。
しかしサンスクリット原典から翻訳された千手観音の経典や儀軌もあり、いくつかの流儀に関しては、インドからどのような経路で、誰によってチベットにもたらされたのかも分かっている。したがって、千手観音がインドに全く存在しなかったとは思われない。しかし他の変化観音の作例が、ほぼ同定された現在になっても、まだ確実な作例が発見されていないのは、インドにおける千手観音の信仰が、地域的に偏っていたか、あまり盛んではなかったからと思われる。
なおインドにおける千手観音の起源と、その成立地については、これからの各章で詳しく検討することにしたい。
ところが同じインドでも、ラダック、ヒマチャルプラデシなどのチベット仏教圏には、千手観音の作例が極めて豊富である。これらのほとんどは、本書第13章で取り上げるソンツェンガムポ王流か、ラクシュミー流の千手観音である。
これに対してラダック・アルチ寺三層堂壁画の千手観音は、チベットに流布するものとは異なる図像を示している。立像と坐像があるが、何れも十一面二十二臂像で、合掌手がなく、主要な二手で転法輪印を結んでいるのは、前述のコーンカナ像に通じるものがある。なお中国領西チベットにも、12~3世紀に遡りうる千手観音の古作が遺されるが、その多くはチベットの流布図像に一致するから、アルチの千手観音は、きわめて異例な作例といえる。
またインド亜大陸で唯一、伝統的な大乗仏教と密教の混淆形態が残存するネパールのカトマンズ盆地には、千手観音の作例が遺されるだけでなく、現在も千手観音像が制作されている。しかしその図像は、本書第13章で取り上げる、チベットのラクシュミー流と同じである。
このように様々な状況証拠から、インドに千手観音が全く存在しなかったとは考えられない。しかし主として漢訳の資料によった従来の研究では、千手観音のようにサンスクリット原典が遺されていない尊格の起源を、十分に解明することができなかった。千手観音の謎を解明するためには、インド仏教を忠実に継承したチベット仏教の資料、とくに敦煌で漢訳から重訳されたのではない、サンスクリット原典から翻訳された資料や、チベット仏教に伝えられる仏教史書や師資相承系譜が必要不可欠となるのである。