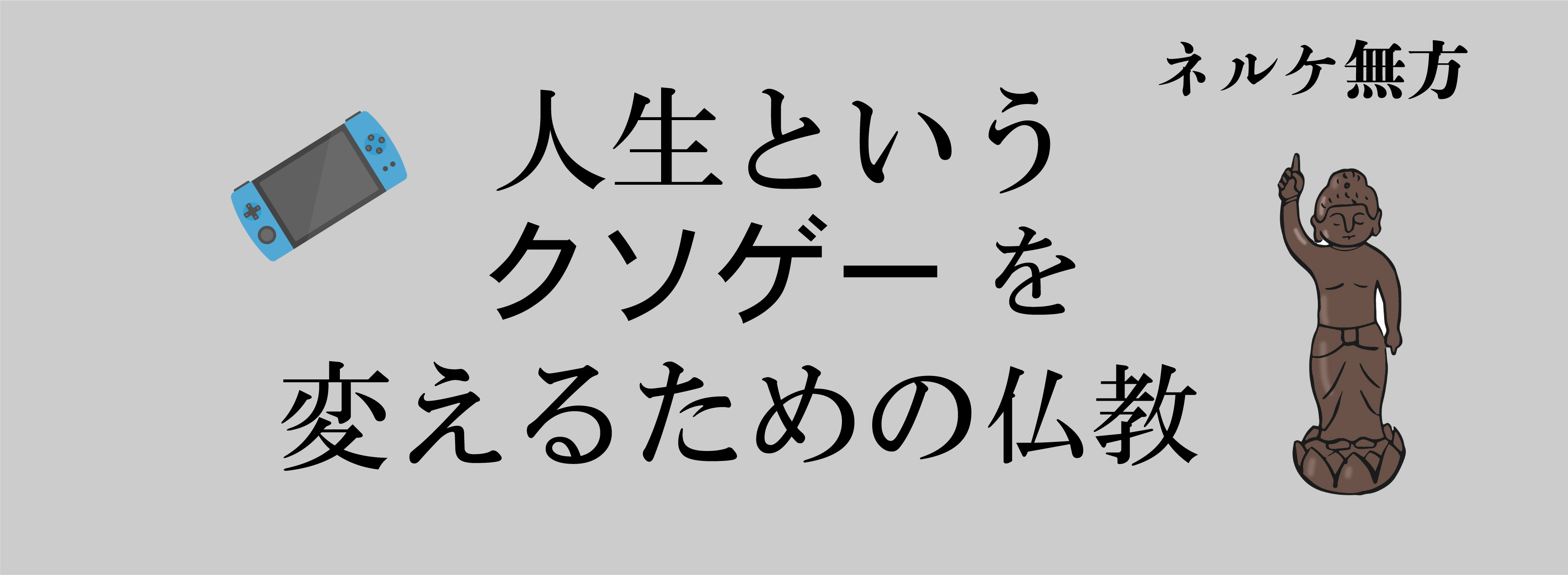〈私〉の気づきと《私》の築き
なぜ私にとって永井均の哲学が大事なのか?
一言で言えば、「永井均先生はひょっとしたら過去のどのお坊さんの説教よりも、私の仏教理解を助けてくれたから」となります。なぜそこまで言うのか?
若き釈尊の「天上天下、唯我独尊」という喝破から、仏法の核心とされている「諸法無我」という法印や、晩年のブッダが弟子たちに残した「自己を拠り所とせよ」という戒めまで、一見はまりそうにないパズルのピースを永井哲学がピッタリとはめてくれるのです。永井哲学の中心概念である〈私〉(やまかっこわたし)こそ、唯我独尊・無我・自己を指しているのです。禅の「無位の真人」や「恁麽人(いんもじん)」もまさに、〈私〉のことでしょう。
永井哲学と私
永井均先生の出発点は「私はなぜ、この人なのか? なぜその他大勢の一人ではないのか?」という問いです。私の場合は「私はなぜネルケ無方なのか」という問いになります。この問いを人に向けて聞けば、おそらく「お前は何を聞いているのか?」という反応にあうのがオチでしょう。確かに、そんなことを聞いていても、何も始まらないのは事実です。永井先生こそ、この問いで一生食っていけている奇人ですが、私たちが同じ問いを持ったとしても、現実生活ではなんの役にも立たないし、その答えが永遠に得られないという可能性も極めて高い。なので、そんな問いは問わない方が得に決まっている。
あるいは「そりゃ、お前の父ちゃんと母ちゃんがセックスした結果さ」と答える人もいるかもしれませんが、ネルケ無方という人の存在をそのように説明できたとしても、それは私がなぜそのネルケ無方として生まれたかの理由にはならないのです。
「私はなぜこの人で、なぜ別の誰かではないのか?」という問いは多くの人の耳には、「リンゴはなぜリンゴだ? なぜバナナではないのか?」と同じように聞こえてしまうらしいです。だから彼らは「リンゴだからリンゴだろ? バナナはバナナさ。お前が仮にお前じゃなかったら、現に「私はなぜ私なのか」と問うこともできないだろ?」と答えます。
しかし、この反論は二つの意味で的はずれです。まず「私はなぜ私なのか」という問いは、「リンゴはなぜリンゴなのか」とはまったく別の問いです。私は「ネルケ無方はなぜネルケ無方なのか?」と聞いているのではないのです。つまり、私がなぜこのような顔なのか? なぜほかのクラスメイトと違い禅僧の道を歩んだのか? といったような事柄に興味はないのです。あるいはそれに興味があったとしても、その説明は遺伝学や精神分析が提供してくれるでしょう。私が聞きたいのは、「なぜネルケ無方がネルケ無方なのか?」ではなく、「なぜ私がネルケ無方か?」なのです。
もう一つの勘違いは、「お前が仮にお前じゃなかったら、現に「私はなぜ私なのか」と問うこともできない」というものです。むしろ逆です。仮に、私がネルケ無方としてこの世に生まれてこなかったとしましょう。その場合でも、ネルケ無方の両親は結ばれ、二人のあいだに長男が生まれたはずです。その長男はおそらく私と同じように坐禅に出会い、そしてゆくゆくは日本に移住し禅僧になったでしょう。そして今や、その彼はネルケ無方としてパソコンに向かって原稿を書き、やたら「私はなぜネルケ無方なのか」と連発していたはずです。つまり、私が仮にネルケ無方ではなかった場合でも、ネルケ無方はやはり「私はなぜネルケ無方なのか」と問うているはずです。そして、その問いは外から見れば、私が現に今問うているこの問いとまったく同じ問いなのです。しかし、私からすれば、私が今現に問うているこの問いと、私が仮にネルケ無方ではなかった時のその偽者のネルケ無方が問うている問いの違いこそ問題なのです。
まだピンとこない方のために、別の思考実験を考えたいと思います。
誰か天才的な生物学者が私の遺伝子を使って、私のクローンを作ったとしましょう。決してロボットのような雑なものではなく、顔や目つきや声から身体の中を流れている血まで、すべて私と同じ人間です。彼は私と同じように「ネルケ無方」と名乗り、そしてやはり「私はなぜネルケ無方なのか」と聞いているわけです。彼と二人で鏡の中で並んだ時、どれが本当の私でどれがクローンのネルケ無方なのか、おそらく私自身も見分けはつかないでしょう。
では、彼の空腹感と私のそれ、彼の問いと私のそれの違いはなんなのか? それこそ永井哲学の核心です。外から見れば、そこには何の違いもありません。クローンが現れたなら、私の妻や子供から見ても、ネルケ無方という奴がそこに二人いるようにしか見えないでしょう。
クローンが家に現れたら、妻が天才的な生物学者に「二人もいらないから、どちらか片方を処分して欲しい」と言い出すかもしれません(あるいは、両方とも処分してくれるように頼むかも……)。その時、私は「こちらが本物だから、間違っても俺を処分しないでくれ!」と叫ぶでしょう。まさにその時、あいつの口から同じセリフが……天才博士もおそらく、どちらが本物でどちらが自分の作品なのか、見当がつかないでしょうね。
しかし、外からの区別がつかないからといって、彼の問い(「私はなぜネルケ無方なのか?」)が私の問いになり得るのか? 決してなり得ないですね。彼は私と同時にお腹が空き、私と同時にトイレに行きたくなるでしょう。だからと言って、彼の空腹感が私の空腹感ではないのです。ましてや、二人のうちのどちらを処分しても同じことにはならないはずです。もちろん、天才博士にとっても妻にとっても、それは同じことかもしれません。しかし、肝心な私にとって、私が現に生きているこのネルケ無方と私ではないクローンのネルケ無方には天地の差があります。
〈私〉こそ世界の開闢
現に今ここ、パソコンのキーボードを叩いている私と、可能世界の中でそれをしている私のドッペルゲンガーになんの差があるかと言われれば、読者のあなたからすれば当然、なんの差もありません。なぜなら、私の書いている「現に……」「今ここ……」なんて言葉が、あなたにとってなんの現実性も帯びていないからです。しかし、現に今この文章を読んでいるあなたと、可能世界でちょうどいまごろ同じ文章を読んでいるあなたのドッペルゲンガーの違いを考えていただきたい。私の目からすれば(そしてあなた以外の誰の目からも)、そこにはなんの差もありません。しかし、あなたにとってその差は有と無のような違いのはずです。
その差は永井哲学の専門用語で「無内包の現実性」と呼ばれています。つまり、それがあるからこそ現に世界が見え、音が聞こえ、身体の諸感覚が感じられるのです。逆に言えば、それがなければこの世界はないにも等しいとい言えます。もちろん、私がネルケ無方では(そして、それ以外の誰でも)なかった場合でも、宇宙は同じように発展し、人類は誕生し、あるいはネルケ無方(のドッペルゲンガーのような存在)が生まれたでしょう。しかし、それらすべてからそれが「現に」見え、聞こえ、感じられているという現実性を剥ぎ取ってしまえば、何も残っていないと言えなくもないでしょう。そのため、永井哲学では「世界の開闢」という用語もほぼ同じ意味で使われています。世界がそこから開かれている、言わばすべての原点のようなものです。その原点を永井先生は〈私〉とも言います。
〈私〉のいない世界は百年前や百年後にもあるでしょうが、そのような世界はまるで物語の中のように感じられる。そのような物語に意味を与えるのも、今ここ、この私が現にその物語を物語っているからではないでしょうか?
しかしそんなことをいくら言って(あるいは思って)も、外から見れば「〈私〉のいない世界」は無論ちゃんと成立します。「お前一人くらい、生まれてこなくてもよかった」と言われるのがオチです。
「なぜそんな自己中心的な考え方をとるのかが分からないな! お前の言うその「無内包の現実性」こそ無に等しいのじゃないか?」
それもその通り。だって、皆それぞれの目から現に世界が見えていると主張しているわけです。私のドッペルゲンガー(つまり、〈私〉ではない私)までもがそうです。皆それぞれ、自分の世界の中心にいて、そこからすべてを見渡している。大人なら、誰だって認めていることです。いや、子供ですら小学校低学年からそれくらいのことをわかってもらわなければ、集団の和を保つことはできないでしょう。しかしそれでもなお、世界中にたくさんある「世界の中心」の一つだけが現に現実化され、そこからまさに今ここ、この時に世界が開かれているというのはとんでもないことではないでしょうか?
「天上天下、唯我独尊!」永井先生はこの驚き(ギリシャ哲学では「タウマゼイン」)から出発し、絶えずこの驚きに立ち返っています。
私が最初に永井先生の著書を読んだ時、御多分に洩れず大きな危機感を覚えました。そこにはところどころ「この話がもし読者に伝わったならば、必ず誤認されているのだ」といった意味合いのことが書かれていたからです。著者である永井先生が、読者である私に理解されてはたまらないと言うのだ! しかし〈私〉が他の誰かではなく、この人であることに驚ける(驚いていい)のは、著者だけなのだろうか? 読者の私だって、現にそのことに驚いているのに……当時の疑問を書けば、次のようになると思います。
「私一人が〈私〉と言ったって、誰だってそうじゃないかな? 他者もそれぞれ自分を〈私〉だと思っているはずだ。そもそも、他者の〈私〉を認めなければ、愛も慈悲もない独我論者になってしまうのでは? 仏教で言えば、〈私〉への気づきを仮に「悟り」と言えたとしても、それはしょせん縁覚の解脱でしかないだろう。その悟りをさらに乗り越えて、菩薩の実践を展開させるのが大乗仏教であったはずだ。」
永井哲学は決してそういう意味での独我論ではなかったことは言うまでもないかもしれませんが、そのことを説明する前に仏教の話をいたしたいと思います。
お釈迦さまは、私たちと同時に成道した?
道元は釈尊の「明星出現時、我与大地有情、同時成道」という言葉を紹介しています。明けの明星が出現したその時、釈尊はこの惑星の生きとし生けるものと同時に道を得た、という意味です。
釈尊がかつて菩提樹の下で坐禅を組み、ある時東の空に浮かぶ明けの明星をご覧になった時、瞬時に悟りを開いて苦しみから自由になったと言われています。小さな王国の王子と言えども、自分の意思で生まれたわけでもなく、仕方なく歳を取り、病気をして死ぬという運命はまげられない。釈迦族の国もいずれ滅びてしまうのが明白な事実でした。横並びできる多くの存在者の中に位置する、釈迦族の自分しか見えていなければ、どうしても「勝った負けた」「損した得した」という次元で自他を比較してしまいます。そうして、やがて「悟り」までがポイント稼ぎゲームの一環として位置付けられてしまいます。
釈尊が明けの明星をご覧になったその時、幼いころから生きていた〈私〉を再び確認できたのではないでしょうか? なんらかの得難い神秘体験をしたのではなく、物心ついた時点で始まっていたゲームがスタートする前の地点から世界を眺めただけだったのではないでしょうか。
しかし……と誰しもが疑問に思うはずです。その時にゲームを降りたのは釈尊一人であって、ほかのプレイヤーたちは相変わらずポイント稼ぎゲームに没頭し続けたではないか! どうして「我与大地有情、同時成道」と言えるのか? ほかでもなく、私自身が長いあいだ、この疑問と格闘してきました。師匠にそのような事を聞けば、だいたい次のような答えが返ってきました。
「お前がこれから悟ろうとするのは間違いだ。ほら、お経にもちゃんと書いてあるではないか。釈尊が悟ったその日から、ワシもお前も、みな悟っているのじゃ」
「私にそんな気配がまったくしないのはなぜだ? 現に、毎日毎日苦しいだけだよ」
「お釈迦さまを信じないからだ。お前はまるで、お母ちゃんのお膝の上で「お母ちゃんの馬鹿め!」と暴れているガキのようだ」
ガキのようだと言われればそれ以上反論もできませんでしたが、救われた気がしないのに「それでもお前は救われているのだ」と言われたって、それこそなんの救いにもなりません。
しかし「我与大地有情、同時成道」とは、果たして「私は皆の代表として悟ったのだ」という意味でしょうか。気づいていようが気づいていまいが、釈尊が成道したその日から、生きとし生けるものは成仏したとはどういうことか?
二〇二〇年八月七日に、雪観英治さんがTwitterで次のつぶやきをした時、私の目から鱗が落ちた気がしました。
そう言えばお釈迦さんの「我と大地と有情と、同時成道」も、築きと気付きが同時とも読めますね(@Yumihiki2010・Aug 7,2020)
ここで言われている「気付き」とは、おそらく菩提樹の下でなされた釈尊の〈私〉への気づきのことでしょう。ところが、世界がほかでもなくこの一人の人間の眼耳鼻舌身意(げんにびぜっしんい)から開かれていることに本当に驚くためには、ただ単に〈私〉に気づくだけでは不十分でしょう。私(ネルケ無方)の場合で言えば、世界の中にたった一つしか存在していない〈私〉がたまたま一九六八年のベルリンに誕生し、今は大阪でパソコンのキーボードを叩いていることはまあ不思議と言えば不思議ですが、「過去・現在・未来のその他大勢の生き物たちも同じように、それぞれにおいて世界の開闢の原点を持っているのだ」という世界像を築いてこそ、一つしか存在し得ないはずの世界の開闢(つまり〈私〉)が数えられないほどたくさんあるのに、なぜ私がたまたまこの人なのかという不思議のほかに、なぜ私がこの〈私〉なのかというさらに驚くべき不思議に気づけるわけです。
物心がつく前の子供はおそらく、なんの疑いもなく毎日〈私〉を生きているのでしょう。なぜならば、その子供はまだ〈私〉以外の存在を知らないからです。初めて「ぼく」や「わたし」が言えて、さらに「昨日・今日・明日」の概念を把握して、なぜ世界があちらからではなく、ほかでもないこちらの〈私〉から開かれているのかということに驚けるのです。つまり、本当に同時と言えるかどうかは微妙ですが、〈私〉に気づくためには「他者の〈私〉」という概念を築かなければならず、「他者の〈私〉」に気づいて初めて、一つでしかないこの〈私〉に改めて気づくのです。「築きと気付きが同時とも読めます」というご指摘を、私はこのように受け止めました。
「他者の〈私〉」という概念は、永井哲学の用語を使えば、《私》です。本当に〈私〉の気づきと《私》の築きが同時と言えるかどうかに関しては、本音を言えば疑問が残っています。そこにはむしろ、卵と親鳥のような関係があるのではないでしょうか。永井哲学っぽく言えば、累進構造? それはともかく、《私》を築いていることが永井哲学と通常の独我論の違いです。
一切衆生は唯我独尊じゃ
一切衆生は唯我独尊じゃ、自分が自分を生きるよりほかはないんじゃ。それをどうして見失うたか。(一一頁)
徳川時代の儒者は、「釈迦という奴は傲慢な奴じゃ。天上天下唯我独尊などと言いおって」と言うておるが、そうじゃない。天上天下唯我独尊はお釈迦さまばかりではない。だれでもかれでもみんな天上天下唯我独尊じゃ。(中略)天上天下唯我独尊を、自分において実現するのが、仏道である。(一一~一二頁)
これらは、澤木興道老師の『禅に聞け』(大法輪閣、一九八六年・新装版、二〇一五年)に出てくる言葉です。釈尊だけではない、私もあなたも「天上天下、唯我独尊」と言っているわけです。
私は安泰寺に入門した当初から、この本からおそらく『正法眼蔵』以上の影響を受けたと思います。夜の坐禅が終わった後に、和独辞典を片手にこれらの言葉を紐解くことが、日々の修行生活の励みになりました。安泰寺を離れて後も、大阪城公園のテントの中で懐中電灯を使って訳しているこの本の一語一句はパンよりも大事な糧でした。さて、この本にある言葉をさらにいくつか引用したいと思います。
屁ひとつだって、人と貸し借りできんやないか。人人みな「自己」を生きねばならない。(十頁)
みなただ自分が自分を自分しているのである。(十頁)
オイ、どっちゃ向いとるんじゃ。藪にらみみたいな目をして――。お前自身のこちゃ。(一一頁)
ケツの穴だからというて卑下せんでもいい。足だからというてストライキやらんでもいい。頭が一番エライというのでもない。ヘソが元祖だというていばらんでもいい。総理大臣が一番エライと思うておるからオカシイ。目の代わりを鼻ではできぬ。耳の代わりを口ではできぬ。みな天上天下唯我独尊である。(一一頁)
この中では「オイ、……」で始まる三番目の言葉が特別な力を持っています。読者一般、皆例外なく「唯我独尊」と言ってしまえば、せっかくの唯我独尊の効力がなくなってしまいます。太郎も花子も私も唯我独尊……ではなく、藪にらみみたいな目をしている、そこのお前! でなくてはなりません。親鸞が「ひとえに親鸞一人がためなり」と言っていたその事実を、澤木老師は目の前にいる相手に渡そうとしている気がします。仏教はよそごとではなく、お前一人のこっちゃ……。
それに比べれば、ほかの言葉は澤木老師特有の味わいがあるものの、どこか説明的な要素が強くてパワーが落ちてしまっていることは否めません。「唯我独尊」はいつの間にか「私だけ」でもなく「お前だけ」でもなく、皆の共有財産になってしまいました。
ダイバーシティーが叫ばれている一方、皆が平等であることが何よりも大切と言われている昨今です。皆と同じであることに安心する人もいる一方、皆とちょっと違って(ズレて?)いることにこそ自分の存在価値を見出そうとする人もいるでしょう。しかし、仏教的な観点からすれば、どちらも中途半端です。「天上天下、唯我独尊」は、「〈私〉の比較は不可能」という意味です。そもそも人と横並びできない〈私〉に気づいていれば、私が生きているこの人なんて、皆と違ってもいいし、皆と同じでもいいのです。