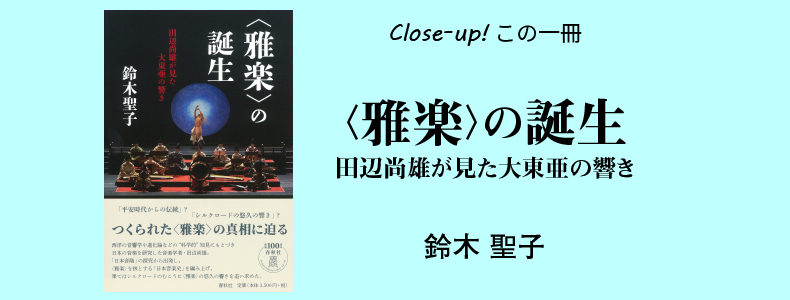雅楽の記憶、人の記憶/鈴木聖子『〈雅楽〉の誕生』
祝 サントリー学芸賞!
このたび第41回サントリー学芸賞〔芸術・文学部門〕に選ばれた鈴木聖子さんより、受賞対象となった著書『〈雅楽〉の誕生 田辺尚雄が見た大東亜の響き』についてのエッセイを寄稿いただきました。(編集部)
もう十年以上も前のことであるが、ある作曲家のお宅をご挨拶にお訪ねすることがあった。初めてお会いする機会であったにも関わらず、その方の紳士的な雰囲気に打ち解けて楽しく滞在し、2時間ほど経ったころであろうか、本書『〈雅楽〉の誕生』(当時は博士論文の一部として構想中)の主人公となる田辺尚雄について話を始めたところ、ひどく立腹されてしまった。「田辺先生を歴史的に批判するなどありえない。純粋に音楽学的に批判をするべきである」と言われるのであった。かつて学生時代に田辺に師事をされており、「よく知っている」と言われる。だが、持参した論文の抜き刷りさえ持って帰るように言われるほどであったので、これはなにか別の次元の大きな失敗をしてしまったのだろうと恐縮して、灰色の空の下をとぼとぼと帰路についた。
それからしばらく落ち込んでいた私に、相談に乗ってくれた日本の科学史を専門とするフランス人の同僚が一言、「怒るのが当たり前ですよ、その人の前で、田辺、田辺と呼び捨てにしたでしょう。田辺先生じゃなくて」
彼の言う通りだった。彼は付け加えて、どうして科学史という分野で研究をしているかを話してくれた。音楽学にせよ民族学(彼の研究対象である)にせよ、ひとつの学問領域には、その学問の科学的認識を支える人々の記憶が蓄積されている。こうした内部の地層を分析するには、科学史という外部からの視点が有効である、と。フランスでは科学史は認識論(エピステモロジー)として捉えられており、科学的認識の場の歴史、つまりパラダイムの変遷の記述という意味が強い。領域内部からみた「学史」とは異なる。
この彼の助言で博士論文に見合った方法論を得た私は、フランスで彼の指導教員である科学史のアニック・ホリウチ教授の元で学ぶことになった。彼女の専門は江戸期の数学史である。私がそこから得たものは、本書では、江戸期から明治期へと科学的な音階理論のパラダイムが移り変わるさまを描いた第一部に結晶しているほか、田辺が「日本音楽史」という学問領域を創出するにあたり、それ以前のパラダイムから何を克服し、どのような新しいパラダイムを築いたのか、といった本書全体を通底する問いの構造にも反映されている。
ともあれ、この「事件」を通して私が理解したのは、近現代の人間を対象とする歴史研究の難しさである。ある人物を研究対象とするということは、その人物の周囲を取り巻くすべての人々の記憶のなかに踏み込むことになるのだから、配慮が必要となる。配慮とはおもねるという意味ではない。人の記憶は研究よりも重いものだと慮ることである。かの作曲家のお宅を訪ねたときは、聞き取り調査のためではなかったから、事前にその方の経歴等を深く調べていなかったとはいえ、田辺を生身の人間として多くの人の記憶に残る人物であったことをよく理解していれば、二人が顔を合わせたことがあるのでは、くらいの前提は立てることができたはずであった。そして、研究者として駆け出しであった私の未熟な物の言い方には、歴史研究の名のもとに人とその記憶を裁きうるかのような傲慢さが潜んでいたに違いない。
この「事件」のお蔭で、自分の意見を定めながらも、同時に複数の見方が可能であるような柔軟な姿勢が必要であることを学んだのである。
◆
かつて田辺尚雄も、これと似たような「事件」を経験している。
田辺は、明治維新から明治末期までに形成された「皇室の音楽」としての「雅楽」像を、大正時代の近代的な科学と生活に適応するよう創り変えようとしていた。大正10年(1921年)1月に出版した雅楽レコード集の解説書『雅楽通解』では、雅楽は古代から平安時代にかけて「進化」し、それが宮内省式部寮楽部(現在の宮内庁式部職楽部の前身)でそのまま行われていると、当時の科学界・思想界を席巻していた進化論を用いて語っている。
その頃、宮内省楽部の養成機関である雅楽講習所で西洋音楽史と音響学を講じていた田辺は、楽師たちと懇意にしており、また自らも楽師の薗兼明について笙を学んでいた。雅楽に「ハマった」田辺は、楽部の名人達によって演奏される雅楽を世に広め、後世へ末長く残したいと願った。そして、大陸由来の器楽である「管絃」「舞楽」や、本邦産の歌物「催馬楽」「朗詠」だけではなく、それまで門外不出であった「御神楽」(年に一度だけ天皇の御前で真夜中に催される「御神楽の儀」の芸能)をも、楽師たちを時間とお金をかけて説得し、初めて録音することに成功したのである。大正デモクラシーの時代、雅楽を「芸術」として民主化することは、知識人としての使命であると田辺は考えていた。
同年4月のことである。楽部楽長の上眞行から、朝鮮(当時は日本の統治下)の旧王朝の李王家の雅楽が廃絶の危機にあると聞いた田辺は、財団法人啓明会から得ていた助成金で、ひとり現地調査へと向かった。この日本初となる「民族音楽学」のフィールドワークでは、当時としては世界的にも非常に珍しかった「活動写真」(映画)による「保存」が行われた。残念ながら現在これらの映像フィルムは存在しない。写真1は「春鶯囀」の女性の舞の映像撮影風景を田辺が撮ったもので、写真の左に撮影機の三脚と、地面に撮影機の影が見える(『続田辺尚雄自叙伝』、邦楽社、1982年、118頁)。
 (写真1)「春鶯囀」撮影風景
(写真1)「春鶯囀」撮影風景
この調査を通して、田辺は朝鮮の雅楽を、「春鶯囀」のような女性の舞を伴う宮中宴会用の「俗楽」と、「宗廟登歌楽」(写真2、『中国・朝鮮音楽調査紀行』、音楽之友社、1970年、図版頁)のような宗教儀式用の「雅楽」に二分類し、前者の「俗楽」のみが日本に渡来して日本の「雅楽」となったと結論している。こうした結論を導くに至った明らかな理由のひとつには、「春鶯囀」と同名の曲が日本の雅楽にもあることにあったろうが、雅楽に女性の演者がいるという発見が田辺の雅楽の民主化構想に新しい視点をもたらしたことにもあるだろう。

(写真2)「宗廟登歌楽」
さて、朝鮮から帰京した田辺は、同年7月9日に日本工業倶楽部で開催された啓明会の講演会で、「朝鮮李王家の古舞楽――我が宮中の舞楽との関係」と題する発表を行った。日本で初めて、朝鮮の雅楽の生きた姿と、日本の雅楽の起源についての研究結果が報告された。講演の最後には「活動写真」の上映が行われ、プログラムによると、第一部「李王家の雅楽」、第二部「宮中宴礼楽及俗舞」(上)、第三部「宮中宴礼楽及俗舞」(下)、と分けられていることから、明らかに「俗楽」の紹介に力を入れていたことが分かる。映像によって芸能を「保存」するという思想は新しいものであったが、映像を使った発表もまた、当時は非常にモダンなものであった。
ところが話の結末から言えば、この田辺の講演は宮内省の一部の人々の機嫌を損ねることになり、期せずして田辺は楽部の講師の職を失うことになるのである。否、期せずしてというより、宮内省の要人や楽部関係者も来場することが分かっていたはずのこの講演会において、「日本の雅楽の由来は朝鮮の雅楽でなく俗楽である」という言説がどのように受け取られるか予期することをしなかった田辺のほうに、落ち度があるだろう。「雅楽」と「俗楽」は反対語であり、「俗楽」でないことが「雅楽」の存在理由のひとつなのだから。
ただし、おそらく彼なりに配慮をしたのではないかと思われる節がある。二か月後に刊行された講演録『啓明会第五回講演集』(大正10年9月)を見ると、講演の前半部分に、
日本の宮中の雅楽(神楽を除く)は俗楽(最も高尚なる俗楽)でありまして、なにとぞ宮中が万民と共に之を楽しまれるというように至られんことを希望します。
と、「雅楽(神楽を除く)」「俗楽(最も高尚なる俗楽)」などの括弧書きの注釈が施こされているからである。尤もこれは講演後の印刷であるから、後日に括弧を挿入したと推測もできる。また、「宮中が万民と共に之を楽しまれる」と傍点を施すことで、田辺が「俗楽」の意味を新たに解釈しなおそうとしているのも見て取れる。
いずれにせよ、田辺にとっては純粋な科学的調査の結果である「日本の雅楽は朝鮮の俗楽」という言説は、宮内省や楽部の関係者にとっては彼らの「雅楽」の記憶に修正を求めるものであり、いかに括弧や傍点を用いても取り返しのつくものではなかったろう。
しかし田辺にしてみれば、日本の雅楽史について新しく発見された事実に対して、当の宮内省から評価が得られないとは、甚だ腑に落ちないことであったようである。講演からひと月後、『東京日日新聞』に「宮中音楽の民衆化に対する誤解」(大正10年8月18日・19日)という記事を書いて、
宮中の雅楽の大部は俗楽であって、必ずしも神聖視すべき性質のものではなく、これを今少し民衆化して、例えば平和博覧会で公開して見せるとか、あるいは場合によっては帝劇などであって見せても差し支えない、むしろ斯くあらんことを望むというような主意のことを申したについて、宮内省一部の保守派の物議を招いたということである。私はこの際誤解のないように、殊に私が民間に於ける最大の宮中音楽愛好者であるという立場から、宮中音楽に災いを及ぼさないために、一言弁解して置きたいと思う。
と、事実を翻すことなく、楽部の雅楽の民主化への願いと楽部の雅楽への思いを叫んで、己の無実を訴えている。
これらの努力も空しく、田辺は楽部の講師職を解雇される。実は正確な原因は分からないのだが、しかしこれは田辺の心に深い傷を残したとみえ、旅先の『京津日日新聞』(大正12年5月17日)でも、「併し辞職問題は小さいことでした。楽の保存は大きい問題です」と繰り返し述べており、当時の彼の雅楽の記憶が楽部の雅楽と切り離せないものであったことが分かる。
こうして楽部から去ることになった田辺は、1920年代を通して、異なる複数の雅楽の記憶を求めてアジアの旅を続けた。その果実をもとに形成された日本音楽史、東洋音楽史、民族音楽学といった研究領域からは、後に多くの優秀な弟子たちが育つことになる。
関連書籍

2019年 第41回サントリー学芸賞〔文学・芸術部門〕