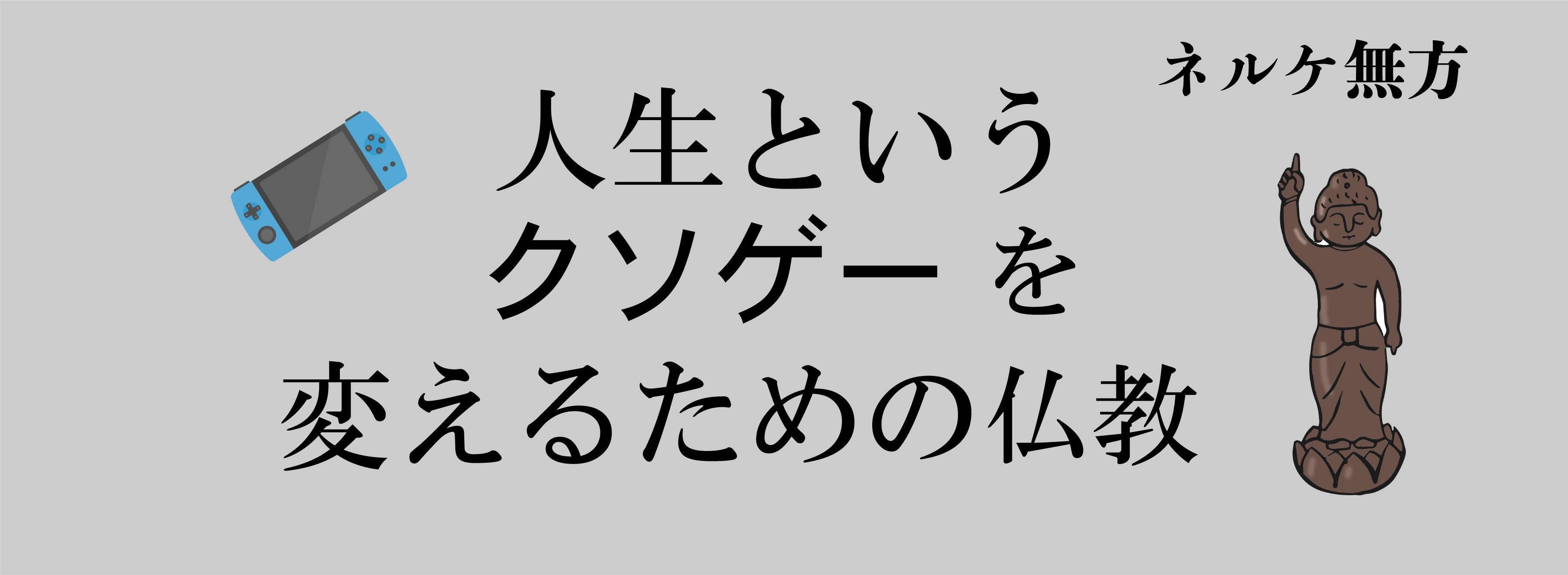仏教とは、ゲームを降りること
仏教とは何か?
「仏教を一言で教えてほしい」――そう言われれば、私はこう答えます。
仏教は、人生というゲームを降りることを教えている。そのゲームを降りることから、仏教がスタートする。
では、人生というゲームを降りた後にはどうするか。ゲームを一服した後、新しいゲームを提供するのが仏教だと私は思います。いや、仏教は新しいゲームを提供するというより、もっと余裕のある遊び方をすることによって元のゲームをより楽しくすると言った方がいいかもしれません。プレイの仕方を変えることによって、ゲームの内容も変わるのです。
近年、私が仏教の話をする時にはよく「ゲーム」という比喩を使っています。ゲームを降りることと、再びゲームに乗ること――仏教には、とりわけ大乗仏教には、この両側面があると思います。
もちろん、こんな比喩を使うと、さまざまな反駁が起こります。
例えば「人生はゲームとは違う」という、ごもっともな意見です。
人生はそもそもゲームではないから、仏教とはそのゲームを降りることではない。むしろ本気で生きることである、一生懸命になることが仏教ではないか。人生をゲーム感覚でやり過ごしている現代人に、自らが生きている「生老病死」の苦を直視させ、その現実との向きあい方を教えるのが仏教であったはずだ。仏教はゲームではなく、リアルを生きることだと。
かつて私自身も「現代人に足りないのは、リアリティー(現実感)だ」というようなことを言ったことがあります。バーチャル化に伴い、世界全体はまるでゲームのように見えてしまったが、人生は決してゲームではないと。しかし、私たちはこの上ないほどリアルなゲームも知っているのではないでしょうか?
ゲームには決まったルールはあるけれど人生にはそれがない、とか、ゲームにはゴールがあるがそれも人生にはない、と言う人はいるかもしれませんが、ルールが定まっていないゲームや「ルールがない」のを特徴とするゲームだってあります。そのゲームは実は、物心がつく前にすでに始まっているのです。私たちが「リアリティー」と呼んでいるのも、しょせんはよくできたゲームの中のリアリティーではないでしょうか。
二つ目の反論は「なるほど、仏教はゲームを降りることだ。しかしなぜ、そのゲームに再び参加する必要があるのか」。
親ガチャでハズレくじを引いて、スペックの低い自分には勝ち目のないこのクソゲーをなんとかして降りたい! 私たちが日々の生活に感じる息苦しさの裏には、そういう感覚があるのではないでしょうか。勝ち負けの基準もはっきりしないゲームに無理やり参加させられている。出口さえ見つかればいい。こんなゲームになんか、再び戻りたくもない!
こう反論するのは、人生を「生きづらいもの」と感じているからでしょう。本音を言えば、生まれてこない方がよかった。生まれてしまった以上はこの一生を自他ともになるべく苦しまないで済むように過ごしたい。そのためには弱肉強食の競争に参加しないのはもちろんのこと、子孫も残さない。子供を産むとは、世知辛い世の中に苦しむ者を増やすだけだからである。
「家を守らなければ」「国を守らなければ」「この惑星を守らなければ」というゲームの暗黙のルールにも支配されたくない。この問題意識は初期仏教に非常に近い部分がありますが、なるほどこういう考え方からは「ゲームへの再参加」という発想は出てこないと思います。
では、なぜいったん降りたゲームに私が再び参加するのか? 一言で言えば、このゲームに外側がないからです。生きるということは、なんらかの形でゲームに参加していることを意味します。
本当は仏教もゲーム?
三つ目の反論は「仏教はゲームを降りるどころか、人生をあえてゲーム化したようなものなのでは? 涅槃とか極楽とか、あるいは悟りの境地――仏教って、「ご利益」というポイントを稼いで「救い」というゴールに到達しようとするゲームだろう」。
「宗教は民衆のアヘンである」「神は死んだ」――十九世紀のマルクスやニーチェが生んだ格言はあまりにも有名です。これにうなずく現代人も決して少なくはないでしょう。宗教は厳しい現実をありがたい物語にして信者たちに現世利益を約束する。あるいは、この世では手に入りそうにない特別賞を、「あの世」で捏造したりします。不条理や理不尽の多いこの人生になんらかの「意味」や「価値」を与えることによって、生きづらい人生がやりがいのあるゲームに変わるのです。しかしありがたいとはいえ、捏造された意味や価値は捏造に過ぎません。
この本では、私はこれらの疑問に答えたいと思います。仏教が降りようとするゲームの正体とその成り立ち。そしてそのゲームに再び参加する時のモチベーション。再び参加した後のゲームが果たして同じゲームなのかどうか、というのもテーマの一つです。ゲームに違いがあるとすれば、それはどのような違いだろうか。仏教もまた一つのゲームに過ぎないのでは? いや、ゲームに過ぎない(だからつまらない)と思わず、ゲームだからこそ楽しい! と思ってもらいたいのです。
ゲームについて考える時、人生一般、宗教一般、仏教一般の話もします。初期仏教と大乗仏教、そしてキリスト教のそれぞれのゲーム。鎌倉仏教のゲームチェンジャーと言われる親鸞と道元はそれをどう変えたか。私自身の「ゲーム」を模索したいと思います。
しかし、それよりも一人称的な立場から私の人生、私の出会った仏教、私のゲームの話に重点を置きたいと思います。読者にもそのつもりで、私を含めこの本の登場人物よりも、自分自身のゲームを自覚し、自分自身の仏教を模索していただければと思っています。
ゲームの始まり
さて、私の言う「ゲーム」はいつ始まったのか。
「一日じゅうゲームばかりしている人もいるでしょうし、私も休みの日などゲームをしている時だってある。しかし人生そのものをゲームだとは思っていないし、ゲームを降りるのに仏教の助けなんか必要としていないよ」――こういう読者もいるかもしれません。そう言いたくなるのも、ゲームをしていることに気づいていないからではないでしょうか。
私たちが物心ついたころには、すでに「ゲーム」をしています。私が初めて自分の足で数歩か歩けることに成功した時、内心、何を考えていたのでしょうか。いや、おそらく何も考えてもいないでしょう、そのころの記憶はもちろんありません。しかしその時見ていた祖母の話によると「勝った!」と言わんばかりの、とても自信に満ちた表情を浮かべていたのだそうです。それは歩けるようになったことを純粋に喜んでいるだけの表情ではなかったかもしれません。祖母がこっちを見てくれていることを確認し、祖母が喜んでくれていることに対する「勝った!」だったかもしれません。
それまではおむつがいっぱいになったら、母や祖母はそれを取り換えてくれるのですが、そのころからトイレトレーニングが始まりました。いや、その記憶はもちろんありませんが、のちに妹たちが同じ目に遭っていたのを覚えています。「またもらしたの?」「したくなったら言ってちょうだいね」「なぜ言わなかったの?」「何回言えば分かるんだ!」
したくもないのに、おまるに坐らされる。どうやら、おむつではなくここで「出す」のがルールらしい。でも、出すべきものは出ない。いざパンツを穿いたら、出てしまう……。
「ええっ出しちゃったの?」(いやいや、「出した」のじゃなくて勝手に出てしまうのですよ)
「したくなったら、言ってちょうだいね」(したいもしたくないも……はいはい、分かりました)
「なぜ言わなかったの?」(僕だって困っているのです、勝手に出ちゃうんですよ)
「何回言えば分かるんだ!」(すみません、もうしません!)
それまで勝手に出ていたものを、こちらが出したり出さなかったりする。そのつど怒られたりして嫌な思いもする。しかしそのうち、それができるようになる。
「えらいね、できたね」(ありがとう。おかげさまです)
いや「おかげさま」もなにも、本当に「自分でできた」つもりになるから嬉しいのでしょうね。そしてそれより、やはり母や祖母に褒められること、「いいね!」をつけてもらえることが嬉しいのです。この時点で、ゲームはもうとっくに始まっています。
ステージを上がるにつれて、難しくなるのもゲームの特徴です。やがてシャツもパンツも自分で着られるようになる。靴下も靴も。靴の紐だけはまだうまく結べていない。
「それもまだできないの? 同じ組の〇〇君は自分で結んでいるよ?」
どんなにポイントを稼いでも、さらに多くのポイントを獲得しているプレイヤーがそこにいる!
「私」というコマ、「今日」というマス
物心がつくまで、出会うものはすべて自分であり、自分の世界です。自分と世界の境界線もまだあやふやだったはずです。しかし、遅くても「私」や「僕」という言葉が使えるようになったころからその境界線は明確になり、自分を複数のプレイヤーが参加しているゲームの中に位置づけることに成功します。私、僕は〇〇家の一人、〇〇幼稚園のすみれ組の一人、〇〇小学校の〇年〇組の一人……自分とはもはやクラスの中の三十分の一の一人、運動会では並んでいる数百人の内の一人、ゲームの一個のコマでしかない。
「私」や「僕」という一人称より少し遅れて、「昨日」「今日」「明日」といった時制の表現が使えるようになる。それまで、子供は大人に「今日はもう遅いから、家に帰ろう。また明日遊ぼうね」と言われても、明日とはいつ来るか分かるはずもありません。いつも今ここ、この瞬間の連続の中で生きているからです。しかし「今日」と「明日」の違いが分かれば、「あと何回寝ればサンタさんがくる」かも大体の見当はつきます。明日のご褒美のために、今日は我慢する。終わる気配のしなかったこの一日も、いつの間にか一年間の三百六十五分の一になりさがってしまう。そうして、その一日はなんとなく見えてきた「人生」というすごろくゲームの一マスとして位置づけられていくのです。
私が生まれるずっと前から世界が存在し、私が死んだ後にも存在し続けるはずだ……と誰しも思いますが、この「世界」だって言葉を覚えることによって各々が構築しなければなりません。この「世界」は言わば人生ゲームのボードの役割を果たします。なぜゲームがそこまでリアルかと言えば、ゲームのOSが言語そのものだからです。物心ついたころ、私たちは世界をゲームの内側からしか見ていません。
ある年齢に達すると、子供はまたとんでもない発見をします。それは「ウソ」の存在です。世界は言葉で構築されていますが、言葉でウソをつくこともできる。
「このお菓子を食べたのはだれ?」
「僕は知らないよ……」
「このウソつき! もう口をきかないよ!」
本当のことを言えば怒られるに決まっている。ウソをつけば、余計に怒られてしまう。厳しいペナルティーが課されることもある。しかし、怒っている親だってちょこちょこウソをついていることに、子供だって気づいています。
「お父ちゃんとお母ちゃんはどうして結婚をしたの?」
「一番好きな子供はだれ?」
親もなかなか、本当のことを教えてくれない。本当のことを言うと、損する場合もあるからです。このゲームでウソをつくのはルール違反とされていますが、ウソで得することもあります。しかし、ばれないウソをつくのはなかなか難しい。親のような「ゲームの達人」になるためには、上手にウソをつくことが一つの条件らしい。
親のウソがばれても、子供はまだペナルティーを課すことができない。親が見ている前では、子供は公式のルールを守る。守らなければならない。しかし誰も見ていないところでは、その限りではない。どうやら、ルールは絶対ではないらしいのです。絶対ではないからこそ、親は「絶対にね!」と念を押したりするのです。
ゲームの裏技
ゲームのステージが上がるにつれ、次々と新しいルールとコツを習得する。家の中でのライバルは、外では味方になる(お兄さんを呼んでくる!)。ほかのプレイヤーと同盟を作らなければ、ゲームには勝てない(友達は大事!)。友達のために自分を犠牲にすれば、長い目で見れば得する。明日のために今日を犠牲にすれば、長い目で見れば得する。いつも自分のことだけ、今日のことだけを考えていればかえって損する。ポイントを稼ぐためには「相手のこと」や「先のこと」も考えなければならない。これもこのゲームの暗黙のルールらしい。
ところが、「人生はゲームである」とは誰も教えてくれません。親や学校の先生はむしろその逆、人生はゲームではないと言います。そして「ウソ」をはじめ、ゲームのさまざまな裏技を背中で示しても、口ではルールしか教えてくれません。
家で天下を取っていた子供たちが、幼稚園では「先生とお友達、みんな仲よく」をモットーに横に並ばされる。その時初めて、その他大勢として「自分」を体験させられる。めでたく小学校に「上がる」と、「自分のことばかりでなく、皆のことを考えて行動すること」が次第に叩き込まれます。給食当番、それぞれの掃除当番、黒板係などプチ・ゲームのさまざまなコマを演じられるようになる。読み書きや算数の学習なんかよりも、学内でのそれぞれの当番が「普通に」できるようになることが小学校教育の大事なポイントでしょう。
私自身は日本の学校に通ったことがないので、親の立場での体験しかありません。おそらくドイツで親として子供を育てることよりも、日本で育てることの方がずっと楽ではないかと思います。なぜなら、ドイツの学校の役割は知識を学習させるほか、先生と議論を交わさせたり自分の世界観や人生観を模索できる場を与えたりすることくらいで、先生は決して生徒たちを「しつけよう」とは思っていませんし、親側からも学校側からもそんな期待はまったくありません。いっぽう日本では朝の挨拶や靴の並べ方から、教室での坐る姿勢、食事や掃除の作法まで――ドイツで絶対に言われない事柄まで禅寺よろしく訓練させられるようです。
私がまだ安泰寺という兵庫県の山奥にある禅寺の住職だった時の話です。このお寺には昔から、世界中から若い人たちが禅の修行をしに来ますが、その様子を傍から眺めている私の子供たちがよく「まず日本の小学校からやり直した方がいいんじゃないの?」と私にアドバイスしたものです。彼らのことを言っていたのか、私自身のことを言っていたのか……。
それはともかく、ドイツ人の私は子供たちに小さいころから「泡だけでも」と晩酌のビールを勧めてきましたが、やはり小学生になったころ「お父ちゃん、子供がビールを飲んじゃいけないんだよ」という反論(?)に遭いました。
「これはビールじゃないよ、麦のジュースだよ」
「いいえ、ここには「おさけ」と書いてあるでしょ?」
子供たちは父親の私のウソを簡単に見破れるようになってしまいました。
「ここだけの話じゃないか。誰にもバレはしないよ。俺が先生にチクるわけないだろう」
「お父ちゃん、あまりしつこく言うと私たちが学校の先生にいうよ」
今までゲームのルールを決めていた私の権威はどこへ?
車が来ていないのに、赤信号を渡らない?
ドイツの横断歩道で歩行者が渡ろうとした場合、車両は止まらなければなりません。日本も同じと思っていたら、実態としてはどうも違うらしい。
「右を見て左を見て、車が来なければ手を挙げて横断歩道を渡る」と子供は幼稚園で習ったらしいのです。
「君たち歩行者が優先だから、車が来ても手を挙げて渡ればいい。だって、向こうには止まる義務があるんだから。それより、なぜ車が来てない時に手を挙げる必要があるんだい? その時は別に手を挙げないで渡ろうよ」
安泰寺がある田舎には昼間でもほとんど車が走っていません。にもかかわらず、近年は街のプライドの象徴としてなのか信号機だけはあちらこちらに立つようになりました。
「車が来ない時は、赤信号だって渡っていいよ。自己責任だけど」
いくらドイツでも、そんな法律はどこにも存在しません。しかし、実際にはそうではありませんか? 交通量がゼロの場合、赤信号を無視するのは当然でしょう?
「お父ちゃん! それは絶対にだめだよ!」
私の常識は日本の非常識らしい。子供が私のことよりも先生のことを信じるようになったのも無理はないかもしれません。これから日本で社会人になった場合、その方がむしろ望ましいかもしれません。しかし私が子供たちに教えていたさまざまな「ウソ」は、まんざらウソでもなかったはずです。ウソではなく、あくまでも裏技なのです。
息子の「おとうさん」という詩が、県の教育委員会から表彰されたのは彼がまだ一年生だった時です。彼以上に、担任の先生と父親の私が嬉しかったかもしれません。
おとうさんは、ドイツでうまれた
にほんにきて、おぼうさんになってざぜんもする
おとうさんは、はたらきものだ
おおきなグローブのような手ではたけをうつ
あたらしいみちをつくる
あたらしい田んぼもつくった
すごい力もちのおとうさんが
ぼくは、大すきだ
いかにも小学校一年生らしいこの詩を読んだ時、涙が浮かびました。息子の偽らない感性がそこに表れているように感じたからです。もちろん、それだけではありません。そこに綴られていた言葉は、父としての私のプライドをうまくくすぐっていたのです。
最愛の妻でさえ、私のことを「はたらきもの」「すごい力もち」と評したことはありません。しかし、最後の「ぼく……」は不思議に思えました。なぜならば、息子はその時、まだ自分のことを「ぼく」と呼んでいなかった。ましてやグローブ……私は息子とキャッチボールしたことがないし、テレビが映らない安泰寺で野球を観戦したこともない。
「この「グローブのような手」って、なんだい?」と聞くと、息子からびっくりする答えが返ってきました。
「それは先生が書いてくれたさ」
なるほど、そういうことだったのか。文化祭や運動会も結局、子供たちが親と先生を喜ばすためのゲームだったのか。彼もやがてそのことに気づくでしょう(いや、その時にすでに気づいていたのか……)。
オンリーワンの抹消
ゲームの公式ルールにうるさいわりに、ゲームの勝ち負けについてはあまり明確なことが言われないのも日本の小学校や中学校の特徴の一つかもしれません。
六年前、小さな背中に真新しいランドセルを背負っていた皆は一斉に中学校のぶかぶかの制服を身にまとい、中学校の大きな体育館に坐っています。
どれが自分の子なのか、親の自分にもすぐには分かりません。なにせ、皆が同じような髪形、同じような髪や肌の色をしています。違いがあるとすれば、男の子と女の子の違いくらいです。彼らはここで集団生活を問題なく送るために、さらに徹底した教育を受けることになるらしいのです。部活という「日本社会の予備校」も含めて。
小学校・中学校で一貫して言われるのは「頑張ることが一番」「勝つことはすべてではない」ということではないでしょうか。楽勝することよりも、報われない努力が美しい。皆のために、自分を犠牲にすること。また道徳の授業では、「思いやりの大切さ」や「和の精神」も習うようです。ゲームに参加するための心構えとして教えられているのは「ゲームは勝利がすべてではないよ、それより皆と楽しく遊ぶためのフェアプレーが大事」「個人プレーじゃなくてチームプレーだよ」ということです。
ところが、入学したその日から、各々の子供は先生から評価され、学期の終わりには成績表をもって家に帰ります。その評価のために「思いやりのある子」や「和を保てる子」を上手に演じることもあるのではないでしょうか? 結局は、各々が稼いだポイント次第で、親に褒められたり叱られたりします。
「出る杭は打たれる」と言われた時代はとうに終わりました。今の学校は、多様性を尊重しているのだそうです。決してロボットのような型にはまった人間を育てるのではなく、各々の子の個性を伸ばそうとしているのです。
「ナンバーワンより、オンリーワン」
だからこそ、運動会でもナンバーワンになるより、各々のオンリーワンの頑張りが評価されます。しかし、「オンリーワン」を全員に振り分けることによってそれが抹消されます。そうして、結果的には多様性という名の画一性が出来上がります。
「オンリーワン」という意味では、誰も違っていないわけです。しかし、その理屈も成績表が出されるたびにひっくり返ります。自分は上からなん番、下からなん番と分かりやすくランク付けされるではありませんか。本当に「ナンバーワンより、オンリーワン」なら、どうしてそんなことをするのでしょうか? 皆(親も先生も仲間も)がどこかで共有している「自分さえよければいい」という暗黙の了解と、ゲームの公式ルールはあまりにも矛盾していませんか。そしてこの矛盾に誰も言及しないのはなぜか⁉
遅くても中学校のころから、誰でもそういった矛盾に気づくはずです。自分が参加しているゲームは、実は「自分のゲーム」ではないことにも気づきます。親の都合や学校の都合で部活を強制させられたり、いやいや試合に出されたりして先生や親のメンツのために頑張らされている。「よくできた子」とは、親と先生のゲームの中で思うように動かされるコマでしかないのではないか? このことに気づいた日から、母の日や父の日に素直に「いつも僕のために、私のために頑張ってくれて、ありがとう」とは言えなくなる。だって、本当は逆でしょう? 親の都合で自分がゲームに参加させられ、親の勝負のために自分が今日まで頑張ってきたんじゃないか? そろそろオレ自身、ワタシ自身のゲームがしたいと思い始めるのも中学生のころではないでしょうか。しかし、それがまだ許されないのも日本の中学校です。いや、義務教育が終わった後でも、他人のゲームに乗せられることなく自分のゲームを楽しむ人はどれほどいるのでしょうか?