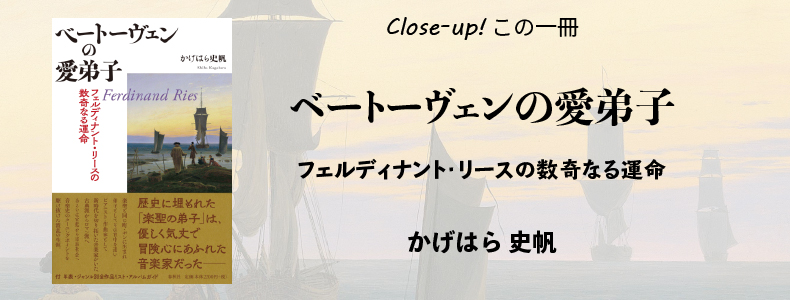序 語る脇役から、語られる主人公へ/かげはら史帆『ベートーヴェンの愛弟子――フェルディナント・リースの数奇なる運命』
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは、金稼ぎやコネクション作りのために貴族の子女を教えることはあったが、それ以外の目的ではほとんど弟子をとらなかった。例外は30代前半の頃だった。難聴に悩まされ、キャリアの岐路に立たされていた彼は、何か思うところがあったのか、プロ志望の若者をふたり門下に入れた。彼らは何年かピアノを学んだあと、それぞれ職業音楽家として巣立っていった。
ひとりはカール・チェルニー、もうひとりはフェルディナント・リースである。
カール・チェルニーが残した業績は、今日でもいくつか知られている。『チェルニー30番』『40番』などと呼ばれる数々のピアノの練習曲を書き残したこと。あるいは、19世紀最大のピアニスト、フランツ・リストを門下から輩出したこと。これらは彼の膨大な活動のごく一部にすぎない。それでも、ピアノの専門家であり名教師であった事実はおのずとわかる。
いっぽうのフェルディナント・リースはどうか。彼について知られている事実は、チェルニーと比べるとはるかに少ない。知名度も劣るし、どういう音楽活動を行ったのかも知られていない。「ベートーヴェンの愛弟子」という一点によって、わずかな人びとに認知されているのみだ。
そのわずかな人びとは、どこでリースに出会うか。ベートーヴェンの伝記や研究書である。リースは、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの人生のドラマを表現する上で、それなりに重宝されている脇役のひとりだ。ウィーン郊外のハイリゲンシュタットでの散歩中、遠くの羊飼いの笛の音が聞こえないと絶望するベートーヴェンの横で、おろおろしている青年が彼だ。あるいは、ナポレオン・ボナパルトがフランス皇帝になったというニュースに激怒するベートーヴェンの横で、やはりおろおろしている青年が彼だ。これらのエピソードには出典がある。『ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する伝記的覚書』という、友人の医師フランツ・ゲルハルト・ヴェーゲラーとともに書かれた一冊の本。これがフェルディナント・リースの名をベートーヴェンの伝記上に、あるいは音楽史上にとどめているほとんど唯一の業績である。
愛すべき人畜無害な証言者として、リースは30代のベートーヴェンの行状を語る役目を果たす。そして師が難聴の苦しみをなんとか飼い慣らし、オペラ『フィデリオ』の初演にこぎつけた頃、彼はなんの説明もないまま、ふっと伝記上から姿を消す。その後、もう一度ウィーンを再訪したとか、どうやらイギリスに渡ったようだとか、いくつかのエピソードは現れるが、それもすぐにベートーヴェンの人生のダイナミックな物語にかき消されてしまう。
いったいこの「愛弟子」は、門下から巣立った後、どこで何をしていたのだろう。
標準的なベートーヴェン伝を読むだけでは何もわからない。
だから、ほとんどの人は知らない。
1811年。ベートーヴェンが『大公トリオ』を書き、文豪ヴォルフガング・ゲーテと手紙を交わし、いよいよ大御所としての貫禄を身につけはじめた頃。
彼が、バルト海の海上でピストルを突きつけられていたことを。
「一艘目の船がやってきて、船長がメガホンで帆を下ろすように叫んだ。何もせずにいると、3発の弾が放たれた。当たらずに済んだ。風が味方してくれ、船長はこちらの船に乗り込もうとしたが失敗した。そこへもう一艘がやってきて逃げられなくなった。また2発が発射された。あっという間に、ピストルの撃鉄を起こした九人の男が僕らの船に乗り込んできた。他の私掠船員たちも来た。船員は15人だった。ぼくたちは巨大な岩山と砕け散る波の間をとおって彼らの港に連行された。ロシア領の島だが、無人島だった」
フェルディナント・リース、ときに26歳。ナポレオン戦争のまっただ中。社会情勢が悪化するなか、平和な音楽環境を求めて、北欧を経由してロシアに向かおうとしていた矢先のこと。乗船した旅客船が、イギリスの船──本人いわく「私掠船」に目をつけられ、バルト海の無人島に強制連行されてしまった。友人に宛てられた右の手紙によれば、彼はその後、水没しかけた小さなジャンク船のなかに軟禁され、船員から与えられた「盗んだ仔牛肉」を食い、悲惨な3日間を過ごしたのち、ようやく解放されたという。
数年前まで自分の隣でおろおろしていた弟子が、ウィーンからはるか遠くの海上でこんな修羅場に巻き込まれていようとは。師が知ったら腰を抜かすような話だ。ところが緊迫感に満ちたこの手紙は、あっけらかんとした一言でしめくくられる。これしきのハプニングがなんだと言わんばかりに。
「ぼくは明日からまた旅を続けようと思ってる。〔……〕アデュー、親愛なる友よ。どうかお元気で」
『伝記的覚書』のなかにも、知られていないエピソードは山のようにある。どうやらベートーヴェンとリースの師弟関係において、おろおろしていたのは弟子の方ばかりではなかったようだ。あるときベートーヴェンは、リースに向かってこう叫んだ。「きみは我の強いやつだな!」──バルト海の事件からさかのぼること7年前。ピアニストとしてのデビュー演奏会の本番中にその一件は起きた。彼は師の事前の忠告に逆らって、禁じられていた高難度のカデンツァ(ソロ部分)をぶっつけ本番で弾くという暴挙に出てしまったのだ。演奏会が終わったあと、ベートーヴェンは弟子に向かってこう言った。
「しかし、きみは我の強いやつだな! あそこでちょっとでも弾きそこなったら、破門するところだったぞ」
リースは、『伝記的覚書』の執筆動機を「故人の完全な伝記を書こうと志す人に『正しい情報源』として活用してもらえるように」と記している。しかし当然ながら、彼自身が主役となるエピソードはベートーヴェンの伝記に採用されにくい。このデビュー演奏会の話が、ナポレオンの皇帝就任の際のエピソードほどに世に知られていないのはそのためだ。
フェルディナント・リースが残した作品や手紙、その他のテキストは、何よりもまず彼自身の音楽人生の所産である。このシンプルな事実は、これまで約二百年にわたってほとんど意識されてこなかった。彼が発した言葉や音楽は、もっぱら、ベートーヴェンの人生を語るための補完的な素材として扱われ、不要な部分は容赦なく捨てられてきた。
しかし、捨てられた言葉、作品、人生は、ベートーヴェンの生涯の活動域を大きく越えたユニークな事件や事象を含んでいる。20歳のとき、リースはやむを得ぬ事情でベートーヴェンの門下から巣立った。それから53歳で亡くなるまで、30年あまりの冒険の日々が彼を待っていた。ちょうどナポレオン戦争の時代と重なった彼の前半生の遍歴は、同じ時代に生きた人びとをも驚かせた。ロンドンの音楽雑誌『ハルモニコン』は、彼を「フランス軍に四度襲われた音楽家」と書きたてた。それだけではない。彼は1810年代から20年代を代表するピアニストのひとりであり、一時期はトップクラスの人気作曲家にもなり、後半生は音楽ディレクターとしてドイツ有数の音楽祭を指揮した。あるときは兵役から逃げまわり、あるときは所属する音楽協会の不祥事を告発し、あるときは最愛の末娘を喪った深い悲しみと抑鬱に耐えた。
作風はベートーヴェンに似ているとよく評された。しかし「似ている」のひとことで済ませられるほど一面的ではなかった。ベートーヴェンの愛弟子という肩書きを、彼は終生、大きな誇りをもって名乗り続けた。これまで世に出たベートーヴェン伝からも、彼の一途な師弟愛や忠誠心を見いだすのは可能だろう。いっぽう、それらが彼の音楽人生にどのように結びついていたかは、彼自身のまなざしを通してでなければ決して語り得ない。1806年、21歳の彼は、はじめてのオリジナル出版作品『2つのピアノ・ソナタ』(op.1)を師ベートーヴェンに捧げた。この献辞のなかで彼は、まだ30代半ばのベートーヴェンを「偉大なるクラシック作曲家」と表現した。そこには、師をたたえるとともに、自分もゆくゆくはその座に連なりたいという願望がはっきりとあらわれている。それは彼の個人的な夢であり、19世紀前半の音楽シーンを象徴する言葉でもあった。
本書は、フェルディナント・リース(1784─1838)の生涯を単独で一冊の本にまとめた、おそらく世界初の伝記である(2019年末時点)。彼の53年の生涯と業績を、幼少期から晩年まで全6章にわたって、時代背景や周辺事情を織り交ぜつつコンパクトに記している。これまではベートーヴェンを語る脇役であった彼を、語られる主人公の側に「転換」することによって見えてくる新しい世界を、本書を通してお届けしたい。「きみは我の強いやつだな!」──賞賛とも呆れともあきらめともつかないその一言は、リースを主人公の座に座らせるための推薦文として機能するだろう。
「転換」は、第1章の冒頭からすでにはじまっている。現在のドイツ中西部、ライン川の下流域沿いに位置する都市ボン。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが生まれた町として世界的に有名なこの場所は、フェルディナント・リースが生まれた町でもあった。