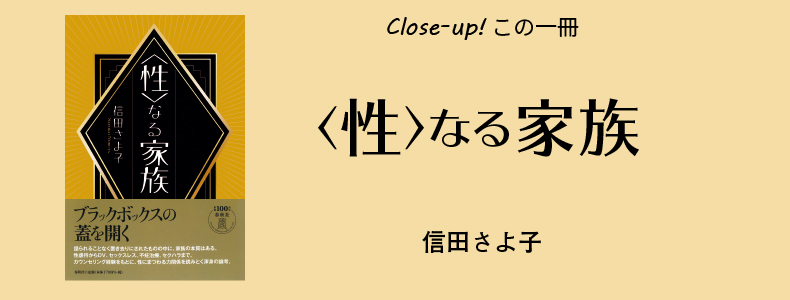「当たり前」を切り崩すことから家族は始まる/信田さよ子『〈性〉なる家族』
性の問題は家族にとってタブーとされてきた。それゆえ、時には性にまつわる力関係が幅を利かせ、さまざまな暴力を生んできたのではなかったか。父・母・子の「当たり前」は同じだろうか。あるいは、男性と女性の「当たり前」、あなたと私の「当たり前」は?
『〈性〉なる家族』は、信田さよ子が長年のカウンセリング経験をもとに、性虐待、DV、セックスレス、不妊治療、セクハラを論じた渾身の一冊である。本書には、現代社会のありよう、そして未来へのヒントがつまっている。
ふりかえってみれば、親子、夫婦、暴力(DVや虐待)、お金、アディクションなど、切り口は異なるが、ずっと家族について考え、それを書いてきた。
開業心理相談の現場で、日々来談者(クライエント)と個別に、時にはグループカウンセリングの場で向かい合うことから生まれる言葉を大切にするよう心掛けてきた。それが枯渇するかどうかが私にとっては一種のサインなのだ。目の前に存在する人たちとつながった具体的な言葉かどうか、書くたびに多くの人の顔や言葉が浮かんでくるかどうか。その問いによって私はこのように書き続ける意味があることを、なんとか確認しているのである。
思想的高みに昇りつめ、抽象化したり、先人の系譜に連なる学派の立場に立つのでもない。そんな私の位置取り(ポジショナリティ)を「ドローン」にたとえたい。地面すれすれに飛び地上の植物の枝葉をくっきりと映したかと思うと、すっと上空に浮かび上がり、手の届きそうな高度から林の全景をとらえる。些末とも思える絡み合った現実を、高度を上げることによってメタ的視点からとらえ、再び個別・具体的地点に帰還する。あくまで現場から出立するという分をわきまえつつも、そんな自在さにあこがれてきたのである。私の身体は地上に縛り付けられているが、カウンセリングにおける意識はドローンのようでありたい、そう思っている。
そんな私がはじめて「性」の問題に取り組もうとしたのが本書である。日々のカウンセリングで性の問題が取り上げられることはそれほど多くはない。もちろん、それに特化したカウンセリングも日本では存在するが。
家族の問題の中で、もっとも忌避されてきたのが実は性の問題だった。そこに触れずとも生きられるし、あたかもそれがないかのように日常生活を送ることはできる。そのため家族におけるジェンダーや性差別、それにまつわる力関係は温存されてきた。秘されたぶんだけ修正される機会がなく、時代がくだっても、家族間、つまり父・母・子の三者の間において、「当たり前」がそれぞれ異なるということが指摘されずにきたといえよう。
先日亡くなった橋本治は「『当たり前』が大問題になる」というタイトルで以下のように述べる。
セクハラという事例の不思議なところは、やる方にその自覚はなくて、やられる方だけが「セクハラだ」と感じるところである。やる側は、「男性優位=自分優位」が当たり前になってしまっているから、その対象となった相手が「被害」を訴えるということが想像出来ない。その行為を成り立たせる一方が「自分の優位性」を当然の前提にしてしまっているから、「被害」を受けてしまった側は、そう簡単に「被害」から抜け出せないし、立ち上がることも出来にくい。
(中略)
する側に自覚のない行為は、される側だけに不条理を一方的に引き受けさせてしまう。セクハラが従来の性犯罪と一線を画すのはここのところで、問われるのは、行為の犯罪性や暴力性ではなくて、「当たり前」の中に眠っている「バイアスのかかった歪【いびつ】な優位性」なのだ。
(『父権制の崩壊 あるいは指導者はもう来ない』朝日新書、二〇一九)
上記を少々補足すれば、DVも虐待も、従来「当たり前」と夫や親が考えてきたことが、される側にとっては一方的な不条理だったことを明らかにし、それを犯罪・暴力と再定義して生まれた言葉なのである。そのことを私は一七年前に『DVと虐待』(医学書院、二〇〇二)で明らかにした。
セクハラは、職場や電車の中といった閉ざされた公共空間における「歪つな優位性」(主として男性にとっての「当たり前」)の発露なのであり、やる側に「加害者意識」などない。同じことが、性虐待にも通じる。
DVや虐待については防止法ができてから二〇年近く経つあいだに、少しは人々の意識も変わったと信じたい。もし変わったとしたらそれは、相変わらず修正されずにいる「当たり前」、つまり男性における「バイアスのかかった歪な優位性」の発露が問題視される土壌ができたということだろう。#MeToo ムーブメントの広がりは、そのことを表している。
家族における性の問題を取り上げようと思った大きな理由は、「当たり前」には複数性があること、そして男性(父、兄など)の当たり前が時には女性(娘、妹など)にとっての理不尽な経験を生むということを伝えたかったからである。後者に母を入れるかどうかは、結婚し親になるにつれ、彼女たちの当たり前が男性と齟齬のないように同化し変化していくかどうかにかかっているだろう。
明らかな暴力を告発するのは簡単である。しかし社会に埋め込まれた、それこそ文字ができてからずっと当たり前とされてきたことを、もっとも親密である関係=家族に軸足を置いて、当たり前でないと感じる立場から描く必要がある、そう思ったことが本書の最大のモチベーションとなった。
第1章は主として性虐待について、第2章は夫婦のあいだの性について、第3章は性加害をめぐる状況について、第4章はトラウマについて、そして家族と国家の性暴力の相似について述べる。家族における性の問題は、日常性を支える深い部分で大きな役割を果たしているのだが、ほとんど表面化することはない。カウンセリングの経験にもとづいて、この問題についてさまざまな角度から、さまざまな関係をとおして述べてみたい。大きすぎるテーマにも思え、掘り下げが不十分なところもあるが、今論じなくてはならないと思うことを盛りこんだ。
性虐待、ジェンダー、セクシュアリティといった性にまつわる問題は、家族の基盤に在りながら、意図して裂け目をつくらなければ、視野には入らない。しかし、そこから見えてくるものこそ、家族の未来を考えるために欠かせないのではないか。そのような思いに駆動されて本書をしたためよう。
(『〈性〉なる家族』「はじめに」より。サイト掲載にあたり、タイトルを変更しています)