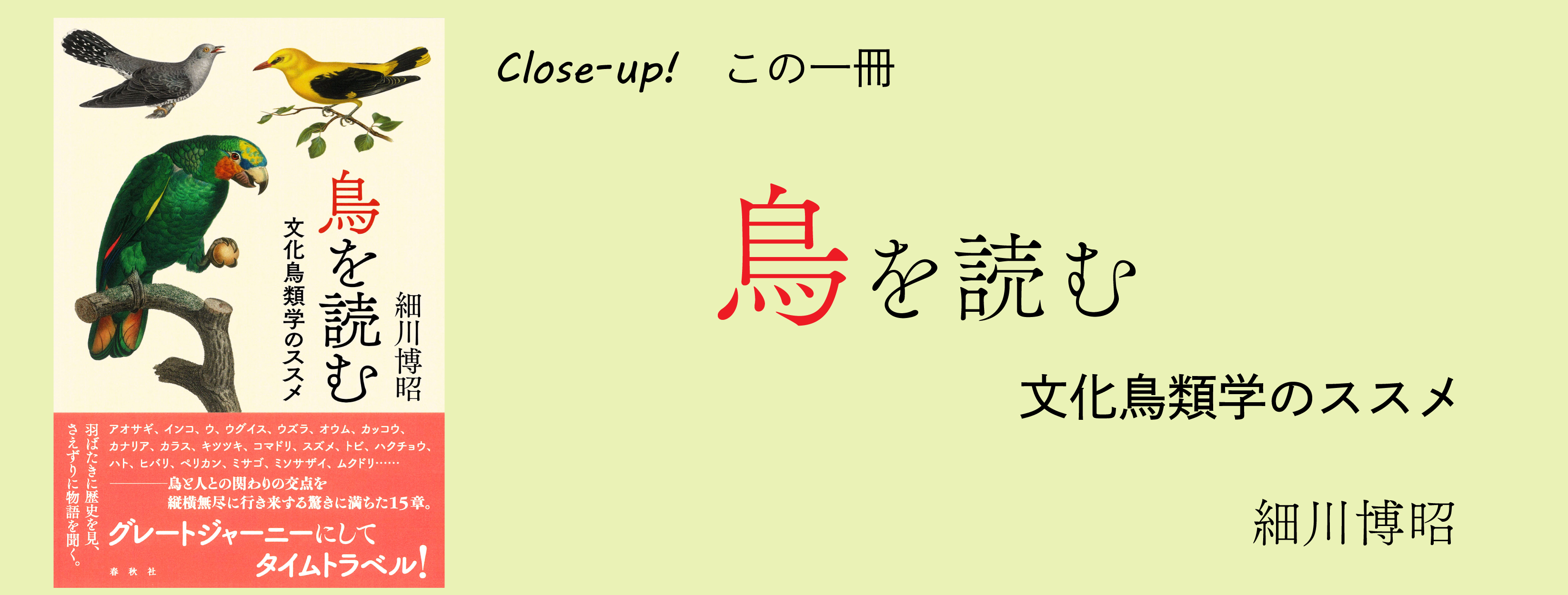鳥と人との関わりの交点を縦横無尽に行き来する驚きに満ちた15章/細川博昭『鳥を読む――文化鳥類学のススメ』
古来、人と深い関係性をもつ生き物、鳥。美しい羽毛をまとい、音楽のようにさえずり、大空を自由に飛翔する様はいにしえの人々を魅了し、イマジネーションをかき立てました。その証左のごとく、シンボルとしてモチーフとして、古今東西の美術や音楽、文学、説話などさまざまな様式の芸術や記録、遺物のなかに彼らは永久に姿をとどめます。本書は、ハト、カラス、アオサギなどの鳥種ごとに人との関わりの歴史、様相を俯瞰。連綿と続いてきた鳥と人との関係に「文化鳥類学」というユニークな視座で迫ります。
はじめに
人間の歴史といっても、そこに登場するのは人だけではない。鳥との関わりも、たしかに歴史の一部だった。あらためて歴史を俯瞰すると、さまざまな土地、さまざまな時代に、鳥と人との接点を見つけることができる。関係は継続しているものもあれば、短期間のものもあった。途絶えてしまったものもある。武器や道具――矢羽根や羽箒(はぼうき)、衣類などに羽毛が活用された鳥もいた。
人の言葉を話す鳥は人気者となり、愛玩されるなかで独特な地位も得た。
大きなきっかけとなったのが、マケドニアの王アレクサンドロス三世の東方遠征である。インドはもともと複数のホンセイインコ属の鳥が暮らす土地であり、支配者は古くから話すインコを宮殿内に置いていた。アレクサンドロス三世の部下がそんなインコを遠征先のインドから本国に連れ帰ったことで、人の言葉をまねる鳥の存在はギリシア世界と、続くローマ世界の知るところとなった。そのインコは、オオホンセイインコ。出会いのエピソードから、のちに「アレクサンドロスのパラキート」と名づけられる鳥である。
物珍しさだけでなく、ふれあいによって生まれる楽しみから手許に置きたがる貴族も少なからずいた。インコはインドからヨーロッパに継続的に輸入されるようになり、それは中世になっても続いた。結果として、「おうむ返し」は、ヨーロッパでもよく知られるようになった。
日本人もおそらく歴史の初期に、おなじ種か近種のインコと出会っている。飛鳥時代以降、朝鮮半島の国などからオウムやクジャクが贈られたが、渡来したインコ目の鳥も、正倉院の宝物に描かれたオウムも、実際にはそのほとんどがホンセイインコ属の鳥だったと考えられている。史書にオウムと記されていたのは、当時はまだインコという言葉がなかったためである。
清少納言が『枕草子』でふれ、藤原定家が日記に綴っているように、渡来したインコは人の言葉を話した。和歌の技法や日常の会話において「おうむ返し」が定着したのは、こうした史実があったがゆえである。
オウムは人の言葉を話す。初渡来からの千年間で、「おうむ返し」という言葉や概念もふくめて、その理解は広がっていき、一度も目にすることのなかった人々にまでインコは知れ渡った。
それゆえ、江戸時代になって市中の鳥屋や、当時の花鳥園的存在だった花鳥茶屋や孔雀茶屋で生きたオウムやインコを実際に見て、「あぁ、なるほど。インコやオウムはたしかに人の言葉を話すのだ」と実感した人も多かったにちがいない。
こうした鳥との交わりもまた、歴史の中に残る興味深い事実のひとつである。
人間に近い場所を生活圏とした鳥の一部は、「害鳥」と呼ばれることもあった。そうした鳥は田畑など、立ち入ってほしくないエリアから追い払われるのが常だった。案山子(かかし)はそんな目的のために、世界の各地でおなじような姿で生まれた。駆除するのではなく、入ってほしくない場所から生き物をゆるやかに追い払うために。それは共存のひとつのかたちでもあった。
かかしの英名「Scarecrow」のscare は「追い払う」の意であり、crow はもちろんカラスである。
カワラバトは人のそばで安全を見つけ、繁栄を得た。帰巣本能と飛行ルートの判断能力、ロケーションを記憶する能力が鳥類の中でもとりわけ優れたものであることに気づいた人類は、「伝書鳩」を誕生させ、長い時間を共有した。伝書鳩はローマ帝国の重要な通信インフラになっただけでなく、帝国が崩壊したのちも帝国の版図だった土地に新たに誕生した国々に引き継がれて現代にいたる。電子的な通信手段が活用されるようになる以前の二十世紀の半ばまで、伝書鳩は軍事と経済の情報伝達などを中心に利用され続けた。
また、羽毛色で白黒の対比が行われることもあった。「烏鷺(うろ)の争い」という言葉もあるように、日本ではシラサギとカラスが対比の軸となったが、ヨーロッパではおおむね白いハトと黒いカラスが軸となった。聖書のノアの方舟における陸地の発見譚でも、白いカワラバトと黒いワタリガラスの対比が見られた。シェイクスピアは『ロミオとジュリエット』において、ロミオ視点で「黒いカラスの中に舞い降りた純白のハト」と表現することでジュリエットを称賛した。
そこには「白=善、聖」と「黒=悪、不吉」という図式も見える。善悪対比の図式は、アジアにくらべてヨーロッパのほうが強い印象があった。このような、鳥に向ける視線の東西のちがいを紐解き、示すことも本書の目的とした。
スズメやカラス、ウ、ハクチョウ、ヒバリ、トビ。広くユーラシアに分布する鳥は多い。亜種や近種がアメリカなど他大陸に分布する鳥もいる。ある鳥の印象が世界に共通する例もあれば、地域によって異なる例もあった。民族、文化圏によって、鳥と人間との関係も異なってくる。共通点やちがいは、神話や伝説、音楽との接点、愛玩のしかた、その鳥の利用などにも見えていた。
特定の鳥に着目し、国や地域や民族がもつ文化誌の比較を通して、人間にとってその鳥がどんな存在だったのか解き明かしていくことも、本書が目指したところである。
比較文化鳥類学。執筆中ずっと、キーワードとしてずっとその名と概念が頭の中にあった。
たとえば、広くユーラシアに暮らすカッコウは、日本でもヨーロッパ各国でも鳴き声が名称の由来となった。どんな鳥よりもネーミングに近さが感じられたが、商売人がもつ印象は国によって大きくちがっていた。日本にはカッコウの別称として「閑古鳥」という名前がある。それは店が寂れたイメージとして商売人が強い忌避感をもつ名でもあった。
時刻がくると鳥が飛び出して鳴く、絡繰(からくり)仕掛けの壁掛け時計は、ヨーロッパでは「カッコウ時計」の名で知られていて、世界の各国に輸出されている。しかし、日本のみが「ハト時計」に名称変更をして、やっと受け入れられることになった。「閑古鳥が鳴く時計など縁起が悪い」と強い拒絶反応が出たためである。鳥の文化誌を追っていると、ときおりこうした興味深い事実にもぶつかる。興味は尽きない。
鳥種によって章を構成した本書は、音楽や神話など鳥の文化誌をテーマごとにまとめた『鳥と人、交わりの文化誌』との相互補完を目的に編まれたものである。本書と、『鳥と人、交わりの文化誌』の二冊を縦糸、横糸として、鳥と人の歴史が描く壮大なタペストリーを眺めていただけたら幸いである。