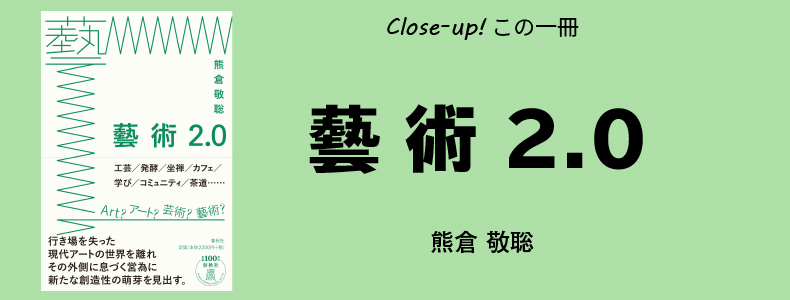『藝術2.0』をふりかえる、そしてこれから 熊倉敬聡
人類の新たな創造性を探し求めて、私は旅に出た。その旅の記録が、この5月に上梓した『藝術2.0』である。
この書で詳述したが、私はArt、そしてContemporary Art(なぜあえてアルファベット表記にするかは本書に当たっていただきたい)が、今や人類の創造性の表現として歴史的使命を終えつつあるという認識をもっている。では、(Contemporary)Art以降、人類の創造性はどこに行き、どのような形をとり、どのような生き方・生存の可能性をもたらしてくれるのか。秀れた直感力をもつ少数の者たちがすでに実践し始め、しかしおそらく未だ誰も明確に名づけ語りえていない、その“何か”を仮初めに「藝術2.0」と名づけてみて、無謀にも語り始めようとした著作である。
そう、この書=旅は実に無謀であった。旅立つ時には、わずか三つほどのおぼろげな道しるべしかなかった。一つは、旅立つ「岸」の在り処、すなわち(Contemporary)Artの終着点。二つ目は、私が移り住んだ京都という町の特異性、そしてその特異性が醸す、単に「伝統」的でも「現代」的でもない、“第三の”創造性の気配。最後に、その「気配」に共感する仲間たちの存在。これらの道しるべを頼りに、己のこれまで培ってきた知と感性の航海術、そして何よりも直感を信じて、かくも無謀な探索の旅に出たのだった。
だが、危ういながらも旅が進むにつれ、私は徐々に自分が書いているという感触よりも、“ある者”たちによって書かされている――彼らが私に取り憑き、私の手を勝手に動かしているような感覚を覚えた。私の無意識の中に、彼らがすでに潜んでいて、目には見えないもう一つの道しるべとなり、旅を促し、導いているかのようだったのだ。因縁――ある死者たち、そして生者たちが、私の預かり知らぬところで、示し合わせ、企み、こっそりと無意識裡に囁きつづける。それら縁起する言葉たちを、私はただただ書き留めていく…。
その最たる因縁が、北軽井沢でひそかに逢瀬を重ねていた哲学者田辺元と小説家野上弥生子との運命的出逢いであり、しかも晩年の田辺がステファヌ・マラルメの『双賽一擲』と格闘していたまさにその時、野上がこともあろうか『秀吉と利休』を執筆していた、という決定的な因縁であった。
本書をお読みいただけるとわかるように、マラルメと田辺、そして利休と野上という「星座」が、おそらくは旅立つ前から私の無意識の彼方ですでに煌めいていて、私に誘いかけ、旅支度をするよう促していたのではなかったか。そう思われるほど、その「星座」の誘いは必然であったと脱稿した今となって改めて感じ入る次第である。この四人以外にも、共鳴するように、他の星座=因縁が閃きかけてきた。それらの意識下の道しるべも頼りに、その囁きに耳を澄まし、指し示す方向へと、私は自然と舵を取っていた…。
タイトルに「藝術」という文字を使いこそすれ(なぜわざわざ旧字「藝」を用いたかその由縁は本書を参照されたい)、本書に何がしかのオリジナリティがあるとしたら、人類のこれからの創造性を、Art(ないし「芸術」「アート」)という言説の呪縛の“外”で語り始めている点であろう。本書で詳述したが、人類は近代以降最近まで(そして人によってはいまだに?)創造性をArtに仮託してきた。なぜか、視覚的な創造性は白い四角い平面に多彩な絵具を塗ること、聴覚的な創造性は白黒の小さい木片を叩くこと、等々に限ってきた。世界に存在するあらゆるものに視覚的表現は可能であり、世界に存在するあらゆるものが音を発しうるにもかかわらず、人類は、西洋近代が発明したArtへと創造性を局限したのだった。
その創造性を局限し究めるArtの論理に、決定的な異議申し立てをし、いわんやその全面的否定こそ逆説的にArtなのだと嘯いてみせたのが、アヴァンギャルドたち、なかんずくマルセル・デュシャンであった。便器という、美の対極にあり、それこそ「用」をしか足さないものを、「これがArtである」というパフォーマティヴな言明=演出を弄することにより、Artの“外”をArt化する、Non-Art=Artという自家撞着の論理ならぬ論理を、アートワールドに持ち込んだ、いやその論理こそをアートワールドに仕立てたのが、デュシャンの画期的な『泉』であった。
以降、(Contemporary)Artは、このデュシャンの天才的奸計を反復するしか能がないかのように、あらゆるArtの“外”、Non-Artを「これがArtである」と僭称し続けてきた。しかし、(あたかもガイアという有限な“外”をMoneyに還元=搾取し続けてきた、もう一つの西洋近代の「発明」である資本主義が今や歴史的限界に達しつつあるのと呼応するように)Artもまた、自らへと還元すべき“外”=Non-Artをもはや決定的に喪失しつつある。それどころか、究極的な“外”=Money――絶対的な“質”としての「美」という価値が決して同一化してはならなかった絶対的な“量”としての「貨幣」という価値=Money――と野合しつつあるというまさに末期的事態。最近のアートマーケットの異常なまでの活況は、このArt=Moneyという、「近代」の人類史的断末魔の阿鼻叫喚ではなかろうか。
しかし、人類の創造性は何もこれに尽きた訳ではない。ひそやかに、(Contemporary)Artの世界が預かり知らぬところで、別な形をとり、別な在り方を模索しているのだ。それを私は今回あえて「藝術2.0」と名づけ、そのささやかだが確かな現れを「工芸」「発酵」「坐禅」「カフェ」「学び」「コミュニティ」「茶道」などと今まで呼ばれてきた営みのうちに探ってみたのだった。
私は、その探求の旅の中で、藝術2.0を特徴づける秘鑰を探り当てようとした。その一つを、私に多大なインスピレーションをもたらしてくれた発酵デザイナーこと小倉ヒラクの『発酵文化人類学』の言葉の内に見出した。小倉は、クロード・レヴィ=ストロースの有名な二分法「冷たい社会」と「熱い社会」を発酵学的に変奏しつつ、現今の醸造家たちのクリエィティヴな挑戦を、「冷たいクリエーション」(先祖伝来の発酵文化)の「熱いクリエーション」(現代的感性とテクノロジー)による再デザイン化、あるいは「オーガニック軸」に沿って原点回帰しつつも、同時に「イノベーション軸」に未来的可能性を開花させるような、いわば「冷たく」も「熱い」逆説的なクリエーションと、捉えていた。
さらに彼は、私が試みたインタビューの中で、「熱いクリエーション」による再デザイン化を可能にするのは、醸造家たちが蔵している「OSとしてのアート」なのではないかと問うた。彼自身はそれ以上含意を詳らかにしなかったが、私はそれを受け、以下のように推察した。「OSとしてのアート」とは(彼の行論からいって)もちろんArt(ないしContemporary Art)という言説のことではなく、それとは全く異質な何か、なのではないか。醸造家たちの発言から推すと、おそらくは彼らがバブル時代以降摂取してきた多種多様なデジタル文化と、ある時点でその飽和に嫌気がさし、バックパック一つで地球のあちこちをさまよい歩き体験・狩猟採集した文化的・美的断片との、奇妙な混成体ではなかったろうか。その混成体、その人独自の「小さな物語」、すなわち「OSとしてのアート」が、どこぞのローカルな「冷たい」発酵文化と出会い、それを再デザインし、特異な発酵食を微生物たちと共に創りだしていく。その「冷たく」も「熱い」クリエーションの逆説的弁証法こそ、藝術2.0の秘鑰の一つであると、私は確信したのだった。
しかし、執筆を終えた今、改めて振り返ると、秘鑰の一つと見えたこの弁証法は、例えば岡本太郎が『日本の伝統』などで唱えた、伝統と創造の弁証法と同じものなのではないか。
「伝統は自分にかかっている。おれによって生かしうるんだ、と言いはなち、新しい価値を現在に創りあげる。伝統はそういうものによってのみたくましく継承されるのです。形式ではない。受けつがれるものは生命力であり、その業―因果律です。註1」
だとすると、岡本のみならず、「東」と「西」、「日本」と「欧米」の狭間で文化的に実存的に懊悩した「芸術家」たちの系譜(岡本太郎、イサム・ノグチ、勅使河原蒼風…)が挑み、世に突きつけた「熱く」も「冷たい」作品群と、藝術2.0はどこが違うのか。今とりあえず私に言えることは、二つだ。一つは、双方とも、その(岡本的に言って)精神的「対極主義」は共通しているかもしれないが、「芸術家」たちは、その表現を「造形作品」へと収斂させたのに対し、藝術家2.0たちは必ずしも「造形」に拘泥せず、自分が修行・修業した領域で(発酵、坐禅から茶道まで)独自の「再デザイン化」を探究している点。もう一つは(その点と連動するが)「芸術家」たちの「熱いクリエーション」のOSがほぼ「大きな物語」としての(Contemporary)Artのそれであるのに対し、藝術家2.0たちのOSは、今見たように(小倉は「OS」という用語をあえて用いているが実のところ)「大きな物語」としてのOSではなく、各自が実存的・文化的に自らの内で醸した特異な「小さな物語」であるという点。いずれにしても、今後両者の共通点・相違点を探れば、藝術2.0の要諦がより明瞭になるはずだ。
脱稿後、心に去来したまた別な想い、そして問い。私はこの書でほとんど全く「民藝」に言及しなかった。なぜなのか。読者によっては、私の主張する「藝術2.0」の内に「民藝」の余響を聴き取るかもしれないのに、である。
柳宗悦は、例えば『南無阿弥陀仏』で、法然・親鸞・一遍の「浄土門」(=他力道)を、絶えず禅宗などの聖道門(=自力道)に対比しながら論じている。だが、その対比は、彼自身が言うように、単に両者が対立し、反目しあっていることを示さんがためではない。そうではなく、両門・両道はむしろ同じ頂きをめざす二つの異なる道筋だと言う註2。聖道門=自力道が「難行道」であり、「己の大を覚る道」、「智者、徳者、強者」「天才の一道」であるのに対し、浄土門=他力道は「易行道」であり、「己の小を省る道」、「小さく哀れな人間がくぐる門」であると言う註3。民藝を作る工人=凡夫たちがくぐりうるのは、もちろん後者の門であり、彼らの「心と手との数限りない反復」が「念仏と同じ不思議」を生み、「自己を離れ自己を超え」、「品物は浄土につれてゆかれる」のである註4。
翻って、藝術2.0は聖道門=自力道なのか、浄土門=他力道なのか。私は、『藝術2.0』で、藤田一照、田辺元、久松真一、千利休らを取り上げ、その「禅宗」的実存の深掘り、自己のゼロポイント=〈空・無〉への「参入」と、そこから〈色・有〉への「還帰」という実存的イニシエーションを「V」という形象で表してみた。が同時に、その「V」が各々の仕方で「いびつ」であること、深浅・広狭において特異であること、「物足りない」(藤田)ままでも「差し控えて」(田辺)もいいことを強調した。しかも、この「いびつなV」が必ずしも単独の苦行である必要はなく、それ自体「純粋なくつろぎの形」(藤田)であるのみならず、それぞれに「いびつなV」たちが集って、「いびつな○」を成し、互いが互いを「歓待」しあいながら、「一期一会」を全身全霊で祝福する、そんな藝術2.0の実践の形をも描いてみせた。この「いびつなV」たちが形作る「いびつな○」により、私は図らずも聖道門=自力道と浄土門=他力道の「交わり」を素描したのではなかったか。が、この書ではまだ素描にすぎなかったがゆえに、今後、特に後者をいっそう探究することにより、「交わり」の現代的可能性(=新しいコミュニティ論?)を醸成していきたい。
最後に、本書の旅の途上で予期しながらも、あるやもしれぬ次の旅へと先送りしてしまった逗留点について触れたい。
私は、「藝術2.0」として、あるセックス思想と実践、そしてマネー思想と実践に、しばし留まろうと思っていた。人類のこれからの創造性が、この対極的(?)な領野で発揮され、全開していくことを願っていた。人類をこれほど根源的に突き動かしているにもかかわらず、なぜかほとんどすべての宗教・宗派が極度にタブー視するセックスとマネー。そのコペルニクス的転回=再創造に、人類の創造性がいかんなく発揮されるのかどうか、そこにこそ人類の未来が賭けられていると言っても過言ではないだろう。
もし、『藝術2.0』の続編があるとすれば、私はぜひこの二つの領野に長く逗留し、そのコペルニクス的転回=再創造を考究したい。
註
1 岡本太郎『日本の伝統』、2005年、光文社、Kindle版位置no.343。
2 柳宗悦『南無阿弥陀仏』、1986年、岩波書店、35頁。
3 同書、112〜115頁。
4 同書、44頁。