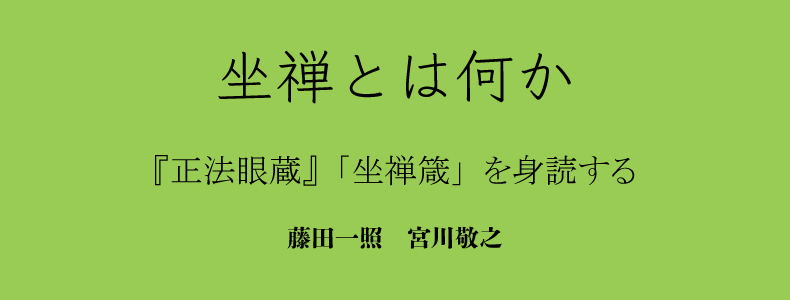仏仏要機、祖祖機要
【宮川敬之】身読コラボ⑯
坐禅箴は、大宋国慶元府太白名山天童景徳寺、宏智禅師正覚和尚の撰せるのみ仏祖なり、坐禅箴なり、道得是なり。ひとり法界の表裏に光明なり、古今の仏祖に仏祖なり。前仏後仏、この箴に箴せられもてゆき、今祖古祖、この箴より現成するなり。かの坐禅箴は、すなはちこれなり。
坐禅箴 勅諡宏智禅師 正覚 撰
仏仏要機(〇五微)、祖祖機要(●十八嘯)。不触事而知(〇四支)、不対縁而照(●十八嘯)。不触事而知(〇四支)、其知自微(〇五微)。不対縁而照(●十八嘯)、其照自妙(●十八嘯)。其知自微(〇五微)、曾無分別之思(〇四支)。其照自妙(●十八嘯)、曾無毫忽之兆(●十七篠)。曾無分別之思(〇四支)、其知無偶而奇(〇四支)。曾無毫忽之兆(●十七篠)、其照無取而了(●十七篠)。水清徹底(●八斎+くさかんむり)兮、魚行遅遅(〇四支)。空闊莫涯(〇九佳)兮、鳥飛杳杳(●十七篠)。
いはゆる坐禅箴の箴は、大用現前なり、声色向上威儀なり、父母未生前の節目なり。莫謗仏祖好なり、未免喪身失命なり、頭長三尺頸長二寸なり。
仏仏要機。
仏仏はかならず仏仏を要機とせる、その要機現成せり、これ坐禅なり。
祖祖機要。
先師無此語なり、この道理、これ祖祖なり。法伝・衣伝あり。おほよそ回頭換面の面面、これ仏仏要機なり。換面回頭の頭頭、これ祖祖機要なり。
『坐禅箴』は、大宋国慶元府太白名山天童景徳寺の、宏智禅師正覚和尚が撰述したものが、仏祖そのものであり、坐禅という箴(はたらき)であり、「要所を言い得ている」のである。この『坐禅箴』だけが、すべての世界のすべての場所に光明となり、むかしから今にいたる仏祖たちを、仏祖として指導しているのである。釈尊以前の仏も、釈尊以降の仏も、この『坐禅箴』の坐禅の世界のうちにあり、今の祖師もむかしの祖師も、この坐禅の世界によって修行を露わにしていくのである。そのような『坐禅箴』とは、つぎのようである。
坐禅箴 勅諡宏智禅師 正覚 撰述
それぞれの仏たちの本質的はたらき
それぞれの祖師たちのはたらきの本質
ものごとに触れることなく知る
対象に対面することなく照らし出す
ものごとに触れることなく知る――その智慧は自然に目立たない
自然に目立たない智慧は、分別する思考を全く持っていない
自然に微妙な照明は、わずかの分離も全くない
分別する思考を全く持っていない智慧は、二分法に陥らず一なるものを見る
わずかの分離も全くない照明は、執着することなく明らかである
水は底まで透き通っている、魚はゆっくり、ゆっくり泳いでいる
空は限りなく広大である、鳥は遠く、遠く飛んでゆく
ここで言われている「坐禅箴」の「箴」とは、仏祖のはたらきの現前という意味であり、音や形を乗り超える修行のありさまの意味であり、父母が生まれる以前のわたしのすがたの意味である。また、仏祖を謗ることのないよき言葉であり、かならず身を喪い命を失する坐禅修行であり、そして頭の長さが三尺、首が二寸という仏の姿である。
仏たちは、かならず、本質的なはたらきとして仏たちを見ている。このはたらきが現前するということが、まさしく坐禅なのである。
「先師は「無此」の語である」とは、この(本質的はたらきとして仏たちを見る)道理なのであり、それを受け継ぐものを祖師たちと言うのである。法が伝わり、衣が伝わるというのも、この本質的はたらきが現前することである。そもそも「頭を回して顔を換える」その顔たちは、みな仏たちのはたらきのことであるのである。「顔を換えて頭を回す」その頭たちも、みな祖師たちのはたらきの本質があることなのである。
〈「宏智坐禅箴」〉
坐禅についての指導書や覚書が数ある中で、道元禅師が、「ひとり法界の表裏に光明なり(これだけがすべての世界のすべての場所に光明となるものだ)」と賞賛したのは、宏智禅師正覚(わんしぜんじしょうがく 1091-1157)が記した「坐禅箴」でした。宏智禅師とはかつて、道元禅師の中国での修行先となる天童山景徳寺の住職を長年勤め、その復興に寄与した人物で、道元禅師の師である如浄禅師も追慕されていた人物です。道元禅師は、「宏智古仏(偉大なる古代の仏、宏智様)」と呼び、賞賛されています。この事跡については、一照さんがしっかりとご紹介くださっているので、そちらを参照してください。私としては、道元禅師が「宏智坐禅箴」のどういったところを賞賛したかについて、しぼって考えたいと思います。
この連載の第2回にすでに論じたことですが、「宏智坐禅箴」を本歌取りするかたちで、道元禅師もご自身の「坐禅箴」を書かれており、それが『正法眼蔵』「坐禅箴」巻の最後に出てくる「永平坐禅箴」です。そして、この両篇を比較してみると、道元禅師の宏智禅師への賞賛とは、単純なものではなく、非常に独特なものであることがわかるのです。なぜそのように判断できるのかについて、もう一度振り返っておきましょう。
そもそも漢詩では、一つの詩のなかで、句末の字の音の母音部分のひびき〔韻〕を合わせるということを基本にします。どういう字が同じ韻であるのかという、韻の分類については、道元禅師の時代である宋代と、現代に使用する分類とは多少の違いがあるのですが、煩雑になるのでとりあえずいまは現代に使用する分類で考えます。現代に使用する韻の分類は百八種類あり、その内訳は、平板な音である平声が三十種類、上下抑揚を持つ音である仄声が七十八種類です。上に挙げた『坐禅箴』の句末の白黒丸印をつけたものがこの押韻部分を指していて、白丸(〇)が平声、黒丸(●)が仄声です。カッコ内の数字と漢字がその分類を指します。上のように、宏智禅師『坐禅箴』は、平声(〇)では四支と五微、仄声(●)では十七篠と十八嘯で押韻している漢詩であるといえるということです。さらにこれは、足を交互に出して歩くように平仄が交互に現れる漢詩ということで、「進退格(しんたいきゃく)」と呼ばれる形式であるということも提示しました。
ある漢詩を尊重して自作の漢詩を作る場合、押韻を継承することが一般的です。継承のしかたにはおおよそ、依韻(えいん)・用韻(よういん)・和韻(わいん)の三種類があります。最高度の敬意を払うなら、和韻をするのが作法であり、実際道元禅師ご自身も、師匠である如浄禅師の「風鈴の偈」に対しては和韻した詩偈を書き、敬意を表しています(『永平広録』)。
道元禅師は、評価としては「宏智坐禅箴」を非常に高く評価していますが、いっぽうで自身の「永平坐禅箴」を書く際に、和韻して敬意を払うという作法については無視しています。それどころか、「永平坐禅箴」では、平仄そのものを交代させて、特定の句末で韻を踏む漢詩であることすらやめてしまい、四六文という散文になってしまっているのです。ここに、道元禅師の賞賛の独特さが現れているといえます。
〈賞賛の独特さ〉
このような賞賛の独特さは、一体なぜなのか。私はまず、「永平坐禅箴」への改変のポイントを次のように推測しました。
禅の伝統での、言葉と言葉を超えた悟り、知覚と知覚を超えた悟り、判断と判断を超えた悟り、表層と深部、通常と超越といった二分法があるわけですが、しかしそこには原理上のつまずきがいつも埋設されています。それはなんでしょうか。(中略)そうした考察は、あらかじめ作られた二分法のなかで安全になされているにすぎないということです。(中略)「宏智坐禅箴」に見える進退格は、平声と仄声との安定した交替であり、それは二分法を説明するその説明自体は見事であっても、いやそうだからこそ、そこに現実の坐禅は出来しないのです。道元禅師が行った改変は、この二分法を動揺させ、「運動」をもちこむことだったのではないでしょうか。(中略)「宏智坐禅箴」が二分法、二元構造であり、二次元的であるのに対して、いわば「永平坐禅箴」とは三肢構造であり、三次元的なのです。もちろんこの三元目は、「運動」すなわち行によってのみ現れるなにかということなのですが。(第2回「二篇の「坐禅箴」」より)
私は「宏智坐禅箴」から「永平坐禅箴」への改変のポイントを、「運動」を持ち込むことであると考えます。この運動とは、二分法を乗り超えようとすることであり、「行」であり、あるいは前回で述べた「坐仏」や「行仏」、あるいは「光明」でもあると思います。それはいわば「はたらき」への注目です。この「はたらき」については、道元禅師はよく、「機」という漢字によっても示しています。『正法眼蔵』にも「全機(ぜんき)」や「都機(つき)」といった巻名によって、この「はたらき」を示そうとしています。奥村正博老師は、この「はたらき(機)」を「total function全体的働き」と訳されます(『「現成公按」を現成する』p.178 春秋社2021)。それは、「自己とダルマを含む「全体的な働き」」(同)であるということです。道元禅師の「坐禅箴」の改変は、この「運動」「はたらき」「行」への強調であると私は考えます。
そのように考えることによって、なぜ道元禅師が「宏智坐禅箴」を「ひとり法界の表裏に光明なり」として評価したのかが、逆にあぶり出せるように思います。「宏智坐禅箴」は「仏仏要機/祖祖機要」としてはじまっています。道元禅師はこの冒頭の二句に対しては一言も変えず、そのまま継承します。「永平坐禅箴」でそのまま継承されている「宏智坐禅箴」の言葉は、実はここだけです。つまりそれは、「宏智坐禅箴」において、最も重要なのはこの冒頭二句であると道元禅師が考えているということです。なぜこの部分が重要なのか。それは坐禅の本体を、「仏と祖師、私たちを含む、すべてのものごとの全体的はたらき」としての「機(ファンクション)」として見ているからです。この「はたらき」は、二分法を乗り超える「運動=行」なのであり、そのことを「それぞれの仏たちの本質的はたらき」と呼んでいるのです。このことをはっきりと宣言したからこそ「宏智坐禅箴」が道元禅師にとって重要であったと考えられます。「仏仏の要機」について、道元禅師はつぎのように展開されています。
仏たちは、かならず、本質的なはたらきとして仏たちを見ている。このはたらきが現前するということが、まさしく坐禅なのである。
あるいはまたつぎのように言われました。
ここで言われている「坐禅箴」の「箴」とは、仏祖のはたらきの現前という意味であり、音や形を乗り超える修行のありさまの意味であり、父母が生まれる以前のわたしのすがたの意味である。
とはいえ「全体的はたらき」ということがらは、非常に提示しにくいことがらです。その困難の理由とは、ひとえに、観察者と対象との距離をとることができず、主体が客体を観察し記述するという表現方法をとることができない、ということに依っています。観察者も対象も同じ「はたらき」、つまり相互の影響を与え合ってしまっています。そうした相互の影響を無視し、区分して、「わたし」が「全体的はたらき」を「知る」という表現をしてしまうと、「全体的はたらき」の提示としては決定的なまちがいとなってしまうということです。
けれども、言語を語るとは、基本的に「区分をする」ということです。区分をせずに言語を語ることはできないのです。ならばどうやってこの「全体的はたらき」を述べればよいのでしょうか。
〈三肢構造ふたたび〉
実際に、「宏智坐禅箴」もまた、「仏仏要機/祖祖機要」を、「仏や祖師たちが伝えてきた大事な教え」あるいは「大事なさとりの境地」として、客体化し、それを語ろうとする傾向があることは否めません。しかし、「大事なさとりの境地」を語ることが、安定的であればあるほど、それは区分的であるということなので、「全体的はたらき」を述べることから外れてしまうという逆説となってしまいます。
道元禅師の「宏智坐禅箴」の読み替えは、この「はたらき」を全面化することを眼目としていると私は推測します。そうした狙いの延長上に、平仄の継承や和韻することからの回避、漢詩であること自体の解体がつながり、結果的に、「永平坐禅箴」への書き換えがなされたのではないか、と考えるのです。「はたらき」を全面化すること、安定的な区分であることを回避すること、それはどのように行われたのでしょうか。たとえばつぎのように述べられています。
いはゆる坐禅箴の箴は、大用現前なり、声色向上威儀なり、父母未生前の節目なり。莫謗仏祖好なり、未免喪身失命なり、頭長三尺頸長二寸なり。
ここで言われている「坐禅箴」の「箴」とは、仏祖のはたらきの現前という意味であり、音や形を乗り超える修行のありさまの意味であり、父母が生まれる以前のわたしのすがたの意味である。また、仏祖を謗ることのないよき言葉であり、かならず身を喪い命を失する坐禅修行であり、そして頭の長さが三尺、首が二寸という仏の姿である。
「坐禅箴」の「箴」とは「仏祖のはたらきの現前」のことだ、と示してから、そのあと五つの表現が続きます。それぞれの言葉の典拠や意味合いについては、一照さんが語って下さっているので、そこに甘えて、ここではこれらの表現の組み合わせがなにを構成しているのかに注目します。ここに挙げられた六つの表現は、三つずつの二組の言い回しなのではないかと思います。一組目は「大用現前」「声色向上威儀」「父母未生前の節目」であり、二組目は「莫謗仏祖好」「未免喪身失命」「頭長三尺頸長二寸」です。これらは、一組目は、仏のはたらき、修行のありよう、言葉による区分(の限界)を指し、二組目は、仏を讃える言葉、修行のありよう、仏のすがたを言い表していると解釈します。おそらく、三つずつ二組の表現でもって、道元禅師はここで「全体的はたらき」を示そうとしているのではないか、と解釈します。かつて仏祖の坐禅のありようを述べた際に、道元禅師は「仏家の為体(ていたらく)」とは、「仏の教え(宗)」「言葉による解釈(説)」「修行(行)」を一等のものとする、という考えを述べられました(『永平広録』第八法語11)。区分性の逆説を乗り超えるために、区分性をくりかえし使いながら、区分性そのものを相対化し、しかもそこに通底する対応すなわち「はたらき」を見て、その対応=「はたらき」に自らも入りこむ、という方法を道元禅師はとろうとしていると私は考えます。それは、私にとっては、かつてから語っている、思量・不思量・非思量という三肢構造と、その立体的一体性の提示とつながるものです。私の三肢構造の読み方については、かつて一照さんからやんわりとたしなめられたこともあるのですが(一照さんのコラボ④)、道元禅師ご自身がそのように区分を区分自体の相対化として乗り越えておられる以上、仕方ないのではないか、と思ってしまいます。ともあれ道元禅師が、坐禅の当体を、「全体的はたらき」として読もうとしてるのは、確実な所だと思います。
【藤田一照】身読コラボ⑯
15回の連載を積み重ねていよいよ、この巻のタイトルそのものになっている二つの『坐禅箴』に取り組むところにまでたどり着きました。道元禅師が「古仏」という最上級の敬称をつけて呼ぶ数少ない禅者の一人である宏智禅師の『(宏智)坐禅箴』、そしてそれに唱和するように道元禅師自身が撰述した『(道元)坐禅箴』です。この巻に『坐禅箴』というタイトルをつけていることからも、この二つの『坐禅箴』を説くためにこそ、道元禅師はここまでずっと薬山非思量の古則と南嶽磨塼の古則について縷々述べてきたのでしょう。「薬山非思量」と「南嶽磨塼」は、この二つの『坐禅箴』を間違いのないように理解するためのいわば基礎固めとして用意されていたのです。ですから、この二つの古則をめぐるこれまでの拈提を通して描かれてきた坐禅の本来の姿、正しいありようをしっかりと念頭に置いて、これから二つの『坐禅箴』を読んでいかなければなりません。二つの古則と二つの『坐禅箴』の四つをワンセットに束ねて、充分に効き目のある「病を治す箴(はり)」として使い、それによって健康で健全な坐禅(「仏祖正伝の坐禅」)がどのようなものであるかを明らかにし、現今の坐禅が罹っている病を根本から治癒することが期待されているのです。
まず、道元禅師が学ぶに値する唯一のものとして推奨している宏智禅師の『坐禅箴』がとりあげられます。次の一節は、『(宏智)坐禅箴』の本文に入る前にまず、それがいかにすぐれた古今無類最上最高の『坐禅箴』であるかを率直な表現で称揚している箇所です。いつものように原文を数回、音読してみましょう。
坐禅箴は、大宋国慶元府太白名山天童景徳寺、宏智禅師正覚和尚の撰せるのみ仏祖なり、坐禅箴なり、道得是なり。ひとり法界の表裏に光明なり、古今の仏祖に仏祖なり。前仏後仏、この箴に箴せられもてゆき、今祖古祖、この箴より現成するなり。かの坐禅箴は、すなはちこれなり。
私はここを次のように口語訳してみました。
「坐禅箴」としては、大宋国慶元府、太白名山、天童景徳寺、宏智禅師正覚和尚の撰述したものだけが、唯一、真の仏祖が坐禅について説いたものであり、真の「坐禅箴」である。そこで言われていることは間違いなく正しいことだ。この坐禅箴だけが法界の表裏をつらぬいて全世界を明るく照らす光明であり、古今の仏祖のなかでもとびきりの仏祖による撰述なのである。これまでの仏もこれからの仏もみなすべて、この坐禅箴によって箴せられ(いましめられ、教えられ、病を癒やされ)て進み、今の祖師も昔の祖師もみなすべて、この坐禅箴によって間違いなく真の仏祖となるのだ。それほどまでに素晴らしい坐禅箴は他でもない次にあげるこれである。
この『坐禅箴』の作者である宏智禅師は1091年に生まれ、1157年に没していますから、1200年生まれの道元禅師は、宏智禅師が亡くなってから50年ほど後に生まれていることになります。「大宋国慶元府、太白名山、天童景徳寺、宏智禅師正覚和尚」というのは正覚という僧名の人物が大宋国の慶元府にある大白名山の天童景徳寺に住して法を説き、宏智禅師という勅諡号を皇帝から受けた人であることを簡潔に述べたものです。ここでさらに、宏智禅師の伝記的な情報を少し記しておきます。
山西隰州の出身で、11歳で出家し、18歳より諸方を遊歴。1124年に中国曹洞宗の丹霞子淳の法を嗣ぐ。1129年、天童山景徳寺に住持し、およそ30年にわたって教えを説き、伽藍の修復増築にも尽力し、中興の祖と称せられる。公案を用いて悟り経験へと導くことをせず坐禅することそのことを重視する「黙照禅(黙は心を鎮めること、照は智慧の意)」を、法兄の真歇清了と共に主導した人物。道元禅師は黙照禅の伝統を受け継いでいる。黙照禅に対するのが宏智禅師と同時代に生きた大慧宗杲(だいえそうこう)の「看話禅」である。67歳で示寂し、皇帝から宏智禅師の勅諡号を受ける。著述には『黙照銘』(禅の奥旨を歌った哲学詩。「黙は唯だ至言、照は唯だ普応」と言い、言句分別と差別対立を絶した寂黙に徹し、修証不二の打坐を勧めたもの。花園大学禅籍データベース禅籍解題より)、語録には『宏智禅師広録』、編集には『宏智禅師頌古百則』(祖師たちの行実の要点を本則とし、それに宏智が頌を付して要諦を説いたもので、曹洞宗で重用されている『従容録』の源泉となった)がある。
「法界の表裏」は空間的な広がりにおいて、「古今の仏祖」は時間的な広がりにおいて、この宏智禅師の『坐禅箴』が卓越した比類のないものであることを言おうとしている表現です。「『坐禅箴』が仏祖である」という言い方は、解釈の分かれるところですが、ここではいちおう仏祖=仏祖の作(真の仏祖が著したもの)という意味に解しておきます。このように宏智禅師の『坐禅箴』を力を込めて称揚した後、その原文がそのまま引用されます。ちなみに、この『坐禅箴』は『宏智禅師広録』巻八にあります。
坐禅箴 勅諡宏智禅師 正覚 撰
仏仏要機、祖祖機要。不触事而知、不対縁而照。不触事而知、其知自微。不対縁而照、其照自妙。其知自微、曾無分別之思。其照自妙、曾無毫忽之兆。曾無分別之思、其知無偶而奇。曾無毫忽之兆、其照無取而了。水清徹底兮、魚行遅遅。空闊莫涯兮、鳥飛杳杳。
いろいろな読み下し方が可能ですが、ここでは次のように読み下しておきます。これを数回、音読してください。アタマで意味を理解しようとするのではなく、性急な意味の確定を保留し、言葉の響きやリズムが引き起こす身体感覚やイメージを大事にするようにしてください。
仏仏の要機、祖祖の機要。
事を触せずして知り、縁に対せずして照らす。
事を触せずして知る、其の知、自(おのずか)ら微(み)なり。
縁に対せずして照らす、其の照、自ら妙なり。
其の知りて自ら微なるは、曾(かつ)て分別の思無し。
其の照らして自ら妙なるは、曾て毫忽の兆無し。
曾て分別の思無き、其の知、無偶にして奇なり。
曾て毫忽の兆無き、其の照、取ること無くして了なり。
水清(すん)で底に徹(とお)って、魚の行くこと遅遅たり。
空闊(ひろ)くして涯(かぎ)り莫(な)ければ、鳥の飛ぶこと杳杳なり。
この後、それぞれの文章について道元禅師が深掘りしていきますので、詳しい参究はそこに譲って、ここではいちおう文章の表層的な意味だけを押さえておくことにします。『正法眼蔵』を読むときには、まず引用部分の表層的な意味、つまり書かれている文字面の意味を常識的なレベルで一通り把握しておいてから、その後に来る道元禅師の拈提によってその同じ部分の文字面の意味があらためて大きくひっくり返されるという心の準備というか、ある種の覚悟が必要です。それはすでに「薬山非思量」や「南嶽磨塼」の参究でわれわれが経験してきたことです。たとえば、「薬山非思量」の話の冒頭に出てくる「兀兀地思量什麼」という文は普通なら「兀兀地、什麼(なに)をか思量せん」と疑問文として読んでそのように解するところですが、道元禅師の拈提の流れの中ではそれを「兀兀地の思量は什麼なり」と読むことが要求されました。また、「南嶽磨塼」の話の冒頭に出てくる「坐禅図箇什麼」も普通なら「坐禅は箇(か)の什麼(なに)をか図(はか)る」と疑問文に読んで、その前提に立って南嶽と馬祖の問答を理解するのですが、その後に続く道元禅師の拈提では同じ文が「坐禅の図は箇(か)の什麼(なに)である」と読むことが前提になって論が展開していました。
このことを念頭に置いて、次の口語訳はあくまでも文字面のレベルでの意訳として読んでください。深い意味合いはこの後の道元禅師の拈提に譲ります。
坐禅箴 坐禅を病から治すための箴としての正しい坐禅について
勅諡宏智禅師 正覚 撰
坐禅はどの仏どの祖にとっても肝心要の契機である。だから仏祖と坐禅を切り離すことはできない。坐禅は仏祖の命脈なのである。
坐禅は『普勧坐禅儀』にあるように「諸縁放捨 万事休息」である。
「万事休息」なのだから、身においては事(違順のわずらい)に触れることもなく、
「諸縁放捨」なのだから、心において縁に対する(外界のことに知らず知らず心が相手になっている)こともない。
坐禅のときは一切の人間的雑務が棚上げにされている(達磨は「外、諸縁を息(や)め 内、心あえぐことなく……」と言い、澤木老師は「打ち方やめ!」と言う)。
しかしそれはいわゆる無念無想の死物状態になるということではない。そこでは同時に、「龍が水を得、虎が山に靠(よ)る」(『普勧坐禅儀』)と言われるようにどこまでも生き生きと、そして了了として覚め続けていなければならない。
つまり「知る」、「照らす」という身心のはたらきは活発におこなわれているのだ。
この事に触れることなく知り、縁に対することなく照らすはたらきは、微妙(みみょう)そのものでわれわれの浅はかな慮知分別ではとらえることができない(それが非思量ということ)。
その知るはたらきが微妙であるのは、そこに是非善悪といった分別の思いがまったく混じりこんでいないからだ。
その照らすはたらきが微妙であるのはそれが迷悟といった兆しを少しもあらわさずにおこなわれるからだ。
分別以前、一切の兆しが現れる以前のところで、ただ知り、照らしている。
分別の思いのないその知は相手(偶)なしに独立している(奇)。
少しの兆しもないその照は向こう側に取るべき相手を持たず了了とただ照らしている。
このような坐禅をしているときには、尽地尽界に混じり物がなく、
底に徹するほどに澄み清まった無限の海であり、そのなかを魚(打坐仏)が水から離れず水をいのちとして悠々と泳いでいる。
果てのない空を鳥(打坐仏)が空を離れず空をいのちとしてゆっくりと自由自在に飛んでいる。
『(宏智)坐禅箴』についていちおうこれくらいの理解を持った上で、次に続く道元禅師の拈提を読んでいくことにしましょう。まず、数回、音読してみましょう。
いはゆる坐禅箴の箴は、大用現前なり、声色向上威儀なり、父母未生前の節目なり。莫謗仏祖好なり、未免喪身失命なり、頭長三尺頸長二寸なり。
まず、「坐禅箴」という言葉のなかにある「箴」についてのコメントが述べられます。その「箴」は文字通りには病を治すための竹製の針のことですが、ここでは仏祖の坐禅のことをそのように喩えているのです。「正しい坐禅という箴は」ということです。そして、道元禅師がしばしば用いる「〇〇は、Aなり、Bなり、Cなり、……」というたたみかけるような表現法でこの箴=坐禅が説明されます。この表現法ではA、B、C、……には和歌の本歌取りのような効果を狙って、仏典や禅籍からの漢文のフレーズがしばしば白文のまま使われます。中国語の原典からあるフレーズをそのまま引用して、道元禅師独自の立場で意味をずらして使用することで、そのフレーズを知悉している人の心の中には豊かな意味の連想の広がりが生まれることを期待していると思われます。この一節がまさにそのような構文になっています。一つ一つ見ていきましょう。全部で六つの引用フレーズが並べられています。
箴としての坐禅は
・大用現前なり 雲門の言った「大用現前、軌則を存せず」という言葉が出典。坐禅は比較を絶した大なる真実の用(はたら)きの実現であることを指します。
・声色向上威儀なり 普通は「声色を向上(超越)している威儀」と読んで「音や形といった感覚的経験の次元を超えた振る舞いであること」と解せますが、ここでは「声色は向上の威儀なり」と読んで、「声色=われわれが生きているという事実は、向上=真実の在り方の威儀=姿である」と解しておきます。
・父母未生前の節目なり 大潙が香厳に自分独自の言葉で言えと迫った、万事発生以前の「生かされて生きている本来のあり方」の節目=基準、目安であること。
・莫謗仏祖好なり 文字通りには「仏祖を謗ずること莫(な)くんば好(よ)し」と読んで、坐禅は「仏祖を誹謗しないことをよしとしていること」と解することもできますが、ここでは「莫謗の仏祖(好は讃嘆の意)」と読んで、坐禅は何一つ瑕疵(かし きず、欠点)のない完全無欠の仏祖の姿であるすばらしいことという意味に取ります。
・未免喪身失命なり 保温の言った言葉で、すでにこの『坐禅箴』の南嶽磨塼の古則が拈提されているところに出てきたフレーズです(連載第9回参照)。「未だ免れず喪身失命することを」と読み下せる文ですが、上から一息に読んで、凡夫としての身命を坐禅に投げ入れ、それにまかせ切って、凡夫の身命を喪失し、仏祖の身心になってしまっているのが坐禅であるという意味に解します。
・頭長三尺頸長二寸なり 洞山が言った言葉で、文字通りの意味は「頭の長さは三尺、頸の長さは二寸」一尺はおよそ30センチ、一寸はおよそ3センチですから、頭の長さが90センチ、首の長さは6センチということになります。これは別に現実の身体の寸法のことを言っているのではありません。現実にはそんなことはあり得ず、もしそんな人がいたらそれはモンスターです。このフレーズのすぐ前にある「喪身失命」と同じように、坐禅しているときには世間一般の人とは全く異なった存在になっていることを比喩的にこう表現していると解します。坐禅のときの身体は普通の人間の姿ではないということです。
このように解釈した上でこの一節を口語訳してみると次のようになります。
坐禅箴という言葉のなかにある「箴」は病を治療する鍼灸の道具であるが、ここでは坐禅の病を治すために正しい坐禅を行じる、そのことを言う。そのような箴としての坐禅は、仏の偉大なはたらき(大用)が実現した(現前)ものである。われわれが生きているという真実の在り方の姿そのものである。父母が生まれる前の本来生かされたままのいのちがいろいろに働いていることの目安である。完全無欠なる仏祖の素晴らしい現成である。凡夫の身命をすっかり失って仏祖の身心になっていることである。だから、頭の長さが三尺で首の長さが二寸であるような人間界にはありえない姿になっているのだ。
ではここから、いよいよ『(宏智)坐禅箴』の本文の拈提が始まります。数回音読してみましょう。
仏仏要機。
仏仏はかならず仏仏を要機とせる、その要機現成せり、これ坐禅なり。
祖祖機要。
先師無此語なり、この道理、これ祖祖なり。法伝・衣伝あり。おほよそ回頭換面の面面、これ仏仏要機なり。換面回頭の頭頭、これ祖祖機要なり。
「仏仏」と「祖祖」という同じ漢字を二つ並べる表記からは、「あの仏もこの仏もみんな」「この祖もあの祖もみんな」というように、「一人も例外なくあらゆる仏とあらゆる祖は」というニュアンスが伝わってきます。「仏は仏を要機(最も肝要なきっかけ、契機)としている」というのは、仏は自己が本来仏であることを契機として仏をしているということです。その契機が現に実現成就(現成)しているのが、坐禅に他ならないのです。ですから本来成仏の仏が今ここで現に仏のする修行をしているのが坐禅です。『弁道話』の第16問答のところに「丙丁童子来求火」という言葉があります。「火の童子が来て火を求める」という意味ですが、すでに仏である者がその事実を契機として仏である修行を今ここでするという事情をよく表しています。
「祖祖機要」の「機要」はレトリック上ただ「要機」の前後を入れ替えただけで意味は同じです。ですから、「祖祖はかならず祖祖を機要とせる、その機要現成せり、これ坐禅なり」というコメントが省かれているとみるべきです。「どの祖師も、本来祖師であることを重要な契機として祖師をしており、その契機が実現しているのが坐禅である」のです。
「先師無此語」という言葉は先ほど言った「本歌取り」のような引用語です。本歌=出典は次のような問答です。
師(趙州の弟子の光孝慧覚)、崇寿に至る。
法眼問う、「近く甚れの処をか離る」。
師云く、「趙州」。
眼云く、「承聞するに趙州に栢樹子の話有りと、是や否や」。
師云く、「無し」。
法眼云く、「往来の皆謂わく、『僧問う、如何なるか是れ祖師西来意。州云く、庭前の栢樹子』と。上座、何ぞ無と言うことを得ん」。
師云く、「先師、実に此の語無し。和尚、先師を謗ずること莫くんば好し」。
『聯灯会要』巻7
(口語訳)趙州の弟子の光孝慧覚が法眼文益のところへ出かけていった。法眼が「貴公はどこからきたのか」と問うと慧覚は「趙州禅師の処から来た」と答えた。それに対し法眼が、「趙州の『庭前の栢樹子』の話はとても有名だと聞いているのだが、そうなのかね?」と聞く。恵覚は「そんな話は無いですよ」と答えた。法眼が、「ここに来た者は、皆趙州には栢樹子の話があるといっているが、貴公はなぜ無いなどと言うのかね」と再度聞くと、恵覚は、「先師には真実そのような言葉は無いのです。法眼和尚よ、先師を誹謗しないで下さい」と返した。
この慧覚の最後の返答の中にある「先師実無此語」が「先師無此語」の出どころです。ちなみに、先ほど読んだ「莫謗仏祖好」の出どころも実はここにある慧覚の「先師を謗ずること莫くんば好し」という文言でした。坐禅は歴代祖師の教え(先師此語)を受けてするものですが、坐禅そのものはあくまでも、過去の師の言葉に頼って、口真似のようにそのまま模倣するのではなく、まっさらに独立して自己の真実のあり方を今ここで現に修行することだということを言うために、この言葉をここに引いてきているのです。そして、「先師無此語」として坐禅するときはじめて「先師此語」を受け継いだということになるという道理があります。先師もその教えももうすっかり坐禅の中に包摂されて隠れてしまい、あるのはただ坐禅のみになるというのが「先師無此語」の意味するところです。
「祖祖機要」という宏智禅師(道元禅師にとってはまさに先師に当たる)の言葉のすぐ後に「先師無此語」と書いているのですから、「祖祖機要」を過去の宏智禅師が言った単なる言葉による教えにとどめてはならず、「祖祖機要」という宏智禅師の言葉(先師此語)が今する坐禅の中に完全に包摂されてしまい、「先師無此語」としての坐禅が具現されなければならないという含意もあるのではないでしょうか。
「先師無此語」という絶対の否定を媒介とした先師の教えの受け継ぎ方の道理(すじみち、ことわり)こそが「祖(から)祖(への伝授)」なのです。そのような「先師無此語」としての坐禅においてはじめて、師から弟子へと法が伝わり、その証としてのお袈裟が伝わるということがあるのです。『正法眼蔵』「坐禅儀」には「坐禅のとき、袈裟をかくべし」という一文がありますが、お袈裟をかけて坐禅している姿がまさに「法伝衣伝」の実態です。
「回頭換面」も「換面回頭」も言葉の前後を入れ替えただけで、同じ事態を意味しています。つまり、頭をくるりと回すとそれと同時に顔も換わるということで、回頭は作仏という証果、換面は坐禅という修行を意味していて、修行と証果を切り離すことができず、両者は一等であり一如であることを表現します。坐禅することがそのままとりもなおさず作仏になっていることをこう表現しているのです。「回頭換面の面面」とは、坐禅においては、回頭、つまり大いなる働きが生き生きと活動していること、それがそのまま換面、つまり坐禅になっているわけですが、換えられる面=坐禅の一つ一つがどれも「仏仏要機」だと言うのです。同じように、「換面回頭の頭頭」も、換面=坐禅することがそのまま、回頭=仏という大いなる働きが進行していることでもある(坐禅即作仏 磨塼即作鏡)わけですが、そのたびごとに回らされる頭=仏の一つ一つがどれも「祖祖機要」なのだと道元禅師は言うのです。
以上のような参究を踏まえてこの一節を次のように口語訳してみました。
仏仏要機 仏が仏である要(かなめ)となっている契機
あらゆる仏はかならず自己本来成仏を契機として成仏している。その契機の具体的実現こそが坐禅である。
祖祖機要 祖師が祖師であるための契機の要
坐禅は確かに、先師(亡くなった師匠)の教えを受けて行うものであるが、その教えのコピー(複製)であってはならない。自己本来の事実を純粋に修行する坐禅が現に行じられているところには、もはや師の教えとそれを忠実に実践している自分というような水臭い二元的関係はない。ただ端的に行じられている坐禅があるのみだ。このような先師と坐禅との同心同体の道理こそが本当の祖祖である。そのような祖祖になってこそ(心には)正法が伝わり、(身には)お袈裟が伝わるということがあるのだ。おしなべて言うなら、頭(仏)を回(めぐら)して面(坐禅)に換えるように、坐禅では仏がそのまま坐禅になっていて、その坐禅の一つ一つはすべての仏が仏であるための要となる契機なのである。面(坐禅)を換えて頭(仏)を回らす、つまりこれも坐禅のことで、坐禅のたびに回らされる頭(仏)の一つ一つはすべての祖が祖であるための契機の要なのだ。
ここで思い出すべきことは、「薬山非思量」の拈提のところで、道元禅師は「坐禅弁道はこれ初心晩学の要機なり。かならずしも仏祖の行履にあらず」という見解を厳しく批判していたことです(連載第6回参照)。「仏仏の要機、祖祖の機要」という表現は、坐禅弁道が仏祖がいやしくも仏祖である以上どうしてもしなければならないまさに肝心要のことであると説いているのです。
次回も引き続き、道元禅師による『(宏智)坐禅箴』の拈提を参究していきます。