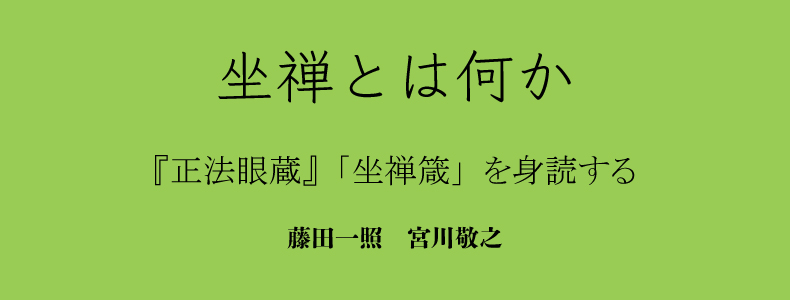車を打つ、牛を打つ
【宮川敬之】身読コラボ⑫
南嶽いはく、如人駕車、車若不行、打車即是、打牛即是。
しばらく、車若不行といふは、いかならんかこれ車行、いかならんかこれ車不行。たとへば、水流は車行なるか、水不流は車行なるか。流は水の不行といつべし、水の行は流にあらざるもあるべきなり。しかあれば、車若不行の道を参究せんには、不行ありとも参ずべし、不行なしとも参ずべし、時なるべきがゆえに。若不行の道、ひとへに不行と道取せるにあらず。打車即是、打牛即是といふ、打車もあり、打牛もあるべきか。打車と打牛と、ひとしかるべきか、ひとしからざるべきか。世間に打車の法なし、凡夫に打車の法なくとも、仏道に打車の法あることをしりぬ、参学の眼目なり。たとひ打車の法あることを学すとも、打牛と一等なるべからず、審細に功夫すべし。打牛の法、たとひよのつねにありとも、仏道の打牛は、さらにたづね参学すべし。水牯牛を打牛するか、鉄牛を打牛するか、泥牛を打牛するか。鞭打なるべきか、尽界打なるべきか、尽心打なるべきか。打迸髄なるべきか、拳頭打なるべきか。拳打拳あるべし、牛打牛あるべし。
大寂無対なる、いたづらに蹉過すべからず。抛塼引玉あり、回頭換面あり。この無対、さらに攙奪すべからず。
南嶽が言った。「牛車に人が乗り、車が進まない時に、車を打つのが正しいのか、牛を打つのが正しいのか?」
「車が進まない時」という言い方について、まずは「車が進む」とはなにか、「車が進まない」とはなにか、と問わなければならない。比較して考えると、「水が流れること」を「車が進むこと」とする場合もあり、「水が流れないこと」を「車が進むこと」とする場合もある。流れることは、水が「進んでいないこと」ともいえる。水の性質は、流れないことでもあるからだ。そのようにして、「車が進まないとき」ということがらを参究する場合に、「車が進まないこと」があり、「車が進まないこと」がないと、実際に修行でもって会得すべきである。「車が進まないこと」とは「時」のありようであるからだ。「もし進まないならば」を、単純に「進まない」ことだけだと理解するだけでは、言い足りていない。「車を打つのが正しいのか、牛を打つのが正しいのか?」と言われるわけだから、「車を打つこと」も「牛を打つこと」と同様に仏道においてはありえるのだ。「車を打つこと」と「牛を打つこと」とは、同じなのか、ちがうのか。通常の考えでは「車を打つ」やりかたはなく、仏道修行を始めていない一般人に「車を打つ」やりかたはないが、しかし仏道には「車を打つ」やりかた、教えがあることをここで知ることができるのだ。これは仏道参究の際の目の付け所である。「車を打つ」やりかた、教えがあるのだとわかっても、それを「牛を打つこと」と同じと思ってはならない。ここで自分の修行に即してよくよく思いをこらせ。「水牯牛」を「打つ」のか。「鉄牛」を「打つ」のか。「泥牛」を打つのか。やりかたは、日常の動作の一つに見えたにしろ、仏道において「牛を打つ」とはどんなことなのかを、正師に訪ね、経典祖録を見て、修行していかなければならない。鞭で打つのか。全世界で打つのか。心を尽くして打つのか。髄まで打つのか。拳で打つのか。拳で拳を打つのか。牛が牛を打つのか。
「馬祖は答えなかった」ということを、簡単に見逃してしまってはならない。「塼を放って玉を引いている」のであり、「ふりむけば別の顔」であるのだ。この「答えない」ということを、軽んじてはならないぞ。
〈牛とはなにか 車とはなにか 「車が進まない」とはなにか〉
今回はいくつかの参照すべき話頭が入り組んでいて、やや複雑な箇所です。複雑になってしまうところは、なるべく単純な話に戻しながらお話したいと思います。では、読んでみます。
南嶽いはく、如人駕車、車若不行、打車即是、打牛即是。
南嶽が言った。「牛車に人が乗り、車が進まない時に、車を打つのが正しいのか、牛を打つのが正しいのか?」
先回までの磨塼の話のあと、「どうすれば正解ですか〔如何即是〕」と訊いた馬祖に対して、師の南嶽が述べた言葉がこのようでした。ここで「牛が引く車」とは、昔の中国の田園地帯で、牛に大八車のような貨車を引かせてその車上に坐ってスゲ笠をかぶり、時折鞭などをふるいながら、あぜ道をゆっくり進んでいる農民のすがたをイメージするとよいかもしれません。この牛車が時折止まり、進まなくなる。牛が休憩したのでしょうか。さて、このときにどうするか、というのが南嶽の問でした。「車を打つのが正しいのか、牛を打つのが正しいのか」。牛車が進まなければ、鞭を振って牛を打って進ませるのが当たり前と思われますが、そこに疑問を呈しているのです。一体これはなにを訊いているのでしょうか。坐禅の話とどのように関係しているのでしょうか。
西有穆山師は、「牛はいつも内心のことに使う。すなわち心牛じゃ。それから車というのは外に表れた身相のことである。いま南嶽馬祖の相見の上では、車はしばらく外形の坐禅、牛というのは内心を調御して作仏することだ」(『正法眼蔵啓迪』「坐禅箴」中巻559頁)と示されています。坐禅において、体のすがたに重点を置いた坐禅〔身形の坐禅=作仏〕か、心のありように重点を置いた坐禅〔心性の坐禅=坐仏〕かという問いとして、この南嶽の問いは解釈されると西有師は述べています(ただし西有師はこの解釈を「俗論」と呼び、それを打破する解釈を示されているのですが、車=体、牛=心という前提は基本的に引き継いでいます)。
しかし「坐禅箴」巻の道元禅師の解説では、車と牛とはなにか、それらを打つとはどういうことかではなく、まずは別のことがらが問題にされているのです。問われているのは、そもそも「車が進まないこと」とはどういうことなのかについてです。つぎのようです。
しばらく、車若不行といふは、いかならんかこれ車行、いかならんかこれ車不行。
「車が進まない時」という言い方について、まずは「車が進む」とはなにか、「車が進まない」とはなにか、と問わなければならない。
そのうえで
たとへば、水流は車行なるか、水不流は車行なるか。流は水の不行といつべし、水の行は流にあらざるもあるべきなり。
比較して考えると、「水が流れること」を「車が進むこと」とする場合もあり、「水が流れないこと」を「車が進むこと」とする場合もある。流れることは、水が「進んでいないこと」ともいえる。水の性質は、流れないことでもあるからだ。
と言われています。「車が進まない」ことを「水が流れること」と比較して参究せよと示されているのです。これはどういうことでしょうか。
〈「水が流れること」と「車が進まないこと」〉
「水が流れること」の考察は、「坐禅箴」巻の二年前に書かれた『正法眼蔵』「山水経」巻につぎのようにあります。
しかあれば、水はこれ真龍の宮なり。流落にあらず。流のみなりと認ずるは、流のことば、水を謗ずるなり。たとへば、非流と強為するがゆゑに。水は水の如是実相のみなり、水是水功徳なり、流にあらず。
そのようにして、水は実在の龍たちの宮殿である。ただ流れ落ちてゆくものなのではない。水を流れるものとだけ認識して、「水は流れるもの」と言うのは、水の多くの功徳を謗っているのだ。その謗りは、「水は流れるものではない」と強弁していることと近いのである。水には水の「現実のありさま〔如是実相〕」ばかりがあるのだ。「水とは水の功徳」のことだ。「流れるもの」だけなのではない。
『摂大乗論釈』には「一水四見(いっすいしけん)」といって、同じ水でも天人は瑠璃、人間は水、餓鬼は膿血(のうけつ)、魚は住処として見るというたとえ話が載っています。道元禅師はこの「一水四見」の話をよく使われますが、ここでもそれを踏まえています。要するに、水を「流れるもの」だと限定して理解してはならない、ということです。「流れるもの」でもあり、「流れないもの」でもある。固くもなり、柔らかくもなる。地にもあるが天にもある。このように水には無量のすがたがあり、そのすべてが水の「現実のありさま」であり、「水の功徳」であると言われます。こうした読み方を「車が進まないこと」に適用すれば、「進まないこと」にも多くの功徳があることをわきまえろ、ということになるでしょう。しかし、この「水とは水の功徳」と言われるときの「功徳」とは、どういうことがらを指しているのでしょうか。同じく「山水経」巻につぎのようにあります。
しかあればすなはち、現成所有の功徳をあやしむことあたはず、しばらく十方の水を十方にして著眼看すべき時節を参学すべし。人天の、水をみるときのみの参学にあらず、水の、水をみる参学あり。水の、水を修証するがゆゑに、水の、水を道著する参究あり。自己の、自己に相逢する通路を現成せしむべし、佗己の、佗己を参徹する活路を進退すべし、跳出すべし。
そのようにして、「あるものに成る」という「功徳」のありようを訝しく思うことはないが、それでも訝しく思うならば、試みに、水とはあらゆる方向〔十方〕にある水のことだと思いきわめて、水のありようを見通す「時」を参究し、修行すべきである。人や天人が水を見るときだけが参究・修行なのではなく、自らが水となって水を見るような参学が、必要なのだ。自分を水として水自身を修行し、水自身をさとることと同じように、水自身がかえって自分となって、水のことを言い述べるようにするという参究もあるのだ。自己が自己に出会うその通路を実現させることである。他なるものが、他なるもののありようを見極めるその活路を進み、通常の考えから飛び出すのである。
「山水経」巻から推測できることは、「水は水の功徳」だとする見方とは、見ている人自身も水に入り、自分と水とを同化させながら、水を見る見方のことだといえます。主体が対象を見るときのようではなく、主体と対象との区分をとりはらい、自分を水とし、水を自分として見る見方こそ、「水の功徳」を現すと言われます。このことは、「自己の、自己に相逢する通路を現成せしむべし」と言い換えられているのです。自己が自己に出会うことができることこそ「功徳」と言われるのです。
このように読み進めると、「車が進まないこと」を「水が流れないこと」と対照させて考えた場合、第一に、「車が進まないこと」を単純に「車が進むこと」が実現されていない状態、打開すべき状態とだけ考えるべきではなく、もっと広い意味の可能性を開いて、肯定的にとらえて読むべきだというメッセージが示唆されます。また第二に、「車が進まないこと」に、「自己が自己に出会うことができる」「功徳」を見るべきだ、というメッセージも示唆されます。特に重要なのは、第二のメッセージです。「自己が自己に出会うことができる功徳」としての「車が行かないこと」。これはどういうことなのでしょうか。ここで示されている「牛車」とは、われわれの坐禅のことを指していますので、坐禅の実践に即してこのことを考えてみましょう。
〈自己と「時」〉
坐禅をする前に、私たちは大なり小なり、予想や期待をもってしまいます。たとえば私は、この連載を執筆していて、難しい箇所、わからない箇所に出会って書きあぐねると、お寺の地下にある坐禅堂に下りて坐禅をします。坐禅でわからない箇所がわかるわけではない、と頭で理解はしていますが、けれどもどこかで、なんとか坐禅によって良い読み方が浮かんでくれればという期待感を持ってしまいます。読みあぐねる、言いあぐねるのは好ましくない状況で、それを打開し、なんとか読み進めたい、解説を進めたいと思ってしまっているのです。坐禅しても(当然ながら)よい解説が浮かんでくるわけではありません。それでさらに焦り、困り、なんとか打開策を探そうとします。これは「車が進まないこと」の一例であるように思います。しかし道元禅師の教えに則れば、読みあぐねる、言いあぐねるときを、解説の失敗とすべきではないのです。むしろ読みあぐね、言いあぐねている自己を見出し、その自己に自己が出会うことができれば、それが「功徳」だと言われるのです。これが「車を打つこと」とされます。どういうことでしょうか。進みあぐねているときの、自己の偏見や焦りや目標によって見えなくなってしまった自己に、もう一人の自己が気づき、冷静にそれを見るきっかけとなるということではないかと思います。ここで「打つ」こととは、ものごとを進めようとすることだけではありません。たとえば熟練の職人さんなら、車を棒で叩き、その音の違いで、車軸や車輪、轅などのとりつきの不備を察知することができるでしょう。そのことによって、その場で進まないことよりももっと大きな不具合や損傷に気が付き、その手入れをすることができるようになります。つまり「打つ」とは、「点検する」という意味に近いと思います。読みあぐね、言いあぐねている自己に出会い、何に対して焦り、困っているのかを点検するならば、「うまく読んで良い解説がしたい」「正解の解説を探したい」と思っている自分がいることを発見します。それは「他からの評価が欲しい」と焦る自己です。恥ずかしいことですが、しかしこの自己もやはり自己です。必要なのは、こうした問いごと、さまざまな自己ごと、坐るということです。そのとき、第一のメッセージである、「車が進まないこと」を、もっと広い意味の可能性を開いて、肯定的にとらえて読むべきだということが響いてくるのです。
しかあれば、車若不行の道を参究せんには、不行ありとも参ずべし、不行なしとも参ずべし、時なるべきがゆえに。若不行の道、ひとへに不行と道取せるにあらず。
そのようにして、「車が進まないとき」ということがらを参究する場合に、「車が進まないこと」があり、「車が進まないこと」がないと、実際に修行でもって会得すべきである。「車が進まないこと」は、「進むこと」と同じく、「時」のありようであるからだ。「もし進まないならば」を、単純に「進まない」ことだけだと理解するだけでは、言い足りていない。
「車が進む」のが望ましく、「進まない」のは望ましくない。そのように限定された理解を超えて、「車が進まないこと」の可能性を開くべきだと言われるのです。牛車が止まれば、「ああ、牛が休憩したいかな」「いい天気だな」「雨がくるのかな」「いい風だな」など、「進まないこと」でわかることの可能性を、開くようにすべきだということなのでしょう。「車が進む」場合もあれば、「車が進まない」場合もある。それらはすべて自己が自己に出会う場面だと言われます。これを道元禅師はさらに、「時」と呼ばれました。「時」についての独特の分析が魅力である『正法眼蔵』「有時」巻につぎのようにあります。
われを排列しをきて尽界とせり。この尽界の頭頭物物(づづもつもつ)を、時時(じじ)なりと覰見(しょけん)すべし。……われを排列してわれこれを見るなり。自己の時なる道理、それかくのごとし。
私たちが「時」と呼んでいるのは、自分をびっしりと並べて世界とし、その世界における自分とのかかわり一つ一つを、その時、その時と言っているのだと、見通さなければならない。………びっしりと並べた自分を自分が見ているのである。自己が時であるというそのありさまは、そのようなものだ。
時計の針が動くのを見ると、時間の経過を感じます。その際私たちは、時計を見ている私たちとは無関係に、時間というなにかの客観物が動いていく様を想像します。自分は観察者で、動かず、こうした流れを外から見ているように錯覚します。しかしそれは錯覚であり、想像物にすぎません。実際の時間にはなにより私たち自身を含んでいるからです。私たちは、自分の五官の知覚で、自分を含めた世界の様子の微細な違いを、自分にフィードバックさせることで時間を感じます。それ以外に時間を感じるすべはありません。道元禅師によれば時間とは、「世界にびっしりと並べた自分を自分が見ている」ことであり、だから「自己は時である」とされています。時間を感じるのは、世界とつながった自己が、世界とつながった自己を見ていることです。これを逆に言えば、「自己が自己に出会う」のは、「時」のありようそのものであるということになるのです。このように「車が進まないこと」をきっかけに「自己が自己に出会う」こと、その構造こそが「時」であると言えるのです。
打車即是、打牛即是といふ、打車もあり、打牛もあるべきか。打車と打牛と、ひとしかるべきか、ひとしからざるべきか。世間に打車の法なし、凡夫に打車の法なくとも、仏道に打車の法あることをしりぬ、参学の眼目なり。
「車を打つのが正しいのか、牛を打つのが正しいのか?」と言われるわけだから、「車を打つこと」も「牛を打つこと」と同様に仏道においてはありえるのだ。「車を打つこと」と「牛を打つこと」とは、同じなのか、ちがうのか。通常の考えでは「車を打つ」やりかたはなく、仏道修行を始めていない一般人に「車を打つ」やりかたはないが、しかし仏道には「車を打つ」やりかた、教えがあることをここで知ることができるのだ。これは仏道参究の際の目の付け所である。
このようにして、車が進まないときに、進むことだけを正解としてそれ以外の可能性を考えないという視野狭窄には陥るべきではないと、道元禅師は教えられます。「車が進まないこと」も「車が進むこと」と同様に修行のポイントが開かれている。さらに「牛を打つこと」も「車を打つこと」も、どちらにも仏道の修行のポイントが開かれていると道元禅師は示されます。むしろ、一般社会ではありえない「車を打つ」ことにこそ、仏道参究の独自の目の付け所があると指摘されます。それは、「車を打つ」とは、「自分の無意識の欲求を点検する」ことだからです。「進まなければならない」という焦りを感じる自己を、別の自己が点検する。この連載も、「早く進めなければ、うまく言わなければ」と思いこみ、焦っている私自身のありようをつねに点検しなければならないのです。そしてそのうえで、もう一度進もうと試みる。それは、自分のどうしようもない欲求のありようを冷静に認めたうえで、しかも前へ進むことです。しかし、その際の「前へ」とはどこなのか。
〈「前へ」とはどこか〉
たとひ打車の法あることを学すとも、打牛と一等なるべからず、審細に功夫すべし。打牛の法、たとひよのつねにありとも、仏道の打牛は、さらにたづね参学すべし。水牯牛(すいこぎゅう)を打牛するか、鉄牛を打牛するか、泥牛を打牛するか。鞭打(べんだ)なるべきか、尽界打(じんかいだ)なるべきか、尽心打なるべきか。打迸髄(たびょうずい)なるべきか、拳頭打なるべきか。拳打拳あるべし、牛打牛あるべし。
「車を打つ」やりかた、教えがあるのだとわかっても、それを「牛を打つこと」と同じと思ってはならない。ここで自分の修行に即してよくよく思いをこらせ。「水牯牛」を「打つ」のか。「鉄牛」を「打つ」のか。「泥牛」を打つのか。やりかたは、日常の動作の一つに見えたにしろ、仏道において「牛を打つ」とはどんなことなのかを、正師に訪ね、経典祖録を見て、修行していかなければならない。鞭で打つのか。全世界で打つのか。心を尽くして打つのか。髄まで打つのか。拳で打つのか。拳で拳を打つのか。牛が牛を打つのか。
以上のように自己を点検した後で、改めて「前へ進もう」とするとは、具体的にどんなことなのでしょうか。私たちの坐禅では、いくら「無所得・無所悟の坐禅だ」と考えようとも、実際には坐っているときにはいろいろな期待や予想をたてながら坐ってしまいます。これは明らかに有所得心でしょう。そうした「無所得・無所悟の坐禅」を有所得心で坐っている自己のありようを認めながら、それごめに坐り、あるいはそうした無所得を所得しようとする心も相手にせず、坐っていくということです。そのときに「前へ進むこと(=牛を打つこと)」は、単に「さとりを得るための坐禅」を乗り越えて、さまざまな意味合いを帯びます。それが「牛」の種類、打ち方になって提示されます。
「牛」の種類として出された例は、潙山霊祐(いさんれいゆう)の「水牯牛」〈『景徳伝灯録』九巻『国訳一切経』史伝部十四223頁〉、風穴延沼(ふうけつえんしょう)の「鉄牛」〈同十三巻338頁〉、龍山(りゅうざん)の「泥牛」〈同八巻213頁〉です。『禅學大辞典』(大修館書店)によれば、「水牯牛」とは「本来の面目を行ずる人」のこと、「鉄牛」とは「不動著」のこと、「泥牛」とは「慮智分別・煩悩のたとえ(「泥牛入海」で差別と平等の交参のたとえ)」とされています。私としては、「水牯牛」は衆生を済度する菩提心の意に、「鉄牛」は「不動心」の意に、「泥牛」は修行道場での「和合心」の意として、それぞれを採りたいと思います。「自己と自己とが出会った」そのうえでさらに「前へ進む」場合、もはや自らの「さとり」を追求するためではなく、別様の意味あいが付与されていく、ということだと思います。
また、「鞭で打つのか。全世界で打つのか。心を尽くして打つのか。髄まで打つのか。拳で打つのか。拳で拳を打つのか。牛が牛を打つのか」という打ち方の区別は、自分という主体が対象を打つ(作用する)という打ち方〔鞭打・拳頭打・打迸髄〕から、世界とひとつながりの自分が、世界とひとつながりの自分を打つ(点検する)打ち方〔尽界打・尽心打・拳打拳・牛打牛〕へと、打ち方そのものが広がっていくということであり、一方向的に「さとり」に向かってゆくことを是とするありようから、視野を広げるように示されているのです。
大寂無対なる、いたづらに蹉過(さか)すべからず。抛塼引玉(ほうせんいんぎょく)あり、回頭換面(かいとうかんめん)あり。この無対、さらに攙奪(さんだつ)すべからず。
「馬祖は答えなかった」ということを、簡単に見逃してしまってはならない。「塼を放って玉を引いている」のであるのか、「凡夫の顔を反して仏のような顔をする」のであるのか。この「答えない」ことは、むりやり奪い取ることができるような、軽いものではないぞ。
こうした南嶽の言葉に、馬祖は言葉では答えませんでした。この「答えない〔無対〕」という点にも注目するよう道元禅師は示されます。馬祖は南嶽の問いの意味をちゃんとわきまえていることの、いわば承認としての沈黙であったからです。南嶽の問いとはなんだったのか。改めてまとめてみます。坐禅において、体のすがたに重点を置いた坐禅〔身形の坐禅=作仏〕か、心のありように重点を置いた坐禅〔心性の坐禅=坐仏〕かという問いとして、南嶽の問いはまずあったのでした。「塼を放って玉を引いている」とは、作仏を捨てて坐仏へと向かうことであり(それは「塼を捨てて鏡をとる」「打車でなく打牛を選ぶ」と同義です)、一方「凡夫の顔を反して仏のような顔をする」とは、作仏のままこれが仏なのだと表面を取り繕う(それは「磨塼を続ける」「打牛でなく打車を選ぶ」と同義です)、ということです。南嶽の問いは、一見、前者を勧めているように読めます(この読み方を西有師は「俗論」と呼びました)。しかし道元禅師によれば、実は南嶽は、この前者後者の両方とも大事であると言い、それを馬祖は承認しているのだ、と言われます。道元禅師によれば、坐禅において、この両者を区別している私たちの無意識の価値観そのものに、むしろ出会うべきなのだと言われます。坐禅はわたしたちの身体で、人間の行ではなく仏の行を実践する修行ですが、それは身体性から遊離する体験を持つことなのではありません。身体性を固定された実体としてではなく、無常なるもの、縁起のなかにあるものとわきまえつつ、その身体性において坐り続けることです。しかし同時に、身体性に固執し、身体を平静に保つことだけが坐禅の目的だと開き直ってもいけない。それは私たちの狭い認識の幅で仏の行である坐禅を判断してしまっているからです。沈黙を通して坐っている馬祖は、こうした両者を同時に表現していると解釈すべきだ、と道元禅師は言われます。
【藤田一照】身読コラボ⑫
これまで読んできたところでは、師である南獄と弟子の馬祖との間で、「磨塼」をめぐる語りの応酬が行われていました。釈尊は菩提樹の下で成道された時に思わず、「奇なるかな、奇なるかな、一切衆生悉く皆な如来の智慧徳相を具有す」とつぶやいたと言われています。そのようにまさに奇蹟としか言いようのない不思議なあり方で、現にそして端的に存在しているこの自己といういのちを、今ここで生き生きと精一杯磨くことが坐禅という営みです。そういう坐禅が磨塼(塼を磨く)という行為に喩えられて、論じられていたのです。そこでは、塼を磨くという行為の全体がそのまま取りも直さず作鏡(鏡となる)の実現でもあるという磨塼(坐禅=修)即作鏡(成仏=証)という仏道修行独特の道理が解明されていました。
この点に関して一言しておきます。歩くという行為はたいていの場合、行為それ自体が目的なのではなく、どこかに到達するための手段になっています。アリストテレスによればそのように自前の目的をうちに含んでいない行為を「キネーシス」と呼びます。これに対して、自前の目的をうちに含んでいる行為というものもあって、彼はそれを「エネルゲイア」と呼んでいます。たとえば、見るという行為では、見ると同時に「見てしまっている」ということが起きていますから、見るという行為にはその行きつく先(目的)である「見た」がすでに含まれています。ですから、行為即目的の完成なのです。見ると見たが同時現成しています(「現在形=現在完了形」)。
「生きる」もまたエネルゲイア的です。生きれば同時に「生き続ける」という目的が達成されているからです。こういうエネルゲイアという観点から、南獄と馬祖のやりとりを考えてみることもできるのではないでしょうか。道元禅師が「坐禅は習禅にはあらず」と強調するのは、エネルゲイアであるはずの坐禅がともするとキネーシス的な習禅と混同されやすい(あるいはすでに混同されていた)ことへの訓戒であったと言えるでしょう。
さて、今回読んでいく箇所では、「磨塼」から一転して「牛車」が新たな喩えとして取り上げられています。まず原文を読んでみましょう。是非、何度か繰り返し音読して道元禅師の書く文章の響きを体感してみてください。
南嶽いはく、如人駕車、車若不行、打車即是、打牛即是。
しばらく、車若不行といふは、いかならんかこれ車行、いかならんかこれ車不行。たとへば、水流は車行なるか、水不流は車行なるか。流は水の不行といつべし、水の行は流にあらざるもあるべきなり。しかあれば、車若不行の道を参究せんには、不行ありとも参ずべし、不行なしとも参ずべし、時なるべきがゆえに。若不行の道、ひとへに不行と道取せるにあらず。打車即是、打牛即是といふ、打車もあり、打牛もあるべきか。打車と打牛と、ひとしかるべきか、ひとしからざるべきか。世間に打車の法なし、凡夫に打車の法なくとも、仏道に打車の法あることをしりぬ、参学の眼目なり。たとひ打車の法あることを学すとも、打牛と一等なるべからず、審細に功夫すべし。打牛の法、たとひよのつねにありとも、仏道の打牛は、さらにたづね参学すべし。水牯牛を打牛するか、鉄牛を打牛するか、泥牛を打牛するか。鞭打なるべきか、尽界打なるべきか、尽心打なるべきか。打迸髄なるべきか、拳頭打なるべきか。拳打拳あるべし、牛打牛あるべし。
大寂無対なる、いたづらに蹉過すべからず。抛塼引玉あり、回頭換面あり。この無対、さらに攙奪すべからず。
南獄が馬祖にこう問いかけます。「人が牛車に乗ってそれを操っているとして、もし、その牛車が動かない場合、車を鞭打ったらいいのか? それとも牛を鞭打ったらいいのか?」
先程までの磨塼の話からいきなり牛車の話に話題が移っているので、それを読むわれわれにはいかにも唐突なことのように感じられますが、ここまで丁々発止にやりとりを交わしている南獄と馬祖の間では決してそうではないはずです。二人が共同で作り上げている坐禅をめぐる深い宗教的思惟の持続をそこに読み取らなければなりません。南獄がこの牛車の話を取り上げたのは、馬祖が「如何即是」と言ったことに対しての応答としてであったことに注目する必要があります。
前回、私は馬祖の「如何即是」に対して下記のようなコメントをつけました。今回の牛車の話を理解する前提ともなることに触れていますので、その部分を再度ここに引用しておきます。
馬祖の「如何即是」も普通は「どうならばいいんですか?」という質問文として解釈されますが、ここでは「如何なるも即ち是なり」と平叙文として読んで、「いかなるものも作仏である」と理解するべきです。この問答の始めのところにわざわざ道元禅師は「江西大寂禅師(馬祖)、ちなみに南嶽大慧禅師に参学するに、密受心印よりこのかた、常に坐禅す。」と書き、この時の馬祖がすでに南嶽の法をしっかりと受け継いでいるという前提に立っていることを明らかにしています。当然のこととして、馬祖は坐禅が同時に作仏であることはすでに充分わきまえているのですから、「どうあればいいのですか?」などという質問をするはずがありません。馬祖は「即心是仏」ということを説いた人として有名ですが、小川隆先生は『禅思想史講義』(春秋社)の中で、この言葉について「己が心、それこそが「仏」なのだ。その事実に気づいてみれば、いたるところ『仏』でないものはない。」と解説しておられます。道元禅師の場合は、坐禅が行じられているところではじめてそれが言えるという立場(「修証一等」)ですが、今読んでいる「如何即是」もそれと同じ線上で理解できると思います。これは、馬祖独特の言い方で、道元禅師の「現成公案」と同じく、坐禅という行為(こちら=「這頭」=如何)とそれが開く作仏の事態(あちら=「那頭」=即是)の同時性を表しているのです。『弁道話』の中には「もし人一時なりといふとも、三業に仏印を標し、三昧に端坐するとき、遍法界みな仏印となり、尽虚空ことごとくさとりとなる。」をはじめとして、この坐禅と作仏の同時現成(「一時の出現」)の様子がいくつも述べられています。
つまり、南獄の「如人駕車、車若不行、打車即是、打牛即是」という言葉は、上の引用のような意味合いで語られた馬祖の「如何即是」、つまり「いかなるも即ち是なり」をさらに深掘りし敷衍するために出されているのです。いかなるも即ち是なら牛車もその中に是として含まれていなければならないはずです。「遍法界みな仏印となり、尽虚空ことごとくさとりとなる」以上、そこから牛車が除外されることはあり得ません。いや、むしろ、遍法界、尽虚空のことを仮に牛車と言っているのだと解してもいいのかもしれません。
ですから、文面上は「人が牛車に乗っていて、もし、その牛車が動かない時には、車を鞭打ったらいいのか? それとも牛を鞭打ったらいいのか?」と、打車がいいのか、それとも打牛がいいのか、二者択一の答えを迫っている質問文になっていますが、そう読んだのでは馬祖の言った「如何即是」の趣旨に呼応することができなくなります。これまでの議論でも繰り返し述べてきたように、この南獄の一見質問文に見える問いかけは、実は問いかけではなく、坐禅の本質を解説している平叙文であると理解するべきです(「問処の道得」)。この南獄の言葉の後に続く道元禅師のそれについての評釈も、如何即是であるからには、打車も即是であり、打牛もまた即是であるという観点からなされていることは明らかです。ですから、南獄の言葉にある、「若」の字も「若しif」の意味にではなく「若(すで)に=現に」の意味にとり、「車はすでに不行であるから、車を打つのも是であり、牛を打つのも是である」ということになります。
道元禅師はまず「車若不行」という表現を問題にし、車が行く、あるいはその逆の車が行かない、というのはどういうことなのかと問います。ここでいう「車」とはそもそも何を喩えたものなのでしょう。常識的には、人を乗せてどこかへと運んでいくために作り出した乗り物が車です。現代のわれわれなら、ガソリン、あるいは電気で動く自動車のことになりますが、この場合は八世紀の中国のことですから、人が車に乗り、それに牛をつなげて引いて行かせる牛車のことを指しています。もちろん、二人が話しているのはそういう世間的な意味での牛車のことではなく、仏法上の「牛車」です。
当然、南獄と馬祖、二人の念頭には、『法華経』にある有名な「三車火宅」の喩えが背景として共有されていたことでしょう。それは大略こんな話です。ある長者の家が火事になりました。彼の子供たちはそれに気づかず遊んでいます。長者は早くこの邸宅から外に出るようにと声をかけますが、子どもたちは言うことを聞きません。そこで長者は一計を案じ、「おまえたちが欲しがっていた羊車・鹿車・牛車が門の外に並んでいるぞ! 早く外に出てこい!」と叫びます。それを聞いた子どもたちが喜び勇んで外に出てくると、長者は約束していた三つの車ではなく、別に用意した大きな白い牛が引く豪華な車(大白牛車)を子どもたちに与えました。
南獄がいう「車」とは、この『法華経』の譬えの中で言われている「大白牛車」のことだと理解する必要があります。羊車・鹿車・牛車は衆生の資質に合わせて方便として説かれた声聞乗、独覚乗、菩薩乗の教えを指し、大白牛車は『法華経』が説く真実無上の一乗の教え(「唯有一乗法」あるいは「唯有一仏乗」)を意味しています。われわれはすでに絶対に落ちこぼれようのない無限大の乗り物に乗って今現在運ばれている最中なのだというのがこの一乗、つまり大乗の教えの核心です。
私はある時期、明治期の宗教哲学者であり真宗大谷派(東本願寺)の改革運動に尽力した清沢満之の書いたものを読んでいたことがあります。彼の『絶対他力の大道』にある「自己とは他なし、絶対無限の妙用に乗託して、任運に法爾に、此現前の境遇に落在せるもの、即ち是なり」という文章に強い印象を受けました。南獄が牛車の喩えで言わんとしているのは、ここで清沢満之が言っている「自己が乗託している絶対無限の妙用」のことと解することができるのではないでしょうか。
では、このような意味での車が行く、行かない(不行)とはどのようなことを指すのでしょう。「絶対無限の妙用」なのですから、もはや、通常の意味での相対的な行く・行かないではないことはお分かりでしょう。この車は外から対象的に眺めて、それが自分に対して動いているとか動いていないとかを論じられるような「水くさい」車のことではなく、すでに自分がその中に親密に浸り込んでいる絶対に対象化できない車のことなのですから、それが行く、あるいは行かないという表現を理解するにはくれぐれも用心が必要です。したがって、「いかならんかこれ車行、いかならんかこれ車不行」という表現は一見すると「どんなことが車行だろうか? どんなことが車不行だろうか?」と質問しているように見えますが、いつものようにこれは質問としてではなく「いかなることも車行であり、いかなることも車不行である」と読む必要があります。一切の事を車行と言ってもいいし、一切の事を車不行としてもいいのだということです。
そのことを明らかにするために、ここでは、道元禅師は車の行・不行を水の流・不流と絡めて「たとへば、水流は車行なるか、水不流は車行なるか。流は水の不行といつべし、水の行は流にあらざるもあるべきなり」と論じています。前にも言いましたが、道元禅師の書いた文章では「○か、□か」という表現が出てくる時は「○であり、□である」という強い断定の意味である場合が多いので、ここでも「水流も車行であり、水不流も車行である」と読みます。水が水として流れるのは水の不行(水自身の変わらぬ性質)と言ってもいいのです。もしそうなら、水が行く(移動する)のは不流ということだとも言えるはずです。この辺りの道元禅師特有のレトリックは、車の行・不行と水の流・不流を交錯させて、われわれの常識の硬直を解きほぐそうとしているように思えます。
ですから、南嶽の語った「車若不行」という表現の深い意味を参究するには、「不行あり」とも「不行なし」とも理解しなければならないと道元禅師は言います。車不行には固定的で決まった姿があるのではなく、その時その時の真実としてさまざまな様相があるのです(「時なるべきがゆえに」)。絶対無限の妙用としての大白牛車においては、「車若不行」と言っても、必ずしも不行の時ばかりでなく、行という時もあるという道理を知らなければなりません。
次に、打車と打牛のことが論じられています。ここで「打」というのは「打ち込むこと」、つまり精進努力のことと考えればいいでしょう。ですから、ここでは打車も打牛も坐禅の努力の仕方のことを指しているのです。「打車もあり、打牛もあるべきか。打車と打牛と、ひとしかるべきか、ひとしからざるべきか。」ここにも例の「○か、□か」というレトリックが使われていて、「打車もあるべきだし、打牛もあるべきだ。打車と打牛と、等しい時もあるべきだし、等しくない時もあるべきだ」の意です。坐禅においてはどちらの努力も両方ともにあり得るというのです。そして、世間や凡夫には打車の法はないけれども、仏道にはそれがあると道元禅師は言います。牛と車と人とが一つになってはじめて「実際に人が乗って動く車」が成り立っているのですから、世間や凡夫のように牛しか打たないというのは極めて一面的であり偏っていると言わなければなりません。それに対して、仏道修行においては牛を打つだけではなく、車を打つという世間では想像もつかない努力もなければならないのです。世間や凡夫には想像もつかない打車の努力というのは、たとえば『正法眼蔵 生死』にある、「ただ、わが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆく」という放下と随順の努力が、その実例ではないかと個人的に連想している次第です。修行にはそういう打車という努力があることを承知しておくことが重要なポイント(眼目)なのです。打牛とは異なる打車のあり方をきめ細かく参究工夫していかなければなりません。
打牛にしても世間のやり方とはまったく異なっているので、仏道の打牛の仕方とはどのようなものかをさらに学ぶ必要があると道元禅師は説きます。打つ対象である「牛」にちなむ古則公案からの連想で、「水牯牛」、「鉄牛」、「泥牛」といろいろな牛が出てきますが、これは決まりきった固定的なパターンを繰り返すのではなく、そのつどそのつど姿を新たにして現れてくる現実に新鮮に出会い、フレッシュに適時適切創造的に取り組むべきことを表現しているのだと思います。坐禅の修行が一本調子に陥らないということです。
次に、牛を打つにしても、何をもって牛を打つかを問題にしたのが「鞭打なるべきか、尽界打なるべきか、尽心打なるべきか。打迸髄なるべきか、拳頭打なるべきか。拳打拳あるべし、牛打牛あるべし」という一節で、いろいろなものをもって牛を打つことができなくてはならないことを言っています。「拳打拳あるべし、牛打牛あるべし」は、究極的には何かが何かを何かで打つというような主体と客体が二元的に分かれた話ではなく、拳が拳を打ち、牛が牛を打つと言う他はない、「自分が自分を自分する」自受用三昧の打牛になります。
南獄の「如人駕車、車若不行、打車即是、打牛即是」という言葉に対して、馬祖は無対、つまり何も答えませんでした。この無対を、馬祖が単に何もできないで言うべきを言わず、口を閉ざしていただけだとその真意をいたずらに浅く見誤ってはいけないと道元禅師は注意をうながしています。「抛塼引玉」は「塼をなげうって玉を引く」と読んで、塼を投げて玉を手に入れるという意味です。「回頭換面」は「凡夫の頭をめぐらして、面を換えて仏になる」ということです。いずれも出典のある禅の言葉ですが、ここの文脈では大寂(馬祖)の無対(無言)が大変優れていることをこれらの言葉で称えていると解するべきです。「攙奪」は「市場の商人が売りたくないというものを無理矢理に奪うこと」で、大寂の無対に対してそういうことをするべきではないというのです。この時の大寂の無対はそれほど貴重な甚深の意味を持つものであるから横から無闇に手を出して奪うようなことをしてはならないということです。
以上のような考察を踏まえて、今回の箇所を次のように現代語に訳してみました。原文と対照させながら、読んでいただければ幸いです。
南嶽が言った。「(おまえの見事な表現『如何即是』をわたしなりに説明してみよう。)坐禅をするということは人が車に乗るようなものだ。車に乗っていること(坐禅していること)それ自体が大事なのであって、車が進もうが進むまいが、作仏には関係がない。車にさえ乗っていれば車を打ってもよいし、牛を打ってもよい」(一般にはこの南嶽の言葉は「坐禅をしていてもなかなか悟りが得られない場合に、身の坐禅をさらに努力するべきか、心の修行をするべきか?」という問いかけとして解釈され、坐禅への執着をやめて心の工夫をすることをすすめていると解されることが多いが、道元禅師の解釈はまったく違う。だからこの文は「人の車を駕するが如し。車若(すで)に行かず、打車も即是、打牛も即是」と読む)
さて、南獄はここで、「車若不行」と言っているが、いかなること(=一切の事)も車行なのであり、いかなることも車不行でもあるという道理があるのだ。たとえば、水が流れるというのも車が行くことであり、水が流れないのも車が行くことなのだ。流れるというのは水が行かないこと(水の本性)だと言えるし、水が行くと言うのは流れることではないとも言えることを見逃してはならない。
なぜなら、流れるというのは水の本来の姿なのであるから、それを不行(水としては変化なし)と言い得る道理もある。したがって、水が行く(=流)というのは流れにあらざる(=不流、つまり不行)ということもある訳だ。(水流、車行は坐禅・磨塼であり、水不流、車不行は作仏・作鏡に対応していると想定することもできるだろう)このようであるから、南嶽の言った「車若不行(通説のように「車が若し行かざれば」、とは読まないで、「車はすでに不行なり」、と読むべきである)」という言葉を深く参じ究めようとするなら、不行があるとも受け取らなければならないし、不行がないとも受け取らなければならない。車行と車不行とを二つ並べて論じるということはできない(お互いに完全に相補的。一方があったら一方は消える。両方が一緒になってどう関係しているかということは問題にできない)。それは「時」しだいだからだ。車不行の「とき」は車行は見えないし、車行の「とき」は車不行は隠れる。時が違えば名も違う。このように、「若不行(すでにいかず)」という表現は、ただ不行の一面だけを断定して語っているのではない。そこには車行と車不行の両面の意味が込められていることを見逃してはならない。
南嶽が「打車即是、打牛即是」と言ったことも、「車を打つのがよいのか? それとも、牛を打つのがよいのか?」とA or Bを尋ねているのではない。つまり、どちらが正しいかを選べと言っているのではない(坐禅に当てはめて言うなら、行と証をわけたうえでそのどちらかをとれ、という話なのではない)。そうではなく、「車を打つ」ということもあるし、「牛を打つ」ということもあるはずだ、と言っているのだ。「打車も即ち是、打牛も即ち是」ということだ。車を打つことと牛を打つことは、等しいのか? それとも等しくないのか? 人が牛車に乗るということは坐禅をするということの例えとして出されているのであるから、<人-牛-車>を一体のものとして見るなら、車を打つことも、牛を打つことも等しく、人が牛車を打つ(=行ずる)こと、すなわち坐禅の営みとして理解することができる。しかし同時に、打車は坐禅という行、打牛は作仏という証という違いもあることを見逃してはならない。強いて言うなら両者は不一不二、不即不離の関係にあるのだ。
世間には牛車が進まない場合に、車を打つという法(ありかた)はない。凡夫の世界では車を打つという法はないけれども、ここでの南嶽の言葉のおかげで仏道には車を打つという法があることを知った。それがここでの参学の大切なポイント、眼のつけどころなのだ。しかしたとえ、仏道には車を打つという法があることを学得したといっても、それが牛を打つことに等しいと単純に決めてかかってはならない。その点については詳細に究明していくべきである。打車すなわち坐禅の道理をよくよく究めるべきだ。
また、牛車が進まないときに牛を打つという法は普通に世間にあることであるけれども、仏道における牛を打つことについて、世間一般の牛のたたき方に準じてそれを理解したと思い込まずに、さらに追及し究明していかなければならない。すなわち、仏道において牛とはなにか、打つとはどのようなことなのかを参究するべきなのだ。水牯牛(南泉普願や潙山霊祐の公案に出てくる牛)を打牛するのか、鉄牛(善月光遠や風穴延沼の公案に出てくる牛)を打牛するのか、泥牛(龍山和尚の言葉に出てくる牛)を打牛するのか(以上、公案に出てくるさまざまな牛が列挙されているが、これらは坐禅における作仏のありようについて、牛のメタファーが用いられた代表的な表現を挙げたものと理解できる)、鞭で打つのか、尽十方界をもって打つのか(尽十方界自己を挙げての坐禅をする)、尽心をもって打つのか(一心一切法 一切法一心としての心を尽くしての坐禅をする)、勢いよく髄に達するまで打つのか(骨髄に徹する坐禅をするということ)、拳をもって打つのか、と問うていくのだ。さらには、拳が拳を打つということがあるべきだし、牛が牛を打つということもあるべきだ。打つというときに普通は「打つもの」と「打たれるもの」という二つの別々な実体を想定するが、ここではそのような二元論が否定される。「それ」が「それ」を打つという表現は、坐禅においては打つ拳と打たれる牛とは一つであり、全体ただ拳ばかり、あるいは全体ただ牛ばかりであることを指している。
これに対して馬祖は返事をしなかった。この無対は返事に窮して答えられなかったということではない。「坐禅のほかに作仏はない」、ということを言語にわたらず、無対という行為で完全に言い抜いていることをわれわれは正しく読み取らなければならない。南嶽の「打車即是、打牛即是」という言葉の趣旨をしっかりと受け止めた上での馬祖の無対なのであるから、馬祖が無言であったことの真意を空しくとらえそこなうようなことをしてはならない。仏教、特に禅の世界における問答では無対=沈黙のもつ意味を簡単に見過ごしてはいけないのだ。彼の無対は「塼を捨てて珠玉を引き取る」、「頭をめぐらして面を換える」という深い意味内容を帯びた無対である。そのような貴重な無対をむりやりひったくるようにして、安物買いしてはならない。