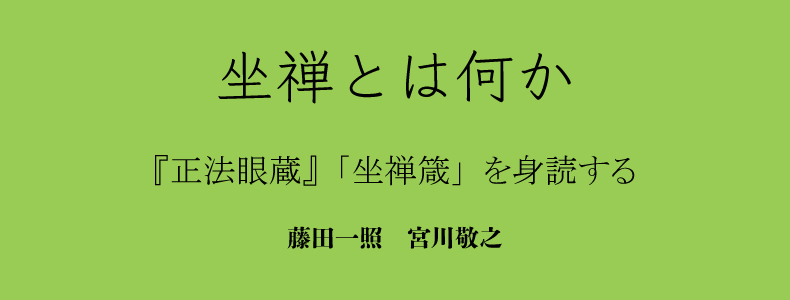磨塼と「わからなさ」
【宮川敬之】身読コラボ⑩
〈「わからなさ」を呼び起こす〉
南嶽、ときに一塼をとりて石上にあててとぐ。大寂つひにとふにいはく、師作什麼。
まことに、たれかこれを磨塼とみざらん、たれかこれを磨塼とみん。しかあれども、磨塼はかくのごとく作什麼と問せられきたるなり。作什麼なるは、かならず磨塼なり。此土・他界、ことなりといふとも、磨塼、いまだやまざる宗旨あるべし。自己の所見を自己の所見と決定せざるのみにあらず、万般の作業に参学すべき宗旨あることを一定するなり。しるべし、仏をみるに仏をしらず、会せざるがごとく、水をみるをもしらず、山をみるをもしらざるなり。眼前の法、さらに通路あるべからずと倉卒なるは、仏学にあらざるなり。
南嶽は、馬祖の「作仏を図る」という言葉を聞くとすぐ、割れ瓦を拾い、そこいらの石に当てて磨きはじめた。大寂(馬祖)はこれを見ていぶかしんで問うて言った。「師よ、什麼(なに)をかなす」。
実のところを言えば、だれもがこれを、割れ瓦を石で磨く(磨塼の)行為であるとわからないわけはない。しかし、磨塼の行為の真実を見ることができるものはいないのだ。だからこそ磨塼ということがらが、「什麼をかなす」と問いただされたのである。「什麼をかなす」という言いとりによって、磨塼の行為の中心が問われたのだ。この世俗諦の世界と、仏の聖諦の世界とは異なるが、その両方で、磨塼は、決して止むことない教えとしてあるのである。自分が見聞きしたところが、自分が見聞きしたところだとは決定できないとするだけでなく、あらゆる作業のうちに仏道の実践のしかたをかならず見る見方をすえよ。しっかりとわきまえよ。われわれは仏を見ても仏とはわからず、理解できないのであるが、それと同じように水を見ても水の真のありようがわからず、山を見ても真のありようはわからないのだ。しかし眼の前には修行を勤めるべき仏法があるのであって、そこになんの修行への通路もないにきまっていると早合点してしまうのは、仏道を学ぶという態度ではない。
今回の読解は、馬祖道一の坐禅と「作仏を図す」という言葉に対して、師の南嶽懐譲が行った行為についてです。南嶽が行ったのは、庭先に落ちている割れた土瓦を拾ってそこらあたりの石に当てて研ぎ、磨くという行為でした。割れた瓦の破片が容易に拾うことができるというのは、南嶽や馬祖が修行している場所が、火事や戦乱などによって焼け崩れてしまった寺院跡に臨時的に建てられた、簡素な小屋のような寺院であったことを想像させます。そこは決して、塵一つ落ちていない立派に整備された大寺院ではなかったということです。また塼という瓦は、現在の瓦によく見る釉薬などは表面に塗られていない、素朴な瓦を想像しておく必要があるでしょう。瓦の表面は光を反射せず、ザラザラとしていて、文字通りの瓦礫です。
ザラザラとした割れた土瓦を砥石でもないただの石に当てて磨いても、何にもなりません。玉や鏡であれば磨けば光るでしょうが、割れた土瓦を磨いても光ることはなく、貴重なものにも、有益なものにもならないからです。ですからこの磨塼の行為は、「常識的には無駄な行為」あるいは「常識的には理解できない行為」を「意味」しているとすぐさま考えられてしまいます。しかし、「常識的には理解できない行為」という「意味」として認識することは、かえって(あるいはいまだに)「常識」の範囲内で理解しているということです。「常識」の臨界に直面することそのものが必要であるならば、むしろここで要請されるのは「意味」よりも「わからなさ」でしょう。それで次のように言われているわけです。
実のところを言えば、だれもがこれを、割れ瓦を石で磨く(磨塼の)行為であるとわからないわけはない。しかし、磨塼の行為の真実を見ることができるものはいないのだ。だからこそ磨塼ということがらが、「什麼をかなす」と問いただされたのである。「什麼をかなす」という言いとりによって、磨塼の行為の中心が問われたのだ。この世俗諦の世界と、仏の聖諦の世界とは異なるが、その両方で、磨塼は、決して止むことない教えとしてあるのである。
「什麼(しも あるいは そも)」とは中国語の俗語で、「なに」という意味です。つまり「師、什麼をかなす」とは、「お師匠様はなにをされているのでしょうか?」という疑問文です。馬祖は南嶽の磨塼の「意味」が理解しなかったわけはない。南嶽の磨塼が「常識的には無駄な行為」「常識的には理解できない行為」だという「意味」であることは、馬祖は十分に理解しているわけです。しかしそこであえて「師、什麼をかなす」と尋ねたのは、改めて磨塼の行為を「常識」すなわち「言葉の範疇での言いとり」の臨界に直面させる必要があったからです。道元禅師はそのように解釈されます。道元禅師が馬祖の「什麼」という疑問=表現に着目したのは、そこに「わからなさ」が要請されているという点であったと私は理解します。「わからなさ」を要請するとはどういうことでしょうか。先回の最後に私は、坐禅の「わからなさ」について述べました。再録します。
坐禅は、論理や意志や主体によって統御できるフィクションではなく、実際に手足を組んで呼吸を整えて坐る実践です。だからこそその実践は、ほぼいつも確実に、意図や意志から外れた結果になります。心を落ち着けたスマートな状態にはなかなかならず、いったい自分はなにがしたいのか、なにを求めているのか、こんなことをして何になるのか、わからなくなるのです。(中略)私は自分では、スマートに坐りたいと思いますが、その思惑はことごとくはずれ、ただ、私は自分の身と心で、出たとこ勝負で坐っているだけです。私には坐禅がなにかは「わからない」のです。
坐禅の意味は「わからない」。それは、坐禅が論理ではなく、実践だからです。
南嶽の磨塼に対して、馬祖が「什麼」と問うて「わからなさ」を要請したのは、坐禅という実践を立ち上がらせるためだと思います。ここで注意したいのは、「什麼」に関して、よく見られる解説のありようについてです。「什麼」は「なに」という疑問詞で疑問文を作りますが、それが不定なものを指すことから、禅の伝統では「什麼」によって「常識(世俗諦)では理解できない仏のさとりのありさま」を表現する場合があります。そうなると「師、什麼をかなす」というのは、「お師匠様はなにをされているのでしょうか?」という疑問文として読むことができると同時に、「お師匠様は什麼(仏のさとり)を示されていますね!」という平叙文にも読めるということになります。よく見られる解釈とは、「什麼」をこうした平叙文の意味にすぐに変換してしまうもので、その代表としてたとえば、「「什麼」とは純一無雑の(純粋でまじりけのない)さとりのことだ! 「これ」がわかるか!」と強く断言する解説がなされ、私もそれを実際に聞いたことがあります。
たしかに「什麼」=「純一無雑のさとり」とすることは、禅の伝統においても、そして道元禅師の坐禅を解釈するのにも必要な視点だと思います。しかしこの解釈を安易に導入してしまうと、せっかく「常識」の範疇での言いとりを外れるために臨界に向かおうとしているのに、その試みについて注目せず、またすぐに「常識」の範囲内に回収してしまっているように思えるのです。先回にも言いましたが、道元禅師の解説を読む限り、「什麼」を「仏のさとり」だと簡単に「常識的」に解釈してしまうことはできません。たとえば「作仏」について述べた先回の箇所では、次のように言われていました。
しるべし、大寂の道は、坐禅かならず図作仏なり、坐禅かならず作仏の図なり。図は作仏より前なるべし、作仏より後なるべし、作仏の正当恁麼時なるべし。且問すらくは、この一図、いくそばくの作仏を葛藤すとかせん。この葛藤、さらに葛藤をまつふべし。
大寂(馬祖)が言った教えによれば、坐禅はかならず「図作仏」だと言うのである。坐禅とは、作仏の図であると言うのである。描かれた絵図としての作仏のすがたは、作仏の行為よりある場合には以前に出現し、また、ある場合には以降に出現し、さらにある場合にはまさしくその行為としての作仏のさなかに出現する。ここでさらに問うならば、この絵図はどれほどの作仏のありようを表現することができているのか。この表現を乗り越える表現を、さらに表現してみよ。
私たちは、磨塼という行為を「磨塼だな」と常識的に言いとりをしてしまうことに対してペンディングをかけ、「常識」の臨界を示そうとした馬祖に倣わなければなりません。このペンディングこそが「什麼」であり、「わからない」という態度なのであって、そのうえではじめて、磨塼についてのそれぞれ独自の考察が始まるのではないでしょうか。いったい磨塼とはどういう行為なのか。その解答はレディ・メイドのものではなく、私たち自身が自分で作り出さなければならないのです(ですからこの「身読」の考察はあくまで私の弁道としての考察にすぎません。読者の方々には、それを鵜呑みにせず、それぞれの弁道において読んでいただきたいと思っています)。
〈磨くこと=画くこと〉
磨塼を検討するにあたって、磨くとはそもそもどういう行為なのかを考えてみましょう。まず、なにかが磨かれていることを私たちはどのようにして知覚するでしょうか。それはいうまでもなく、その面になにかが映りこむことによって知覚します。ですからなにかを自分が磨く際には、自分の顔やすがたが磨いた面にどれほどクリアに映りこむか、つまり自分の顔やすがたがそこにどれだけ詳細に画かれているかによって、磨かれた度合いを判断するのです。この意味で私たちにとって磨くという行為は、磨くべきその面に自分のすがたを画きだしていく行為と密接に関連していることになります。しかし磨塼の行為において、塼=土瓦のうえに、どのように自分のすがたを画き出せるのでしょうか。「画に画いた餅」というトピックを中心的に扱った『正法眼蔵』「画餅」巻において、道元禅師は画くということがらをつぎのように言っていました。
いま山水を画するには、青緑丹雘をもちい、奇巌怪石をもちい、七宝四宝をもちいる。餅を画する経営もまたかくのごとし。人を画するには、四大五蘊をもちいる、仏を画するには、泥龕土塊をもちいるのみにあらず、三十二相をももちいる、一茎草をももちいる、三祇百劫の熏修をももちいる。(『道元禅師全集』第一巻 270-271頁 春秋社 1991)
現在山水を画くには、青緑や丹雘(などの顔料)を用いるのであり、奇岩、怪石を用い、七宝、四宝を用いるのである。餅を画く行為もまたこのようなことである。人を画くには、四大五蘊を用いるのであり、仏を画くには、泥の厨子や土塊を用いるだけではなく、三十二相(仏の三十二の身体的特徴)を用い、一茎草(一本の草)を用い、三祇百劫の菩薩としての修行を用いるのである。
山水の図を画くには、青や赤の顔料を使うわけですが、その顔料のもとは鉱物であり、それをすりつぶして粉にし、膠と混ぜて初めて顔料となります。要するに、山水を画く顔料はもともと山水の一部であるわけです。画くものと画かれるものとは、別々に見えても、根本は一つなのだということです。七宝(金・銀・瑠璃・シャコ・メノウ・サンゴ・琥珀・真珠などの宝石類)、四宝(同様の宝石類を指すか)にしても、山のなか水のなかから取れた鉱物や動物、動物や植物の分泌物ですから、それは山水の一部です。同じように、餅を画くにしても、墨や顔料で画けば食べられませんが、もち米などのエディブルな材料で画くならば当然食べられることになる。ならば人間も四大五蘊を使って画けば本物の人間を画くことになる。仏を画くには土や木だけではなく、仏の三十二相によって画くならば仏そのものとなる。つまり、画くことが偽物をつくることのように(「画にかいた餅は飢えを充たさない」という言い方のように)認識されるのは、ただ単に材料の選択の問題にすぎないというのです。材料をそのものと同じにするならば、画く主体と画かれた対象とのあいだに違いは無くなってゆく。そして、山水であれ餅であれ私たちであれ、構成する四大(地水火風)という構成要素は同じであるため、画く主体と画かれた対象の違いは、いずれにせよ限りなくゼロに近づくのです(仏祖を画く場合には、四大の構成要素ではなく仏の構成要素である三十二相によって画かれるといわれます)。
このように道元禅師によって画くこととは、そのものを同時に相手側にも作り出すことです。自分を画くときには、自分を自分の構成要素によって相手側にも同時に作り出すことだといえます。その場合に、自分とむこうの自分とのあいだの鏡面対称面上に、まさに画くという行為があることになります。すると画くという行為は、一種の鏡面を作り出すことに近づき、さらに磨くという行為に近づいていくことになるでしょう。実際に、『正法眼蔵』「古鏡」巻で次のように言われています。
しるべし、いまいふ古鏡は、磨時あり、未磨時あり、磨後あれども、一面に古鏡なり。しかあれば、磨時は、古鏡の全古鏡を磨するなり。古鏡にあらざる水銀等を和して磨するにあらず。磨自・自磨にあらざれども、磨古鏡なり。未磨時は、古鏡くらきにあらず、くろしと道取すれども、くらきにあらざるべし、活古鏡なり。おほよそ鏡を磨して鏡となす、塼を磨して鏡となす、塼を磨して塼となす、鏡を磨して塼となす。磨してなさざるあり、なることあれども磨することえざるあり。おなじく仏祖の家業なり。(同237頁)
わきまえよ。ここに言う古鏡は、磨する時も、まだ磨していない時も、磨した後も、同じように一面の古鏡なのだ。そのようにして、磨する時は、古鏡でもって、古鏡の全体を磨するのである。古鏡でない水銀等を加えて磨するのではない。自分が磨されるのか、自分を磨するのかは判別できないながらも行うのが、古鏡を磨するという行為なのだ。磨していない時には古鏡が黒ずんでいるのではない。黒ずんでいるとしても、それを汚れによって暗くなっているわけではなく、生き生きと映し出す古鏡なのだ。そもそも、鏡を磨して鏡になるのと同じ行為でもって、土瓦は磨して鏡となり、土瓦は磨して土瓦となり、あるいは鏡は磨して土瓦となるのである。(磨することとその結果とは必ずしも一致しない。)磨してそのものにならない場合もある。そのものになっているのになにも磨することもしていない場合もある。しかしそれは、(ともに古鏡の全体でもって古鏡全体を磨しているという)仏祖の日常の行いなのである。
まことにしりぬ、磨塼の、鏡となるとき、馬祖作仏す。馬祖作仏するとき、馬祖すみやかに馬祖となる。馬祖の、馬祖となるとき、坐禅すみやかに坐禅となる。かるがゆえに、塼を磨して鏡となすこと、古仏の骨髄に住持せられきたる。(同238頁)
ここにおいて真によく理解できるのである。磨塼によって鏡となるときに、馬祖は作仏するのだ。馬祖作仏のときとは、馬祖がすぐさまに馬祖となるときである。馬祖が馬祖となるときとは、坐禅がすぐさまに坐禅となるときである。そのようであるから、塼を磨して鏡となすことを、古からの仏たちは教えの骨髄として守ってきたのである。
土瓦の上に自分の四大五蘊を使って自分を画く=磨するとは、土瓦と自分がおなじ四大の構成要素によってできていることを感じ、土瓦に自分を見ることです。すると磨塼のさなかに、磨いている人が自分の自我でもって磨いているのか、土瓦に四大によって画かれた自分に磨かされているのか、よくわからなくなってくるのです。これは墨を磨ることを例にとって考えればよく理解できることがらです。墨を磨る際に私たちは、自分の意志で墨を磨っているのか、墨が私に磨らせているのか、墨を磨るという行為そのもののうちで、よくわからなくなってしまうことが起こります(いやむしろ、以前に述べたように、そのように誰が墨を磨っているのかわからなくなるときにのみ、真に墨は磨ることができる(=出来する)ともいえるでしょう)。
このようにして、磨塼のさなかにおいて、自分自身を絶対的な起点とする認識に動揺が生まれます。それが新たな認識、いわば、行為の主体が磨く人の自我ではなく、むしろ磨塼の行為そのものが、自分に知覚できない「なにか」として立ち上がってゆくという、新たな認識への変容を促します。画く=磨する行為の結果として土瓦のうえに自分が画かれるのではなく、画く=磨く自分と画かれた=磨かれた自分とが対応するところに、画く=磨する行為そのものが、「わからない(什麼)」=「なにか」=「非思量」として立ち上がってゆくのです。
重ねて注意すれば、こうした認識の変容は、磨く人の側からすれば、まずはなにをしているのかよくわからないというように、自分の認識の臨界に直面した認識(=「わからない」)ということがらとして認識されるはずです。決して「自分は認識が変わった! 新たな認識を獲得した!」と自分が主張できる変容ではない、という点が重要なところです。もちろんその一方で、「わからない」から表現することを放棄してよいということにもなりません。道元禅師が私たちに要請するのは、「わからない」というペンディングをしつつも、その表現に対してなおも新たな言いとりを実践してみろということです。磨塼についてこのように迂回して考えてみて初めて、今回の箇所の後半部分が読めてくるように思えます。
此土・他界、ことなりといふとも、磨塼、いまだやまざる宗旨あるべし。自己の所見を自己の所見と決定せざるのみにあらず、万般の作業に参学すべき宗旨あることを一定するなり。しるべし、仏をみるに仏をしらず、会せざるがごとく、水をみるをもしらず、山をみるをもしらざるなり。眼前の法、さらに通路あるべからずと倉卒なるは、仏学にあらざるなり。
この世俗諦の世界と、仏の聖諦の世界とは異なるが、その両方で、磨塼は、決して止むことない教えとしてあるのである。自分が見聞きしたところが、自分が見聞きしたところだとは決定できないとするだけでなく、あらゆる作業のうちに仏道の実践のしかたをかならず見る見方をすえよ。しっかりとわきまえよ。われわれは仏を見ても仏とはわからず、理解できないのであるが、それと同じように水を見ても水の真のありようがわからず、山を見ても真のありようはわからないのだ。しかし眼の前には修行を勤めるべき仏法があるのであって、そこになんの修行への通路もないにきまっていると早合点してしまうのは、仏道を学ぶという態度ではない。
〈それは断固として可能である〉
「自分が見聞きしたところが、自分が見聞きしたところだとは決定できない(自己の所見を自己の所見と決定せざるのみにあらず)」という道元禅師の今回の言葉を読むと、私にはどうしても参照したい箇所があります。それは、先回から参照している美術家岡﨑乾二郎氏の著述のなかの、つぎのような言葉です。
けれど制作者の立場からすれば、こんな他人と共有されることを前提にした経験というものは問題にするには値しない。ゆえに「他人が見ている青と自分が見ている青が同じかどうか確かめることはできない」というヴィトゲンシュタイン流の問いもこの問いに限り、偽の問いとして斥けなければならない。そもそもわれわれは「自分が見ている青が自分が見ている青と同じかどうかすら確かめることはできない」はずなのだから。絵を描く人なら誰でも知っている、こうした条件のもとで経験そして作品はいかに組み立てられるのか。つまりは他者と共有できないどころか、それに対応するいかなる外的対象も持たない経験、外在的な徴も差異もいっさい持たない経験の確かさを組み立てることが何故可能になりうるのか(それは断固として可能である)。(岡﨑乾二郎『ルネサンス 経験の条件』319-320頁 筑摩書房 2001)
ここで岡﨑氏が述べている「自分が見ている青が自分が見ている青と同じかどうかすら確かめることはできない」ということと、道元禅師がいう「自分が見聞きしたところが、自分が見聞きしたところだとは決定できない(自己の所見を自己の所見と決定せざるのみにあらず)」こととは正確に同じです。また、「われわれは仏を見ても仏とはわからず、理解できないのであるが、それと同じように水を見ても水の真のありようがわからず、山を見ても真のありようはわからないのだ」という箇所とも響きあうでしょうでしょう。われわれは、自分が主体となって坐禅(=磨く行為)をしていると思ってしまいますが、坐禅において直面する「わからなさ」=「磨塼」においては、そうした図式は変容せざるをえない。われわれは、自分のやっていることが「わからない」し、自分が見ていることがらも「わからない」のです。しかしそうでありながらも、その「わからなさ」に直面しつつ、直面し動揺する自分自身をあらためて表現していかなくてはならない。道元禅師が、「そこになんの修行への通路もないにきまっていると早合点してしまうのは、仏道を学ぶという態度ではない(眼前の法、さらに通路あるべからずと倉卒なるは、仏学にあらざるなり)」ということは、岡﨑氏がいう「外在的な徴も差異もいっさい持たない経験の確かさを組み立てることが何故可能になりうるのか(それは断固として可能である)」という言葉と、私にはほとんど交差して聞こえてしまうのです。「それは断固として可能である」。岡﨑氏の言葉は、初めて読んだ二十年前から、坐禅弁道を促し、それを表現する試みへと促し続けています。坐禅論は絵画論であるとする道元禅師の示唆は、こうした交差を私に迫るものとしてあるのです。
【藤田一照】身読コラボ⑩
南嶽と馬祖という中国禅における二人の巨頭(この二人は師匠と弟子の間柄です)の間で行われた坐禅をめぐる丁々発止のやりとりについて、道元禅師の執拗なまでの拈提(ねんてい 古則公案に対する工夫参究の作業)がさらに続いていきます。
先に進む前にこれまでの経緯をざっと振り返っておきましょう。そもそも、師匠の南嶽が弟子の馬祖が坐禅している現場へ行って、「大徳よ(敬意のこもった呼称です)、坐禅図箇什麼」と呼びかけるところから二人のやりとりが始まったのでした。そして、この南嶽の問いに対して、馬祖が「図作仏」と応じました。われわれのこれまでの参究は、こういういわば師弟間の応酬の第一ラウンドをどう理解するかというところまで進んできていました。
南嶽の言った「坐禅図箇什麼」を「坐禅して箇(こ)の什麼(なに)をか図(はか)る」と質問文として読み下し、「なんのために坐禅をしているのか?」あるいは「何のつもりで坐禅をしているのか?」という意味に取るのが普通の読み方です。また、馬祖が言った「図作仏」は「作仏を図る」と読み下して、南嶽の質問に対して「仏になるつもりです」と答えたことにするのが普通です。しかし、こう読んでしまうと、なんの変哲もない問いと答えになってしまいます。道元禅師は南嶽の問いに対しては「この問、しづかに功夫参究すべし」と言い、馬祖の答えに対しては「この道、あきらめ達すべし」と書いています。そのような通り一遍の理解にとどまっていたのではダメだ、さらに参究し、真意に達せよと言うのです。
その程度の浅い理解では、「あなたはなんのためにそんなに一生懸命に勉強しているのか?」と先生が聞いたら、生徒が「はい、いい大学に入るためです。」と答えたという話とたいしてかわりばえのしない「世間的なつもりの話」になってしまうからです。坐禅をしているそのこととは別に、何かを未来に実現されるべき理想として思い描いて(それが「はかる」、「つもる」という意味の「図」です)、それを目指すというtask-orientedな枠組みの話になってしまいます。
「坐禅かならず図作仏なり、坐禅かならず作仏の図なり」と書く道元は、この「図」という漢字を、「仏になろうとする意図」という通常の意味には取らず、「仏が描かれた絵図(作仏の姿)」として論じようとしています。この点については、宮川敬之さんが、この問答を「坐禅図箇什麼=坐禅とは何の絵画か(あるいは、坐禅はどのように絵画で描くのか)」「図作仏=作仏の絵画である(あるいは、作仏を描くのである)」という問答として読むという考えを説得力を持って展開してきています。詳しくは、このコラボ連載の彼の第8回、9回の論考をご覧ください。ここで展開されている道元の坐禅論を絵画論として読み解くという彼のアプローチはとても興味深いものです。
このことに関して、思い出すことがあります。先日、『ゾウの時間ネズミの時間――サイズの生物学』(中公新書)という大変面白い科学書を書かれた本川達雄先生(東京工業大学名誉教授)と対談する機会がありました。その対談に先立って本川先生は「生命の時間・坐禅の時間」と題された講演をされました。その中で、アリストテレスが行為を「キーネーシス」と「エネルゲイア」の2つに区別していることに言及されました。「キーネーシス」というのは、「自前の目的を含んでいない行為」のことで、たとえば、普通の「歩く」という行為は、そのことによってある場所へ到達するのが目的で、歩くこと自体が目的ではありません。「エネルゲイア」というのは、「自前の目的をそのうちに含んでいる行為」のことです。たとえば「見る」という行為は見ると同時に「見てしまっている」のですから、見るという行為にはその行きつく先(目的)である「見た」が含まれており、行為即目的の完成になっています。つまり、「現在形」が「現在完了形」も意味しているような行為なのです。われわれが「生きる」とき、生きれば同時に「生き続ける」という目的が達成されているのですから、「生きる」のはエネルゲイアだということになります。
キーネーシス的行為は目的が行為の外側にありますから、速く到達することにこそ意味があるのです。したがって、キーネーシス的な時間は速さが問題となり、「今」は目的が達成される未来への通過点でしかなく、それ以上の格別な意味は持ちません。それに対して、エネルゲイア的行為は目的が行為の内にあり、行きつく先がないので、速さということはまったく問題になりません。その代わり、現在形が現在完了形になるには、今に、行為をするある程度の長さが必要とされ、その長さの中で今がどれだけ充実しているか(時間の質)が問題になります。
わたしは、この「キーネーシス」と「エネルゲイア」の対比を聞きながら、南嶽と馬祖の問答のことを連想していました。「図」という漢字を、「意図」として読めば、坐禅を「キーネーシス」的に理解していることになります。坐禅の外側に作仏という目的を設定しているからです。もし、それを「絵図」として読むなら、坐禅を「エネルゲイア」的に理解していることになります。絵を描くことはそれ自体が目的であり、その行為自体をいかに充実させるかが最も重要な問題になるからです。道元にとっては当然のことながら、坐禅はエネルゲイアでなければなりません。もし、坐禅をキーネーシス的に行った場合は、もはやそれは坐禅ではなく「習禅」というまったく質の違った行為に変質していることになります。この二つのタイプの行為の分類論を借りるなら、坐禅や経行は「〜のために坐る(たとえば、本を読むために坐る)」、「〜のために歩く(たとえば、駅に行くために歩く)」といったキーネーシス的行為をエネルゲイア的行為に転換したものと言えるでしょう。そうだとすれば、坐禅や経行以外の洗面や掃除やトイレを使うことなど日常的生活行為万般も同じく修行の現場として真摯に取り組むことを強調する禅の伝統は、普通はキーネーシス的行為として行なっていることを最大限、エネルゲイア化することを志向しているということになります。そこでは、洗面すること(掃除をすること、トイレを使うこと、など)がはたして作仏の絵画になっているかどうかということが問われるのです。洗面では洗面仏の絵画、掃除では掃除仏の絵画を描くのですが、この作仏という絵画を描く努力を最も純粋簡素に行なっているのが坐仏を描く坐禅だったのです。
さてでは、今回参究する一節を読んでみましょう。ぜひ、何度か繰り返して音読してみてください。わたしは師匠から、「ありがたくも日本人に生まれたおかげで、『正法眼蔵』の原文が読めるのだから、解説書などに頼らず、何度も音読して理解しなさい」と言われてきました。わかってもわからなくても真剣に音読していると、その日本語のリズムに助けられて、深い意味がどこからか立ち上がってくることが確かにあるのです。
南岳、ときに一塼をとりて、石上にあててとぐ。大寂つひにとふにいはく、師作什麼。
まことに、たれかこれを磨塼とみざらん、たれかこれを磨塼とみん。しかあれども、磨塼はかくのごとく作什麼と問せられきたるなり。作什麼なるは、かならず磨塼なり。此土・他界、ことなりといふとも、磨塼、いまだやまざる宗旨あるべし。自己の所見を自己の所見と決定せざるのみにあらず、万般の作業に参学すべき宗旨あることを一定するなり。しるべし、仏をみるに仏をしらず、会せざるがごとく、水をみるをもしらず、山をみるをもしらざるなり。眼前の法、さらに通路あるべからずと倉卒なるは、仏学にあらざるなり。
ここからが、いわば南嶽と馬祖の問答の第二ラウンドになります。わたしが第一ラウンドと呼んだ「坐禅図箇什麼」→「図作仏」という言葉による応酬のあと、ガラッと場面が変わって今度は南嶽がそこらへんに落ちている瓦のカケラを拾って石にあてがって研ぎ始めます。ここでなぜ塼(かわら)が出てくるのかという疑問が湧いてきます。禅の問答集を調べてみると「南陽慧忠国師の処にある僧問ふて曰く『如何にあらんかこれ古仏心』、国師曰く『墻壁瓦礫(しょうへきがりゃく)』」という道元もよく引用している古則があります。古仏の心とは何かという問いに対して、「垣根、壁、瓦、石ころ」と答えているのです。きっと、この問答をしていた二人の目に見えるところにそういうものがあったのでしょう。禅の問答においては、その現場に当たり前のように存在しているなんの変哲もないものが重要な意味をになって言及されることがあります。
「祖師西来意(達磨大師がインドから中国までわざわざやって来たのはなぜか?)」という或る僧の問いに対して趙州は「庭前の柏樹子」と答えていますが、この柏の樹も彼らの見えるところに実際にあったものでしょう。この僧は「和尚、境を以って人に示すことなかれ」と切り返しますが、趙州は「我、境を以って人に示さず」とそれを否定します。ですから、向こう側に見えている客観的対象として柏の樹のことを言っているのではありません。「わたしがこうしてあの柏の樹を見ていること」というその事実の当体を示しているのです。南嶽が取り上げた塼も二人の足元に一片のかけらのような形で何気なく落ちていたに違いありませんが、これもまた「境」としての塼ではないことは言うまでもありません。客観的対象としての塼が問題なのではなく磨塼、つまり「塼を磨く」という行為そのものに着目しなければなりません。
内山興正老師は「磨塼」と題された次のような法句詩を作られています。
みがき みがき ただみがく
みがくなかに いのちあり
いのちのゆえに ただみがく
ものたりぬまま ただみがく
この詩では何を磨くかということは書いてありません。ポイントは「塼」の方ではなく「みがく」の方にあるようです。この詩では、何をみがくのでしょうか?思うに、われわれが磨くべき塼とは、そのときそのときの「(我がいのちが生々しく出会っている)今ここの具体的現実」のことではないでしょうか。ここでいう現実とは、そのときその場で抜き差しならぬ形で自分が出会ってしまっている現なる(actual)真実のことです。南嶽が二人の眼の前に落ちていたその塼を磨いたというのは、坐禅のときは坐禅にいのちを完全燃焼させ、典座(てんぞ 禅の修行道場において「食」を司る重責を担う役職)のときは典座の仕事にいのちを尽くす「出会うところ我がいのち」という修行のあり方を示そうとしたのではないかとわたしには思えるのですが、どうでしょうか。
この南嶽のプレゼンに対して、馬祖は「作什麼」と応じます。普通ならこれは、「先生、何をなさっているのですか?」という質問文として受け取られることでしょうが、ここでも道元禅師独特の深読みがなされます。「作什麼(そしも)なるは、かならず磨塼なり」とコメントし、「作什麼」ということの実態が磨塼であるとされるのです。ですから、什麼は「何?」という疑問詞としてではなく、思いではつかみきれない、概念で理解することのできない(『法華経』の術語で言えば「言辞相寂滅(ごんじそうじゃくめつ)」)現なる真実そのものを暗示する言葉として使われていると理解すべきです。「什麼(何)をか作す?」ではなく「什麼(いんも)を作す」と平叙文として読み、「真実を修行する」と解するのです。現なる真実というものは、「これこそがそれだ!」と言えるようなコロっと決まった姿、形として既製品的にあるのではありません。たとえば、どのような天候であっても、そのときそのときの状態がそのときの現にして真実な天候であるというようなことを例にして考えることができるでしょう。
『正法眼蔵 現成公案』の中に「何必(かひつ)」という言葉があります。「何ぞ必ずしも~ならんや」という意味で、具体的現実というものは、さまざまな姿をとり、「~でなければならない」というような一定の限られたものではないことです。どのような天候であれ、それは何必なのですから、自分の好みで取捨選択せず、そのときそのときの天候の現実に応じてわれわれは作すべきことを誠実に作すだけです。そして、その現実の全体をわれわれは知り尽くすことはできません。
われわれがどんなに頑張っても自分の感覚の限界、枠組みを超えることはできないので、現実の全貌を見ることはできないということについて、道元禅師は『正法眼蔵 現成公案』の中で次のように論じています。「たとへば、船にのりて山なき海中にいでて四方をみるに、ただまろにのみみゆ。さらにことなる相、みゆることなし。しかあれど、この大海、まろなるにあらず、方なるにあらず、のこれる海徳、つくすべからざるなり。宮殿のごとし、瓔珞のごとし、ただわがまなこのおよぶところ、しばらくまろにみゆるのみなり。かれがごとく、万法もまたしかあり。塵中・格外、おほく様子を帯せりといへども、参学眼力のおよぶばかりを、見取(ケンシュ)・会取(エシュ)するなり。万法の家風をきかんには、方円とみゆるよりほかに、のこりの海徳・山徳おほくきわまりなく、よもの世界あることをしるべし。かたはらのみかくのごとくあるにあらず、直下も一滴もしかある、としるべし。」(『道元禅師全集』第一巻 4-5頁 春秋社 1991)。だから、自分の見たところに落ち着いてしまったり、それでわかったと決め付けたりしてはいけないのです。
以上のような考察をもとに、今回の一節を次のような現代語に訳してみました。
すると南嶽はひとつのかわらをとり上げて石の上にあててそれを磨ぎはじめた。そこで大寂=馬祖は南嶽に問うた。「師よ、それは什麼(なに)と疑問詞でしか指すことができない何とも限定できない「現なる真実」を実際にただ修行するのみということを示そうとして、かわらを磨いておられるのですね!(表面的には「師よ、それは何をなさっているのですか?」と質問しているように聞こえるが、道元禅師はそうはとらない。この文は「師、什麼(なに)を作(な)すなり」と読む。)
たしかに、この南嶽の行為は誰が見ても「かわらを磨いている」と見ない人はいないだろう。しかし、それはものごとの表面だけを見ているのであって、真の意味での「磨塼」として見ている人はだれもいないだろう。だからこそ(「しかあれども」という語は道元禅師の場合、逆接ではなく「しかあれば」という意味で使われることが多い)磨塼は馬祖がやったように「作什麼(そしも)」という問いの形で言い表されてきたのである。「作什麼(そしも)」としか言いようのない、いかなる限定をも超脱した修行=坐禅は、かならず磨塼というありかたをしているのだ。この娑婆世界と他の世界とは異なってはいるが、このような意味での磨塼は決して止むことがないという道理がある。自分の見たところだけをもって自分は確かに見たのだから間違いないなどと決め付けてしまわないだけではなく、いろいろの成す業(わざ)には謙虚に学び取っていくべき根本的な趣旨があることをはっきりと思い定めることが大切である。
次のことはよくよく承知しておかなければならない。(自分の見るところにこだわり、決め付けにとらわれているなら)実は朝から晩まで仏に出会っているにもかかわらず、仏を見ても仏を知ることができず、理解することもできない。それと同じように、水を見ても水を知らず、山を見ても山のことがわからない。水も山も自己の正体と別物ではないにもかかわらず、自己の分別で対象的に向こう側にあるものとして眺めているだけだからだ。目の前にある事物や現象からは奥深い真実に通じる路がないと軽率にも思い込んでしまうようでは、仏道を学んでいるとはとうてい言えない。塼を磨くという眼前の作業そのものに作仏への通路などあるわけがないと軽々しく決めつけてはいけないのだ。