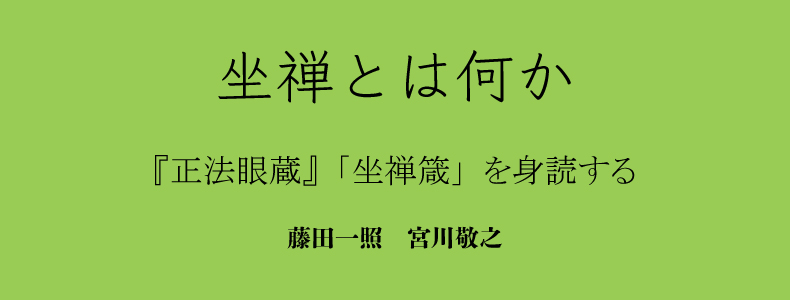坐禅かならず作仏の図なり
【宮川敬之】身読コラボ⑨
〈仏となる主体〉
江西いはく、図作仏。
この道、あきらめ達すべし。作仏と道取するは、いかにあるべきぞ。仏に作仏せらるるを作仏と道取するか、仏を作仏するを作仏と道取するか、仏の一面出・両面出するを作仏と道取するか。図作仏は脱落にして、脱落なる図作仏か。作仏たとひ万般なりとも、この図に葛藤しもてゆくを図作仏と道取するか。
しるべし、大寂の道は、坐禅かならず図作仏なり、坐禅かならず作仏の図なり。図は作仏より前なるべし、作仏より後なるべし、作仏の正当恁麼時なるべし。且問すらくは、この一図、いくそばくの作仏を葛藤すとかせん。この葛藤、さらに葛藤をまつふべし。このとき、尽作仏の條條なる、葛藤かならず尽作仏の端的なる、みなともに條條の図なり。一図を回避すべからず。一図を回避するときは、喪身失命するなり。喪身失命するとき、一図の葛藤なり。
江西(馬祖道一)が言った。「作仏を図る(あるいは作仏を描いた図である)」この言葉を、明確にし、その意味するところに達しなければならない。作仏という言葉は、どのようなものであるのか。仏に作仏されるのを作仏と言うのか。仏を作仏するのを作仏と言うのか。仏が出現し、その仏と自分とが顔を合わせることを作仏と言うのか。「作仏という絵図を描く(図作仏)」とは、(自己の身心が)脱落することだとすると、(自己の身心の)脱落自体も「作仏という絵図」なのか。作仏のありようはたくさんあるが、この「作仏という絵図を描く」ということがらにおける、表現を乗り越える表現(葛藤)を、図作仏と言うのか。
大寂(馬祖)が言った教えによれば、坐禅はかならず「図作仏」だと言うのである。坐禅とは、作仏の図であると言うのである。描かれた絵図としての作仏のすがたは、作仏の行為よりある場合には以前に出現し、また、ある場合には以降に出現し、さらにある場合にはまさしくその行為としての作仏のさなかに出現する。ここでさらに問うならば、この絵図はどれほどの作仏のありようを表現することができているのか。この表現を乗り越える表現を、さらに表現してみよ。こうしたときに、作仏のすべてが同時にそれぞれの細かいありようによって出現し、さらに出現する表現の一つ一つが同時に作仏そのものとなっている。それが表現の一つ一つが絵図となるということだ。絵図として描くことを逃げてはいけない。逃げれば結局この話頭の命を捉えそこない、修行の要点を見落としてしまうのだ。捉えそこない見落とせば、ただ真に迫らない表現だけになるのである。
道元禅師にとって、絵画論と坐禅論とはつながっています。先回に確認したように、「坐禅して什麼(なに)をか図(はか)る」「作仏を図(はか)る」という南嶽懐譲と馬祖道一との問答において、道元禅師が注目したのは「図」という言葉についてでした。この問答における「図」とは、通常であれば、「意図する」と言う意味にとることが正解です。つまり「坐禅して何をしようというのか」「仏になろうと思う」という問答と取ることが、まず妥当な解釈なのです。そうであるところを、道元禅師は、この図を「絵画として描く」という意味に強調して解釈を捻じ曲げます。その結果として、「坐禅とは何の絵画か(あるいは、坐禅はどのように絵画で描くのか)」「作仏の絵画である(あるいは、作仏を描くのである)」という問答として読む可能性を広げたのです。
なぜこうした曲芸のような読み方をする必要があったのでしょうか。絵画論としての坐禅論を見る前に、まず通常の読み方が含む問題について、道元禅師が提起するところを見ておきましょう。「坐禅して何をしようというのか(坐禅して什麼をか図る)」「仏になろうと思う(作仏を図る)」という問答で道元禅師がまず問題にしたのは「仏となる(作仏)」主体はだれか、ということでした。今回の箇所でつぎのように言われています。
作仏という言葉は、どのようなものであるのか。仏に作仏されるのを作仏と言うのか。仏を作仏するのを作仏と言うのか。仏が出現し、その仏と自分とが顔を合わせることを作仏と言うのか。
こうした言い方は、すぐに『正法眼蔵』冒頭の「現成公按」巻にあるつぎの有名な一節を思い起こさせます。
自己を動かして万法を修行し――悟ろうとするのは迷いである。万法がやって来て自己を修行し――悟ろうとするのがさとりである(自己をはこびて万法を修証するを迷とす、万法すすみて自己を修証するはさとりなり)。
「現成公按」巻の一節を響かせて読めば、「坐禅箴」巻において、作仏の主体として自己を立ててしまうことが、警戒されるべきことがらであることがわかります。「現成公按」巻では、自己と万法とのあいだで、修証という行為を行う主体の移動がなされるべきことが説かれていましたが、「坐禅箴」巻ではさらに、そのような作仏の主体の移動を、具体的にどのように行うかが問われています。作仏の主体とは、作仏ということがらに先立って、作仏を行う実体のことです。ですがはたして、こうした実体が実在するのでしょうか。たしかに、「図作仏」の「図」を「意図する」と解釈すれば、作仏という行為に先立って作仏を「意図している」主体を想定しなければならないでしょう。しかし、「図」を「絵画として描く」と読み替えれば、このような「意図する」主体という想定を、外すことができると思えるのです。それはなぜでしょうか。
〈絵画論と坐禅論との接点〉
道元禅師が「図」を「意図する」と読まず、「絵画として描く」と読むのは、「意図する」主体という想定から外れるためである、と私は言いました。けれども普通に考えれば、「図」を「絵画として描く」と読むにしても、そこでもまた、それを「描く」主体が要請されてしまうと思われがちです。しかし私の考えでは、「絵画として描く」ということがらは主体なるものから離脱します。そしてだからこそ、絵画論と坐禅論との接点がありえるのです。
上述した南嶽懐譲――馬祖道一の法脈に列なる禅僧であった石濤(1642-1707)は、明末清初を代表する画家でもありました。石濤は絵画の実作とともに、優れた絵画論である『画語録』を残しています。道元禅師が坐禅を論ずるのに絵画を適用するのとはちょうど反対の方向から、石濤は、絵画を論ずるのに、僧侶としての思考や修行の知見を援用しているのです。絵画論と坐禅論との接点を見るのに、私は、石濤の論述を参考にしてみたいと思います。
『画語録』において石濤は、すべての絵画表現の元に「一画」を置き、その展開として絵画を見ました。一画とは文字通り、筆で線を画くワン・ストロークのことを指します。このことについて石濤は「一画は衆有の本にして、万象の根なり」と言いました(なお福永光司氏は、これは「易」の一画のことだと解説します)。しかし、われわれにとって重要なのは石濤にとっての一画の出現の仕方にあります。次のように言いました。
夫れ画は、天地万物を形すものなり。筆墨を舎けば、其れ何を以てか之を形さんや。墨は天に受け、濃淡枯潤これに随う。筆は人に操られ、勾皴烘染これに随う。古の人、未だ嘗つて法を以為さずんばあらざるなり。法無ければ則ち世に干て限る無し。是れ一画は、限る無くして之を限るに非ざるなり。法有りて之を限るに非ざるなり。法に障え無く、障えに法無し。法は画より生じ、障えは画より退く。法と障えと参らずして、乾旋り坤転くの義得られ、画道彰れ、一画了せらる。
いったい絵画というものは、画家が天地万物を芸術として造形するものである。筆墨を用いなければ、どうして対象を造形することができようか。筆墨のうち、墨は造化の自然に本づいて、あるいは濃く、あるいは淡く、あるいはカサカサに、あるいはしっとりと、対象に従って変化させ、筆は画家の操作によって輪郭線や皴の画き方、乾かしてはまた塗る画き方など、対象に随って描きわける。
古人は必ず画法に随って絵画的造形を行った。画法がなければ、この世界に形を限ること――絵画的造形といういとなみはありえない。だから一本の描線を画くということは、画法的な限定を全く否定して造形するのでもなく、既成の画法をそのまま肯定して造形するのでもない。
いったい画法には本来、画家を束縛するということなどなく、画家を束縛するものはもはや画法ではない。画法は画をかくという画家の実践の中から自然に成立するのであり、束縛は画をかくという画家の実践において自然に消滅する。画法と画法による束縛とが明確に区別されるとき、「乾旋(けんめぐ)り坤転(こんうご)く」天地造化の生きた法則が悟得され、絵画の真理が明らかとなり、一画――一本の描線――のもつ哲理が、はっきりと認識されるのである(原漢 福永光司『芸術論集』416-417頁 朝日新聞社 1971)。
石濤が書画の根源とする「一画」は、「衆有の本にして、万象の根なり」とありますが、その出現は、やや奇妙なありかたをしています。一画は恣意的に表れるのではなく、なにかの規範に基づいて出現します(是れ一画は限る無くして之を限るに非ざるなり)。この規範が画法ですが、一画はそのような画法に基づきつつ、同時にあらかじめ存在する画法によって限定され、一画が成立するのでもないというのです(法有りて之を限るに非ざるなり)。さらに、法があって画が生じるわけではなく、むしろ、画が画かれることによって法が見いだされ、それに一画が従っていることがあとでわかると言われています。要するに、一画は、画法に対して、ある場合にはそれに先立ち、ある場合にはそれに遅れ、ある場合にはそれと同時に出現するということです。
これは一見、なにを言っているのか、わかりにくいことがらです。しかしそれは論理の上で考えるからです。実践の側面から考えれば、これはむしろ、日常的な、ありふれたことがらだといえます。たとえば私たちが半紙に向かって、筆に墨をつけて字を書く時のことを考えてみましょう。「永」という字を書く場合、第二画をどこにどのように、第三画をどこにどのように書くのかは、たしかに字の形として決まっています。しかし、実際に墨をつけた筆を半紙に載せるときに、それを半紙のどこにどのように載せるのかは、載せてみなければわかりません。二画目の起筆の位置、節筆の角度、直線部の伸び、鈎の跳ね上げ、三画目の入筆の位置、二画目との位相など、これらは規範としてあるにしても、実際に筆を半紙に載せるときには、そんな規範は全く私たちの運動を統御しません。筆を半紙に載せるときは、私という主体が完全に運動を統御しているのかといえば、そんなことは誰にもできません。筆に墨をつけて紙に載せるのは、まったく出たとこ勝負だということです。載せた結果として、ほぼ必ず、あらかじめ書こうとして狙ったはずの印象とは、まったく異なった線になります。ところが、そのときにこそ、書法が出現しているのです。その出現は、そうならなかったものとしての過去と、そうであるべき未来との意味を担いながら、しかもいま現実に出現している線に寄り添うものとして出現します。書と画という違いはありますが、石濤が言う一画が、画法に先立ち、遅れ、そして同時に出現することとは、こうしたありようが述べられていると思えます。
大寂(馬祖)が言った教えによれば、坐禅はかならず「図作仏」だと言うのである。坐禅とは、作仏の図であると言うのである。描かれた絵図としての作仏のすがたは、作仏の行為よりある場合には以前に出現し、また、ある場合には以降に出現し、さらにある場合にはまさしくその行為としての作仏のさなかに出現する。
道元禅師が「図」を「意図する」と読ませないのは、「意図する」という論理上のありようでこそ、主体が完全無欠なかたちであらわれてしまうのを避けたからだと思います。言い換えれば、主体は、論理的、理性的な必要においてのみ完全なのであって、実践のうえからは、そのような完全な統御をもたらす主体などは実在しないことがわかるのです。私たちは、実際に、自分の意志どおりに一本の線を引くことすらできない。それは、行為に先立ちそれを意図する主体の実在が、実はフィクションだからです。出たとこ勝負で筆を下した一画においてはじめて、私たちは自分の主体のありかを(主体がフィクションであることがわかるかたちで)初めて認識できるのです。道元禅師が「図」を「絵画として描く」と読むのは、「意図する」主体という想定から外れるためだったと私が読むのはこの意味においてです。
〈坐禅はやってもわからない〉
たとえば「坐禅はやってみなければわからない」と言われる場合があります。実践は言語論理を乗り越え、直接的体験によって超理性的に理解するものだから、言語ではなく実践でしかわからないのだと言われるのです。しかし、ここで参考になるのは「坐禅がわかる」体験ではなく、むしろ「坐禅をやってみてもわからない」体験だと思います。坐禅は、論理や意志や主体によって統御できるフィクションではなく、実際に手足を組んで呼吸を整えて坐る実践です。だからこそその実践は、ほぼいつも確実に、意図や意志から外れた結果になります。心を落ち着けたスマートな状態にはなかなかならず、いったい自分はなにがしたいのか、なにを求めているのか、こんなことをして何になるのか、わからなくなるのです。私のことを言えば、私は坐禅が下手で、足が太くて短いので、結跏趺坐を組むのも組みにくく、また鼻炎があって、呼吸もすぐ口呼吸になってしまいます。おまけに坐ればすぐ眠くなるし、起きていればいろいろ考えてしまいます。私は自分では、スマートに坐りたいと思いますが、その思惑はことごとくはずれ、ただ、私は自分の身と心で、出たとこ勝負で坐っているだけです。私には坐禅がなにかは「わからない」のです。
坐禅の意味は「わからない」。それは、坐禅が論理ではなく、実践だからです。この「わからなさ」は、書画の一画が、論理ではなく、実践であり、一画の行方は「わからない」のと同じだと思います。「わからない」実践を行うこと、自分では知覚できない、統御できない実践に出たとこ勝負で身と心とをゆだねること、おそらくこれが「作仏という絵図を描くこと」です。そこでは、主体が統御するのではない身心のありよう、すなわち「わからなさ」に直面するでしょう。おそらくこれが「脱落」です。しかし、道元禅師が周到なのは、「作仏という絵図を描くことが、わからない(脱落である)坐禅を行うことである」ときに、今度は、「坐禅はわからないものだから」と、安易な開き直りを行ってしまいがちであることも、注意している点です。そして、「坐禅はわからないものだ」ということがらは、終着点ではなく、出発点であり、そこから表現を行うよう説いています。このことは、主体の統御ができない一画において、しかしその一画でもって絵画を描き始めなければならないとすることと、正確に一致します。この点においても、坐禅論と絵画論とは接点を持っていると思います。
「作仏という絵図を描く(図作仏)」とは、(自己の身心が)脱落することだとすると、(自己の身心の)脱落自体も「作仏という絵図」なのか。作仏のありようはたくさんあるが、この「作仏という絵図を描く」ということがらにおける、表現を乗り越える表現(葛藤)を、図作仏と言うのか。
大寂(馬祖)が言った教えによれば、坐禅はかならず「図作仏」だと言うのである。坐禅とは、作仏の図であると言うのである。描かれた絵図としての作仏のすがたは、作仏の行為よりある場合には以前に出現し、また、ある場合には以降に出現し、さらにある場合にはまさしくその行為としての作仏のさなかに出現する。ここでさらに問うならば、この絵図はどれほどの作仏のありようを表現することができているのか。この表現を乗り越える表現を、さらに表現してみよ。こうしたときに、作仏のすべてが同時にそれぞれの細かいありようによって出現し、さらに出現する表現の一つ一つが同時に作仏そのものとなっている。それが表現の一つ一つが絵図となるということだ。絵図として描くことを逃げてはいけない。逃げれば結局この話頭の命を捉えそこない、修行の要点を見落としてしまうのだ。捉えそこない見落とせば、ただ真に迫らない表現だけになるのである。
作仏という絵図を描くことは、自分では「わからない」坐禅を基にして、仏行を行じることです。しかも、その行じていることを、こまかく表現せよと道元禅師はいいます。「坐禅はわからない」などと開き直って、なにも表現しないのはいけないということです。表現するときには、表現する主体が「自分」として立ち上がってしまいます。それはフィクションですが、強力なフィクションです。これを破らなければならない。「フィクションを破るにはフィクションをかぶせて使え(この葛藤、さらに葛藤をまつふべし)」と道元禅師は言います。「図作仏」の「図」という漢字を「意図する」という意味だけでなく、無理に「絵図を描く」という意味をぶつけて使ったこの箇所の解釈こそは、「フィクションを破るにはフィクションをかぶせて使」った実例であるでしょう。表現すること、絵図として描くことを逃げてはいけない、逃げれば結局この話頭の命を捉えそこなうぞ、話頭の命を捉えそこなえば、ただの真に迫らない薄っぺらい表現に落ちるのだ、と、まるで私の七転八倒の解釈を激励してくれているかのような言葉が、心に沁みます。
【藤田一照】身読コラボ⑨
第8回の敬之さんの論究は非常に刺激的でした。そこではこういう問題提起がなされていました。
道元禅師の坐禅は、通常、「無所得・無所悟」の「只管打坐(しかんたざ ただすわるという意味)」といわれているので、後者の解釈(目的を求めない磨塼の行為としての坐禅こそがわれわれの目指す坐禅であるという解釈 筆者付加)こそふさわしいように思えます。とはいえ、実際に「坐禅箴」巻に展開されている論述をたどると、こうした解釈をあてはめることに躊躇をおぼえます。というのは、無所得・無所悟の坐禅の鼓吹、などという単純なことがらとは明らかに異質の論述が、そこに展開されているからです。
異質性の根幹は、道元禅師の見ているものが、私たちの知覚と異なるように思えるからです。言い換えれば、道元禅師は、単に無所得・無所悟の坐禅を鼓吹しているのではなく、なにか別のありようを知覚し、探求していこうとしているように思えるのです。「南嶽磨塼」の話頭を論じながら、道元禅師が見ている知覚とはいったいどのようなものか。それをさぐることがこれからの私たちの身読の中心となります。
敬之さんはこう問いかけた上で、
道元禅師は「図」ということばにつなげて、坐禅論を絵画論として見ようとしているということです。そのために「図」には、はかる=意図するという意味と、図=えがくという意味との二つの意味が託されているわけです。
と述べ、坐禅論と絵画論をつなげるという独自の路線で、道元の「南嶽磨塼」の拈提を理解しようと試みています。
私も前回、自分の論究において、
この「図」という漢字はいまある現実とは別ななにかを思い描くという意味の「図(はか)る(意図 つもり)」ではなくいわば「姿形」という意味の「図(ず)(図形)」
と理解して、話を進めました。ですから、南嶽が馬祖に向かって語りかけた「大徳、坐禅図箇什麼」という呼びかけは、「大徳、坐禅は箇の什麼の図なり」あるいは「坐禅の図は箇の什麼なり」と読み下して、「貴公はそうやって一生懸命坐禅をしているが、それは什麼(なに)という疑問詞を使ってしか指し示すことができない無限定なものの図(=具体的な立ちあらわれ、姿形)なのだな」という、質問ではなく、実は問いに見せかけた坐禅の記述であったと解釈しました。しかし私は、そういう解釈の論拠については詳しい説明をせずにさらりと通り過ぎていました。それに対して、敬之さんの「図=えがく」という主張の説明はたいへん説得力に富むもので、私の論旨にとっても力強い援護射撃になり、より確かな立論の立脚点を与えていただきました。また、そこからの展開としてさらに論じられている〈墨というメディウム〉のセクションは彼の視野の広さがうかがわれ、とても興味深いものでした。私はここを読んで、こういう人に『正法眼蔵 坐禅箴』を一緒に読んでいくパートナーになっていただいて本当によかったとしみじみ思ったのでした。道元の「南嶽磨塼」の話へのコメントはまだこれから当分続いていくので、敬之さんのユニークな絵画論的身読がこの先どのような展開を見せるのかがとても楽しみです。褒めるばかりでは能がないではないかと言われそうですが、もう少し彼の論究の成り行きを見てから、私の論評を記したいと思います。
道元が「図」を「図(はか)る」という読み方だけではなく、「図(ず)にする」、つまり「絵に描く」という意味でも使っていることは本文を素直に読めば理解できることです。しかし、そのことの重みをどう評定して解釈に盛り込むかということに関しては、これまでの解説書の多くはあまり積極的ではありませんでした。そうした解説においては、南嶽と馬祖の問答の口火である「坐禅図箇什麼」という一文は通常、「坐禅して箇(か)の什麼(なに)を図るか」というように、疑問文として読み下されます。そして、「坐禅などして何か目的があるのですか」(中村宗一『全訳 正法眼蔵』誠信書房刊)とか「そなたは、坐禅して、なにごとを図るのであるか」(増谷文雄『現代語訳 正法眼蔵』角川書店)というように、「図」を「図る」と読んで「目的」や「意図」を尋ねる質問として現代語訳されています。それと比較すると、私の現代語訳や、敬之さんの「坐禅はどのような図に描けるものかね」という訳は、『正法眼蔵 坐禅箴』全体で展開されている道元の主張に対する一定の理解に基づいて、「南嶽磨塼」の問答をはじめから解釈していることになります。この巻を最後まで読んでから、その上でもう一回「南嶽磨塼」の則にまでもどってきて、前後一貫した解釈をしようとしているのです。
道元の『正法眼蔵』の各巻には、原典からの引用がたくさんありますが、道元独特の読み下し方や解釈のもとに論じられていることが多く、一つの巻全体の要旨、あるいは全巻の枠組みを踏まえたうえでなければ、それらの引用文を解釈することが困難なケースが多いのです。通常の解釈では前後の文脈と整合性が取れなくなってしまうからです。この「図作仏」の「図」の取り扱い方に関しても、そのような配慮が必要だというのが私の立場なのです。二人で示し合わせてそうしたわけではないのですが、奇しくも同じような見地から「図」の意味を読解することになったようです。
『正法眼蔵』には、普通の仏教語辞典や日本語の辞書で見つかる意味で読んでいては、理解不能に陥る言葉が多々あるので、私は『正法眼蔵』は日本語Japaneseとしてではなく、日本語のように見えるが実は別な言語である「道元語Dogenese」として読まなければならないとよく言っています。あるいは、虚妄分別に基づいた常識で話される「凡夫語」で読むのではなく、無分別智に基づく「仏陀語」として読まなければなりません。そして、そのような道元語の習得は、母国語を習得するのと同じように、『正法眼蔵』を普段から声に出して読み、目でも読んで、時間をかけてじっくり親しんでいく以外にすべはないと思います。
目的や意図の意味での「図」と解釈するなら、それはまだ到来していない未来の話になりますが、描くこと、あるいは描くことの結果としてそこに現れた図(図画、図像)という意味での「図」と解釈するなら、それはただいま現在の話になります。これは重大な見解の相違ということになり、どちらの前提に立つかで南嶽と馬祖の問答の解釈がまるっきり違ってきます。
今回身読する箇所のテーマである「図作仏」は通常は、「作仏を図る」と読み下しますから、「仏になるためです」(中村 上掲書)とか「作仏を図るのでございます」(増谷 上掲書)と口語訳されています。しかし、私は前回、南嶽の「坐禅図箇什麼」という問いを「坐禅は箇の什麼の図なり」と読み下して解釈した以上、ここも「作仏の図なり」と読まなければ、前後の一貫性が保てません。この際、私としてはより大胆に「図」というのは完成図のことであり、「現成(現在只今において余すところなく完成、完結、成就している、という意)」という意味にさえとって解釈したいのです。ですから、「作仏の図なり」は「成仏の現成なり」という意味になります。この路線に従ってみると、今回の箇所はどのように読むことができるのか、これから論究していくことにしましょう。
ではまず今回の箇所の原文を読んでみます。できたら、音読してそのリズムと響きを感じてみてください。
江西いはく、図作仏。
この道、あきらめ達すべし。作仏と道取するは、いかにあるべきぞ。仏に作仏せらるるを作仏と道取するか、仏を作仏するを作仏と道取するか、仏の一面出・両面出するを作仏と道取するか。図作仏は脱落にして、脱落なる図作仏か。作仏たとひ万般なりとも、この図に葛藤しもてゆくを図作仏と道取するか。
しるべし、大寂の道は、坐禅かならず図作仏なり、坐禅かならず作仏の図なり。図は作仏より前なるべし、作仏より後なるべし、作仏の正当恁麼時なるべし。且問すらくは、この一図、いくそばくの作仏を葛藤すとかせん。この葛藤、さらに葛藤をまつふべし。このとき、尽作仏の條條なる、葛藤かならず尽作仏の端的なる、みなともに條條の図なり。一図を回避すべからず。一図を回避するときは、喪身失命するなり。喪身失命するとき、一図の葛藤なり。
前回「その審細な功夫参究のよすがとして、「……か」と末尾に「か」のつく文章がこの後に立て続けに並べられています。『正法眼蔵』にはそういう表現がよく出てきます。文字通りによめば問題提起をした質問文のリストのように見えますが、真意はそうではなく、実は断定の言葉であるというのが曹洞宗門の伝統的な解釈になっています。つまり、質問の形で述べられていることがすべて「イエス(その通りだ)」と肯定されていると解するべきなのです。」と書きました。今回読む箇所にもそのような「……か」と末尾に「か」のつく文章が立て続けに並べられています。整理のために、その原文を列挙してみます。
・仏に作仏せらるるを作仏と道取するか。
・仏を作仏するを作仏と道取するか。
・仏の一面出・両面出するを作仏と道取するか。
・図作仏は脱落にして、脱落なる図作仏か。
・作仏たとひ万般なりとも、この図に葛藤しもてゆくを図作仏と道取するか。
と五つの「……か」が並んでいます。ここでも前回同様、いずれの文も、「イエス、然り」という答えを想定した断定のための文章と解釈しました。その意味を私なりに敷衍すると次のようになります。
・作仏には、仏(大自然のおのずからなる働き)によってすべてさせられているという面も確かにある。
・私が坐禅を行じて仏を実践することが作仏であるということも確かに言える。
・昨日の坐禅、今日の坐禅、明日の坐禅、とそのたびに表情の違う仏を現成させることを作仏ということもできる。
・作仏の図である坐禅は身心が脱落(刻々に姿を変えて停滞することなく流れ続けている)している状態そのものであり、また脱落している身心で作仏の図になっているとも言える。
・作仏のありようとしてはいろいろ無数にあるとしても、それらは必ず図(坐禅修行)に絡み合っている。そういうことを図作仏と言うこともできる。
以上のように、作仏のありようというものは、実にさまざまな言い方(道取)ができるのであって、決して一言で言い切れるようなものではないから、どこまでも審細に参究し続けていくべきなのです。ここに挙げられた作仏の「道取(取は助字で強調 道は言うこと、つまり言葉)」はそのほんの数例に過ぎないのです。ここでは言外に、われわれ自身の作仏の道取を道得することが問われているのだと思います。
「坐禅かならず作仏の図なり」というのは、坐禅は作仏が描かれた図、つまり実践であるということです。坐禅の実践は作仏より前のこともあるだろうし、後のこともあるし、また同時であることもあります。ここもまた一言で片付けられない図と作仏の関係のことが言われているのです。このように、「ああも言えるし、こうも言える、さらにはこのようにも言える」、という具合に、簡単に言い切りを許さず、視点をずらしながら異なる表現を畳み掛けていくやり方は道元が多用するところです。私はこの図(坐禅=修)と作仏(成仏=証)の前・後・同時の関係をそれぞれ「修せざれば(証)あらわれず」、「証上の修」、「修証一如」に対応させられるのではないかと考えています。
「且問すらくは」というのは「ここでいったん考え直して、改めて問うてみよう」ということで、一図、つまり坐禅という実践について別な角度からの考察がなされています。道元は、坐禅には実にさまざまな作仏のありようがまとわりついている(葛藤)と言います。「葛藤のうえにさらに葛藤がまとわりついている」という凝った表現さえ使っています。坐禅を実際にやってみれば実感できると思いますが、同じ川を二度と渡ることができないように(刻々に姿を変えて流れ続けている川は、そのときそのときで一回きりのあり方をしているから)、同じ坐禅は二度と坐ることはできません。坐禅をしているわれわれの身心は川のように刻々に状態を変え続け、厳密に言えば二度と同じ状態になることはないからです。同じ一回の坐禅といっても、そのコンテンツは毎回違っているのです。坐禅はいつも作仏の図なのですが、坐るたびごとに、そのとき独自の作仏のありようがそこに現成しています。その作仏の全体像は坐禅している当人の覚知では決して把握することはできません。当人には把握できないあり方で作仏しているのです(「諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと覚知することをもちいず。しかあれども証仏なり、仏を証しもてゆく」『正法眼蔵 現成公案』)。そして、そのどれもが作仏として唯一絶対の価値を持つのですから、比較の話ではなくなります。
最後の部分にある「一図の回避云々」の解釈に関しては、諸説あって紛糾しています。ここではとりあえず、素直に「一図=坐禅を回避する」という意味に解することにしましたが、大いに検討の余地を残しています。
以上のような考察を踏まえて、私はこの箇所を以下のように現代語訳してみました。あくまでも仮の試案ですが、みなさんの読解の参考にしていただければ幸いです。
それを聞いて、馬祖が答えた。「はい、確かに坐禅は仏に作(な)っている、成仏の完成図です」と。
この表現を明らかに理解しそれに通達しなければならない。ここで言われている「作仏」という表現はどのようなことがあっても言われなければならないことなのだ。それは仏によって自分が作仏されることを言っているのだ。また自分が坐禅という仏を行じて作仏していることを言っているのでもある。さらに、仏の具体的な姿がそのときそのときで一つ、二つと出現していることを言っているのでもある。「図作仏」は身心が脱落している本来の姿そのものであって、そのように脱落した身心が作仏の図となっているのでもある。このように作仏という事実にはいろいろなあり方があるのだが、この坐禅という図に引きずられ、それにからまりあっていくこと(「葛藤」)を図作仏と言ったのだ。
だからこのことはよく承知しておきなさい。馬祖の言ったことは、坐禅はかならず図作仏であるということだ。坐禅はかならず作仏の図である。そしてその図は作仏よりも前でなければならない(坐禅によってわたしが作仏されるのだから、つまり坐禅は作仏の必要条件である 「修せざればあらわれず」ということ)。またその図は作仏よりも後でなければならない(わたしが坐禅することで本来作仏を実証しているのだから、つまり「証上の修」であるということ)。さらに、その図は作仏のまさにそのときのことでもある(坐禅において仏の具体的な姿がそのとき同時に出現しているのだから、つまり「修証一如」ということ)。
さてここであらためて、次のような問いを立ててみよう。
この一つの「図」つまり、一つの坐禅の具体的な姿形には、どれほどの量の「作仏」がまとわりついている(「葛藤」)のだろうか? 坐禅の全体は坐禅している当人が意識できる体験内容にとどまるものではない。実はそれと意識できてはいなくてもあらゆる「作仏」がこの図にはまとわりついているのだ。このまとわりつきにさらにまとわりつきがまとわり続けることによって坐禅は坐禅として継続していく。そのときには、あらゆる作仏の一枝一枝であるまとわりつきは、かならずあらゆる作仏の当体そのものであり、一枝一枝がすべて一つ一つの図として現成している。一図、すなわち坐禅から逃げてはいけない。坐禅を回避するときには、たちまちに自己の生き生きとしたいのちを失ってしまうことになるからだ。しかし、そのような自己の生き生きとしたいのちを失うということもまた、一つの図(坐禅の実践)のまとわりつきとしてあるのだ。だから、どうあってもこの一図から外れるということはないのである。