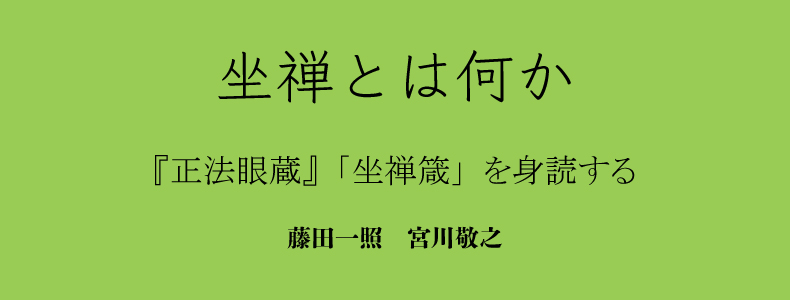作仏を図する
【宮川敬之】身読コラボ⑧
〈南嶽磨塼(なんがくません)〉
今回から新たな箇所に入ります。題材となるのは、「南嶽磨塼」とよばれる有名な話頭(わとう 禅の逸話のこと)です。この話頭自体が抜群におもしろいので、「坐禅箴」本文に入る前にまず原典を引いてみます。『景徳伝灯録』巻五(大正蔵五一 国訳一切経和漢史伝部一四・一五)から引きます。
南嶽懐譲禅師は、姓は杜氏、金州の人なり。(中略)……唐の先天二年、始めて衡嶽に往きて、般若寺に居る。開元中に沙門道一なるもの有り。即ち馬祖大師なり。伝法院に住して常日坐禅す。師、是れ法器なりと知り、往きて問ふて曰く。大徳、坐禅して什麼(なに)をか図(はか)ると。一曰く。作仏を図(はか)ると。師、乃ち一塼(いっせん)を取り、彼の庵の前の石上に於いて磨す。一曰く、師、什麼をか作(な)すと。師曰く、磨して鏡と作さんと。一曰く。塼を磨するも豈に鏡と成すことを得んやと。師曰く、坐禅、豈(あ)に成仏を得んやと。一曰く。如何なるか即ち是なると。師曰く。人の駕(が)するが如し。車、行かずんば車を打つが即ち是なるや、牛を打つが即ち是なるやと。一、対ふること無し。師、又曰く。汝、坐禅を学ぶとや為(せ)ん、坐仏(ざぶつ)を学ぶとやせん。若し坐禅を学ばば禅は坐臥に非ず。若し坐仏を学ばば仏は定相(じょうそう)に非ず。無住の法に於いて応に取捨すべからず。汝、若し坐仏せば即ち是れ仏を殺す。若し坐相を執すれば其の理に達するに非ずと。一、示誨(じかい)を聞くや、醍醐(だいご)を飲むが如し(国訳一切経史伝部一四 125~126頁)。
『景徳伝灯録』にはこのあとの話もあるのですが、道元禅師の引用はここでおわっていますので、私たちの引用もここまでにしておきます。一読、非常におもしろい話頭であることはわかります。細部もわかるように翻訳をしておきます。
南嶽懐譲禅師(道元禅師の引用では南嶽大慧禅師とよばれる)は、姓は杜氏、金州(山東省)の人であった。唐の先天二(713)年に衝嶽(南嶽)に行って般若寺の住職となった。開元のころ(713-741)、道一という僧侶がいた。のちの馬祖大師(ばそだいし 道元禅師の引用では江西大寂禅師とよばれる)である。彼は伝法院に住んで毎日坐禅していた。師は道一を、法を伝える器量がある者と見て、彼に対して問いをかけた。
「おまえさん、坐禅してなにをしようとしているのだね」
道一は応える。
「仏になろうとしています」
師は、土瓦のかけらを拾って、伝法院の庭先の石でそれを磨りはじめた。道一は言う。
「お師匠様、なにをなさっているのですか」
「磨って鏡にしようとしているのだ」
「土瓦を磨って鏡にすることができましょうか」
「坐禅をして仏になることができるかね」
「……では、どうしたらよいでしょうか」
「お前が牛車に乗っているとしよう。車が止まって動かない。このときお前は、鞭で車を打つのがよいか、鞭で牛を打つのがよいか」
道一は答えない。
「おまえは、坐禅を学んでいるのか、坐仏(坐って仏となる修行)を学んでいるのか。もし坐禅を学んでいるのなら禅は坐臥ではない。もし坐仏を学んでいるのなら、仏はきまったすがたをあらわさないものだ。固定されたものなどないとわかって、取捨することそのことをやめなければならん。おまえが坐仏を求めると仏を殺すことになるぞ。坐禅のすがたに執着すると本質にはたどりつけないぞ」
道一はこの教えを聞いて、この世ならぬうまい味わいを味わうようであった。
この話頭は、坐禅をどのようなものとしてとらえるかということをテーマにしています。その際、「坐禅をして仏となろうとするのは、塼を磨いて鏡にしようとすることと同じだ」という比定がなされています。そのため、坐禅への評価は、坐禅に重ねられている「塼を磨く」という行為への評価と相互に連動することになります。
通常の解釈はつぎのようです。塼を磨いて鏡にするなどということは不可能ですから、「塼を磨く」行為は「不可能な行為」であって、見当違いの行為とまず解釈されます。そこからフィードバックされて、坐禅によって仏となろうとすることも、不可能であり、見当違いであると解釈されるのです。これがもっとも素直な解釈のしかたです。
さらにまた、そこからもう一歩進める解釈もあります。磨塼の行為が不可能であり、見当違いの行為であるのは、そこに塼を磨いて鏡にするという目的を据えたからです。もし鏡にするという目的を外して見た場合、磨塼の行為そのものは、不可能でも、見当違いなのでもなく、ただそうした行為としてあることになります。このことをフィードバックさせて、坐禅もまた仏になることを目的とすると見当違いな行為となるので、「無所得(むしょとく)・無所悟(むしょご)」の坐禅をめざすべきである、つまり、目的を求めない磨塼の行為としての坐禅こそがわれわれの目指す坐禅なのである。そのように、一歩進めた解釈もありえるのです。
道元禅師の坐禅は、通常、「無所得・無所悟」の「只管打坐(しかんたざ ただすわるという意味)」といわれているので、後者の解釈こそふさわしいように思えます。とはいえ、実際に「坐禅箴」巻に展開されている論述をたどると、こうした解釈をあてはめることに躊躇をおぼえます。というのは、無所得・無所悟の坐禅の鼓吹、などという単純なことがらとは明らかに異質の論述が、そこに展開されているからです。
異質性の根幹は、道元禅師の見ているものが、私たちの知覚と異なるように思えるからです。言い換えれば、道元禅師は、単に無所得・無所悟の坐禅を鼓吹しているのではなく、なにか別のありようを知覚し、探求していこうとしているように思えるのです。「南嶽磨塼」の話頭を論じながら、道元禅師が見ている知覚とはいったいどのようなものか。それをさぐることがこれからの私たちの身読の中心となります。
〈図の問題〉
前節の「南嶽磨塼」の話頭を踏まえたうえで、今回の当該箇所を読んでみます。
江西大寂禅師、ちなみに南嶽大慧禅師に参学するに、密受心印よりこのかた、つねに坐禅す。南嶽、あるとき大寂のところにゆきてとふ、大徳坐禅シテ箇ノ什麼ヲカ図ル。
この問、しづかに功夫参究すべし。そのゆゑは、坐禅より向上にあるべき図のあるか、坐禅より格外に図すべき道のいまだしきか、すべて図すべからざるか、当時坐禅せるに、いかなる図が現成すると問著するか、審細に功夫すべし。彫龍を愛するより、すすみて真龍を愛すべし、彫龍・真龍ともに雲雨の能あること、学習すべし。遠を貴することなかれ、遠を賤することなかれ、遠に慣熟なるべし。近を賤することなかれ、近を貴することなかれ、近に慣熟なるべし。目をかろくすることなかれ、目をおもくすることなかれ、耳をおもくすることなかれ、耳をかろくすることなかれ、耳目をして聡明ならしむべし(春秋社版道元禅師全集第一巻 105-106頁)。
ここにすでに論述の異質性があらわになっていることがわかると思います。前節にあげた通常の二つの解釈では、どちらも「図=はかる(意図する)」という箇所、あるいは文字には注意が向けられていません。二つの解釈では、この文字は素通りされ、結論だけが一足飛びに出されています。
しかし道元禅師が着目するのはこの「図」に対してです。しかも「図」を、文章の意味の上での「意図する」という意味だけにとどめていません。道元禅師が読む「図」は、図画の図であり、描くこと、描かれたこと、そうした問題系につながることばとして見ています。つまり道元禅師は「図」ということばにつなげて、坐禅論を絵画論として見ようとしているということです。そのために「図」には、はかる=意図するという意味と、図=えがくという意味との二つの意味が託されているわけです。
坐禅論と絵画論とがつなげられるというのは突飛な発想に見えます。しかし、それがなされているのはこの「坐禅箴」巻だけではありません。同じ『正法眼蔵』の「仏性」巻でも同様に、坐禅と絵画とを比定して論じています。こちらをまず見ておきます。
「仏性」巻では、龍樹(りゅうじゅ ナーガールジュナ)尊者が坐禅・説法したとき、円い月のすがた(円月相 えんげつそう)をあらわしたという逸話(もとは『景徳伝燈録』巻一 国訳一切経史伝部一四 34頁)が論じられています。この逸話自体は、一種の聖人伝説(ハギオグラフィ)にすぎませんが、興味深いのは、この伝説を実際の絵画として描くとき、どのように描くべきかを道元禅師が論じている箇所です。留学先の宋の寺院では、回廊にこうした祖師聖人の奇跡のすがたを描いた実際の絵画がありました。そこで描かれたのは龍樹尊者のすがたではなく、法座(仏法を説く指導者の席)の上に、円形の輪が描かれている、それだけだったといいます。その絵画を見た道元禅師が、その描き方を論じています。それがひいては坐禅論と絵画論とを結びつけることになりました。つぎのように言っています。
大宋国むかしよりこの因縁を画せんとするに、身に画し、心に画し、空に画し、壁に画することあたはず、いたづらに筆頭に画するに、法座上に如鏡なる一輪相を図して、いま龍樹の身現円月相とせり。すでに数百歳の霜華も開落して、人眼の金屑をなさんとすれども、あやまるといふ人なし。あはれむべし、万事の蹉跎たることかくのごときなる。もし身現円月相は一輪相なりと会取せば、真箇の画餅一枚なり。弄他せん、笑也笑殺人なるべし。
(中略)
しるべし、身現円月相の相を画せんには、法座上に身現相あるべし。揚眉瞬目、それ端直なるべし。皮肉骨髄正法眼蔵、かならず兀坐すべきなり。破顔微笑、つたはるべし、作仏作祖するがゆえに。この画いまだ月相ならざるには、形如なし、説法せず、声色なし、用弁なきなり。もし身現をもとめば、円月相を図すべし。円月相を図せば、円月相を図すべし、身現円月相なるがゆえに。円月相を画せんとき、満月相を図すべし、満月相を現ずべし。しかあるを、身現を画せず、円月を画せず、満月相を画せず、諸仏体を図せず、以表を体せず、説法を図せず、いたづらに画餅一枚を図す、用作什麼(春秋社版道元禅師全集第一巻 30-31頁)。
龍樹の坐禅のすがたとして法座のうえに円い満月を描いた図を、道元禅師は、「まったくの「画に描いた餅」で、笑止千万なことだ」と、強烈に批判します。しかしそれならば、どのように描くべきであったのでしょうか。
道元禅師によれば、法座上で坐禅をしている龍樹尊者のありようを、具体的にしっかりと描くべきであったのです。それは、姿勢・目の開け方、口のかまえ、法界定印(ほっかいじょういん 坐禅のときに定める手のかたち)のありよう、足の組み方など、釈尊から伝わった坐禅を継承したことがわかる姿として、明確に描かれた絵画=図です。このような図が描かれれば、それと対峙したときに円月相は表れる。そのように道元禅師は考えます。
それはどのようなことがらなのでしょうか。例えばつぎのような仏像=仏画を例として考えてみてもいいかもしれません。パキスタン・ラホール博物館のガンダーラ仏「仏陀苦行像」、唐招提寺蔵の鑑真和上像、高山寺蔵の明恵上人樹上坐禅像、運慶作の重源像、雪舟筆の慧可断臂図。もちろんこれらの作品を道元禅師が念頭に置いて論述しているわけではありませんが、これらの像=絵画=図は、制作された時代の、あるいは写された当人の坐法がはっきりとわかるものとしてあります。そしてこれらの図に私たちが対峙するとき、そこにそれぞれの「精神」が出現するのを「見る」ことができます。ただしこの「精神」は、描写そのものではなく、むしろそれ自身は出現しない一種の空白として出現するといえます。雪舟が達磨像の身体を空白のままにしたのは、私たちの知覚が見ることができない「精神」の出現が、そこに賭けられたからです。円月相は、そのようにして、正確な坐法の描写における知覚の「空白」として出現する。それはさらにいえば、見る私たちの知覚が動揺し、変容してしまうことを指しているともいえるのです。
正確な坐禅の描写によって、見る私たちの知覚が変容し、見えないもの「精神=円月相」が出現する。道元禅師がいう円月相の出現は、このようであったと私は考えます。ここに坐禅論と絵画論(芸術論)とのつながりを見ることができます。「作仏を図る(図作仏)」ということばにおいて「図」という文字に道元禅師が執着するのは、そうしたねらいを共有していたからだと考えます。
〈墨というメディウム〉
そもそも、東アジアの表現世界で表現のメディウム(材料)として最も使われてきたものは、いうまでもなく墨です。墨とは、それによってなにかを描くことによって、見えないものが見えないままで出現するという表現を、実はもっとも得意とするメディウムです。造形作家の岡﨑乾二郎氏は、「(墨は)地から形象を分割する図/地の認識図式に繋がっている」(インタビュー「メディウムとしての墨」『墨』236号68頁 芸術新聞社2015)と指摘します。岡﨑氏によれば、墨がもたらす黒白の文節と、多色の文節と、私たちの認識図式が異なっているために、「墨は色ではない」。むしろ「黒一色の諧調で描かれた絵を見て、そこにたくさんの色調が見えてくることも起る」、「見る側がこうして認識を変化させることによって色や形も変化する」ことを可能にするメディウムだと言います。
墨という単一なメディウムを使用するからこそ、多様な生成変化の認識が可能になるのですね。それは見る主体の変化、いわば複数の主体の到来をも可能にします。書や水墨画の魅力は、地に対して図が確定的にあるのではなく、むしろ地のなかに生じる無数のギャップ、落差が、新しい図を現出させることにある。物質的連続に穴が空き亀裂が入る、この落差が複数の潜在的空間に気づかせます。この物理的に与えられていたはずの場の連続性、画面の平面性を忘却させ、そのつど別の空間へと更新されていくのですね。また文字の一字一字のギャップ、落差とそれをなお、のりこえる応答が画面全体の連続性を凌いでしまう。墨は、そういう表現を可能にするメディウムなのだと思います(同上72頁)。
このような墨を実際に使う場合、当然のことながらそのままでメディウムになるのではなく、そこには「磨る」という行為が必要となります。墨を硯で磨って水に溶かしこむというこの行為は、実は非常に難しい。私たちは墨を磨るときに、早く墨液を得たいと速度をあげ、力をいれて磨ろうとしてしまう。しかし、「墨は病人のようにして磨るべし」ということばがあるように、ゆっくりと力をいれず磨ることがこの行為の秘訣です。墨液とは要するに炭素粒が膠の油膜でコーティングされ、それが水の中にコロイド状に存在する溶液のことですので、墨液を作るには、墨を硯で磨ることによって膠成分がまず水に溶け、炭素粒を覆い、親水性の粒子となって水に散在することが必要となります。そこに必要となるのは、速度や力ではなく、むしろ時間だといえます。ただしその時間とは、自分でコントロールできない時間、自分を明け渡す時間、いってみれば墨の時間です。つまりきわめてあたりまえなことなのですが、墨を磨るためには、一滴ずつ硯に垂らし、そこで力を入れずに、墨の時間をかけて墨を磨るという、それだけの行為であることが必要だということです。
このようにして東アジア芸術表現の最大のメディウムである墨は、墨を磨るという行為そのものも、また、それをメディウムにして黒白の画面分割をする場合にも、「見る主体の変化、いわば複数の主体の到来をも可能」にするメディウムとしてあります。
道元禅師が、磨塼の行為を「図」という点において注目したのは、メディウムとしての墨、特に磨る行為と表現する行為において、主体の変化、複数の主体の到来を可能にするからだと考えます。磨塼の行為において重ねられているのは、まずは墨を磨るという行為であり、そこから墨で図=像=画=字を描くという行為へ展開していると考えられます。そうした絵画論(表現論)が坐禅論に結び付くのは、坐禅もまた、「複数の主体の到来を可能にするメディウム」だからではないか、と予想をすることができます。こうした問題系の広がりを踏まえながら、「坐禅箴」本文の解説に入ります。
〈坐禅とその外〉
現代語に翻訳してみます。
江西大寂禅師(馬祖道一)が南嶽大慧禅師(南嶽懐譲)に参学した折、法の後継者と認められてからも、馬祖はつねに坐禅していた。南嶽はあるときに馬祖のところに行って問うた。「おまえさん、坐禅してなにをしようとしているかね(坐禅はどのような図に描けるものかね)」。
この問いに、われわれは心を深くしずめて修行参究していかなければならない。どのように参究するかといえば、坐禅そのものを詳細に描くことで坐禅の図を描くのか、坐禅の外側にまだ描かれていない部分があると描くのか、あるいは図として描くことはできないのか、ならばまた、馬祖が坐っている当時の姿を描く図というのはどのようにしてできるのか、各自それぞれに、こうした問いを精密に検討していくべきなのである。
彫刻された龍を愛でて、その想像力でもって真の龍も愛でなければならない(坐禅をどのように図として描けるのかという問題から、坐禅そのものの問題へ近づくべきだ)。彫龍・真龍のどちらも、龍の力である雨を降らせる能力を持っていると学ぶべきだ(坐禅の図も、生身の坐禅の姿同様に、われわれに仏祖の坐禅を教えるものだ)。坐禅の外側があると殊更に尊ぶべきではないし、そんなものはありえないと殊更に卑しむべきでもない。そういうこともあるなと慣れればよいのだ。坐禅そのものに固執しすぎてはならないと卑しむべきではないし、坐禅そのものを精密に行おうと殊更に尊ぶべきでもない。そういうすがたに慣れればよいのだ。目を疑いすぎるな、目を信じすぎるな、耳を疑いすぎるな、耳を信じすぎるな、耳目を聡明に保ちなさい。
翻訳を見ていただくと、ここで言われていることがらが「仏性」巻の龍樹円月相を描くときの話とパラレルであることは、容易に見て取れるでしょう。
前節でもいいましたように、墨を磨るときに、また、墨で描くときには、磨る主体、描く主体の変容がおこらざるを得ません。墨を磨るときには墨の時間が到来し、墨で描くときには、描き見えるものと同じほど、描けない見えないものが到来する。坐禅も同じように、坐禅する自分という主体が変容し、坐禅の外側から、自分ではない別の力の到来が起こる。だがそうであれば、坐禅を描く場合にどう描くのか。たとえば道元禅師が宋の寺院で見た龍樹円月相の図は、法座上に円い月の像を描いていたものでした。道元禅師はこの描き方に強く反発したのは先ほど見たとおりです。宋の寺院の描き方がまずいのは、描けない見えない姿――それが円月相ですが――を、円を描くことによって安易に描いたという点にあります。見えないものの出現は、見えるものを詳細に描いたうえで初めて現れる見えないものの出現によって、描かれなければならない。それが道元禅師の考えです。この考えからつながっているので、今回の坐禅を描くということがらの問題が、つぎのように提起されたのでした。
1、坐禅そのものを詳細に描いて坐禅の図を描くか。
2、坐禅の外側にまだ描かれていない部分があると描くか。
3、図として描くことそのものを放棄するか。
4、馬祖の坐禅の様子は、どのように描かれるべきか。
道元禅師の答えは次のようでした。たしかに坐禅は、坐禅する自分という主体が変容し、坐禅の外側から、自分ではない別の力の到来が起こる。しかし、そのような複数の別の主体の到来を待ち望みすぎるのも、またダメだ。もちろんそうした別の主体の到来を端からバカにしていてはそもそも坐禅にならない。まあこんなこともあるなあと慣れ、期待しすぎず絶望もしないのがよい(「慣熟すべし」)。このように言われます。同じように坐禅そのものに固執しすぎてはならないとバカにすべきではないし、坐禅そのものを精密に行おうと殊更に尊ぶこともダメだ。まあこんなこともあるなあと慣れるべきだ(「慣熟すべし」)と言うのです。そこから次のように言われます。目を疑いすぎるな、目を信じすぎるな、耳を疑いすぎるな、耳を信じすぎるな、耳目を聡明に保ちなさい。つまり、固定された知覚に執着することもなく、新たな知覚の到来を待ち望むこともなく、知覚からなるべく先入観をはずしておきなさい、と教えています。そのようにして道元禅師は、この1、2の問いに対して、その中間をねらおうとし、しかも3に対しては絶対に描かれるべきで、4に対しては、どのように描くかを考えることも参学のポイントとせよと注意しているのです。坐禅論と絵画論とをつなげて論じることは、このように展開していくのです。
【藤田一照】身読コラボ⑧
前回で、「薬山非思量」の則の拈提が終わり、これから次の「南嶽磨塼」の則の拈提が始まります。道元が『正法眼蔵 坐禅箴』を説くにあたって取り上げている「薬山非思量」の則も「南嶽磨塼」の則も、二人の禅者の間で交わされる問答でした。「薬山非思量」では坐禅をしていた薬山と無名の僧との間で、また「南嶽磨塼」では坐禅をしていた弟子の馬祖とそこを訪ねてきた師の南嶽との間で、坐禅をめぐる問答が交わされました。いずれの則も、まさに坐禅がなされていた現場でいきなり起こったやり取りであったことに注目する必要があります。禅の問答というのは、具体的な文脈を離れた、いわば真空中で起こるのではなく、そういうふうに抜き差しならぬまさに当の「現」場で突発的に始まるというところにその真骨頂があります。坐禅している薬山に向かって、ある僧がいきなり「兀兀地思量什麼」と問答を仕掛けてきましたし、つねに坐禅していた馬祖のところに師の南嶽がやってきて、いきなり「坐禅図箇什麼」と問うたのです。どちらも「あなたがやっているその坐禅はいかなるものなのか? それを示してみよ!」と迫っていく語気を孕んでいます。その問答の場に張り詰めている緊迫感というか、臨場感をこの身に実感しつつそれぞれの則に向かい合わなければなりません。『正法眼蔵 坐禅箴』における道元の拈提もまた、過去の問答へのそのような向き合い方から生まれてきたものとして受け取ることができるでしょう。
禅問答を読む際にもう一つ心しておくべきことがあります。それは、「薬山非思量」のところでも述べましたが、表面上は問う者と答える者とに分かれて、二人の間で問いと答えが行き来しているように見えますが、「問処の道得」とか「問処は尚答処の如し」と言われるように、深いところでは質問がそのまま答えになっているという点です。僧から薬山に向かって発せられた「兀兀地思量什麼」を例にしていえば、「兀兀地、作麼(なに)をか思量せん」と普通に読めば質問文であるものを「兀兀地の思量は什麼なり」という平叙文として読んでいくことができるということです。什麼という俗語は普通は疑問詞ですが、禅の世界では、言葉で「何か」として限定できないものの当体を指し示す働きを持たせて使っている場合が多いのです。その典型的一例として「什麼物什麼来」という一文があります。これは、南嶽が六祖慧能のもとに参学にやってきたとき、六祖から発せられた言葉でした。これは「何ものがそのようにやってきたのか」という質問文であると同時に「何ものとしか呼びようのないものが現にそのようにとしか言いようのない仕方でやってきているのだ」という平叙文でもあるというのが禅独特の理解です。現に、この問いかけに対する南岳の応答は「説似一物即不中[一物を説似すれば即ち中(あた)らず]」でした。それは「言葉で何かだと言えば、すでにもう違います」という意味で、限定的な名前や指示語を使った断定的な答えをすべて拒否する形になっていることからもうかがえます。実があって名がないものを仮に「什麼」と呼ぶのですから、説いて一物を示すも即ち中(あた)らずなのです。
これら二つの点を念頭に置いて、これから「南嶽磨塼」の則についての道元の拈提を味わっていきましょう。まず原文をあげておきます。
江西大寂禅師、ちなみに南嶽大慧禅師に参学するに、密受心印よりこのかた、つねに坐禅す。南嶽あるとき大寂のところにゆきてとふ、大徳、坐禅図箇什麼(坐禅は箇の什麼を図る)。この問、しづかに功夫参学すべし。そのゆゑは、坐禅より向上にあるべき図のあるか、坐禅より格外に図すべき道のいまだしきか、すべて図すべからざるか。当時坐禅せるに、いかなる図か現成すると問著するか。審細に功夫すべし。彫龍を愛するより、すすみて真龍を愛すべし。彫龍、真龍ともに雲雨の能あること学すべし。遠を貴することなかれ、遠を賤することなかれ、遠に慣熟なるべし。近を賤することなかれ、近を貴することなかれ、近に慣熟なるべし。目をかろくすることなかれ、目をおもくすることなかれ。耳をおもくすることなかれ、耳をかろくすることなかれ、耳目をして聡明ならしむべし。
ここで「江西大寂禅師」というのは馬祖道一(709〜788)のことです。彼は、六祖慧能の法を嗣いだ南嶽懐譲を師とします。坐禅修行に骨を折った多くの仏祖の中から道元がこの人こそ優れた行持の実物見本だと認める極めつきの32人を選んで、その素晴らしい修行ぶりを個別的に賛嘆している『正法眼蔵 行持』の巻に、馬祖が二度も登場することからもわかるように、道元にとって極めて重要度の高い禅匠の一人だと言えます。ここでは、馬祖とは呼ばず「江西大寂禅師」と敬称を用いていることからも道元が馬祖をたいへん高く評価していることがうかがわれます。
行持の巻の初出の箇所では、次のような短い文で馬祖のことが紹介されています。
「江西馬祖の坐禅することは二十年なり。これ南獄の密印を受するなり。伝法済人のとき、坐禅をさしおくと道取せず。参学のはじめていたるには、かならず心印を密受せしむ。普請作務のところに、かならず先赴す。老にいたりて僻倦せず。いま臨済は江西の流なり。(江西の馬祖は、坐禅すること二十年におよんだ。その坐禅は師の南嶽から親密に伝えられたさとりの心印をまっすぐに受け継いだものであった。だから、法を伝え、人を救済する時にあたっても、坐禅をないがしろにするようなことは決して言わなかった。参学者がはじめて馬祖の道場で修行する際には、かならず心印を密受させた上で坐禅をさせた。普請作務のときには、かならず自ら率先して赴いた。その行持は老年にいたっても懈怠することがなかった。いまの臨済宗の人々もまたその江西の馬祖の流れを汲むものである。)」
この文章の中に「心印の密受」ということが二度も出てきますが、今回身読する『正法眼蔵 坐禅箴』の引用箇所でも「南嶽大慧禅師に参学するに、密受心印よりこのかた」というように、馬祖の長年にわたる坐禅修行は「密受心印」の後であったことが強調されています。
「心印を密受する」というのは、要するに真実の修行のあり方を親密な師弟関係を通して習得するということだと私は理解しています。具体的には、正しい坐禅の行じ方を師から学んで会得することだと思います。坐禅の正しい方向性の理解なしに、坐禅を始めることの危険性は『普勧坐禅儀』の中で、「毫釐も差有れば、天地懸に隔り」とか「若し一歩を錯れば、当面に蹉過す」といった表現をもって繰り返し強調されています。馬祖が、「参学のはじめていたるには、かならず心印を密受せしむ」という方針を採っていたのは当然のことなのです。坐禅は人間がアタマを使って考え出すようなものではないので、必ず明眼の正師から親密に心印を密受した上でなければ坐禅が坐禅にはならないというのが道元の強調するポイントなのです。
中国の禅籍においても南嶽と馬祖の「磨塼作鏡」の話は重要な意味を持つものとして随所で取り上げられていますが、その扱われ方はこの『正法眼蔵 坐禅箴』のそれとは問答の位置づけも意味合いもまったく異なっています。中国の禅籍においては、この「磨塼作鏡」の問答は南嶽と馬祖が最初に出会った時になされたことになっています。そして、坐禅という行為に執着している馬祖に対して、塼を磨いても鏡とはならないように、坐禅しても仏にはなれないということを教えるために、南嶽が塼を磨いてみせて誡めたことになっています。こういう南嶽の「磨塼豈得成鏡耶(塼を磨いて豈に鏡と成すを得んや)」という教えを受けて修行態度を改め、その結果としてその後に密受心印があったということになっています。つまり、「磨塼作鏡」の問答の後に密受心印を置く中国の禅籍と、密受心印の後に「磨塼作鏡」の問答があったとする道元とでは、二つの出来事の順序が逆になっています。さらに「磨塼」の意味合いも、「磨塼は鏡に成らず」とする中国の禅籍と、「磨塼こそが作鏡である」とする道元では、一方は否定、一方は肯定なのですから、真反対になっていることになります。道元は中国の禅籍に見られるオーソドックスな解釈のことは当然承知していたでしょうから、こういう独自の主張は確信犯的なものだと言わなければなりません。道元の立場からすれば、原典である中国の禅籍にはもともとなかった「密受心印」の語をあえて加筆してまで、どうしてもそのように読まなければならなかった理由があるのです。『正法眼蔵 坐禅箴』を読むわれわれは、道元の原文に忠実に従う限りは、この問答は馬祖が南嶽から心印を密受してのち、それに従った坐禅をずっとしていたという文脈の中でなされたものとして受け取らなければなりません。
この点からしても、「坐禅はしょせん初心の者のする修行だ。悟りを開いた後にはもはやする必要はない」という見解があやまりであることは明らかです。ここで展開されている南嶽と馬祖の二人の問答は、馬祖が坐禅を誤解して坐に執着し作仏するつもりで坐っているのを師匠の南嶽がいましめたというような底の浅い話ではありません。二人のどちらもが坐禅の真髄を本当に究めた対等の者同士が互いに協力し合って真の坐禅のあり方を表現し浮き彫りにしようとしている話として理解しなければなりません。先の薬山と僧の話がそうであったように、道元は、この二人の対話も普通のいわゆる質疑応答ではなく、坐禅についてそれぞれの立場から語を換えて、坐禅についてぎりぎりの真実を語り合っているものとして考察しているのです。
密受心印の坐禅をしている馬祖のところに師の南嶽が訪ねてきて、「坐禅図箇什麼」と問いかけます。これは普通には「坐禅して箇の什麼(なに)をか図(はか)る?」と読んで「先生は、坐禅をしてどのようにしたいのですか? どんなつもりで坐禅しておられるのですか?」という質問のように聞こえます。しかし、南嶽はそんな初歩的な質問したのではなく、この一文も「問処の道得」として解釈すれば、「坐禅の図は箇の什麼なり」と読めて、馬祖に向かって「あなたのしている坐禅とはこういうものだな。」と自らの理解を馬祖に示してみせた言葉だと解することができます。
この問い(に見せかけた答え)が素晴らしいものなので、道元は「この問、しづかに功夫参学すべし」「審細に功夫すべし」と勧めています。その参学功夫の態度については、『正法眼蔵 密語』のなかで「参学すといふは、一時会取せんとおもはず、百回千回も審細功夫して、かたきものをきらんと経営するがごとくすべし。かたる人あらば、たちどころに会取すべしとおもふべからず。(参学するというのは、いっときに理解しようと思わないで、百回千回もきめ細かく功夫して、あたかも堅い物を切ろうと苦心惨憺して営むようにしなさい。語る人がいたら、その場ですぐ理解できるはずだと思ってはならない。)」と書かれているのが参考になります。短兵急に一挙にわかろうと焦らず、何度も何度もかみしめてじっくりと取り組むべきだというのです。
その審細な功夫参究のよすがとして、「……か」と末尾に「か」のつく文章がこの後に立て続けに並べられています。『正法眼蔵』にはそういう表現がよく出てきます。文字通りによめば問題提起をした質問文のリストのように見えますが、真意はそうではなく、実は断定の言葉であるというのが曹洞宗門の伝統的な解釈になっています。つまり、質問の形で述べられていることがすべて「イエス(その通りだ)」と肯定されていると解するべきなのです。
その次には、彫龍と真龍の喩えが出てきます。『普勧坐禅儀』の中に出てくる「冀(こいねが)はくは其れ参学の高流(こうる)、久しく摸象(もぞう)に習つて、真龍を怪しむこと勿(なか)れ」と同じく、中国の葉公(せっこう)という人が龍が大好きで龍の彫刻や画をたくさん集めて部屋に飾っていたところに本物の龍が現れると驚いて気絶してしまったという故事が背景になっています。ここで、彫龍、つまり龍を彫るというのは、われわれの生身のからだを素材として龍、つまり仏を彫り上げることですから、それは坐禅のことをさします。真龍というのは本当の仏のことです。彫龍と真龍という対比で坐禅という修行とその証果である作仏(仏に作[な]ること)を表し、「彫龍、真龍ともに雲雨の能あること学すべし」と述べて、その二つが不二一体であることが説かれています。遠と近の対比も同じで、遠は作仏、近は坐禅に対応していると解していいでしょう。そのどちらにも貴賎を決めつけてはならず、どちらも慣熟すべきことは、目と耳を平等に大切にして聡明にしなければならないのと同じだと説かれています。
以上のような、理解に立って今回の一節を次のように口語訳してみました。皆さんの身読の参考にしていただければと思います。
江西大寂禅師、すなわち馬祖道一は南嶽大慧禅師のもとで仏道を学修していた。馬祖は禅の伝統をしっかりと体得して、師から親しく心印を受けて以来(師資相契(ししそうかい)=本当に道を得て師匠と通じ合ったのち)たえず坐禅をしていた。あるとき、南嶽が馬祖のところへ行って次のように話しかけた。
「貴公は(「大徳」は第二人称の代名詞で尊公、貴師の意 師が弟子に使うにしてはていねいすぎの敬称であることに注意)そうやって一生懸命坐禅をしているが、それは「什麼(なに)」という疑問詞を使ってしか指し示すことができないものの図(=具体的な立ちあらわれ、姿形)なのだな(この「図」という漢字はいまある現実とは別ななにかを思い描くという意味の「図(はか)る(「意図(つもり)」)」ではなくいわば「姿形」という意味の「図(ず)(図形)」)。
この問いを静かに落ち着いて思い巡らし、実際の坐禅を通して参究しなければならない。なぜならば、坐禅をさらに上に超えたなにかをめざすような図があるのか?(その通りだ)。坐禅の外側になにか別に図とすべきことがあってそれがまだ言い表されていないのか?(その通りだ)。あるいはそのような「上」とか「外」といったあらゆる図をもってはいけないのか? (その通りだ)。坐禅しているそのときには、どのような図がそこに現成(完成)しているのかと問うているのか?(その通りだ)。このように審(つまび)らかに考えてみるべきである。
彫刻の龍(=坐禅)を愛するレベルからもっと進んで本物の龍を愛するべきだ(=作仏)。しかし、彫刻の龍にも本物の龍にもともに雲を呼び雨を降らす能力があることを学ばなければならない。遠いもの(=作仏)を貴いとしてはいけない。遠いものを賤しとしてはならない。そうではなく、遠いものに慣熟(ものごとに精通していてそつがないこと、熟達・熟練)しなければならない。また近いもの(=坐禅)を賎しとしてはならない。近いものを貴いとしてはならない。近いものに慣熟しなければならない。目で見ていること(=近)を軽んじてはならない。目で見ていることを重んじてもいけない。耳で聞いていること(=遠)を重んじてはいけない。耳で聞いていることを軽んじてもいけない。どちらにも偏ることなく耳も目も聡明にしなければならない。(坐禅と作仏もまたそのようでなければならない)