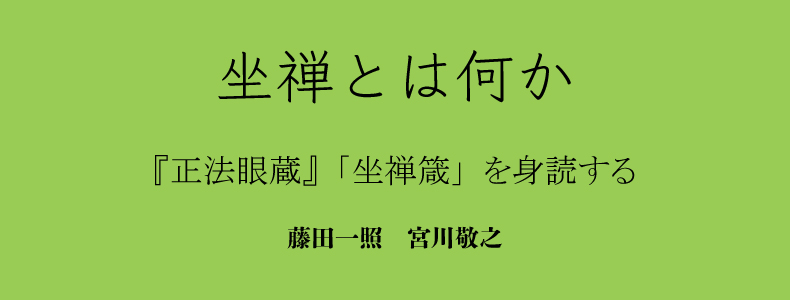坐禅は作仏を待たない
【宮川敬之】身読コラボ⑪
南嶽いはく、「磨作鏡」。
この道旨、あきらむべし。磨作鏡は、道理かならずあり。見成の公案あり、虚設なるべからず。塼はたとひ塼なりとも、鏡はたとひ鏡なりとも、磨の道理を力究するに、許多の榜様あることをしるべし。古鏡も明鏡も、磨塼より作鏡をうるなるべし、もし諸鏡は磨塼よりきたるとしらざれば、仏祖の道得なし、仏祖の開口なし、仏祖の出気を見聞せず。
大寂いはく、「磨塼豈得成鏡耶」。
まことに磨塼の鉄漢なる、他の力量をからざれども、磨塼は成鏡にあらず、成鏡たとひ聻なりとも、すみやかなるべし。
南嶽いはく、「坐禅豈得作仏耶」。
あきらかにしりぬ、坐禅の作仏をまつにあらざる道理あり、作仏の坐禅にかかはれざる宗旨かくれず。
大寂いはく、「如何即是」。
いまの道取、ひとすぢに這頭の問著に相似せりといへども、那頭の即是をも問著するなり。たとへば、親友の、親友に相見する時節をしるべし。われに親友なるは、かれに親友なり。如何・即是、すなはち一時の出現なり。
南嶽は言った。「磨だ、作だ、鏡だ〔磨なり、作なり、鏡なり〕」。
この修行の要点を、見極めよ。「磨作鏡」は、(「磨いて鏡にする〔磨して鏡と作す〕」という通常の読み方ではなく)、そこに修行の道理が示されていることとして読むべきなのだ。それは、「あるものに成る」ことを示した公案なのであって、空疎な言葉ではない。塼は塼であっても(鏡との比較を絶した塼であり)、鏡は鏡であっても(塼との比較を絶した鏡なので)、そうした(「あるものに成る」)磨=修行の道理を全身全霊で努めるときに、仏道の教えの多くが、リアルに立ち上がってくるのだ。「古鏡の教え」も「明鏡の教え」も、磨塼の修行において、鏡となることを得ていたのである。もし、そうした「鏡を喩えとする教えの数々」が磨塼の修行においてありえているということをわからないと、仏祖たちの言葉には修行の実践がないことになり、それでは仏祖がわれわれに語りかけてくることはなく、仏祖の生き生きと息づく生身にお目にかかるということもなくなってしまうのだ。
大寂(馬祖)は言った。「磨塼はどうして成鏡などだろうか!〔磨塼、豈得てんや、成鏡をや〕」。
さすがに(馬祖は)磨塼=修行の鉄漢である。他との比較をすることなく、磨塼が成鏡ではないこと、成鏡は鏡そのものになるためにすばやく成し遂げられることを、わきまえているのだ。
南嶽は言った。「坐禅はどうして作仏などだろうか!〔坐禅、豈得てんや、作仏をや〕」。
この言葉で、坐禅は作仏を待つ修行ではないという修行の道理が、はっきりとわかるのである。作仏と坐禅とが因果関係として結びついているのではない、という教えの中心が明らかとなっているのだ。
大寂は言った。「如何が即是だ!〔如何は即是なり〕」。
この言葉は、単純に(「正しい〔即是〕のは、なに〔如何〕か?〔即是は如何なるか〕」という)こちら(われわれの思考)からあちら(仏のさとり)への問いのように見えるが、実は(「なにか〔如何〕とは、このもの〔即是〕だ!」という)あちら(仏のさとり)からこちら(われわれの思考)への問いかけでもあるのだ。たとえるならそれは、親友だと思っていた相手に、向こうから親友だと言われるときのようなものだ。自分から親友だと思っていたが、相手側からすでに親友と思われていたということである。(親友というありようが、こちらとあちらとの相互の働きによって成り立つように)「修行弁道のポイント〔如何〕」と「ここにあるものになること〔即是〕」とが、同時に出現しているのである。
〈あるものに成る〉
今回は南嶽と馬祖との対話の言葉、「磨作鏡」「磨塼豈得成鏡耶」「坐禅豈得作仏耶」「如何即是」という言葉を道元禅師がどのように独特に(あるいは無理矢理に)読み替えているかを明らかにすることが中心となります。その読み替えの主題について道元禅師は、「見成の公案なり」と言われました。この連載の第7回に、「見成の公案なり」の前後逆の表現である「公案見成」を、私は「仏のさとりとわれわれの思考とが接続できる場所」と訳しました。「見成の公案なり」もまた、こうした「公案見成」の意味と同じものとして解釈したいと思っています。しかし今あらためて振り返ると、この翻訳はまったく不十分なものに思えます。私は、「仏のさとり」を「見=現」の訳語として、「われわれの思考」を「成」の訳語として、それぞれを訳しましたが、どうしてそのように訳せるのかをちゃんと説明できていませんでした。さらに「公案」を「接続できる場所」と訳しているのも不正確です。今回は、第7回で解説したことを整理しなおし、解説を新たにして、「見成の公案なり」が「あるものに成ること」へと翻訳できることを示し、それを読み替えの主題とすることについて述べてみたいと思います。
「現成」ということを解説するには、やはり『正法眼蔵』「現成公案」巻に戻らなければなりません。第7回にも述べましたが、「現成公案」巻冒頭の三文こそ、「現成」の意味構造を端的に示すものであるからです。
1,諸法の仏法なる時節、すなはち迷悟あり、修行あり、生あり、死あり、諸仏あり、衆生あり。
2,万法ともにわれにあらざる時節、まどひなく、さとりなく、諸仏なく、衆生なく、生なく、滅なし。
3,仏道もとより豊倹より跳出せるゆえに、生滅あり、迷悟あり、生仏あり。しかもかくのごとくなりといへども、花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり。
私はこの三文を、1=われわれの思考、2=仏のさとり、3=修行のありようを示すものと読み、さらにそれを1=思量=作仏、2=不思量=身仏、3=非思量=行仏と当てはめました。その上で、次のような解説をしました。
作仏とは、「(私が)仏になる(目的をもつ)」あるいは「(目的として私が)なろうとする仏」という構造をもちます。要するに、私という主体が、仏という客体に接続しようとすることです。しかしこの構造には、仏のさとりの内容を、われわれの思考で理解する範囲にとどめてしまっているという問題があります〔1で示されたことがら〕。もし、仏のさとりがわれわれの思考をのりこえるものであれば、そこにわれわれの思考によって接続しようにも、接続することはできません〔2で示されたことがら〕。(中略)仏に接続するならば、固定され安定した「私」を揺り動かさなければならないわけです〔3で示されたことがら〕。(中略)つまり「作仏」は、「行仏=坐仏」によって、「私の視点」そのものを揺り動かし、「目的への修行」を、否定されなければなりません。(〔〕は今回の引用にて追加)
この解説の大枠自体は現在も妥当だと私は理解しています。今回も「磨作鏡〔磨きて鏡と作す〕」を「磨だ、作だ、鏡だ〔磨なり、作なり、鏡なり〕」と読み替えた前提には、この図式をあてはめて、一つの文章ではなく、この一語一語が、磨=3(修行のありよう)、作=1(われわれの思考)、鏡=2(仏のさとり)、という構造へと分解されていると理解しています。けれども不十分なのは、こうした構造の基幹となる部分について、私の考察が浅いという点です。そもそも私は、仏のさとりとはなんなのか、そしてそれに対してわれわれの思考が届かないのはなぜなのかを、はっきりとつかめていませんでした。私の理解の不十分さを教えてくれたのは、奥村正博老師のRealizing Genjokoan(『「現成公按」を現成する』Wisdom 2010 以下RG)という著作です。奥村老師はアメリカで50年以上にわたって道元禅師研究と坐禅修行を続けられ、一照さんの先輩でもあられる方です。奥村老師の行論を導きとして、仏教の根本に帰って考えたいと思います。
初期仏教において仏のさとりといわれるものは、この世の中の実相である「縁起」のありようを見極めるということでした。それは世の「無常」と「無自性」のありさまを知ることとも言われます。しかしそのように言われても、これらの語句は私たちには新鮮なものではなく、そのため「縁起」「無常」「無自性」の三者における構造的つながりに関しても、私はなんとなくわかった気でいただけで、はっきり理解できていませんでした。
奥村老師は、「縁起」を「インターディペンデント・オリジネーションinterdependent origination」と英訳され、「無常」を「インパーマネンスimpermanence」、「無自性」を「ラック・オブ・インディペンデント・エグジスタンスlack of independent existence」という用語として述べられて、RGにおいてこれら三者の構造的つながりを明確に述べられています。「インターディペンデント・オリジネーション」とは、「相互に(インター)依存して(ディペンデント)生起していること(オリジネーション)」であり、「縁起」の原語であるサンスクリット語「プラティーティヤ・サムトゥパーダ」に正確に対応した訳語です。この訳語において私ははじめて「縁起」ということがらが理解できたのです。それは次のようなことです。
私たちは普段、自分たちを独立した個々の存在であると考えて生活しています。しかし実は私たちは「インターディペンデント・オリジネーション」、すなわち十重二十重に相互影響されるネットワークの網の目の結び目一つ一つであるにすぎず、ありとあらゆるすべてのものやことがらとつながって生きているのです。これが「縁起」であり、世の実相であって、奥村老師の師である内山興正老師が「生命の実物」と呼ばれたものです。
この「縁起」の網の目は、端の一部が動かされただけで全体が動いてしまうような、相互関連し、絶えず動きつづけている世界なのであって、その動的なありように注目すると、私たちは「永続性のない=無常の(インパーマネント)」世界に生きていると言えますし、また、個々の「私」という独立した存在性を持ち得ないありように注目すると、「独立した存在性の欠如(ラック・オブ・インディペンデント・エグジステンス)」、すなわち「無自性」であると言えます。このように「縁起」「無常」「無自性」は同一の世界の実相についての構造的つながりにおいて、理解されるべきことがらです。これこそが初期仏教の思想の枠組みといえるのです。さらに大乗仏教になると、こうした相互影響しあい独立した存在性を欠損させている世界全体を「空」(『般若経』)と呼び、また「諸法実相」(『法華経』)とも呼びました。
こうしたありようは、知識として頭で理解する場合、そんなに難しさは感じません。しかし、こうしたありようは現実そのものであり、そうした相互影響しあう世界の実相に生きながら、私たちは普段それをわきまえることができず、依然として自分を独立した存在であるとして生きているのはなぜか、と考えると、急激に難解になってしまうのです。
問題となるのは、こうした全体として相互影響しあう世界の実相(生命実物)は、私たち自身がその一部であるがために、私たちの知覚では捉えることができないという点です。私たちの、世界の一部から局部的にしか見ることができない知覚では、世界の総体を客観的に捉えることは決してできないからです。連載第7回において私の理解が浅かったのはまさしくこの点です。奥村老師はつぎのように解説されています。
私たちは移ろいゆく、小さい人間存在であるために、生命実物の真のすがたである全体性を対象として見ることはできません。この生命実物の内部で生まれ、生き、死んでゆくために、自分の個人存在によって隠されている部分を見ることはできません。例えば、視界の角度は百八十度よりも小さいので、前を向いている時には私たちの後ろ側を見ることはできません。そして後ろになにがあるのか振り返って見ようとすると、前にあるものを見ることはできません。鏡か何かを使わなければ、自分の後ろを見ることはできないということです(RG p.147 Wisdom 2010 宮川訳)
われわれの知覚や思考は、原理的に私たちの外部にあると知覚し思考する対象に向けられています。通常はそうした外部対象をさらにいかに細かく分離(分ける)できるかが、理解(分かる)することの基礎であるのです。仏教の教説に対しても、迷いと悟り、悟りと修行、修行と迷い、生と死、仏と衆生という区分をして考えるのがわれわれの思考です。これは知識として「縁起」を理解しようとしているのであり、それが「現成公按」巻冒頭第1文で示されていることだと言えます。
しかし、私たちを含み決して客観的に分離することができない、実際の「相互影響しあう世界の実相」である「縁起」の世界にすでにいることを踏まえると、第1文で示された仏教の教説も、私たちの局部的な知識にすぎないことになり、教説の区分自体の独立性が無くなってしまうのです。それが第2文で示された「まどひなく、さとりなく、諸仏なく、衆生なく、生なく、滅なし」です。私たちは自分たちがすでにその一部である世界全体を思考できず、知覚することができません。特に知覚としては無であり闇であり、それを無理に思考しても、それは結局、さらに「生命の実物」の現実から離れた、勝手なでっちあげを各自の思考において行ってしまうことに過ぎなくなるのです。そのようにして、第1文と第2文、言い換えれば、「私たちの思考」と「仏のさとり」とを接続する方法は無いことになるのです。しかし道元禅師は、両者の性質の差を踏まえながら、その両者をともに「実現」していく方法があると考えました。それが「現成公案」、「公案の現成」であって、第3文に示されたことがらでした。
そのように考えると、「仏のさとりとわれわれの思考とが接続できる場所」という先回の私の翻訳は、「接続できる」という点が翻訳として不正確であることがわかります。「接続する」という言い方は、「仏のさとり」を客観的なものと見て、私たちの独立した主体を残したまま、そこに働きかけようとしているからです。求められるのは、「仏のさとり」にすでに内在している私たち、しかもそれを知覚できない私たち、ということを認めながら、好悪、善悪といった「思考」の分別をしてしまう私たちのありようをも否定せず、その両者をともに実現することです。それが「仏道」であると第3文で言われます。これが坐禅修行の眼目となるわけです(「公案(按)」の本義は、奥村老師によれば、縁起による全体性の世界〔公〕と思考による個別の世界〔案=按〕を示すとされます。つまり「現成」と「公案(按)」とは、全体と個別の総体を示す、同義語と解釈されています)。
「私たちの思考」では、それまで存在していない(と信じる)ものに「成ろう」とし「成らせ」ようとする方向性を持ちますが、一方「仏のさとり」では、世界の実相としてすでに私たちを包含している「現在ある世界」に私たちが(私たちという個別性が解体されるかたちで)「ある」ことそのものを認めることを主眼とします。ですからこの両者をともに実現することは、「あることに成る」というありようを目指すことになります。それは外部的、対対象的に動く動きではなく、内部的であり、かつ、対対象的であることをやめるような働きとして実現していきます。これが「現成」であり、「公案(按)」であることです。
このことは、内部的であることを徹底させているという意味で「自受用三昧(じじゅうゆうざんまい)」と呼ばれます。すなわち坐禅において現成されるありさまです。このようなありさまを目指す場合に、「私たちの思考」もまた、外部的ではなく内部的に、主体の対象への働きかけではなく、主体と対象とのあいだで働く働きかけそのものへの着目へと重点をシフトすることになります。外部的で対対象的である思考から、内部的で対対象的であることを放下する思考へ。こうした思考の重点のシフトの仕方は、通常の言葉の読み替えを私たちに迫るものとなると道元禅師は考えられました。「あることに成る」という、対対象的な方向を放下した思考こそ、本稿冒頭に示した読み替えの根拠をなす、ということです。
〈内部にいること〉
対対象性を放下して、世界の内部にいることに自足する行為=思考は、道元禅師以外の思想にも認められることがらです。たとえば先回に一照さんが触れられたように、アリストテレスの「エネルゲイア(自前の目的をそのうちに含んでいる行為)」もその一つであるといえるでしょう。同じ「エネルゲイア」でも私としては、14世紀の東方キリスト教会で、グレゴリオス・パラマス(1296-1359)によって大成された、ヘシュカスム(静寂主義)の考えにおけるエネルゲイアを、参考と対照のために挙げておきたいと思います。
ヘシュカスムとは、東方修道制の中で展開した霊性運動の一つで、ギリシャ語「ヘーシュキア(静寂・休息などの意味)」を語源とすると言われます。ヘシュカスムの実践者をヘシュカストといい、彼等は静寂のうちに神を観相し、「イエスの祈り」をくりかえし唱え、神との一致を図ろうと修行します。ヘシュカスムでは、神の本質を「ウーシア」、神の働きを「エネルゲイア」と区別して、人間は神のウーシアに絶対に与れないが、エネルゲイアには与りうるとしました。エネルゲイアという働きに一体化することで、修行者は神の光を見ることができるというのです。私がこれらのことを知ったのは、これまでも何回か言及してきた美術家岡﨑乾二郎氏の諸論考においてでした。岡﨑氏は、建築家白井晟一の思想を探る論考のなかで、ヘシュカスムのエネルゲイアの考えに触れ、つぎのようにまとめています。
ヘシュカスムではこう考える。〔三位一体において、イエス、精霊、父の三つの位格が一つであるとされるが、その〕一つであることはエネルゲイア=働き、活動である。働きは働きの中でだけ把握されるのであって、対象としては認識されない(位格ではない)。たとえばy=f(x)という回路を考えよう。この回路はxに代入された値をyの値に変換(写像)する働きを持つが、ここで認識されうるのはx、yで値として現れる数だけである。回路それ自体はブラックボックスであり、値を持つわけではない。すなわちそれは暗闇に閉ざされている。ペルソナとはxそしてyに代入されるこの値であり、この二つの変数を繋ぎ、変換する回路の働きがエネルゲイアである。神の本質とはこの回路=函数の働きそのものである。それを認識することは、この回路の働きに祈ることで一体化すること、この変換過程=エネルゲイアの流れとして自ら身を投じることである。光は見るものではない。光とはエネルゲイア(エネルギー)であり、祈るとはそのエネルゲイアの流れに一体化し、光を自らの内部に感じることだ(岡﨑乾二郎「白井晟一という問題群3」『抽象の力』p.365 亜紀書房 2018)
ヘシュカスムの修行では、修行者が神の光(エネルゲイア)を見るとは、自らが祈りの働き(エネルゲイア)となることでした。それは、「自分自身の働きを心に集中させ、心が全体として自己の内奥に入るという心の自己再帰を表しまた実現する」(宮本久雄「心身観における東洋と西洋」『教父と愛知』p.269 新世社 1989)修行と言われます。ヘシュカストたちは、呼吸法や坐る姿勢の考察を含んだ具体的な身体的修練に基づく瞑想法を実践していました。それは椅子に座ったまま体を円形に丸めて聖人の名を唱えるというもので、その姿からしばしば「オンファロプシィコイ(霊魂をほぞに向ける人びと)」と揶揄されたそうです(詳しくは宮本同論文を参照)。これは、やり方は違いますが、道元禅師が言われる「自受用三昧」の坐禅を思い起こさせるものです。また、「この変換過程=エネルゲイアの流れとして自ら身を投じること」は、道元禅師が称揚される「身心脱落」や「弁道」のありようにもつながる点があるように思います。道元禅師とほぼ一世紀を隔てながら、こうした共通項を持った思想が世界の別の場所に現れていたことを知るのは、大変刺激的なことがらだと思います。
さらに、エネルゲイアのような内部の働きへの合致と自己再帰のありようが、言語、特に動詞のうえで働く場合、それは「中動態」と呼ばれました。ギリシャ語などでかろうじて残っているこの奇妙な動詞の態(voice)は、近代言語で能動態と受動態との対立になってしまう以前の形をしているといわれます。つまり、古代では、そもそも動詞の態は能動態と中動態の対立であったものが、しだいに能動態と受動態の対立になったといわれているのです。能動態と中動態とがどのように違うのかについて、フランスの言語学者エミール・バンヴェニストは次のように説明しました。
能動では、動詞は主語から出発して、主語の外で完遂する過程を指し示している。これに対立する態である中動では、動詞は主語がその座となるような過程を表している。つまり、主語は過程の内部にある
(『一般言語学の諸問題』p.169 みすず書房 1983)
國分功一郎氏はこうしたバンヴェニストの中動態についての規定を詳細に検討しながら中動態の変遷とそれが示す事態について丹念に追い、『中動態の世界』(医学書院 2017)という驚くべき書物を書きました。國分氏の著書を読むと、中動態には、パラマスの言うエネゲイアのありようが動詞の態変化の問題として反映されていることが見て取れます(ただし、文法用語としての「エネルゲイア」は能動態のことを言い、中動態は「メソテース」と言われるので、やや混乱してしまいますが)。たとえばギリシャ語の動詞「ポリテウエスタイ」は中動態になっていて「自らが政治に参加し、公的な仕事を担うこと」という意味ですが、それが能動態「ポリテウエイン」になると「統治者として統治すること」という違いが生まれるそうです。このように、主語が外部ではなく、動詞が示す過程の内部に主語があるとき、動詞は中動態という形をとっていたといいます。重要なのは、國分氏がこのような中動態の研究に本格的に乗り出したのは、小児科医で研究者の熊谷晋一郎氏からの依存症研究についての質疑応答が契機となっていたという点です。國分氏の中動態の探求は、医療などの実践の場を念頭におかれていたということです。実際に、最近の『〈責任〉の生成』(新曜社 2020)では、熊谷氏との共同の研究によって、中動態と当事者研究(精神疾患などのトラブル発生の原因を、患者自身が他者とともに語り合いながら探り行う研究)について、実践的で刺激的な知見が多く示されています。
グレゴリオス・パラマスのエネルゲイアの実践と、バンヴェニスト―國分氏の中動態の分析とは、どちらも私たちがすでになにかの内部にいることを表現しようとする点に共通項を持っています。そして道元禅師の坐禅もまた、「自受用三昧」という、世界の内部に「あることに成る」ありようを狙っていて、また、その内部に「あることに成る」ありさまを読み替えの論理として「磨作鏡」「磨塼豈得成鏡耶」「坐禅豈得作仏耶」「如何即是」を読み替えていると私は考えます。
まず「磨作鏡」は、「磨いて鏡にする〔磨して鏡と作す〕」ではなく、「磨だ、作だ、鏡だ〔磨なり、作なり、鏡なり〕」と読まれます。これは前述したように、作=われわれの思考(塼)と、鏡=仏のさとりとが、磨=修行の働きによって、同時に成り立ち、表現されるべきだという、世界の内部にあることに成る修行のありさまとして、読み替えているといえます。そうした内部にあることに成る修行は、塼をいったん縁起に分解してしかも比較を絶した塼のすがたに再生し、鏡もまたいったん縁起に分解してしかも比較を絶した鏡に再生して、磨、塼(作)、鏡の三つの位格が、世界内部での働きのなかでそれぞれが独立しつつしかも相互に影響をあたえつつ成り立ってゆくありさまを語ろうとしています。そのありさまによってこそ、「磨塼豈得成鏡耶」は「塼を磨いてどうして鏡に成るだろうか、なりはしない〔塼を磨くも豈に鏡を成すを得んや〕」ではなく、「磨塼はどうして成鏡などだろうか!〔磨塼、豈得てんや、成鏡をや〕」と読み替えられ、また「坐禅豈得作仏耶」も「坐禅をしてどうして仏に作るだろうか、なりはしない〔坐禅、豈に仏と作ることを得んや〕」ではなく、「坐禅はどうして作仏などだろうか!〔坐禅、豈得てんや、作仏をや〕」と読み替えられます。磨塼と成鏡、坐禅と作仏とは、それぞれがそれぞれの内部に入り、働きになることによって、外部的な比較を超越してしまうのです。
また、主体と客体とが独立し、主体が客体に対対象的にかかわってゆくという、通常の私たちが考えているありようは、実は私たちの心理的捏造なのであって、すでに一つの世界の内部の中でいる私たちには、そのような主体と客体の一方的な対対象的なかかわりが成立しません。世界の内部では、働きは必ずインタラクティヴであるからです。そこで「如何が即是だ!〔如何は即是なり〕」という読み替えが可能になります。道元禅師の解説は次のようでした。
この言葉は、単純に(「正しい〔即是〕のは、なに〔如何〕か?〔即是は如何なるか〕」という)こちら(われわれの思考)からあちら(仏のさとり)への問いのように見えるが、実は(「なにか〔如何〕とは、このもの〔即是〕だ!」という)あちら(仏のさとり)からこちら(われわれの思考)への問いかけでもあるのだ。たとえるならそれは、親友だと思っていた相手に、向こうから親友だと言われるときのようなものだ。自分から親友だと思っていたが、相手側からすでに親友と思われていたということである。(親友というありようが、こちらとあちらとの相互の働きによって成り立つように)「修行弁道のポイント〔如何〕」と「ここにあるものになること〔即是〕」とが、同時に出現しているのである。
外部へと向かい、いつでも対対象的であろうとする「われわれの思考」を使いながらも、同時にその放下を不断に試み、すでに私たちがそのなかにいるために知覚することができない「仏のさとり」=「縁起」のありように、内部的に、働きとして「なる」ことを目指して自分のありようそのものに徹底すること。道元禅師の坐禅は、およそこうした、叙述するとかなり奇妙で、また非常に複雑に見えるありようを、ただシンプルに坐禅することによって表してしまうことだと言えると思います。
【藤田一照】身読コラボ⑪
師匠の南嶽と弟子の馬祖の問答、いわゆる「南嶽磨塼の則」に対する道元禅師の徹底した拈提がさらに続いていきます。それによって道元禅師はいったい何を明らかにしようとしているのか、読む者に何を伝えようとしているのか。われわれはそれを注意深く読み取っていかなければなりません。『正法眼蔵』のような古典と呼ぶに値する書物は、書かれている字句を辞書的なレベルで単に現代語に翻訳するだけでは、本当に読んだことにはなりません。「眼光紙背に徹す(書物の表面上の意味だけでなく、字句の背後にある意味まで読み取ること)」る味読、身読、深読が要求されます。あたかも固い地面を手で掘っていく作業のような参究の努力が読者の側を育てていくのです。
若松英輔さんの『悲しみの秘儀』(文春文庫)の中に「よむ」ことに関しての深い洞察を述べた次のような一節があります。「作品は、作者のものではない。書き終わった地点から書き手の手を離れてゆく。言葉は書かれただけでは未完成で、読まれることによって結実する。読まれることによってのみ、魂に語りかける無形の言葉になって世に放たれる。読み手は、書き手とは異なる視座から作品を読み、何かを創造している。書き手は、自分が何を書いたか、作品の全貌を知らない。それを知るのはいつも、読み手の役割なのである。」この『正法眼蔵 坐禅箴』もそのような「よみかた」をしていけたらと願っています。
「南嶽磨塼の則」は、馬祖が行なっていた坐禅という「行為」に対して、南嶽が「大徳、坐禅図箇什麼」と「言葉」によって問いかけたことが発端となって始まりました。それは、言葉の絶えた黙々たる坐禅に対する、敢えてそれを言葉の世界に持ち込んで、坐禅とは何かを開顕させようとする働きかけであったということができます。だとすれば、坐禅という行為とその言語的表現・把握という問題の提起として読み取ることができそうです。たとえどれほどささやかなものであっても、或る具体的な行為を言葉で捉えて表現するということは、多面的・多義的・流動的な行為の全体性そのものではなく、ある観点から光を当てた特定の界面のみを静止的に抽出することになります。これは、言葉の持っている原理的な働きであり、本質的な限界です。
たとえば、食事をするという誰もが日々繰り返している極めて平凡な日常的行為の一つを取り上げて、「それはそもそも何をしていることなのか?」と自問自答してみてください。「食事をするということは生命維持のための栄養補給の営みである。」と言えば、おそらく学校の試験ならそれで合格ということになるでしょうが、果たしてそれで現実の「食べるという行為」全体が含んでいる豊かな意味や体験の世界が言い尽くされているでしょうか? 人間にとって食べるという行為は本来非常に豊かな営みであり、単なる栄養補給どころではなく、それをはるかに超えて、個々の食材との出会い、味や見た目、食感などの感覚体験、食べる環境との交流、食事を共にする人との一期一会のインタラクションといった実に多様な体験が食べる行為には含まれています。そういう食べるという行為の豊かな体験をフルに味わうことが大切であるにもかかわらず、われわれは「食べることは栄養補給である」というような狭い「定義」にとらわれてしまいがちです。そのことが、逆にわれわれの食べるという経験を狭く貧しいものにしているのではないでしょうか? 現在の日本の「食」の現実が抱えているいろいろな意味での悲しいまでの「貧しさ」が報告されていますが、その一因はこういうところにあるのかもしれません。
坐禅という行為を言葉で理解し表現しようとすると、必然的に坐禅を矮小化し、限定し、貧しいものにすることになるのです。そんな言葉のトラップに南嶽や馬祖のような本物の禅者が無自覚なはずがありません。「思いでは思うことができず、言葉では言うことができないことをやるのが坐禅である」という澤木興道老師の言葉があります。坐禅という行為は思いや言葉という有限の入れ物には収めることができないのです。しかし、そういうどうやっても無理なことをやってしまうのがわれわれ人間というものです。そのことで思い出すのは、詩人のまどみちおさんの「そもそもアリや菜の花ちゅう名前自体、人間が勝手につけたものですよね。われわれが社会生活をする上では名前がなくちゃ困るけれど、名前で呼ぶことと、そのものの本質を感じることは別なんじゃないでしょうか。なのに『あ、チョウチョだ。あれはモンシロチョウか』と思った瞬間たいていはわかった気になって、その対象を見るのをやめてしまう。どんな存在も見かけだけのものじゃないのに、人間はその名前を読むことしかしたがらないんですよね。本当に見ようとは、感じようとはしない。それはじつにもったいないことだと思います。」(『いわずにおれない』集英社be文庫)という指摘です。「坐禅とはこういうものである」という理解は、それがたとえ正しいものであっても、その理解と坐禅そのものとは天地懸隔なのです。その「こういうもの」は坐禅の一面ではあっても全面ではない以上、その理解の範囲にとどまって、坐禅を「本当に見ようとは、感じようとはしない」とすれば、「それはじつにもったいないこと」です。坐禅という行為の当体はいつでもその理解以上のものだからです。これはチベット語の表現らしいのですが、坐禅は「『ここ』と言って指を置くことができない」ことなのです。指を置いている「ここ」は確かに「それ」の一部ではあるのですが、「ここ」以外の指の置かれていない領域が無限に広がっているからです。「それ」のどこに指を置いても事情は同じです。このたとえの「それ」が坐禅の実物であり、指が言葉にあたります。
またこれは、一般意味論でよく言われる「地図と現地の違いの自覚」という問題ともつながってきます。一般意味論の創始者であるアルフレッド・コージブスキーは、言語などの表現方法(地図)によって、生の現実(現地)がどれほど破棄されているかということへの深い自覚を持つことを通して、自然言語に本来的に組み込まれている「観念化」の罠に陥ることや吟味されることのない常識の前提への盲目的依拠を避けるべきであることを提唱しています。内山興正老師は「思いで煮たり焼いたりする以前を生(なま)と言い、どっちへどう転んでも現ナマの生命だけが実物である。そして、生命の実物をただ純粋に実物しているのが坐禅だ。」とおっしゃっていました。ですから、生命の実物をただ実物している坐禅という生(なま)の行為そのものとそれを思いや言葉で煮たり焼いたりして加工した坐禅についての言説とを混同してはいけないのです。
樹下に打坐し「目覚めた者」となった釈尊が、自分の見出した法(ダルマ)を説法によって人に伝えることは不可能であるという絶望感を感じて、説法を始めることに躊躇逡巡したということも、その問題に深く関わっているはずです。しかし実際には、釈尊はその地点に止まって沈黙を守り説法を放棄した(もしそうなら釈尊はただの「神秘家」だったということになる)のではなく、そこからさらに梵天の勧請によって、説法への絶望を翻して積極的な説法(コトバによる伝達)へと立ち上がるという革新的な一歩を踏み出しました。私はこの沈黙から説法への転換も釈尊の成道の必須の成分になっていると考えています。つまり、それなしには本当の成道の完成とは言えないだろうということです。不立文字・教外別伝を標榜する一般的な禅のイメージとは違って、道元禅師が「道得」とか「説取」(「得」も「取」も、音を強めるための中国語の用法で助字といわれるもので、特別の意味はない。どちらも言葉で説くことと意味する)と呼ぶ、言語による表現の努力を重視していることを見逃してはなりません。われわれが今読んでいる南嶽と馬祖のやりとりは、「梵天勧請」と呼ばれる釈尊の生涯における重要なエピソードにつなげて理解できるような気がします。黙って坐禅する馬祖が釈尊で、それに呼びかけた南嶽が梵天という対応を見るのはうがちすぎのこじつけでしょうか?
坐禅という行が「言辞相寂滅」、「言語道断」、「言詮不及」といった次元のものであることは百も承知のはずの南嶽がなぜわざわざ「坐禅図箇什麼」と言葉で問い、それには何も答えず坐禅し続けていても良かったはず(自分のしている坐禅そのものが答になっているから)の馬祖も、なぜ「図作仏」と言葉で応えたのかをよくよく考えてみなくてはなりません。私は、坐禅という行為(この「坐禅」もすでに言葉です)を、言葉によって明確に規定しようとして南嶽と馬祖の問答が行われていたのではないという理解に基づいてこれまでの論釈をおこなってきました。「什麼」を、答えを要求する疑問詞としてではなく、言語的限定の不可能性を指す指示語として、語句の通常の用法を破った解釈をしています。そして、彼ら二人のねらいは、坐禅という行為はいかなる言語的な限定によっても絡め取ることができない(思いによって思うこともできず、言葉によって言うこともできないこと、それを「什麼」という表現で表している)もので、現に坐禅をするという実際的行為によるしかそれに触れる道はないことを、言葉と行いを応酬し合うやりとりによる共同作業で生き生きと表現することではなかったかと考えています。道元禅師は『普勧坐禅儀』の中で、「什麼の事を得んと欲せば、急に什麼の事を務(つと)めよ(思いで思えず、言葉で言えないことを会得したいと思うなら、そのことを直ちに行じなさい)」と書いています(道元禅師の『正法眼蔵』にはこの「什麼」に関して詳細な検討を加えた『什麼』という巻がある。乞参照)。原理的に言えないことをどう言葉で表現するかという釈尊が直面したのと同じ課題を、坐禅に関して引き継いでいるのがこの二人のやりとりだというのが私の理解です。そして、道元禅師もその課題を継承し、そういう問題意識のもとにそのテーマをさらに深く掘り下げようと拈提しているのです。
馬祖の「図作仏」という言葉による応答を聞いた南嶽はそばに落ちていた瓦のかけらを取り上げ、石に当てて研ぎ始めます。今度は、南嶽の方が黙って或る行為をしてみせる番なのです。それに対して、馬祖が「師、作什麼」と言葉で問いかける役を引き受けます。これは、黙って坐禅している馬祖に南嶽が言葉で問いかけたことと、二人の役割は交替していますが、対をなしています。ですから、坐禅をすることと塼を磨くという行為、それに対する「坐禅図箇什麼」と「作什麼」というどちらも「什麼」を含む言葉による問いかけは対応関係にあると見ることができます。どうやら、南嶽と馬祖は行為する役とそれについて言葉で問う役を二人で交替しながら、坐禅についてそれぞれの理解を開陳し合っているように私には見えます。だとすれば、その問いかけに応えた「図作仏」と「磨(塼)作鏡」という応答の言葉も相互に対応関係にあるとみなすべきでしょう。図=坐禅=磨塼=修行、作仏=作鏡=証果という対応です。そのような仮説に基づいて今回の箇所を読んでいきたいと思います。
まず次の原文を、できたら黙読ではなく声に出して音読してください。言葉の音や響き、リズムが、概念的な意味を知的に考えてそれらの辻褄を合わせることを超えた何かを伝えてくれるはずです。そういうことも音読するという行為の持つ力の実例だと思います。私は『正法眼蔵』を音読するたびに、日本語で書かれた『正法眼蔵』を、翻訳ではなく原文のまま、理解はともかくとして声に出して読める日本人に生まれて本当に幸いであったとつくづく有り難く思う者の一人です。
南嶽いはく、「磨作鏡(まさきょう)」。
この道旨、あきらむべし。磨作鏡は、道理かならずあり。見成(げんじょう)の公案あり、虚設(こせつ)なるべからず。塼(せん)はたとひ塼なりとも、鏡(きょう)はたとひ鏡なりとも、磨の道理を力究(りききゅう)するに、許多(こた)の榜様(ぼうよう)あることをしるべし。古鏡も明鏡も、磨塼より作鏡(さきょう)をうるなるべし、もし諸鏡は磨塼よりきたるとしらざれば、仏祖の道得(どうとく)なし、仏祖の開口(かいく)なし、仏祖の出気(しゅっき)を見聞(けんもん)せず。
大寂いはく、「磨塼豈得成鏡耶(ませんきとくじょうきょうや)」。
まことに磨塼の鉄漢(てっかん)なる、他の力量をからざれども、磨塼は成鏡にあらず、成鏡たとひ聻(にい)なりとも、すみやかなるべし。
南嶽いはく、「坐禅豈得作仏耶(ざぜんきとくさぶつや)」。
あきらかにしりぬ、坐禅の作仏をまつにあらざる道理あり、作仏の坐禅にかかはれざる宗旨かくれず。
大寂いはく、「如何即是(いかんがそくぜ) 」。
いまの道取、ひとすぢに這頭(しゃとう)の問著(もんちゃく)に相似(そうじ)せりといへども、那頭(なとう)の即是をも問著するなり。たとへば、親友の、親友に相見(しょうけん)する時節をしるべし。われに親友なるは、かれに親友なり。如何・即是、すなはち一時(いちじ)の出現なり。
私は次のように言葉を補いながら現代語にしてみました。原文と対照しながら読んでみてください。
南嶽が言った。「磨が作鏡である」。
道元禅師はこの言葉を「(塼を)磨いて鏡を作る」とは解さず「磨塼という行為がとりもなおさず作鏡である」と解す。だから「磨(塼)は作鏡なり」と読むべきだ。この言葉の真意を参究し明らかにしなければならない。この「磨作鏡」という表現にはちゃんとした道理が確かにあるのだ。その言葉には眼前の事実が絶対の真実としてそのようにあるという現成公案の道理が貫徹しているのであって、決して虚妄なつくりごとやこじつけであるはずがない。「磨塼作鏡」においては、塼がたとえ塼であっても、また鏡がたとえ鏡であっても、われわれが問題としなければならないのは実は「磨く」という行為そのものであって、「磨く」ことの道理を力の限り参究するならば、そこにはたくさんの多様な手本があることを知らなければならない。だから、浅く狭い特定の見方で決めつけてはいけないのだ。たとえば、鏡と言っても、「古い鏡」(雪峰の用いた表現)もあれば「明るい鏡」(六祖の用いた表現)もあるけれども、いずれにせよ磨塼によって得た作鏡なのだ。もし、いろいろな鏡が磨塼によって来るということを知らないならば、仏祖の言葉もなかっただろうし、仏祖の説法もなかったであろう。また仏祖がものを言うところを見聞することもなかっただろう。
馬祖が言った。「磨塼という行為それ自体が作鏡そのものの表現なのですから、塼を磨いて、その結果あらためて塼から完成した鏡ができるということでは決してありませんね。」
まったく磨塼は磨塼で絶対であって、他のどんな力量も借りないでそれに徹底している。だから磨塼は磨塼として独立自足していてそれ以外の何事も、つまり成鏡も必要としていないし、その余地もない。さらに言うなら磨塼のあるところには成鏡がすでに成就している。成鏡は成鏡そのものなのだが、この二つの事柄の間には(空間的にも時間的にも)いささかのずれもない。磨塼がそのまま成鏡であることを「すみやか」というのだ。
南嶽が言った。「(おまえの言うとおりだ。磨塼はどこまでも磨塼のままでよく、成鏡を待つ必要がないのと同じように、)坐禅はどこまでも坐禅のままでよい。あらためて作仏を待つ必要はない。坐禅それ自体が作仏に他ならないのであるから、そこにさらに作仏を加えるべき必要も余地も無いのだ」。
この言葉で明らかに知ることができよう。坐禅は坐禅だけで満足しており、独立無伴であり、絶対であって、作仏を待ってはじめて成立するものではないという道理があることを。それを逆に言うなら、作仏は作仏で絶対であり、坐禅によって得られるというようなものではない。従って、作仏は坐禅とは関わりがないという趣旨がここで明らかに打ち出されている。
馬祖が言った。「如何なるものも、そのままで真実そのものなのですね。」
これを南嶽の言ったことに対する質問と解して、「それではどのようにすればいいのでしょうか?」と教えを請う単純な問いとしてはならないことに注意。だからこの文は「如何は即是なり」と読むべきである。この馬祖の言った言葉は、こちら=坐禅(磨塼)についてひたすら質問しているように見えるが、あちら=作仏(成鏡)もすなわち是であることについてもたずねているのだ。たとえて言うなら、自分の親友のそのまた親友に出会うようなものだ。つまり二人が別々というのではなくそこにはブッ続いているものがあるということだ。われ(=坐禅)に親友であるものはかれ(=作仏)にも親友である。だから、「如何即是」とは、坐禅(磨塼)と作仏(成鏡)が、一時(=同時、即時)に現れたときのことを指しているのだ。
以上で、私がここをどう読んだかは一応ご理解いただけると思いますが、残りの紙面で、ここに書かれていることのポイントをいくつか箇条書き的に考察することにします。
①「磨作鏡」を「(塼を磨いて)鏡と作(な)す」と読むと、塼を鏡に変えるという現実的にはあり得ない不可能、不合理な主張になりますが、ここで焦点が当たっているのは、塼とか鏡といった対象物の方ではなくて、「(塼を)磨く」という行為の方なのです。動詞の「磨」の後に、その行為の対象である塼が省略されて、「磨塼作鏡」ではなく「磨作鏡」となっているのはそのことを暗示しているように私には受け取れます。ですから、ここは、塼が鏡になるという物の変化の話ではなくて、磨くという行為(これは「修行」のメタファー)が、とりもなおさず作鏡(これは「成仏」のメタファー)になっているという行為の「二重作動」(ダブル・オペレーション オートポイエーシスという学問の用語で「何かをやっているのに、それとは別のことが同時にシステムとしては実現されていくこと」)の話なのです。道元禅師はそれこそが「見(現)成公案」、つまり、生ま生ましい(概念で加工される前の生の)事実=現生(げんなま)の真実であり、でたらめ(虚説)なことではないと言います。塼は凡夫を、鏡は仏を象徴的に表現しているのでしょうが、凡夫が仏になるということを、塼が鏡に変わる魔法使いのマジックのようなものとして理解してはいけないのです。塼はどこまでも塼ですし、鏡はどこまでも鏡であって、それ以外にはありえないし、そうであっていいと道元禅師は書いています。ここで問題とされているのは、そういう塼(凡夫)とか鏡(仏)といった死んだ名詞的概念のことではなく、磨塼(修行)とか作鏡(成仏)という生きた行(修行)の世界の話(「磨の道理」)なのです。行を行として正しく理解するには名詞的世界観から動詞的世界観に切り替えなくてはなりません。どんな鏡(「諸鏡」)も磨塼から来ていることを知らなければ、仏の説法を理解できていないということになります。仏の説法は釈尊が歩いたのと同じそういう修行の道(「仏祖の道」)へと導くためになされているからです。
②馬祖の「磨塼豈得成鏡耶」は「塼を磨いて、どうして鏡になるでしょうか?」という反語的否定表現ではなく、それとはまったく逆の「(師匠のおっしゃる通り)磨塼こそが成鏡でなくてなんでしょう」という肯定的断言と受け取らなくてはなりません。それは、磨塼がある時点でいつのまにか成鏡に変わるというような変化の話ではなく、磨塼はどこまでも徹底的に磨塼である(「磨塼の鉄漢」)こと自体が成鏡なのだということを言っているのです。
③そういう意味の馬祖の言葉「磨塼豈得成鏡耶」を、再び坐禅の話にもどして確証するのが南嶽の「坐禅豈得作仏耶」という言葉です。これも「坐禅しても仏になるだろうか、なるわけがない」と普通の読み方をしてはいけません。馬祖の言葉の磨塼が南嶽の言葉の坐禅に、得成鏡が得作仏に対応していることは明らかです。坐禅がそのうちに作仏に変わるという話ではなく、坐禅がどこまでも徹底的に坐禅であること、道元禅師の表現を借りれば、「坐禅の鉄漢」こそがとりもなおさず作仏であるので、坐禅と作仏が横並びになることはありません。『普勧坐禅儀』にも「作仏を図(はか)ること莫(なか)れ」というお示しがあります。坐禅は既にして作仏なのだから、今さらあらためて仏になろうとする必要はないということです。
④馬祖の「如何即是」も普通は「どうならばいいんですか?」という質問文として解釈されますが、ここでは「如何なるも即ち是なり」と平叙文として読んで、「いかなるものも作仏である」と理解するべきです。この問答の始めのところにわざわざ道元禅師は「江西大寂禅師(馬祖)、ちなみに南嶽大慧禅師に参学するに、密受心印よりこのかた、常に坐禅す。」と書き、この時の馬祖がすでに南岳の法をしっかりと受け継いでいるという前提に立っていることを明らかにしています。当然のこととして、馬祖は坐禅が同時に作仏であることはすでに充分わきまえているのですから、「どうあればいいのですか?」などという質問をするはずがありません。馬祖は「即心是仏」ということを説いた人として有名ですが、小川隆先生は『禅思想史講義』(春秋社)の中で、この言葉について「己が心、それこそが「仏」なのだ。その事実に気づいてみれば、いたるところ『仏』でないものはない。」と解説しておられます。道元禅師の場合は、坐禅が行じられているところではじめてそれが言えるという立場(「修証一等」)ですが、今読んでいる「如何即是」もそれと同じ線上で理解できると思います。これは、馬祖独特の言い方で、道元禅師の「現成公案」と同じく、坐禅という行為(こちら=「這頭」=如何)とそれが開く作仏の事態(あちら=「那頭」=即是)の同時性を表しているのです。『弁道話』の中には「もし人一時なりといふとも、三業に仏印を標し、三昧に端坐するとき、遍法界みな仏印となり、尽虚空ことごとくさとりとなる。」をはじめとして、この坐禅と作仏の同時現成(「一時の出現」)の様子がいくつも述べられています。