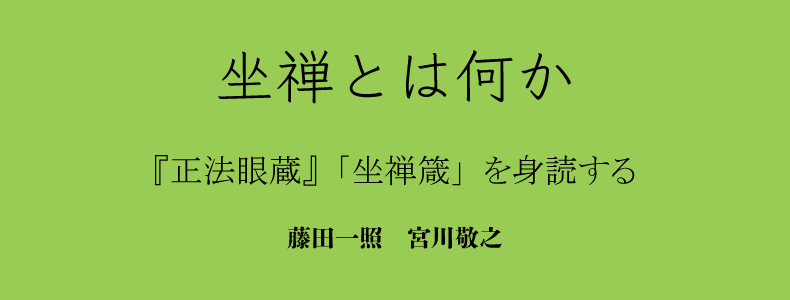コロナ時代の坐禅
【宮川敬之】身読コラボ⑦
<コロナ禍の世界で>
今日は2020年の5月14日ですが、新型コロナウイルスのパンデミックはいまだ収束の様相を見せていません。世界中の、お亡くなりになった方へのご冥福と、罹患されていらっしゃる方々の早期の回復とを、こころより願うばかりです。そして医療関係者の奮闘への感謝をはじめとして、物流、販売、ゴミの収集、インフラ保持の方々など、エッセンシャル・ワーカーの方々が毎日を支えて下さっていることに、深い敬意を表します。
いくつか有益な番組をテレビで見ることができました。ETV特集の『緊急対談 パンデミックが変える世界~歴史からなにを学ぶか~』(4月4日放送)、同『緊急対談 パンデミックが変える世界~世界の知性は何を語るか~』(4月16日放送)などです。それらのなかでも、『サピエンス全史』で世界的に有名になったイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏の発言が、深く印象に残っています(『パンデミックが変える世界 ユヴァル・ノア・ハラリとの60分』4月25日放送)。
私が印象に残ったのは、対話者である道傳愛子(どうでんあいこ)氏がハラリ氏にたずねた最後の質問における、ハラリ氏の発言です。道傳氏は、新型コロナウイルスの状況を毎朝目にするたびに、自身が非常な恐怖感に襲われていると告白し、どのようにハラリ氏はこの恐怖を克服しているのか、とたずねました。するとハラリ氏は、「瞑想をすることです」と即答したのです。そして、「わたしは毎朝2時間の瞑想を行っています。われわれは自分の心をいたわらなければなりません(to take care of our minds)」と続けたのでした。
ハラリ氏は、やはり世界的ベストセラーとなった『ホモ・デウス』の冒頭に、「重要なことを愛情をもって教えてくれた恩師、S・N・ゴエンカ(1924-2013)に」という献辞を書いています。ゴエンカ氏とは、上座部仏教における瞑想法であるヴィッパサナー瞑想を世界的に広めた、ミャンマー出身の在家仏教者のことです。ハラリ氏が、コロナ禍に直面する現在に、ゴエンカ氏より学んだヴィッパサナー瞑想を毎朝行って恐怖や不安に立ち向かっているということを、私は知ることができました。それこそが深い印象に残りました。というのも、今回のパンデミックに際して私なりに考えていたことに、ハラリ氏の言葉が重なったからです。私が考えていたのはつぎのようなことです。
<八大人覚>
周知のように今回の新型コロナウイルスとは、老若男女国籍を問わずだれもが感染し感染させる危険性をもち、しかも発症し重症化すれば、わずか2週間ほどで死亡してしまう場合もあるという厄介なウイルスです。このウイルスの感染症が日々世界中で拡大する様子は、仏教に言う世の「無常」のありさま(われわれはすべて、いつ訪れるかわからない死にさらされた存在であること)そのものに他ならない、と私は考えるようになりました。
もちろんパンデミック以前の世界においても、世の中のありようは無常でした。しかし私たちは、自らのそして他人の欲望をかきたて、他人と交わり、移動し、群れ、自分を忘れるようにすることで、この無常から目をそらし、向き合わないようにしてきました。けれどもパンデミック下の現在、だれもがいつでも感染し発症して、急速に死が訪れるという状況に、まったく自分ひとりで、隔離され、この不安に立ち向かわなければいけなくなったのです。私もまたこの蟄居の時間をすごしていますが、私はこれは、きわめて仏教的な時間なのではないかと思うようになってきました。つまり、単なる隔離や避難ではなく、むしろこの蟄居は、「無常」に対して向かい合う唯一の方法なのではないか、そしてそれこそは、釈尊と道元禅師とが、死期に臨んで遺された「八大人覚(はちだいにんがく)」という最期の教えに示された内容なのではないか、と思い至るようになったのです。「八大人覚」とは、「大人(だいにん 仏や菩薩などのこと)が心得るべき八つの項目」という意味で、次の項目を指します。
第一 少欲(しょうよく) 欲するところを少なくする
第二 知足(ちそく) 満足することを知る
第三 楽寂静(ぎょうじゃくじょう) 独りでいることを楽しむ
第四 勤精進(ごんしょうじん) 勤め励む
第五 不妄念(ふもうねん) 自分の思いに振り回されない
第六 修禅定(しゅぜんじょう)坐禅してこころをおちつける
第七 修智慧(しゅちえ) 状況を正確に見る
第八 不戯論(ふけろん) うわさ話に加わらない
この八大人覚は、釈尊の最期の説教とされる『仏垂般涅槃略説教誡経(ぶっしはつねはんりゃくせっきょうかいきょう)』(通称『遺経(ゆいきょう)』)というお経に描かれていて、また、道元禅師は、それを自身の最期の教えである『正法眼蔵』「八大人覚」巻に引用しました。八大人覚とは平たく言えば次のようなことです。修行者は、欲求を小さくし、頂いたものに感謝をして多く求めず、独りでいることを楽しみ、しかも怠惰に流れず、自分の思いに振り回されず、坐禅につとめてこころを穏やかに保ち、冷静に正確に状況判断を行って、根拠のないうわさ話には加わらない。そうした「大人」の生き方を見習って生きて行けという教えです。
今回のパンデミックで、無常が新型コロナウイルスというかたちをとって迫り、世界中の人々がそれぞれの家で蟄居せざるをえない状況下では、この教えは不可避の選択となりました。パンデミックに際して初めて、私は、八大人覚が、無常の猛威に対して私たちがとることのできる唯一の姿勢なのだということを思い知らされたのです。
ハラリ氏の言葉が私に響いたのは、まさに私がこうしたことを考えていた時でした。ハラリ氏が、パンデミックへの恐怖や不安に対抗して、自身が毎朝「瞑想し、自分の心をいたわ」っていると告白したことが、八大人覚こそ無常への対抗として私たちが行うべき生活のありようであるという私の考えに、重なったのです。
今回のパンデミックにおいて、私は、八大人覚と、その第六項目としてあげられている坐禅を、無常への対抗として考えていくことを、必要としています。この必要性は、「坐禅箴」の講読にも影響を与えずにはいられません。私の「坐禅箴」の講読は、これまでの読み方に加えて、これからはパンデミック=無常への対抗という意味においても読んでいくことになるでしょう。
<作仏と行仏>
では、今回の箇所を挙げます。
しるべし、学道のさだまれる参究には、坐禅辦道(ざぜんべんどう)するなり。その榜様(ぼうよう)の宗旨は、作仏(さぶつ)をもとめざる行仏(ぎょうぶつ)あり。行仏さらに作仏にあらざるがゆえに、公案見成(こうあんげんじょう)なり。身仏さらに作仏にあらず、籮籠打破(らろうたは)すれば、坐仏さらに作仏をさへず。正当恁麼(しょうとういんも)のとき、千古万古(せんこばんこ)、ともにもとよりほとけにいり、魔にいるちからあり、進歩退歩、したしく溝にみち、壡(たに)にみつ量あるなり。
この箇所を講読する場合に悩ましいのは、「○仏」というかたちで示されたことがら同士の関係性を、どうとるかという点です。順番からいえば、作仏、行仏、身仏、坐仏と、四種類のありようが示されていますが、これは大きく分けると、作仏とそれ以外に分かれるでしょう。なぜなら、作仏は「仏と作(な)る」という意味で、「坐禅箴」の後半にでてくるエピソード「南嶽磨磚(なんがくません)」の中心をなすことばですが、これは動詞と目的語の関係にある中国語の表現です。しかしそのほかは、ほぼ道元禅師のオリジナルの表現といってよく、その意味も、「行ずる仏」「身体としての仏(仏という身体)」「坐禅する仏」といったように、修飾語と名詞の関係が強く押し出されているからです。「作仏」は、ここでは、「行仏・身仏・坐仏」の意味にひっぱられて、「作(な)す仏」という、本来の中国語では決してありえないような、修飾語と名詞の意味あいを響かせて表現されています。これらの四種類の表現の位相が追求されなくてはなりません。
この四種類のありようを、これまで考えてきた思量・不思量・非思量にあてはめて考えてみます。思量・不思量・非思量は、私の解釈では、われわれの思考、仏のさとり、修行のありよう、という三つの側面を述べたものです。これはまた、「説・宗・行」とも「教・証・行」とも呼ばれた三側面ですが(『永平広録』巻八)、これにあてはめると、思量=作仏、不思量=身仏、非思量=行仏=坐仏という分類ができると思います。
作仏とは、「(私が)仏になる(目的をもつ)」あるいは「(目的として私が)なろうとする仏」という構造をもちます。要するに、私という主体が、仏という客体に接続しようとすることです。しかしこの構造には、仏のさとりの内容を、われわれの思考で理解する範囲にとどめてしまっているという問題があります。もし、仏のさとりがわれわれの思考をのりこえるものであれば、そこにわれわれの思考によって接続しようにも、接続することはできません(「不思量底如何が思量せん」)。道元禅師の考えでは、この接続できない理由とは、「私からの視点」「私の見る目的」という、固定された「私」があることによります。そのために、仏に接続するならば、固定され安定した「私」を揺り動かさなければならないわけです。この揺り動かしは、目的をめざして動くこと、いいかえれば、さとりをめざして修行することを否定することによって行われるというのが、道元禅師の考えです。つまり「作仏」は、「行仏=坐仏」によって、「私の視点」そのものを揺り動かし、「目的への修行」を、否定されなければなりません。「行仏」そのものは、すでに仏のさとりに接続されていると考えられますが、残念ながらそのありようは、「私の視点(意識)」から把捉されないので、非思量というしかないのです。私はそのように解釈したいと思います。前半を訳してみましょう。
しるべし、学道のさだまれる参究には、坐禅辦道(ざぜんべんどう)するなり。その榜様(ぼうよう)の宗旨は、作仏(さぶつ)をもとめざる行仏(ぎょうぶつ)あり。行仏さらに作仏にあらざるがゆえに、公案見成(こうあんげんじょう)なり。
注意せよ。仏道を修行する定まった方法とは、坐禅辦道なのである。その看板とするところは「作仏を求めない行仏=坐禅をせよ」という教えである。(吾我をはなれる)行仏の修行は、(吾我にまつわられた)作仏とは異なっているがゆえに、「仏のさとりとわれわれの思考とが接続できる場所」となるのだ。
実はここには、翻訳に当たってもうひとつ考えておくべきところがあります。それは、「公案見成」という意味についてです。見ということばは現ということばと通じているために、これは「公案現成」ということばと同義と考えます。周知のように道元禅師の著書である『正法眼蔵』劈頭の巻は「現成公案(按)」であり、「公案見成」の意味はこの巻における主張とつながっています。「公案見成」の構造は「現成公案(按)」巻の冒頭に出ていますので、番号をつけて挙げてみましょう。
1,諸法の仏法なる時節、すなはち迷悟あり、修行あり、生あり、死あり、諸仏あり、衆生あり。
2,万法ともにわれにあらざる時節、まどひなく、さとりなく、諸仏なく、衆生なく、生なく、滅なし。
3,仏道もとより豊倹より跳出せるゆえに、生滅あり、迷悟あり、生仏あり。しかもかくのごとくなりといへども、花は愛惜にちり、草は棄嫌におふるのみなり。
この「現成公案(按)」における構造は、「坐禅箴」における思量・不思量・非思量の三肢構造と重なるものであると私は解釈します。すなわち1=思量、2=不思量、3=非思量という対応が成り立つと考えられるのです。順番に検討してみると、1ではわれわれの思考のうちで「仏法とはこんなものだ」と考えている場合を指しています。そのときにやはり思考において、迷いも修行も生も死も諸仏も衆生も、このようなものだという予測をして考えているわけです。しかしこれは「私」という主体から見るという前提が外れていない状態です。2は、われわれの思考を超えた仏のさとりの状態から見た場合です。「私」という主体が無くなってしまい、「私」から見ているまよいもさとりも諸仏も衆生も生も滅も、認識することができません。3は、修行のありようであって、1と2の両者が、3において交わるとされます。1からは決して知覚することができない2の世界となぜ交わることができるのかといえば、それは「仏道もとより豊倹より跳出せる(仏道がもともと、豊かとか貧しいとかを跳び越えている)」からだといわれます。つまり、2から1への影響が浸透しているということです。この浸透が強い部分において仏道が行われる。それが3の示す所です。1の世界で煩悩に振り回されつつ、しかも修行する道があり、そこにおいて2へ接続していると考えられるということです。
この1~3のありようは、砂浜の海岸のありさまにたとえてみてもいいでしょう。1は砂浜であり、2は海です(このたとえは実は逆なのかもしれませんが)。3は1と2とが交わる波打ち際です。私たちは、思量と不思量とが接続する、長い長い波打ち際を歩いて行く、それが3であり、非思量であり、仏道であるということだと思います(だから仏道を行じることは、到着する果てもなく、またいつはじめてもいいのです)。こうしたありようの全体こそが「現成公案(按)」なのであり、「公案見成」であるといえます。それで私はこの箇所を、「仏のさとりとわれわれの思考とが接続できる場所」と訳しました。
<身仏と行仏>
残りの部分を挙げます。
身仏さらに作仏にあらず、籮籠打破(らろうたは)すれば、坐仏さらに作仏をさへず。正当恁麼(しょうとういんも)のとき、千古万古(せんこばんこ)、ともにもとよりほとけにいり、魔にいるちからあり、進歩退歩、したしく溝にみち、壡(たに)にみつ量あるなり。
身仏はもとより作仏とはならない。だが、(「吾我」という)竹籠を打ち壊すならば、坐仏において作仏を排除することはない。「まさにその場面」には、遙かな過去から続き、仏ばかりか魔性の者にもつながり、行く道も帰る道も、都市の溝から村落の谷まで溢れかえる、仏道の道が延びてゆくことになる。
前述に続いて、作仏=思量、身仏=不思量、行仏=坐仏=非思量としたときに、身仏と作仏とが一致しないのは、思量と不思量とが一致しないこととパラレルとなります。とはいえ、行仏=坐仏においては、身仏と作仏の両者が接続するのです。ただし「籮籠打破」することにおいて、という前提があります。籮籠とは竹籠のことですが、これは前述した「私の視点(吾我)」をたとえたものと見ることができます。「私の視点」を外したときに、身仏と作仏とが行仏=坐仏によって接続する。それを「正当恁麼時(まさにその場面)」と呼ぶのです。その「場面」とは、先ほどのたとえでいえば、延々と続く波打ち際のように、遙かな過去から現在まで、さらに未来へと続き、仏ばかりか魔性の者すらもつながり、行く道も帰る道も、都市の溝から村落の谷までと続く、仏道の道が延びてゆくことになる、と道元禅師は言うのです。なお、仏道が魔性の者にもつながるというのは奇妙に聞こえるかもしれませんが、それはたとえば歴代仏祖のうち第十三祖迦毘摩羅(かびもら)尊者が、もとは神通力を持った魔性の者とされていることなどの故事に因っていると考えられます(『景徳伝灯録』巻一)。魔性の者であっても仏道を行ずることはできるのです。また「溝にみち、壡(たに)にみつ」とは、「坐禅箴」奥書に、「仁治三(1242)年壬寅三月十八日、記興聖宝林寺/同四(1243)年癸卯十一月、在越州吉田県吉峰精舎示衆」とあり、京都から越前へと移転したまさにその時期に「坐禅箴」が語られていることが、反映していると思われます。
思量=作仏でも不思量=身仏でもない、非思量としての行仏=坐仏の追求、それこそが仏道である。これが今回の箇所の内容です。しかしなぜ道元禅師はこのような位相を主張しているのか、それを最後に考えておきましょう。
先回詳しく触れたとおり、この「坐禅箴」を記す一年前の仁治二(1241)年、道元禅師の下に帰投してきたのは、達磨宗を学んできた集団でした。達磨宗では黄檗希運(おうばくきうん)『伝心法要』などを重要な依拠文献としていました。『伝心法要』では、「一心による回収」と「初心晩学の修行としての坐禅」ということが主張されます。つまり、仏のさとりにわれわれは自動的に接続することができるのであって、初心者のための方便として坐禅があるにすぎない、という考えを奉じていたわけです。道元禅師は「坐禅箴」の先回の箇所で、坐禅が初心晩学の手段であるという主張を批判し、また今回の箇所では、「現成公案(按)」巻をふまえることで、われわれの思考が仏のさとりに接続することは不可能であって、実際の坐禅修行においてのみ、それに辛うじて接続できるのだという考えを示しました。そうした主張が達磨宗への意識のもとにあったことは確実です。このうえで道元禅師は、「作仏(さぶつ)をもとめざる行仏(ぎょうぶつ)あり」という宗旨の「榜様(ぼうよう)」すなわち看板を上げて、これこそが仏祖の坐禅辦道である、と宣言したのです。
道元禅師が「作仏」を批判するのは、行為を行う「私」という意識、目的をねらう「私」という意識がつきまとうからです。目的意識において行為することは、最短距離、最速度、最大効率をねらうことですが、それではうまくいかない。仏のさとり(自然のありよう)は、最短でも最速でも最大効率のものでもなく、そもそも「私」のためのものでもないからです。道元禅師の坐禅における目的意識の放棄は、現在のコロナパンデミック=無常に直面しているわれわれにこそ、深く受け取るべきありようだと思われるのです。
【藤田一照】身読コラボ⑦
私の最初の単著である『現代坐禅講義 只管打坐への道』(佼成出版社、角川ソフィア文庫)は次のようなパスカルの『パンセ』の中の一節を引用することから始まっています。坐禅についての本なのに、なぜパスカルが出てくるのか? といぶかしく思った人もいたようですが、逆にそのミスマッチ(?)が印象深くてよかったという声も聞いています。かなり大げさな表現になりますが、人類にとって坐禅が秘めている重要な意義について語るにはそれが格好の手がかりになるのはないかという私なりの目論見によるものでした。その一節とは次のようなものです。
「人間のさまざまな立ち騒ぎ、宮廷や戦争で身をさらす危険や苦労、そこから生ずるかくも多くの争いや、情念や、大胆でしばしばよこしまな企て等々について、ときたま考えたときに、わたしがよく言ったことは、人間の不幸というものは、みなただ一つのこと、すなわち、部屋の中に静かに休んでいられないことから起こるのだということである。」
ブレーズ・パスカル『パンセ』(前田陽一・由木康訳 中央公論社)
今、世界中で猛威をふるっている新型コロナウィルス感染症の拡大を抑えるために、私たちは外出自粛の要請を受け、望まない形で「ステイホーム(家で過ごすこと)」を強いられています。そういう状況が思いのほか長く続いている昨今、多くの人がここでパスカルが指摘している「部屋で静かに休んでいられない」自分に直面させられているのではないでしょうか? 私は、パスカルが洞察した人間の不幸の唯一の原因そのものを癒すのが坐禅ではないかという問題提起を『現代坐禅講義』のなかでしています。今回のパンデミック状況下におけるわれわれの振る舞いを見ていると、そこで行なった問題提起の意味をまた新たな文脈で考え直さなければならないと思いました。
この連載のはじめにおいて、巻名になっている「坐禅箴」という熟語は、「坐禅の病を治す箴」という意味だけでなく、人間の根本的な病を癒す「坐禅という箴」とも深読みできるのではないかと書きました。そして、坐禅がそのような癒しの箴としてその効能を十二分に発揮することができるためには、坐禅が坐禅として正しく行じられていなければならず、この『正法眼蔵 坐禅箴』はそのためにこそ書かれているということを強調しておきました。今こそ、部屋で静かに休んでいられない人類の根本的な病を癒す力を持つような坐禅が挙揚されなければなりません。現代人にとって坐禅は、もはや少数の人のための贅沢品ではなく、万人にとっての必需品になっていると思うからです。
われわれが部屋の中に静かに休んでいられないのは、そこでfeel at home(くつろぐこと、居心地がよいこと)ができないからです。それはなぜなのでしょう? 自分のいるところが心底自分の「ホーム(わが家、故郷)」だとはどうしても感じられないのです。ここではなく、どこか別のところに本当のホームがあって、今いるのは仮のホームでしかないというなんとなくの居心地の悪さを大なり小なり誰もが心のどこかで感じているのです。自分で自分に落ち着けず、現在に安住できない。そのせいで、そのうちじっとしていられなくなって部屋の外にさまよい出てしまいます。本来いるべき本宅を見失って、この仮宅からあの仮宅へと彷徨い続けているというのが、仏教の描く凡夫的あり方の一つです。流転輪廻というのはそういうことを言うのでしょう。
「ステイホーム」と言われてもそのホームがどのようなものであり、どこにあるのか、ステイホームがどういうことなのかを実はわれわれはよくわかっていないのではないでしょうか。「ステイホーム」と今、声高に叫ばれていることが意味しているのは、建物としての家の中に物理的にとどまっていろということなのですから、正確には「ステイ・イン・ザ・ハウス(蟄居する)」というべきです。たとえ肉体は「ステイ・イン・ザ・ホーム」していても、精神的には「ホームレス」であるのがわれわれだとすれば、「ステイホーム」ということは宗教的な課題として取り組まなければならないことでもあるのです。
坐禅のことを「帰家穏坐(きかおんざ)」と言うことがあります(たとえば、堂頭和尚示して曰く「世尊言わく、聞思猶お門外の処の如し、坐禅して直に乃ち帰家穏坐すべし。」 道元『宝慶記』)。これは、坐禅してそれからぼちぼちと家(自己の落ち着きどころ)に帰ろうとするということではなく、坐禅そのものが取りもなおさず(即)本当の家(存在の故郷)であり、それこそが真実安穏に落ち着くことができるところだということです。新型コロナウィルスによる感染症の広がりは結果的に、世界的規模でわれわれの社会が抱えているさまざまな問題を浮き彫りにしてくれました。これまでは場当たり的な処理でなんとか乗り切ってきたように見えていましたが、実はもはやそうした小手先の対処法ではすまないところに来ていることが多くの人の目に明らかになったのです。人間生活の再吟味、再構築が根本のところから考えられていかなければなりません。その一つの切り口が、「部屋の中で静かに休んでいられる、自己という存在の故郷(ホーム)を見出した人間に成熟する」ということだと私は考えています。われわれ一人一人が世界史の新たな転換期に立ち会っているという実感をヴィヴィッドに持ちつつ、そういう問題意識でこの『坐禅箴』を読んでいきたいと思います。
今回は
しるべし、学道のさだまれる参究には、坐禅辦道(ざぜんべんどう)するなり。
その榜様(ぼうよう)の宗旨は、作仏(さぶつ)をもとめざる行仏(ぎょうぶつ)あり。行仏さらに作仏にあらざるがゆえに、公案見成(こうあんげんじょう)なり。
身仏さらに作仏にあらず、
籮籠打破(らろうたは)すれば、坐仏さらに作仏をさへず。
正当恁麼(しょうとういんも)のとき、千古万古(せんこばんこ)、ともにもとよりほとけにいり、魔にいるちからあり、進歩退歩、したしく溝にみち、壡(たに)にみつ量あるなり。
という一節を身読していきます。
これからする解釈を元に、この一節を次のような現代文に私訳してみました。
次のことはよくよく心に命じておくべきだ。仏道を学ぶ上でどうしてもはずしてはならないこととして定まっている参究のありようがある。それは初心者であろうがベテランであろうがいやしくも修行者である限りは坐禅に力を尽くすということだ。
その坐禅を修行するうえで手本・よりどころとすべき根本の趣旨は、「仏に作(な)ることを求めないで仏を行ずる(=只管に打坐すること)」ということである。行仏すなわち坐禅を実践している姿はそれ自体で完結していて、それとは別にいまからあらためて仏に作(な)ろうと努力しているのではない。だからそこにはなにひとつ欠けたものがない真実の姿がそのまま現在(いま)のありようとして生き生きと立ち現れている(公案見成)のだ。
尽十方界真実人体の身としての仏を実際に行じているのが坐禅であって、そこには作仏というような余計なはからいがいまさら入り込む余地はまったくない。坐仏が原因で作仏が結果という前後二つに分かれた見方をしてはならないのだ。
しかし同時に、鳥や魚を捕まえ閉じ込めておく籮や籠のようにわれわれを束縛し自由を奪う囚われた考え方(二元論的考え方)を打ち破るなら、坐仏(=行仏=身仏=坐禅)が作仏をすこしも妨げない、坐仏が作仏そのものであるといっても少しも差し支えないのだ。
言葉や概念の束縛から離れて、まさにこのような自由無碍さが実現しているときには、大昔から今にいたるまで、いつでも坐禅には仏の世界にも魔の世界にも自由に入る力がそなわっている。また歩を進めることにも退くことにも、そしてあらゆる溝や谷に満ち渡るだけの大きさを持っている。
この一節の直前には、「しかあるに、近年おろかなる杜撰いはく、・・・」と「又一類の漢あり、・・・」という二つの段落があって、当時流布していた、坐禅についての誤った見解の代表的なものが二つ挙げられています。まず、坐禅を心理操作の手段と考えて、自分の気に入ったような気分、たとえば無念無想の心境になろうとする人たちのことが批判されます。次に、坐禅は初心晩学の者には必要であるが、一定のレベルに達した者には必要がないと考える人たちのことが批判されています。どちらのグループに対しても「祖道の荒蕪かなしむべし」とか「仏法の正命つたはれることおろそかなるによりて、恁麼道するなり」と、かなりキツイ言葉による指弾がなされています。いずれも、坐禅を目的に対する手段として、道具的連関(今はまだない何かを作り出し、手に入れるための技術・方法という枠組み)の中で考えているところに大きな問題があるわけです。そういう枠組みの中ですべてを考えている限りは、三界の法ではあっても、仏祖の法ではないというのが道元禅師の立場です。
それを受けて「しるべし!」と読む者の注意をあらためて喚起する呼びかけの後に、真実の修行は坐禅弁道以外にはないという力のこもった説示が続いています。この箇所に限らず、道元禅師が著作の中で「しるべし」と書かれるときには、そのあとに非常に重要な説示がなされるのが通例です。
「作仏をもとめざる行仏」というのは、坐禅によって成仏してやろうというような個人的な意図を持ち込んで坐ったのでは行仏、つまり坐禅にならないということです。「作仏」といえば、『普勧坐禅儀』の中に「莫図作仏(作仏を図(はか)ることなかれ)という一文があることを思い出さなければなりません。坐禅していること自体が仏になっている状態である以上、現在坐禅することによって、いつか未来に仏になろうと「図(はか)る」のはいかにも余分なことです。それがたとえ仏になろうとする(作仏をもとめる)というような高尚なことであっても、何かを目的として追求すれば、意思・意欲が働きますから、必ず身心は緊張します。本当にくつろいでいることができる(=部屋で静かに休んでいられる)のは、今起きていることを無条件に受け容れているときだけです。「心意識の運転を停(や)め、念想観の測量(しきりょう)を止(や)めて」(『普勧坐禅儀』)、正身端坐している坐禅には、もはや自我意識に基づく「求める」、「図る」という営みの余地はありません。身心一如であるからには、心が何かを追いかけたり、何かから逃げたりしているときには、身体は正身端坐(「正身端坐すべし。ひだりへそばたち、みぎへかたぶき、まへにくぐまり、うしろへあふのくことなかれ。かならず耳と肩と対し、鼻と臍と対すべし。」 『正法眼蔵 坐禅儀』)を実現することはできません。立身中正の正身端坐で坐している坐禅の状態がとりもなおさず、仏を行じていること(行仏)になっているのです。そしてそれが同時に、自分の勝手な思いつきの世界(「公案」に対する「私案」)ではなく、思い以上の絶対の真実(「公案」)が現に成就していること(公案見成)でもあるのです。
作仏を求めて坐禅をするのは個人の仕事にはなっても、仏を行じていること(行仏)にはならず、坐禅は「作仏を求めざる行仏」でなければならないことがここではっきり述べられているわけです。それが、道を学ぶ上での参究のあり方の本筋としてこれ以外にはないとされている坐禅辨道のポイントです。この箇所の前の部分で「おろかなる杜撰」や「一類の漢」と呼ばれた人たちは、その「榜様の宗旨」をまったく理解できていないがゆえに批判されることになったのです。彼らは坐禅によって作仏することを求めているために、本来「不染汚(ふぜんな)の行」であるべき坐禅を個人的な意図や好みによって染汚し、仏行ではなく個人業にしてしまっているからです。
「身仏」というのは非常に興味深い表現です。坐禅のときには、脚を結跏趺坐に組み、手を法界定印に合わせ、口を閉じ、思いを手放し(「三業(身・口・意)に仏印を標し」『辨道話』)ていますから、身体を自分勝手に操作し、動かすことはできなくなっています。私はそれを「凡夫が坐禅に磔(はりつけ)になっている」、あるいは「仏印によって凡夫性が封印されている」というような表現で話すことがあります。普段は身体の働きのおかげではじめて立ち現われることができている自我意識が、あたかも主人であるかのように身体を使いまわしていますが、坐禅の時には自我意識が磔にされ、封印されている結果、身体全体が生き生きと全面的に働くようになります(意識が受動的になればなるほど、身体は能動的になる)。その身体本来の様子を「身仏」、つまり、「身としての(あるいは、身という)仏」と呼んでいるのではないでしょうか。身=仏を実践するのが坐禅だったのです。ここで言う「身」はもちろん、私という個人の持ち物として妄想されている観念の身体ではなく、「尽十方界真実人体」として万法に証せられて現に生きている真実のからだのことですから、身仏はもう行き着くところへ行き着いた仏です。さらにそれ以上の仏になろうとすること(作仏)ではありません。
籮籠というのは、『普勧坐禅儀』にも「籮籠未到」という表現で出てきますが、あみとかごのことで、われわれを捕まえて身動きの取れない状態にしてしまうあらゆる種類のとらわれのことを指します。ここでは、坐禅はそういう籮籠が打破されていること、籮籠が未到であることだと言われています。ちなみに、「参禅は心身脱落なり」と言われるときの「身心脱落」というのは、身心を束縛していた籮籠が打破され、籮籠が未到の状態になることを指し、それをひっくり返した「脱落身心」というのは、籮籠が打破されて籮籠未到で生き生きと自由自在に働いている身心のことを言うのです。「坐仏さらに作仏をさへず」というのは、籮籠打破の坐禅が現成しているときには、仏を坐っているのであり、それがそのまま作仏にもなっている、つまり成仏が実現しているということです。坐禅は坐仏であり同時に作仏なのです。
「正当恁麼のとき」というのは、禅門の常套句で、「真実は以上のようなことであるから要するに」とこれまでの議論をまとめる際に用いられます。その上で、「千古万古、ともにもとよりほとけにいり、魔にいるちからあり、進歩退歩、したしく溝にみち、壡にみつ量あるなり。」と、坐禅の自由無碍さ、「道本円通 宗乗自在」性(『普勧坐禅儀』)を称揚して、「薬山非思量の話」の参究を締めくくっています。そして、次には「南嶽磨塼の話」の参究が始まります。