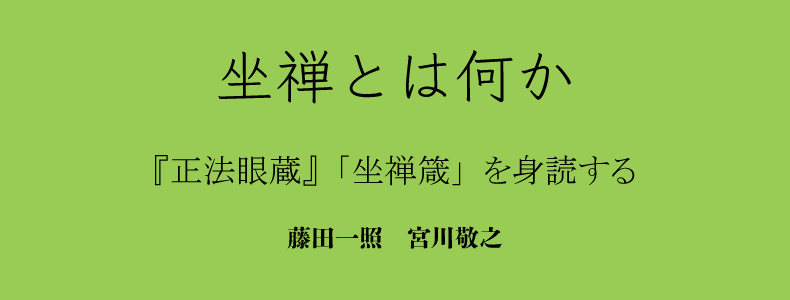坐禅を坐禅なりとしれるすくなし
【宮川敬之】身読コラボ⑮
仏祖の光明に照臨せらるるといふは、この坐禅を功夫参究するなり。おろかなるともがらは、仏光明をあやまりて、日月の光明のごとく、珠火の光耀のごとくあらんずる、とおもふ。日月の光耀は、わづかにこれ六道輪廻の業相なり、さらに仏光明に比すべからず。仏光明といふは、一句を受持聴聞し、一法を保任護持し、坐禅を単伝するなり。光明にてらさるるにおよばざれば、この保任なし、この信受なきなり。
仏祖の光明が輝き、それに私たちが照らされるということは、このような坐禅を修行し、参究することそのことである。愚かな連中は、仏の光明をまちがって理解して、太陽や月が光り照らすようだろうとか、あるいは、パッと輝く火の光のようだろう、と考えてしまう。しかし、太陽や月の輝き(とわれわれの感覚でとらえる光明)は、ただ六道輪廻するものたちが、それぞれのカルマのありさまによって見ているすがたであり、仏の光明とは比較にもならないのだ。仏の光明とは、仏のことば一つに出会って、それを引き受け、聴き浸る、ということであり、仏のおしえ一つに出会って、それを引き受け、聴き浸る、ということであって、すなわちそれは、(自受用三昧の)坐禅を単伝することなのだ。仏の光明に照らされたことがないものには、こうした(仏のことばやおしえに)保たれること(が光明であること)も、信じ引き受けること(が光明であること)も、わからないのである。
しかあればすなはち、古来なりといへども、坐禅を坐禅なりとしれるすくなし。いま現在大宋国の諸山に、甲刹の主人とあるもの、坐禅をしらず、学せざるおほし。あきらめしれるありといへども、すくなし。諸寺にもとより坐禅の時節さだまれり。住持より諸僧、ともに坐禅するを本分の事とせり。学者を勧誘するにも、坐禅をすすむ。しかあれども、しれる住持人はまれなり。このゆえに、古来より近代にいたるまで、坐禅銘を記せる老宿一両位あり、坐禅儀を撰せる老宿一両位あり、坐禅箴を記せる老宿一両位あるなかに、坐禅銘、ともにとるべきところなし、坐禅儀、いまだその行履にくらし。坐禅をしらず、坐禅を単伝せざるともがらの記せるところなり。景徳伝燈録にある坐禅箴、および嘉泰普燈録にあるところの坐禅銘等なり。
そのように、(仏のことばやおしえに保たれることが光明であり坐禅であり、信じ引き受けることが光明であり坐禅であるのであって)、昔の人々であっても、こうした坐禅が坐禅なのだとわきまえている人は、少ないのである。実際、現在も、大宋国の諸山でも、一箇寺の住職だという人にしろ、そのような坐禅を知らず、学ばないものが多い。しっかりとわきまえている者がいるにしても、その数は少ない。たしかに、修行者に勧める修行として、坐禅を勧めてはいる。けれども、坐禅(が仏のことばとおしえの受持であり、信受であり、光明そのものであること)を、知っている住職は稀なのだ。このために、昔から現在まで、「坐禅箴(坐禅のすすめ)」などを記した老僧はちらほらいたが、(「坐禅箴」も)「坐禅銘」もともにとるべきところもなく、「坐禅儀」であっても、実践する際の検討が足りない。それは坐禅のありようを知らず、(自受用三昧の)坐禅を、(自らの身心において)単伝していない連中が記したものである(のは明らかだ)。『景徳伝灯録』にある「坐禅箴」や、『嘉泰普灯録』にある坐禅銘などはみなこうしたものだ。
あはれむべし、十方の叢林に経歴して一生をすごすといへども、一坐の功夫あらざることを。打坐すでになんぢにあらず、功夫さらにおのれと相見せざることを。これ坐禅の、おのが身心をきらふにあらず、真箇の功夫をこころざさず、倉卒に迷酔せるによりてなり。かれらが所集は、ただ還源返本の様子なり、いたづらに息慮凝寂の経営なり。観練薫修の階級におよばず、十地・等覚の見解におよばず、いかでか仏仏祖祖の坐禅を単伝せん。宋朝の録者、あやまりて録せるなり、晩学、すててみるべからず。
残念なことだ。さまざまな修行道場を遍歴して一生をすごしたと言われている者でも、一回の坐禅に対しての修行参究が足りないとは。また、坐禅に打ち込んでも、「仏祖の行」とならず、修行参究しても(自受用三昧という)「自己」へと出会うことになっていないとは。そうした修行参究が足りないのは、自分の身心が坐禅に向いていないからではなく、真実の仏法を現成する修行を志さず、短兵急な考えに酔い、迷ってしまっているからだ。短兵急な考えによって、坐禅とは、ただ、「本来の仏性に戻ること〔還源返本〕」だけだと考えたり、むやみに、「思考を止めて何も考えない〔息慮凝寂〕」ことだと努力してみたりするのである。そのような考えでは、「観練薫修」といった(坐禅を修行の手段と考える)段階にもおよばず、「十地」や「等覚」といった(菩薩の)見解にもおよばない。どうして仏が仏に授け、祖師が祖師へと授けた坐禅を単伝できようか。宋朝の記録者は、まちがって記録したとしか考えられない。後進の者たちよ、こういうものは捨ててしまいかえりみてはならない。
〈「仏祖の光明」〉
今回の箇所で考察するのは、「仏祖の光明」とはなにか、ということです。まず、「仏祖「の」光明」という表現において、「の」ということばをどう受け取るかを、はっきりさせる必要があります。「の」を、仏祖に付帯する属性の意味ととると、「仏祖の光明」とは、仏祖が自身に付帯させている光明、という意味になります。一方、「の」を、仏祖にとってという意味にとると、「仏祖の光明」とは、仏祖にとって見えている光明なるもの、という意味になります。要するに、「の」は、仏祖の属性をさすと取るべきなのか、その知覚(視覚)をさすと取るべきなのか、という問題です。どちらをとるべきでしょうか。仏祖の属性をさす解釈もありえるでしょうが、私は、その知覚をさすと取りたいと思います。「仏祖の光明」とは、仏祖にとって見えている光明なるもの、という意味だと考えます。
では、仏祖にとって見えている光明なるものとは、どのような視覚なのでしょうか。ここでは、「太陽や月が光り照らすようだろうとか、あるいは、パッと輝く火の光のようだろう〔日月の光明のごとく、珠火の光耀のごとくあらんずる〕」という知覚のありようでは「ない」と断言されています。「仏祖の光明」について集中的に論じられている『正法眼蔵』「光明」巻においても、「赤・白・青・黄にして火光・水光のごとく、珠のごとく、龍天の光のごとく、日月の光のごとくなるべし」と考えるのは「文字づらばかりを追う学者〔文字の法師〕」であり、「自分を禅師と僭称する者のことば〔禅師胡乱の説〕」であるから、聴いてはならない、と注意されています。なぜそのような知覚としては「ならない」のでしょうか。同じく「光明」巻に次のように言われていることが、非常に重要です。
いはゆる仏祖の光明は、尽十方界なり、尽仏尽祖なり、唯仏与仏なり、仏光なり、光仏なり。仏祖は仏祖を光明とせり、この光明を修証して、作仏し、坐仏し、証仏す。
「仏祖の光明」と呼ばれるものは、「あらゆるすべての世界〔尽十方界〕」そのものであり、「あらゆるすべての仏と祖師〔尽仏尽祖〕」そのものであり、「仏と仏とのみ知り合う修行〔唯仏与仏〕」であって、それが仏の光であり、光の仏なのである。仏祖は(それまでの)仏祖の修行そのものを光明とするのであり、その光明を自ら修行し、証明することとして、修行する仏となり、坐禅する仏となり、悟りを修行する仏となるのだ。
自己の光明を見聞するは、値仏の証験なり、見仏の証験なり。尽十方界は是自己なり、是自己は尽十方界なり。
自己の光明を見聞するとは、実際に悟って仏に会うことなのであり、実際に悟って仏に対面することなのである。それは「あらゆるすべての世界」を「すべて自己である」とすることであり、また、「すべて自己である」ことを「あらゆるすべての世界」とすることなのである。
ここで言われているのは、仏祖の光明には三つの側面があるということです。まずは「尽十方界」であり、そして「自己」であり、さらに「仏に会う(値仏、見仏)」ことです。まず、光明が、それを見ている自分を含む「尽十方界」そのものであるということは、通常の知覚とは異なって、見る主体と見られる客体との距離がとれないということです。そもそも、青・黄・赤・白といった色を見るのも(色自体が光の波長であるので、色を見ることがそのまま光を見ることでしょう)、また、太陽や月、なにかの光を知覚するのも、見る主体と見られる客体とのあいだに距離をもち、別の存在であることが前提となっています。ところが、「尽十方界」という、見る主体と見られる客体とが独立しておらず、全体とひとつながりであり、全体のなかに入っている状態ならば、それを知覚することは、もはや通常の知覚ではできないことです。この意味で仏祖が知覚する光明は、通常の光明とは違います。しかし、これはむしろ逆にいうべきなのかもしれません。すべてがつながり、私たちもその内部にいて、主体と客体との距離がとれないことが本来であって、逆に主体と客体とが距離が取れているように見える知覚のほうが、私たちの視点の一時的な条件(すなわちカルマ)によって、見えているように知覚されているだけのことだ、と考えるべきなのです。このことはちょうど『正法眼蔵』「現成公按」巻に、つぎのように言われていることと同じです。
塵中・格外、おほく様子を帯せりといへども、参学眼力のおよぶばかりを、見取・会取するなり。万法の家風をきかんには、方円とみゆるよりほかに、のこりの海徳・山徳おほくきはまりなく、よもの世界あることをしるべし。
塵にまみれた世界にいるのもいないのも、そこには数えきれない側面と性質とがあるのである。私たちは、自分の参究と修行の眼が見ることのできる力の範囲で、ものを見、掴むことができるだけなのだ。万法の現実を聞くときに、円く、あるいは四角く見えたりする以上に、多くの海のありさま、山のありさまが、そのほかにあると知るべきなのだ。
いま見えているありさま以外に、同じ状態を示す他のありさまがあると知ること。自分の知覚が、限られているものであるとわきまえ、自分を含んでいるつながりそのものに対して知覚を開こうとすること。これが「尽十方界」という状況への知覚だと考えられます。そしてそれが、「仏に会う」ことであり、「自己」なのだと、「光明」巻では示しているのです。これらは、特定の対象に対して、見たり、聞いたり、出会うことではもはやありません。むしろそれは、ひとつながりの内部において修行を行うことによって、主体と対象とが分離していない仏の知覚のありようを、自分の身心で表現することです。その修行の実践において、果てのない無限の仏行に浸されます。それはやはり「現成公按」巻に、つぎのように言われていることと対応します。
人もし仏道を修証するに、得一法通一法なり、遇一行修一行なり。これにところあり、みち通達せるによりて、しらるるきはの、しるからざるは、このしることの、仏法の究尽と同生し同参するゆゑに、しかあるなり。
得処かならず自己の知見となりて、慮知にしられんずるとならふことなかれ。証究すみやかに現成すといへども、密有かならずしも見成にあらず。見成これ何必なり。
人が仏道において修行―さとりに従事しているときに、その人は一つのダルマを実現し、そのダルマに通暁しているのである。さらに、その人が一つの修行に出会ったならば、その人は(十分に)その修行を修行するのである。(このために)場所と道があるのだ。知られる境界は、はっきりとはわからない。そのわからない理由とは、(限定されて現れる)知られたものは、仏法に完全に通暁して、それと同時に生まれ、修行するものであるからだ。われわれが得たものが、われわれによって知覚され、われわれの分別する心でもって知られると考えるべきではない。完全な悟りはすぐさま実現するが、その親密さは、必ずしも、目に見えるものとしてかたちをなすのではない。(事実として)見方は固定したなにかではないのだ。
「仏祖の光明」という、仏祖にとって知覚される光明が、通常に知覚されるような対象としての光や輝きではなく、すでにひとつながりの内部において修行を行うことであるとすることは、このようにして理解できます。そこで改めて、今回の箇所で「仏祖の光明」がどのように語られているかを見てみましょう。
仏祖の光明が輝き、それに私たちが照らされるということは、このような坐禅を修行し、参究することそのことである〔仏祖の光明に照臨せらるるといふは、この坐禅を功夫参究するなり〕。
仏の光明とは、仏のことば一つに出会って、それを引き受け、聴き浸る、ということであり、仏のおしえ一つに出会って、それを引き受け、聴き浸る、ということであって、すなわちそれは、(自受用三昧の)坐禅を単伝することなのだ〔仏光明といふは、一句を受持聴聞し、一法を保任護持し、坐禅を単伝するなり〕。
仏祖の知覚が、すぐさま、ひとつながりの内部での修行へと転化していくことを、ここに見ることができます。これは、道元禅師の「坐禅箴」の最大の特徴といえるものであると思います。このありようは、かつて論じた「坐仏」という、「尽大地」とともに悟りつつ坐り続けるブッダのありよう、それを私たちも引き受けることで、坐仏と「出会い」、「自己」と出会うというありようと、同じです。つまり、「仏祖の光明」とは「坐仏」を行じることと同じであると言えるということです。
〈他の「坐禅箴」「坐禅銘」との違い〉
今回の箇所ではまた、『景徳伝灯録』や『嘉泰普灯録』などに載る他の「坐禅箴」「坐禅銘」について批判がなされています。これらがなぜ批判されるべきなのかを考えておく必要があります。
道元禅師は、特定の坐禅箴を名指しで批判してはいないのですが、書籍を特定しているので、ある程度絞り込むことができます。石井修道師は「『坐禅箴』考」(『駒澤大学禅研究所年報』第八号 一九九七)において、道元禅師の批判の相手を想定し、列挙されました。石井師が挙げているのは以下のものです。
①『景徳伝灯録』巻三十所収『杭州五雲和尚坐禅箴』(『国訳一切経』和漢撰述部史伝部十五476頁)
②『嘉泰普灯録』巻三十所収『龍門仏眼遠禅師坐禅銘』(『卍続蔵経』一三七巻427頁下)
③『嘉泰普灯録』巻三十所収『上封仏心禅師坐禅儀』(同上431頁上)
④『禅門諸祖師偈頌』上巻上所収『察禅師坐禅銘』(『卍続蔵経』一一六巻919頁下)
⑤『禅門諸祖師偈頌』上巻下所収『天台大静禅師坐禅銘』(同上944頁下~945頁上)
詳細の検討は石井論文をあたってもらいたいのですが(論文検索エンジンciniiでかんたんに検索とダウンロードが可能です)、ここではなぜ道元禅師がこれらの「坐禅箴」や「坐禅銘」を批判したかという、私の考えだけ述べておきます。
私の見る所、これらの「坐禅箴」「坐禅銘」においては、道元禅師が強調する「坐仏」あるいは「仏祖の光明」の考えが述べられておらず、その点が批判されていると思うのです。石井師も言われるように、道元禅師の坐禅観とは非常に独特なもので、前節で見たように、「仏祖の光明」においても、「坐仏」においても、「尽十方界」(あるいは「尽大地」)と「自己」と「仏祖に会う」ことが強調されています。そのような強調がなされる「坐禅箴」や「坐禅銘」は、『景徳伝灯録』にも『嘉泰普灯録』にも見ることができません。その意味で、道元禅師の坐禅観は、中国仏教の伝統からも独立しており、独特なものであるのです。
実は、道元禅師が最も重要で史上最高の「坐禅箴」と絶賛する宏智正覚の「坐禅箴」ですら、道元禅師の言われるような側面を十分に満たしたものではありません。後で見ることになりますが、道元禅師は、宏智「坐禅箴」を解釈する際に、かなり無理をして、自分の「坐仏」や「光明」の考えにあうように解釈しなおしてしまいます。
道元禅師が言われる「坐仏」では「尽大地」、「光明」では「尽十方界」が強調されていました。これは、主体と客体が分離しておらず、ひとつながりのありようを示していることばでした(奥村正博老師は「相依生起interdependent origination」と言われます)。さらにこれが「自己」と呼ばれます。これは一見、たとえば①ではつぎのように言われていることと、近いように見えます。
吾、強いて説くと雖も、爰(ここ)に聖言に符(かな)えり。聖言とは何ぞや。重ねて宣べんことを仮らんと要す。「動にあらず禅にあらざるは是れ無生禅なり」〈『金剛三昧経』大正蔵九〉。又た云く、「若し諸々の三昧を学せば、是れ動にして坐禅にあらず。心は境界に随って流る、云何が名づけて定と為さんや」〈偽作『法句経』大正蔵八五〉。故に知りぬ、歴代の祖は、唯だ此の一心を伝えるのみ(石井一九九七 41頁下 ただし〈〉は引用者付記)。
ここで語られている「一心」とは、仏の境界における、主体客体の区別を超えたひとつながりのありようであり、道元禅師が「尽十方界」や「自己」と呼んでいるものと近いように思われます。しかし、重要なのは、こうした状態から、そこにとどまらずに行へと返るそのありさまが、ここには欠けているという点です。道元禅師が「坐仏」や「光明」を論じる際に、くりかえし強調するのは、私たちの身心で行う修行なのであり、それが「仏と会う」ということがらです。道元禅師が、安定した寂常無為の様子ではなく、一種の往復運動を強調するからこそ、この①のようなありようは「坐禅箴」として否定しなければならなかったと私は解釈します。道元禅師が強調するのは、一方では私たちの身心を忘れて仏の境界へと向かうことですが、さらにもう一方で、仏の境界からも離れて、私たちの身心の行へと返るという往復運動であると思います。その絶えざる往復の動きこそが、「身心脱落」であると考えられていると私は解釈します。
【藤田一照】身読コラボ⑮
『正法眼蔵』「坐禅箴」の巻はその巻名が示しているように、われわれが坐禅に取り組むときに陥りがちな坐禅の偏向、歪曲という病いに対する適切な処方を示すことがねらいとして書かれています。「坐禅箴」の「箴」は鍼治療で道具として使う「箴(いしばり)」のことです。また「箴」の字は「箴言」という熟語に使われているように「戒(いまし)め」という意味もありますから、坐禅がそのような偏向や歪曲に陥らぬように、坐禅は本来どういうものでなければならないかと道元禅師が弟子たちに戒めている巻であるということもできます。
道元禅師は坐禅について語るときには、しばしば「坐禅は習禅にはあらず。安楽の法門なり」とか「坐禅は三界の法にあらず、仏祖の法なり」という具合に「坐禅はAにはあらず、Bなり」という言い方をされます。これらの言葉は、人々が本来Bであるべき坐禅をAとして誤解、曲解し、正しい坐禅の姿を見失っている場合が多いという現実に対してなされた「箴」として理解されるべきでしょう。坐禅はAではなくて必ずBであるべきだということを強調する、英語で書けばZazen is not A but Bとなる「強調構文」だからです。
その「箴」の拠り所、基準として、取り上げられているのが
(一)薬山の非思量の話
(二)南嶽の磨塼の話
(三)宏智の坐禅箴
の三つです。これらの話はいわば、坐禅の病に対する三つの「箴」ということになります。
前回までのところで、道元禅師による(一)と(二)の話に対する独特で詳細な拈提(ねんてい 古則公案を提起して修行者に示すこと。またそれを工夫参究すること)を読み解いてきました。巻名が「坐禅箴」とされていることから見て、(一)と(二)の話の意味を深く理解することを通して、宏智禅師の坐禅箴を高く宣揚することをねらっているように思われます。しかし、その後に自らの手になる道元禅師自身の坐禅箴を置いていることからすれば、宏智禅師の坐禅箴を範にしているとはいえ、さらにまだひと鍬掘り下げるべきところが宏智の坐禅箴にはあると感じられていたに違いありません。それがどのようなことであったのかを読み取っていくことが、われわれ読む者に課せられた課題となります。
さて、今回読む箇所は、(一)薬山の非思量の話と(二)南嶽の磨塼の話の拈提をいちおう終えて、次の(三)宏智の坐禅箴へと論を進めるにあたっての「つなぎ」となるようなパートになっています。便宜的に三段に分けて、身読していくことにします。では、いつものように原文を何度か音読してみましょう。
仏祖の光明に照臨せらるるといふは、この坐禅を功夫参究するなり。おろかなるともがらは、仏光明をあやまりて、日月の光明のごとく、珠火の光耀のごとくあらんずる、とおもふ。日月の光耀は、わづかにこれ六道輪廻の業相なり、さらに仏光明に比すべからず。仏光明といふは、一句を受持聴聞し、一法を保任護持し、坐禅を単伝するなり。光明にてらさるるにおよばざれば、この保任なし、この信受なきなり。
この段には内容的にさほど難しいことは書かれていませんので、私の口語訳をまず挙げておきます。
仏祖の光明に照らされるということは、この坐禅を功夫参究することである(なぜなら仏の教えとその恩恵によって初めて坐禅を正しく行ずることができるからだ)。それなのに愚かな連中は、仏の光明ということを誤って日月の光のようなもの、あるいは珠玉の輝きか炎の光のようなものだろうと思っている。しかし、そのような客観的対象物である日や月の光や輝きはたかだか「六道に輪廻する業のすがた」でしかないのであって、決して仏の光明に比べられるようなものではないのだ。仏の光明というのは、仏法の真実を端的に言い当てているような一句を聞いて信受し(受持聴聞)、そのような一法をしっかりと保ち護って(保任護持)、坐禅を単伝することだ。光明に照らされるのでなければそのような保任も信受もあり得ることではない。
私は宗教的な言説は主観を排して客観的な事実を記述しようとする科学的な言説とは性質の異なるものだと考えています。宗教的な言説は自分の向こう側にある客体についての話ではなく、「私は〜をこういうものとして受け取っている」という主体の側の受け取り方を問題にしているということです。誰にとっても妥当するような普遍的で客観的な事実が問題になっているのではなく、第一人称のこの私(実存)にとってどういう意味をになっているのかという主体的(主観的ではなく)、実存的真実の話なのです。
デンマークが生んだ実存主義思想の開拓者キルケゴール(1813~1855)は「私にとって真理であるような真理を発見することが必要なのだ。しかもその真理は、私がそのために生き、そのために死ねるような真理である」、「ヘーゲル哲学体系には全世界があり、絶対精神があるが、そこには一個の悩める実存としての人間的な生命はない」と言いました。彼によれば、真理には2種類あって、一つは「客観的真理」、もう一つは「主体的真理」です。客観的真理とは「私」に関係なく成立する真理です。一方、主体的真理とは「私」に直結する真理のことです。生きている魂としての「実存」にとっては主体的真理のほうがむしろ重要だというのが彼の立場です。私は仏教の教義も、キルケゴールが言う意味での「主体的真理」として受け取る必要があるのではないかと思っています。
ここの一段もそのようなものとして理解される必要があります。道元禅師においては、自分が今ここで「坐禅を功夫参究する」ことは、「仏祖の光明に照臨せらるる」ことであるとして実存的に受けとられているのです。三界の法ではなく、仏祖の法である坐禅に、いかなる因縁か心ならずもこの世で出逢うことができ、正師のもとでそれを親しく学ぶことができ、それを伝えられてこうして今行じることができているのは、仏祖の光明に照らされるという途方もないありがたいことなのだということが、喜びと感激を込めて書かれています。
難値難遇である仏法に遇うことが今生でできたという感動は、「無上甚深微妙の法は百千万劫にも遭い遇うこと難(かた)し。我今見聞し受持することを得たり。願わくは如来真実の義を解せん」という「開経偈」や、「人身得ること難し。仏法値(お)うこと希なり。今我等宿善(しゅくぜん)の助くるに依りて、已(すで)に受け難き人身を受けたるのみに非ず、遭い難き仏法に値(あ)い奉れり、生死の中の善生、最勝の生なるべし」という道元禅師の言葉によく表現されています。この段は、そういう宗教的心情を背景に読まれなければならないと思うのです。
「仏祖の光明」と聞いて、文字通りに「日月の光のような、あるいは珠玉の輝きか炎の光のような」目に見えるものを想定するのは「愚かな」ことだと道元禅師は一蹴します。われわれは自分の目や耳で確認できること(見聞覚知)を頼りにしがちです。それは意識の対象にすることができて、こちらの欲望にとって何らかの手応え感が感じられるからです。宗教の世界においても、特殊な神秘的体験を手に入れ、宗教的な陶酔や感激、達成感を求める「精神の物質主義」(チベット仏教の指導者チョギャム・トゥルンパが使った表現)がしばしば見受けられます。そういう欲求は人情としてはわかりますが、それはけっきょく自我意識が相手にできる「モノ」の世界に心を奪われ翻弄されることになります。それは、道元禅師の表現によれば「六道輪廻の業相」にすぎません。奇跡や奇瑞、神秘体験、超常的なこと、そういうものを追いかければますます輪廻のサイクルに巻き込まれるだけです。仏道修行者はそういうトラップ(罠)に引っかからず、落とし穴に落ちないように用心しなければなりません。
「一句を受持聴聞し、一法を保任護持し、坐禅を単伝する」(これが道元禅師にとっての修行の内実をなす)という主体的な行為の事実そのものが仏の光明に他ならないのです。こういう光明に照らされるという仏の恩恵があればこそ、坐禅することも、坐禅を信受することもできているのだという主体的受け取りの態度がここで表明されているのです。
では、次の段を音読してみましょう。
しかあればすなはち、古来なりといへども、坐禅を坐禅なりとしれるすくなし。いま現在大宋国の諸山に、甲刹の主人とあるもの、坐禅をしらず、学せざるおほし。あきらめしれるありといへども、すくなし。諸寺にもとより坐禅の時節さだまれり。住持より諸僧、ともに坐禅するを本分の事とせり。学者を勧誘するにも、坐禅をすすむ。しかあれども、しれる住持人はまれなり。このゆえに、古来より近代にいたるまで、坐禅銘を記せる老宿一両位あり、坐禅儀を撰せる老宿一両位あり、坐禅箴を記せる老宿一両位あるなかに、坐禅銘、ともにとるべきところなし、坐禅儀、いまだその行履にくらし。坐禅をしらず、坐禅を単伝せざるともがらの記せるところなり。景徳伝燈録にある坐禅箴、および嘉泰普燈録にあるところの坐禅銘等なり。
ここも内容的には難しいところはありませんから、次にあげる私の口語訳を参考にして読解してください。
このようであるから、昔からずっとみても坐禅を坐禅と知っている者はきわめて少ない。(『正法眼蔵 三昧王三昧』には「…たとひ打坐を仏法と体解すといふとも打坐を打坐としれるいまだあらず…」とある)現在、大宋国にあるもろもろの山で、名の通った大きな寺の住職となっている者であっても、坐禅を知らず、坐禅を学ばない者が多い。明らめ知っている者もいないではないが、その数は少ない。もちろん、それぞれの寺では、坐禅をする時間がちゃんと定められている(四時の坐禅 黄昏7PM 後夜3AM 早晨9AM 哺時4PM)。そして、住持をはじめとして僧たちにいたるまでみんながいっしょに坐禅をすることを本来なすべきつとめとしているし、修行者にも坐禅を勧める。しかし、坐禅をほんとうに知っている住持はまれなのである。したがって、昔から近年にいたるまでに、『坐禅銘』を書いた老宿(高僧)は一人二人いるし、『坐禅儀』を撰述した老宿も一人二人、『坐禅箴』を書いた老宿も一人二人いるのだが、どの『坐禅銘』もとりあげるに値しないし、どの『坐禅儀』も坐禅の様子に暗いものが書いたものだといわざるを得ない。たとえば『景徳伝燈録』にある『坐禅箴』や『嘉泰普燈録』にある『坐禅銘』といったものがそれにあたる。そういうものを書いた人たちは、諸方の叢林を行脚し経めぐって一生をすごしたにもかかわらず、一坐の坐禅を正しく功夫(打坐の努力)しなかったのだ。
「坐禅を坐禅なりとしれるすくなし」と、ここで道元禅師はたいへん厳しい批判を下します。箴の箴たるゆえんです。確かに人々は坐禅をしていることはしているが、それは坐禅の正しい理解に基づいた正しい坐禅ではないと言うのです。一言で言えば、みんなが坐禅と呼んでやってることは、坐禅ではない「習禅」なのです。ですから、当時坐禅の手引きとして使われていた『坐禅銘』(具体的には、仏眼清遠の『坐禅銘』(普灯録)、天台大静の『坐禅銘』(禅門諸祖偈頌)、同安常祭の『坐禅銘』(禅門諸祖偈頌)など)、『坐禅儀』(具体的には、仏心本歳の『坐禅儀』(普灯録)、長蘆宗賾の『坐禅儀』(禅苑清規)など)、『坐禅箴』(具体的には、五雲志逢の『坐禅箴』(伝灯録)など)は、坐禅についての書と銘打ってはいるものの、正伝の坐禅へのガイドとしては「ともにとるべきところなし」、「いまだその行履にくらし」なのです。それは、「坐禅をしらず、坐禅を単伝せざるともがらの記せるところなり」と坐禅を本当には知らない者が書いたものだからだとバッサリと切り捨てています。
道元禅師が宋より帰朝して先ず最初に撰述されたのが『普勧坐禅儀』ですが(『弁道話』に坐禅のやり方に関しては「すぎぬる嘉録のころ撰集せし普勧坐禅儀に依行すべし」と言われていること、及び帰朝が嘉録三年(1227年)の秋であったと伝えられていることなどから、一般に撰述のタイミングはその頃であったと推察されている)、それをどういう理由で書くことにしたのかを述べた永平寺収蔵の道元禅師親筆とされる『坐禅儀撰述由来書』という著述があります。それには、
教外別伝・正法眼蔵、吾朝、未だ嘗て聞くことを得ず。矧んや坐禅儀は、則ち今に伝わる無し。予、先の嘉禄中、宋土より本国に帰りしに、因みに参学の請有り、□□□□(撰坐禅儀か)と。已むことを獲ず赴いてこれを撰す。昔日、百丈禅師、連屋連牀を建て、能く少林の風を伝う。従前の葛藤□□(旧窠か)に同じからず。学者これを知って混乱すること勿れ。禅苑清規に曾て坐禅儀あり。百丈の古意に順ずと雖も、少しく頤師の新条を添う。所以に、略には多端の錯あり、広には昧没の失あり。言外の領覧を知らず、何人か達せざらんや。今乃ち、見聞の真訣を拾い、心表の稟受に代えんのみ。 (原漢文)
と書かれています。道元禅師は『禅苑清規』に収められている長蘆宗賾の『坐禅儀』には多くの錯誤と意味不明な点があるので、肯うことができず、自らの手で『普勧坐禅儀』を撰述し、百丈の真意を発揚しようとしたと言うのです。しかし、長蘆宗賾の『坐禅儀』と『普勧坐禅儀』を比べてみると、語句の上ではかなり類似したところが見られますから、『普勧坐禅儀』が長蘆宗賾の『坐禅儀』をベースにして、それに根本的な修正を加えたものだということが推測できます。実際、坐禅の具体的なやり方と坐禅の功徳について述べている『普勧坐禅儀』の中段の文章は長蘆宗賾の『坐禅儀』とほぼ同一と言っても過言ではありません。両者の違いはしたがって、『普勧坐禅儀』の前段と後段に見いだされることになります。その部分に含まれている思想は、この『正法眼蔵』坐禅箴のこれまでの(一)薬山の非思量の話と(二)南嶽の磨塼の話を吟味する中で展開されてきた議論を背景としていることは言うまでもありません。
坐禅そのものの本質、意義や修行者の心構えについては、長蘆宗賾の『坐禅儀』は道元禅師の立場とは根本的に異なっていました。一言で言えば、坐禅は修行の一方法、一手段に過ぎず、特殊な心境に到達することを目的とする「習禅」だったのです。一方、道元禅師の説く坐禅は、仏法の全体であり、仏道修行のすべてであるというものでした。ですから、当時流布していた『禅苑清規』の『坐禅儀』では、正伝の仏法に基づく坐禅の弘通に役立たないどころか、反って人々を間違った坐禅に導くことになるという判断から、やむにやまれぬ思いで自らが『普勧坐禅儀』を書かなければならないという決断に至ったのでした。
『普勧坐禅儀』が書かれたのが1227年ごろ、『正法眼蔵』坐禅箴が書かれたのが、1242年頃のことですから、この間の約15年、道元禅師はずっと、当時の人々の坐禅の理解がまったくの見当外れであることを重大な問題とされ、その是正に心を砕いてきたということです。前回読んだように「仏法つたはるるといふは、かならず坐仏のつたはるるなり。……仏法つたはれざるには、坐禅つたわれず、嫡嫡相承せるは、この坐禅の宗旨のみなり」というのが道元禅師の坐禅観なのですから、坐禅が正しく行じられていないということは仏法が正しく伝わっていないことを意味します。ですから、ここにあるようないかにも厳しい表現になるのは当然と言えます。
では第三段を音読してみましょう。
あはれむべし、十方の叢林に経歴して一生をすごすといへども、一坐の功夫あらざることを。打坐すでになんぢにあらず、功夫さらにおのれと相見せざることを。これ坐禅の、おのが身心をきらふにあらず、真箇の功夫をこころざさず、倉卒に迷酔せるによりてなり。かれらが所集は、ただ還源返本の様子なり、いたづらに息慮凝寂の経営なり。観練薫修の階級におよばず、十地・等覚の見解におよばず、いかでか仏仏祖祖の坐禅を単伝せん。宋朝の録者、あやまりて録せるなり、晩学、すててみるべからず。
ここでも、まず私の口語訳を挙げておきます。
まことになげかわしく気の毒なことに、彼らはあちらこちらの禅の道場を巡り歩いて一生を過ごしても、一坐の功夫もできていないのだ。そしてかれらの場合、自己本来の面目に親しむはずの打坐が、そういうものになっていないから、かれらの坐禅の努力はどこまでいっても自己本来の面目に出会うことがない。これもまたかわいそうなことである。そういうことになるのは、坐禅がかれらの身心を嫌って逃げていったからではなく、真実の功夫(修行)をしようと思わず、軽々しく、いい加減な態度で、自分の心理状態に陶酔しているからだ。かれらがそういう書物に書いていることといえば、ただ還源返本(げんげんへんぽん)(心を外に向かって流転させず内なる本源に返すこと)の様子であり、息慮凝寂の経営(心の働きをやめ精神を静寂・平静にすること)なのである。それはいずれも主観主義化・心理主義化した坐禅の偏向というべきである。そういう坐禅では天台の止観で言われている観禅(法相を観ずる)・練禅(諸穢を除くこと)・薫禅(種子を薫習する)・修禅(自在の境地を修得する)といった修行の階梯にもおよばないし、十地や等覚といった菩薩の最高位の見解にもおよぶところではない。そのようなことでは、どうして仏祖から仏祖へと正しく伝えられてきた坐禅を単伝したといえるだろうか。そのような連中の書いた坐禅についての著述を『景徳伝灯録』や『嘉泰普灯火録』などに収録したのは宋の編集者たちが誤ってしたことなのだから、これから禅を学ぶ者はそういうものは捨ててしまって目にするべきではない。
この段で道元禅師は、間違った坐禅をしている人々のやっていることの実態を「還源返本の様子」、「息慮凝寂の経営」と呼んで手厳しく批判しています。しかし実際のところ、今でも、坐禅についてこういう理解を持っている人が多いのではないでしょうか。かくいう私もその例外ではありませんでした。どこから仕入れたのかわかりませんが、なんとなくそういうものだと思いこんでいたのです。大人たちがそういうものとして坐禅のことを云々しているのを子供心に耳にして、知らないうちにそれを鵜呑みにしていたのでしょう。小説や漫画、テレビや映画でも坐禅のことが精神統一とか無念無想といったことと関連づけられて描かれているのが普通です。坐禅の背後にある仏法の道理をきちんと学ばなければ、人間というものは自分に都合のいい、自分勝手な常識的解釈で坐禅のことをわかったつもりになるようです。「私が仏になるために坐禅するのではない。仏が私になって坐禅しているのだ(坐仏)」などということは凡夫には思いもよらないことだからです。
ですから、よほど用心しなければ、当人は坐禅のつもりで坐っていても、実際は坐禅になっていないことになりがちです。そういう状態を、道元禅師は「打坐すでになんぢにあらず、功夫さらにおのれと相見せざる」と表現します。坐禅が本来の自己(「尽一切自己」)の表現になっておらず、深い考えもなく自分個人の主観的、心理的情態にのみ関心を払って、手に入った心境に酔っ払ったようになっている(「迷酔」)と言うのです。
釈尊の最期の言葉であると言われている「不放逸にして修行を完成させなさい」の中の「不放逸」はappamadaの漢訳語です。a(否定辞)+(p)pamada(酩酊状態)という意味の言葉ですから、「不放逸」=「素面(しらふ)」=「はっきりと覚めて」ということです。もし、坐禅が「還源返本の様子」や「息慮凝寂の経営」であるなら、それはこの釈尊の遺誡に真っ向から背くことになります。ですから、道元禅師にとってはそのような坐禅の偏向、歪曲を黙って見逃すわけにはいかないのです。そのような偏向し、歪曲された坐禅へと人を導くような、巷に流布している「坐禅箴」、「坐禅銘」、「坐禅儀」を読んではいけないと強く戒めるのは、道元禅師としては当然のこととして理解できます。
そのような中にあって、宏智禅師の撰述した『坐禅箴』だけは読むべき価値がある稀有のものだというのが次の段からの内容になります。この宏智禅師の『坐禅箴』を持ち出すためにこれまでの議論があったと言ってもいいかもしれません。次回はいよいよ宏智禅師の『坐禅箴』を身読することになります。