左営旧城300年のマジナイ
ある日、「北部中国のかなり奥地」にある県城を守っていた日本軍の部隊で、「迷子病」と呼ばれる奇病が発生する。自分がどこにいるのか分からなくなった兵士たちは、部隊内部に大きな混乱をもたらすことになるが、やがてそこにあったはずの県城自体が迷子になったことで、敵地区掃蕩に駆り出されていた部隊は帰る場所を失ってしまう。守るべき城を失った兵士らは「何のために、ここにいるのですか」と上官に問い、それに答えられない上官もまた異郷を右往左往するしかない。
東京帝国大学出の知識人でありながら、一兵卒として華北戦線に従軍していた小島信夫が描いた短編小説「城壁」(1958年)は、不条理でありながらどこか狂気じみた滑稽さを備えている。日本兵たちにとって異郷の象徴であった「城壁」は、当地における旧権力の象徴であると同時に、近代化によって無残に打ち壊されてしまった前近代的世界観の亡骸でもあった。20世紀以降、中華世界に存在した大小様々な城壁は、鉄道敷設や幹線道路建設のために次々と取り壊されていったが、埋葬されることなく野晒しにされた城壁の跡には、当然ながら怪異や迷信の類が雨染みのごとくこびりついている。そう思えば、数百年にわたって城壁とともに生きてきた人々にとって、小島信夫の描く「城壁」は一種の怪談として語られるべきものなのかもしれない。
*
そんなことを考えながら、ぼくは赤蓮が咲き誇る蓮池潭を横目に、隘路の続く勝利路を駆け抜けていた。観光地としては、台北や台南のはるか後塵を拝する高雄において屈指の観光スポットでもある龍虎塔の斜め向かいには、いまから300年ほど前に建てられた鳳山県旧城の城壁がそびえ立っていた。
かつて鳳山県と呼ばれた高雄市の政務全般は、ここ左営区に建設された県城において執り行われていた。拱辰門こと北門の城壁には、神荼と鬱壘と呼ばれる二柱の門神が彫り込まれているが、この兄弟神は悪鬼を縛り上げてその魂を虎に喰わせる力を持ち、城外から悪霊の類が侵入してこないように描かれたのだとされている。

旧城北門に描かれた神荼と鬱壘
城壁にカメラを向けると、厳めしい門神の足下でコーヒーをすすっていた老人が悪戯っぽくシャッターを押す仕草をしてみせた。
「城壁、ずいぶんときれいになりましたね」
老人が口を開きかけようとした瞬間、神荼と鬱壘の間から一台のバイクが飛び出してきた。顔見知りらしい両者は山東訛りの言葉で二言、三言話すと、そのまま手を振って別れた。義民巷と呼ばれる城内には、かつて山東省の離島から逃れてきた「反共義民」たちが数多く暮らしていて、城壁が国定古跡になったいまでも、数十年前と変わらない生活を営んでいた。あるいは、目の前にいるこの老人の故郷もまた万里の波濤を越えた先にあるのかもしれない。
「こいつもずいぶん歳をとったんだよ」壁は最近役所によって修復されたばかりで、古い城壁を知る者からすれば、なにやらひどく着飾って見えた。老人と同じように、ぼくは視線を真っ白な城壁に張りつけたまま答えた。
「鴨母王の頃からあるんでしたっけ?」
「どうだったかな」
「だとすると、300年は経っているはずです」
「歳だ歳だ」
ぼくたちはスカッシュを楽しむように、頭に浮かんだ言葉を城壁に向けて打ち続けた。老人はときに黙ったまま手元のコーヒーを見つめていたが、ぼくが立ち去ろうとすると、それを牽制するように新しいボールを打ち込んできた。
「城壁が消えてしまう日がくると思いますか?」
ぼくの打ち込んだ変化球は、神荼の肩のあたりに当たって老人の目の前に転がった。
「城壁が消えてしまう?」
老人はオウム返しに言葉を繰り返した。目じりによった深い皺が、まるで放射線状に延びたこの街の路地のように見えた。どの道を選んでも城壁にたどり着くことができるが、もしも城壁自体が消えてしまえば、あるいはこの皺は重ねた歳月以外の意味を失ってしまうのかもしれない。老人はしばらくの間カップに揺れるコーヒーの波紋を見つめていたが、ふいに「これ以上消えてしまっては困る」とつぶやいた。
老人の言葉に、ぼくはふと郷里の瀬戸内海に浮かぶ無人島を思った。季節や天候によってその表情を千変万化させる海と違って、その離島は常に同じ表情でそこに佇んでいた。故郷を失った浦島太郎たちにとって、歳月の変化を拒み続ける城壁とは、新たな郷愁を生み出す記憶の碇でもあるのだろう。
城壁の背後にある亀山を見上げた老人は、ぼくが日本人であることを知ってか知らずか、最後にひどく皮肉めいたスマッシュを打ち込んできた。
「日本人に斬られた亀山の首もやっと繋がったんだ。これ以上、城壁が消えてしまうなんてことはないはずだよ」
*
左営の街は長らく亀神によって守られてきた。
旧城の城壁は亀山と呼ばれる海抜63メートルほどの低山を取り囲むように建てられているが、当地の人々はこの山を亀神の化身として崇めてきた。蓮池潭に向けて首を伸ばした亀山は、龍宮で暮らす龍王から地上の賢人を探し出すように命を受けた亀将軍の御神体とされ、長らく左営を守る守護神とされてきた。

亀山遠景。龍虎塔に向けて亀が首を伸ばしているように見える
そのせいもあって、朝廷は鳳山県の行政機能を交通の要であった下埤頭街(現在の高雄市鳳山区)ではなく、亀山の麓に定めたのだった。県城には鳳山県署といった政府機関の他にも、保生大帝を祀る慈済宮や孔子を祀る文廟などの宗教施設、さらには高雄で初となる高等教育機関・屏山書院などが整備され、漢詩「亀山八景」の作者・卓肇昌など豊富な人材を輩出していった。
城壁が民衆反乱に利用されることを恐れた朝廷は、当初台湾に城壁を築くことを禁じていたが、羅漢門で朱一貴が反清復明の旗をあげると、城壁をもたない鳳山県城はあっけなく落城してしまった。卓肇昌の父親で詩人でもあった秀才・卓夢采は、連戦連勝を重ねていた鴨母王から反乱への加入を要請された際に「たとえ飢死しようとも賊に従うものか」と、文人らしからぬ気焔を吐いたとされている。
朱一貴事件の翌年、左営の県城には台湾史上初となる土壁を用いた城壁が築かれることになったが、鳳山県知県であった劉光泗は、この際に鳳山県城を亀神の化身とされる亀山とその南西に聳える寿山へと連なる蛇山を城壁の一部として取り込むことを決めた。
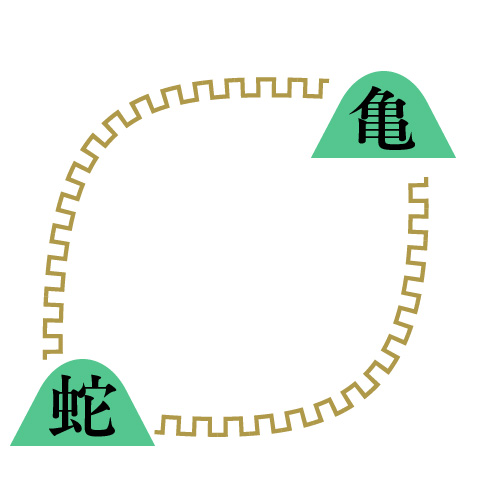
人々の脳裏に浮かんだのは、玄天上帝の威容であった。玄天上帝は北方を守る守護神とされ、歴史的に北方異民族による南進に悩まされてきた中華世界ではとりわけ重視されてきた神であった。水を司ると言われる玄天上帝は、四霊(青龍、朱雀、白虎、玄武)における玄武と幾つかの神々が統合されたものとされているが、この玄武がまさに亀と蛇が融合した神霊であるのだ。
ぼくは、蓮池潭に屹立する巨大な玄天上帝の神像を思い浮かべた。面積あたりの宗教施設の密度が台湾で最も高いとされるここ蓮池潭一帯においても、玄天上帝を祀った元帝廟はひと際異彩を放っている。蓮池潭上に建立された巨大な神像は、その左足で亀と蛇の像を踏みつけているが、この二匹こそが玄天上帝に仕える亀将軍と蛇将軍だと言われている。朝廷は民衆からの信仰が篤い二山を城壁に組み込むことで、県城を守護する藩屏としたわけだが、そこには「亀蛇聯保」によって県城の弥栄を願うといったマジナイの意味も込められていた。

蓮池潭にある玄天上帝の神像。その足下には亀と蛇が踏みつけられている
ただし、このマジナイは百年ほどで破られてしまう。
乾隆51(1786)年、台湾中部で林爽文の乱と呼ばれる大規模な民衆反乱が起こる。反乱は燎原の火のごとく台湾全土へと波及し、南部でもこれに呼応した荘大田率いる反乱軍によって鳳山県城が二度にわたって攻め落とされる事態へと発展した。反乱軍は城壁の守りが固いことを知ると、亀蛇両山をつたって城内へ侵攻し、屏山書院を含む施設の多くを破却した。荘大田の反乱軍はやがて大陸から派遣されてきた官軍によって打ち破られ、屏東県車城郷まで逃れたところを六堆義勇軍によって搦めとられ、台南府城で首を刎ねられた。
県城は荒廃した。やがて、人々は左営にあった県城を捨て、下埤頭街で新たな街と城壁を再建した。以降、左営にある県城は「旧城」と呼ばれ、下埤頭街が「新城」と呼ばれるようになったが、開けた平野にL字型に作られた新城はその後も民衆反乱や海賊の侵入が起こる度に落城の危機に瀕した。
道光5(1825)年、朝廷は民間からの寄付金を集めて、防衛拠点として優れていた旧城にサンゴ石を使った城壁を築いた。その際、林爽文の乱のときと同じ轍を踏まないようにと、石造りの城壁には亀山と蛇山の二山を組み込まないことが決定された。亀山を城内に囲い込み、蛇山を城外に追い出す形で城壁の建設が進められたのだ。
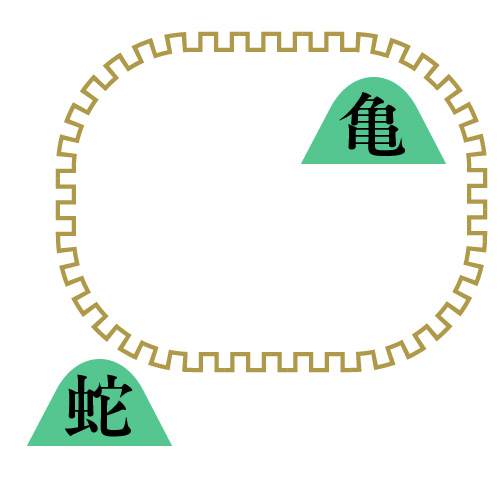
こんなことをして、神さまの勘気に触れはしないだろうか?
人々の顔には不安の色が浮かんでいた。亀蛇両神によって加護されていた旧城から、蛇山だけを追い出してしまおうというのだ。しかも、亀山を城壁で囲い込んでしまったことで、亀山は蓮池潭からも遮断される形となってしまった。追いやられた蛇山は悲嘆にくれて、囲われた亀山も自由を失った。結局、旧城に立派な城壁が完成しても新城に遷った人々が戻ってくることはなかった。鳳山県署の行政機能は完全に新城へと移管され、屏山書院は鳳義書院として同地で再建されることになった。
弱り目に祟り目とはよく言ったもので、亀山にさらなる悲劇が襲いかかる。清朝から台湾を割譲された日本政府が、城壁の取り壊しとともに、亀山の首を真っ二つに切断してしまったのだ。明治33(1900)年、旧城近くに左営駅が建てられると、多くの幹線道路が城壁を貫く形で建設されていったが、大正9(1920)年には、亀山と小亀山の間に軍用道路が敷かれ、旧城の繁栄を保証してきた亀山が二つに分断される形になったのだ。
人々は亀神の苦しみを思い臍を噛んだが、昭和5(1930)年には交通の妨げになるとして城壁の大部分が破却されてしまった。左営に新しく軍港を開いた日本人は、この帝国の南進基地に様々な近代インフラ設備を持ち込んだが、亀蛇をめぐる風水に関しては迷信深い本島人のマジナイとして取り合わなかった。
100年にわたる乾きに苦しみ、首まで失ってしまった亀神には、もはやこの地を加護する霊力は残っていなかった。
大戦末期、左営の空には多くの米軍機が襲来した。高雄市には2,559トンもの爆弾が投下され、4,093人もの死傷者を出すことになったが、これは実に台北空襲を上回る被害であった。鄭成功時代に開拓され、網の目のような細い路地が広がる五甲巷を歩けば、いまでも古民家の壁に左営旧城に飛来したP‐38による機銃掃射の弾跡を見ることができる。迫りくる米軍に対抗するために、旧城の西門付近には小型艇に250キロ爆薬を搭載した自殺攻撃部隊・震洋特別攻撃隊の基地がつくられ、城壁には佐世保の「亀山」八幡宮から分祀された震洋神社が設置された。
城壁を切り崩して作られた参拝道を上っていくと、祭壇の跡と手水舎が目に飛び込んできた。祭壇のそばで干からびた虫の死骸を見ながら、ぼくは輪郭が浮かび上がるほど濃厚な死神の影を感じていた彼らが、この城壁の上で何を祈っていたのか想像してみた。予科練出身の隊員と海軍特別志願兵であった本島人兵士たちは、かつて震洋特攻隊員として加計呂麻島で神話的時間を過ごした作家の島尾敏雄と同じく、いずれ確実に訪れる死に向けて日々訓練を繰り返していた。幸いにも「出発は遂に訪れず」に戦争は終わりを迎え、旧城の隊員たちは自らの手で神社を焼却して、城内の施設を新たに進駐してきた中華民国海軍に引き渡すことになった。

西門城壁に作られた震洋神社跡。祭壇や手水舎などが残る
しかし、日本人に斬り落とされた亀神の首は戻ってこなかった。
中華民国海軍の参謀総長として左営に赴任した桂永清は、日本が敷設した軍用道路を勝利路と名付けてそこを黒く輝くアスファルトで塗り固めたが、人々はこれを将軍が亀神の首に膏薬を塗ったのだと褒めそやした。ところが、そんな「功徳」を施したはずの桂永清将軍も、その後謎の急死を遂げてしまう。
民国45(1956)年、急死した桂永清将軍を記念したいと、高雄市参議会議長らによって小亀山上に記念塔が建てられた。しかし、永清塔と呼ばれるこの記念碑が建てられてから、旧城では奇妙な事態が相次いで起こった。亀山付近では交通事故がしばしば発生して住人の間で争いが絶えず、極めつけには蓮池潭の水面が真っ赤に染まるという怪異まで発生した。人々は不吉の原因を探したが、やがて永清塔で退役軍人が首を吊って自殺するという事態が起こるに至って、ようやくその原因を悟った。
針だ。
赤く染まった蓮池潭の湖畔に立つ男が言った。
針?
そばにいたもう一人の男が聞き返すと、件の男は黙って小亀山を指さした。
永清塔が針のごとく亀神の脳天を突き刺していた。蓮池潭の水が赤く染まったのは、脳天を突き刺された亀神から流れ出る血であったのだ。
人々は亀山の麓にある慈済宮に祀られていた保生大帝に事の次第を報告すると、急いでその神意を問うた。医療の神でもある保生大帝は、蓮池潭に龍虎塔を建てることで当地の風水を恢復せよとの神旨を下した。

左営慈済宮に祀られた保生大帝。真向いには龍虎塔が立つ
センセイは、蒋介石が亀神の化身だって言われていることを知っていますか?
ある日、龍虎塔の由来について語ってくれた学生がこんなことを語ってくれた。都市伝説の類に目がないその学生は、タブレットに映し出した玄天上帝とその背後に広がる亀山を指さしながら言った。
民間伝承では、辛亥革命をなし遂げた国父孫文は、この玄天上帝の化身だとされているんです。その眷属神である亀将軍と蛇将軍は、それぞれ蒋介石と毛沢東を指すと言われています。つまり、亀山頂上に記念塔を建てるという行為は…
独裁者を呪うためだった?
件の学生は口元に小さな笑みを浮かべた。桂永清将軍の急死には不審な部分も多く、当時から蒋介石によって暗殺されたのではないかと噂されていた。1950年代、台湾はまさに白色テロの全盛期で、「共匪」への投降が多発していた海軍はとりわけ粛清の対象となることが多かった。
*
マジナイは所詮マジナイに過ぎないが、人間はどれだけ近代的な生活を享受していても、こうした迷信から逃れて生きることはできない。ちょうど今年、高雄市役所は実に8年の歳月と10億元(およそ45億円)の税金を使い、断ち切られた亀山と小亀山の間に空中遊歩道をかける形で亀山の「縫合手術」を行った。空中歩道の完成式典には、高雄市長をはじめとする多くの政治家たちが集まって手術の成功を祝った。

勝利路にかけられた空中遊歩道。切断された亀神の首を「縫合」した
日本の観光雑誌などで、龍虎塔が「台湾屈指のパワースポット」と紹介されているのを見る度に、ぼくはどう説明したものかと頭を悩ませる。確かにパワースポットと呼ぶに相応しい場所ではあるが、龍虎塔は300年に及ぶ旧城の戦争と平和、支配と被支配、祈念と呪詛が拮抗し、交じり合うなかで生まれてきた解呪の象徴でもあるのだ。旧城城壁とそこに連なる諸々にはこの地に生きる、あるいは生きてきた人々が思い思いにかけたマジナイや呪いが深くしみ込んでいる。
日の暮れかけた城内を歩いていると、小島信夫の「城壁」で「迷子病」に罹ってしまった部隊長がうわ言のように繰り返していた言葉が頭をよぎった。
「おれ達はここにいるが、実はいないのだ。この場所の分かるやつはいって見ろ! いや違う。曹長、お前はそう思っているだけだ。実際はそうじゃない。何? 帰れない? 帰れないさ。今おるところが分からないのに、どうして帰れるかね。城壁の中へ? そんなものはありはしない。ああ部隊の位置が分からない。ああ、おれ達は何者なのだ」
夕暮れに沈む旧城東門の城壁を見上げながら、ぼくは部隊長の言葉を口腔で繰り返していた。帰れない、帰れないさ。今いるところも分からないのに。

黄昏時の旧城東門



