割り稽古のための3×3の分割表を作る
連載第二回では、伝統的な調身・調息・調心という考え方を援用して、姿勢・呼吸・心という、坐禅を構成する三つの成分に基づいて坐禅を割る割り方について述べた。
道元は『学道用心集』の中で「身心を調えてもって仏道に入るなり」と言っている。身心を調えることを最も端的にやっているのが坐禅だとすれば、坐禅がその唯一の入り口ではないとしても、この言葉は、坐禅を通して仏道に入るのだと言っていると解してもあながち的外れではないだろう。別のところでも道元は「坐禅は仏道の正門である(「端坐参禅を正門とせり」)」と言っている。
彼の文章にしばしば出てくる「身心」という表現がここでも使われているが、彼の場合、「身心」といつでも「身」の方を「心」より前に置いて表記しているのが特徴だ。もちろん、身心一如という仏法の立場でこの言葉を使っているのだから、身心を「身と心」という二元的な意味で理解し、身の方を心よりも重視しているなどと理解してはいけない。身心は、心身二元論的な body and mind ではなく、body-mindと -(ハイフン)で分かち難くリンクさせた一つの単語として理解すべきである。さらに、ハイフンさえ省いて、文字通り bodymind と直結させて、一語で表記することもできるだろう。この意味での bodymind に対応するような漢字は存在していないが、もしあえて作るとすれば、左側(偏 へん)に「身」、右側(旁 つくり)に「心」と書いて一字にした漢字にしてはどうだろう。そして、ふりがなは「しんじん」あるいは「しんしん」とするか、この漢字の左側には「からだ」、右側には「こころ」とふりがなをつけるのだ。それとも、親鸞が「弥陀の五劫思惟(ごこうしゆい)の願をよくよく案ずれば、親鸞一人がためなりけり。さればそれほどの業をもちける身(み)にてありけるを、たすけんとおぼしめたちける本願のかたじけなさよ。」(『歎異抄』後序)と言うときの「身(み)」は、道元の言う「身心」と対応していると思うので、その意味で「み」とふりがなを振ってもよいかもしれない。道元の「身心」、親鸞の「身」は、誰にでも当てはまる一般的・抽象的・理論的な身心や身のことではなく、今ここで具体的に現に生きて活動している他ならぬ「この」自分の丸ごとのいのちのこととして受け止める必要がある。
この現に生きている身心という丸ごとのいのちに触れていく(坐禅はその典型の一つである)にあたって、身の面から触れていくのが調身であり、心の面から触れていくのが調心である。触れているのは同じものなのだが、触れている面が違うのである。だから、同じであるが違う。逆から言えば違うが同じである。身に本当に触れていればそれはけっきょく心にも触れていることになるし、心に本当に触れているのならそれは必ず身にも触れていることになる。だから、調身をしているといつのまにか調心的にならざるを得ないし、調心をしているといつしか調身的なことになるのだ。
身心を調えるのなら、調身と調心でよいのではないかということになるのだが、実際にはその真ん中に調息が入っていることに留意する必要がある。呼吸は身の側面に入れることもできるが、心の側面に入れることもできるというとても興味深い現象である。熟睡時にも呼吸が続いていることからもわかるように、身体はわれわれがコントロールしなくても問題なく呼吸をすることができる。その意味で確かに身の一部とみなすことができる。呼吸は身体がしている運動の一つなのだ。しかし、覚醒時のわれわれの呼吸の実態を少し吟味すれば、それが単純な生理現象に留まっているのではなく、そこにわれわれの心理状態が色濃く反映していることがわかるだろう。呼吸は心の動き、たとえば恐怖とかショック、不安などに敏感に反応して変化するし、呼吸を制御することによって、心に影響を与えることもできる(たとえば、深呼吸をして心を落ち着かせるなど)から、心理現象の一部ともみなせるところがある。呼吸は心の表現でもある。つまり、われわれの普段の呼吸は、生理現象に心理現象が掛け合わさったもの、あるいは重ね合わさったものになっているのだ。呼吸はその人の身心相関のレベルを繊細に示す指標だと言える。
だから、先ほど言った調身と調心の関係をより精密に言うなら、調身は調息を通って調心につながり、調心が調身につながるには調息を経由するのである。以上のような事情から、身心を調えるにあたっては、調身と調心の他に、さらに調息ということを独立に取り出しておくことが実践上極めて有効であるとされてきたのだろう。生きて動いているナマの身心と言えばそこには当然、呼吸が含まれているから、「身心を調える」と言えば呼吸を調えることも理屈の上ではもちろん含意されている。しかし、そのように言わずもがなの調息を、調の営みの独立項として明確な形でさらに加えて、調身・調息・調心の三位一体のセットとしたことは、坐禅を身心を調える行法として実践する上では極めて重要な意味があるのだ。
連載第三回では、『正法眼蔵 生死(しょうじ)』の一節を援用して、release(手放す)・ receive(受け取る)・ enjoy(享受する)という、坐禅を行う際の努力の仕方(道元の用語を借りれば「功夫(くふう)」)に基づいた坐禅の割り方について述べた。「わが身をも心をもはなちわすれて、仏のいへになげいれて」を一言で release とまとめ、「仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆく」を receive 、「ちからをもいれず、こころをもつひやさずして、生死をはなれ、仏となる」を enjoy とまとめてみた。これは、姿勢・呼吸・心のような坐禅そのものの構成成分ではなく、坐禅に取り組んでいるこちら側がやる営みの性質、クオリティに沿った割り方と言える。
release、receive、enjoy という英語の動詞を使ってそれを表してみたが、この三つのいずれも積極的に何かをするという「doingモード(作業モード)」の動詞ではないことで共通している。release は今、身心を緊張させて握りしめているものをゆるめ、ほどいて、手放すことである。つまり、やっていることを止めることであるから、doing ではなく undoing モードである。receive は何かを手に入れようとこちらから能動的に手を伸ばしてつかみにいくのではなく、やってくるものを受け取ることだ。enjoy は自ずからに起きていることをそのまま享受する(外部から差し出された、何らかの好ましい物事を受け入れ、その好ましさを存分に味わう)ことである。つまり、receive も enjoy も発信モードではなく受信モードなのだ。能動的ではなく、どちらかといえば受動的だ。しかし、単なる受動でもない。「仏の家に」向かって「わが身をも心をも」手放すということを確かにしているし、「仏のかたより」やってくることをきちんと受け止めて、それにしたがっているからだ。
能動でもなく受動でもない「被動(ひどう)」というあり方があることを、オートポイエーシス論を探究している河本英夫先生から最近、教えてもらって知った。release によって身(心)の構えをほどく、つまり普段の能動のモードを一時的に保留状態にすると、向こうからこちらにやってくるものがある。それにしたがい、まかせていくのだが、自分が「仏のかたよりおこなはれてくる」ことにまかせてそれにしたがっていることをちゃんと知っている。そういう知、自覚があるかないかということが単なる受動と被動の違いだと河本先生はおっしゃっていた。坐禅における receive は単なる受動ではなく被動になっていなければならない。
「生死をはなれ、仏となる」ということが「仏道に入る」こととほぼ同義だとすれば、「release・receive・enjoy」というこれら三つの動詞によって表されるような調の仕方で坐禅が行われるべきであることが例の『正法眼蔵 生死』の一節によって示唆されていることになる。そしてその坐禅は「調身・調息・調心」という三つの調から成り立っているのであるから、「調身・調息・調心」を「release・receive・enjoy」という取り組みかたで行うべきことが、結論として導かれてくるはずだ。そう考えれば、これら二つの割り方をクロスさせることはそれほど荒唐無稽の試みでもあるまい。これ以外の割り方がないというわけではないが、今のところこの線に沿って、坐禅を割っていく可能性とその有効性を検討していくことにする。
坐禅の成分に基づく三つの割り方と坐禅の功夫の仕方に基づく三つの割り方を縦と横に掛け合わせて、坐禅を3×3の九つに分割するのである。具体的に言えば、調身・調息・調心の稽古のそれぞれをさらに release・receive・enjoy という三つの功夫に割るのである。するとこういう3×3の表ができて、九つのセルが作られることになる。
|
|
Release |
Receive |
Enjoy |
|
調身 |
① |
② |
③ |
|
調息 |
④ |
⑤ |
⑥ |
|
調心 |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
第三回において、
調身は、「大地とのつながり方」、調息は「大気とのつながり方」、調心は「感覚刺激とのつながり方」がテーマになっているというのが私の理解だ。これら三つのつながり方のそれぞれに、より良質の調和がもたらされるような姿勢・呼吸・心の調律、調整のあり方を、全力を挙げて探究するのである。
と述べた。これは、調身・調息・調心という三つの調の営みは、単に「自分の」肉体の内側(皮膚の内側)と心の内部(内的意識)で閉鎖的に行う意図的な操作・制御ではなく、そういう狭義の肉体や心にとっては「外部」にあるとされる大地、大気、外からやってくる感覚刺激との関係、つながり方の探究的調律であるということだ。坐禅の調は閉じた内職仕事なのではなく、開かれた関係的な探究なのである。そうみなすことではじめて、「仏の家」、「仏のかた(方)」ということが単なる抽象的観念ではなく、坐禅の実践において具体的リアリティを持つことができると思うからだ。つまり、「仏の家」「仏のかた」とは、調身においては大地のことであり、調息においては大気のことであり、調心においては感覚刺激の源のことになるのである。そして、release・receive・enjoy という三つの功夫を、大地とのつながり方、大気とのつながり方、感覚刺激とのつながり方という文脈において稽古するようなワークを考えることが可能になる。
三つの調(調整・調律)の方向性に関しては、坐禅の基本テキストである道元の『普勧坐禅儀』から、調身には「正身端坐(しょうしんたんざ)」、調息には「鼻息微通(びそくびつう)」、調心には「非思量(ひしりょう)」というキーワードを割り当てることができる。release と receive を通して大地とのつながり方を調整・調律し、坐るそのつどの諸条件下における未知の正身端坐とはどのようなことなのかを実践的に探究することを enjoy することが調身(①・②・③)であり、release と receive を通して大気とのつながり方を調整・調律し、坐るそのつどの諸条件下における未知の鼻息微通とはどのようなことなのかを実践的に探究することを enjoy するのが調息(④・⑤・⑥)であり、release と receive を通して感覚刺激とのつながり方を調整・調律し、坐るそのつどの諸条件下における未知の非思量とはどのようなことであるかを実践的に探究することを enjoy するのが調心(⑦・⑧・⑨)であることになる。これを先ほどの表に書き込むと次のような表になる。
|
|
Release (手放す) |
Receive (受け取る) |
Enjoy (享受する) |
|
調身 正身端坐 大地とのつながり |
① |
② |
③ |
|
調息 鼻息微通 大気とのつながり |
④ |
⑤ |
⑥ |
|
調心 非思量 感覚刺激とのつながり |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
これから①から⑨までのセルの内実(コンテンツ)がどのようなものになるかをみていこう。
①
自分の体の重さを「仏の家」、つまり大地に向かって「放ちわすれる」ことである。自分の重さを感じ、その重さをすっかり手放して大地にあずける(全託する)のだ。「仏のかた(方向)」とはこの場合、重力の向かう先である、母なる地球の中心ということになる。正身端坐を骨組みと筋肉でねらう調身とは、体重を通した地球、大地との交流にほかならない。この①はわれわれから大地への重さの投げかけである。しかし、われわれは、さまざまな事情で身体の各所に「人間的な力み」を抱えており、それは筋肉的な緊張や収縮という形をとっている(身の構え)。身体の深部に本人も気づかれないままにずっと存在しているような緊張もあるだろう。そうした緊張は身体全体の重さを大地に向かって解放し、あずけることを妨げている。地球の中心に向かって自分の重さを全託することは、言うは易く行うは難い。それをテーマとして稽古するのがこのセルのコンテンツとなる。一言で言えば正身端坐における「接地性 groundedness」の稽古と言えるだろう。
さらに、「わが身をも心をも」なのであるから、「心理的な」自分も手放す。それは、防衛的な姿勢をとっている普段の自分の心の構えを手放すことである。『普勧坐禅儀』にある「諸縁を放捨し、万事を休息して、善悪を思はず、是非を管すること莫(なか)れ。心意識の運転を停(や)め、念想観の測量(しきりょう)を止(や)めて、作仏を図ること莫(なか)れ。(/あれやこれやのとらわれを放って、心をゆるやかに寛がせて静かならしめ、万事のいとなみを休息(とりや)め、善悪や是非の思慮分別にかかずらわないのである。普段のように心がはたらき動くのを停(や)め、一切の思量をめぐらすことがなく、また仏に成ろうと図ることもない。)」もまた、そのことに含まれている。
②
自分の体重を大地に全託する(「わが身をも心をもはなちわすれて、仏の家になげ入れ」る)と、それと同じだけの反作用が鉛直線に沿って大地から天に向かって自分の身に返ってくる。これこそまさに、「仏のかたよりおこなはれて」くることの実例である。これは、自分が努力してやっていることではなく、自然の働きが一方的にしていることだ。正身端坐の特徴は上半身がまっすぐに立ち上がっているところにあるが、それは意志の力で筋肉を張って無理やりに自分をまっすぐにしようとするのではない。全託した体重の反作用として大地から自ずと返ってくる上に向かう力を内的感受性を活かして感じとり、その感覚が垂直性に至らせてくれるのにただ任せるのである。それが「仏のかたよりおこなはれて、これにしたがひもてゆく」ということだ。大地からやってくる支えの力を正身端坐における「垂直性 uprightness」へと変換していく稽古が②のコンテンツになる。
③
これは release と receive を通して生まれる正身端坐という、この地上における最も安楽な在り方をフルに味わい、愉しむ稽古をコンテンツとするセルである。調身とは、身心から身構え、心構えという「重荷」をおろして(身心脱落)、重力と最も親和的な関係を築くことだ。骨や筋肉を包む筋膜へのアプローチを中心にする身体調整の技法である「ロルフィング」を創始したアイダ・ロルフ(1896〜1979)は、「からだが適切に機能し始めると、重力がその中を通って、流れてゆくことができます。その時自然に、からだが自らを癒すのです。」と言っている。正身端坐を探究する調身は、彼女がいう「重力が治療者として働くような自ずからなる癒しのプロセス」を起動させるような学びなのである。③はそのプロセスのもたらす功徳を心おきなく満喫する稽古だと言える。大地との一体感は安心(安身)の源でもある。
 アイダ・ロルフ
アイダ・ロルフ
④
呼吸における手放しとは、出息のことだ。どこへ向かって息を「はなちわすれるか(release するか)」といえば、自分を包んでいる大気へ向かって、である。坐禅のときの呼吸は、「鼻息」というように鼻を通して行われているが、体感としては「微通」と言われるように、微細な感覚を生み出しながら、どこにも滞りなく全身において行われるように感じられる「全身呼吸」である。さらに厳密に言えば、自分を包んでいる大気と一体的につながって行われているのであるから、真の呼吸は空間の中(虚空の中)で起こっていて、どこか特定の場所で起きているということは言えないことになる。
しかし実際には、息が完全に出ていく前にもう吸い始めてしまうといった不自然な仕方で呼吸する癖(それが自分の「自然な呼吸」だと思い込んでしまっている)が身についてしまっているわれわれは、呼吸が起こるままにできていないところから出発することになる。この④は、息の自然な流れに干渉せず、出る息が消えていくのにただまかせるという、呼吸における「わが身をも心をもはなちわすれ」る稽古になる。「仏の」家に自分の出息を投げ入れるのであるから、それは供物であり、捧げ物でなければならない。出ていく息をどのようなクオリティで出ていかせているかということが問題になってくる。出ていく息を手放そうとしない傾向がないか、あるいはその逆に、出る息を押し出そうとしていないか。本当に自然に、出ていく息を捧げ物として「はなちわすれ」「なげいれて」いくことを割り稽古するのである。いずれ、捧げるのは息だけではなく、自己の全体であり、出る息と共に自分が虚空の中に溶け去っていくような体験が訪れるかもしれない。
⑤
呼吸における「受け取る receive」とは、入息のことだ。自然な息の流れに干渉することなく、「仏のかたよりおこなはれて」くるようにやってくる入息を、そのままに受け取り、それに「したがひもてゆく」のである。しかし、われわれには入ってくる息をつかんだり、その邪魔をしたり、余計に吸い込んだり、といった心理的操作を加える傾向が多分にある。そうした傾向性に繊細に気づき、それが自然と消えていくように稽古するのがこのセルのコンテンツになる。出る息が捧げ物なら、入ってくる息は仏からの贈り物、恩寵であるから、贈り物の受け取り方の稽古ということになる。
呼吸においては受け取るものがもう一つある。それは、息と息の間の間(ま)、スペースだ。捧げ物としての息が出ていった後、贈り物としての次の入息が始まるまでの間に、呼吸が止まっているような無息の時間が生まれる。これは、自分が意図的に作り出すものではなく、出息が入息に切り替わる際に自然に与えられる呼吸の間隙だ。それは、息が休んでいる、文字通り「休息」の時間である。この自然な休息があるかないかで呼吸の風景はまったく違ったものになる。多くの場合、われわれはこの休息をそのままにできず、すぐ息を吸い込む傾向がある。「仏のかたよりおこなはれて」くる、この自ずからなる休息の時を受け取れず、それに「したがひもてゆく」ことができていないのだ。贈り物としての入ってくる息を受け取り終わった後、捧げ物としての次の出息が始まるまでの間にも、この休息の時間が生まれる。
出る息、入る息が音あるいは動きだとすると、この休息の時間は沈黙であり、静止である。はじめは、この休息の間(ま)は、呼吸の単なる隙間(すきま)ほどの意味にしか感じられないが、出る息がそこに消え去っていき、入る息がそこから生まれてくる実際を一回一回の呼吸のたびに目撃していると、この休息の時こそが呼吸の故郷であり真の家であることが実感されるようになる。息と息の間がリアリティをもってそこに存在し始めてくると、呼吸の光景に大きな質的転換が起こるのだ。
⑥
呼吸を enjoy する稽古とは、呼吸を快として味わってゆくことだ。呼吸における release と receive によって「ちからをもいれず、こころをもついやさずして」自然(じねん)に生じている息には求めずして自ずからなる快感が伴うのだ。実人生においてさまざまの苦難を経験した哲学者・西田幾多郎(1870〜1945)は「斯の如き世に何を楽しんで生るか。呼吸するも一の快楽なり。」という断想を残している。捧げ物として出ていく息、贈り物として入ってくる息、息と息の間に生まれる休息、という呼吸の三つの相それぞれの快を繊細に深く味わうことのできるキャパシティを養うことである。出息には、緊張を手放し、身心が緩む(ほっと一息つく)リラクセーションの心地よさがある。入息には、新鮮で生気に満ちた空気を取り入れる、文字通り「うまい空気を食べる」快感がある。休息(無息)には、深い静けさという静寂の心地よさがある。呼吸の一サイクル一サイクルごとに、この三種の快を心ゆくまで味わうことができれば、呼吸という「原初的な生」「生が生自らを直接に享受するところ」(西田幾多郎の境涯があらわれている最も単純な言葉であるとして、哲学者の上田閑照氏が西田の上の断想に対して述べたコメント中の言葉)に、生の肯定を見出すことができる。
 西田幾多郎
西田幾多郎
⑦
調心における「手放す」とは、眼・耳・鼻・舌・身・意という六つの感覚器官をくつろがせ、開いていくことを意味している。普段のわれわれは、自我の防衛・拡大のために感覚器官を使役させている。もっと見ようとして眼を緊張させ、嫌なことを聞きたくないと耳を閉じているといった具合である。あるいは、満員電車の中にいる時の、自分の感覚器官の状態を思い起こしてみればいいだろう。坐禅ではよく「半眼」ということが言われるが、情報をとらえに行こうとする緊張した普段眼の状態のままで「半眼を作る」のではない。現れる対象の情報がやってくるままにそれを迎え入れるくつろいだ眼を外から見ると「半眼になっている」のである。
「マジカル・アイ」という面白い絵がある。一見すると、同じような図柄が二次元に広がっているだけなのだが、どこにも焦点を合わせないでボーッとその絵を見るともなく見ていると(そういう見方を「マジカル・アイ」という)、そのうちさっきまでは見えなかった三次元の立体的な図が向こうから立ち上がってくるのだ。立体的な絵を見つけようと普段の眼のまま頑張るのではなく、マジカル・アイになって向こうから現れてくるのを受け取ろうとリラックスして待っているのだ。この比喩を使って言うなら、坐禅の時は、眼だけでなく、耳も鼻も舌も体も脳もみんなくつろいで、そのつどやってくる情報を迎え入れる「マジカル・アイ」的な状態になっているのである。だから、⑦のセルは、六つの感覚器官を「マジカル・アイ」化する稽古ということになる。
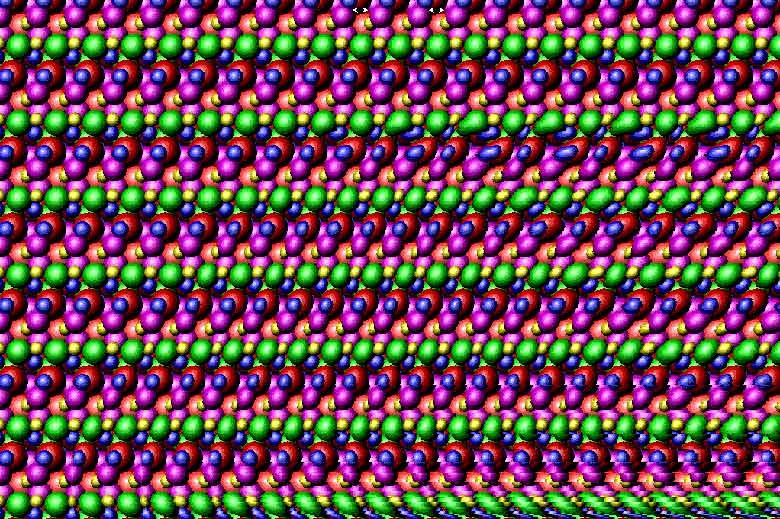 マジカル・アイ
マジカル・アイ
⑧
調心における「迎え入れ receive」とは、六つの感覚器官にやってくるインプット(光・音・匂い・味・身体感覚・思考)を、完全に開かれた状態で、概念化せず、やってくるままに受け入れることを意味する。ここでは「仏のかたよりおこなはれて」とは、光源、音源のようにそれぞれの感覚のやってくる方向のことを指す。「これにしたがひもてゆく」とは、聴覚の場合なら、無心になって聴くということだが、普段はそうなっていないことが多い。何かを探して安心しようとする密かなアジェンダ hidden agenda(隠された思惑[意図・計画])が隠れているのだ。マジカル・アイで言えば、向こうから見えてきた立体の図をもっと見ようとして「目を凝らす」ことにあたる。そうした途端に、3次元の図は消えてしまう。そういうものに気づいて、それを手放し、純粋に聴くとはどういうことかを探究する。純粋とは、聞くものと聞かれるものとの分裂がなく、ただ聴くことだけが起きているというあり方だ。どこにも焦点をおかず、動機もなく、只管に聴く稽古をする。私が何かを何かのために聞くのはなく、ただ何かが聞こえている。聴覚だけでなく他の感覚においてもそれと同じようなシフトが起きるような稽古をするのが⑧である。
⑨
くつろぎ完全に開かれた感覚器官を通して、自分に届いてくる感覚刺激に対して、名前をつけず、概念化せず、純粋に知覚していると世界が新鮮に経験できるようになってくる。調心における「享受する」とは、全身が迎え入れの器官となることで、生をその瞬間瞬間の新鮮さの中で経験することを意味している。仏伝には釈尊が悟りを開いた瞬間、「奇なるかな。奇なるかな。一切衆生ことごとくみな、如来の智慧・ 徳相を具有す。ただ妄想・執着あるを以ての故に証得せず」と、思わずつぶやいたと記されている。しかし、「奇なるかな……」と言葉が出てくる前には「!?」という言葉にならない感動があったはずだ。われわれは経験にとどまることなくすぐにその経験を言葉にして概念化してしまう。そのことによって感覚は既知のものになり、瑞々しさをうしなうことになる。そして、われわれが経験する世界はどこにも wonder(奇なるもの)のないプログラム化された地図のようなものになる。⑨では活き活きとした〈今ここの自己〉が帯びている現実性を驚異の念と共に味わうことを稽古することになる。地図を離れて現地としての自己と世界をフレッシュに味わうのが坐禅なのである。
以上、①から⑨のセルについて少し詳しく論じてきた。これを表に書き入れると下のようになる。
|
|
Release (手放す) |
Receive (受け取る) |
Enjoy (享受する) |
|
調身 正身端坐 大地とのつながり |
接地性 体重を大地に全託する |
垂直性 大地の支えによって坐る |
大地との一体感を味わう |
|
調息 鼻息微通 大気とのつながり |
出息を余すところなく捧げる |
入る息と休息を贈り物としてフルに受け取る |
呼吸の快感を味わう |
|
調心 非思量 感覚刺激とのつながり |
感覚器官をくつろがせ、開く |
やってくる感覚刺激をそのまま迎え入れる |
刻々の生をその新鮮さにおいて味わう |
これで、とりあえず坐禅を九つに割って、「割り稽古」するための分割表ができた。これからは、これをもとにして、それぞれのセルにふさわしい適切なワークを具体的に作り出す作業を始めることになる。



