はじめに
道元禅師(どうげんぜんじ)が『普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)』、『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう) 坐禅儀』、『正法眼蔵 坐禅箴(ざぜんしん)』などで説いている坐禅は、観法(かんぼう)[1]や看話(かんな)[2]など、種々の瞑想的技法を用いて坐る他の坐禅と区別するために、「只管打坐(しかんたざ)」と呼ばれている。道元禅師自身は、「坐禅は習禅(しゅうぜん)[3]にはあらず」という言い方をして、只管打坐の坐禅とそれ以外の坐禅を区別しているのだ。
たとえば、チベット仏教僧、テーラワーダ仏教僧、臨済宗の禅僧、曹洞宗の禅僧が四人並んで同じような格好で坐っていても、彼らが実際にやっていることの内実は必ずしも同じであるとは限らない。チベット仏教僧はマントラ(真言)を用いた瞑想をしており、テーラワーダ仏教僧は腹部の動きを観察するヴィパッサナー瞑想をし、臨済宗の禅僧は公案の拈提(ねんてい)に余念がなく、曹洞宗の禅僧は只管打坐をしていて、四人四様のことをしている、ということが充分にあり得るのだ。だから、坐って行う仏教的行法にもいろいろなものがあるということはよく承知しておかなければならない。同じような格好といっても、繊細に見ていけば、坐りのコンテンツの違いに相応した違いが見つかるかもしれない。
そのいろいろある坐禅の中で、この連載で主題的に論じていくのは、「只管打坐」である。行法間の優劣を問題にするのではなく(それはそれで一定の意味のあることだが)、只管打坐という行法の独自性、そして、その独自性のゆえの修行の仕方の具体相、実践の道筋などを集中的に掘り下げていくのがここでの目的である。特に、只管打坐を「割り稽古」するという、これまで誰も論じたことがないであろうアプローチについて論じていく。
はじめに、もう少し「只管打坐」という言葉の詮索をしておこう。「只管」というのは「ただ」という意味であり、「打坐」の「打」は、「打つ hit」という意味ではなく、動詞の上についてその意味を強める接頭語である。日本語で言えば、「殴る」という動詞をさらに強めるのに「ブン殴る」と言い、車を勢いよく走らせるのを「ブッ飛ばす」と言うが、その「ブン」とか「ブッ」に相当する。だから、只管打坐とはただ掛け値なしにドン坐る(あるいは、ブッ坐る)ということだ。つまり、坐ることの中に瞑想のための技術や技巧を一切持ち込まず、「ただ」正身端坐(しょうしんたんざ)[4]して坐ることがすべてであるように坐ることが、只管打坐の意味である。只管打坐は、唯(ただ)打坐することにのみ務めるので「唯務打坐」とも言われる。
内山興正老師は「坐禅する(この場合は只管打坐の坐禅を指す:筆者注)とは、居眠りせぬよう、考えごとにならぬよう、そして生き生きと覚めて、骨組みと筋肉で正しい坐相(ざそう)をねらい、その姿勢に全てまかせきってゆくことである」(内山興正『坐禅の意味と実際』大法輪閣)と説明している。
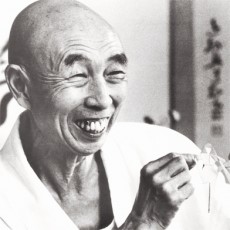
内山興正老師
私は、アメリカで坐禅の指導していたときは、この内山老師の定義を英語でみんなに説明していた。すると、「坐って、それから何をすればいいのですか?」という質問が返ってくることがしばしばあった。「正しい坐相をねらい、その姿勢に全てまかせきってゆく」と心がすべきことはそこで既にちゃんと言われているにもかかわらず、そういう質問が出るということは、内山老師の言わんとすることがその質問者には伝わっていないということだ。
そういう質問をする人たちの中には、以前にチベット仏教やテーラワーダ仏教の瞑想を経験している者が多かった。おそらく彼らには、脚を組んで坐るというのは身体のやる仕事であって、心はそれとは別の何か特別なことをするのが瞑想だという先入観があるのだ。そういう先入観で内山老師の定義を聞けば、そういう疑問が出てくるのは当然かもしれない。心でする何か特別のこと、たとえば、呼吸を数えるとか身体の特定の部位に注意を向けるといったいわゆる瞑想技法的なことが、内山老師の定義にはまったく見られないために、面食らうのだろう。只管打坐は彼らの持っている瞑想の枠組みには収まらないのだ。
道元禅師は「衲子(のうす)坐禅。直(じき)に須(すべから)く端身正坐(たんしんしょうざ)を先と為すべし。然る後に調息致心(ちょうそくちしん)す。若(も)し是れ小乗ならば、元に二門有り。所謂(いわゆる)数息(すそく)、不浄(ふじょう)也。小乗の人は、数息を以って調息と為す。然り而して仏祖の弁道、永く小乗と異なる。仏祖曰く、白癩野干(はくらいやかん)之心を発すと雖も、二乗自調之行(にじょうじちょうのぎょう)を作(な)すこと莫(なか)れ。」(『永平広録』巻五)と言い、数息観のようなセルフ・コントロール法(自調之行)を坐禅に持ち込んではならないとしている。私は、この一節を彼らに紹介し、只管打坐においては「身の結跏趺坐(けっかふざ)すべし、心の結跏趺坐すべし。身心脱落の結跏趺坐すべし」(『正法眼蔵 三昧王三昧』)と道元禅師が言うように、身だけでなく心も結跏趺坐するのだと返答することにしていた。
私は、こういう経験をしてからは、英語で坐禅のことをzen meditation(禅的瞑想)と言うのをやめることにした。その訳語ではどうしても瞑想臭さが残ってしまい、いろいろある瞑想法の中の一つが坐禅だと思われかねないし、何をmeditateすればいいのかという瞑想対象に関する問いを誘発してしまうからだ。zen meditationと言うかわりに、私は日本語のままでzazenとかshikantazaと言うか、英語に直訳してjust sittingとかsoley sittingという言い方をすることにした。そうすれば、瞑想meditationという「三界の法(人間技)」と「仏祖の法(仏行)」としての坐禅を混同することが少しは避けられると思ったからだ。(アメリカ時代に、Zazen is not the same as meditation.(坐禅は瞑想と同じではない)ということをいろいろな機会に言ったり、書いたりしたせいで、この英文でGoogle検索をすると私の名前Issho Fujitaがヒットすることが多いという結果を招いてしまった。)
ちなみに、この「ただ just」ということで思い出すのは、唐代の禅僧、保唐寺無住禅師が説法の中で使った次のような喩え話である。
とある一人の男が、小高い丘のうえに立っておった。
そこへ、三人の男が連れだって通りかかる。
遠くに人が立っているのを見て、三人は口々に言い出した。
「あのお人は、家畜を見失のうたのであろう」
「いや、連れとはぐれたのだ」
「いや、いや、風にあたって涼んでおるのだ」
こうなると、言い争いになって収拾がつかぬ。
それで近づいて行って、当の本人にたずねてみた。
「家畜を見失われたので?」
「いや」
「では、連れのお方とおはぐれに?」
「べつに」
「なら、風にあたって涼んでおいでで?」
「ちがう」
「はて、そのどれでもないとなると、こんな高いところで、いったい何の為に立っておいでで?」
「只没に立つ――うむ、ただ、立っておるのだ」
小川隆『禅思想史講義』(春秋社)より
この話の男が何の為にでもなく「ただ立っていた」ように、「ただ坐ること」を実際に修行するのが只管打坐なのだが、実際にそれを行ずるとなると、「言うは易く行うは難し」ことを誰もが痛感させられる。「ただ坐る」ことは超難題なのだ。
只管打坐の基本的手引書である『普勧坐禅儀』をひもとくと、そこには坐禅の作法が細かに規定されている。「ただ坐れ」と言いながら、それをするためのあれやこれやの守るべきルールのようなことを提示するというのはどう見ても矛盾しているのではないか。一方で自由や自発性を強調しながら、他方で、厳密なスケジュールに従って生活することや細かな食事作法を守ることを課すといった例からもわかるように、禅の世界には、「けっきょく、どうすりゃいいんだ!?」と人を困惑させる、そういうダブルバインド[5]的なメッセージが満ちているのだ。

グレゴリー・ベイトソン
心理療法の世界では、親や教師が日常的にダブルバインド的なメッセージを発していると、それを受け取る子どもの自己肯定感を下げたり、メンタルに悪影響を与えたりすると言われている。公園で遊んでいてなかなか帰ろうとしない子供に、親が「もう勝手にしなさい!」と強い口調で吐き捨てるように言う光景をよく見かける。言葉の上では「勝手にしろ=自由に遊んでいい」と言いながら、非言語レベルでは「もう遊んじゃだめ。すぐ帰りなさい!」というメッセージを強烈に発しているのである。こういう矛盾した指示を受け取った子どもは、その矛盾を指摘できないままダブルバインド状況に陥り、最終的には親の意思に従うほかなくなり、ストレスを溜め込むことになると言われている。だから、そういうダブルバインド的なメッセージにならないような工夫が勧められるのだ。
ところが、只管打坐の世界では、「造作することなく、ただ打坐せよ」というメッセージと「この作法通りに坐れ」というメッセージが同時に与えられ、しかもそれら相互に矛盾し合うような二つの要求を同時に満たすような坐禅を実現させるよう迫られているのである。禅の公案というのはこういうダブルバインド的状況を創造的に打破して新しい局面に打って出ることを稽古するための教育装置ではないかと私は愚考している。もし、それが当たっているとするなら、只管打坐それ自身が禅の公案そのものだと言えるだろう。
FAS協会[6]という在家の禅会を主宰した久松真一(1889~1980、宗教哲学者)は「どうしてもいけなければ、どうするか」という問いを「基本的公案」として参禅者に取り組ませたという。

久松真一
そもそもこの問いはいったいわれわれに何を問いかけているのだろう。只管打坐の実践にも、この基本的公案とよく似た、一筋縄ではいかない問いかけのようなものが潜んでいるように感じられる。いろいろな作法に従いながらも、それが同時にただ端的に坐っていることにもなっているとはどういうことなのか、それをここでお前の坐りでもって実際に見せてみよ、と言われているのだろうか。
只管打坐に、安易に技法や技術、作為、造作を持ち込むと、それがたちまち習禅の方向に変質してしまうから、細心の用心をしなければならない。もちろん、只管打坐に技術的な側面がないわけではない。結跏趺坐で脚を組み安定した姿勢を作り、全身に呼吸の波が微細に行き渡るような息をし、居眠りや考え事に陥らないように高い覚醒度を保って坐るには、それなりに高度な技術が要求される。しかし、そうした技術を習得しさえすればそれでそのまま只管打坐ができるわけではない。それは音楽の世界において、ピアノ演奏のテクニックを完璧にマスターした者が必ずしも優れた「ピアニスト」であることを意味しないのと同列である。ここではこうしたテクニック(訓練)とアート(稽古)の本質的な違いはどこにあるのかという探究すべき大事な問題があることを指摘するにとどめる。このテーマについては今後、さらに突っ込んだ形で論じることになるだろう。
「ただ〇〇するだけ」と強調しておきながら、他方で同時に「ただ〇〇をする」ための細かな作法があって、それを守ることがやかましく言われているのは何も只管打坐の世界だけではない。お茶の世界でもそういう一見矛盾したダブルバインド的な言説が普通に見られるのである。茶人の心得・作法などを和歌に詠んだ利休百首の中に「茶の湯とはただ湯をわかし茶をたててのむばかりなる事と知るべし」という教えがある。その一方で、部屋への入り方、歩き方、茶道具の扱い方、茶碗を置く位置、茶碗の運び方、お茶の飲み方などが事細かに決められていて、それらすべてをマスターし淀みなく正確に行うことができるようになるまでには長期にわたる稽古が必要とされている。同じ利休百首の中に「稽古とは一より習ひ十を知り十よりかへるもとのその一」という教えがある。「ただ湯をわかし茶をたててのむ」のが茶の湯のはずなのに、なぜそんな稽古が必要とされるのだろうか? 茶道を学んだことがある人でこういう疑問を持った人は相当いるのではないだろうか。
若き道元禅師は「顕密二教(けんみつにきょう)ともに談ず。本来本法性(ほんらいほんほっしょう)、天然自性身(てんねんじしょうしん)と。若(も)しかくの如くならば、三世の諸仏、甚(なに)によってか更に発心(ほっしん)して菩提(ぼだい)を求むるや」という疑問を抱いたと言われている。顕教でも密教でも、人は生まれながらにしてすでに仏なのだと説く。それならなぜ歴代の仏たちや祖師たちはさらに心を発(お)こして仏法を求め仏になろうと修行を重ねたのか、という問いだ。これは、今われわれが論じている「ただ」を強調しながら、同時に稽古の必要性が言われることと同型の問題としてつながっているように思われる。
只管打坐と茶道という二つの異なる世界で、こうした「ただ」と「細かな作法・儀則」の両立あるいは統合という共通の課題が存在し、それぞれの道の学人が稽古としてその課題に取り組まされるのは単なる偶然ではないだろう。
「ただ」も作法を無視したただの「ただ」ではないし、「作法」も「ただ」と無関係なただの「作法」ではないのだ。作法に裏打ちされての「ただ」であり、「ただ」が自らを象(かたど)りとして表現したものが「作法」であるというように、それぞれが他方を媒介として高次のものへと高められ、そこで両者が一つのものとして成立しているのである。だから、矛盾し合う「ただ」と「作法」はそのままでは敵対的な相互排除の関係にある他はないのだが、稽古を通して、それを相補的な相互扶助の関係へと高めていくことが学人に要求されていることになる。言い換えれば、矛盾を矛盾のまま、どちらか一方を安易に切り捨てることなく、高い次元へジャンプすることで乗り越え統合するというのが稽古の眼目であり、修行のポイントであるということだ。
お茶の稽古法として、「割り稽古」と言われるやり方がある。割り稽古とは、お点前をするために必要な、一連の所作を細かく分割して、基本になる動作を一部分ずつ丁寧に深く稽古することだ。本来のお点前はひとつらなりの動作の滑らかな連続であり、川の流れのようにどこにも切れ目や割れ目があってはならない。それが「ただ湯をわかし茶をたててのむばかり」と言われていることだ。書道で、筆を半紙の上に置いたら、最後まで気が途切れることなく、簡素にシンプルに「ただ一つ」の筆運びで書き上げなければならないのと同じである。しかし、だからといって、本来のお点前の一連の所作を通しで繰り返しているだけでは、浅いレベルから脱することはなかなか難しいという現実がある。そこで、「善巧方便」として編み出されたのが「割り稽古」という稽古法だった。
一連の所作の流れを人為的に「割って」、襖(ふすま)の開け閉め、お辞儀の仕方、立ち方、坐り方、帛紗(ふくさ)の扱い、帛紗のつけ方、帛紗さばき、茶器の拭き方、茶杓の拭き方、茶筅とおし、茶巾のたたみ方、茶碗の拭き方、お茶の点て方、……といったようにさまざまな基本の動作として取り出し、それを何度も繰り返し稽古して(それが「稽古とは一より習ひ十を知り十よりかへるもとのその一」ということだ)一つ一つの基本動作を深いレベルで習得していくことを目指すのである。そしてさらに今度はそれを再び、割れ目のない本来の一連のお点前の流れの中にもどし、いわば「通し稽古(演劇・オペラ・バレエなどで、途中で中断することなく、本番どおりに行う稽古)」をするのだ。この割り稽古と通し稽古の繰り返しによって、深いレベルでの流れるような一連のお点前が手に入るようになることが期待されている。
お茶の世界で採用されているこういう「割り稽古」のような稽古法を、只管打坐の稽古にも応用できないだろうかというアイデアがいつの頃からか、私の中に生まれてきた。しかし長い間、只管打坐をどう割ればいいのか、さらに割ったものをどう稽古していけばいいのかということについての満足のいくような見通しはなかなか浮かんでこないまま、時間だけが過ぎていった。そもそも只管打坐を「割る」などということが果たして許されるのだろうかという躊躇逡巡の思いがあったし、たとえ割れたとしてもそれを通し稽古としての只管打坐にきちんともどせるような稽古はどうすればいいのかということについて確固とした方針が立たなかったからだ。それが最近になってようやく、夜が明けて朝の光がさすような感じで、進むべき道筋が見えてきたのである。
只管打坐の世界では「坐ればもうそれでよい」ということが伝統的に言われてきている。それは、坐ることに技巧を持ち込んで優劣を競ったり、自己満足的な坐禅の進歩向上をめざしたり、人間的な観点から自分の坐禅を評価して一喜一憂したり、といった落とし穴に陥ることを防ぐためであったことは充分に理解できる。しかし、一方では、坐ることへの参究工夫をおろそかにする口実にもなってきたのではないか。坐禅が坐禅になっていないのに、「坐ればそれでよい」にあぐらをかいていていいのだろうか? それで果たして自分の人生が片づいているのだろうか? 本当の意味で、「坐ればもうそれでよい」ところに果たして坐れているのだろうか? そういう自己点検が必要なのではないか。少なくとも私にはそう思えるのである。
「坐ればもうそれでよい」という坐りを本当に坐り得るためには、過去の先人たちはいざ知らず、現代人のわれわれは通し稽古の只管打坐をするだけでは充分ではなく、只管打坐の割り稽古が必要なのではないか。そういういわば「別枠の補習」をしなければ、只管打坐への「はまりが浅い」ままでとどまってしまうのではないか。そういう問題意識をもって、思索したり、実践してきたことをこれからこの欄で少しずつ紹介していく。
あらかじめ断っておくが、通し稽古としての只管打坐そのものと、只管打坐の割り稽古は同じではない。只管打坐のときは、割り稽古はあっさりと放ち忘れられなければならない。そうでなければ、只管打坐の中で何かを内職的にしていることになって、ただ坐ることが現成しないからだ。割り稽古が育てた何かが通し稽古で自ずと現れてくることが大事で、そのためには、逆説的だが、割り稽古がそこでは忘れ去られていなければならないのだ。だから、割り稽古は只管打坐の中では使われることがないし、使われることがあってはならない。それは、現れなければならない。割り稽古とは、通し稽古で意図的には使われないことを一生懸命に稽古することであり、使わなくても通し稽古で自然に現れるような稽古をしなくてはならないのである。
[1] 「観」は、サンスクリット語「vipaśyanā」の訳。心を集中し特定の対象に向けて思念して悟りに至る方法一般をいう。「観」「観心」「観想」「観念」などの総称。観法はその対象によって、日想観(にっそうかん)・月輪観(がちりんかん)、九想観(くそうかん)や、仏・浄土の具体的様相を想起する初歩的な観想から、現象の背後にある空(くう)・無我などの哲理や真理そのものを観ずる高度なものまで、多種多様である。天台宗では、一念三千の相を観ずるなど、心的な自己体験を重視するところから、観心(かんじん)という。『岩波仏教辞典』より。
[2] 話頭[古則公案]に参究し工夫することによって自己究明をはかる。『岩波仏教辞典』より。
[3] 禅定(ぜんじょう)という一定の心理状態に到達するための瞑想技法に習熟することを目指す営み。
[4] 身を正して端(ただ)しく坐ること。『普勧坐禅儀』には「正身端坐して、左に側(そばだ)ち右に傾き、前に躬(くぐま)り後(しりえ)に仰ぐことを得ざれ」とある
[5] 統合失調症の研究者であった文化人類学者のグレゴリー・ベイトソンが使った言葉で、二つの矛盾したメッセージを出すことで、相手を混乱させる可能性のあるコミュニケーションのこと。一つのメッセージと、もう一つのメッセージに矛盾が起きていて、どちらに従ったとしても相手を満足させられない状態を作り出す。
[6] FASとは、形なき自己(Formless self)に目覚め、全人類(All mankind)の立場に立ち、歴史を越えて歴史を創ろう(Superhistorical history)という主張を意味する。



