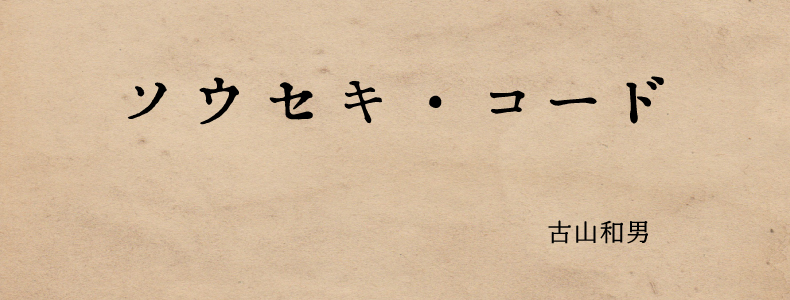夏目漱石の暗号
筆者は2017年10月に春秋社から『明治の御世の「坊っちやん」』(以下前書と記す)を上梓し、夏目漱石の『坊っちやん』が、能楽の様式を借りた筋立てであり、江戸の戯作の手法によって当局の検閲を出し抜き、強権的な政府を批判し攻撃する諷刺小説であったことを明らかにした。前書では、漱石が洒落・地口や漢字の読み替えなどによって、文字面の裏に本意を潜めてかなりきわどい政治風刺を世に発信していたことを、できるかぎり丁寧に読み解いたつもりだが、一方で紙幅の制約などもあり、その具体的な手法についての説明が十全に尽くせなかった部分があったことは否めない。
作者が本当に言いたいことは、たいてい表の物語の裏に隠されており、それを読み取る作業は、暗号解読にも似ている。地下に繋がる道に通じる秘密の入り口を見つけ、鍵となる言葉「コード」を手にしないと、隠された真実に辿り着く事はできないからである。こうした「コード」は、「真意を読み取るために必要である」と漱石自身が言う「文章の趣味」とは無縁ではないはずである。
本連載では、前書では漱石の真意の解釈に主眼を置いていたために不十分となっていた、あの手この手で韜晦され、隠蔽され、偽装されている漱石の本意に迫る暗号解読の鍵を紹介していく。万能なものはないとしても、さまざまな「ソウセキ・コード」がある中で、今回は「字余りの法則」、「んの活用」、「胃弱、胃カタル、胃潰瘍の原理」とも言うべき「コード」の有効性について検証する。
字余りの法則
和歌や俳句などの五七調(七五調)で、文字が5つや7つに余るものは「字余り」と呼ばれている。この「字余り」は明治の近代俳句や短歌成立以降と以前では意味が異なる。本来「字余り」は、母音のみのシラブルである「あ行」の文字を含む場合に許されるものであった。この場合、母音のみのシラブルが直前の母音と結合してその音が消え、字が増えても音は余らない。そして、字は余っても音は余らないので、2つのシラブル(2モーラ)を1拍とする、4拍子のリズムは揺るがず、拍節にうまく嵌る。しかし、近代の無制約な「字余り」はシラブルの音も増やすため、リズムが乱れ散文的になる。
こうした伝統的な「字余り」の規則については、本居宣長の『字音仮字用格』(安永5年)や富士谷成章『北辺随筆』(文政10年)などに定義され、橋本進吉の「国語の音韻構造と母音の特性」『国語音韻史の研究』(1941)、佐竹昭廣の「万葉集短歌字余考」『文学』(1946)でも論じられている。
百人一首にも収録されている藤原公任の有名な歌
滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ
の第一句、「たきのおとは」は6文字であるが、「の」と「お」が結合して
た き の お と は
ta ki no-o to wa
た き の ぉ と は
た き の と は
と5音で吟じられる。また、同じく百人一首の小野小町の
花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
の第一句「はなのいろは」でも、「の」と「い」が結合して、
は な の い ろ は
ha na no-i ro wa
は な の ぃ ろ は
は な に ろ は
と複合母音のように処理される。そうしないと破格となってしまうからだ。
このシラブルの結合は、五七調でなくても、日本語に脈々と受け継がれている現象である。「吾が妹子(わが・いもこ)」を「わぎもこ」とし、人名の「五十嵐(いが・あらし)」を「いがらし」、「渡会(わたる・あい)」を「わたらい」、「松浦(まつ・うら)」を「まつら」と呼ばせ、また地名の「青梅(あお・うめ)」が「おうめ(おーめ)」、「大原女(おおはらめ)」が「おはらめ」、「ザラ飴(ざら・あめ)」が「ざらめ」になり、「西郷どん」を「せごどん」と言うのもこの法則によるものである。
漱石の文に隠されている裏の本意を解読するための鍵の中には、この母音結合の原理に拠るものがある。
たとえば『坊っちやん』で「うらなり」が転勤させられるのは、〈山の中も山の中も大変な山の中〉の「延岡」の学校である。しかし、宮崎県の延岡は海に面しているから、山の中にはない。この「延岡」の学校がどこであるのかを明かす仕掛けが「赤シやツ」のいう〈土地が土地だけに〉という説明である。これはもともと「とちがあとちだけに」の「があ」が結合して「が」になった言葉であることに気が付けば、「土地が跡地だけに」と読め、「延岡」の謎が解ける。江戸の「延岡藩邸」の跡地にあったのは「貴族学校(学習院)」であり、そこの院長に任じられたのは乃木希典である。したがって、「うらなり」とは乃木を諷刺する人物であることが解るという仕掛けである(前書126~127頁)。
また、前書では「マドンナ」が「女」の姿で迷い出た霊であることを示唆したが(202~205頁)、これも字余りの法則によって説明することができる。
『坊っちやん』の「マドンナ」は、その出現が予告される釣りの場面(五)の
〈線香の烟の様な雲が、透き徹る底の上を静かに伸ばして行つたと思つたら、いつしか底の奥に流れ込んで〉
や、
〈水晶の珠を香水で暖ためて、掌へ握つてみた様な〉
という表現から受ける印象から、「数珠」が連想される抹香臭い不気味な存在であるが、字余りの法則でみても
ま ど ん な
ma do n na
ma do-o n na
ma do-u-o n na
ま ど う お ん な
となり、「迷女」(あるいは「魔道女」)であることがわかる。
漱石の小説では「女」と書かれた人物は幽霊、それも日露戦争で死んだ兵士の霊魂であることが多い。『吾輩ハ猫デアル』で旅順口が陥落した正月の街で苦沙弥先生が遭遇する「旅鴉の皺枯れた声の芸者」、『趣味の遺伝』の旅順で戦死した浩さんの「墓に現れる女」、『草枕』の池に飛び込む「那美」、『虞美人草』の「必死の紫の女」、『三四郎』で〈ちいとながしましょうか〉、つまり「血、いと流し、魔性化」と言いながら帯を解く「黒い女」や、舞台下手の橋懸りを渡って来て〈実は生つてない〉、つまり「実は生つてない」と名宜る「美穪子」、そして池に〈私?飛び込みませうか〉と言う「よし子」はすべて旅順で死んだ兵士の迷える霊であり、夢幻能のシテの役回りである。
んの活用
母音の結合が音の数を減らしてリズム整えるのとは逆に、日本語では拍数を増やしてリズムを調整するのに、無音の「長音」や「促音」や「ん」が用いられる。「ん」の文字は11世紀までは存在しなかったようであるが、日常会話や本読み、詩歌で「ん」の機能が活用されていなかったわけではなく、字に書かれていなくても、「ん」は上古の昔から言葉のリズムに貢献していたと考えられる。
能や歌舞伎など語りの日本語では「凄く」を「すんごく」のように言うことは珍しくない。東北の人が「自動車」を「ずんどうしゃ」と言うのは、「じどうしゃ」の強音の「ど」が拍の裏にきてシンコペーションのようになって収まりが悪いからである。京都の京嵐電鉄の停車駅「西院」は「にし」と仮名で表示されている。これは、「にしいん」の「しい」で母音が結合し、「ん」が書かれていない古い書き方なのであろう。
さて、「坊っちやん」が就職の「口」を求めて赴く海浜の〈針の先程小さく見える〉町があるという国は、原稿に最初に書かれた字が「◯国」と消され、「四国」と書き直されている。消された「?国」がどこであったかは、「四国」という糸口と「ん」の活用によって読み解くことができる。「凄く」を「すんごく」と読み、「至極」は「しんごく」でもあるということなら、「四国」は「しんこく」つまり「清国」であると読める。したがって「坊っちやん」は清国の、それも遼東半島の針のような先端にある「旅順口」の戦場に行ったことが解るのである(前書58~61頁)。
胃弱、胃カタル、胃潰瘍の原理
このコードは、「い」の字に限って加減し置換する細工である。これは漱石が生涯苦しんだ「胃」の持病に掛けた自虐的諧謔のようにも読み取れ、筆者はこれを勝手に「胃弱、胃カタール、胃潰瘍の原理」と呼んでいる。
『吾輩ハ猫デアル』では、唐突に「杉原」が「すいはら」、「蝦蟆」が「かいる」、「透垣」が「すいがき」と例を挙げて「名目読み」に言及している。現代でも「すみません」を「すいません」と言い、歌舞伎で「申した」を「申いた」などと言うが、本来「起こいて」であったのが「起こして」となった現代の言い方も、「い」の音の変形である。
『坊っちやん』では、女中の「清」が「坊っちやん」に〈あなたは結構な御気性〉と言うのは、「清」に身を窶した前ジテの孝明天皇が、「坊っちやん」であるワキの明治天皇に皇位を継がせたこと、つまり「気性」を「継承」と解する事が出来ることは前書でも指摘した(p.40~41)が、ここで「けいしょう」が「けしょう」と聞こえるのは「い」音が弱くなっていると言える。つまり「胃弱」である。
こうした「い」音の加減操作は、真意を隠蔽するための「騙り」の変換技法であり、「い」で「騙る」、つまり「胃カタル」であるとも言え、また、「い」音を融通無碍に変換し、「い」で「如何様」にも「如何様」ができるので、「胃潰瘍」でもある。
『坊っちやん』には〈母が病気で死ぬ二三日前䑓所で宙返りをしてへつついの角で肋骨を撲って大に痛かつた〉というところがある。狭い台所でわざわざ宙返りをすることに意味はなく、何かを当て擦っていると考えるのが自然で、ここは幕末の政治状況に言及している文と考えられる。
公武合体を推進する幕府への「宙返り」、つまり「忠節のお返し」として、孝明天皇の妹和宮が将軍の正室である「御䑓所」となるべく「へつついの角で」「嫁いだかどで」のことである。また「肋骨」つまり「胸部」が痛かったのであるから、「胸部が痛かった」「きょうぶがたいかった」、つまり「公武合体派が勝った」という地口で読める。この「母」とは、公武合体によって政治生命を失って都落した、三条実美らの御所の過激派攘夷論者の「おっ過さん」のことであろう。
「山城屋」の「やな女」も「いやな女」の「い弱」で「い」の一字違いである。これは旅順口の要塞に「上がれ上がれ」と多くの兵を肉弾突撃させて殺しておきながら、「砲弾をくれなかったから」と言い訳して、総参謀長の児玉源太郎に「女」と罵倒された第3軍参謀長の伊地知を示唆するものである。
また、「坊っちやん」が〈こんなのが江戸っ子なら江戸には生まれたくないもんだ〉と嫌うのは、自分が「江戸っ子」であると騙る「野だいこ」である。「野だ」は「坊っちやんに」「御国は?」「え?東京?」と聞き、「私もこれで江戸っ子でげす」と言うが、この「江戸っ子」は「スットコドッコイ、エードッコイ」の「馬鹿囃子」の「エードッコイ」の「い弱」「い騙る」による揶揄であろう。馬鹿囃子から「い」を加減すれば「スコットどこ?江戸っ子?」という地口になり、「野だ」がスコットランド出身のトマス・グラバーであることが示されている。〈江戸つ子は軽跳な風がある〉と「軽佻」ではなく「跳ねる」の字が使われているのは、この「馬鹿囃子」の踊りの諧謔を読者に気付かせるためであろう。
次回以降、本連載では前書で書き残したことを拾いながら、『坊っちやん』のみならず他作品も含めて、そこに秘められた漱石の本意が引き出せるように設けられている言葉の「糸口」について書いてみたい。