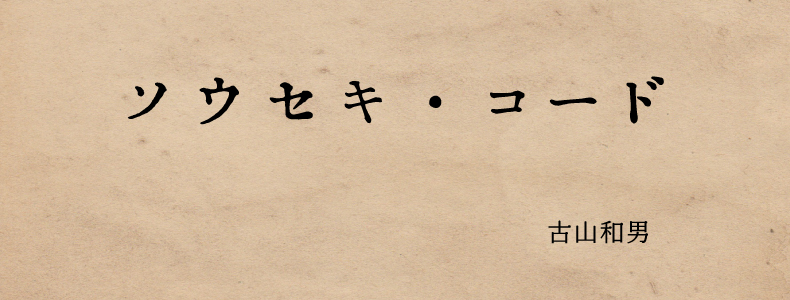二重の含意(ダブルミーニング)の仕掛け
ヨーロッパのアナグラムと地口
母音と子音の種類が少なく、その組み合わせが限定される日本語の文芸には、和歌の掛け詞や戯作の駄洒落などの同音異義を活かした多彩な技がある。しかし、アナグラムや地口で真意を隠し、その時々の権力に果敢な抵抗を試みてきたヨーロッパ文学の二重含意の伝統の術もこれに劣らない。
ローマ字を並べ替えて別の意味を作るアナグラムは、歴史の中で様々な工夫が凝らされてきた。なかでも「révolution française (フランス革命)」を「Un veto corse la finira (一人のコルシカ人の拒否権がそれを終わらせるであろう)」と読ませる例がよく知られている。この「コルシカ人」とは、言うまでもなく皇帝ナポレオンのことである。前書では「坊っちやん」を明治天皇に読み替えることができることを示したが、「エンペラー」の「坊っちやん」が「べらんめえ」である必然は、このアナグラムの一種として読めば納得できるかもしれない。
地口も、西欧では古代から継承され、幅広く使われている仕掛けである。『地口の技法、79の規則による言葉の精華』(The Art of Punning; the Flower of Languages; in Seventy-nine Rules, 1719年)なる書物が出版されていたくらいである。漱石が多大な影響を受けた諷刺作家のスウィフト、その喜劇をロンドンで観たトマス・シェリダンなど、錚々たる文士が関わったとされる。
この地口教本の序には、ローマ皇帝ネロの「典雅の指南者」であったガイウス・ペトロニウスを引用して、「地口は演芸娯楽を面白くするのに欠かせなかった」とある。漱石の『それから』で、高等遊民の代助に与えられている異名「 arbiter elegantiarum 」は、ラテン語で「典雅の指南者」のことであり、もともとはペトロニウスにつけられたものであった。
ペトロニウスは、ヘンリク・シェンキヴィッチの『クォ・ヴァディス』(1896年)の主要な登場人物である。漱石はロンドンでこの小説の英訳版を購入しており、蔵書の書き込みから、この小説を丹念に読んでいたこともわかる。漱石が『地口の技法』をも読んでいたかどうかは不明だが、西洋流の地口の技法については、漱石は留学中になんらかの形で学んでいたのではないか。そうでなければスウィフトらの真意は読み取ることはできない。
地口の規則
『地口の技法』では、 「鼠が絃楽器を恐れる理由は?」 「それはgut(catのもじり)が張られているから」 のような謎々や、 「legacy(遺産)」を「leg as he(彼のような足)」 「grape-lover(ぶどう好き)」を「gray plover(灰色の千鳥)」 のように読み替えるもの、 「born in Bark-Shire(バークシャー生まれ)」を 「bark(吠える)」のは「bitch(雌犬)」という連想から 「a son of a bitch(あばずれ女の息子)」に読み解く例など 様々なものが挙げられている。 英語の洒落だけでなく、 フランス語の「champagne」を英語風に「シャンペイン」と読んで「shame pain(恥ずかしい痛み)」と解くような、外国語との組み合わせも許されている。 漱石の小説でも、外国語を洒落の鍵にしているところがある。「坊っちやん」が天婦羅を注文して平らげる話は、ロシアの戦艦群の撃破を命じたことを言うものである。それが解るのは、「注文」の英語「order」は「命令」の意味もあるからである。(前書24ページ)
「坊っちやん」が嫌う「野だいこ」は「野の太鼓持ち」、つまり「野交幇間」であるから「砲艦外交」に長けた「英国人」というわかりやすい洒落であるが、釣りの場面には「野だいこ」が〈糸丈でげすと顎を撫でて黒人じみたことを云った〉とある。「玄人」ではなく、あえて「黒人」と書かれているのは、「野だ」が「黒人」を奴隷にして畜生のように扱った「白人」であること伝えるためであろう。そしてこの白人は「坊っちやん」が〈蓄生、此蓄生〉と擲きつけた卵で「顔中が黄色」になる。この下司の「野だ」の口癖は「guess(推察する)」の「げす」でもあり、〈御気の毒さま見た様でげす〉は、「気の毒」が「生の毒」であるなら、「I guess it might be genuine poison.」と「坊っちやん」の父の死が毒殺であったことを仄めかしているようでもある。
また、〈こんな大僧を四十人も前へ並べて只一枚の舌をたゝいて恐縮させる手際はない〉も英語の地口で、「日本軍の単発銃では、機関銃を備えている大柄なロシアの兵隊には歯が立たない」と読める。「舌」は「tangue」であり、鉄砲の尾部の金具を指す「tang」は引き金などの発射駆動部を含むこともあったからである。『三四郎』の「ベルがちんちんちんちん」と鳴る電車が「機関銃」のことであるのは、「ベル」が「ベロ」、つまり「タング」であるからであろう。電車は「チンチン」と発車しても、「チンチンチンチン」という連続音で発射しない。
『地口の技法』29番の規則では、「顔の真ん中に卵を投げつけられた晒者の名」として「Alexandrinos」を挙げ、「all-eggs-and-dry-nose」の地口であると説明する。「dry-nose(乾いた鼻)」を「晒す」「顔の中」から想像しなければならないので少々難度が高いものの、30番目の規則では「Tom where are you? 」の音が、「temeraia(軽率な)」というラテン語に読み替えられるというほど許容度が広いのが地口である。
それに較べれば、『坊っちやん』の〈前䑓所で宙返りをしてへつついの角で肋骨を撲つて大に痛かつた〉が「御䑓所へ嫁いだかどで公武合体が勝った」となるのも、「肋骨を撲って痛かつた」から「胸部が痛かった」さらに「公武合体勝った」を導き出すところは高度であるが、「い」を移動させる簡単なアナグラムを手掛りとすれば辿り着ける(本連載第1回を参照)し、「坊っちやん」が赤シやツに誘われる釣りで設定されている海の深さの「六尋」を「六尋」と読んで、明治天皇の「睦仁」に結びつけることなど、飛躍でも何でもない。
言葉の秘宝を隠す
隠された意図を解読するヨーロッパの言葉の秘技は「treasure trove(宝を探す)」の意から「トロバール・クルス」とも呼ばれた。これは教会の異端審問や火炙りから命と自由、良心や組織を守るためにトロバドゥールやトルヴェールなどの吟遊詩人によって歌にされ、人文主義者や科学者、自由主義者たちの結社などに受け継がれた二重含意の仕掛けである。特定の人々にだけに解るこのような閉鎖言語を熟知し、秘密結社的な作品を数多く書いた作家としてはジュール・ヴェルヌがよく知られている。
『坊っちやん』の「赤シやツ」が山県有朋を当て擦ったものであることは前書(第3章)で示したとおりだが、「西人之ヲ称シテ血税トイフ。ソノ生血ヲ以テ国ニ奉スルノ謂ナリ」の文言が物議をかもした「徴兵令」を公布した人物であり、日露戦争で兵士に大量の流血を強いた参謀総長を「赤し奴」とした漱石の発想は、ヴェルヌの『征服者ロビュール』の名「Robur」がラテン語の「rubor (赤、赤面、恥辱)」を示唆するのと酷似している。
ヴェルヌを崇拝し、言葉の秘法を極限にまで突き詰めたのが音楽家でもあったレーモン・ルーセルである。その「Les letures du blanc sur les bandes du vieux billard (古ぼけた玉突台のクッションに白墨で書かれた文字)」の「billard (ビリヤード)」の1文字を変えて「pillard(簒奪者)」にするだけで「年老いた簒奪者の一派について書かれた白人の手紙」になるメタグラムが有名だが、他にも
J’ai du bon tabac dans ma tabatière
(私の煙草入れにはうまい煙草がある)
に
jade tube onde aubade en mat à basse tierce
(硬い玉、管、波紋、3度音程を下げて不透明にされた夜明けの歌)
を隠した技巧は、地口としてよく引用される例である。
ちなみにこの「aubade(夜明けの歌)」は、オック語で歌われたカタリ派の「夜明けの歌」、トロバドゥールの「alba(アルバ)」を思い出させる。
このように文中に秘宝を隠す創作には、人並み外れた柔軟な発想と豊かな想像力が求められる。門下の森田草平が「直覚力がほとんど病的に発達していたのは、連想と推理の力が異常に秀でていたためである」と書いているから、漱石がこの技法の天才であったことは間違ないであろう。そこに気付かず、「『虞美人草』は美文に溺れた失敗作」などと評する人がいるなら、その人たちこそ自らの想像力の欠如、直覚の鈍さを自覚し反省すべきである。
そこに秘められている宝を見つけられなければ、『虞美人草』などは冗長な駄作に思えても無理もない。この小説の秘密の宝に到る扉の鍵は、文中に一度しか出てこない「虞美人草」であろう。それは、死者の枕頭に立てられた屏風に〈吉野紙を縮まして幾重の襞を、絞りに畳み込んだ様に描いた。色は赤に描いた〉花である。英国ではこの花を「field poppy」つまり「 戦場の芥子」と呼び、11月11日を戦死者追悼の「ポピーの日」としている。この日、式典の参列者は「縮ました紙を畳んで皺をつけた赤い造花」を襟に付け、慰霊碑にはこの花輪が供えられる。〈純白と深紅と濃き紫のかたまりが逝く春の宵の灯影に、幾重の花弁を皺苦茶に畳んで、乱れながらに、居を欺く風情は艶とは云へ、一種沃沙な感じがある。余の小説が此花と同じ趣きを具ふるかは〉がこの作品の連載の予告であるから、「逝く」春の「紫」とは、白を赤に染めた藤尾の「必死の色」なのであろう。
地口の伝統は現代にも引き継がれ、日本でも確実に定着している。SNSに◯◯を褒め讃える「◯◯△」という投稿があったと聞く。つまり「◯◯三角形」で、「◯◯さんカッケー」「◯◯さん、格好いい」であり、「kakkoui」の3つの母音「oui」を1音にする「字余りの法則」(第1回)によるものである。『坊っちやん』の〈燗徳利が頻繁に往来し始めたら、四方が急に賑やかになった〉の「燗徳利」は、これと同様に海軍軍令部の「艦隊送り kantaiokuri」の3音「aio」をまとめたものである。(前書 149-150ページ)