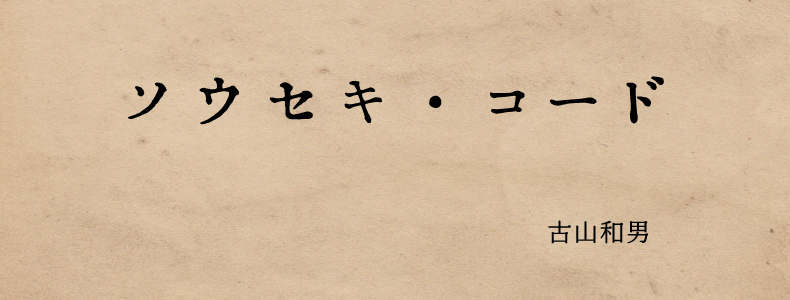手がかりは不自然と不整合にあり
『第9交響曲』の暗号
ベートーヴェンは、『第9交響曲』の第4楽章の冒頭の断頭台のファンファーレが鳴らされた直後の口上、「レシタティーヴォ」と呼ばれる「一人語り」を、「言葉を語れない」低音の絃楽器群が寄って集って斉奏させている。言葉のない「語り」という発想自体が自己矛盾であり、拍節リズムのない「語り」を楽器の集団に演じさせるのは奇妙でもある。この不自然さは作曲者によって仕組まれた謎掛けである。そして、この口上の音形が後でバリトン独唱によって「おー同志たちよ、これらの調べではなく」と朗詠されて始めてその意図がわかるようになっている。そもそも「交響曲」あるいは「シンフォニア」とは「音を共振させる」が語源の「器楽曲」を意味する言葉であるのに、この曲には独唱、重唱、合唱の声楽が付けられているのは奇怪なことではないだろうか。
バリトン独唱が「これらの調べではなく」と詠唱することで否定しているのは、それまでに演奏された第1〜3楽章のことであるが、これらは自由を抑圧する「旧体制」と「暴力的独裁」を意味する音楽パロディである。このことに気づけば、言葉を奪われた「口上」が「何も言えない」という無言の抗議であることが理解できよう。
フランス革命の影響を直接受けた都市のボンから反革命勢力の牙城ウィーンに移ったベートーヴェンは、音楽家として活動する一方、各地の自由主義者や秘密結社メンバーと連絡を取り合う革命家でもあった。当時の文学者や芸術家の多くがそうであったように、彼は階級や国籍を超えた幅広い交友人脈を生かしたインテリジェンス(諜報員)としても活躍していた。しかし、ナポレオンが失脚すると同時に、メッテルニヒの政権下で自由を奪われて監視される立場に陥った。この反動体制の厳しい検閲を出し抜いて、人々に体制批判の本意を伝えるためにベートーヴェンが敢行したのが、不整合の違和感を暗号とする音楽による諷刺であった。壮大な『第9交響曲』には、「器楽」による「語り」、そして「声楽」のある「器楽曲」という二つの自己矛盾にとどまらず、他にも当時の常識から逸脱した奇妙な点が少なくないが、それらも革命的なメッセージを暗に伝える仕掛けとして理解できる。
意図された誤謬と不規則
ジュール・ヴェルヌの『クローヴィス・ダルダントール』(1896)は、アルジェリアのオラン(oran)への旅行記である。この物語の最初の寄港地のマジョルカ島のパルマのリエラ(Riera)溝渠がリエナ(Riena)と表記されているのは、この小説の本当の舞台を伝える細工であると言われている。「オラン(Oran)」は「黄金の中(アンオル/アノル)(en or)」を、そして「リエラ(Riera)」 ⇒「リエナ(Riena)」は「レンヌ(Rennes)」をほのめかす。つまり本当の舞台はフランス西南部ラングドック地方の古都、テンプル騎士団とカタリ派の本拠であったレンヌ・ル・シャトーであり、この物語がここに隠されたメロヴィング朝の黄金探しへの旅であることを示している。活字が似ている「r」と「n」をすり替えるのはよく使われる手であり、奢侈贅沢が禁じられていた英国の清教徒革命の時代に、「宮廷舞踏(courtly dance)」の教本を「田舎踊り(country dance)」として出版した業者もある。
旅順口の二百三高地で次男を戦死させた乃木希典は、「二〇三」を「爾霊山」と詩に書いて戦死者を慰霊しているが、この戦場で命を落とした兵士の亡霊である『三四郎』の美穪子は、
「爾霊(nirei)」
に r → n および n → m の変換に加えて字余りの法則(第1回参照)を適用することで
「美穪(mine)」
となったと読める。「穪」の字が「ノ木(乃木)」と「爾」から成っていることもヒントであろう。
レンヌ・ル・シャトーで発見された羊皮紙文書『ヨハネ福音書』の第12章は、ずり上がって不揃いに書かれている文字を拾って並べることで解読可能となる古典的なコード表であると言われているが、『三四郎』(八章九)の冒頭は、漱石自身による「一字下ゲニセズ」という奇妙な注意書きによって、文頭で「美穪子」の活字がずり上がる仕掛けになっている。この規則破りは、美穪子がフワフワと浮き上がる幽霊であることを伝えるため敢えて指示されたものである。浮き上がることによって、比較的背の低い美穪子でも、その直後に背の高い三四郎の耳に口を近づけたり肩に肩で触れることができたのである(前書55ページ)。
このような奇妙な不整合にこそ注目する必要がある。事実や常識と違う設定、奇妙な名前、間違って書かれた綴り字などを謎解きの鍵にする仕掛けは、『第9交響曲』のように弾圧に抵抗し、検閲を出し抜くために考え出されたものであることが多いからである。また、コード解読の糸口は、このような「話の筋の破綻や矛盾」だけでなく、「馬鹿げた無駄話」であることもある。例えば、『坊っちやん』で「山嵐」が腕の力瘤を見せるところ、〈力瘤がぐるりぐるりと皮になかで廻転する〉、〈かんじん縒りを二本より合わせて、この力瘤の出る所へ巻つけて、うんと腕を曲げると、ぷつりと切れるさうだ〉がその例である。「砲弾に廻転をつけて射程を延ばし命中率を上げた薩長軍のアームストロング砲」、つまり「腕強(arm strong)」にやられた会津藩主の松平容保が「山嵐」であるからである。「かんじん縒り」が出てくるのは、この新兵器は、金箔和紙の「観世縒り」を織り込む「佐賀錦」で知られる藩から借りたものであることを知らせるためである。
不整合だらけの『草枕』
俳句、漢詩、英詩、美術や文芸、それに芸事の蘊蓄、及び警句が満載の『草枕』であるが、明らかに間違っている記述や矛盾もさりげなく散りばめられている。
〈こゝから那古井迄は一里足らずだつたね〉、〈二十八丁と申します〉のやり取りから、茶店から宿までは「28丁」(約3km) だということがわかる。しかし、画工の宿への到着については、〈夜の八時頃であつたから、家の具合庭の作り方は無論、東西の区別さへわからなかつた〉と書かれている。茶屋の景色は夕暮れではないから、山中で狸にでも化かされていたのであろうか。『琴のそら音』の『浮世心理講義録』なる架空の書には〈狸が人を婆化かすと云ひやすけれど、何で狸が婆化かしやせう。ありやみんな催眠術でげす〉とあるように、夜の宿に始まる一連の出来事は催眠術にかけられた夢幻のようである。
宿では「紙燭」を持った「小女」が廊下を廻って画工を部屋まで案内するが、いかに山中でも明治の世に紙燭は時代錯誤であろう。宿の女将の那美が、画工と茶店の婆さんが交わした話の内容を、その場に居たかのように知っているのも不気味である。婆さんがすらすらと詠じた〈あきづけば、をばなが上に置く露の、けぬべくもわは、おもほゆるかも〉を、那美が深夜に繰り返し歌うのはとくに奇怪である。これは馬子が城下から帰って来て、茶店の情報をもたらすことができる以前の行為でだからである。
「をばな」と「露」なら粋筋で唄われる「露は尾花と寝たと言い、尾花は露と寝ぬと言う」が思い出される。この場合、芒の「尾花」は女であるが、「をばな」は「雄花」でもあり得る。「けぬべき」の「けぬ」は、「消えぬ」の「kie」が「ke」となった字余りの原理(第1回参照)によるものである。
〈上方の検校さんの地唄にでも使われそうな太棹〉ともあるが、太棹は義太夫に用いられる三味線である。
宿の欄間の額の「竹影払階塵不動」を、画工は「黄檗の高泉和尚の筆致」と断じているが、この語は明末期の儒者洪自誠の『菜根譚』一節であり、18世紀に日本で広まった儒仏道の三教を融合したこの処世訓を、隠元に招かれて渡来した17世紀の高泉性潡が揮毫する筈はない。
那美について、〈あの女を役者にしたら、立派な女形が出来る〉とあるが、女形になるのは「男」である。
また〈二三年前宝生の舞台で高砂を見た事がある。その時これはうつくしい活人画だと思つた。箒を担いだ爺さんが橋懸りを五六歩来て、そろりと後向きになつて、婆さんと向ひ合ふ〉には決定的な誤謬がある。能楽の『高砂』で「翁」の「尉」が持つのは箒ではなく「竹の把」である。この爺さんの「尉」と婆さんの「姥」の正体は「住吉」と「高砂」の「相生の松の精」であり、両者は同体であるが、先に登場するのは婆さんの方である。
夢幻能として読む『草枕』
画工は旅中の出来事と、出逢う人間を「能の仕組と能役者の所作」に見立てると言っている。『高砂』の舞台について〈余の席からは婆さんの顔が殆んど真むきに見えたから、あゝうつくしいと思つた時に、其表情はぴしやりと心のカメラへ焼き付いて仕舞つた。茶店の婆さんの顔は此写真に血を通はした程似て居る〉のであるから、この小説は、茶屋の婆さんを前ジテの「姥」に見立てる夢幻能として読める。
すでに前書『明治の御世の「坊っちやん」』の序章で夢幻能については触れているが、ここでも簡単に説明しておこう。夢幻能とは能の形式の一種で、諸国一見の僧であるワキに、亡霊のシテがその苦しみ妄執を語って舞うことで心を鎮め、冥界に帰って行くという筋が一般的であり、亡霊は先ず身を窶した姿の前ジテとして現れてワキを案内し、その後に正体を現した後ジテとして現れる。この前と後の幕間ではアイの狂言が演じられる。
『草枕』では亡霊として現れるシテは那美である。前ジテが茶店の婆さんであれば、『高砂』の「姥」である「婆さん」と那美は同一の霊ということになる。そして「姥」と同体の「尉」も那美と同体である。「掃く」箒を「尉」が「掃射」する鉄砲のように担ぐのであれば、その正体は軍人の「尉官」であろう。漱石は『坊っちやん』で、鉄砲足軽使いの「小使」に箒を担がせ、武器商人の「野だいこ」にも宴会で箒を担ぐ狂態を演じさせている。とすれば『草枕』で「正面を向いてぴしゃりと焼きついて血が通わなくなった尉」とは、那美という女の姿のシテとなって現れた亡霊の中尉か少尉であり、この「尉官」は「松樹の下」の正面の窪地で戦死した軍人なのであろう。このように夢幻能の世界で考えれば、怪奇に見える現象も那美の奇矯な行動も、人物のすり替わりも不思議ではなくなり、誤謬や齟齬と見えたことが合理的に説明でき、仕掛けられた謎のすべてが解ける。
漱石には「宿乞う僧を、紙燭して見る」という俳体詩の1句があるが、「小面」を着けた「小女」に案内される画工が、まさに霊界に誘い込まれたワキの僧である。「猫の額のよう小さな松永町」の床屋だけが江戸庶民の方言で演じるのは、この役者が能舞台で若松が植えられた狭い「橋掛かり」で狂言を演じるアイであるからであろう。
そして次の謎が生まれる
画工はこの夢幻の「蚊の国」「蚤の国」、つまり「彼の国」「黄泉の国」の彼岸から此岸の「現実世界」の娑婆に舟で帰って来る。宿の扁額の「高泉」とは「黄泉」を意味するものであったのであろう。
舟の上で〈「あの山の向ふを、あなたは越して入らしつた」と女が白い手を舷から外へ出して、夢の様な春の山を指さす〉のところは、「那美が」ではなく「女が」と書かれている。漱石が「女」と書くのは「女の姿をした亡霊」の意味である。「夢のような春の山」が「女」の棲む夢幻界であれば、〈「日影ですかしら。禿げてるんでせう」「なあに凹んでるんですよ。禿げて居りや、もつと茶に見えます」〉というやりとりは奇妙である。「女」は天狗岩のところが禿げていることを最もよく知る者であるからである。ここに最大の謎が掛けられている。
画工が夢幻界から解放されたのは、亡霊の訴えを聞いて那美の悲劇の真相を理解し、その心に寄り添って「憐れ」を感じたからである。その時に、茫然とした那美の一面に「不思議にも今までかつて見た事のない憐れ」が浮き、画工の胸中の画が成就する。それは発車した汽車の窓に〈茶色のはげた中折帽の下から、髯だらけな野武士が名残り惜気に首を出した〉ことによって引き起こされる。
この野武士は那美の別れた亭主であるが、「女」は、先にその麓でこの男に会った場所である「凹んだ禿げ茶」の「天狗岩」を指すことで「茶色のはげた中折帽」を予告している。あるいは、「女」を死なせた責任を負って「首を差し出す」よう叱責された「禿茶瓶」が当時実在したのかもしれない。『趣味の遺伝』には〈亡者は古伽藍の剥げかかった額の下を潜る〉とある。「ガランドウ」とは参謀総長であった山県有朋の渾名であり、「剥げかかった額」は「禿げかかった額」と読める。この汽車の男の謎は、汽車の場面から始まる『三四郎』に持ち越され、そこでシテは「美穪子」として再び現れ、責任を取らない「茶色の中折帽」の男が断罪され、「女」の画が披露されることになる。