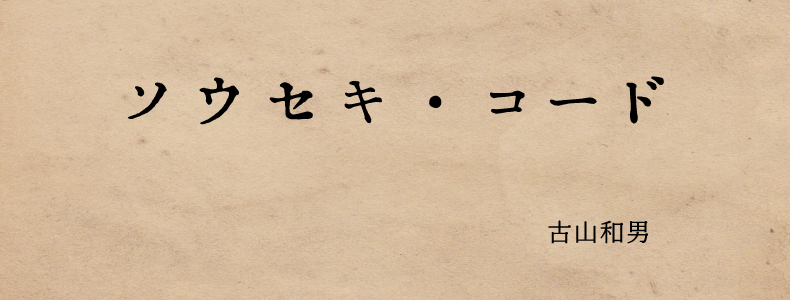本歌取りの手法
『ローマ人の休日』
日本では『ローマの休日』の題名で人気のあるウィリアム・ワイラー監督の映画『Roman Holyday』(1953)は、正確に訳せば『ローマ人の休日』である。「ローマ人の休日」とは古代ローマ市民が熱狂した円形闘技場での剣闘士(グラディエーター)たちの殺し合いの観戦のことを言うが、この映画でグラディエーター・サンダルを履くのは宮殿から逃げて来た王女である。
新聞記者が取材対象の女性と恋に落ちるという筋は、スクープ欲しさに記者が富豪令嬢の逃避行に同行するフランク・キャプラ監督の映画『ある夜の出来事(It Happened One Night)』(1934)の焼き直しである。しかし、『ローマ人の休日』の主題はキャプラのコメディとは全く別の次元にある。
和歌の「本歌取り」は、往年の秀作を引用、あるいは借用して擬えることによって感興を得る手法であるが、借りた本歌とは主題を違えて新しい境地を切り開くことが求められる。作品の筋を借りて主題を違えるという意味では、この『ローマ人の休日』は『或る夜の出来事』を本歌取りした映画と言えるかもしれない。記者とその取材の獲物との恋愛という表面の話に隠されたこの映画の真の主題は、2千年の放浪の末にユダヤの民が実現したイスラエルの建国であるからだ。
レイモン・ルーセルは「3度音程を下げる歌」と言っているが(第3回)、この映画のテーマ音楽は、ユダヤの民の悲願を歌う「望み」を「3度上げた」旋律になっている。このことから、ヒロインのアン王女はユダヤ民族の「望み」の象徴であることがわかる。王女が「奇跡の壁」の前で祈る写真がこの物語の「ハイライト」であるのは、この「壁」がエルサレムの「嘆きの壁」を思わせるからである。
また、レセプションで王女がドイツ人の挨拶を受けるとき、靴と眼鏡が床に転がり、床屋では女性の髪が集められる。これら「靴」「眼鏡」「髪」は、大量虐殺を伝えるコードとして絶滅収容所で展示されている物である。髪を切り落とす床屋が独裁者であることは、床屋と独裁者が入れ替わるチャップリンの映画『独裁者(The great dictator)』(1940)を知っていれば容易に気付くことができる。ユダヤの神殿を破壊し王国を滅ぼした皇帝ティトゥスの征服を記念する凱旋門やコロッセウムが旧跡として遺され、ユダヤ教徒を迫害したカトリック教会の本山がある永遠の都ローマには遺恨があっておかしくない王女である。しかし彼女は、最後に「すべての意味でローマが好き」と発言する。歴史的な怨讐を乗り越えるという未来志向のこのメッセージが、『或る夜の出来事』を本歌取りしたこの映画の主題なのであろう。
漱石の小説の本歌取り
漱石の小説にはその筋書きや構成を他の作品から借りているものが少なくないことは知られており、漱石が過去、あるいは同時代の作家の小説を借用した「本歌取り」をしていることは事実である。「小説の感興は只漫然と湧き、物になるのは百に一つ位であり、天来のインスピレーシヨンは棚の上の御牡丹と同じ事で当てにならないから、人巧的にインスピレーシヨンを製造する」(明治39年の虚子宛の手紙)の意味は、小説の発想を他に求め、それを換骨奪胎した創作を行うということでもあろう。「人巧的にインスピレーシヨンを製造する」ことが「本歌取り」を意味しているものだとしても、漱石の作品は「本歌」の単純な焼き直しではない。実際、漱石が「本歌取り」をしたと考えられる作品をみると、「本歌」からの借用はしていても、「本歌」とは似ても似つかない表現と主張となり、話の結末も全く異なっている。この「本歌取り」をどのように考えるかが、漱石小説の秘密を解く前提となる。
誰の何の作品を「本歌」として借りて小説を書いたか、このことを突き止めること自体は研究として非常に興味深い。しかし、表の物語の裏に隠された漱石の趣意が何であるかを洞察、解明して、理解しなければ、漱石の作品を読んだことにはならないであろう。それは、『ローマ人の休日』を『或る夜の出来事』の単なるリメイクとして観るのでは、ワイラーら製作者たちの意図が読み取れないことと同じである。
『草枕』(六)で
〈己れはしかじかの事を、しかじかに観、しかじかに感じたり、その観方も感じ方も、前人の籬下に立ちて、古来の伝説に支配せられたるにあらず、しかし尤も正しくして、もつとも美しきものなりとの主張を示す作品にあらざれば、わが作と云ふを敢えてせぬ〉
〈此心持ちを如何なる具体を籍りて、人の合点する様に髣髴せしめ得るかが問題である〉
と書いた漱石である。誰の作品であれ、その筋や設定、あるいは言葉という「具体」を本歌として借りるのは、その二番煎として改作するためではなく、そこに忍ばせた「最も美しく正しい主張」を髣髴させるためである。そして、この髣髴せしめられる主張を読み取るには暗号解読に似た作業が必要となろう。
『三四郎』のストレイシープ
漱石は『三四郎』を〈たゞ口の内で迷羊、迷羊と繰り返した。〉で終わらせている。「迷羊」と繰り返した三四郎の真意はおろか、この言葉の意味も説明されていないので、この幕切れは物語としての完結感が乏しい印象を与える。
この「ストレイシープ」がこの小説に隠された真実に到る鍵である。
谷中の小川の傍を三四郎と歩いていた美穪子が口にするこの語は、ロバート・ブラウニングの詩『炉辺(by the Fireside)』から採られているという指摘がある。この詩は秋の野中を一緒に歩いて心の距離を縮める男女を語る独白であり、散策の状況がよく似ている中での「ストレイシープ」であるから、ブラウニングが引用されているという説には一定の説得力がある。しかし、この小川の場面は単なるブラウニングのリメイクではない。〈解る解らないは此言葉の意味よりも、寧ろ此言葉を使つた女の意味である〉とあるから、本歌取りされた「ストレイシープ」は、これを使った美穪子が何者であるかを知らせる言葉と捉えるべきである。美穪子の〈迷へる羊 ─── 解つて?〉の「───」と伏せられた謎掛けの答えは、「この言葉を使った」美穪子自身であることを暗に伝えている。〈ヘリオトロープの罎。四丁目の夕暮。迷羊。迷羊〉の「ヘリオトロープ」「四丁目」に関わるのも美穪子である。
ラファエル前派のウィリアム・ホルマン・ハントの絵画『我が英国の海岸』に描かれている羊も「ストレイシープ」と呼ばれる。英国の宗教的危機に警鐘を鳴らす作と言われ、神に捧げられる「犠牲」を暗示するこの絵画は、漱石がよく訪れていたテート美術館に当時から展示されていた。
つまり、漱石は「ストレイシープ」の語を、男女の散歩という表の話ではブラウニング、美穪子が犠牲であるという裏の意味の暗示のためにはハントから借りているようである。
〈実は生つてないの〉と登場することからも解るように、美穪子の正体は亡霊、しかも日露戦争の旅順口で戦死した兵士の霊魂である。したがって、この「迷女」の美穪子の言う「迷羊」は、行方もしれぬ兵士の迷える霊魂と読める。
「私にお捕まりなさい」と言う三四郎に美穪子が飛びつくのは、兵士の亡霊が三四郎に「取り憑いた」ことを示唆するものであるが、ここでも美穪子は口の内で「迷える羊」と言う。美穪子は香水の「ヘリオトロープ」を白い手帛で三四郎に嗅がせ、敬礼をして消え去るのであるが、この香水は、戦死した遺体が異臭を放たないよう、出征する2人の息子に最高級の西洋香水を携帯させた母親を思い出させる。それは旅順口で膨大な犠牲を出した第3軍司令官乃木希典の妻静子である。そして、その息子の勝典、保典の兄弟は2人とも国の犠牲となったことを国民の誰もが知っていた。
『倫敦塔』から『明暗』まで
〈憂の国に行かんとするものは此門をくぐれ。
永劫の呵責に遭わんとするものは此門をくぐれ。〜〉
これは『倫敦塔』で引用されているダンテの『神曲』「地獄篇」の一部である。漱石はここでもダンテを論じているわけではない。漱石自身が〈実のところ過半想像的〉と書いているように、短編小説『倫敦塔』は実在する歴史的建造物についてではなく、〈二十世紀の倫敦が我が心の裏から次第に消えると同時に眼前塔影が幻のごとき過去の歴史を吾が脳裏に描き出してくる〉想念を語るものである。これは〈九段の遊就館を石で造つて二三十並べてそうしてそれを虫眼鏡で覗いたら或はこの「塔」に似たものは出来はしまいかと考へた〉幻想である。「遊就館」とは戦争記念物を展示した靖国神社の施設である。それを「二三十」並べて「虫眼鏡で覗いて」拡大するのであるなら、その言わんとするところは想像できよう。ロンドン塔の刑場の露と消えた若者の何千何万倍もの数の若者たちを屠殺したことで「永劫の呵責」に遭うべきは、〈眼の凹んだ、煤色の、脊の低い斬首役人〉の語が仄めかす人物なのであろう。
漱石最後の作品『明暗』の冒頭で貸し借りされる、漢詩集の『明詩別裁』と『呉梅村詩』が、この小説の展開を暗示していることを指摘する研究がある。『明詩別裁』と言えば高啓(青邱子)であるが、この人物が詩によって妻を得たように、主人公の津田由雄は漢詩集を縁にお延と結婚するからである。高啓は明の始祖朱元璋の専横を批判する諷刺詩を書いて車裂きの刑に処せられた詩人であり、『呉梅村詩』の呉梅村も、征服者の満州族によって仕えていた明朝の皇帝を殺されながら、清王朝に召し出された不本意と屈辱、新政権に対する反感を長編詩に託した宮廷詩人である。したがって、この2つの漢詩集は、粗野で強権的な新政権を批判する反体制の書である。だからこそ、教養ある旧幕臣の津田とお延の父親たちが明治の世で愛読しているのである。このような設定は、明治政府に仕えるのを潔しとしなかった漱石の反権力的な思いが、この小説に隠されていることを予告するものであろう。
『それから』の主人公代助は「典雅の審判者」と呼ばれているが、この名は西洋の諷刺文学の元祖のペトロニウスに由来するが(第3回参照)、その主著『サテュリコン』を最初に日本に紹介したのは、他ならぬ漱石自身であり、『吾輩ハ猫デアル』の参考にされたローレンス・スターンの『紳士トリストラム・シャンディの意見と生涯』やカーライルの『衣装哲学』も、この書の流れを汲む諷刺文学であると言われている。
したがって、『明詩別裁』や『サテュリコン』『紳士トリストラム・シャンディの意見と生涯』も、漱石の小説の本歌であると言うことができよう。漱石の作品の本歌が何であるかが特定されることは興味深いことである。しかし、そのことをただ指摘するに留まるのであれば、作者の真意を理解することはできない。その理解を助けるため、それぞれの作品には手掛りが作者によって与えられている。例えば『それから』では、代助が欄間の「ワルキューレ」を眺めるところ、『明暗』では、津田由雄の「津田由」が御霊文楽座の「竹本津太夫」に通ずるところなどに求められるのかもしれない。「ワルキューレ」は、戦場で勇者の霊魂を拾い集める戦いの女神であり、「御霊文楽」は、初期の小説が幻想怪奇文学の扱いであった漱石の「怨霊文学」に掛けられているのかもしれない。