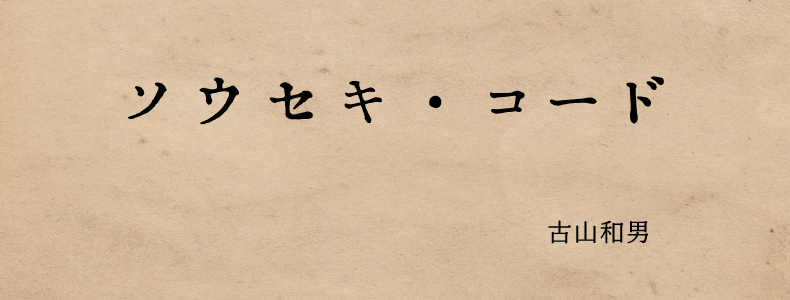本音が聞こえるトボケ
猫もトボケる
『吾輩ハ猫デアル』(七)で、洗湯を偵察に行った猫は、裏口に薪と石炭が積んであるのを見つける。
〈忍び込んで見ると、左の方に松を割つて八寸くらいにしたのが山の様に積んであつて、その隣りには石炭が岡の様に盛つてある。なぜ松薪が山の様で、石炭が岡の様かと聞く人があるかも知れないが、別に何の意味もない、只一寸山と岡を使い分けただけである〉
〈別に何の意味もない〉と恍けているが、わざわざ書いている以上、意味がないわけはない。猫が〈口にするを憚かるほどの奇観だ。この硝子窓の中にうじやうじや、があがあ騒いでいる人間はことごとく裸体である。〉と言うこの「洗湯」は、野蛮で赤裸々な営みが行われる「戦闘」のことである。ここの「松薪」の山は日本軍が強襲に失敗して夥しい犠牲を出した旅順口の「松樹山」であり、「石炭」の「岡」は要塞群の「炭」つまり「隅」にある標高203メートルの「後石山」、「二百三高地」の仄めかしである。
洗湯は壮絶な大混洗で、〈突然無茶苦茶に押し寄せ押し返している群むれの中から一大長漢が〉〈うめろうめろ、熱い熱いと叫ぶ〉のに対して、〈湯槽の後ろでおーいと答えた〉「三介」は逆に、石炭を釜に放り込んで火勢を煽る。
「三介」は風呂屋の接客下男「三助」のことであるが、乃木希典、勝典、保典の親子も当時「三典」として知られていた。また、「介」の字が使われているのは、参謀長として第三軍の司令官の乃木を補佐し、無謀な突撃作戦で多くの兵士を殺した伊地知幸介を当て擦るためでもあろう。
猫は自分の素性について、〈どこで生まれたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニヤーニヤー泣いて居たこと丈けは記憶して居る〉と言っているが、「頓と見当がつかぬ」も漱石流のトボケであろう。
三四郎もトボける
こうしたトボケは『三四郎』にも見られる。三四郎は、汽車で出会った髭の男(廣田)に対して、〈此位の男は到る処に居るものと信じて、別に姓名を尋ね様ともしなかつた〉のであるが(一の八)、これはあきらかに作者のトボケである。というのも、三四郎が〈教師にして仕舞ふ〉この髭の男は、どこにでも居る訳ではない「稀」な男、「ノ」「木」に「希」の「乃木希典」であるからである。
『三四郎』を『坊っちやん』や『草枕』同様に夢幻能として読むなら、物語の展開を予告する前場にあたるのが汽車と旅館の場面であろう。この物語は、汽車で「黒い女」と「田舎者」の爺さんの会話を「三四郎」が夢現に聞くことから始まるのであるが、息子を旅順で死なせたことを嘆いているこの爺さんには息子を戦死させた乃木大将が重ねられている。いっぽう三四郎に接触する「黒い女」は美穪子の前ジテの役回りである。
〈君、不二山を翻訳して見た事がありますか〉、〈自然を翻訳すると、みんな人間に化けて仕舞ふから面白い。崇高だとか、偉大だとか、勇壮だとか〉(四の三)と廣田に言われても「三四郎」には何のことかわからない。しかし、当時人口に膾炙していた乃木の漢詩「富岳」「嶺蒼富岳千秋聳 矍鑠朝輝八州照 罷説区々風物美 地霊人傑是神州」を作者は充分過ぎるくらい知っていた。漱石の講演を記録した『砲煙集』(明治44年)では、「外国人に対して乃公の国には富士山があるというような馬鹿云々」とさりげなく名指している。
また、「三四郎」が〈のん気な時代もあつたものだ〉と呑気に考えるのは、廣田の「三頭の馬」の逸話である。売り飛ばされたアラビア馬の白馬は〈ナポレオン三世時代の老馬〉(三の二)と聞いたからである。アラビア馬がナポレオン3世から日本に贈られたことはあるが、それは遥か以前の幕末のことである。廣田の白馬は、ロシアの旅順軍総司令官ステッセルから乃木に贈られて「寿号」と名付けられた白馬のことである。白馬の飼い主の廣田が乃木大将であることは、「老馬」に「老婆」あるいは「老母」が掛けてあることからもわかる。乃木の老いた母の名は「寿」であったからだ。
「坊っちやん」がトボケた「御真影」
『坊っちやん』では、漱石は独善的な語り手の「坊っちやん」にとんでもない勘違いや誤解をさせることで、裏に込めた微妙な意味を伝えているが、肝腎なところを伏せ字にしてトボケさせているところもある。
旅館の山城屋で「坊っちやん」は、〈五円札を一枚出して、あとで是を帳場に持つて行け〉と、法外な心付けを下女に渡す。そして次の日に宿に帰って来ると、〈帳場に坐わつていたおかみさんが、おれの顔を見ると急に飛び出して来てお帰り・・・・・・と板の間へ頭をつけた〉のである。「……」が伏せ字となっており、普通は「お帰りなさいませ、先生」であろうが、伏せ字にして「板の間へ頭をつけた」とあるのは尋常ではない。旅館の女将は高額なチップをもらったくらいで、新任教師にそこまで卑屈にはならない。
女将は「五円札」を下女から受け取っているから、それまで「坊っちやん」に会っていない。それで、帰ってきた「坊っちやん」の顔を初めて見て「お上」であると知って驚き、飛び出して平伏叩頭したのであろう。「坊っちやん」が「御真影」のその人であり、女将は「御真影」を描いたエドワルド・キヨッソーネによって作成された「五円札」からそれに気づいたのであろう。こう考えれば、漱石が伏せ字にしてトボケている女将の言葉「・・・・・・」が聞こえてくる。「五円」ではなく、わざわざ「五円札」と言っているのは、紙幣に天皇肖像を載せることが、政府内で賛否が分かれた微妙な問題であったからであろう。
日本は日清戦争の賠償金を英国金貨に変えて、1897年に金本位制を導入した。これに伴い、日本銀行は、国家元首の顔がある西洋の通貨に倣い、キヨッソーネが作成した天皇肖像を載せた紙幣として、国際決済にも使える金兌換銀行券「五円札」の発行を準備した。しかし、何らかの不都合が生じてこの計画は頓挫したようである。発行された新「五円札」の肖像は同じキヨッソーネが神田神社の神官をモデルに以前に描いた武内宿禰となっていた。お雇い紙幣製版師で画家のイタリア人キヨッソーネは、写真に撮られて「御真影」になった1888年の天皇のコンテ画とは別に、軍装の天皇の肖像を1893年12月25日に銅製凹版で完成させていた。1891年に退任していたにもかかわらず、完成させるために印刷局に通い詰め、5年の歳月をかけてキヨッソーネが銅版に刻んだこの肖像画は、彼の紙幣製版職人としての技法と経験の集大成であったにもかかわらず、明治天皇に関する記録や紙幣史はこの肖像にほとんど触れていない。猪瀬直樹氏は『ミカドの肖像』で、旧大蔵省印刷局記念館に展示されていたこの印刷肖像画に限って撮影を強硬に拒否されたことと、天皇の肖像が紙幣に使われなかった不可解さについて指摘している。

キヨッソーネ作の銅版画 1893年
『坊っちやん』執筆当時に流通していた金兌換の「五円札」は、武内宿禰の「甲五円券」であった。キヨッソーネが作成した上記の武内宿禰肖像の銀兌換「漢数字一円券」が既に流通していたにもかかわらず、同じ人物を「五円札」にも使い回すという計画性の無さ、及び、金本位制の導入に備えるべきであるにもかかわらず、この金兌換券は導入の翌年から準備されて1899年4月、つまり金本位制が発効した2年後に発行されていることは、印刷局が想定外の事態に急ぎ対処しなければならなった何らかの事情があったことを想像させる。「中央武内」と呼ばれているように、この紙幣では肖像が中央の菊の紋章の下に置かれているのも異例である。日本銀行券で中央に肖像が配置されているものは、5年後の発行予定も含めて武内宿禰の3点、1945年から半年だけ通用した和気清麻呂の「ろ十円券」と聖徳太子の「ろ百円券」、及び1957年の聖徳太子の「C五千円券」だけである。

1899年発行の甲五円券 通称「中央武内五円」
「C五千円券」の肖像が中央にあるのは、同じ聖徳太子肖像の「C一万円」との混乱を避けるためと言われているが、1953年の時点では大蔵省による新「一万円札」の肖像の第一候補はキヨッソーネによる明治天皇であった。
「甲五円札」以外で武内宿禰が中央に位置するのは、昭和の恐慌時に印刷されたものの、仕上がり具合が問題となって破棄された「い五百円券」、及び、太平洋戦争中の昭和18年発行の「い一円券」であり、いずれも急拵えである。
下女が「変な顔をした」のは、「坊っちやん」は発行されなかった、キヨッソーネが描いた天皇の「顔」が載った貨幣価値のない「変な五円札」を山城屋のおかみに下賜したためであったのかもしれない。もし、そうであったとしても、それは宿泊の対価ではなく、遣っても遣らなくてもいい心付けであるから問題はない。それが「中央武内」の流通兌換券であったとしても、キヨッソーネに絡むこの下りには、「・・・・・・」と伏せられるだけの、奥深い含みがありそうである。
顔の中をお祭が通る
キヨッソーネは下女の「清」に音が通じる。したがって、下女の「清」から山城屋の下女、そしてキヨッソーネへと連想がつながる。「毒の笹の葉」を食べる「清」の夢から「坊っちやん」が目覚めると、〈下女が雨戸を明けてゐた〉のであり、そこには〈相変わらず空の底が突き抜けたような天気だ〉とあるから、宿の下女は「空の底」つまり「天界」から「突き抜け」た「清」に直結する。
〈どうするか見ろと済して顔を洗って、部屋へ帰って待つてると、夕べの下女が膳を持って来た。盆を持って給使をしながら、やににやにや笑っている。失敬なやつだ、顔のなかを御祭りでも通りやしまいし〉
〈中途で五円札を一枚出して、あとで是を帳場に持って行けと云たら、下女は変な顔をして居た〉
とあるが、「済して顔を洗つて」は何を「済ました」のかわからない。「顔を洗って部屋で待つ」ことは、わざわざ記述する程のことでもない。さらに、「給使をしながら」が食事の世話のことであるなら「給仕」であるが、この「給使」は自筆稿では「絵師」にも見える。「盆を持って」も「給仕」なら不要な説明である。ここは実に奇妙な記述が続き、何が言いたいかよくわからない。しかし、この女中が「絵師」の「キヨ」でもあると考えれば、ここは矛盾なく読める。つまり、「坊っちやん」が肖像画を「よく見て描け」と、顔を洗って「澄まして」いると、キョッソーネがイーゼルを持って来てパレットを手にして絵師の務めを果たした」と読める。「顔のなかを御祭りでも通りやしまいし」「帳場に持って行け」の本意は、「キヨッソーネが紙幣のために描いた肖像を、お祀りしても通用しない」であろう。
キヨッソーネが描いた肖像画は写真に撮られ、政府の皇民化政策により「御真影」として全国の学校で祀られたが、その取り扱いが不敬と断じられる事件も各地で起き、1898年には、それを火事によって毀損したとして、長野県の上田尋常高等小学校の校長が割腹自殺した話も伝わっていた。
「坊っちやん」に託して、漱石が「五円札」で言いたかったことを忖度するなら、「御真影なんてことを誰が言い始めたんだ。お札の絵なんぞで、人が死ぬことがあっていいのか」であろう。
後年、この上田の「御真影」事件のことを『父の死』と題して書いた若者が最晩年の漱石の門を叩いた。師の長女筆子への失恋を小説にした『破船』を『婦人之友』に、『蛍草』を『時事新報』に連載したことで世に知られるようになった久米正雄である。
『父の死』には、事件の直後、神社で遊んでいた筆者を、下女が「坊ちゃん大変です」と迎えに来たと書かれている。しかし、当時の地方で「坊っちゃん」という洒落た呼称は使われていなかったし、貸家住まいの校長宅には下女を置くような余裕もなかったはずである。実際には「御真影」は焼けていなかったという研究もあるが、『父の死』はあくまで小説であるから、現実と齟齬があっても怪しむに足りない。私小説を装った久米のこの短編は、あるいは「坊っちやん」と「下女」の「キヨ」によって、「御真影」という国民統制の仕掛けを批判した漱石の真意を伝える小説『坊っちやん』のスピンオフ作品として捉えることができるかもしれない。
関連書籍