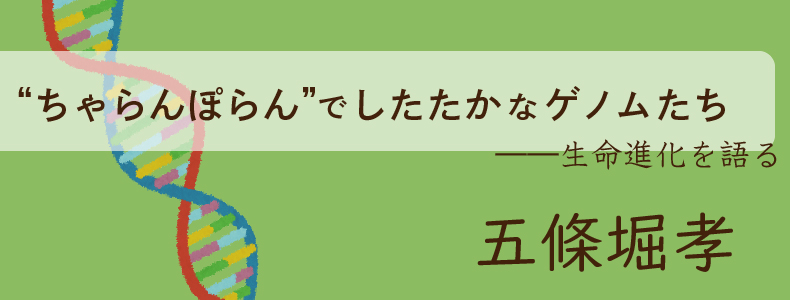遺伝子の起源を探る――大野理論とその応用
生命の起源の謎
生命の起源は、古くて新しい問題です。それには、生命を構成する化学物質の起源を探る化学進化から、生体の進化を探る生物進化の過程を探究する幅の広さとスケールの大きさに関する問題が包含されています。最近話題となっている月への人類の再着陸を目論む国際プロジェクト「アルテミス計画」の一つが、宇宙において生命の起源に関する物質や水の存在を探査することであることからも、その並々ならぬスケールの大きさが容易に推測できます。
化学進化から生物進化に連なる「生命の起源」問題において、次世代への生体情報を継承するDNAなどの遺伝情報を担う物質の起源と、その遺伝情報がどのように地球上に誕生し遺伝的な情報を担うことができるようになったのかを問う、いわゆる遺伝子の起源については、これまであまり触れられてきませんでした。これに関する仮説や論説もほとんど皆無であったといえます。
D N Aの二重らせん構造をJ. ワトソンと一緒に発見したF.クリックが、アミノ酸とDNAの塩基の関係性を示す遺伝暗号の起源について、たまたま現在のように過去に固定されてしまったとするコドン暗号の凍結説や、生命の起源は地球外に存在するという生命の宇宙起源説を提唱したことは有名ですが、そこでは生命進化に連なる一貫した論理構成を成す進化説までは見出されていません。
一方、大野乾の進化説は「遺伝子の起源」について直裁的に捉えています。生命のダイナミズムがいかに進化に繋がっていくか、それに関する一貫した論理が構築され言及されています。特に、彼の打ち出した新しい仮説は、自然淘汰説やネオダーウィニズムとは全く異なる論理構造を有しており、それはいささか哲学的ではあるものの、彼の主張する原理のみに注目すると、構成される論理は合理性を持ち科学的であるといえます。
大野の考える生命の起源
大野は全宇宙の原理として、「はじめに、秩序が存在していた」ことを明かしています。ここでいう彼の「秩序」とは、「繰り返し」あるいは「反復」の現象で、宇宙は約250億年を周期として膨張と収縮を繰り返しながら存続していることをその淵源としています。この繰り返し現象をすべての始まりの「秩序」と捉え、熱力学の世界では孤立系におけるエントロピーの増大が自然現象の原理の一つであるように、この繰り返し現象から「無秩序」になっていくことを自然の摂理と考えたのでした。
同様に生命進化の基礎となる遺伝子の起源と化学進化についても、「秩序」から「無秩序」への変換という原理に沿って生成していくものとみなしていたのです。塩基配列においては、はじめに数塩基(オリゴヌクレオチド)からなる繰り返し配列が存在していたと想定します。これに無理やり3塩基ごとのコドンに対応するアミノ酸を遺伝暗号から対応させようとすると、頻繁に終止コドンが出現するため、タンパク質のコーディング領域は機能的に出現できないものと思われます。しかし、これに突然変異が断続的に起こって徐々に終止コドンがアミノ酸をコードするコドンに替わり、自然淘汰が加われば、その過程は加速され、ついにはタンパク質としての機能を発揮するに十分な長さのコーディング領域ができて遺伝子が出現する、という仮説を大野博士は立てたのでした。もちろん、この場合の前提条件として、遺伝子の誕生以前に遺伝暗号のシステムが確立していることが重要となります。
ダーウィンの自然淘汰説にしても、メンデルの遺伝の法則や突然変異を包括したネオダーウィニズムにしても、さらに木村資生博士の中立説においても、遺伝子がどう生み出され生成するかという「起源」の問題には一切触れず、遺伝する因子すなわち遺伝子の存在は予めあるものとして議論が行われてきました。生物集団内における遺伝子の頻度を構成する時間変化がどういう要因によって引き起こされるかに着目し、長時間にわたって生物集団の全個体に特定の遺伝子の頻度が圧倒的多数となって引き起こされる変化を進化と彼らは呼んで議論してきたのです。先述したように、そこでは遺伝子自体がどう生成されたかという起源の問題は全く語られてきませんでした。それだけに大野博士のこの考えは進化学の歴史においても画期的で独創的であったのです。
背景には、彼が1970年に出版した本『Evolution by Gene Duplication」で述べた遺伝子重複こそ遺伝子進化の根源的な機構であるという指摘が、多くの科学者の共感を呼んだことがあると思われます。遺伝子重複によって遺伝子のコピーがゲノム上に出現すると、もともとの遺伝子は従来の遺伝子機能を保持できるため、そのコピーは進化の過程で以下の3つの可能性のどれかの性質を持つに至ると大野は考えたのです。(1)従来の遺伝子機能には似ているけれども、少し異なる機能をもつようになる(sub-functionalization)、(2)従来の遺伝子機能とは全く異なる、新しい機能をもつようになる(neo-functionalization)、(3)機能を失い死んだ遺伝子となる(Non-functionalization; dead gene, pseudo-gene)で、特に(1)と(2)は、生物進化の基盤となる遺伝子の進化にとって、非常に重要なことがよくわかります。
さらに大野は、機能を改善したり新しい機能を獲得したりした遺伝子が1個か2個できたとしても生物進化を加速させるには到底足りないだろうと考え、一挙にそのような遺伝子をたくさん、しかもそれぞれいろいろに異なった機能を持つものを創造するには、多くのの異なった遺伝子のコピーが必要となることに気づきます。それには、ゲノム全体を重複させれば、遺伝子セット全体のコピーを丸ごと手に入れることになるので、これは進化に好都合であるといえます。そうした視点で脊椎動物の起源に近い生物群のゲノムを注意深く見てみると、少なくとも1回か2回のゲノム重複が脊椎動物の出現前に起こったのではないかという仮説(one- or two-round genome duplication hypothesis)に大野は到達したのでした。
大野がゲノム重複による生物進化の重要性を主張した後、分子進化の宮田隆は、脊椎動物の出現よりさらにずっと遡って、さまざまな形態形質を持った生物種が短い時間に爆発的に出現した「先カンブリア爆発」と言われる現象に目を向けました。そこでの現象を遺伝子進化のレベルで説明するには、この「先カンブリア爆発」が起こる以前にそれらの祖先種においてゲノム重複が頻繁に起こり、新しい機能を持ちうる遺伝子のコピーをたくさん用意していた時代が存在していたはずであると推測しています。
ゲノム重複とハブ遺伝子の発見
ゲノム重複に関する見解から、さらに踏み込んだ仮説を展開できます。遺伝子には生物進化に本質的に寄与する遺伝子とそうでない遺伝子とがあり、ホヤを例にとると、ホヤの発生に関係する遺伝子に機能を無くしたり減衰したりするような突然変異を人為的に与えて発生過程を観察すると、発生過程に大きな影響を与える遺伝子とそうではない遺伝子が存在することがわかってきました。数からすると、発生過程にあまり影響を与えない遺伝子の方が圧倒的に多く、影響を与える数少ない遺伝子は、遺伝子のネットワークにおいて他の多くの遺伝子と相互作用している、いわゆる「ハブ」遺伝子であることも判明してきました。ちょうど航空機の運行路線において、さまざまな都市と結んでいる空港を「ハブ」空港といい、それ以外の空港は「ローカル」空港と言われるように、発生過程に大きな影響を与える遺伝子はまさに「ハブ」遺伝子であったのです。ハブ遺伝子の多くは、生物進化において重要な種分化の前に突然変異を起こしており、生物進化の形態変化に大きく寄与している可能性が考えられます。筆者のグループは、これらの遺伝子を「エポック・メイキング遺伝子(画期的遺伝子)」(epoch-making genes)と名付けました。
ゲノム重複が生物進化において重要なのは、単に遺伝子のコピーの数を増やすことではなく、画期的遺伝子の数を増やすことであることがわかります。しかしながら残念なことに、画期的遺伝子だけを増やすようなメカニズムを生物は持たないため、ゲノム重複によってそれを達成したと考えられます。画期的遺伝子以外は、機能を失っていっても一向に構わない訳で、実際にはそのようにして捨てられていった遺伝子も数多くあったと思われます。
淘汰説、中立説、ゲノム重複説
進化学の主流であった自然淘汰説あるいはネオダーウィニズム(進化の総合説)が決定論的(deterministic)で、木村資生の中立説は確率論的(stochastic)と言われるのに対して、大野の進化説は決定論として位置づけられ、中立説とはやや相容れない関係性や対立構造を持つように思われます。これには、それぞれの進化説のバックボーンである生命観に基本的な大きな相違があり、それに起因していると考えられています。
大野は、機会あるごとに、「話の通りが良すぎる話は十分に気をつけよ」と警鐘を鳴らしていました。とくに生物の形態や機能が環境に適応した説明でうまく出来すぎる話が時々あるが、生物は必ずしも万能的に環境に適応するとは限らないからそれには注意を要するということです。鳥類はどうして飛行機のジェットエンジンのような機能を獲得し得なかったのだろうか。より早く飛べる方が生存競争に打ち勝つ可能性が高いというなら、飛行機のジェットエンジンのような機能を獲得しても良かったはずなのに……。これは、大野の口癖のような述懐ですが、合目的な自然淘汰万能主義に対する科学論的な嫌悪感が彼には強くあったように思われます。
大野の考える独創性の発露とは、何も前提のないところに突然にブレークスルー的なアイディアが生まれるはずはなく、まずは既存の考え方や仮説を真似たりコピーしたりすることから始まり、それを自分流に少しづつ改変していくことで最終的には全くオリジナルなアイディアとなることであり、それが独創性の源泉であるという信念を持っていました。彼の生み出した遺伝子重複による進化仮説や遺伝子の起源を辿る道についても相通じるものがあり、大変興味深いものです。
対淘汰説という点では、木村の中立説と同じ立場を共有するところが多く、その意味では大野は木村に共感し良好でしたが、一方でここに説明したように、両者の説や考え方については根本的な相違が存在し、両者が折り合える余地など全くなかったことも明らかです。それは、大野が当時強く進めていた「遺伝子音楽」をめぐる対立というかたちで表面化していきました。「遺伝子音楽」とは、国立がんセンターのグループが最初に発案したもので、DNAの塩基配列を音階に見立て、そうすることで魅力的な音楽になるというものです。京都で行われた生物進化をテーマにした国際シンポジウムで、講演中に大野自身が応用した遺伝子音楽を聴衆に披露したことから、講演終了後に真っ先に質問に立った木村の激しい批判によって二人の理論的相違は決定的なものとなりました。
木村は、「科学的な発表や討論を行う真摯な場で、遺伝子音楽のような「遊び」を行なってはならない!」と、叱責に近い言葉で大野を批判したのに対し、大野は、「これは遊びではない。列記とした科学的な研究成果の発表である」と強く反論したのでした。大野は、DNAの塩基配列には、「繰り返し」構造が多々含まれ、そのような「繰り返し」構造を明確に認識するには、音楽として表現し聴覚的に把握する方法は有用だと考えたのでしょう。もちろん、大野は音楽好きな生活スタイルを送っていたので、DNAの「繰り返し」構造を音楽で楽しむという一面があったことは否めないですが、本稿で述べたような大野の進化説における論理的な背景がもっとよりよく理解されていたならば、木村だけでなく他の多くの科学者から大野の進化説に対する共感や支持はもっと強く得られたように思われます。
新しい進化説を独創的に提案した科学者が日本人であったということは、偶然でないのかもしれません。ダーウィンの自然淘汰説が我が国に導入された明治初期、それに関する大きな論争や宗教からの大きな反発などは見られなかったようです。それは、牧野富太郎や南方熊楠の流れを底流にしながら、昭和に入って国際的な視野で活躍した木原均や駒井卓といった卓越した遺伝学者の出現や台頭、木村資生や大野乾といった進化説の国際的な巨頭が日本人であったということと無関係でなかったのではないだろうか、とつくづく感じているところです。