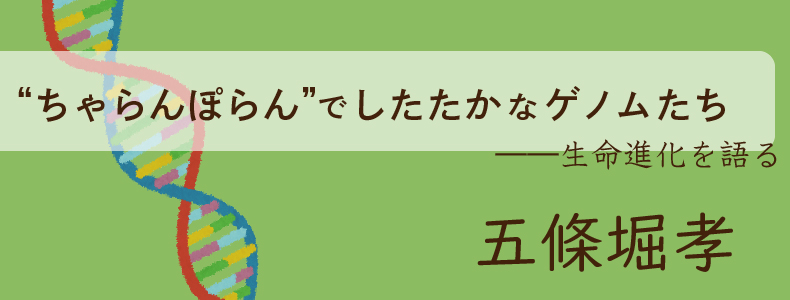生命進化と利他的行動
比較生化学との出会い
去る2月5日、106歳の父が亡くなったこともあって、一冊の本の思い出から振り返ってみたいと思います。
私が大学1年の頃、エルンスト・ボールドウィン著『比較生化学入門』という本を父が駅近くの本屋で買ったらしく、机に向かって物思いに耽っていた私にヒョイ! と何気に渡してくれました。文系畑で郵政省に関係する仕事をしていたサラリーマンの父は、なんの風の吹き回しか、自分とは縁遠い理系の難しそうな本を突然買ってきて、私に素気なく与えてくれたのです。父に、どうしてそんな本を私に買い与えたのかを特に聞く機会もなく、父のいなくなった今でも、その理由は分かっていません。自分なりに過去を振り返り、気になる思い出を反芻してみると、父の気持ちもだんだん読めてきたように思われます。
当時、理学部生物学科に在籍していた私は、生物学に手ごたえを感じられず、途中で方向を変えてもっと実用的な医学の道を目指そうか、そのために医学部を受け直そうかと真剣に悩んでいました。こうした私に対して、“生物学の道でしっかり頑張れ! 手探りで生物学の楽しみを見つけよ!” というような父親なりの励ましの言葉を、この本に託して私に伝えたかったのだろうと感じるようになりました。そうした父親の気持ちを知る由もなく、渡された難しそうな本を一応はしっかり読もうと、夜更けまで机にかじりついて格闘していた記憶があります。その甲斐あってか、「生化学」とは、生物学の一分野で化学の方法論や考え方で生命現象を解明していく学問であることが、自分也にだんだん分かってきました。ところが、本の題名の枕になっている「比較」の意味が全くわからないのです。一体、何のために、どうして、「比較」という2文字が最初についているのか、全くもってちんぷんかんぷんなのです。
生物学で比較すること
「比較」という意味の重要性に気づいたのは、この本の存在もほぼ記憶の片隅に消えさり、当時の就職難から就職を一時的に先延ばして、大学院でも受験しようかという頃。生物学のような生命を扱う世界では、さまざまな生物種が多様な形態形質を持って存在することから、「比較する」ということは、基本中の基本の方法論であり、古より今日まで脈々と受け継がれてきた思考様式なのだということに気づいたのです。実際、生物学の歴史をちょっと垣間見るだけでも、この比較という基本的な方法によって、さまざまな重要なことが解明されてきたことが直ちに分かります。
血液中の酸素運搬に関与するタンパク質、すなわちヘモグロビン(赤血球)の機能が、マウスとニワトリの間でどのように違っているか?その違いを分析すれば、それをもたらした生命進化上の理由あるいはその過程を調べることができます。それによって、マウスの特性とニワトリの特性が明確になるのはもちろん、さらにもっと深い生命進化の謎が解き明かされていくのです。
一般に細胞の中には「核」あるいは「細胞核」という細胞内の小さな器官が存在します。しかし、私たち人やマウスを含む哺乳類は、赤血球に核が存在しません。鳥類・爬虫類・両生類・魚類、そして絶滅した恐竜の赤血球にも核が存在するにも関わらず……。何故でしょう?
生命体にとってもっとも大切といわれるDNAは細胞の核の中に存在します。私たち人間のDNAを血液から抽出するとき、赤血球からは取ることができません、したがって、白血球など赤血球以外の血液中の細胞から抽出することになります。人の体の内では、1日に約2000億個の赤血球が常に産生され、1個の赤血球の寿命はおよそ120日と言われています。幹細胞から産生されたばかりの赤血球は赤芽球と呼ばれ、その時点ではまだ核を持っているのですが、生成していくにつれて、核部分が凝縮されてしまい、いわゆる「脱核」現象が生じて核がなくなってしまうのです。哺乳類の赤血球にだけそのような現象がどうして起こるのか、これは進化学的に大変興味深い謎に今も包まれたままでいます。
このように生命進化を理解するうえで「比較」という手法は、その本質的な役割を果たしています。そこでは、生物学において「比較」というと即座に「比較=進化」という構図を思い浮かべるほど進化学との関係性は強く、その両者は生命現象を紐解く際に欠かせないものなのです。
生命進化とは、変化すること
生物種の間で異なって見られる現象は、共通の祖先種からそれぞれの種へと分岐していく過程で、ある「変化」が生じて現在観察できるような異なり方に到達したと解釈することができます。この「変化」こそが、生命の「進化」なのです。一見、過去の形質に戻ったような「退化」も生物学や生命科学においては「進化」とみなされています。ところが、通常私たちが日本語でいう「進化」という言葉には「前に進む」という意味が暗黙裡に含まれているので、考え方としては「進化」というよりは、「変化」という言葉に置き換えた方が納得しやすいのかもしれません。このことからも、生物学では「進化」とは「変化」の同義語と言っても過言ではありません。
ただ、ある機能や能力に優劣を決めるために明確な基準を定義しなければならない場合には、その基準に照らして以前より「優れた」、以前より「劣った」と変化の度合いに言及することが可能です。このときには、前者を「進化」、後者を「退化」という言い方を用います。ただ、概ね生命進化において、そうした基準に絶対的なものはほとんどなく、環境や時代(時間)によっても大きく変わっていくものと考えられています。それゆえ「進化」は単なる「変化」と割り切って議論を進めていくのが、科学的な見地から最も客観的であると考えられます。
およそ17億年前に共通祖先から分岐してきた大腸菌と人は、それぞれ現在まで連綿と生き延びてきています。大腸菌も17億年も生き延びてきたということを横に置き、単純に人を進化の頂点に置いて「もっとも優れたもの」とする考え方は、あまりにナイーブ過ぎると言わざるをえないでしょう。私たち生命進化を研究する世界では、そのように考えます。
分子生物学のセントラルドグマ
生命進化を考える上で、生物の持つ普遍的かつ遺伝的なメカニズムを理解することは、極めて重要なことです。その一つに、「DNA→RNA→タンパク質」という生命情報の流れを示す分子生物学の「セントラルドグマ」といわれるものが存在します。この情報の流れは、ある種のウイルスを除けば基本的に、いかなる生物であれ、いかなる種類の遺伝子であれ、普遍的に成立するものであることからそのように呼ばれています。遺伝子の情報が刻まれたDNAからRNA へとその遺伝情報が伝わり、RNAの持つ遺伝情報に基づいてタンパク質が産生されます。産生されたさまざまなタンパク質は、生物の体の基本ユニットを構成したり、その他のタンパク質とさまざまに相互作用しながら、生命体にとって重要な機能を果たしていくのです。また、酵素としてもいろいろな代謝経路に関与し、体の構造や機能に深く関係して生物の持つ形状などのいわゆる形態や、より高次の行動などを含む形質の形成や維持、そしてそれらの機能の発現に寄与していくのです。
例えば、FOXP2という名の遺伝子。これは、重度の発話障害や言語障害が3世代にわたって発症している家系の遺伝的な分析から、その症状の原因となる遺伝子の一つとして特定されたものです。このFOXP2という遺伝子から産生されるタンパク質は、運動を学習するときに重要とされる脳回路の発生に強く関与することが推察されています。このため、この遺伝子がどういう進化過程を通って現在に至ったかを理解することは、言語能力の進化を知る上で非常に興味深く、進化学においても重要な課題の一つになっています。
このように現代の進化学は、分子生物学のセントラルドグマを基盤に据え、生物のさまざまな存在様式に関する時間的な変化の過程を異なる生物種の間で比較して追跡し、その起源や変化を通して進化の過程を解明しようとするのです。
進化は一方通行―「獲得形質の遺伝」の否定
ここで重要なのは、セントラルドグマとして行われる生命情報の流れは必ず一方の方向に進むのであって、原則として逆には戻らないということです。つまり、「DNA→RNA→タンパク質」という分子レベルにおける生命情報の流れは、基本的に逆には流れないのです。
1972年、米国のハーワード・テミン博士とデービット・バルチモア博士が独立にRNAからDNAを産生する逆転写酵素をウイルスで発見して、ノーベル賞を受賞しました。それから四半世紀を過ぎた現代、それでも尚、逆転写酵素の発見はRNAからDNAに留まり、タンパク質からRNAに情報が逆流する現象は見つかっていません。
したがって先ほどの例に戻ると、言語を学習したからと言って、その能力が次の世代に受け継がれる、すなわちFOXP2遺伝子が産生するタンパク質に特徴的な変化が起き、それがFOXP2遺伝子に伝達されてDNAが変化し、次世代に受け継がれるということは、分子生物学のセントラルドグマにおける一方通行性からあり得ないことになります。例えて言えば、車を製造するときに、設計図から必要部品のところだけを写し取り、それを基に必要なパーツを製造しようという流れ作業は一方通行であるわけですが、車のパーツで生じた変更が自動的に設計図に置き換えられるということはあり得ない、こうした状況に似ていると言えます。
同様に、キリンの首が長くなった部分のタンパク質の情報がRNAやDNAに逆流的に写し取られて、次世代に継承されていくということはあり得ないと考えられています。これが、進化概念を近代的に提唱したラマルクの「獲得した形質が遺伝する」というテーゼは間違いであったという現代的な根拠になっています。これに異論を唱える少数の人々がおりますが、現代進化学はその異論を認めてはいません。
確かに、自分が獲得した知識を持って子供が産まれてくるとしたら、教育など全く不必要になるかもしれません。しかし、一方でそうなると仮定すると、生まれながらにして知識のある人とない人が存在する訳で、永久に硬直した格差社会のなかで生きなければならないことになり、人生は実につまらないものになってしまうでしょう。
カルチュラル・エボリューション
ここで、生命進化の視点から私たちの社会を考えてみましょう。
これまでみてきたように獲得形質の遺伝は継承されませんが、人間社会では教育や文化によって知識や経験が次の世代に受け継がれていきます。そこでは、継承する媒体は遺伝子ではなく、教育や文化がそうした役割を果たしていることに気づきます。
私たちが話す言語の伝承はもっとも良き例でしょう。どの国やどの地域に生まれようとも、すべての赤ちゃんは産まれたままの状態ではほとんど話すことができません。親や家族、学校教育を通じて言葉を学んでいきます。なかでも読み書きのようなリテラシーは、教育を通じて次世代に継承されていく典型例といえます。その過程で言語も変化していくことから、その変遷の有り様は生命進化になぞられ、生命進化と似た特徴を多く持つと言われています。ただ、生命進化には遺伝情報としてのDNAが存在するのに対し、言語の時間的な変遷などには過去を映し出す決定的な遺跡の記録や文書などが残っていることは稀で、その点で議論がかなり推測的になってしまうのは否めません。
学問の継承などについても、同じことがいえます。足し算や引き算などの基本的な算数から量子力学や天文学に至る高度なものまで、伝え継がれていく内容や対象には大きな差はあるものの、学問体系は教育によって確実に次の世代に伝えられていきます。そして、それらも時の流れとともに変容し、進化していきます。このような文化の世代間の継承をカルチュラル・エボリューション(Cultural Evolution)と言い、進化遺伝学の分野においても重要な学問対象のひとつとなっています。
とりわけ言語のカルチュラル・エボリューションとしての研究は、人類集団が大陸を移動して地域的に分散していく過程を研究する人類集団遺伝学や人類進化学そして言語学とも深く関連して、現在でも盛んに議論されています。このカルチュラル・エボルーションは、人間社会だけでなく、サルなどの他の生物集団でも観察されていて、数理モデルを駆使するとともに活発に議論されているのです。
利他的行動と包括的適応度
カルチュラル・エボリューションでよく議論されるのが、「利他的行動」と言われるものです。「あの人は自己中心だから!」「利己主義は困る!」というのは、「利己的行動」・「利己行動」を指します。まさにその反対が「利他的行動」です。
そこでしばしば好例として取り挙げられるのが、チドリの親が子を保護する行動。「♪♫~青い月夜の浜辺には 親を探して鳴く鳥が 波の国から生まれ出る〜」の歌詞で有名な「浜千鳥」のチドリです。タカやワシなどの猛禽類などが天敵であることで知られていますが、それらがチドリの巣を襲うとき、卵や雛を守るため、親鳥が囮(おとり)となって傷ついたふりをして天敵の前に出て天敵を巣からできるだけ遠ざけようとします。親が自己を犠牲にして子供を守ろうとする振る舞いです。
さらに、自分の体を子供に差し出して餌として食べさせるクモの例も知られています。人でも、自分の幼い子どもが車に轢かれようとしたら母親は身を挺して子どもを守り、自分がたとえ車に轢かれて死んでも我が子の命を車から守ろうと普通はします。これがまさに「利他的行動」です。
この他、社会的昆虫と言われるハチやアリなどのように、働きバチや働きアリが女王バチや女王アリの生存や生育のためだけに行動する場合や、ライオンのように集団で狩りをする共同作業や配偶者を助ける行動も「利他的行動」に分類されます。
この利他的行動を含めて生命進化をみてみると、これまでの自己=個の生存を主として、他者との「生存競争」において環境に適応するかたちで生き残りを図ることを主題としてきた「自然淘汰」の考え方では、生物行動の全てを説明できないということになります。
進化学には後述するように、利他的行動を含む生物集団の遺伝的多様性を考える方法として「包括的適応度」という見方があります。集団遺伝学では、さまざまな遺伝的変異をもった個体が生存競争にさらされるとき、環境にどの程度に適応しているかということを定量的に表現していく必要があります。しかし、環境には空間的にも時間的にもさまざまな状態が存在するので、生物個体の環境への適応度を定量的に表現することは至難の技と考えられてきました。
個体の「適応度」f (英語でfitnessという)を「親の数P(普通は父母の2人で「P=2」)を分母として、それらの親が産んだ子供で繁殖可能になる時期まで生き残った数Oを分子とした比率f(=O/P)」として定義していきます。例えば、父母の2個体の親から2個体の子供が産まれて繁殖可能な時期まで生き残ったとすれば、f = (2/2) = 1 となります。ところが、1個体の子供しか生き残らなかった場合には f = (1/2) = 0.5 となり、3個体の子供が生き残った場合には、f = (3/2) = 1.5となります。このように適応度を超簡単化して定義するという知恵を見つけ出したことによって、多様な数理モデルを構築することが可能になったことから、生存競争を量的に議論できるようになり、集団遺伝のさらなる発展に繋がっていきました。
利他的行動を研究していたイギリスの理論集団遺伝学者のウイリアム(ビル)・ハミルトンは、利他的行動が存在する場合には、助けた子供や他個体の適応度を按分して「適応度」を考えねばならないとして、「包括的適応度」という定量化された新しい概念を提唱しています。このようにカルチャル・エボリューションは、生物の持つ遺伝的特性や形質だけでなく行動をも考慮して「進化」を議論する必要性を明らかにしました。
「進化」を「変化」として捉えることによって、客観的に生物の進化を議論するという基本的な理解から、カルチュラル・エボリューションという生物の特性的な行動や社会的な行動を考慮した議論に至るまで、生命進化という学問は生命科学の基盤的で包括的な学問領域であることを強く意識することが重要であるように思われます。
きっかけは、50年以上も前に出会ったたった一冊の本。それも父が何気にくれた本の存在を今も忘れずに覚えているということは、心の内奥に強烈な記憶としてこの本が残っていたのかもしれません。お陰で生物学を追究していく糸口を自分のなかで見つけることができ、「比較」という一つの鍵概念を正確に理解することで、さらに生命進化学の領域に繋がっていきました。「比較」の重要性と面白味にふと気づいた瞬間、生物学の世界は輝きをもって自分に近づいてきてくれているように感じられ、研究することの意義を深く理解するようになったのです。研究者になっておよそ40年、多くの先達の知見を継承しながら今でもその魅力に引き込まれています。