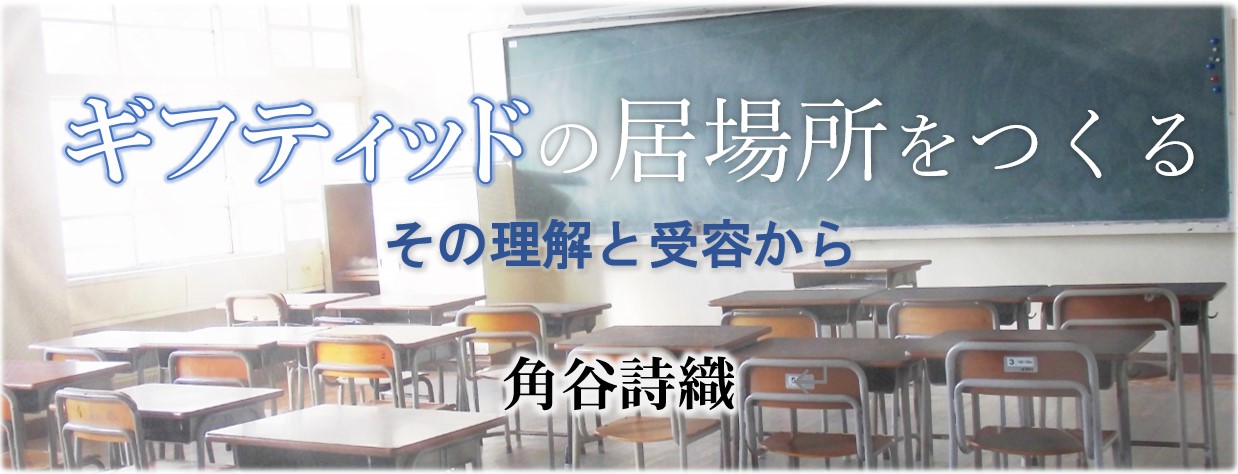ギフティッドと共に生きていくために
7.日常的な応じ方:『わが子がギフティッドかもしれないと思ったら』より
ギフティッド児を育てるということは、非常に難しく、孤独なことです。ここでは、『わが子がギフティッドかもしれないと思ったら』にあげられている、ギフティッド児との日常的な関わり方をいくつかご紹介したいと思います。この本に書かれている育児上の重要要素は、決して、ギフティッド児の育児に限定されるものではありません。そこに記されている知見や提言の根拠はギフティッド業界を超えて、広く発達心理学、臨床心理学、精神医学、教育心理学において蓄積された知見に基づいています。ですから、広く、子育てに行き詰まりを感じている親にとって、豊かな糧となり安心できるヒントとなるはずです。
乱暴な言い方かもしれませんが、子どもが元気に育つために必要不可欠な要素――多少の困難は避けられなくとも、家族との信頼関係が構築されており、安心して日々を過ごすことができ、自分は認められ価値ある人間だと思うことができ、適度に難しいことへの挑戦と成功体験を積み重ねることができ、自信をもつことができる――は、ギフティッド児であろうと障害のある子どもであろうと、標準的な子どもであろうと関係なく共通しています。ではなぜ、本書が「ギフティッドの育児」というテーマを掲げているのかというと、標準的な子どもであれば多少の困難はあれど極度の困難なく得られるであろう必要不可欠な要素を、ギフティッド児は、その特性や置かれた環境、マイノリティであることなどから、非常に得にくい状態にあるためです。ギフティッド児がこれらの必要不可欠な要素を得るには、親や教師が、立ち止まり、耳を傾け、「いったいなんなのっ!」と湧き上がる怒りや焦りを自ら治め、子どもが示す「心配な行動」に対しても落ち着いて対応できるようになる必要があるためです。
まず、この本の第一著者であるDr. ウェブは、「子どもとの関係性を最優先に考えるように」という強い考えをもたれています*1。それは、主観的・個人的な思いとしてだけではなく、ギフティッドの専門家、臨床家としての長年の臨床経験と研究から導き出された考えです。この「関係性の構築」を最優先にすることが、ギフティッド児が自ら困難を克服し、飛躍するために必要不可欠だと考えられています。
〇良好な関係構築のために
では、良好な関係構築のために、具体的にどのような関わり方をすればよいのか、そのポイントをいくつかあげてみようと思います。
まず、「感情に善悪はない」(『わが子がギフティッドかもしれないと思ったら』p.65~)という認識が重要になります。たとえば、怒って泣き叫んでいる子どもに対して「そんなに怒らないの」となだめる大人は珍しくありません。このときに注意しなくてはならないのは、そのことばが「怒るあなたは間違っている」というメッセージを伝えていないかという点です。怒りという感情は自然に湧き上がるものです。怒りを感じることが悪いことだというメッセージを受け取り続けた子どもが、自分は間違っていると考えるようになることは、想像に難くありません。
「感情は個人的なもので、その感情を抱いている本人にとっては真実そのものだ。…(中略)…ただし、その感情を表現するのにどのような行動をとるかについてはコントロールできる」(同、p. 65)
これは、あまり新鮮味のない一般的なアドバイスかもしれません。それが、なぜここに書かれているのか。それは、ギフティッドにみられる感情の過興奮性からもわかるように、ギフティッド児の感情は、その感じ方、表出のしかたともに、一般的な想定の範囲を超えたものとなることと関連します。親をはじめとする周囲の大人は、通常ならば「そうだね、嫌だったね」と共感できるはずが、その「あまりの激しさのために」、つい、「もうおにいちゃんなんだから、そんなに怒らないの」「いつまで怒っているの!」と言いたくなります。ここが、難しさです。だから、常に「感情に善悪はない」と肝に銘じ、応じていく覚悟が必要なのだよと、本書に書かれているわけです。
第二に、「子どもの話に耳を傾ける」(同、p.75~)ことです。ただ、耳を傾けて話を聴く。「子どもは、ただあなたに話を聴いてもらいたいだけで、それ以上は何も望んでいないということがよくある。必ずしもあなたのコメント、意見、評価などを必要としているわけではない――ただ、自分の感情をわかち合いたいだけ」(同、p.75)です。何を言ったらよいかわからないとき、子どもの感情に賛同できないとき、そんなときにも、ただ「聴く」だけの威力が記されています。これも、よく知られていることです。カウンセリング・マインドの基本とでも言えましょう。ただ、ギフティッド児に応じるとき、これが非常に難しくなるのです。 まず、矢継ぎ早に話が出てきます。その感情は激しく、ときには泣き叫びながらの話になることもあります。そのあまりの激しさに、親の心情として、「何とかしなければ!」という焦りが沸きあがるでしょう。さらに、1週間、1か月と、同じ話に耳を傾けても、その激しさと鮮烈さは変わりません。 目の前の子どもが、まるで今日の出来事のように、3年前、いや、7年前に起こった辛い出来事を話します。 すると親は、「私には、聴く力がないのだろうか? 聴くのが下手なのだろうか? 聴いたところで、この子の感情は少しも収束しない!」という不安に押しつぶされそうになるかもしれません。それでも、「聴く」ことは子どもを生かすことにつながると、ウェブらは確信をもって記しています*2。
第三に、「スペシャルタイム」(同、p.81~)をもつことです。毎日3分でもよいから、「毎日」、その子と一対一でともに時間を過ごす機会をもつこと、その子のやりたいことをして過ごすこと(ただし競争やゲームは除く)。これは、年に1回の家族での海外旅行よりも貴重で大切な時間となります。
〇子どもの望ましい行動を高めるために
続いて、子どもの望ましい行動の高め方も書かれています。
第一に、意欲との関連では、「子ども自身が大切だと考えているもの」(同、p.112)を見極めること。そこに意欲の灯があるはずなので、そこから始めようということです。これにかかわる注意点として、トークン・エコノミー法という、望ましい行動がみられたらシールやお小遣いなどご褒美をあげて意欲を高めようとする手法は、ギフティッド児には逆効果だと指摘されています。
「ギフティッド児は、このような方法が自分をコントロールしたり操ろうとするものだと見透かすからだ。意志の固いギフティッド児の多くは、大人の『権力による工作』に屈するくらいなら、自身のあらゆる権利を放棄する――自身の行動が招く惨憺たる結果さえも我慢する――ほうがましだと考えるだろう」(同、p.113)
第二に、「期待のほめ言葉」(同、p.139~)を使い、成功体験のチャンスを増やすこと。「期待のほめ言葉」とは、まさにその行動をやってほしいときを逃さず、前もって「~してくれて、ありがとう」と言うことです。たとえば、あなたは、子どもに上着を床に脱ぎ捨てないでコート掛けにかけてほしいと思っているとします。子どもが帰宅し、上着を脱いで床に放り投げようとしたそのとき、「上着をかけてくれて、ありがとう」と言うことなどです。「え? そんなこと、しようとしていないけど?」と反応されたら「あら? そうだったの? じゃ、かけてくれると助かる!」と応じればよいこと、「この本読んで、『期待のほめ言葉』使おうとしているでしょ」という反応には、「そうだよ。文句を言われるより、そのほうがよいでしょ」と言えばよいことが書かれています。
しつけとのからみでは、「子どもは経験からもっともよく学ぶ」(同、p.165)という認識が重要となります(ただし、ADHDには適さないとされています)。親が助け舟を出したくなってしまうようなときにも、できる限り(命に危険がない限り)、当然の事態(起こるべくして起こる結果)に任せ、見守ることが大切です。スケボーを外に置きっぱなしにすれば、雨でびしょぬれになったり、翌日なくなっていたりするかもしれません。それでも、そのまま見守ります。親は決して、「まったく、もう!」とブツブツ言いながら家に取り込むことはしません。お弁当を忘れていけば、お腹が減り、ひもじい思いをするでしょう。それでも、親が届けるようなことはしません。宿題を忘れていけば、成績がさがるかもしれません。それでも置かれたままの状態にしておきます。当然の事態から子どもはもっとも多くを学ぶためです。親には、非常に勇気の要ることですが、「『誤った助け』をするのは、子どもが当然の事態から学ぶチャンスを奪っていること」(同、p.166)になります。また、当然の事態を受けて落ち込む子どもの話に、親は耳を傾ければよいので、「まったく、何度言ったらわかるの!」と叱る立場から、「落ち込んでいる子どもを慰め、励ます」立場に立ち位置を変えることもできます。大切なのは、落ち込んでいる子どもに、「ほ~ら、ね。」というメッセージを送らないことです。
まだまだたくさんありますが、ここでは紹介しきれません。思春期になり、うつや自殺の問題が他人事ではなくなったときの応じ方なども書かれています。孤独を感じている親の慰めとなり、安心と光を得られる内容となっています。
8.ギフティッドをめぐる日本の状況
日本でも、メディアでギフティッド(ギフテッド)が取り上げられるようになり、注目されるようになってきています。ギフティッドということばを聞いたことのある人、関心を向ける人が増えていくことは、とても素晴らしいことであり、また、必要な段階だと思います。ただ、ここでもう一度、ギフティッドについての的確な理解という点に目を向ける必要があります。発達障害とギフティッドの混同以外にも、日本におけるギフティッドの的確な理解の妨げとなり得る風潮があります。
『ギフティッド その誤診と重複診断』の序章には、次のように書かれています。
「たとえばメディアでは、ギフティッド児はちっちゃな変人として描かれることが多い。とてつもなく難しい数学の問題を解いたり、楽器を名演奏家のように演奏できたり、12歳で大学に入学するような天才だとか、一日中本を読んだり練習したり勉強したりしているような子ども像となる」
以前、とある報道番組を見ていた際、Dr. ウェブが上のように警告を発していた光景そのものが目の前に映し出されました。(あからさまに「変人」とはしていないまでも。)そして今でも、インターネット上に、眼鏡をかけた小学生が難しい数式を解いている姿が前面に押し出されています。
重要なのは、「こういうギフティッド児もたしかにいるが、皆が皆、そうではない。こういうギフティッド児はむしろ少数だ」と、大人は肝に銘じて子どもとかかわることです。
メディアで取り上げられるギフティッド像は、超人的な才能を発揮する子どもというイメージを植えつけているように感じられることがあります。大学数学を学ぶ小学生、名演奏家のように楽器を奏でる子ども、眼鏡をかけて学者のようなしゃべり方をする子ども等々です。これらは的確なギフティッド理解を阻むものとして、注意しなければなりません。
ギフティッド児の割合は3~10%と言われますが、3~10%全員が、大学数学を解けるわけではありません。解ける子もいますが、解けないギフティッド児の方が圧倒的に多いでしょう。たとえばプロファウンドリー(極度の)・ギフティッドの割合は、100万人に1人より少ないと考えられています*3。ところが、ギフティッド児であれば(つまり、3~10%の子どもが)超人的な力を発揮できるという誤解を引き起こすような伝え方がなされることがあります。ギフティッドを、超人的な才能を発揮している天才と誤解してしまうと、本来ギフティッドであろう子どもを見落とし、さらには誤診の問題を引き起こしかねません。「ギフティッド児なら数学ができる、物理ができる、文才がある、音楽の才能がある、芸術的な絵を描く」などという幻想があると、すぐ目の前にいるギフティッド児を、問題児、障害児、あるいは「ちょっと変わった子」と捉えてしまう可能性が高まります。一見普通に見えるギフティッド児、あるいは、年齢がまだ低いことや、才能を開花させるような環境に巡り合えていない場合、過興奮性や、教室環境に馴染めない点ばかりが目立つというギフティッド児もいる――いや、むしろそのほうが多い――のです。
インターネット上でも諸外国のギフティッド・プログラムの様子を垣間見ることができます。それらを少し見れば、そこに映し出されるギフティッド児は、日本のテレビメディアで取り上げられるような、「見るからに標準と異なる」子どもではないという点に気づくと思います。日本の教室にもいるような子どもたちが大勢出てきます。実際、ギフティッド児のほとんどが、一見普通に見える子どもです。たとえばIQ130の子どもが一見して「違う」子どもではありえないことは、教師や臨床家の多くが経験知として有していることなのではないでしょうか。また、ギフティッド児のつくった作品や成果発表物(スポーツやら演劇含め)は、決して、「超人的」なものではありません。実に「子どもらしい」という印象を強く受けることと思います。
今後、日本でギフティッド判定などが現実的な課題となったとき、教師や保育者が正しいギフティッド・イメージをもつことが大切になると思います。幼少期からベートーヴェンを弾きこなしたり、一流画家のような絵を描いたり、大学数学を解いたりする子どもというイメージがあると、 実はギフティッドであるのにそのように理解されず必要な教育支援を受けることのできない子どもが多く出かねません。
〇日本におけるギフティッド研究
日本でも、ギフティッドに関する研究がなされています。その実証性の弱さは国際的な課題であり、日本も例外ではありませんが、ギフティッドの特性やニーズ、抱えやすい困難、どのような教育的配慮の可能性があるのかなどについて日本国内に向けて、さまざまに発信されています。論文等が多く一般の方にはアクセスしにくいかもしれませんが、ひとつの参考にしてください。
‣ギフティッドの過興奮性を中心としたギフティッドの社会・情緒的特性
・林睦. (2018). ギフテッドの概念と日本における教育の可能性. 滋賀大学教育学部紀要, 67, 199-204.
・松本茉莉衣・是永かな子 (2015). ギフテッドの情緒社会面・行動面・感覚面における特別なニーズと対応. 高知大学教育学部研究報告, 75, 169-178. …など
‣2Eのニーズや特性
・松本茉莉衣・是永かな子 (2017). 日本のギフテッド当事者に対する特別な教育的ニーズに関する聞き取り調査(第3報). 高知大学教育実践研究, 31, 135-143.
・松村暢隆. (2018). 発達多様性に応じるアメリカの2E教育 : ギフテッド(才能児)の発達障害と超活動性. 關西大學文學論集68(3), 1-30. …など
‣ギフティッドの困難とその支援
・日高茂暢 (2020). 知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解 : 特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育. 佐賀大学教育学部研究論文集/佐賀大学教育学部 4(1), 147-161.
・小泉雅彦 (2019). 学習に困り感を抱える子どもを支える:土曜教室の成果からギフテッド支援を考える. 札幌学院大学心理学紀要, 2(1), 29-36. …など
‣諸外国のギフティッド教育
・合田美穂 (2010). 香港におけるギフテッド教育の歴史・政策・課題. 甲南女子大学研究紀要. 人間科学編, 46, 21-32.
・デイバーケイス, S.,隅田学 (2012). イギリス総合中等教育における科学才能児のニーズへの方策 : ASCENDプロジェクト. 科学教育研究 36(2), 101-112.
・松村暢隆. (2018). 発達多様性に応じるアメリカの2E教育 : ギフテッド(才能児)の発達障害と超活動性. 關西大學文學論集68(3), 1-30.
・関内偉一郎 (2016). 才能教育における高大接続に関する一考察:アメリカ合衆国の早修制度に焦点を当てて. 教育学研究83(4), 436-447.
・植田みどり (2012). イギリスにおける才能児教育. 比較教育学研究, (45), 66-79.
・三宅志穂・中山 迅 (2014). 才能児にふさわしい学力を発揮させる教育プログラムと教材の特色:英国SLCLの提供する教員研修を事例として. 理科教育学研究, 55(1), 121-130. …など
‣医療専門家の立場からのギフティッドへの見解、誤診への警告
・榊原洋一 (2020)『子どもの発達障害――誤診の危機』ポプラ社
・杉山登志郎 (2015)『ギフテッド 天才の育て方』学研プラス …など
‣2Eへの医療の立場からの支援
・宮尾益知 (2019). 発達障害と不登校:―社会からの支援がない子どもたち:2Eの観点から―. リハビリテーション医学56(6), 455-462. …など
これら以外にも多くの発信がなされています。
国内メディアで発信されている内容の真偽を見極める力を培い、ギフティッド児の特性の的確な理解を浸透させること、これこそが、まず日本に求められていることだと思います。
(了)
参考文献
*1 Harlow, T. B. (2018). Helping gifted kids thrive: Insights from the experts.
*2 Webb, J. T., Gore, J. L., Amend, E. R., DeVries, A. R. (2007). A Parent’s Guide to Gifted Children. Great Potential Press. (ウェブ, J.T., ゴア, J. L., アメンド, E.R., デヴリーズ, A. R. (著)角谷詩織(訳) (2019).『わが子がギフティッドかもしれないと思ったら――問題解決と飛躍のための実践的ガイド』. 春秋社)
*3 Webb, J. T., Amend, E. R., Beljan, P., Webb, N. E., Kuzujanakis, M., Olenchak, F. R., & Goerss, J.(2016). Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults: ADHD, Bipolar, OCD, Asperger's, Depression, and Other Disorders (2nd Edition). Great Potential Press. (ウェブ, J.T. アメンド, E.R., ベルジャン, P., ウェブ, N. E., クズジャナキス, M., オレンチャック, F. R., ゴース, J. (著)角谷詩織・榊原洋一(監訳)(2019). 『ギフティッド その誤診と重複診断――心理・医療・教育の現場から』. 北大路書房)
関連書籍
|
わが子がギフティッドかもしれないと思ったら 問題解決と飛躍のための実践的ガイド J.T.ウェブ他著/角谷詩織訳 |
L.K.シルバーマン著/角谷詩織+北條礼子訳 |