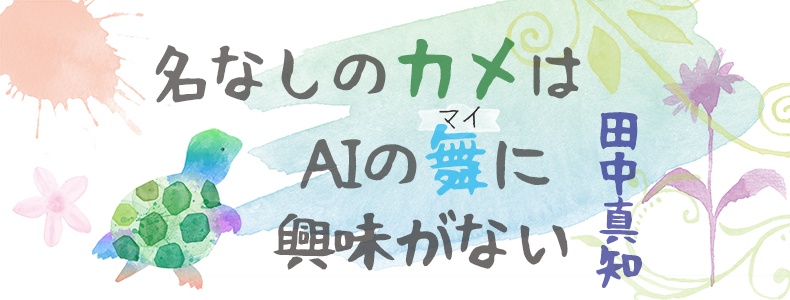夢のあとに (最終回)
強い風とともに電車の窓に雨が吹きつけていた。かっぱ橋を出るときにぱらぱらと降り出した雨は、電車が郊外へと抜けて地上に出るころに激しい雷雨となっていた。
「降られなくてよかったですね。亀山様は本当に運がいい」
鴨志田が両手に持つ大きなふたつの紙袋が、電車が揺れるたびにがらがらと音を立てる。かっぱ橋で買った鍋やざるや砥石などの調理道具がつめこまれた紙袋だ。座席は埋まっていたが、立っている乗客は多くなかった。
「鴨志田さん、荷物、下に置いたらいかがですか」
シュウイチがいった。
「だめです。調理道具を床に置くことはまかりならんと、祖母に口酸っぱくいわれたものです。祖母は毎晩、台所で包丁を一本一本砥石で研ぐのが習慣でした。そのシャリッ、シャリッというリズミカルな音を聞きながら、幼い私は眠りについたものです。いまも、包丁を研ぐ音を聞くと、あのころの思い出がよみがえります」
鴨志田は紙袋をがらがらといわせながら目を細めた。
「それなら、網棚に上げたらどうですか」
あひるのマイがいった。
「いい考えです」
鴨志田は紙袋を抱えて、上にあげようとした。途中で鴨志田の手が止まった。
「だめです」
「どうしました」足元のマイがいった。
「祖母は研いだ包丁を毎晩、神棚に納めていたんです。ところが、夜中に地震があって、朝起きたら、床に包丁が刺さっていたことがありました。下にいなくて幸いでした。それから祖母は包丁を高いところに置いてはいけないというようになりました」
「包丁も入っているんですか!」
「はい! 砥石も入っています」鴨志田が明るく答えた。
目の前の座席の乗客が突然、席を立ち、足早に去っていった。
「おお、ラッキーにもちょうど、席が空きました! 私、年長者ですので失礼して、すわらせていただきます」
鴨志田は袋を抱えて腰を下ろした。
しばらくすると、暗かった窓の外がふいに明るくなった。暗い雲がふたつに割れ、隙間から光がさしている。雨が上がっていた。車内から声が上がった。太陽と反対側の窓の外に乗客たちがスマホを向けている。シュウイチも窓の外に目をやった。
「あっ」
「なにが見えるんですか。ここからだと見えません」
足元でマイが上を見て足をバタバタさせた。シュウイチが抱え上げた。
「あっ」とマイが声を上げた。
虹が出ていた。それもひとつではなかった。鮮やかな虹の外側にもうひとつ薄い虹がかかっていた。
「雨がやんだのか」シュウイチがいった。
マイはそれには答えず、虹を見つめていた。マイの目を通して、その奥にいる芽衣が虹を見ていた。そのメイの目の奥から、さらにべつのだれかが虹を見ていた。そのだれかが芽衣に話しかけた。
⸺芽衣、虹が見えるよ。
あひるのマイは人形のように反応がなかった。マイの視野の奥にいる芽衣もまた魂を奪われたようにモニターの前で硬直していた。芽衣に話しかけたのがだれかはすぐわかった。それは幼い頃、丘の上に登ったときに舞衣のいった言葉だった。ただ、あのときの舞衣の声ではなかった。声変わりを経た大人の声だった。それでも、芽衣には、それが舞衣の声であることは、なぜかはっきりとわかった。
⸺舞衣はここにいたんだ。いっしょに年をとっていたんだ。
「マイ、どうした?」
反応のないマイにシュウイチが声をかけた。
AIの自動対応モードに切り替えるのも忘れて、芽衣はモニターに映る虹を見つめていた。
*
そのとき居眠りしていた鴨志田が目をがばっと顔を上げて、「大丈夫です。心配いりません!」と大きな声でいった。
シュウイチとマイはびっくりして鴨志田を見た。乗客たちもスマホから目だけを上げて見た。
「どうしました?」シュウイチがいった。
鴨志田がわれにかえってシュウイチを見た。それから左右を見回した。
「夢でしたか! これは幸先がいい。ある事情から、この10年ほど夢を見ていなかったのですが、夢が戻ってきたようです。それにしても、いい夢でした。亀山様、せっかくなので忘れぬうちに夢をお聞かせしましょう」
「せっかくですが遠慮します」
「その遠慮深さが亀山様のいいところですが、この鴨志田に遠慮は無用です。それに10年前、もしいつか夢が戻ってきたら、そのときいちばんそばにいる人に、その内容を聞かせなさいといいつかっています」
「だれがそんなこといったんですか?」
「マレーシアの夢占い師です。私、夜の森で道に迷って、木の洞で寝ていたとき、一人の男に起こされたんです。目をさますと、その男はいきなり『いま見ていた夢を売ってくれ』といって、目の前に札束をさしだしたんです」
「えっ?」
「私も寝ぼけていたので、よくわからないままオーケーし、お金をもらって、いま見ていた夢の話をしました。男は満足して立ち去っていきました」
「それが夢占い師だったんですか」
「ちがいます。その男に夢の話をした日から、私は眠れなくなってしまったんです。 夜になってもまったく眠くならない。いや、 体は疲れて眠くなるんですが、眠れないんです。病院で睡眠薬を処方してもらったんですが効かない。医者に、夢を売った話をしたところ、医者がそういうことなら治せない、ここへ連絡しろといわれて電話番号を教えられました。それが夢占い師でした」
「ややこしいですね」
「夢占い師がいうにはですね。世間には夢を買い集める者たちがいるんだそうです。夢を売ってしまうと、しばらく夢が見られなくなって、場合によっては眠れなくなるとのことで、まさに私がそのケースでした。だから夢を買いたいといわれても、けっして売ってはいけないといわれました」
「夢を買ってどうするんですか」
「売るんだそうです」
「売る?」
「そうです。最近では怪しげな夢販売サイトもあります」
鴨志田はスマホを出して操作して、シュウイチに見せた。
「闇夢市場? こんなのあるんですか」
「そうです。人気のある夢は高額で取引されています。世間には夢難民がたくさんいるんです。私は幸い、夢占い師のおかげで眠れるようになりましたが、この先しばらく夢は見られないといわれました。夢が戻ってきたときは、すぐそばの人に話しなさいといわれたんです。そばにいたのが亀山様でよかった。肝心の10年ぶりの夢ですが、きれいな虹が出てくる夢でした」
「虹?」
シュウイチとマイが同時にくりかえした。
「はい、虹です」
「いま、ちょうど虹が出ています」
車窓の外の虹は薄れて消えかけていたが、まだぼんやりと二重の弧を描いていた。
「なんと! じつは夢の中で見たのも、こんな二重の虹でした。田んぼの広がる日本の田舎のようなところで、姉妹らしき幼い女の子が二人でその虹を見ていました。丘から降りると一人が走り出して外側の虹の付け根から虹によじのぼり、上までかけあがって、そこから下にいるもうひとりの子に手を振ったり、声をかけたりしている。でも、下の子にはその声が届かず、姿も見えないようで、あたりを探しまわっているんです。私はなぜかマイさんのようなあひるの姿をしていて、田んぼからその様子を見ているんです。そして下にいる子に、大丈夫です。お友だちは虹の上から手を振っていますよと教えてあげようとするんですが、ガアガアという声しか出ない。マイさんなら、しゃべれたんですけどね」
あひるのマイは鴨志田を見つめた。そのマイの目を通して、奥にいる芽衣が呆然とモニターを見つめていた。
「まじ? うそでしょ」
芽衣は、マイをとおして聞いた。
「あのう、虹に登った女の子、それからどうなったんですか」
「はい。虹の反対側まで行って、そこから降りたところまでは見ました。でも、そのあとはよく覚えていません。こうして話している間にも、なぜかどんどん細部が曖昧になっていきます。もう一度夢の中に入れればわかるかもしれませんが」
「夢の中に入るって、どうやって?」
「さあ、やり方は知らないのですが、夢占い師によると、そういう能力を持っている人がたまにいるらしいです。ただし、夢を見ている本人が目を覚ましてしまうと、夢から出られなくなって、その夢の中で生きなくてはならなくなるので注意が必要とのことでした」
「夢から出られなくなると、どうなるんです?」
「その夢を現実として生きることになるそうです」
「夢を現実として生きる?」
「そうです」
「鴨志田さん、さっき『大丈夫です。心配いりません』ていって起きましたね。あれは、だれにむけていったんですか?」
「私、そんなこといいましたか?」
鴨志田は首を傾げて、しばらく考えていた。
「下にいる女の子にかけた言葉かもしれません。虹に登った女の子は無事だといいたかったのかも」
*
さっきまで虹が出ていた空は、一変して黒い雲で覆われていた。稲妻が激しく明滅し、雷鳴がとどろき、まもなく大粒の雨が落ちてきた。雨脚は強く、車窓の外の風景が霞んで見えなくなるほどだった。
電車は次の駅までたどり着くと、そこで動かなくなった。しばらくして、落雷による架線故障という車内アナウンスがあった。
運転再開を待つ人びとでホームはごったがえした。雨脚はますます強まり、ホームにも吹き込んできた。
鴨志田が手にしていた紙袋から、小さな包みを取り出した。
「人形焼です。亀山様もいかがですか」
「いつのまに買ってたんですか……。ありがとうございます。いただきます」
「亀バージョンの人形焼を売っているのは一軒だけなんです。彼女の好物でした。まだ店があってよかったです。マイさんは食べられなくて残念ですね」
「残念です。人形焼、好きなんです」
「おお、そうでしたか」
シュウイチと鴨志田が人形焼を頬張っていると、後ろから声がかかった。
「あたしも食べたいな」
二人は同時に声の方にふりむくと、いるか商店のタマミが、そこに立っていた。
*
「亀印の人形焼知ってるなんて、あんた通ね」人形焼を頬張りながらタマミがいった。
「おそれいります。好物なんです」鴨志田がにかっと笑った。
「ところで、どうしてここへ……」シュウイチがいいかけると、タマミが鴨志田を見ていった。
「あんた、なにか忘れてない?」
鴨志田は胸に手を当てた。
「愛はしっかりここにありますが、はて、なにを忘れたのか……」
タマミは鴨志田の言葉を無視して、手提げから泡立て器を取り出した。鴨志田が30万5000円で買ったものだった。
「あっ。私としたことがなんという失態。わざわざ来てくださったとは、タマミさんの愛を感じます」
「届けるのは、ついで。あんたたちが帰ったあと、ばあちゃんに電話したんだけど、つながらないの。イルカの家にも連絡がつかない。ちょっと気になって、行ってみようと車に乗ったんだけど、途中まで来たら、この雨で道路が大渋滞で動かない。仕方ないから電車でと思ってホームに来たら、あんたたちが人形焼食べてたの。電車止まっているのね」
雨はますます激しく、雷鳴がひっきりなしに轟いた。運転再開の目処は立っていなかった。鴨志田はカバンの中から小さな枕のようなものをとりだした。外側のひもを引っ張ると、それはパタパタと広がって、たちまち、4、5人も入れそうなテントになった。
「なに、これ? やばい」タマミがいった。
「遭難に備えて持ち歩いています。いつもは一人用なんですが、今日はたまたま大きいのを持ってきてよかったです。まさか、駅のホームで使うことになるとは思いませんでした。防水だし、保温性もすぐれています。ささ、中へ」
ホームの乗客たちが怪訝そうに見ている中、鴨志田たちはテントに入った。鴨志田が明かりをつけた。
「キャンプみたいです」マイがいった。
「いるかの家、大丈夫かな。カメも心配だなあ」シュウイチがいった。
「あんたカメ飼ってんの?」タマミがいった。
「ええ、変な事情があって飼うことになったんです」
「変な事情?」
シュウイチは、自分がカメを飼うにいたった経緯とそのあとのことをかいつまんで話した。
「変なの……」
「変ですよね」
「でも、変じゃないものなんてないからね。この人も変だし」タマミは鴨志田を見て、それから「このけったいなあひるも」といってマイを見た。
「けったいなあひるじゃありません、マイです」マイがいった。
「タマミさんも変ですよね」シュウイチがいった。
「そうね。だいたい、駅のホームにテント張って人形焼食べてるなんてことが変よね。おかしな夢の中にいるみたい」
そのとき鴨志田が「あのう」といって手を上げた。
「私、さきほど10年ぶりに夢を見たとこなんです。それで思い出しましたが、ある方にこんなことをいわれました。『だれもが、だれかの夢から出られなくなっている。ただ、本人はそのことを忘れていて、これが現実だと思いこんでいるんだ』と」
「それ、私、聞いたことがある。どこだっけな」
「ひょっとしてマレーシアではありませんか?」
鴨志田の言葉にタマミが驚きの表情を浮かべた。
「そう! マレーシア。なんでわかるの? あんた、何者?」
「話せば一昼夜はかかりますが、よろしいでしょうか」
「遠慮する。でも、マレーシアはほんと。山の中にいたとき」
「そんなところで、なにされていたんです?」シュウイチが聞いた。
「話すと一昼夜かかるけど」
「次の機会にします」
「マレーシアの山の中を旅していたとき、人づてに占い師がいるって聞いて、おもしろそうだから訪ねたの。そしたら、『あんた、厄介な夢の中にいるね』っていわれた。そのときに、それを渡された」
タマミは鴨志田が買った泡立て器を指差した。
「意味わかんなかったんだけど、とりあえず7年手元に置いといて、そのあとは売りなさい。ただし、値段は30万円以下ではいけない。もし、30万円で買う人が現れたら、あんたは夢から自由になるだろうといわれたの。『ただの古ぼけた泡立て器じゃない。そんな値段で売れっこない』っていったんだけど、占い師は『これは夢を泡立てる道具だ』っていうの」
「夢を泡立てる?」
「意味わかんないよね。でも、ばあちゃんのせいで、意味わかんないことには慣れてたの。っていっても、すっかり忘れてて、見つけたときには10年くらいたってたけど。その間に店をすることになったので、冗談のつもりで置いてみたの。一応調理道具だし、骨董ぽいし、興味を持つ人もいた。でも、30万ていうと、みな唖然とする。バカにしてんのかって怒りだす人もいた。当然よね。夢を泡立てるものですなんていえないし……でも、まさか本当に買う人がいたとはね」
タマミは鴨志田をしげしげと見た。
「じつは、この泡立て器はですね……」
鴨志田がなにかを話しだそうとしたそのとき、テントの布地が一瞬まぶしいほど明るくなり、つづいてつんざくような落雷の音がした。その余韻が地鳴りのようにホームを震わせた。
「カメ、大丈夫かな」
シュウイチがスマホを取り出した。SNSのタイムラインには、突然の雷雨と川の氾濫を伝えるニュースが流れていた。イルカ団地のあるあたりは洪水浸水想定区域だ。この半世紀、川が溢れたことはなかったが、氾濫したら大惨事になりかねなかった。イルカの家の人たちはチヨや鶴田さんも含めてネットを使いこなせる人はいなかった。イルカ団地の住民も高齢者ばかりなので心配だった。
「鴨志田さん!」シュウイチがいった。「トータス・リコール社に連絡してください。緊急事態です」
「わ、わかりました」
鴨志田は電話をかけた。しかし、回線が込み合っているのか、いっこうに通じない。
「私が連絡します」
マイがいった。
「マイ……」
モニターを前にした芽衣が、浦島次郎に電話をかけた。コール音が3回繰り返されたあと通話がオンになった。
「はい」
いつもと同じく暗く無表情な浦島の顔が映った。
「浦島さん、この大雨でイルカ団地の様子がわからないんです。トータス・リコールがかかわっている亀山さんが住んでいる団地です。なにか情報はありませんか」
「……」
「浦島さん!」
「いま、調べてます。ちょっと待ってください」
キーボードを叩く音がしばらくつづいたあと、浦島が口を開いた。
「イルカ団地、一階部分は浸水して、停電してます。でも、カメは無事です」
「よかった。それとイルカの家がどうなっているかわかりませんか」
「イルカの家? ああ、これですね」
またキーボードを叩く音がした。
「見当たりません」
「見当たらないって?」
「地図にある場所に、それらしき建物は見当たりません。雨でそのあたりが浸水しています。水没したのか、流されたのか」
「流されたですって!」
マイの声が急に大きくなってシュウイチや鴨志田やタマミが顔を見合わせた。
「正確にはわかりませんが、建物は見当たりません」浦島がいった。
「マイ、だれと話しているの?」シュウイチがいった。
「浦島次郎です」
「浦島次郎? 太郎じゃなくて……」
「そのうち説明します」
稲妻がするどく空を走った。
「わかりました!」鴨志田が突然大きな声でいった。
「なにがですか」シュウイチがいった。
「方舟です」
「はっ?」
「人形焼、まだありますけど、どなたかいりませんか?」鴨志田が袋を手にした。
「あたし、いただく」タマミが手を出した。「それで、方舟ってなに?」
「私、かつてイルカの家の秘密調査をしたとき、裏山で木造の船を見つけたんです。中にヤギやイヌやネコが何匹もいて、それを見てぴんときたんです。イルカの家は大洪水に備えて方舟をつくっているんじゃないかと」
「へえ、そういえばじいちゃん、つまりばあちゃんの死んだ旦那だけど、船大工だったんだよね。海で行方不明になったんだけど、死んだんじゃなか、旅に出たんだってばあちゃんはいってたなあ……」タマミがいった。
くりかえし状況を知らせる放送が流れたが、運転再開の目処は立っていなかった。乗客の多くは雨風を避けて改札の方へと移動していた。日が暮れて、だれもいなくなったホームに黄色いテントがひとつ、灯台のようにほのかな光を放っていた。
*
雨は翌朝まで降り続いた。イルカ団地につながる道路は寸断され、団地までたどり着くことができたのは翌日の午後になってからだった。
団地の住民の多くは昨夜のうちに、高台にある学校の体育館などに避難したと聞き、マイを抱えたシュウイチ、そして鴨志田とタマミは体育館を訪ねた。しかし、チヨや鶴田さんなど、イルカの家の住人たちの姿はなかった。
体育館を歩いていると避難者の一人から声をかけられた。シュウイチがふりむくとそこにいたのは盲目の男性だった。以前カメが迷い込んだ、同じ階の部屋の住人、滝だった。
「滝さん」
「ああ、やっぱりそうか。あのときの声がしたから。AIのお嬢さんは元気かい」
「こんにちは、滝さん」
その声を聞いて、滝は一瞬黙った。
「お嬢さん、この前と声がちがうね」
「さあ」
「なにかあったのかな。くっきりとした揺らぎのない声だ」
マイは前に滝に会ったとき、「色が揺らいでいる」といわれたことを思い出した。
一行は体育館をあとにして、イルカの家へと向かった。
水はまだ完全に引いていなかった。雑木林の地面には枯れ葉が浮き、足を踏み入れるとくるぶしまで沈んだ。しかし、イルカの家は見当たらなかった。
「ばあちゃん……」タマミが不安そうにつぶやいた。
流されたとしたら残骸などが見当たりそうなものだが、それもなかった。
「方舟が!」
裏山の方へ向かった鴨志田の声がした。
「方舟がありません」
タマミやシュウイチが見に行くと、船のあったあたりに鴨志田が立っている。
「方舟なんて本当にあったんですか?」シュウイチがいった。「見たのは鴨志田さんだけなんですよ」
「ありましたとも」鴨志田があたりを見回した。
もし船が流されたとしたら、どこかに流れ着いているかもしれない。しかし、そんなニュースはまだなかった。
「夢見ているみたいだな」シュウイチがいった。
「夢……」タマミがくりかえした。「私たち、夢から出たのかもね」
「夢から出たって?」シュウイチがいった。
「ほら、だれもが、だれかの夢から出られなくなっている。ただ、本人はそのことを忘れていて、これが現実だと思いこんでいるっていう占い師の言葉。あれよ。私はばあちゃんの夢の中にいたのかも。ばあちゃん、なにしろ魔女だしね」
イルカの家そのものが、じつは夢だったのかもしれない。いやそんなはずはない。たしかに、イルカの家はあった。でも、それがあったことを証明できるだろうか。たしかにあった。ただ、それを根拠付けるものが自分の記憶でしかない。それが夢というものならば、生きているとは夢にほかならない。……シュウイチはそんなことを考えた。
「あひるさん」タマミがいった。
「は、はい」マイがいった。
「あんた、人間でしょ」
「えっ」
シュウイチがぎょっとした顔をした。
「もういいのよ。夢から出てくれば」
「ど、どういうことですか」
「まあ、いいわ。無理しないでいいのよ」
「……」
「そうそう、先ほど話しかけたことですが」と鴨志田がいった。「タマミさんから購入した泡立て器なんですが、ロマノフ王朝のニコライ二世の宮廷料理人が使っていたもののひとつと伝えられていたもので、長いこと行方不明になっていたのですが、まさかマレーシアの占い師の手に渡っていたとは意外でした。この泡立て器、タマミさんがおっしゃっていたように夢を泡立てる道具と聞いています」
「それ、意味がわからないのよ」タマミがいった。
「私もわかりませんが、まさにいま夢が泡立てられているのではないでしょうか」
「なるほどね。そんな気もしなくもないか」タマミがいった。
「ねえ、亀山様」鴨志田がいった。
「はあ……」
「ねえ、マイさん」
「はあ……」
そのときタマミが上を見て「あっ」と声を上げた。
「虹が出てる!」
シュウイチと鴨志田とマイも空を見上げた。鮮やかな虹が橋のようにかかっていた。
「あれ?」シュウイチがいった。
「おお、あれは!」鴨志田が叫んだ。
虹の上を方舟がゆっくりと進んでいった。その前方に船を導くようにイルカの群れがジャンプしながら虹の航路を進んでいく。イルカの群れに先導された船は、やがて虹の反対側へと姿を消した。そのあとも一行は虹がすっかり消えるまで空を見上げていた。
みな無言だった。
鴨志田が「なんか、おなかがすきましたね」といった。
そのとき雑木林の方からがさごそと音がした。みながいっせいに、その方向を見た。
「だれか、いますか」と雑木林から出てきた人がいった。女性だった。
ヘルメットをかぶり、レスキュー隊のような明るいオレンジ色の制服を着ている。
「あっ」と彼女はいった。「みなさん、大丈夫ですか」
「はい。元気そのものです」鴨志田がにかっと笑った。「探しものをしていたところです」
「探しもの? そういえば、そこでカメを拾ったの。もしかして、あなたたちの?」
「あ、それはうちの……」シュウイチがマイを抱えたまま走り寄った。「なんでこんなところに」
マイが、シュウイチの腕の中から女性の顔をじっと見つめている。
それに気づいたレスキュー隊の女性が、一瞬びっくりした表情を浮かべ、それからぽつりといった。
「メイ……」
「惜しい。このあひるちゃんはマイさんです」鴨志田がいった。
「あっ、そうなの。なんでメイなんていっちゃったのかな。この子、マイっていうの。私と同じ名前」レスキュー隊の女性が笑った。
モニターを見ていた芽衣が立ち上がった。スマホを手にして、玄関に向かうと、スニーカーをつっかけ、マンションのドアをあわただしく開けた。雨上がりの新鮮な光が殺到し、芽衣は一瞬目がくらんだ。それから靴を履き直すと、芽衣は光に向かって走り出した。