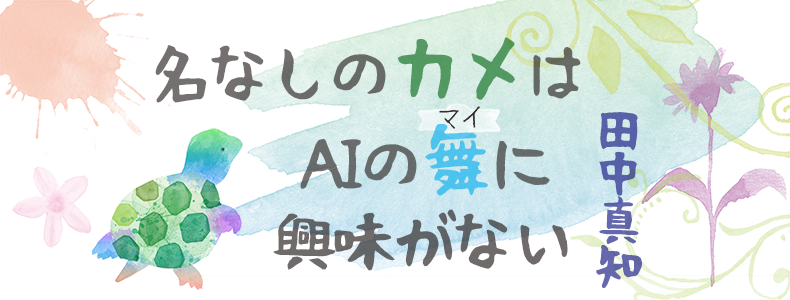魔女の孫
キュウキュウという甲高い音がした。チヨは食事の手をとめて、懐から携帯をとりだした。バンドウイルカの歌は、鶴田マユミからの着信音だ。
「マユミさん。愛してます。どうしました」
「おチヨさん、あの、あたくし……どうしたらいいか」
電話を通して取り乱している様子が伝わってくる。
「マユミさん、どうしました?」
「あのう、来たんです」
「来た?」
「そう、来たんです。あたくし、てっきり……でも、ちがうんです。ああ、おチヨさん、どうしましょう?」
「マユミさん、愛してます。大丈夫ですよ。いま、どこから電話してます?」
「あたくし、川にいます。見に来たんです。そしたら、来たんです」
「マユミさん、愛してます。なにが来たか教えてくれますか」
「あたくし、てっきりイルカが戻ってきたと思って、でも、ちがったんです。ちがうのが来たんですの」
「なにが来たんです?」
土手の上にしゃがんでいた鶴田は川の水の中で揺れる細長く白いものを見つめていた。水面がゆらめくと、その長いものもいっしょになって、たなびくように揺らめいた。細長い胴体の後ろの方から、何本もひものようなものが長く伸びていた。
「マユミさん、大丈夫?」
「あの、それがイカみたいなんですの。でも、イカにしては、とても大きいんですの」
「イカ……」
チヨの脳裏に何十年も忘れていた記憶がふいによみがえった。子どもの頃、故郷の海辺の村にいたときのことだ。
その日は学校にいるときから腹がぐるぐると動いた。イルカが来ているときの腹の動き方とはややちがった。なにか得体のしれない生き物が腹の中にいるようだった。体が重く、だるくて、少し熱っぽかった。
学校の帰りに、海の風を浴びたくてチヨは浜へ寄った。イルカはいなかった。
⸺なんなんやろ、こん感じ。
チヨはしくしくとさしこむ腹をさすった。そのとき波打ち際で白っぽく輝く大きなものが揺れているのに気づいた。
⸺なんやろう?
チヨは水の中に膝までつかって近づいた。細長くとがった帽子のような部分が日射しを浴びて虹色に光っている。真ん中あたりに顔のような部分があり、そこからひものような触手が幾本も伸びている。イカだった。でも、こんな大きなイカを見たことはなかった。チヨは呆然として波間で揺れている巨大なイカを見ていた。
⸺死んどるとかな?
そのとき波が打ち寄せた拍子に、イカの胴がねじれて見開かれた大きな黒い目がチヨの視線と合った。無表情な目が自分を睨みつけているように思えて足がすくんだ。
チヨは入り江の外れにあるタマミの暮らす漁師小屋に向かって走っていた。イカの大きな目がいまもじっと自分を睨んでいる気がした。腹がきりきりと差し込むように痛んだが、足を止めたらあの長い触手に巻きつかれて海に引きずり込まれそうな気がして、必死に走った。
たどりついた漁師小屋にタマミはいなかった。そのとき急に目の前が暗くなって、チヨは意識を失った。
目を開けるとタマミがチヨの顔をのぞきこんでいた。
「戸ん前で倒れとったけん、びっくりしたばい」
下半身がスースーするのを感じて、チヨはからだを起こした。下腹部に布が当てられていた。チヨはタマミを見た。
「月のものが来たとね。あとでお母さんにいいなっせ」
チヨは腹に手をあてた。差し込むような痛みはやわらいでいた。
「下着は洗うといた。大丈夫。心配いらん」
チヨははっと思い出した。
「うちゃ大きなイカば見た」
「ああ、知っとるばい。うちもあぎゃん大きなイカ、初めて見た。珍しかね」
「うちイカに睨まれた。逃げようとして走りよったら腹がどんどん痛うなってきた」
思い出したように下腹部に痛みが押し寄せてきて、チヨは顔をしかめた。
「大丈夫か」
チヨはうなずいた。
「イカは漁協んほうで持っていった。よそでも同じごつ大きなイカや珍しか魚が揚がったちゅう話ばしてよった。なんかん前触れかもしれんと噂ばしとった」
漁師たちの不安が的中したのか、翌週から急に天気が崩れ、予想外の嵐がやってきた。強い風を伴う豪雨がまる二日続き、海は荒れ、浜に近い家屋は浸水し、倒壊する家屋も少なくなかった。住民たちは高台にある学校の体育館に避難して、雨がやむのを待った。チヨも両親に連れられて体育館へ避難した。タマミの姿は見当たらなかった。
やっと雨が上がったとき、チヨは真っ先に浜の漁師小屋へ向かった。浜には打ち寄せられた残材や海藻が堆積していた。漁師小屋はあとかたもなかった。
チヨは漁師小屋のあったあたりを放心したように見つめていた。ほかの避難所にも足を運んだがタマミの姿はなかった。警察による捜索も行われたが、村人たちは海にさらわれたんやろうと噂した。タマミの行方はわからずじまいだった。
*
「おチヨさん! 聞こえてます?」
電話の向こうで鶴田マユミの呼びかける声がして、チヨは我に返った。
「はい、聞こえてますよ、マユミさん。大きなイカがいるんですね」
「そうなんですの。あたくしね、今朝起きたとき、川にイカなきゃって思ったんですの。いいえ、しゃれじゃございませんわ。昔、イルカが来る前に感じたときのような胸騒ぎがして、もしかしたらイルカが戻ってきたんじゃないかって思って、どきどきしながら川まで歩いてきたんですの。いつか、おチヨさんおっしゃってましたよわね。イルカがここへ来たのは、ここがミタマの場所だからだって。これからお祭りをするって、おっしゃってたから、きっとイルカが戻ってくるんだって思ったんです。でも、イルカじゃなくてイカでしたの」
話をしているうちにマユミの中に複雑な感情がこみ上げてきた。
「マユミさん、愛してます。大丈夫ですよ」
「おチヨさん、イルカが来たときは、あたくし、とてもわくわくいたしましたのに、今回はざわざわしてしまって……。イカの目ってあんなに大きいなんて存じませんでしたわ。わたくし、目が合ってしまいましたの。ああ、どうしましょう」
「マユミさん、帰ってきなさい。大丈夫です。愛してます。イカと目が合っても、イカはなにもしません」
しばらくすると、マユミが憔悴した様子で「イルカの家」に戻ってきた。
「おかえりなさい。マユミさん」
チヨとその世話をしている女性たちがマユミを迎えた。
「きっとニュースになっていますわ」といってマユミは、イルカの家テレビをつけた。しかし、巨大なイカのことを報じているチャンネルはなかった。ネット上にはダイオウイカ出現のニュースがいくつか見つかったが、いずれも、この町の話ではなかった。
「おかしいわ。あたくし、たしかに見たんですの。写真も撮ったんですのよ」
マユミはスマホを取り出して、写真アプリを開いた。
「ここにちゃんと……あら?」
スマホの画面には土手から撮影した川の写真が映っていた。穏やかな水面に雲の影が映りこんでいた。だが、巨大なイカらしきものの姿はなかった。マユミは焦って画面を指でスライドした。次の写真も、その次の写真も同じような構図だった。
「変よ、たしかに撮ったのに……おチヨさん、本当にいたんです。でも写っていない。どうしたのかしら。あたくし、この目で本当に見たんですのよ」
チヨは混乱しているマユミの肩に手を当てた。
「私は写真に写っていようがいまいが、目の見えない私には同じことです。私はマユミさんのことを信じますよ。マユミさんはまちがいなくイカを見た。私は疑っていませんよ」
*
「そうそう、祭りのことだったわね」
タマミは紙コップのお茶を飲み干して立ち上がった。
「なにか、ばあちゃんから聞いてる?」
「いえ、なにも」シュウイチがいった。
タマミはうなずくと、スマホをとりだし、すばやい指さばきで、なにやら操作していた。
「たぶん、これでよし。つくっといてよかった。やっと役に立ったわ。あなたたちも、おつかれさま」
シュウイチたちは、ぽかんとした。
「あのう、なにがこれでよしなのでしょう。この鴨志田、祭りの買い出しと聞いて張り切って参りましたのですが、30キロの荷物を背負ってヒマラヤの高原を跋渉した私の真価をまだお見せするに至っていないのですが」
タマミが目線を上にむけた。
「ああ、買い出しとかはやってもらえるから大丈夫。手配しといたから」
「手配?」
「本当になにも聞いてないのね。話してもいいのかな。まあ、泡立て器買ってくれたからいいか。このかっぱ橋にはね、ばあちゃんが一声かけると無条件で協力してくれる人たちがいるの。前回はばあちゃんが直接やってきて、みんなのところを回ったんだけど、それじゃたいへんだからって、みんなと話してメーリングリストをつくっといたの」
「無条件で協力してくれるって?」シュウイチがいった。
「いったでしょ。ばあちゃんは魔女だって」
タマミによると、故郷を出て東京に出てきたチヨは、かっぱ橋の小料理屋で働いていたらしい。初めはまかないの手伝いをしていたが、店の主人が急病になり、チヨが切り盛りをまかされるようになった。
「料理も上手だったんだけど、ばあちゃんは〈見える人〉だったから、そこでいろんな人たちの相談に乗ったのね」タマミがいった。「ここでの商売のことや、病気のことや、家族関係のこととか。中にはそれで商売上の危機を脱した人や、なぜか病気が治った人とかもいた。口コミで評判が広がって、いろんな人が来るようになって、政治家とか大きな会社の社長さんとか外国の要人とかまで、こっそり来るようになった。話が長くなるんで省略するけど、そんなわけで、ばあちゃんがここを出るとき、ここの人たちが、どんなことでも協力するからといってくれたそうなの。ここって調理道具だけじゃなくて、なんでもそろうし、流通と職人のネットワークがあるの。イルカの家も、そのネットワークのおかげでできたって聞いてる」
「すごいですね」
「でもね、私、ばあちゃんは、最初からそのつもりだったんだと思う。偶然を装っているけど、じつはちがう。みんな、気がつくとばあちゃんの手の内で踊らされている」
「そういうタマミさんはどうなんですか?」
タマミはシュウイチを見て、それから小さく微笑んだ。
「私は魔女の孫よ。手の内はわかっている。ちなみに魔女の血ってね、隔世遺伝するんですって」