第3回 地球外知的生命体との交信は可能か?―『大般若経』に見る多仏世界―
前章で見たように、太陽系外の惑星、いわゆる系外惑星の発見により、これまでSFの世界の話だった地球外知的生命体の存在が、十分な現実性をもって語られるようになった。最近では系外惑星の大気から、生命の存在を示唆するバイオシグネチャーを捜索する試みもなされている。
しかしこれらの研究は、あくまで原始的な生命体や、植物などの存在を示唆するだけで、系外惑星に知的生命体が存在することを示す決定的な証拠とはなりえない。そこで近年は、知的生命体が発する電波などのシグナルを捉えることで、宇宙に人類とは別の知的生命体を捜索する試みがなされている。とくに米国カリフォルニア州にあるSETI, Search for Extra-Terrestrial Intelligence(地球外知的生命体探査)研究所上級研究員のセス・ショスタックは、講演活動やラジオ放送を通じて、地球外知的生命捜索に関する啓蒙活動を行っている。彼が果たしている役割は、かつてカール・セーガンが果たした役割に比肩できるかもしれない。
銀河系内に地球外知的生命体が存在する確率については、1961年にフランク・ドレイク博士が提唱したドレイクの方程式が有名である。これはN(銀河系に存在し、交信可能な地球外知的生命体の数)は、R*(銀河系で年に何個の恒星が誕生するか)とfp(その恒星が惑星を持つ確率)、ne(惑星を持つ場合、そのうち地球のように生命誕生可能な惑星の平均数)、fl(そこで生命が誕生する確率)、fi(その生命が知的生命体まで進化する確率)、fc(その知的生命体が星間通信をする確率)、L(その文明が維持される年数)の計7つの因子を掛け合わせることで見積もることができるとするものである。
ドレイクがこの方程式を考案した当時、系外惑星はまだ一つも発見されていなかったが、Nの値は20程度と見積もられた。これは地球外生命体との交信の可能性に希望を与えるものであった。
SETIは1985年に創設されて以来、40年に亘って、電波望遠鏡や光学望遠鏡を使用して地球外知的生命体が発する電波を探索しつづけているが、いまだ確たる成果を挙げていない。そこで単に宇宙からの信号を受信するだけでなく、地球から生命が存在する可能性がある惑星系に向けて信号を発信し、相手の応答を待つというプロジェクトも始められた。これは従来のSETIが受動的だったのに対し、Active SETIあるいはMETI, Messaging to Extra-Terrestrial Intelligenceと呼ばれている。
このような地球外知的生命体に人類の存在を知らしめる計画は、1977年に相次いで打ち上げられたボイジャー1号と2号に搭載された、ゴールデンレコードをもって皓歯とする。これは、カール・セーガンの提案に基づくものといわれる。ゴールデンレコードには各国語で収録された人類の挨拶の音声データをはじめ、地球の位置を地球外知的生命体に教えるため、地球近傍のパルサーとの位置関係を示した図も添付されている。
ボイジャー1号は2012年に太陽圏を出て、広大な星間空間に出たことが確認されたが、他の恒星の近くに到達するには、さらに数万年かかるといわれている。そこで地球外知的生命体がゴールデンレコードを発見したとしても、その頃には地球や人類は、すでに存在しなくなっていると予測されている。
このように広大な宇宙に、地球外知的生命体が存在する可能性は高いが、地球近傍の地球外知的生命体を発見し、それと交信することは極めて困難といわざるを得ない。ドレイクが見積もったように、銀河系内に20の地球外知的生命体があったとしても、銀河系の直径は10万光年もあるため、直近の地球外知的生命体と交信するにも数万年かかる可能性があるからである。
いっぽう地球近傍の系外惑星まで探査機を飛ばし、調査を行うという計画も進行している。太陽系から最も近い恒星は、ケンタウルス座の赤色矮星プロキシマ・ケンタウリである。ところが2016年に、ケプラー宇宙望遠鏡により、プロキシマ・ケンタウリを周回する系外惑星プロキシマ・ケンタウリbが発見され、それが主星のハビタブル・ゾーンに存在することが分かった。他の系外惑星とは異なり、太陽系とプロキシマ・ケンタウリの間は4.2光年しか離れていない。超巨大な宇宙のサイズからいえば、きわめて至近の距離にあるといえる。
2015年7月、英国王立協会がロシアの投資家ユーリ・ミルナーの資金援助を受けて発表したブレイクスルー・イニシアチブは、地球外生命探索を活性化させるための総合プロジェクトで現在、複数のプロジェクトが進行している。
その中でも、2016年にミルナーと理論物理学者のスチーブン・ホーキングによって発表されたブレークスルー・スターショットと呼ばれる計画は、プロキシマ・ケンタウリまで超小型の宇宙船「スターチップ」を飛ばして、プロキシマ・ケンタウリ星系のスナップ・ショットを撮影し、地球に送信するというものである。
通常のロケット推進システムでは、4.2光年離れたプロキシマ・ケンタウリに到達するのに、ボイジャー1号のように巨大惑星の近くを通過して加速するスイングバイを用いても数万年かかる。そこで地上に巨大なパラボラアンテナを建設し、そこからレーザー光を「スターチップ」の帆に照射して、持続的な推力を得るという方式が検討されている。これによって光速の20%にまで到達すれば、20年ほどでプロキシマ・ケンタウリに到達できるが、撮影されたデータが地球に届くまでは、さらに4年を要するとされている。
ケプラーの法則で有名なヨハネス・ケプラーは、かつて宇宙を帆船で移動する宇宙航海を夢見たといわれるが、これはその現代版である。
このように1990年代に最初の系外惑星が確認されて以後、初期に発見された主星近傍のホット・ジュピターから、固体の地表をもつ地球型の系外惑星、さらにハビタブル・ゾーンに存在する地球型惑星がつぎつぎと発見され、人類は地球外に生命が存在するかという長年の課題解決に大いに近づいてきた。しかしそれは、あくまでバクテリアなどの単細胞生物を含む地球外生命体の話であり、地球外知的生命体の探索は、いまだ道遠しというのが実態といわざるを得ない。
とくに最近は、UFOなどの目撃情報に加え、宇宙人との遭遇や宇宙人に拉致されたとの体験談、さらに宇宙人の遺体と称されるものの発見など、マスコミには地球外知的生命体に関する多くの情報が氾濫している。さらに地球外知的生命体はすでに何度も地球を訪問しているのに、政府によってその事実が封印されているとの陰謀論もある。
しかしそれほど地球外知的生命体が頻繁に地球を訪れているのなら、どうしてSETIやMETIなどのプロジェクトに一向に反応しないのだろうか。私は、地球外生命の発見は遠からず実現すると考えているが、地球外知的生命の誕生に関しては、それが極めて稀な事象であり、しかも地球外知的生命体の存続期間、つまり前述のドレイクの方程式のLが、宇宙の悠久の時間に比して、極めて短いからではないかと考えている。
これに対して、初期の大乗仏典には、他土仏とその国土の衆生という形で、地球外知的生命体の存在と、彼らとの相互交流の話が至る所に説かれている。
とくに初期大乗仏典の開幕を飾る序分には、ブッダが経典を説くに先だって眉間の白毫から光明を放つと、それが他の世界に到達し、それぞれの世界のブッダが娑婆世界に菩薩を派遣して、ブッダの説法を聴聞させるという物語が数多く語られている。大品系の『般若経』「縁起品」や、『華厳経』「如来光明覚品」に説かれる十方世界からの菩薩の来詣は、その典型的な事例である。
その中でも大乗仏教の根本聖典である『般若経』「縁起品」の物語は、チベット仏教圏において何度もタンカ(軸装仏画)や壁画に描かれ、重要なモチーフとなった。(写真)
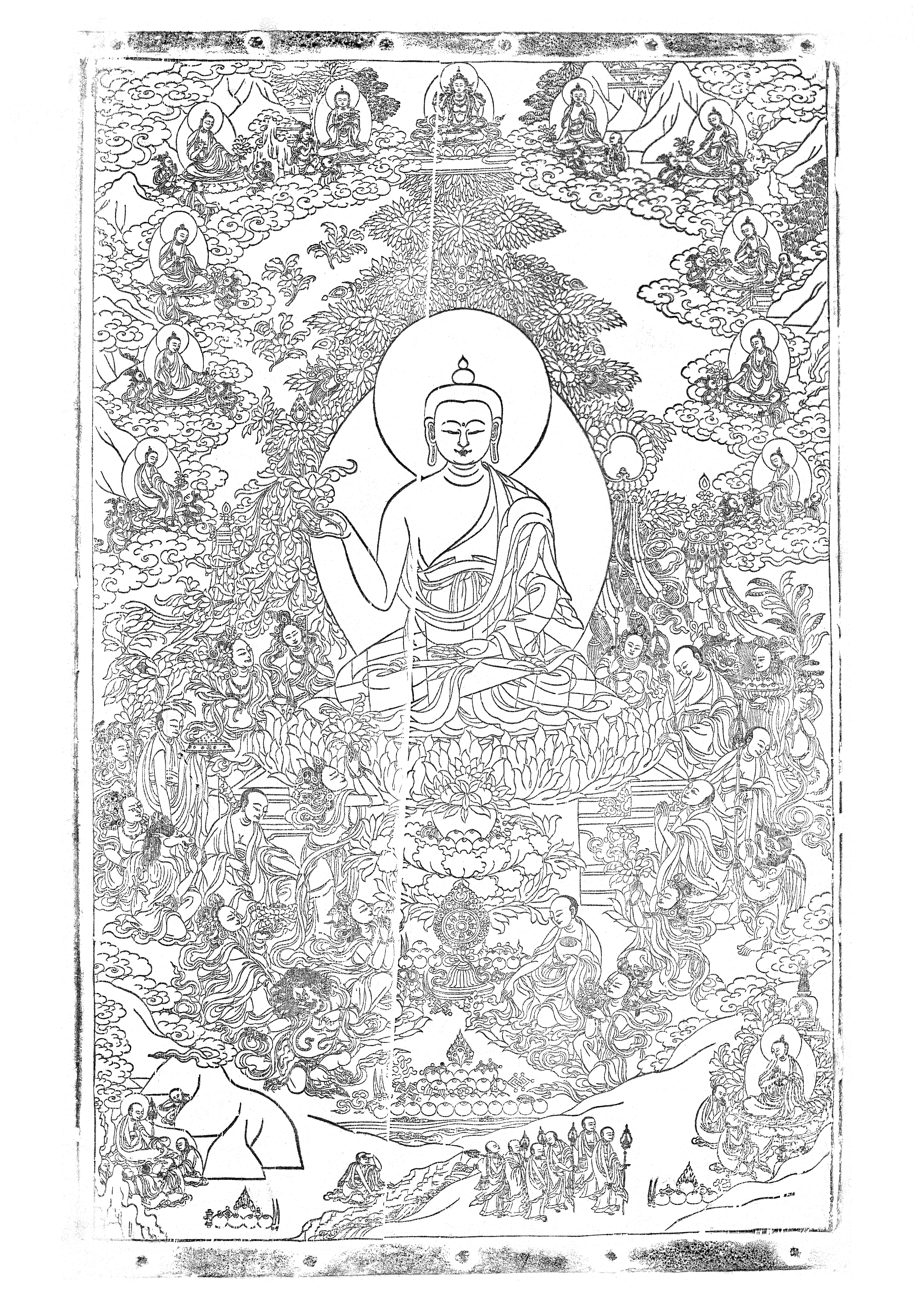
写真の作品は、ブッダの誕生から入涅槃までを描いた仏伝のタンカ・セットの1幅で、転法輪つまりブッダの説法の場面を描いている。その構図は、東チベット出身の仏画師プルブツェリンの原画に基づき、デルゲ印経院で開版された仏伝図9幅セット(ゼーパグタン)の図像を踏襲している。
仏伝図の転法輪としては、サールナートにおけるブッダの最初の説法、いわゆる初転法輪を描くのが通例である。ところが写真のブッダは、説法を象徴する転法輪印ではなく、右手に蓮華を持っており、その上方には『般若経』を尊格化した般若仏母、その左右には5尊ずつ十方仏が配されている。これは初転法輪ではなく、霊鷲山における『般若経』の説法を描いたものである。
チベットでは、『大般若経』の説法を描いた「十万頌般若縁起図」(ブムギ・レンシイ・ディークー)という絵画が描かれたことが知られている。これはブッダが『大般若経』を説くに先立って、眉間の白毫から光明を放つと、その光が十方世界に至り、十方世界の仏は、それぞれ一人の菩薩を娑婆世界の霊鷲山に遣わせて、金色の蓮華を奉献し、『大般若経』を聴聞させたという『十万頌般若経』「縁起品」の所説を絵画化したものである。
本作品では、十方仏が、それぞれの国土で菩薩に蓮華を託する場面が描かれているので、『大般若経』「縁起品」を描いたことが確認できる。これはチベット仏教が大乗仏教に属し、小乗の教えを説いたサールナートの初転法輪より、大乗の根本聖典である『大般若経』を重視していることを示している。
この問題については、拙著『仏菩薩の名前からわかる大乗仏典の成立』(春秋社)で紹介したが、大乗仏教では、菩薩が第十地に至って首楞厳三昧を成就すると、十方の仏国土の間を自由に往来することができるとされている。つまり初期大乗仏典にしばしば登場する異なった世界間を瞬間移動できる大菩薩は、首楞厳三昧によってその能力を獲得したとされている。
つまり古代においては光速は無限大と考えられており、現代の用語でいえば、数十万光年離れている世界間でも、光によって瞬時に交信可能と考えられていた。そして高位の菩薩は、数十万光年離れた世界間でも瞬間移動できるため、このような異なった世界間のコミュニケーションが可能とされたのである。
なお第12回で話す予定である「量子もつれ」が存在する確率が高まった現在、「量子もつれ」を利用した瞬間的高速通信の可能性が議論されている。ただしこれが実現可能であれば、光や電磁波を利用した地球外知的生命体の捜索自体が無駄になる恐れがある。捜索対象である地球外知的生命体が高度に文明化されていた場合、すでに電磁波を用いた通信は時代遅れになっている可能性が高いからである。
また科学者の間では、光速を超えて宇宙旅行ができないという難点を解決するため、時空の歪みを利用したワープ航法の可能性が真剣に議論されているが、初期大乗仏教においては首楞厳三昧によってワープが可能であるとされていたといえる。
このように大乗仏教では、仏教を通じた異世間交流の物語が、至る所に語られるが、それは仏教が、時間空間を超えて万物に適用される因果律の存在を認め、仏はその因果の理を悟って成仏したという大前提をもっていたからに他ならない。
そこで次回では、仏教の因果観について考えてみることにしたい。



