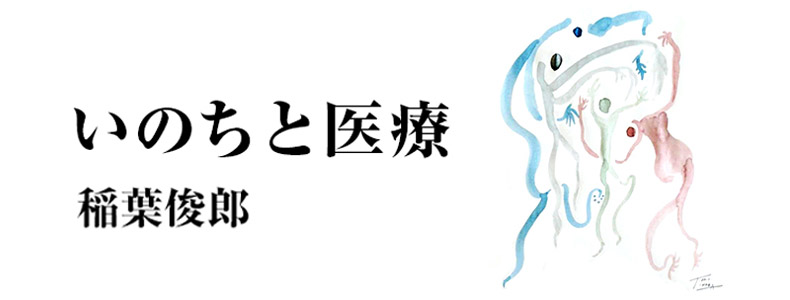芸術と医療
芸術と医療には接点がある。それは、共に人間の全体性を取り戻す営みだからだ。
「わたしたちはなぜ芸術を必要とするのだろうか」と、真剣に考えてみたことがあるだろうか。すこし立ち止まって考えてみたい。
心には全体性がある。意識できるところから、意識できないところまで。よくわからない心の場所は無意識と呼ばれたり、潜在意識や深層意識と呼ばれる。はっきりとつかむことはできないが、時々表に顔を出すことがあり、確かに存在はするのだろうと考えられる場所だ。心の領域は広く深い。ただ、わたしたちが普段接する場所はほんの上澄み液しか使っていないように見えるし、心も活動して動き続けているように思えるのだが、その動きの全貌はどうも見えにくい。そうした心の動きや働きを理解するには何かしらの補助線が必要になる。そのために、心が動いて活動している以上、駆動力となるエネルギー源があるはずだと考えてみたい。心という漠然とした掴みどころのないものを考えるために、心を動かす源である心のエネルギーの動きを考えてみると、心の活動の全体像がイメージしやすくなるので、まずそこから考えてみたい。
そもそも、エネルギーとは何だろう。エネルギーとは、もともとは19世紀ころから使われるようになった物理学の用語で、「物体の内部に蓄えられた仕事をする能力」のことを指す。エネルギーという言葉の語源は、哲学者アリストテレス(紀元前384年‐322年)が使った「エネルゲイア(energeia:現実態)」に由来している。アリストテレスは、すべてのものは、「デュナミス(可能態)」という可能性を持った潜在的な状態から「エネルゲイア(現実態)」として可能性を実現し変化したものであると考えた。つまり、表面に見える結果のもの(エネルゲイア(現実態))だけではなく、そのものを成立させている潜在的な段階(デュナミス(可能態))も重ね合わせて見ることを大切にしたのだ。デュナミス(可能態)とエネルゲイア(現実態)という二つの変化の状態を見ることは、木材から家が建てられること、種から花が咲き果実が実ること、などを考えれば理解しやすいだろう。そして、そうした存在物を示す言葉としての「エネルゲイア(energeia:現実態)」という用語が、「仕事(ergon)」を意味する言葉から作られている。木材から家が作られることは「仕事」であり、種から樹木が作られるためには「仕事」が必要である。あらゆるものごとの中に「仕事」の働き、その結果としてすべてのものが存在すると考えた。紀元前のアリストテレスの時代の後、19世紀の初めまで「仕事(ergon)」の概念は、ラテン語で「vis(ウィス)」(日本語では「力(ちから)」の意味に近い)と呼ばれ、広い概念で捉えられていた。19世紀頃の自然科学の発展の中で、「熱の力」が蒸気機関車を動かす「仕事」へ変換されたり、「電気や磁気の力」が別の「仕事」へ変換されることが発見された。熱も電磁気も「力」は相互に変換可能であることが分かってきたこともあり、「vis(力)」という言葉ではなく、19世紀ごろに「エネルゲイア(energeia:現実態)」から「エネルギー」という用語が作られたのだ。そのため、「エネルギー」という新しい言葉の中には、最初から「仕事」や「力」という概念と深い関わりがある。自然科学の発展の中で、熱も光も電気や磁気も、本質的には「仕事をする力」を潜在的に持っていて、しかもそれは相互に交換することができるし、別の形で取り出すことができることが分かってきた。アインシュタインが指摘したように、物質の「重さ」自体も実はエネルギーの一つの形態でさえあることも発見された。自然の存在物を統一的に説明する言葉として、「エネルギー」という言葉は非常に有用だった。あらゆる存在物(「重さ」さえも)は、「仕事」をする「力」を内在している。
その後、19世紀ごろに物理学で使われるようになった「エネルギー」が転じて、一般用語でもエネルギーという言葉は使われるようになる。「もうエネルギーが切れた」「あの人はエネルギーが溢れている」という表現からもわかるように、物事を成し遂げるため、その活動の源として必要な力、気力、活力などの意味でもエネルギーという言葉は使われている。個人の「気力」、「活力」という言葉の中に「力」という言葉が入っているように、エネルギーという言葉には「力」や「仕事」という概念と深く関係があることが重要なことなのだ。
わたしたちの体は日々生命活動をしている。生命を維持するという重要な「仕事」をしている。生きている限り、その「仕事」は行われ続けている。そうした「生きる力」を得るためのエネルギー供給源として、我々は毎日食事をしているし、人は食事をしないと生きていけない。そして、体の世界と同じように、心の世界でも日々「仕事」は行われている。心の仕事としては、「気配り」「気疲れ」「気が揉む」「気がはやる」など、「気」(正字は「氣」)という言葉が日本語では多く使われていることがわかるだろう。心が行っている色々な目に見えない仕事も、わたしたちの命を適切に維持するため行われている重要な「仕事」の一環なのだ。
心の仕事は様々なものがある。日常的に行っている仕事としては、自分の心の中に受け入れられるもの、受け入れがたいものを選別する仕事があるだろう。「気配り」したり、「気疲れ」しているのも、目の前の現実をなんとか自分なりに対応していこうとする中で、自分の心に受け止め、受け入れていく過程で起きるズレや違和感の中から感じられる身体感覚だ。意識しようとも意識しまいとも、わたしたちは日常の体験を心の中に収めていく。「受け入れがたい」と感じられるものは、どうしようかと、あらゆる策を講じてベストを尽くす。時には原体験にすこし手を加えることもあるし、原体験を受け入れやすい形に加工、編集することもある。合理化して自分なりの理由付けをして心におさめやすくもする。時には一時的に排除し、なかったことにしてその場をやり過ごすことも止むを得ない常套手段だ。生きている限り、心はあらゆる手段を講じて、自身の体験を自分の心の器へと収める「仕事」をし続けている。ただ、そうした心の仕事は目に見えないから分かりにくい。そうした心の仕事を行うために、体がとる食事と同じように、心にもエネルギーが必要だと考えてみてはどうだろうか。
心は動き活動し続けているから、心のエネルギーも目に見えないが存在していることは感じられる。元気がでない、やる気が出ない、という状況の時、そうした心のエネルギーがうまく働いていないことを実感するだろう。エネルギーが心を動かすために心全体に行き渡っているならば、この自然界を栄養源として支えている「水」をイメージして考えてみたい。水はこの自然界を循環している。今この目の前の空気中にも、見えないだけで水は細かいガス状に存在している(冷たいコップの外側に突然水滴がつくのはそのことが理由だ)。空では水は雲となり、雨に変わって降り注ぐ。雨は山や大地に染み込んでいき、水は小さい流れとなり、支流は川となり、海へと通じていく。陸地に降り注いだ水は、土の中にも奥深く染み込んでいき、自然を養う。地下の土の中にはあらゆる年代の水が貯蔵され、還流している。川や海だけではなく、池や湖もある。地下水もある。大地の水の流れのはじまりには水源があり水の泉がある。海の水は表面で見える波だけではなく、深い海底に静かに存在する水もある。やがて海や川の水は水蒸気となり空気中に浮かび、雲となる。また雨となり降り注ぎ、自然界を循環することであらゆる生命を養っている。
こうした自然界を支える水のイメージを、自分の心という自然環境、生態系に適用して考えてみよう。体も心も、わたしたちが日々抱えている内的自然なのだ。
わたしたちが外側の世界に向けて活動できているとき、心のエネルギーは表向きの場所を循環しながら流れている。陸地を流れる雨や川や海の流れのように。陸地に流れる水を見るとき、そこには地下水や海底のような水の流れに同時に感じることが大切だ。陸地の水が適切に循環して流れていくためには、表面上は見えないが確かに存在している地下水も同じように循環して流れていることが前提条件として相補的な関係性として重要なことなのだ。
わたしたちが内側の世界にひきこもってしまい、外側の世界に向けてうまく適応できなくなっているときを考えてみる。そのとき、心のエネルギーは地下水や海底など、一見すると目に見えない場所で停滞して、光が当たる陸地をうまく還流できていないのではないかと想定してみるのだ。人は生きている限り、命のエネルギーは必ず存在している。エネルギーは存在しているのだが、その内的な心のエネルギーがうまく循環していかないと、心は表に向けて活動できなくなってしまう。
そう考えると、心が仕事をするためには、地上と地下に流れる水路を適切に作り直すことが必要になるし、地下水を表にくみ出す通路も必要になる。水路づくりは自分という存在の再構成が起きることであるし、地下水をくみ出す通路は、芸術などを含んだ、生きる「表現」を行うことでもある。
地下の水がうまく流れていかないとき、地下水の水源が枯れていたり破壊されていたりすることもあるだろう。その場合は、さらなる別の水源を探す必要がある。同じ地平に水源を探せなくなった時には、時にはさらに地下へと深く掘り進め、冒険や探検をするように未知の水源を探しに行く必要も出てくる。
水の流れが滞っている原因を探し出し、その原因に対して適切に対処すればうまくいくこともある。水路が壊れているなら、その水路を修理しなおせば水の流れが回復するように。ただ、原因をさかのぼるという行為は過去へ過去へと視点が向かうことでもあり、過去を変えることができない時には袋小路に陥ってしまい、どうにも手詰まりに感じられる場合もある。そのときは、視線を未来へ向け、「さて、ではどうするか」と、新しい水路づくりに取り組まなければいけない。未知の水源を探るには、深く掘り進めるしかない。そうした深い「仕事」に取り組むことは孤独で大変な作業でもあるが、生きている限り、そうした仕事は避けられないこともあるだろう(そして、こうした仕事の質や量、時期・・には大きな個人差がある)。人によっては避けられない「運命」という形で向こうからやってくることもある。もちろん、そうした仕事に取り組むには適切な時期やタイミングを計ることも大切だ。そうした一大プロジェクトに取り組むにはそれなりの「力」が必要になるからだ。周りも、本人の力が蓄えられるまでに「待つ力」も必要になる。水路づくりや水源探しの適切なタイミングを見つけるのに単純な解法は存在しないが、そうした心の内部でひそかに行われている仕事をイメージして共有することこそが大切なことなのだ。
ここで最初の話題に戻る。わたしたちはなぜ芸術を必要とするのだろうか。芸術は、こうした私たちの偉大な心の内部の基礎工事と、大きく関係している。それは自分自身が芸術に取り組んでいるときでも、鑑賞者として見ているときでも。生きるという生命活動を行っている以上、わたしたちは体験や環境の中からあらゆる矛盾したものを心の中に同居させて受け入れていくプロセスが進行しているのは避けられないことなのだ。たとえば、命は、生だけではなく最初から死が初期設定として埋め込まれている。生と死とは矛盾する概念として最たるものであり、どんな生命にも共通している前提なのだ。ただ、上という概念がなければ下という概念もないように、死という概念がなければ生という概念自体が存在しない。わたしもあなたも、男性も女性も、赤ちゃんもお年寄りも、人間も動物も植物も菌類も。わたしたち生きとし生きるものたちは、生と死という矛盾したものを心というひとつの器の中に同居させながら、日々生きているのだ。心は、そうした困難な仕事を粛々と続けている。
芸術の体験は、わたしたちの心の内部で仕事を行うための心のエネルギーが還流する水路づくりとも大きくかかわっている。たとえば、わたしたちが感動した時。日常では使うことがない心の層が揺さぶられているのがわかるだろう。そのとき、わたしたちの心の内部では地殻変動が起き、水源から新しい水路を経て水が流れ出すように、心のエネルギーが動き出す。地層が深ければ深いほど、わたしたちはわけのわからない力に揺り動かされるように感じる。心の深層が揺らぐことで、心全体の構造がグラリと揺らぐのだ。そうした時、何かがひらめいたり、許せないと思っていた人を突然許せるようになったり、悩みが吹き飛んだり、理解できなかった人がなんとなく理解できるようになったりすることが起こる。心が動き、心の構造が組み替えられることで、わたしたちは結果として異なった心で物事を見るようになり、別の視点を得ることができるのだ。
芸術には、わたしたちの意図を超えて心を動かし、心の全体像を組み替える力がある。 ある画家の言葉を紹介したい。それは猪熊弦一郎という画家の言葉である。彼は、「美術館は心の病院」と言い、香川県丸亀市に現代美術館であるMIMOCA(Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art)を作った。その言葉を描いた色紙はいまも同美術館に大切に保管されている。
猪熊氏は、1902年香川県に生まれ、1993年に83歳で亡くなった。東京美術学校(現・東京芸術大学)に入学した後、フランスに渡りアンリ・マティスの指導を受けた。第二次世界大戦時には従軍画家として戦地へ派遣される辛い時期も経て、日本は終戦を迎えた。彼は戦後の日本に何が必要なのか、美術が何に貢献できるのかを徹底的に考えただろう。その中で、生活の中に美や芸術を届けるため、1950年には三越の包装紙「華ひらく」のデザインを行い、1951年には上野駅の壁画「自由」というパブリックアートも手掛けている。戦争で荒れ果てたのは土地だけではなく心も荒廃したのだと考えた。そのために生活の希望の光を照らすために美や芸術を広く届けることを意識的に行った。その後、1955年には新しい絵画の追求のために活動の拠点をニューヨークに移す。人工的な都市生活にインスピレーションを受け、この時期に画風は具象から抽象へと一気に変化している。表面的な人工都市の奥深くに存在する、わたしたちの複雑な心そのものをそのまま表現するために、抽象画という手段を使わざるを得なかったのだろう。その後、脳梗塞で身体の不自由が生じてからは、冬は温暖なハワイで生活をしながら新しい画風を創造しながら絵を描き続けた。生活の場を移しながら、画風も常に変化し続けた。それは自分の日常生活を壊すことで同時に画風をも壊し、芸術と人生を一体化するように新しい絵画やイメージ世界を創造し続けたのが猪熊弦一郎の人生なのだ。
猪熊弦一郎『猪熊弦一郎のおもちゃ箱
「日本に美を分かる人をもっと増やしていきたい。美を分かる人こそ、平和を求める人だと思います。」
「絵画は独占するものではなくより多くの人を喜ばせ、みちびくもの、多くの人々のためになるべきもの」
猪熊氏が求めていたものは果たして何だろうか。戦争を経験した彼がそれでも真摯に美術の世界で追求したことは何だろうか。「美術館は心の病院」という言葉の中には、日々の暮らしの中で美術館に行く時間が増えることで心の深層が活性化され動き出す。そうした心の深い動きは、不思議と自分の心がまとまること、新しい形におさまっていくことへとつながっていくだろう。美術がもたらす全体的な体験による内なる世界が変化することの可能性を、強く信じ続けていた人なのだろうと思う。
現代の暮らしはどうしても時間に追われる。それは自分の体内を流れる生命の時間とはまるで異なっている時間だ。利便を中心とした、人々の意図が複雑に絡み合った慌ただしい時間。速い時間感覚に飽和していくと、どうしても呼吸も浅く速くなる。わたしたちの内的な時間は、呼吸によって大きく影響される。それは原因にも結果にもなる。浅く速い呼吸をすると、わたしたちの主観的な時間も速く急き立てられていく。それに対して、深く静かなゆっくりした呼吸をすると、わたしたちの主観的な時間もゆっくり流れだす。美術館に入る体験だけでも、そうした忙しい日常の時間から離れ、ゆっくりとした内的な時間を過ごすことにもつながるのだ。
世間の評価と関係なく、自分が美術作品を見たときに何か心が動いたことを感じたら、それこそが大事なのだ。そのとき、果たして何がやりとりされたのだろう。「イメージ言語」のやり取りの中で、自分の中のどういうイメージ世界が反応しているのだろう。それは自分たちを支えている内部のイメージ世界の源泉を、探っていくことになる。それは、寝ている時に接しているイメージ言語である「夢」の体験と似ているのだ。「夢」も、外向きの目は閉じているが、イメージ体験はしている。内なる目で捉えたイメージ世界。
たとえば、なぜこの赤と白と黄色の配置が美しいのだろうか、と自分の感受性に今一度立ち止まり、問い直してみる。きっと、そこには「心の自然」にとって、形態やバランスに意味があるはずなのだ。自分の心におさまりがつくとは、そもそもどういうことなのだろう、と自分自身に問い直してみる。目は外向きについているが、そうした外向きの目では決して見ることのできないものが内部に広がる心という抽象的な存在だ。心は内なる目でしか捉えられないものだが、外にあって響きあうイメージ世界と呼応させ響かせる形で、間接的に感じられる。
そうして、心という存在も常に全体性を保とうとしてバランスを求めている。それがあるときには美術作品の中でイメージとして提示されることで、心の動きや揺らぎとして感じられることがある。もしくは、自分自身の深いイメージ体験である「夢」というイメージ体験の中で。 覚えていなくても忘れてしまおうとも、眠りという重要な休息の時間の中で、わたしたちは日々「夢」というイメージ体験をしている。だからこそ、命が生きている限り、美術や芸術と関係がない人なんているはずがないのだ。
芸術と医療には接点がある。それは、共に人間の全体性を取り戻す営みだからだ。そして、「人間の全体性を取り戻す営み」として芸術や医療を考えなおしてみると、人間が生み出したその他の文明や文化の中にも、「失われた全体性を取り戻す」ことに源を発して、「全体性を取り戻す」ことを目的としている営みを数多く発見することができるだろう。
そうした異なる世界の根底に接点やつながりを発見し、異なる世界に通じる通路を発見することは、この世界の中から美を発見する行為としての美術や芸術とも似ている。わたしたちは、そうした自分たちの感受性を再発見して取り戻し、新しい視点で日々を創造しながら生きていくためにも、芸術を必要とするし、医療を必要とする。そして、そうした生命の営みがすべて一つになっていることが、「生きる」という全体像のことなのだ。