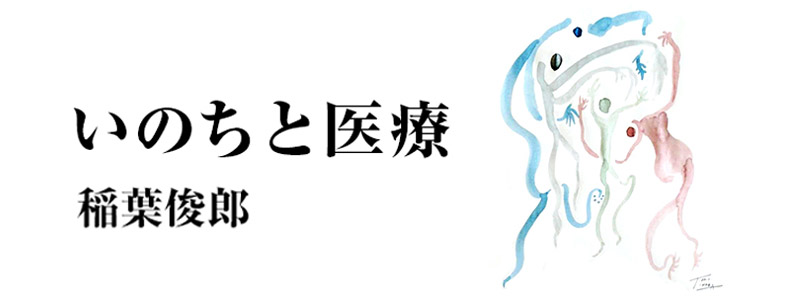養生から幸せを問いなおすーー養生と医療
「いのち」を「養う」ということ
養生は「生」を「養う」と書く。
「生」とは「生まれてくること」であり「生きること」である。そう考えれば、「養生」とは生きているものすべてが関わらなければいけない重要なことだ。「生」は単にそのまま手つかずで放置していれば維持されるものではなく、自然を手入れするように、自分自身が自分自身の「生」を「養う」必要がある。医療は人の生命の神秘に関わるものだから、「養生」が基礎にあるはずだ。それは患者さんに対してだけではなく、医療に関わるものこそが自分自身に対して行う行為としても重要なことだろう。
現在の医療システムでは「病院」という場が医療を行う主役を担い、日本全国に展開されているが、「病院」は名前の通りあくまでも「病」を扱う場所として作られている。つまり、「病院」は「病気」を持つ「病人」を対象にした場所である、ということだ。「病気」を持たない人は、「病院」が扱う対象から外れてしまう。もちろん、体のバランスが崩れて「病」を発症すると、誰もがなんとかしてほしいと思うし、「病」を解決する場所が必要となるのは当然のことだ。ただ、体や心は常に病を発症しているわけではない。60兆個という圧倒的な細胞の数で構成されている私たちの体は、調和と不調和の間を常に行き来するように動きながら体全体を、心全体を調整し続けている。いのちはそうした部分と全体が織りなす究極の存在形態でもある。そんな奇跡的な仕組みを与えられたわたしたち人間は、何事もなく体や心が機能している期間も多い。だからこそ、そうした奇跡的な生命の状態を養い育むような「養生」の時間も、自分に与えられた命に貢献する行為として重要である。「病気」であろうとなかろうと、「養生」を育む場所も、「病院」と同じくらい必要であると思う。
そう考えると、普段から養生する場としての「養生所」、病になってしまった特別な時期に病気の治療に専念する場としての「病院」は、互いに補いあう場ではなかろうかと思う。現在の医療に何か欠けているところがあるとすれば、まさにそうした「養生」を扱う場所ではないだろうか。
自分自身の考えで「みずから」治療行為に関与して心身の改善へ至るのが「病院」という場であるとすると、生命が生まれながら備えている自然治癒の力で「おのずから」身心がいい状態へと向かっていく生命の条件を整えていくのが「養生所」であるとも言えるだろう。生命は、「みずから」と「おのずから」のあわいの状態を行き来しながら、絶妙なバランスを維持し続けている。
病院の近代史
医療現場で働いていても、現代の日本の医療システムで、平常からの「養生」を扱う感覚が欠けていると思う。では、そもそも日本の「病院」はどういう流れでここまできているのだろうか。そうした日本の病院の歴史を簡単に触れたい。
「病院」という施設が広く普及するようになったのは明治以降であり、つい最近のことだ。小規模な医療施設は過去にも存在していたが、現代につながる「病院」というシステムのような大規模な施設はここ100年くらいで発展した最近のものだ。
ちなみに、「病院」という言葉自体は、江戸時代の医者・戯作者・蘭学者である森島中良(ちゅうりょう)が、『紅毛雑話』(1787年)の中で、「Ziekenhuis」を病院と訳したのが最初であるとされている。
西洋のキリスト教世界では修道士が病人を集めてお世話をしており、そうした宗教的施設が「病院」としても機能していた。16世紀の宗教改革以降、プロテスタントの地では宗教から病院が切り離されるようになり、18世紀には、病院は宗教的な貧民救済としてではなく、病気やけがの治療のために使われるようになり、高度に専門化していくことになる。ヨーロッパでの宗教を背景とした「病院」が、訳語として日本に18世紀頃に入ってきてから、実際に日本各地に「病院」のシステムが作られるまでに約100年近くかかることになる。そうして、江戸時代から明治期にかけて、西洋の考え方が流入してくるとともに「病院」というシステムが生まれてくるが、病院には四つの大きな流れがあった。
一つ目は、貧民救済のための無料施設としての病院、二つ目は、外国人教師による西洋医学教育の場としての病院、三つ目は、戦争による負傷者の軍陣病院、そして四つ目は個人の志で作られた私立病院である。それぞれを見ていこう。
(1)貧民救済施設としての病院
江戸時代までには日本には「病院」というシステムがなかったため、一般市民が入院・治療を受ける場所は皆無であった。それまでの日本の医療は往診を主としており、家族や共同体による自宅内での介護が前提であった。ただ、様々な事情で独り身の者もいて、そういう人たちは適切な医療のケアを受けられず、貧富の差は激しかった。1722年(享保七年)、小川笙船(しょうせん)という町医者が、目安箱に江戸の貧困者や身寄りのない者のための施薬院を設置することを希望する意見書を投書。それを受けた徳川吉宗は、享保の改革の一環として小石川御薬園(現在の小石川植物園)内に養生所を設立し、幕末まで無料の貧民救済施設として機能した。黒澤明監督の「赤ひげ」という映画は、この小石川養生所をテーマとした映画である。貧民救済のための医療施設が、和漢薬の素材となる植物園内にできたことが、病院の流れの一つとしてあることは重要なことだ。
(2)外国人教師による西洋医学教育の場としての病院
日本の病院の二つ目の流れとしては、西洋医学に基づく西洋式の病院の流れがある。厳密には日本で最初の西洋式病院は、1556年(弘治三年)に、豊後府内(大分)領主である大友義鎮の援助を受け、イエズス会の宣教師であるルイス・デ・アルメイダ(Luís de Almeida)が設立した病院とされる。医師でもあったポルトガル人のアルメイダが外科を担当し、日本人医師キョウゼン・パウロが漢方医として内科を、のちにミゲル、内田トメが引き継いで診療を行った。ただ、入院病床が16人と小規模であり、30年後の1586年(天正一四年)には、島津軍が大友軍を破り府内を占領した際に病院は焼失している。そのため、軍医ポンぺが関わった1857年の長崎での洋式の近代型病院が、現代につながる病院の一つの流れのはじまりと考えられる。長崎や大分などの九州の地は、異国からの様々な文化がやってくる土地でもあったため、そうした新しい医療の潮流が生まれる土地でもあった。
1857年(安政四年)、オランダ医学を伝えにやってきたオランダ海軍の軍医であるポンぺ(J. L. C. Pompe van Meerdervoort)(1829-1908年)は、長崎で洋式の近代型病院を作った。長崎大学医学部の前身である。この施設は、同時に蘭学の臨床実習の場でもあった。1858年(安政五年)にはコレラ大流行もあったことが、病院建設の後押しとなった。
上記の1722年に設置された小石川養生所は無料施設だったが、この長崎養生所は有料施設である。長崎養生所での支払い料金に関する当時の養生所規則が、その後の日本の病院規則のモデルともなっている。この長崎養生所は、実際には高級武士や裕福な町人、往来する外国人の入院・治療が中心で、一般の人には近づきにくいものだった。貧困者を救済し、慈愛の手を差し伸べるというヨーロッパの病院や、小石川養生所のような面影はなかった。また、この西洋式病院は、最高水準の医療最先端の学を行う場所として発足しており、病院こそが最高の医療機関であるという日本の病院の特色の原型もここにある。
(3)戦争の影響による軍陣病院
三つ目の病院の流れは、戊辰戦争(慶応4年/明治元年)(1868-1869年)のときに負傷兵のためにできた軍陣病院である。その中でも最大規模のものが、東京下谷和泉橋の藤堂邸跡に建てられた「大病院」であった。英国公使館付き医師のウィリアム・ウィリス(William Willis)が治療の指導者であった。当時は、開国により海外の見たことのない病気が流行すると噂されていたこともあり、外国人教師を医療の指導者として雇っていた。病人は貴賤に関係なく受診するように、とされていたが、実際の入院費は高額であり、一般人には縁のない病院として始まっていた。ちなみに、明治政府がその後ドイツ医学を採用したので、イギリス人であるウィリスは辞任した。
(4)個人の志による私立病院
四つ目の病院の流れとして、上記三つの流れを補完するために貧民救済を主目的とした有料受診の私立病院の流れが生まれた。蘭方医である佐藤尚中(たかなか)は、1872年(明治五年)、佐々木東洋らとともに日本初の私立病院「博愛舎」を設立、これが順天堂医院開設へとつながる。現在の順天堂大学医学部である。当時は私立病院こそが、貧しい人たちに手を差し伸べる病院の役目を果たしていた。
上記の4つの流れから分かるように、日本での「病院」というシステムは江戸後半から明治以降にかけて急速に設立されたものでもある。それまでは町医者による在宅往診、もしくは民間医療、療術、加持祈禱などを含め様々な手段で医療は行われていた。しかし、日本では明治維新後の1874年(明治七年)に医師を免許制とする制度が導入されたとき、西洋医学を採用したためすべての漢方医でさえも無免許医となってしまった歴史もある。当時存在していた多様な医療は、急速な文明開化を行った明治維新の時期に、急速に失われてしまったのだ。
16世紀に日本へ渡来した南蛮人(ポルトガル人・スペイン人)の伝えた南蛮医学も、江戸時代初期に蘭学を伝えた紅毛人(オランダ人・イギリス人)の紅毛外科も、いずれも戦争の経験から得られた外科学や外傷学を得意としている。戊辰戦争を契機とした軍陣病院も含め、戦争での負傷者への対応という側面からも日本の近代の病院が生まれてきていることも重要な点である。西洋医学は、外傷や感染症など、因果関係が単一に特定しやすい急性期の医療に対して極めて劇的な効果を果たす。そうした医療をベースにして、日本の近代化の流れの中で「病院」というシステムは作られてきた。こうした歴史的背景を踏まえて考えてみると、やはり「病院」だけで人々の生命や健康に関するすべてのことをカバーすることは難しいことが分かるだろう。
養生所に必要なこと
病気の治療を中心とする「病院」では、「病気が治れば元気になる」と考えるし、健康を目指す「養生」を中心とする「養生所」では、「元気になれば病気が治る」と考える。どちらの考えが正しいとか間違っているということではなく、それは心身への考え方の違いでありアプローチの違いに過ぎないのだ。どちらか、ではなく、どちらも大切なことだ。いずれにしても、心や身体を持つ主体である自分自身が正しい知識を得ることは共通して大切なことだ。その人にとって適切な体の運用方法、その人にとって適切な心の運用方法を学ぶことは、予防医学にも通じる。
そうした医療の土台となる体や心の仕組みに関して、現在の学校教育では深く学ぶ機会がないのが現状だ。多くの人は、自分の心や体に関する勉強をほとんどしないまま大人になっていく。病気になって慌ててインターネットなどで情報を検索しても、身体や心に対する基礎となる知識が前提になければ、情報の質の違いがわからず、情報に踊らされてしまうことになる。病気の情報を探している時は、焦りや不安の真っただ中にいるため、断定的に言い切った情報や権威付けされた情報に安易に飛びついてしまう。そういうことがトラブルの元だ。養生法の基本は、身体や心に対する正しい知識だ。心身を深く理解することが、そのまま予防医学になる。
すべての知識は日進月歩であり、どんな知識も常に更新されていく宿命にある。西洋医学では手に負えない状態や、病として発症する手前で未然に防ぐ予防医療として、さまざまな伝統医療、補完代替医療、民間医療で伝えられているものには、西洋医学の限界を突破する可能性もある。ただ、同じ程度に危険性も含んでいる。可能性と危険性は常に同居していることを肝に銘じながら、未知のものに対してバランス感覚を持つことが大切だ。
例えば、医療では短期的な視点だけではなく、長期的な視点も重要である。即効性がある医療は、別の言い方をすれば現在の体の状態を急激に変化させているとも言える。だからこそ、医療においては短期的な効果だけではなく、必ず長期的な視点を持ちながら、心身への影響を考えていく必要がある。人の体は十人十色で極めて多様なものだ。他人と自分とでは、まったく逆に作用する可能性もあることを考えながら、身心のことに取り組んでいく必要がある。
「養生」を扱う「養生所」には、医療コーディネーターのような役割を果たす存在がますます重要になるだろう。基本的な医療知識と適切な治療者についての情報をもった存在だ。西洋医学はもちろんのこと、それ以外の伝統医療や補完代替医療にも広く目くばせをしながら、俯瞰的で客観的な視点で適切な医療を提案できる存在として。
体のトラブル、心のトラブルが起きてしまったとき、インターネットで情報を検索したり、突然大学病院に飛び込んでいくのではなく、まず医療コーディネーターに相談しに行く。そこではその人の症状や要望、予算などから適切と思われる医療の組み合わせのプランを考える。たとえばマインドフルネスを主としながら、アロマセラピーや断食療法を従として行い、それに西洋医学による薬物療法をプラスする……といったプランをつくって提案する。そして本当にそれが適切なのかを継続的にフォローしながら、常に現場にフィードバックしていく。介護におけるケアマネジャーのような役割だ。西洋医学も必ずメニューに入れておくことで、患者が主治医と決裂してしまうケースも防げるだろうし、極端な方向に外れてしまうことも防げるのではないだろうか。
暮らし、幸せ、養生
もちろん、そうした広い意味での「養生」を考えていくときには、人間が必要な「衣食住」にまで気を配る必要も出てくる。冒頭にも、養生とは「生」を養うことであると記したが、「生活」や暮らしも、「生」の側面でもある。着る衣服、食べるもの、住んでいる場所、こうしたものに、身心は無意識に大きな影響を受けている。生活や暮らしを支える衣食住が大切な理由は、心身の健康に密接に関係しているからだ。自分自身の心身が健康であるとき、わたしたちは幸福感を感じる。それは外の条件に依存するものではなく、自分の内部の状態のことを呼ぶ。
では、「幸福」とはなんだろうか。その前提となるのは、ほかならぬ「わたし(自分)」が感じる主観的なものであるということだ。他の誰かが「幸せ(幸福)」と感じていることと、世界にたった一人しかいない「わたし」が「幸せ」と感じるものは全く別のものだが、混同されやすい。それは心や身体に対しても同じことだろう。本来的には、他者と比べることはできない類のものだ。
「幸せ」を感じるためには、まず「わたし」自身の感覚や感受性を育むことが大前提となる。自分の人生は自分だけのオリジナルなものであり、他の誰とも比較できない。自分自身の感受性を土台として、いのちの声である「幸せ」という感性は生じてくる。それは心身の調和の状態とも関係があるだろう。一般的には、誰かの欲望がコピーされたものを「幸せ」と思いこむ(思いこまされる)ことで人生の大半を使っている場合が多く、その場合は自分自身の「幸せ」という感覚は生まれにくいものだ。
では、なぜこのようなことが起きてしまうのだろうか。医療現場で多くの人を診ていると、内なる自然である自分自身の身体や心との対話やつながりを忘れてしまっている事が大きな原因ではないかと感じることが多い。自分の身体は、生命や自然の歴史すべてがパッケージされた最高の芸術作品だ。外の世界ばかりではなく内側に意識が向かうと、そうした自分自身の生命を支えている土台を思い出すことができる。
そもそも、身体や心との関係性を取り戻すこと、自分自身の感受性を取り戻すことはそんなに難しいことなのだろうか。いや、そんなことはないはずだ。芸術や美術や音楽など、人類が生み出した文化は、感受性を育んで行く土台となるものであり、そうしたものに日々触れることで、私たちの感受性は眠りから目を覚ます。自然科学は自分の外の世界を変えることで発展してきたものだが、芸術をはじめとする文化は自分の内側の世界を、自分自身の在り方を変えることに本質がある。仏教では「幸せ」を「安心(あんじん)」と呼んだ。心が安定することこそが、幸福な状態なのだ。心と体は同じもの(心身一如)と考えられていたため、心や体が安定することが、「安心立命」につながる。
一人一人のそういった内なる対話の全体像が、養生法の核にあるものであり、医療の土台にあるものだ。すべては、自分自身から始まるのだ。それはどの世代の人であってもあてはまることだ。医療は、そうした心身のよりよいあり方をサポートするものとして生まれたはずであり、そうした原点を思い出しながら、よりよき医療へとみんなで力を合わせて協力する必要がある。現在行われている「医療」の枠を外してみて、「養生」という観点から改めて見直してみると、あらゆる領域に様々な可能性を発見できるのだ。
<参考文献>
新村拓編『日本医療史』吉川弘文館(2006年)
酒井シヅ『日本の医療史』東京書籍(1982年)