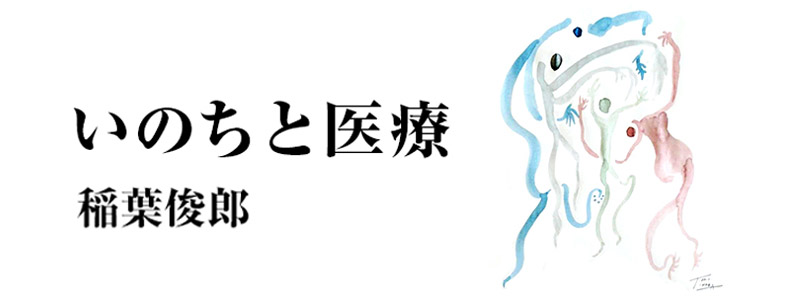身体に耳を澄ますーーことばと医療
氾濫することば
医療において、「ことば」は大切だ。
体に異変があり、病院に行く。すると、そこで「お腹がズキズキ痛いんです」「何かやる気が出ないんです」と、言葉で説明する。あるときには「仕事のストレスだと思うんですけど」「生活が不規則だからだと思うんですけど」などと、自分なりに合理的な説明を添える。それを受けた医療者は「その症状は胃炎ですね。検査をしましょう。もしくは、薬を飲んでみて様子を見ますか?」「その症状はうつ病ですね。この薬を5種類ほど必ず飲んでください。1ヶ月後にまた来てください」などと、状況を言葉で説明しながら対応する。一般的なコミュニケーションは「言葉」を媒介として行われ、医療においてもそうだ。「お腹」や「ズキズキする」という表現も言葉によるものだし、診断名である「○○病」という病名も言葉だ。よくもわるくも、言葉にあふれている。
人は、自分の体に何か異変が起きると不安になる。それまで何も問題なく動いていたと思っていた体が、思いもかけず自分の意に沿わなくなるからだ。「本当は仕事を×時までに終わらせないといけないのに……」「本当は友人との約束があったのに……」と、予定していたことの歯車が、体の状態によってかみ合わなくなってくる。うまくいかなくなる。状況によっては体を恨む人もいるし、体を罵倒してしまう人もいるかもしれない。「なんでこんな大事な時期に骨折したんだ」「なんでこんな大事な時期に風邪なんてひくんだ」と。もし、こうしたことが友人など自分以外の他者に起きた場合には、「それは体が休めって言ってるんだよ。しっかり休んだほうがいいよ」と、距離を置いて見ることができる。ただ、自分の身に降りかかってきた場合、なかなかそうして客観的に見ることができない。なぜなら、体も心も、自分自身そのものだからだ。普段意識することがなかった自分自身と出会うとき、人はそう冷静に対応できない。しかし、自分自身の問題と出会うことは、生きている以上、いずれ向きあわなければいけない問題でもある。
「からだ言葉」と「こころ言葉」
「お腹が痛い」。これは自分の「頭」の中で考えた末に出てきた言葉だ。ただ、本来は「体」が発する言葉であり表現であったものを、誰かに伝えるために「頭」の中で自分が知る限りの言葉を検索し対応させ、苦労して言葉に変換した末にたどりついたものが「お腹が痛い」という表現だと言える。つまり、体自体が何かしら表現を、言葉を持っているのだが、その表現手段は必ずしも日本語ではなく、英語でもない。だから、それぞれの人が自分の母国語へと変換せざるをえない。体が何かを伝えようとしているという意味では、元々は体の言葉、つまり「からだ言葉」なのだ。それと同じように、心の世界にも特有の言葉として「こころ言葉」がある。ただ、そんな言葉は誰一人として学校で学ぶことはない。日本語は国語として学び、海外の言葉は英語や第二外国語を学ぶ機会はあるのだが、「からだ言葉」「こころ言葉」という言葉は教科書もなく学ぶ機会自体もなく、そもそもそういう言葉があるとすら思っていない人の方が多い。
ただ、自分が臨床医として医療現場で働きながら常々感じることは、身体言語ともいうべき「からだ言葉」「こころ言葉」があると仮定しない限り、自分自身の「体や心という全体」と自分自身の「頭の世界」が、うまくコミュニケーションがとれない、ということだ。相異なる存在同士が出会い、コミュニケーションをとるためには、間をつなぐ通路が必要となる。コミュニケーションの本質は、相手のことを理解できるかどうかという「頭」での理解の以前に、コミュニケーションの「通路」が存在しているかどうかが、より大切なのだと思う。相手の考えが全く理解できなくても、分かり合えなくても、互いが行き来するための通路が存在してさえいれば、コミュニケーションは成立する。たとえ嫌いな相手であっても、たとえ相手の考えに全く共感できなくても、通路を完全に閉ざさずに、何かしらの通路を開けておくことこそが、お互いの立場や考えを尊重して、お互いが深い理解へ至るために大事なことだ。ちなみに、愛の本質は距離なのだと思う。好きか嫌いかというのは、相手との距離感の近さや遠さの問題だ。嫌いな人とは、好きになれるところまで距離をとればいいし、干渉しすぎてしまう相手には程よい距離をとって離れないといけない。そうした距離をはかることが愛の本質にはあるのだと思う。相手との距離をとること、それこそがコミュニケーションであり、コミュニケーションのために、相手と自分との通路があり、その通路のひとつとして共有する言葉もあるのだと思う。
症状の所在
最初に「お腹がズキズキ痛いんです。」という例を出した。このことを今一度丁寧に考えてみよう。そもそも、「お腹」とはどこだろう。これは、当事者が「お腹」と考えている場所があるわけだが、「お腹」と言っても実は広大な領域で、それぞれがイメージしている場所はまったく異なっていることを、医療現場でコミュニケーションをしているときに日々感じている。「お腹」を指す場所としては、基本的にはお臍の周辺を指すことが多い。ではお腹の上下はどこまでだろうか、左右はどこまでだろうか。そして、お腹は表面だけではなくて中に広がる内臓の世界もある。お臍の奥には皮下脂肪や筋肉がある。さらに奥には、腸間膜という腸を覆う膜がある。腸間膜の奥には、小腸や盲腸や大腸などの腸管の内臓がある。小腸の頭側には十二指腸や胃も連続しているし、大腸の最後尾は肛門まで連続している。皮膚の下には腸管だけではなく体の水分バランスを黙々と調整している腎臓もある。腎臓は尿管という出口があり、それは膀胱という尿を貯めるタンクへとつながり、そこから外性器へとつながる。腸管や腎臓だけではなく、大動脈や大静脈などの血液が通るための大きな血管もあるし、リンパ管では免疫機能を担当するリンパ液が運ばれている。すべての体には神経が張り巡らされ、体に異変が起きようと起きまいと、体は神経系のシステムを総動員させて体の活動を常にモニターしながら情報のやりとりが行われている。すべての臓器、組織、細胞には、動脈や静脈や毛細血管など、無数の血管が張り巡らされている。
「お腹」という何気ない言葉の中には、これだけの人体の奥深さと多様さが広がっている。現代の西洋医学では「臓器別」に分野が分かれる形をとっているので、「お腹が痛い」と思ったときに、「これは胃の症状だろう」と思われると「消化器内科」を、「これは尿管にある結石の症状だろう」と思われると「泌尿器科」を、「これは血管に異常があるのだろう」と思われると「血管外科」を、「これは生理と関係があるのだろう」と思われると「婦人科」を、「これは皮膚や皮下に関係があるのだろう」と思われると「皮膚科」や「形成外科」を、受診するようにすすめられる。それぞれの科で「この臓器には異常ありませんね。ほかの科を受診してください」と言われてしまうと、どこに行けばいいのか、そもそも原因を知りたくて来ているのに何も分からずに途方に暮れてしまう。
そうしたことからもわかる通り、「お腹」が訴えている「何か」は、そう簡単に一つの原因が特定できないことも多いものだ。一つの原因だけではなくて二つ以上のものが原因である場合もあれば、別の場所の異常がすこしずつ形を変えて、結果的に「お腹」という場所に一番大きな症状が現われてきていることもある。それは、「お腹」に限らず人体のあらゆる部分においても同じことが言える。
西洋医学においては、基本的に「因果論」で体の現象を捉えていく。「原因」があるからこそ「結果」が起きていると考えるので、「原因」さえ解決すれば「結果」として起きている問題は解決するのだと考える。そういう考え方の中で、「原因」としての「病名」が数多く命名されてきた。もちろん、一つの原因が判明した場合には、極めて迅速にかつ確実に対処できるだろう。外傷や感染症などが、「因果論」で説明しやすい最たるものだ。身心に起きている原因を突き止め、「病名」として分類し、「病気」へと至った因果の鎖を断ち切るように治療を行う。こうした西洋医学のアプローチが有効である場合も多いことは、医療従事者であればもちろんよく知っている。
ただ、現場で数多くの症例を見ていると、たった一つの原因ですべてを説明できること自体が、かなり稀なケースであることもよく知っている。なぜなら、人には誰もが生きてきただけの時間の蓄積や重みがある。人には生きてきただけの歴史という厚みがある。そうした生きる営みを重ねていく中で、体は不具合を起こさざるを得ない様々なことが起きてしまうのは当然とも言える。食生活、ストレス(と簡単に述べたが、複雑に起きる心の反応はほとんどが未知だ)、住環境、生活習慣、体質や気質……あらゆる要素がひとりひとり異なる。たとえば、川が氾濫を起こした場合を考えてみよう。大雨や台風が川の氾濫を起こしたと考えることもできるが、もっとひいた視点で全体像を見てみると、川が氾濫しやすい状況が様々な状況の中で少しずつ準備されていて、大雨や台風はその最後の一押しを押したきっかけに過ぎない、と考えることもできる。川と一言で言っても、すべての風土や地形や大きさなど実に多様である。そう考えると、川が氾濫してから災害に対応するよりも、災害が起きないように事前に行う対応策や予防策の方が、より重要であることが分かるだろう。
メッセージを読み取る
では、そうした「因果論」だけで体や心に起きる現象を考えることに限界があるとしたら、他にどのような選択肢があるのだろうか。自分は、心身に起きる現象に対して、「因果論」で原因も考えることは当然行っているが、同時に「目的論」としても重ねて考えあわせるようにしている。「因果論」では視線が過去の方に向かっていくが、「目的論」では視線を未来の方に向けていく。「目的論」とは、「いまこういう状況が起きていることは、どういう目的があるのだろうか。何を実現しようとしてこうした状況を起こしているのだろうか」と考え、「では、どうすればいいだろう」と、前向きに捉えてみる考え方のことだ。因果論で原因を探していると、「そもそもあの時こうすればよかった」「もう過去には戻れないからどうしようもない」というように、どうしても考え自体が後ろ向きになってしまう。アドラー心理学においても、心の働きを「目的論」の結果として捉えてみることを提案している。
たとえば、「引きこもり」の状態である人の対応を考えてみる。「うつ病だから外に出ることができない」と考えるのが従来の因果論であるとすれば、「外に出ることができないのは、どういう目的を実現するためだろうか。何を実現するために、外に出ないという状況を創りだしているのだろうか」と、考えてみる。現在の体に起きている状態(この場合は「体が外に向かって動かない」)を尊重し、そうした心身の行動には、自分が気づいていないだけで、実は合理的で「隠れた意図」があると考えてみるのだ。
こうした「目的論」で体に起きる症状や現象を考えてみることは、そのまま冒頭で挙げた「言葉」の問題にもつながる。つまり、「体」をあたかも人として、擬人化して考えてみる。「体」全体だけではなく、体を構成するそれぞれの部位も、一つの人格を持った人間だと考えてみる。すると、今まで耳を傾けていなかった「からだ言葉」「こころ言葉」に対して「何を伝えようとしているのだろうか」と、耳を澄ませて聞き取ろうとする態度が育まれていく。どの言語もそうだが、学習するにはある程度は慣れが必要になるし、聞き取ろうとする努力をしない限り、なかなか身につかないものだ。つまり、自分自身の態度こそが重要なのだ。そして、体は体特有の、心は心特有の表現があるので、自分自身の「腑に落ちる」ように、身体感覚で言葉の感受性をはぐくんでいく。
たとえば、最初の「お腹がズキズキ痛い」という状況を考えてみる。「お腹」の「痛み」の原因を探っていくのが「因果論」であるとすると、すこし立ち止まって「お腹」の立場になって「お腹が痛むことで体は何をしようとしているのだろうか」と考えてみるのが「目的論」である。自分の「お腹」の立場になって考えてみると、みなさんはどういうことを感じられるだろうか。まず、あまり活発に動かずに安静にして休んでほしい、という風に思えてくる。すこし活動を止めて立ち止まると、普段意識していなかった「お腹」という場所が、自分のからだ全体の中でどうした役割を持って働いている場所なのかと、自分なりに今一度考え直してみるいいきっかけにもなる。「お腹」が痛むという強い信号を送ることで、すべての活動を一度止めてでも注意を向けてほしいという非常事態を告げていると受け取ることができる。「お腹」の痛みは、「お腹」が普段の控え目な立場を止めてでも活発に働くことで、からだ全体の危機を回避するために事前に手を打っているのではないかと考えることもできる。「お腹」も、体全体を、命全体を安全に働かせるために、全体の中でひとつの役割として部分を担っている場所だ。そもそも、体や命という、働く場自体がなくなってしまうとお腹も生命活動が行えなくなる。体のそれぞれの場所は常に全体と部分との関係をモニターしながらある合理性をもって働いているので、危機的な状況では何かしらの手段で緊急事態であることを知らせる必要がある。日本語や英語が話せれば、言語で表現すればいいのかもしれないが、そうもいかない。すべての細胞や臓器が仮に「日本語」を話し出したらどうだろう。情報量が多すぎて頭は逆に混乱してしまうのではないだろうか。だからこそ、体は無意識の世界で膨大な仕事を行いながら、非常事態が訪れた時だけ意識の上に浮上してきて、身体症状としての「からだ言葉」を発することで大切な「何か」を伝えようとするのだ。
つまり、「からだ言葉」や「こころ言葉」から、私たちが意味を発見しないと、それは「言葉」にならない。ノイズなのではなく、シグナル(信号)なのだと考えてみないといけない(そもそも、シグナルかノイズか(S/N)という判断は人為的なものなのだが)。たとえば、異国へ旅をしたと考えてみよう。ジャングルの奥地で、英語も日本語もまったく通用しない人と遭遇したとき、あなたはどうするだろう。命がけで、必死になんとか意思疎通をしようと試みるのではないだろうか。「頭」を介した言語が通じないと分かったら、ボディ・ランゲージ(body language)と言われる、体そのものを言葉として全身で表現して思いを伝えようとするはずだ。body languageも、「からだ」自体を「言葉」として、全身で表現している。それは人間だけではなく、動物であっても、昆虫であっても、植物であっても、自然現象であっても、同じことだ。その間にコミュニケーションの通路が開いてさえいれば、お互いが「何を伝えようとしているのだろうか」と、表現された形を「言葉」として受け取りながら、暗号を解読するようにお互いが意味を読み取ろうとするはずだ。
芸術家は、「美しい自然」を描いているというよりも、自然の中から美を発見して描いているのだと思う。セザンヌが描いた机の上に置かれたリンゴ、ゴッホが描いたひまわり、そうしたものに私たちが感動するのは、リンゴやひまわりに隠された美を発見し、それを表現することができたからだろう。それは、リンゴやひまわりの秘された言葉を読み取る行為とも言える。自分のからだやこころを含め、そこに隠された意図や意味を読み取ろうとする行為は、芸術においてなされてきた行為でもあるのだと思う。
オノマトペは「からだ言葉」?
改めて、「お腹がズキズキ痛い」というところに戻ってみよう。そもそも、「ズキズキ」とはなんだろうか。
「ズキズキ」は、「オノマトペ」と言われる特殊な言葉である。オノマトペには、「擬音語」(発する音や声を真似て表現した言葉(「ドカン」「サラサラ」など)と、「擬態語」(状態や心情など、元々音がしないものを音で表現した言葉(「ズキズキ」「ムカムカ」「ワクワク」など))とがある。日本語では「擬音語」と「擬態語」を合わせて「擬声語」と呼ぶこともあり、これがオノマトペにあたる。わたしたちはほぼ無意識に使っているが、わたしたちの日常の言葉の中に膨大なオノマトペ(「擬音語」や「擬態語」)が含まれている。特に日本語は動詞が少ないために動詞を補うオノマトペの種類が多いと言われていて、オノマトペ抜きに表現することは極めて難しい。日本では「ムカムカ」「ワクワク」「イライラ」など、同じ音を繰り返す「畳語(じょうご)」のオノマトペが多いのも特徴的だ。自分も、あまり文章で「ベラベラ」書きすぎると、伝えたいことが「フワフワ」することがあるし、読み手を「イライラ」させることもあるかもしれない。ただ、本当は読み手に「ニコニコ」しながら読んでほしいと思って「ツラツラ」と書いている。こうしたことを書きながらも「ドキドキ」「ハラハラ」している自分もいるが、「ワクワク」している自分もいる。
こうした「オノマトペ」による表現は、言葉を育んできたそれぞれの文化や音感やリズムなどがギュッギュッと凝縮されている。そして、音を聞いただけで、言葉を読んだだけで何か身体感覚が伴ってこないだろうか。例えば、「ワクワク」「ドキドキ」という言葉を聞くと、自分の体や心そのものにダイレクトに働きかけてくるような気がしないだろうか。まさに、「オノマトペ」は「からだ言葉」「こころ言葉」でもあるのだ。言葉が、人から人へと伝わるには通路が必要だ。音が響くだけで相手に伝わらなければ、言葉にならない。わたしたちの言葉の通路になるのは体や心そのものであり、体や心に雨水が染み込むように言葉がグイグイと染み渡って行きさえすれば、身体という通路を介してズンズンと人へと伝わっていく。体や心に染み渡る音感や語感を探りながら伝わってきたのが、「オノマトペ」として表現される言葉なのだ。
たとえば、平安時代末期に成立した説話集である『今昔物語集』(全31巻)にも、「キラキラ」「コソコソ」など、現代にも通じるオノマトペが多数登場する。ただ、赤ちゃんの泣き声が「イガイガ」、嘔吐するときの様子が「エブエブ」と表現されていたりして、現在ではほとんど使われていないオノマトペも登場する(もちろん、誰かが今でも使っているかもしれない)。それは、自然環境や身体感覚が当時と変わったからなのかもしれないが、はじめて聞いた語感でも頭の中よりは身体そのものに「イガイガ」や「エブエブ」が働きかけてくるような気がするのは不思議なものだ。冒頭に挙げた「お腹がズキズキ痛い」という表現も、「ズキズキ」「チクチク」「ドンドン」「シクシク」「キリキリ」「ジンジン」「ビリビリ」「ガンガン」……などで、微妙に身体感覚が変化することもお分かりだろう。「細い針で何度も刺すような痛み」と言うこともできるが、「チクチク痛む」と言えば十分に相手に伝わる。オノマトペの表現は、まさに体が発している言葉をそのまま表現しようと切実な状態から生まれてきた言葉だろう。宮沢賢治の詩には「オノマトペ」が多用されているとよく言われるが、それは賢治自身が自分の体や心、そして命、それは自分自身の命だけではなく、あらゆる存在物の命、そうしたものと交流し交歓するための通路として必要としたものだったのだろう。
わたしたちは体や心を与えられているが、なかなかそうした存在を思い出すことはない。不調になったときはじめて、いのちの働きを感じるのは皮肉なことでもある。それは単なるコミュニケーション不足なのだ。わたしたちの根底を支えている存在とよりよい関係性を保っていくためにも、「言葉」への感受性を育みながら、自分なりの通路を保ち続けることが大切なことだ。
体や心に起こる問題を、治療の場として捉えるだけではなく、教育の場として捉えてみる。体や心の言葉を読みとり、その隠された働きや意味を学ぶ場として。健康な状態のときでも、バランスが崩れた時でも、体や心のことを学ぶことはそのまま予防医学となるし、自分自身の体や心のことを学ぶこと自体が自己治療にもつながる。そこには、むしろ仲間としての関係性こそがあり、上下などのヒエラルキーは必要としない。体や心、命全体の中で決して頭(脳)が偉いわけではない。哲学者カントが「われわれは哲学を学ぶことはできない。哲学することを学べるだけである。」(『純粋理性批判』「純粋理性の建築術」より)と述べているが、このことは人間の体や心、生命についても同じことが言える。「われわれは「いのち」そのものを学ぶことはできない。「いのち」が働いていることを学べるだけである」