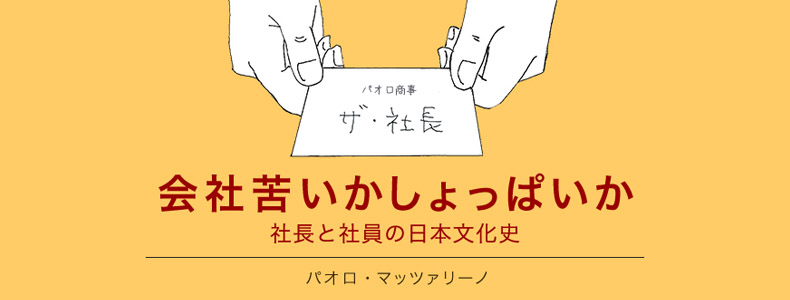秘密の秘書ちゃん
女秘書を手籠めにした老重役
秘書といえば愛人。そんな淫靡なイメージがいつごろ広まったのかは、はっきりしません。戦前はまだ女性秘書という職種が一般的ではなかったので、おそらくは、女性の社会進出が一気に進んだ戦後のことと思われます。
ただ、戦前の日本でも、ごく少数ながらそれらしき例はあったようで。
大正一五年の読売新聞が報じた、女秘書を手籠めにし、生き恥さらす老重役という記事。
丸の内の大会社に勤める六〇歳の重役が、二二歳の秘書を手籠めにして愛人同然に時計や指輪を買い与えていたことがバレ、警察に呼び出されて大目玉を食ったという内容で、いまならテレビのワイドショーの守備範囲に属するネタです。でも戦前の新聞には、およそどうでもいい庶民のゴシップ記事が、けっこう載ってるんです。どっかのジジイとババアが駆け落ちした、とかね。そんな記事を好きこのんで読んでる私も私ですけども。
さて、その秘書を手籠めにした記事なんですが、よく読みますと、これが発覚したのは女性の母親が事情を知って警察に相談に行ったからなんです。女性秘書本人が被害を訴えたのではありません。
二二歳の大人の女性で、一流企業に勤めるくらいなら、それなりに世間ずれしてるでしょ。仮にきっかけは手籠めにされたことだったとしても、高価な装飾品をくれるおじさまとの割り切った関係を続けていたのではないかと。
それに戦前は、会社社長や重役が女を囲うのはあたりまえって風潮です。もしその重役が本当に彼女を気に入ったなら、秘書をやめさせて妾にすることもできたはずです。なのにそうしなかったということは、やっぱり両人とも合意の上で、ヒミツの関係を楽しんでいたんじゃないかな、なんてのは深読みのしすぎでしょうか。
愛人を秘書に偽装した国会議員たち
戦後、よのなかの風向きが変わります。おエラいさんとはいえ、おおっぴらに愛人の存在を誇示することがはばかられるようになりました。そこで、愛人を秘書だと偽装する手口が増えたのではないでしょうか。
いち早くそれを実践していたのが、こともあろうに国会議員だったって話を前回の最後にちょろっとしました。
これがなかなか強烈な内容で、スルーするのは惜しいので、会社というテーマからは脱線しますけど詳しくご紹介しておきます。
一九五一(昭和二六)年の一月から、国会議員の歳費と秘書の月給が倍近くに増額されることが決まると(ていうか議員が自分たちで決議したお手盛りだけど)、愛人を秘書にする議員が続出、どう見ても秘書とは思えないケバい化粧や派手な服装の女が、国会内をやたらとうろちょろするようになった、とマスコミが報じました。
読売新聞や『サンデー毎日』の記者は、代議士や事務局員に取材を重ね、議員たちの呆れた行状や手口をあきらかにしています。
娘として事務局に登録した秘書を伴い、出張旅行に出掛けた某議員。車中や旅館での二人の振る舞いに周囲の者は、「これが親子か」と唖然としたのだとか。
これを参考にしたか、はたまた民間の社長にも同様のことをやる人がいたのか、『三等重役』には、桑原社長が取引先の社長と一緒に九州出張旅行に出掛けるエピソードがあります。桑原は本当の秘書(男)を連れて駅で待っていると、相手の社長は秘書とは名ばかりの愛人を同伴して現れます。目的地で汽車を降りると、奥さんが飛行機で現地に先回りしていたもんだからあわてた社長、とっさに愛人を桑原の妻だと紹介したところから、口裏合わせのドタバタがはじまります。
小説だったら笑えますけど、現実の議員のドタバタはノンフィクションですからね。歳費アップに先駆けて、一九五〇年十一月には衆院第二議員会館が完成、これによって議員はひとり一室ずつ事務所兼勉強室を持てるようになりました。
が、自由に使える個室が与えられたのをこれさいわいと、こちらにも愛人が盛んに出入りして、なんの勉強室なんだか。あまりの風紀の乱れっぷりに憤慨した議員からは、これじゃあ国費で怪しげな宿を作ったようなもんだ、と嘆く声すら上がります。
書類上では妻や娘を秘書として登録していても、実際に国会に出入りするのは愛人という例も多かったとか。当時、国会内に入るのに必要だった身分証は粗末な作りで、容易に写真だけをあとから別人のものと張り替えられました。愛人の写真に張り替えられた妻名義の身分証を使い、堂々と国会に出入りする愛人たち。いまでは考えられない、ゆるゆるふわふわのセキュリティ。
しかしここまでやりたい放題されると、マジメな議員たちがついに怒り心頭、有志の代議士が「議員と女秘書に関する粛正決議案」を衆院に提出する動きを見せるのです。
こんな前代未聞の議案が出されて議事録に残ったら、さすがに不名誉この上ない。各党の代表が協議の上、自粛をうながすことを約束して議案提出はなんとか見送られました。
秘書はもともと男性だった
いまでこそ企業で働く社長秘書といえば、もっぱら女性のイメージですが、もともと社長秘書はほとんどが男性でした。映画の社長シリーズでも、社長秘書役は小林桂樹が演じてます。
男性の社長秘書は秘書課長の肩書きを与えられ、部下の秘書課員が事務仕事を担当するしくみが一般的でした。
なぜ社長秘書が女性だと都合が悪かったかというと、社長の接待や出張には、秘書がつねに同行することを求められていたからです。むかしは男社会ですから、接待の宴会の席ではきれいどころの芸者を呼びますし、下品な宴会芸が披露されることもありました。もっとストレートに、性的サービスを提供するお店での接待なんてのもあったでしょうから、女性秘書では勤まらないわけです。
出張となるとまたべつの問題が。いまみたいに日本全国どこでも飛行機で日帰りできる時代じゃありません。遠方への出張は長距離列車を利用した泊まりがけが普通です。そんな旅行に社長と女性秘書が同行となれば、仕事とはいえ、社長夫人は心おだやかでいられましょうか。
一九五六(昭和三一)年の『実業の日本』には、「秘書課業のうらおもて」なる記事が載ってます。名前を聞けばだれもが知ってる一流企業に勤務する現役の男性秘書による座談会記事。
そもそも秘書というのは、「秘密の文書を扱う人」の意味ですから、仕事内容をべらべらしゃべってはいけません。当然、この座談でも会社の不利益になるようなことはしゃべってませんけど、それでも実際の具体的な秘書業務がどんなものだったのかが垣間見える貴重な資料です。
彼らのような社長秘書のおもな仕事は、社長のスケジュール管理を担当するのはもちろんですが、「人と会うこと」に多くの時間を費やしていたようです。
一流企業の社長ともなると、面会を希望する者が毎日ひっきりなしに訪れます。全員と会うのは不可能だから、秘書が会って選別作業をします。
事業をやるので援助をお願いしたい、なんていってくるけど、実態はゆすりたかりみたいなゴロツキも多いんです。なかには記者を装って来るヤツもいます。電話で「ニッケイの○○」と名乗り取材を申し込んできたら、日本経済新聞の記者だと思いますよね。でも実際に会って名刺を見ると、まぎらわしい名前の全然ちがう新聞社だったりする。その手の有象無象は、総務部の専門担当者にまわします。そっちはそっちで大変そう。
社長が出す手紙と、新聞雑誌から社長に依頼された原稿を代筆するのも秘書の役目。大企業の社長が自分でコラムのような原稿を書くことはまず、ないと断言しています。
座談会の司会者は、社長の出張旅行に随行するのは気疲れしてさぞかし大変じゃないかと話を振るのですが、意外なことに秘書たちは、かえって楽だというんです。たしかに最初は緊張するけど慣れれば普段の業務よりもラクだ。なにしろ出張旅行中は来客もないし、電話もかかってこないから解放された気分になれるのだ、と。
これは携帯電話がなかった時代ならではですね。携帯電話によって人類はこれまでにない便利さを手に入れましたが、それと引き替えに、自由を手放したことが、はたして賢い選択だったのでしょうか。
秘書の適正に関しても意外なことをいってます。一流企業の社長秘書といったら、経営者の懐刀、切れ者軍師と思われがちですが、みなさん謙遜でなく、それを否定します。
そういう切れ者は社長のそばに置くと、かえって寝首をかかれる危険があるのかもしれません。どちらかというと、野心のなさそうな、平凡な人間に白羽の矢が立つことが多いのだそうで。座談会出席者のみなさんも一様に、秘書を命ずる辞令を受け取ったときは動揺、困惑したといいます。宴会芸も苦手で、気のきいたお世辞もいえない自分には、社長秘書など向いてるはずがない、と。
ただひとつ、彼らは共通点を見出します。失敗や叱られたことを引きずらず、わりとすぐに忘れる能力を、みなさんお持ちのようです。
「考えると命が縮まりますね」
「クヨクヨしていたら勤まりませんね」
「覚えていたら長生きしませんよ」
どうやらこれが、もっとも秘書に必要とされる能力みたいです。
女性秘書ブームの立役者たち
このように、社長や重役付きの秘書は、もともと男性の仕事でした。一九五〇年代には、女性はようやく使いものになったころに結婚して辞めてしまうから社長秘書にはしない、という声まであったほど。
その職種にいつごろ女性が進出してきたのでしょうか。いろいろと資料を漁っていくと、一九五〇年代後半に女性秘書の社会進出に関する記事やレポートが雑誌などにちらほら載りはじめ、一九五九年からかなり増えていることがわかりました。
もっとも影響力があったのは、アメリカです。アメリカではすでにだいぶ前から女性秘書が職業として世間に認知されてましたので、日本ではまず外資系企業が、英語に堪能な日本人女性社員を重役の秘書として使いはじめたのでした。
その仕事ぶりが紹介されるにつれ、若い女性のあいだであこがれの職業になっていきました。
東京お茶の水地区で戦前から女性の英語教育・職業教育に力を入れていた東京YWCA(戦前は駿河台女学院)も女性秘書の増加に大きな役割を果たしました。戦後、駐留軍からの要請で女性秘書教育を受け持ったのをきっかけに、一九五一(昭和二六)年から秘書養成科を設けて、実践的な職業訓練教育をやっていた老舗です。
当初は毎年一五人くらいしかいなかった学生が、五四年からは九〇人、五九年には一五〇人にも増える盛況ぶり。『週刊東京』『週刊サンケイ』の記事によれば、定員の三~四倍の応募者が殺到するため、試験で入学者を選別していました。
なにせ就職率一〇〇パーセントを誇っていたのですから、その人気もわかります。いったん大学を出て就職したけれど、待遇や仕事内容が不満でくすぶってた人が、こちらで勉強し直してキャリアアップをはかる例もかなり多かったのです。
あと、複数の記事で若い女性たちが「テレビのスージーみたいになりたいわ」なんていってるのも気になります。
このスージーとやらが何者かというと、日本でもKRテレビ(現・TBS)で一九五八年から放送されたアメリカ製コメディドラマ『女秘書スージー』のことらしいけど、資料がほとんどないのでよくわかりません。この番組を懐かしむファンの声がほぼ皆無ということは、たいした出来ではなかったのでしょう。
それでも、ブラウン管に映った女性秘書の姿にあこがれて、女性秘書養成校を受験するミーハー女子を急増させるのに一役買ったのですから、むかしからテレビの力はあなどれません。
さらにもうひとかた、社長秘書ではなく国会議員の秘書ですが、辻トシ子さんの活躍にも無視できない影響力があったはず。
辻さんは、益谷秀次議員の秘書として活躍したかたで、一九五九年に益谷議員が副総理になると、辻さんが初の女性秘書官になったことで一躍脚光を浴び、新聞雑誌にインタビュー記事がいくつも載りました。
当時、男女すべての国会議員秘書のなかでもっとも有能といわれてたほどの実力者で、五一年ごろに広まった「議員の秘書イコール愛人」という悪評を覆し、女性秘書の評価を高めた功労者といえるかもしれません。
BGとビジネスワイフ
五〇年代末ごろの雑誌記事では、女性秘書を「ビジネスワイフ」と紹介している例がかなり多いんです。同じころ、一般の女性事務職社員をビジネスガールの略称であるBGと呼ぶようになったので、そこからの連想だったのでしょう。
そりゃたしかに身のまわりの世話もするからワイフっぽいかもしれないけれど、本人たちが自分の職業を聞かれて、ビジネスワイフですなんて絶対いうわけがないんですから、あからさまな蔑称ですよね。
当時のマスコミもまた男社会だったので、蔑称を使ってるという意識すら希薄な感じが伝わってきます。『婦人公論』でさえ、防衛庁の空将付きの女性秘書が衣類の手入れや送り迎えなどをする仕事ぶりを紹介した記事で、「ビジネス・ワイフと云う言葉の実感の来る内容である」なんて平然と書いてるくらいですから。
女性秘書たちへの取材記事では、彼女たちは口々に、女性秘書というだけで、周囲からヘンな色目で見られると不満を漏らします。実際の秘書の仕事は華々しいものではなく、地味な作業の連続なのに、玉の輿を狙ってるだとか、お高くとまってる女とか、そんな偏見ばかりが聞こえてくると。
新聞は朝日も読売も、記事見出しにビジネスワイフという言葉は一度も使ってません。ちなみにですが、ビジネスガールという言葉も新聞の記事見出しにはありません。一九五八年ごろから六〇年代にかけてやたらと使われたのは、BGという略称だけです。
ところがBGが英語では売春婦を連想させるという説(これにはちょっと誤解があるのですが)が取りざたされたことで、六三年ごろから、BGの使用をやめるマスコミが増えました。そして六四年ごろから新語の「OL」がじょじょに浸透していき、六〇年代末には、ほぼOLで統一されました。
さて、秘書学校などでの勉強や訓練を経て、ようやく念願の秘書の道へと行きたいところですが、元社員などの内部証言によると、企業によっては秘書の採用や社内からの異動に関して、かなりキビシい――というより奇妙な条件を設けている例もありました。
たとえば、某電気メーカーでは、会社内に知人友人がいないこと、を秘書の第一条件にあげていたのだとか。
まあ、開発中の新製品の情報が外部に漏れたらえらいことですから、秘密を握る社長や重役に近いところにいる秘書がスパイにならぬよう警戒するのはわかります。でも社員食堂も使わせない、社内に友人ができた場合は退社してもらうなんて縛りまであるようだと、会社で働くのが全然楽しくなさそうです。
またべつの企業では、家族に税務署員・裁判官・警察関係者がいないこと、なんて条件があったそうですが、これはもはや、その会社がほぼ確実に違法なことをやってるって証拠ですよね。
単行本になりました
パオロ・マッツァリーノ『会社苦いかしょっぱいか:社長と社員の日本文化史』