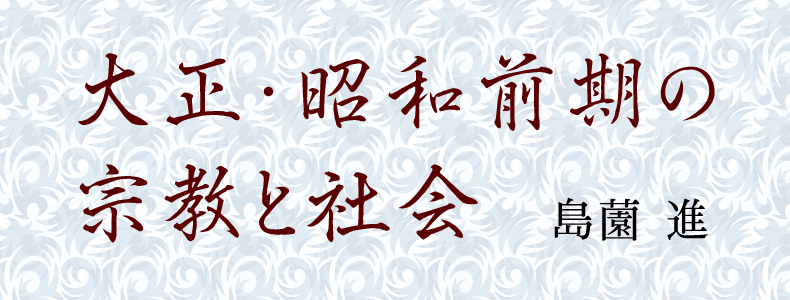第3回 明治天皇の大喪と乃木希典の殉死
明治天皇の大喪
明治天皇が「明治大帝」と称され、やがて明治神宮が創建されて、帝都の中心的な神社となり全国民の崇敬対象へと高められていく過程は、日本の宗教史の大きな転換点の一つである。この転換点の里程の中でも要となる日付が、1912年9月13日、すなわち、明治天皇の大喪の日である。
7月31日から8月13日にかけて、明治天皇はあたかも生き続けているかのように遇された。櫬殿と仮に名付けられた宮城内で女官たちが1日3度、供御と呼ばれる食事を天皇におそなえした。そして、8月13日から大喪の日までは、天皇の遺体は殯宮とよばれた正殿の間に安置された。
9月13日、現在の神宮外苑にあった青山の帝国陸軍練兵場で大喪の礼が行われ、翌9月14日に明治天皇は伏見桃山陵に埋葬された。その過程は以下のとおりだった。
13日の朝、権殿と呼ばれることになった宮中桐の間に明治天皇の御霊代が奉安される。1年後、宮中三殿の皇霊殿に祀られるまで天皇の聖霊が仮に宿る場である。夜8時に公の儀式が始まる。葬送の鹵簿が宮城を出て二重橋を渡り、馬場先門から青山練兵場の葬場殿へと向かった。葬送の行列には1万人を超える儀仗兵、皇族、文武高官が加わり、沿道には2万4千人近くもの兵士が並んだ。
葬場殿は鳥居の向こうに建てられた木製の仮の神殿で、そこで神道形式の葬儀が執り行われた。祭官長・鷹司煕通の祭詞と玉串奉奠に始まる葬儀は、長く仏教で葬られてきた天皇の葬儀としてはまったく新しいものであった。葬儀が終わると、天皇の棺は霊柩列車に乗って京都へと運ばれた。桃山駅仮停車場に到着した天皇の柩は葱華輦という乗り物に移され、慣例のとおり比叡山麓の八瀬村の八瀬童子52名に担がれ、天皇陵へと運ばれていった。
乃木殉死の衝撃
大喪はそれ自身、壮大な全国家的行事だったが、この日を宗教史上画期となる日とした主人公は、葬られた明治天皇だけではなかった。学習院の院長だった乃木希典とその妻、静子がその日、殉死をとげた。
この乃木の殉死は、大帝とよばれるようになる明治天皇の「偉大さ」をいやが上にも強烈に印象づけることになった。山室建徳『軍神――近代日本が生んだ「英雄」たちの軌跡』(中公新書、2007年)には、乃木殉死後のマスコミの論調が詳しく紹介されている。当初、否定的な論調、すなわち乃木夫妻の殉死が納得できるものではないという主旨の論が、一定の力をもつかに見えた。
たとえば、9月14日の『東京朝日新聞』は、乃木殉死に「武士道」の鼓吹に通じるものを見て、それに警戒感を示している。「欧米新文明の潮流は一時本邦の旧道徳旧信仰を破壊したりしが、日清戦争日露戦役によりて自国の価値を自覚したりし国民は、旧文明の破壊に対する反動的大勢と相倚りて、数年以来こゝに武士道鼓吹の声四方に反響し、武士道を以て殆ど日本道徳の根本となし新道徳は武士道によりて復古的に建設せらるべしと説くものすらあるに至りた」る状況だ。これは国民のナショナリズムへの目ざめだが、武士道は「一種の軍隊教育」に過ぎず、「之を軍隊以外一般の社会に絶対に強ひんとするは到底不可能事」であるという。武士道が軍人たちを結束させる道徳として唱えられるのは意味があるとしても、日本社会全体がこれを規範とするようなことは無理があり好ましくないとして、乃木の殉死が礼賛されることに警戒感を示した論説である。
9月15日の『時事新報』の社説も同様だが、そこでは殉死の動機を西南戦争のときの軍旗の喪失よりも、日露戦争における旅順攻略の多大な犠牲の方に求めている。旅順攻略は予想以上に難航し、多くの戦死者を出した。第三軍の長である乃木の采配に問題があるとの疑いがかけられた。乃木自身も多くの戦死者や遺族に対して申し訳なかったとの思いをもち続けた。
他方、数か月にわたる作戦中に、乃木の長男、勝典と次男、保典が戦死した。乃木の子供はこの2人だけだったから、乃木夫妻は家を嗣ぐ子供を失った。そして、そのこと故に人々の多大な同情が乃木に寄せられた。人々の共感という点では、軍事的な英雄としての翳りを長男次男の戦死が補ったようなかっこうになっていた。
日露戦争における乃木の悲劇
『時事新報』社説はこう述べている。
大将は公人として其名誉赫々たりしと雖も、私人としての生涯は極めて悲惨なるものあり(中略)我輩は右の事情より、大将の死に就き批評を試みるは私情に於て忍びざる所なりと雖も、世間或は理と情とを混同し、乃木大将は流石に忠臣なり先帝に殉死して其終りを全うしたりなぞ其死を称賛するものあらんか、大なる心得違ひと云はざるを得ず。
乃木の殉死は私的な事情を動機とするものであるのに、それを公的な責任を取って行われた高潔な行為であるかのように受け取るのは適切ではないと、この社説は論じる。
乃木大将の生涯に於て若しも自殺の場合ありとせば、日露戦役後凱旋の時に在りしならん。即ち、旅順の攻略は大将の司令の下に行はれて遂に其功を奏したりと雖も、之が為めに意外の戦死者を出して我兵力を損したること夥大なりしは司令官の責任なれば、役終りて凱旋の暁に、作戦その当を得ず陛下の軍隊に損害を及ぼし国民の子弟を殺したるは上下に対し相済まざる次第なりとて、責を引いて自殺したりとせんか、其事の是非は論外とし、忠誠一偏の点より云へばむしろ其死所を得たりしものならん。
日露戦後の復命書奏上
なお、日露戦争後、乃木は天皇に戦果を報告し、多くの兵士を失ったことを詫び、割腹したいと申し出た。明治天皇への「復命書」奏上の場面について、松下芳男『乃木希典』(吉川弘文館、1960年)はこう述べている。
右の旅順城攻略に多大の犠牲を供したという字句にいたるや、熱涙双頬にながれいくたびか言葉たえて、痛恨の状きわまるところをしらなかった。そして復命を終ってから「ひとえにこれ微臣が不敏の罪、仰ぎ願わくは臣に死を賜へ、割腹して罪を謝し奉りたい」と言上して平伏した。天皇はしばらく言葉もなかったが、やがて悄然として退出しようとする乃木を呼びとめられて、「今は死ぬべきときではない。卿もし死を願うならば、われの世を去りてのちにせよ」といわれたという。この日第三軍と乃木軍司令官に、「卿の勲績と将卒の忠勇を嘉尚す」という意味の勅語をたまわった。(187―188ページ)
『時事新報』の社説の立場からすれば、そうであるならなおさら、乃木は天皇との私的な関係において忠誠を貫いたが、国家的な役割を担う軍人としては死ぬべき時期を誤ったということになるだろう。
以上、紹介してきた批判論は、近代的な社会倫理という基準から見て、乃木の殉死は古い価値観にとらわれたもので、近代社会にはふさわしくないと見るものだ。
神人としての乃木の殉死
他方、乃木の殉死を褒め称える論調もにぎわった。少し後になるが、11月1日刊行の奥付をもつ宗教学者加藤玄智の『神人乃木将軍』では、進化論的な比較宗教論の理論的枠組みにそって、その崇高な意義が組織的に述べられている。(66―67ページ)
斯様に観察して来ますといふと、乃木将軍の死は、独り現代人心を其の危機に救ふたばかりではない、そは時間を超越して無限恒久である、現代人心が漸々無信仰に陥り、無宗教となり、世の中には神も仏もなく唯々功利あるのみと斯う考へて居つた所の思想を全然根本から覆へして、世の中に実際至誠もあり赤誠もあり、純没我的献身的の精神に充ち満ちたものがあると云ふことを示して呉れたのであるから、そは独り現代人心を救済したのみならず、耶蘇教の感化が独り耶蘇の在世に止まらず、又釈迦の感化が釈迦在世に止まらず、二千年三千年と云ふ長日月中に尚影響感化を及ぼした如く、乃木将軍の死が独り現代人心を救済するのみならず、未来永久日本の国家を救ひ世道人心を救済するに与かつて力あることを知るべきであらうと思ふのであります。此の意味に於て乃木将軍は実に各宗教の教主が永遠不朽なるが如くにまた不死であり不滅であると言はんければならぬのであります。蓋し将軍は神人即ちDeus-Homo であつて、仮りに一たび人間の如く肉体を取って生れたのでありますけれども、実は神其ものであつたのであります。
宗教理論に基礎付けられた乃木礼賛
浄土真宗の寺に生まれ、近代性と合致できる仏教のあり方を求め、宗教学にその理論的基礎づけを求めて来た加藤玄智だが、乃木の自死をとおして、神道の伝統において、近代性と合致できる、あるいは近代の限界を超えていけるような普遍的な宗教性が具現されたと考えた。乃木の人格は「無限恒久の神」から来た「不朽不死恒久不滅」の神格を宿していた。「自刃して肉体的に死せる乃木将軍はその実死せぬのであつて、将軍は宗教家の言葉を仮りて云へば、其肉に死んで霊に生きたのであります」。(69ページ)
此の如くにして乃木将軍の死に於て直に有神論は立証されたのであります。世に唯物主義の思想の為めに翻弄されて、従来信じて居つた神を失つて煩悶して居る所の人、唯物論に影響されて自己精神上の主を見失ひて懐疑にさまよへる所の人は、乃木将軍の死が吾人に与へて呉れた其の天来の福音に依つて再び神を此に見出し真の意味の(有神観)不死長生の事実(有霊魂)を感得すべきであると思ふのであります。
加藤玄智も自死した乃木希典の精神に伝統的な武士道の再生を、即ち幕末に讃美された楠正成の精神を引き継ぐものを見出している。だが、加藤は新たに、そこに近代的な唯物論や無宗教の精神傾向を超えていく方向性を見出している。加藤があげている「煩悶」は、1903年に自殺した一高生、藤村操が用いて以来、広く近代的な教養をもち、懐疑に陥って苦悩する若者の精神を表すのに用いられるようになった語である。加藤は近代思想の用語を盛んに用いながら、乃木が体現する天皇崇敬や国体論や尊皇論を弁証しようとしている。1912年の乃木大将の殉死は、このような思想的展開にかっこうの機会を提供したのだった。
『春秋』2016年12月号