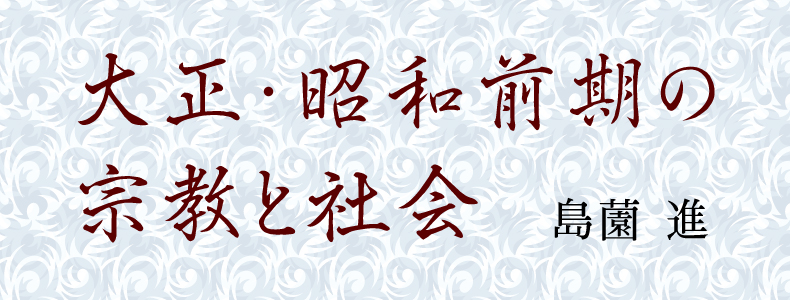第2回 明治聖徳論の展開と天皇崩御
「聖徳」論の歴史的展開
大正元(1912)年は明治天皇の「聖徳」という観念が国民に大きく広まった年だった。宗教学者の加藤玄智によって明治聖徳記念学会が発足させられたのは、そのことをよく示すものだろう。だが、「聖徳」を讃える言説が、明治天皇の崩御後に急速に生まれ育ったというわけではない。佐藤一伯氏の『明治聖徳論の研究』(2010年)にそって、「聖徳論」の歴史をたどっていくと、1891年の『萩の戸の月』にまで遡る。わずか16ページほどのものだが、初めてのものだからその意義は大きい。
佐藤氏の紹介を引く。冒頭で「余輩が特筆して宇内に比類なしといふは、現在の吾 天皇陛下の叡聖仁慈にわたらせたまふ乾徳(島薗注―天の徳、天子の徳の意。聖徳に等しい)にぞありける」とある。そして、「おもふに、九重雲深。余輩草莽の民、いかで悉伺ひ知ることを得ん。たゞ年来心にとめて、伝へ承れるはしはしを記して、本日を祝ふしるしとなすのみ」と続けている。
この後、「立憲政体に御熱心なる事」、「政務に御励精あらせられ厚く国民福利をおぼしめさるゝ事」、「宮禁厳粛なる事」の三節に分けて逸事が収録されている。たとえば、「立憲政体に御熱心なる事」では、「憲法草案の枢密院会議に欠かさず臨御され、昭宮猷仁親王(明治天皇第四皇子)薨去の知らせがあった際にも、「かまい(構・手偏)なく議事をつゞけよと仰出」があり、議長は議事が一段落した後、散会を宣言した」ことがあげられている。公務に着く高位の者として、私情を抑えた尊いふるまいということだろう。
「政務に御励精あらせられ厚く国民福利をおぼしめさるゝ事」では、「周知のとおり露国皇太子殿下御遭難の際には、宵衣肝食(夜の明けきらないうちから礼服を着、日が暮れてから食事をとること)の御労苦により、「陛下の御指揮のみにて、何事も決」した」こと。「宮禁厳粛なる事」では、「お手回りの品々は好みなく倹素を旨とされる」。「世界文明の度」において欧州各国に劣るとも、この「帝室の美徳」はどこに類例があろうか。「おもふに叡聖仁慈の、天皇上にあり、忠良義勇の臣民下にあり、吾国の将来、誰か望みなしとやはいふべき」といったものである。
天皇の像が大きく迫ってくる過程
『明治聖徳論の研究』には、続いて、1893年の宮本政躬著『天皇陛下皇太子天下御聖徳』(刊行者、辻本秀五郎)、1894年の原田真一編『銀婚聖典』(岡島支店刊行)があげられている。後者の本文の筆者は、大槻修二(如電)である。その「緒言」には、天皇への崇敬は江戸時代の将軍や藩主への忠誠を引き継ぐもので、自分はそれで納得している。だが、そうは言っても「今の時代に生まれし青年者等は君と臣とのけぢめ痛く隔た」っている。だから、「やゝもすれば民権とか云へることなど取りひがめ」てしまうようなこともあるようだ。そこで、「天皇の御徳と御恵とを我家の児等の心に染め」させるため、「人の人たる道のしをりともなるべし」とこの書をまとめたのだという。この頃には、明はる子こ皇后(昭憲皇后)の「坤徳」について述べた書物も刊行されるようになる。
この時期は「教育勅語」が煥発されてさほど時を経ておらず、国民は天皇を崇敬するという儀礼的チャンネルをあまりもっていない時期だった。やがて、学校で頻繁に「教育勅語」が読まれ記憶されるようになる。修身の授業で天皇や皇室について学ぶようにもなる。また、御真影に対する拝礼もなされるようになる。そして、日清戦争や日露戦争を通して、大元帥である天皇の指揮のもとに国をあげて戦い、勝利する。祝賀の祭典には多くの人々が繰り出す。国と天皇のために戦った多くの軍人・兵士が死亡し、靖国神社に祀られる。臨時大祭では天皇が自ら列席するし、戦没軍人・兵士と天皇が対峙する。
さらにまた、タカシ・フジタニが『天皇のページェント』で述べるように、さまざまな儀礼的機会に天皇は人々の前に姿を表し、国民は群衆としてそうした姿に向き合うことになる。「聖徳」は天皇のあれこれのすぐれた行為というより、輝かしい偉大な、しかし身近でもある帝王の像として人々の心に焼き付けられていった。
神聖な天皇の和歌、「御製」の登場
この間に聖徳録もその性格を変えていく。日露戦争時には、天皇の御製、皇后の御歌が頻繁に紙面を賑わせるようになる。徳富蘇峰主宰の『国民新聞』には1904年11月7日、「御聖徳の一端」と題して3首の御製が紹介される。
こらはみないくさのにはに出ではてゝ翁やひとり山田もるらむ
ちはやふる神のこゝろにかなふらむわかくに民のつくす誠は
四【よも】の海みなはらからとおもふ世になと波風の立さわぐらむ
そして翌日の社説で『国民新聞』はこう述べる。「吾人が前号の紙上に於いて、敬録の栄を辱ふしたる、御製の三首は、単り帝国臣民の心胸を躍らしむるのみならず。併せて世界列国国民をして、我が天皇陛下の聖徳を仰がしむ可き、高調を発揮したるを信ず」。
りっぱな歌なので、世界列国の国民を感動させるような聖徳が現れているという。そして「天皇陛下の大御心を中心とし、一国の人心、悉く皆な之に向て一致する」ことこそが、真実の「挙国一致」だと強調している。
『国民新聞』はこれを皮切りに、以後もしばしば御製と皇后の御歌数首を紙上で紹介した。他紙も追従するように掲載を開始するが、とくに大きく取り上げたのは1905(明治38)年3月28日の『東京日日新聞』で、「玉の御声」という記事に御製27首・皇后御歌7首、計34首を掲げている。紹介されている御製「をりにふれて」は次のようなものだ。
きたひたる剣の光いちしるくよにかゝやかせわかいくさ人
いかならむ薬すゝめて国のためいたておひたる身をは救はむ
山を抜くひとのちからも敷島の大和こころそもとゐなるへき
こうして次第に偉大な聖徳が讃えられるようになった明治天皇だが、崩御に至る過程でその神聖性は一段と高められていく。その大きなきっかけは、天皇の「御重態」の報道だった。
明治天皇の崩御と「大帝」という呼称
1912年7月20日、「国民は、天皇が日露戦争時に糖尿病を患われ、のちに慢性胃炎をご併発、一週間前より重患の兆しがあり、十九日午後には昏睡状態となり、尿量が減少しかつ蛋白質が増加、体温が四十度を超え、脈拍も百以上になっていることを突然知らされる」(『明治聖徳論の研究』、123ページ)。
20日の夜から二重橋前には皇居を遥拝し、平癒を祈願する人々の数が次第に増えていく、25日には午前3時頃から正午までに遥拝する者が6200名に及んだという。この時、新渡戸稲造はカーネギー平和基金による日米交換教授の任を終えて、日本に帰る前、欧州で夏を過ごそうとして大西洋の船上にあった。そこで天皇崩御の報に接し、シベリア横断鉄道で帰国の途についた。
1ヶ月以上後になって、新渡戸は明治天皇のことについてなかなか情報が得られなかったことに触れ、「一体大帝の御事に関しては、世に漏れていることが、我国に於ても極めて少なかった」と述べている。天皇の御不例の報はそのご様子を知りたいという国民の気持ちを高めた。そのこともあって、病状が初めて報じられてから、崩御、御大葬へと至る過程で、天皇をめぐる情報が一挙に国民に身近なものになっていった。佐藤一伯氏はそのことが聖徳論の展開にもたらした効果に注目している。
「明治大帝」という表現
新渡戸の言葉のなかに「大帝」という表現があるのは注目すべきだ。飛鳥井雅道氏の『明治大帝』(筑摩書房、1989年)によると、この表現が用いられた天皇は日本史上、明治天皇しかいない。そして、その「大帝」という表現は明治天皇の崩御後、つまりは1912年以後に用いられるようになり、広く用いられるようになったのは1920年代だという。
「大正」の元号を初めて印刷した新聞は『大阪毎日新聞』の1912年7月31日号で、京都帝國大学の国史学の教授、三浦周行の「嗚呼明治聖天子」と題する談話記事においてだ。飛鳥井氏の要約を引く。三浦は「奇蹟の如き御治世」との小見出しのもとに、「日本は「維新の大改革」による「武家政治の最期」から、「日清日露の二大戦役」をへて、「世界一等国の班に列するを得たり」とのべ、一転して、後醍醐、天智の二天皇を引き合いに出す」。後醍醐天皇による建武の中興はわずか2年しか続かなかった。天智天皇の大化の改新の方が明治の変革に近いが、これも朝鮮に背かれ、海外に国威を宣揚するには至らなかった。
ヨーロッパでは、明治日本は極東の一孤島が世界強国の一つとなった奇蹟だとまで言われ、「陛下の御生涯も亦実に奇蹟を以て満たされ」、「もし欧州の帝王にて在すならんには、必ずゼ、グレートと冠し奉る英主に在す御方なりしなり」――三浦はこう語った。「つまり「大帝」の表現は、ヨーロッパのピョートル大帝などとの対比で、まずカタカナの「ゼ、グレート」として出現したのである」と飛鳥井氏は述べている。
大正時代をまたぎ越して、昭和2(1927)年に刊行された『キング』附録『明治大帝 附明治美談』(大日本雄弁会講談社)を見てみよう。そこには、内閣総理大臣兼外務大臣・陸軍大将男爵、田中義一等、4人による序が付されている。田中総理大臣の序にはこう述べられている。
天に白日あり、炳として八紘を照らし、世に聖君あり、赫として千紀に光あり。畏くも我が 明治天皇を称え奉るに、聖君中の聖君として瞻仰し奉るべきこと、猶宇宙の光輝、独り天の白日を仰ぐがごとしとすべきか。
世界の局面に上って、欧米列強の伍班に入り、我が日本をして、夙に東方の和平を鎮護するの使命を荷ひ、久しく九鼎大呂よりも重からしむるを致さしめられしは、洵に 天皇の御丕徳御稜威の然らしめし所にあらずや。宜なるかな、中外期せずして、推尊するに 大帝の称呼を以てすることや。
この頃には、「大帝」の呼称とそれに伴う美辞麗句が広く使われるようになっていた。大正年間とはそのような変化をもたらした時代でもあったのだ。
『春秋』2016年11月号