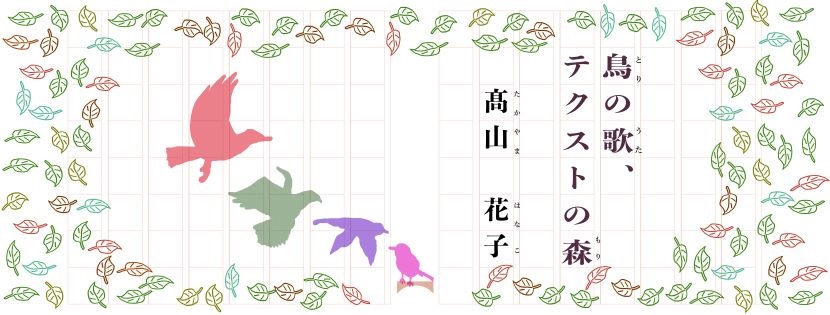祈りについて——武満徹とジャズ
1 即興と変奏
マドリードが陥落し、フランコ独裁政権が誕生したスペイン戦争の最中の1939年、災禍に襲われた街アランフェスを想って、スペインの作曲家ホアキン・ロドリーゴ(1901-1999)は、祈りの曲をつくった。《アランフェス協奏曲》である。管弦楽編成による伴奏付きの「ギター協奏曲」であるこの曲は、その後、いくつもの仕方でジャンルを越境し、ジャズの名曲としても知られてゆく。
まず例として浮かぶのはアメリカのジャズトランペット奏者、マイルス・デイヴィス(1926-1991)のアルバム『スケッチ・オブ・スペイン』(1960)に収録されている演奏だろう。それに加えて、1975年に発表された、ギタリスト、ジム・ホール(1930-2013)の『コンチェルト』にある《アランフェス協奏曲》の演奏をあげたい。
LP盤のB面に収められた20分弱のこの1曲は、ジム・ホールのギター、ポール・デスモンド(1924-1977)のサックス、チェット・ベイカー(1929-1988)のトランペット、ローランド・ハナ(1932-2002)のピアノ、ロン・カーター(1937- )のバス、スティーヴ・ガッド(1945-)のドラムスの音色の重なりあいによって、哀愁をたたえながらも力強いメロディーとして奏でられ、21世紀に至る現在までロドリーゴの響きの変奏を残している。
音楽には、一音として決しておなじ響きなどない、と言ってみることができるとして、しかし、いっぽうには、必ず、なにかしら同じものが引き継がれ繰り返される側面がある。その両義性を担保するひとつは、反復にともなう変奏——ヴァリアシオンの可能性だろう。そこには、なにか持続しているものがある。
前回、自然の音はもちろんのこと、なかでも鳥に少なくなくインスピレーションを受けていた作曲家、武満徹(1930-1996)による音の探求を、彼のテクストに分け入って追うなかで、彼が生き生きとした一音を生み出そうとするもくろみが、《鳥は星形の庭に降りる》(1977)に代表されるように、視覚的な風景の創出と結ばれていることを見てきた。そして、最後、武満にとっては、独立した個としての音同士が響き合うように、個としての人間が社会と結ばれる契機として、映画音楽が大きな意味をもっており、集団制作に参与することで、ある種の匿名性がそこからひらけてくる創作のプロセスを垣間見た。
思想的には、人間の耳では迫ることのできない鳥の啼き声の一回性やその都度の意味、響きに耳を傾けることに重きが置かれていたとわかるが、制作としては、たとえ鳥をテーマにするとしても、鳥の声を旋律によって模倣するといった次元ではまったくなく、表現を追求するなかで、自然の鳥たちの啼き声が混ざりあい、音の扶(たす)けあいが実現する境地が目指されていること——そのためにこそ生きた一音が希求されていること——を確認した、そのようにまとめられるだろう。
それらを踏まえて、今回は、武満が「個」について書きながら探究するときに、しばしばジャズを挙げていたことに迫ってみたい。ジャズは、その場かぎりの、まったく新しい形で出現する唯一無二の演奏であるとともに、多くの他者に共有可能である——それはすなわち、我々が、二度と同じ囀りはないとされる鳥の歌声を、どういうわけかそれぞれ種や鳴き方ごとに分類し、それ相応の名前を、ひとまとまりに、とりいそぎ、つけているという構図に似通っている。ゆえにジャズを、新しく独自の個性をもった音が生まれるものとして、それがそれでもなお、他者に共有可能なものとして立ち現れてくる点について考えていきたい。
武満徹とジャズ
武満が作曲を志した原点として、以下のエピソードが知られている。武満は、埼玉での勤労動員中に、見習い士官が、手回しの蓄音機で、禁止されていた、フランスのシャンソン、《聞かせてよ愛の言葉を》のレコードを流しているのを聞いた。武満は父親がジャズ好きだったこともあり、子供の頃からジャズを聞いていた。また、終戦後の進駐軍との間にも、ジャズという繋がりがあった。ジャズは、武満のすぐそばに、ずっといた——ここから武満の作曲の源泉の一つにジャズが大きく関わっていたということが想像できる。それを裏付けるように、武満は自身の生年の1930年が、デューク・エリントンの《Mood Indigo》発表年と同じであると回想したり[1]、父親が手回し蓄音器で聞いていたディキシーランド・ジャズのトロンボーンを想起したり[2]、記憶の奥底にジャズがあることを、認めている。
しかし、それだけでなく、彼は、ジャズの即興という性質そのものに、人間の激しい個性の現出と生命の躍動をみてとっていた。
なんとはなしに聞こえてくる鳥の歌は、無意味なのではなく、鳥たちにとってはコミュニケーションのために機能している。即興的で、自由なものと聞いてしまうこともできるジャズの演奏そのものもまた、音の生成とその聴取理解を試す側面をもっているだろう。そして、武満は、そのようなジャズへの親近感を強く示しながらも、個と個が関係のなかで結ばれる境地としては、ジャズとは異なる方向へ向かっていった。その点を、彼の「祈りをめぐる思索」に着目して、考えてみたい。
2 ジャズと即興性
チャーリー・パーカー、鳥の歌の文法
ジャズとはなにか、と聞かれて、定義を答えることは簡単ではないが、ジョン・コルトレーン(1926-1967)、ビル・エヴァンス(1929-1980)、キース・ジャレット(1945-)、去年この世を去ったチック・コリア(1941-2021)といった風に、プレイヤーの固有名を挙げてゆくと、なんとなく、聞いたことのある曲や雰囲気が浮かんでくるのではないだろうか。
あるいは、スタンダード・ナンバーと呼ばれるような、ビッグ・バンドでも演奏される定番曲として、《チュニジアの夜》、《マイ・フェイヴォリット・シングス》、《枯葉》、《マイ・ファニー・ヴァレンタイン》、《フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン》などは、一部分でもフレーズを聞けば、ああ、どこかで聞いたことがある、と思い出される馴染みあるメロディーだろう。では、それは、どこで聞いたのか——そう問われたまさにその時、とたんにあらわとなるのが、ジャズの楽曲の同一性と反復をめぐる問題である。ジャズは、ある曲が繰り返されるとしても、奏者によって、そのたびごとにアレンジされる割合が、譜面に楽音の指定されている楽曲よりも大きい、そう言って差し支えないと思われる。コード進行や主旋律はありながら、余白として残される自由度が高いわけだ。とりわけ、モダン・ジャズが盛んであった1960年代後半よりもずっと前のジャズでは、個々のプレイヤーによって、即興性が競われていた側面が強かった。
そのようにして、古くをさかのぼりつつ、あれこれジャズを聞いていると、どこかで必ず出会うのが、モダン・ジャズの原点としてのサックス奏者、チャーリー・パーカー(1920-1955)だろう。
楽譜がないどころか、録音音源すらもかぎられているパーカーの奏法は、ただ聞くだけでは、どのように生起しているのかもわからないほどに、再現不可能な一回性の音楽であるように思われる。たとえば、1946年3月28日に録音された、鳥類学を意味する名前のついた《オーニソロジー》という曲があるが、鳥の自由溢れる囀りを聞いているように、サックスの響きは、音符であれ言葉であれ、いわゆる「記録/記譜」とは遠いところにあるように思われる。しかし、音である以上、その音を分解して視覚的にスコアに起こすことは可能である。
近年、パーカーの奏でる旋律には、複雑とはいえ次々と入れ替わるコード進行に連動した和声が組み立てられているという「生成の文法」があることが、残された音源の採譜と分析から示されている[3]。なによりも、パーカーのそうした奏法そのものが、まったくおなじとは言えないとはいえ、現代に至るまで、数え切れないほどのジャズ奏者たちによって引き継がれ、変奏されつづけていることが、一度きりである部分がありながらも、それがなんらかのかたちで生き続けてゆく運動性を物語っている。即興とは、ゼロからその瞬間に生まれて決して再現されないということだけではないと、パーカーの演奏とその後の歴史からはよく伝わってくる。
それでは、武満は「即興」についてどのような考えを持っていたのか。『樹の鏡、草原の鏡』(1975)序盤に収録されたテクスト「樹の鏡、草原の鏡」のなかで、彼は即興性について、こう書いている。
即興性ということは、ひとつの大きな規律のなかで行われるものであり、そこに面白さや意味があるのである。スンダニーズの音楽に限らず、アジアの音楽、殊に印度音楽やガムラン音楽にはそれが著しい。ガムラン音楽では、現在でも毎日のように新しい音楽がその演奏から創りだされている。それらは民族の固有の感性に強く支えられて古典性を失ってはいないが、字義的な古典とはならずに、生きたものとして地に殖えて行く。/即興は、旋律とリズムの音階(旋法)に魂を委ねてはじめて可能になる。そして、音階はまたその時にはじめて姿を顕わす。それは日々生まれ変り、特定の日や時間、特定の場所、また特定の内的な場景と深く結びつく。音階は人間が歩む道であり、果てしないが、その無数の葉脈のような道は、いつか唯一の宇宙的な音階へ合流する。それは「神」の名で呼ばれるものであり、地上の音階は、「神」の容貌を映しだす鏡の無数の細片なのである[4]。
ここに浮かび上がるのは、古典と重ねられるかたちで、アジアにおけるある土地に根ざした音楽が、生き生きと日々変遷してゆく姿である。そして、それが宇宙や神のイメージと結ばれて語られている。「魂」という言葉がまっすぐに使われている。
さらに武満は同書収録の、ハワイやインディアンの言葉の発音から人類の声について考察するテクスト「磨かぬ鏡」において、「現在、自分がもっとも強く魅かれている音楽について考えてみると、そこに共通するのは、それらの音楽の多くが、表記する文字を有たない民族のものである、ということに気附く」[5]と書き始める。武満は、呪術的力があらわれる社会での発声について語るなかで、人間存在が一つの個としては完結しないことを、音楽のありかたとともに考えている。
耳に知覚されることのない、形而上学的な音の存在がたしかに措定されている非西欧かつ非日本的な音楽に、神に通じてゆく姿があること――というより、「音楽を通して神に到達する」[6]可能性が信じられていること――を見てとる武満は、それと引き比べて、作曲家が個人としての自己主張のために音楽をつくる営為を自省する。そこから、近代社会においては、人間存在がひとつの音であることに困難が生じていることを洞察する。武満は、その過程で、インドの詩人タゴール(1861-1941)の詩集『ギーターンジャリ』(1910)を引用しながら、神を待つ詩人に対して、自分自身が、そのような神をもたずして、それでもなお、歌を、メロディーを求める欲求の苦しみに向き合っていることを考察する。
興味深いのは、そのあと、武満が、個人について再び語るにあたって、ジャズピアニスト、デューク・エリントン(1899-1974)の演奏と、ジャズにおける個人の「自由」を取りあげていることである。1968年にマンハッタンの教会で行われたエリントンのチャリティコンサート「自由」で、幾人もの演奏者だけでなく、集まった聴衆たちをもが自由を叫んだのに対して、「その音楽は名付けようもない魂の状態であり、欲望の匂う祈り(プレイヤー)であった」[7]と武満は書く。
ここから武満は、音楽は個でも複数でもなく、誰かに、何者かに所属するのではなく、他との関係のなかにあり、形をあらわすのだとして、関係(リレーション)への欲求こそが言葉にならない祈りなのだと言語化するのである。それが、ジャズによって実現しているというのだ。しかしながら、ジャズの根底にアフリカ系アメリカ人によるキリスト教信仰と黒人霊歌——ブルースの起点——があることを、武満は感じていたはずである。強い共感とともに常に距離が見え隠れするのは、神と信仰の問題が伴われているからではないだろうか。
3 武満徹のジャズ論
武満は、『音楽を呼びさますもの』(1985)に収録された「私の受けた音楽教育」の中で、「音楽は生活の中から生まれて、常に個人から出発して、そしてまた個人へもどるものです」[8]と書いていた。その「個人」について考えるヒントが、ジャズについて書いたいくつかのテクストから見て取れる。
「The try——ジャズ試論」(1957)ではっきりと書かれるのは、ジャズが「祈りの呪文」だということである。武満は、ジャズが論じられるべきものなどではなくて、感じるものだと前置きをしつつ、それでも、生命の即興の方法としてのジャズの性質を言葉で説明している。ここからは、彼がジャズに見出す「獣的ともいえる生命感」や「不思議な静けさと安らぎ」[9]が、彼の同時代の世界においては、感じられなくなりつつある——そのような人間の感覚世界と実在についての危機感とつうじてジャズが語られていることが、うかがわれる。
武満は「ジャズは、表現よりも行動という言葉の感覚に近い。それは欲望の呻きであり、嗚咽であり、祈りの呪文である」[10]、「生に対する激しい執着が、彼らをしてジャズさせたのだ。だから彼らのうたは、神を讃美すると同時に、獣的な欲望の匂いを発散させている。[…]ジャズは生命を証すものなのだ」[11]と綴る。こういうふうに、ジャズの激しい強度と静かなやさしさを讃えつつも、武満の脳裏にあるのは、静けさややさしさとはまた異なる生や音のありようであるように思われるのである。
「この大きな力、われわれをとり巻く世界の豊かさと、不安と、美しさについて、少しでも、本気になれないとしたら、それは人間の小ざかしさのためだ」[12]と武満が書くとき、彼が問題としているのは、現代世界におけるそのような人間の小ざかしさそのものだろう。
このように、短いテクストで、彼は、ジャズ奏者が、所与のメロディー、リズム、コードを制約ともせずに、生きることそのものとして演奏する様子について、「優れた即興は再び繰り返すことはできない。小さな論理を越えたはるかに大きな力で、彼は自然との神秘的な交感を終る」[13]と讃えている。
そのようにして、武満は、規則を安全に守るだけの生活を批判し、人間の言葉が虚しくなってしまったことを嘆く。そして、虐げあったり疑ったりをせずに、どのように人間が結びつき生きることができるのか、と自問をして、自分が出会ったサックス吹きについて、このように書くのである。
さっき、サキソフォンを吹いている男がいた。彼の吹くという行為は、生の挙動そのものだった。吹くことで、彼は自分を証しした。そして、いつか彼をとり囲むすべてのものと結びついていた。彼と僕の距りはほんとうに近いものになった。そして、彼はもう一人の男と結びついていた。僕たちに言葉はなかった[14]。
ここにあらわれているのは、演奏者と聴衆とが結ばれる姿でもある。サックス吹きがその行為によって、周囲と結びつき、その音色を聞く武満とも言葉なしに近づいたことから、武満は、「人間の結びつきは、行為の中に自分のすべてを没くした時にだけ可能なのだ。その時、世界は大きく拡がって、自分と他とは区別できないものとなる。/それは愛だ」[15]と、自他の境界がなくなる「愛」という言葉を持ち出して語っている。
武満がここで愛と呼んでいる、関係への欲望は、言葉なき祈りとしての音楽と結ばれるだろう。先ほど見たような、個でも複数でもない関係のなかにこそ形をもつ音楽の極致とも読み取れるように、ジャズが讃えられている。
もうひとつ、短くはあるが、武満は『音、沈黙と測りあえるほどに』(1971)収録の「ジャズ」と題した文章で、ジャズが集団的体験ではなく、個人の音楽的体験であるとして、ふたたび、祈りの感情について、言及している。
武満は、ジャズを他の民族音楽と区別して、「移り変る瞬間ごとに演奏者の心にくみたてられる感情を音楽的におきかえる」として、「様式であるよりはむしろひとつの状態であり、それらは、魂のひとつの容貌をうつしだしているものだ」[16]とする。そして、「ジャズは集団的体験ではない。個人の音楽的体験である。それは神の存在があくまでも個人的体験としてあるように、祈りの感情によってささえられ、そこに生まれたからだ」[17]と書いている。最後、彼は、個人的音楽体験の集合としての「普遍」を獲得するジャズの強度を確かめながら、このように結んでいる。
私の音楽とジャズとの間にいくらかでも共通するところがあるとすれば、自分に対して純潔な仕方で他者と交わりたいと希っていることかも知れない[18]。
この一文には、個人から生まれ、そしてジャズのように、純粋な仕方で他者と交わることを果てしなく望みながらも、とはいえ関係のなかに形をもつ音楽表現を希求している武満にとっては、みずからの音楽が、もはやジャズではないということ、あるいは、もっと強く言ってしまえば、ジャズではありえないことが、反実仮想のように、はっきりと告白されているとも見えないではないだろうか。まちがいなく、武満は激しい個々のぶつかりあいによって立ち昇るジャズの熱狂的即興に惹かれていた。しかし、「祈りの呪文」と表現されるそれが、どんなに幼い頃の憧憬とも重なるメロディーであったとしても、音楽家としての彼の創作の洗練は、オーケストレーションを中心とする記譜による音世界の立ち上げに向かってゆく。
おそらく、その理由は、武満にとっては、信仰する神がいないということ、そして、それにもかかわらず、彼にとって、祈りが本質的な問題となっていることが関連しているように思われる——このような問いを胸に、もう一度、武満による自然の音をめぐるテクストを読んでみたい。
4 神に支えられた「音」に対する距離
「樹の鏡、草原の鏡」にて、武満は、インドネシア旅行後に、ガムランをはじめとする同地の音の響きと比較して、西欧音楽と、邦楽について、振り返りを繰り返している。このとき、まず武満が言語化するのは、運搬可能な西洋音楽に対して、非西欧的な音楽は地上を覆う草のようで、他の土地に運ぶことはできない、ということである。そして、邦楽を含めた非西欧音楽を「自然の音楽」[19]と呼ぶのだが、彼は、尺八に代表される個別性が、個人ではなく、「家」に回帰する点が、ジャワやバリで聞いてきた音楽とは異なると回想する。
彼はこのように書いている。
ジャワ島やバリ島で聴いたガムランの、あの空の高みにまで昇るような音の光りの房は何なのだろうか、と思う。私たちの音楽のどの部分にあのような眩いかがやきを見ることができるだろうか。陽光の木魂のように響くガムランの数々の銅鑼を聴きながら、私は邦楽器の音について考えていた。私が感じたことを率直に表せば、ガムランの響きの明るさとその官能性は、「神」をもつ民族のものであり、日本音楽の響きは「神」をもたない民族のものなのではないか、ということであった[20]。
これは、武満が感じたことである。ガムランを聞いて、音楽の幸福感に浸るときにそれが悲しみに連なるという彼は、「自分の深部において悲しみに目覚めながらも、魂が高揚するような祝福の裡に在った」[21]という。
そして、その違いの一つが、即興性の有無であると彼は考察する。より具体的には、個人による演奏解釈が許されているかどうか、が問題であるとするのである。もう一度、このテクストのなかで、即興について書かれた箇所を読んでみよう。
即興性ということは、ひとつの大きな規律のなかで行われるものであり、そこに面白さや意味があるのである。スンダニーズの音楽に限らず、アジアの音楽、殊に印度音楽やガムラン音楽にはそれが著しい。ガムラン音楽では、現在でも毎日のように新しい音楽がその演奏から創りだされている。それらは民族の固有の感性に強く支えられて古典性を失ってはいないが、字義的な古典とはならずに、生きたものとして地に殖えて行く。/即興は、旋律とリズムの音階(旋法)に魂を委ねてはじめて可能になる。そして、音階はまたその時にはじめて姿を顕わす。それは日々生まれ変り、特定の日や時間、特定の場所、また特定の内的な場景と深く結びつく。音階は人間が歩む道であり、果てしないが、その無数の葉脈のような道は、いつか唯一の宇宙的な音階へ合流する。それは「神」の名で呼ばれるものであり、地上の音階は、「神」の容貌を映しだす鏡の無数の細片なのである[22]。
西欧音楽に出会い、日本の伝統音楽に接し、そしてインドネシアを旅して、武満は、「インドネシアの音楽そのもの、そしてその文化を創造している情熱の根底をなす強い宗教的感情というものに動かされ」、「ジャワ島やバリ島に営まれている美しい草の音楽の蔭に、往き場を失った変種の西欧文明が歪んだ貌を曝しているのを見ると、歴史というものの醜悪な素顔に接したようでやりきれなかった」[23]とアジアの近代化と戦争の記憶と日本自体を思考するに至る。
ここには、ジャズにも深く通じる「即興性」に強く惹かれながら、個人によるときに激しい解釈の自由を支える「神」の存在に、日本人として絶対的な距離を感じる作曲家の姿がある。
その姿を受け止めると、『音、沈黙と測りあえるほどに』に収録された「自然と音楽——作曲家の日記」にて、1962年10月、宮内庁にて雅楽を聞いて、音が樹のように立ち上る印象をもち、仏教的な影響に目配せをしつつも、その音の河の流れから無常観だけでなく、生命の歴史を感じるとする武満の感性は、神と宗教的なものと隣接しながら、無意識のうちに、樹の風景に重ねている点に、特徴があるとはいえないか。
それは、前回の連載でも確認をした、《独奏ピアノとオーケストラ群のための弧》(1963)によって実現された、オーケストラの庭をそれぞれの音に呼応しながら横切ってゆく独奏ピアノの自由さを支える、生命の樹々、草木の庭の創出へと回路を繋いでいる——。
武満の著作である『音楽の余白から』(1980)に収められたテクスト「鏡と卵」において、彼は『弧』の創作におけるメシアンやドビュッシーからの霊感を明言しながらも、「物を生み出す母胎は、外在するものではなく、内にあるのです。/私はそれを現実と呼びたいと思います」[24]とする。彼の言葉からは、どこかに超越論的な方向を措定する——そこにはキリスト教の神が含まれるだろう——音楽を横目にしながら、そのような神も信仰ももたないながらに祈りを希求する現実主義者として振る舞う態度が見受けられはしないか。
5 祈りのかたちとしての非ジャズ――未完のオペラに向かって
最後に、個人としての人間が結びつく方法として、ジャズ音楽を愛しながらも、ジャズではない音楽へと向かった武満が、オペラを構想していたことに触れたい。具体的には、未完のままに終わったこの構想について、1990年に「オペラをつくる」と題された大江健三郎との対談を読んでみたい。というのも、そこには、これまでみてきた祈りと救済のテーマの探究が読み取れるからである。この対談は、I. 世界のヴィジョンにねざしつつ、II. 物語にむかって、III. 劇的人物像をめぐって、IV. 芸術家が未来に残すもの、の4部に分けられる。
預言詩を残したイェーツ(1865-1639)による詩人のヴィジョンを、ある世界観あるいは人間観の実現としてオペラに結実させたい、と言う大江に対して、武満は、第二次世界大戦という地球規模での災厄に対するヴィジョンを実現するためのテクノロジーによって、かえって、音楽家たちが管理機構に組み込まれてしまった現実を省みている。そうした芸術の現状を打開するために、二人は、個人を超えた、共同作業によってしか生まれてこないオペラの可能性を話す。
序盤で、武満はこう言っている。
つまりオペラの場合はやはり共同の作業を通してしか生まれてこない。またそれは必ず人間たちによってパフォームされなければならない。それからそうした作品がつねにある時間・空間の中でたくさんの人びとと共有される、経験を共有することができること、それからテクスト、つまり言葉、詩、物語を使うことで、より具体的に現実状況に対して批判的な発言ができるだろうということ[25]。
その世界観を支えるキリスト教の信仰を持たない大江が、物語から、物語をも超えたヴィジョンをめざしている話をつづけてゆく。そして、超越的なイメージを結実させる物語の力、神秘的なヴィジョンに向かってゆく小説の話と宇宙感覚についての質問を受けて、武満は、自分自身の信仰について打ち明けるのである。すこし長いが、引用したい。
僕自身が生活していて、また芸術家としての生活のなかで、やはり避けられない関心のひとつは宗教だと思います。/宗教というと、ある既成の、特定の宗教ということにいきがちですが、僕自身も、それでは、神を信じているかということになると、信じていないのです。絶対的な神というものに対してはともかく、たとえば、仮に特定の名で呼ばれるような神を信じることはありません。/自分自身は音楽をするときに、音楽というものはあるひとつの祈りの形式だろうと思っています。そしてつねに音楽を書くときには、最初は、現実的ないろいろな出来事から喚起されて、怒りの感情とか、古代インド人が類別したいくつかの大きな感情、喜びの感情、楽しみの感情、そういうものに衝き動かされて音楽を書いているのですが。でも、最後にそうしたいろいろないくつかの感情がせめぎ合って、そこに沈んでくるものは、それこそうまく説明できませんが、祈りの感情というものである[26]。
武満は、対談の別所で、自分自身の作る音が「キリスト教的な神という概念からは遠い、汎神論的なもの」であり、「最初から雑音のようなものとして、音というものをとらえている」[27]と言う。それは主題にもとづく構造的組み立てとは齟齬をきたすと自覚しながら、彼がそれでもオペラに救済の可能性を見出すのは、それが、単なる共同作業、共同制作であるだけでなく、小説も詩も美術も映画もすべての音楽も参加する、「作品というものの複数」[28]として成立しているからである。
このように振り返ると、武満がみずからの、あるいは、さらに人間の聴覚そのものを変容させる契機としても耳を深く澄ませていた、鳥たちの啼き声は、ある種の神の使いとして鳥を思い描き、モチーフとして用いるような仕方とは異なっていただろうと想像される。鳥が舞い降りるような、可動的な風景を創出する背後には、神なしに、信仰なしに、音楽の音を宇宙的な次元へと届けてゆこうとする熾烈なもくろみがうごめいていたように思われるのである。
[1] 小沼純一編『武満徹 エッセイ選——言葉の海へ』ちくま学芸文庫、2008年、417頁。
[2] 同上、418頁。
[3] たとえば、濱瀬元彦『チャーリー・パーカーの技法——インプロヴィゼーションの構造分析』(岩波書店、2013年)を参照。
[4] 小沼純一編『武満徹 エッセイ選——言葉の海へ』前掲書、30頁。
[5] 同上、45頁。
[6] 同上、51頁。
[7] 同上、58頁。
[8] 同上、186頁。
[9] 同上、393頁。
[10] 同上、393頁。
[11] 同上、394頁。
[12] 同上、396頁。
[13] 同上。
[14] 同上、398頁。
[15] 同上。
[16] 同上、400頁。
[17] 同上、401頁。
[18] 同上、406頁。
[19] 武満徹『武満徹著作集1』新潮社、2000年、231頁。
[20] 同上、232頁。
[21] 同上、233頁。
[22] 同上、234-235頁(小沼純一編『武満徹 エッセイ選——言葉の海へ』前掲書、30頁)。
[23] 同上、259頁。
[24] 同上、26頁。
[25] 武満徹『武満徹著作集4』新潮社、2000年、216頁。
[26] 同上、257頁。
[27] 同上、267頁。
[28] 同上、274頁。