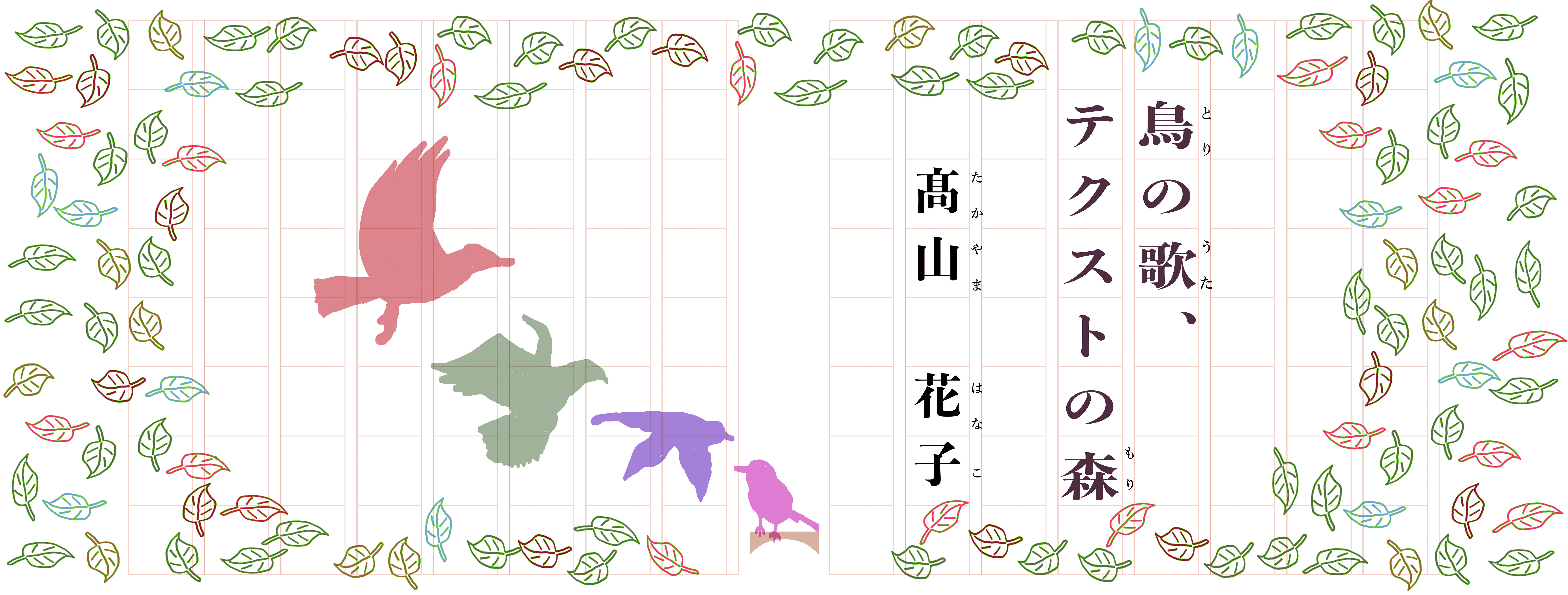大江健三郎と鳥の歌――イーヨーと森のフシギ
ときに空を舞い、ときに歌をうたい、ときに色彩ゆたかな羽を纏う鳥。煌びやかな孔雀、街中に佇み囀る雀や鴉、電線にとまる鳩、海辺に浮かぶ水鳥、木の実を啄みに訪れるやかましい鵯、優雅に水上でむくむくとした羽を繕う白鳥、不意に住宅街に現れる派手な見た目をしたインコ、姿は見えずとも朝方に遠くどこからか声が聞こえてくる雉鳩。
春、夏、秋、冬。季節ごとに鳥たちのいる景色は、移ろってゆく──あるいは、屋外で聞こえてくる鳥たちの奏でる音風景は、その日ごとに、その場ごとに、微細に無限に彩を変えてゆく。海を渡り繁殖を繰り返す鳥もいれば、大空には決して羽ばたかない鳥もいる。目立たない小さな鳥も枚挙にいとまがないほどにいる。わたしたちには、きっと知らない鳥の数のほうが多いのだろう。
世界中のありとあらゆる土地に生息するこの夥しい種類の鳥たちは、その起源や進化の謎、多彩な形態、さえずりの美しさから、はるかむかしから現在に至るまで、ひとびとの心を惹きつけ、古今東西のさまざまなテクストに、その姿が描かれ、記録されてきた動物であると言えるだろう。この連載では、鳥の「歌」がどのように作家によって聞かれ、音楽家によって追求されてきたのか、いくつかのテーマにもとづいて、テクストの森の中で鳥の声に耳を澄ますように、紐解いてゆきたい。
特別な動物、鳥
鳥に縁深い作家のひとりに、ノーベル文学賞を受賞した大江健三郎(1935- )が挙げられる。もとより大江の作品の中を歩いていると、鳥に限らず、いろいろな動物たちに出会えるのではあるが、そのなかでも鳥は特別な意味を込められているように思われる。
というのも大江の作品には、あるときから名前が「鳥」という、一見すると奇異な普通名詞をあたえられた主人公あるいは登場人物が出現しはじめるからだ。
象徴的なのは、1964年に発表された『個人的な体験』の主人公、「鳥」である[1]。彼はアフリカ地図を見つめながら海外へと旅することを夢見つつ、女友達である火見子と放蕩をつづける。この作品には、例えば眠り込んでしまった火見子を見つめる主人公について、「鳥は雛をまもっている牝鶏のような気持だった」[2]といった一文があるように、鳥が人間のように動いている情景が浮かんでくる箇所がいくつもある。
ストーリーの中で、鳥は頭に大きな瘤をつけて生まれた脳ヘルニアの新生児の父親となる。このとき、保育器の中に眠るほかの赤んぼうは、「毛を毟った鶏ほどにも小さく異様に黒っぽくカサカサしている皮膚をした赤んぼう」[3]と書かれていたりする。鳥の赤んぼうは、他の赤んぼうとは異なって、「茹でたエビみたい」[4]と形容され、なおかつ、植物的存在としてとらえられている。
ここで思い出されるのは、『個人的な体験』が発表される前年の1963年、大江健三郎に脳に障害のある息子の光が生まれたことである。ある意味ではこの光が、鳥の形象とともに作品の中に投影されはじめるのが、1960年代以降の大江作品の特色のひとつであると言えるだろう。そしてその後、「光と鳥の声に関するある出来事」が、大江の作品を新しい仕方で創り上げてゆくことになるのである。
鳥の歌に反応する子供
やがて音楽の才能を開花させ、作曲家となる大江光が、はじめて自発的に発した言葉は鳥の名を告げるものであった。このエピソードは、いくつかのテクストで読むことができる。まずは『大江健三郎自選短篇』(岩波文庫、2014年)の最後にも収録された「火をめぐらす鳥」(初出1991年7月)の記述にしたがって、鳥の声と大江親子の関係を、見てみたい。
このエッセイは、大江が伊藤静雄(1906-1953)の詩「鶯」の詩句に激しく感情を動かされた少年期を回顧するものである。大江は、当時、口笛で鶯を呼び寄せた友人や、川沿いの栗林に時鳥(ほととぎす)や郭公(かっこう)が啼いていた風景を想起しながら、伊藤の詩句にある「(私の魂)といふことは言へない/しかも(私の魂)は記憶する」といったフレーズを、もう一度読み返す。そこに読まれるのは、老年を迎えて、かつて読んでいた詩句をあらためて呼び寄せて、過去といまとを折り重ねながら自省する作家の姿である。そしてテクストの中には、「鶯」を読んでいた20歳前後の頃からおよそ10年後に生まれた、障害をもった長男も登場する。
大江は、息子がラジオやテレビの効果音の野鳥の声に反応するので、NHKの技術班がつくった、それぞれの鳥の啼き声のあとに、アナウンサーの声音がその鳥の名を告げるテープを彼のために子守唄がわりに聞かせつづけていた。あるとき、北軽井沢の山荘の人造湖近くで実際に野生のクイナが啼いているときに、大江が息子を肩車していると、頭の上から、初めて彼が自発的な言葉として、「クイナ、ですよ」と話すのが聞こえてきた[5]。以後、大江の息子は、テープの鳥の声を聞かせると、その鳥の名前を正確に答えるようになるのである。
この衝撃の体験を紹介したあと、大江は、ウグイスの鳴き声を聞いてから、息子が「ウグイス、ですよ」と発話するとき、伊藤静雄の「鶯」に惹かれた少年時の自分と息子を重ねあわせるようになったことを告白している。大江はこのように書いている。
(私の魂)といふことは言へない、という一行の意味が、自分の心と身体のうちに生きていることを確かめたのだ。しかも、その時すでに亡くなっていた友達の魂が、鶯の声のように山や野のいたるところで光を発している。自分の魂は息子の魂とピッタリ一致して、それに照応する、それがしかも(私の魂)は記憶する、ということだ……[6]。
ここには、伊藤静雄の詩句を鍵として、自分の魂と息子の魂が、鶯によって結ばれることを事後的に確認する晩年の作家の姿がある。
その息子は、自宅の庭先を訪れる鳥の声にはそこまで反応を示さなくなる。やがて、音楽そのものへの関心をむしろ深めて作曲家になってゆく。彼が生まれた頃、自らを鳥に重ねるかのように主人公の名前を「鳥」とする作品を手がけていた大江は、図らずも鳥の声を契機として言葉を発し、音楽の才能をひろげてゆく障害を持った息子の存在を、1970年代以降、いくたびも変奏することになる──
『洪水はわが魂に及び』に描かれるジン
鳥の声を聞いて、その種名を当てる障害をもった子供が現れる作品に、長篇『洪水はわが魂に及び』(1973)がある。これはSF的な想像力にあふれた物語である。主人公の大木勇魚は、ジンという名前の5歳の息子を連れて、かつて宣伝企画に関わった民間の核避難所に隠遁している。ジンは、知的障害があり、聴覚が鋭敏で、レコードから移した鳥の鳴き声のテープに反応し、50種類以上を聞き分ける鳥の専門家として描かれている。
ジンは鳥の鳴き声に敏感に反応し、その名前を答える。それだけでなく、勇魚が鳥の声を模倣すると、それに対してキジバトですよ、と言ってくれるのである。ここには、鳥の声を介して息子とコミュニケーションを図ろうとする父親の姿がある。
さらに、物語の終盤、爆破攻撃を受けた地下壕が揺れる最中、繰り返しかけつづけられる鳥の録音に対してジンは変わらずその名前を答えるのだが、そのとき、彼はただ名前を発するだけでなく、伊奈子という女性に語りかけるように声を発していると描写されているのである。ここからは、鳥の名を告げる行為から、ジンの言語によるコミュニケーションがわずかながら進化してゆく様子が読み取れる。
しだいに主人公は、世界最終戦争によって衝撃波が訪れたならば、息子が「世界の終わり、ですよ」と、まるで鳥の声に対して答えるように言うことを期待する。しかし、実際には、ジンがそのように答えることは決してないように描かれている。そもそもの世界の終わりは訪れない。だが、そのような発話が思い描かれながら、実現はしない点に、大江による息子の描き方の特徴があるだろう。
実の息子が鳥の名前を自発的に声に出すようになったことを契機に、大江作品の中の息子のモデルたちも言葉を発するようにはなってゆく。しかし大江は、このように自分自身とその家族をモチーフとして変奏しながらも、まったく異なる子供の姿を描くには至らない。その点に、現実と虚構との境界を究め続けた作家の姿が見て取れるのである。
『静かな生活』に描かれるイーヨー
それでは次に、「子供の視点から」描かれた作品として、『静かな生活』(1990)を見てみよう。のちに伊丹十三によって映画化された小説『静かな生活』には、大江と思しき小説家の父をもつ大学生のマーちゃん(「私」)の視点から、母や、4歳年上の障害を持つ兄のイーヨー、それから弟で大学生のオーちゃんとともに日常生活を営むひとときの家族の姿が描かれている。
タイトルの「静かな生活」とは、20歳になったマーちゃんが、家族で食卓を囲みながら、自分自身の将来の結婚について語る際、結婚をしても自分はイーヨーと一緒だから、相手は2DKのアパートを手にいられる人がいい、そこで静かな生活を送りたい、と述べる冒頭の言葉に由来している。この時点から、成人して、父と母から離れて暮らすとしても、兄を保護する役割を担いつづけるのだと、妹のマーちゃんが想定していることがわかる。
小説家の父の周囲には、花束を置いて行ったり、水を入れた瓶を運んできたり、奇怪な行動をする人たちがたくさんいることが匂わせられるなか、イーヨーをめぐっては、林間学校の女生徒を障害者の男が襲うニュースによって、もしもイーヨーに同じようなことがあったら、と懸念をする家族の姿が肉薄して描かれている。
印象的なのは、イーヨーが家族団欒の風景にはいながら、家族たちの想像力が、どこか抽象的な方面へと進んでゆくことである。ある日、テレビで録画したアンドレイ・タルコフスキーの映画『案内人(ストーカー)』(1979)を見ていると、耳のよいイーヨーがその音楽に敏感に反応し、ベートーヴェンの「歓喜の歌」が流れるシーンでは、激しい指揮までする、ということがあった。
しかし、イーヨー以外の家族たちは、映画の中で、登場人物のストーカーの妻が、夫が呪われているから呪われた子供しか生まれない、と述べたことについて話すことになるのである。マーちゃんにいたっては、映画の中の「呪われた子供」とイーヨーを、自分たちの母が重ねていたのではないか、と考えはじめる。そして家族たちは、「呪われた子供」をはじめとする子供のイメージが、イエスの再臨なのか、それともアンチ・クリストなのかを議論しはじめ、徹底した世界の破壊の後で、キリストが再臨するのではないか、とまで語らうのである。どこかイーヨーが置き去りにされている感がある。
ここからは、世界をめぐるきわめて大きな問いの一つとして、「救済」の訪れが作家本人である大江にはあり、それが作中の家族に共有されていることがうかがわれる。
『静かな生活』における「救済」のイメージは、クリスマスの夜に中華料理店で兄弟3人で美味しい食事をし、帰宅してからイーヨーの選んだバッハとモーツァルトを聴きながら、マーちゃんとオーちゃんが、父親の書いた小説『M/Tと森のフシギの物語』、それからセリーヌの『リゴドン』を読んだ感想を交わし合うときにも顕著に現れている。
このテーマは、しかし、イーヨー自身の作曲と具体的に響きあっていることがわかってくる。創作上のピンチに瀕しはじめていた父は、「魂のことをするために、すべてを捨てて発心する境地」の必要性を感じ、母を連れて、自分を呼んでくれた大学のあるカリフォルニアへと発ってしまう。ちょうどその頃、重藤さんという人に作曲を教えてもらっているイーヨーは、「ステゴ」という謎めいたタイトルの曲を作る。
父と母が不在となったあるとき、マーちゃんとイーヨーは、父方の親族の葬儀のために四国に行く。そこで、葬儀の場にいたフサ叔母さんが「森のフシギ」の言い伝えの話をする。昔、大人にとっては不気味にブーンと聞こえる、「大怪音」と呼ばれる轟音が響き渡る時代があった。しかし、子供たちにはそれが柔らかく聞こえるので、子供たちは楽しく聞いているということがあった。
すると、フサ叔母さんは、イーヨーは「森のフシギ」のために「ステゴ」という音楽を作ったのだと言う──そのあたりから、魂のことをするためになにもかも「捨てる」という父のテーマと、「ステゴ」というタイトルが不思議に共鳴しはじめる──そして、この「ステゴ」が、この惑星の人間全員が捨て子だったと仮定したときに、その捨て子たちを助けるイメージで名付けられていることが判明する。
やがて、信仰の問題を深めてゆく小説家の父親は、自分が「森の伝承を覚えてつたえる人」[7]になることを重要視する。その姿を見ていたマーちゃんは、その父親と作曲家であるイーヨーの2人によって、「森のフシギ」が表現されるような気がしたことを語るのである。
しかし、かたやイーヨー本人は、一貫して、そのような世界の壮大な問題をどのように引き受けるのか、であるとか、そのような救済にかかわるのか否かといった、家族たちによって議論される超地上的な次元からは離れて、地に足をつけている存在として描かれているようだ。そのエピソードのすこし手前で、マーちゃんがイーヨーの作った曲「Mのレクイエム」について、それはあくまでも地上の人間の音楽の主題と文法で作曲されていることを説明しているのだが、そのこと自体が、イーヨーの性格をしっかりと描き出しているだろう。
やがて、イーヨーに水泳を教えることを頼まれたコーチの新井くんが、マーちゃんの下腹部をむき出しにして、彼女の脚をM字型に縛り猥褻行為を働こうとする事件が起こる。そのとき、新井くんの頸動脈を押さえつけて、マーちゃんが逃げ出すのを助けたのは、ほかならぬイーヨーだった。「呪われた子供」を想起させ、天上の救済の問題をイメージさせるイーヨー自身は、かわいそうな永遠に保護されるべき、介護されるだけの存在などではないことが如実に示される強い場面である。
半年ぶりに父と母がカリフォルニアから帰国したあと、母親は、マーちゃんが書いていた日記「家としての日記」を父に読ませることで、彼が自分に家族がいることを思い出すかもしれない、と述べる。そしてイーヨーは、その日記のタイトルを決めるように聞かれて、「静かな生活」とするのがよいとあっさり答える。いったんは深刻に「呪われた子供」に重ねられたイーヨーは、妹によって将来を空想的に心配されながらも、もっとも快活に地に足をつけて目の前の現実を生き、「静かな生活」がここにあることを告げこすのである。
映画『静かな生活』に現れるクイナのエピソードと捨子
こうした鳥と息子をめぐる主題をかぎりなく汲み取みとったのが、この作品を映画化した伊丹十三(1933-1997)であると言ってみたい。
大江健三郎の妻ゆかりは伊丹の妹で、伊丹自身、松山東高校で、大江と在学時期が重なっている。
伊丹による映画化では、冒頭が、福祉作業所に通う障害者たちが散歩する途中、抜け出したそのうちの男女二人が「磁石」のようにくっついてしまっているのを、通行人たちが騒ぎ立てている場面からはじまる。「二十歳を過ぎて、体は成熟して、性的な衝動は訪れる。しかし、知能は発達していない」──そのような障害者に対する世間の人々の差別や偏見を問う側面が、主に性犯罪の可能性を示唆する形で正面から表現されている。
そのほか、夫妻の渡航先が「カリフォルニア」ではなくオーストラリアの「シドニー」になっていたり、小説家の父親が家長としての自分の存在感を示すことに挫折して自殺を考えている様子がコミカルに映し出されていたりするなど、小説からはずいぶんと改変と削除がされている。
映画において新たに挿入されたエピソードのひとつに、鳥の声に反応を示したイーヨーをめぐるものがある。それは、祈り、という大江にとっての人生と創作の双方に関わるテーマを説明するために大きな役割を果たしているのでみてみたい。
眼鏡をかけた小説家が屋外で耳を傾ける人たちにむかって、このような内容を話すシーンがある。
……言葉を話さず、母親の話しかけにも反応しない子供が、なぜか鳥の声のレコードだけには反応する。それで、鳥のレコードを朝から晩までかけつづけることになった。そうして、彼が6歳になったある夏の日のこと、高原の別荘にいき、朝、息子を肩車して、外を歩いていると、クイナがとんとーん、と鳴いた。それから、頭の上で、クイナです、と言う声がした。幻聴だと思った。しかし、もしかして息子がしゃべったのかもしれない。だとすれば、もう一度、クイナの声がして、そして息子の声がすれば、息子が人間の言葉を話しはじめるかもしれない。
そのように、待っていたときについて、彼は、そのとき、紛れもなく祈っていたんです、と述べる。そして、もう一度クイナが鳴き、息子はクイナです、と声を発した……
この仮定形にあふれた「祈り」をめぐる発言が収録されたテレビ放送がきっかけで、小説家のKに対しては、宗教家たちからの勧誘が起こるようになった。マーちゃんとオーちゃんは、映画の中では、自宅へしばしば水の入った瓶を届ける者も、狂信家なのではないか、と仮説を立てたりしている。
ともあれ、小説の大枠には沿いながらも、大江自身をみているこのような伊丹の演出によって、鳥の歌を聞いたあとに祈りの行為が作家に生まれるというように、祈りのイメージが鳥によって結ばれているのである。
伊丹の最初の作品『お葬式』(1985)でも深々とした森が描かれていたが、『静かな生活』(1995)でも、小説家のKがかつて少年期を過ごした森が、自然の他にはなにもないとさえ思われる一面緑の風景として、しっかり現れている。魂のために、すべてを捨てることができるか、という人生にも関わる壮大な問いを抱えた作家は、子供たちを置いて、オーストラリアの森に囲まれた生活をすることで、最終的には窮地を脱する。
映画のなかでは、実際に大江光の作曲した音楽が、なだらかに響き渡っている。そして、小説家がかつて、故郷で神隠しに遭い、のちに帰還した子供たちは、「宇宙船によって連れてこられた捨子なのだ」と考えていたこととが、大江光の音楽と時を越えて繋がっているように示されている。主な舞台となっている家族の住む家の庭でも、障害者の作業所に通う人たちが引率されて散歩する原っぱでも、葬儀で訪れることになる愛媛と思しき森でも、さらには、小説家夫妻が電話をするシーンとして現れる滞在先のオーストラリアでも、緑のなかの鳥のさえずりは絶えない。やがて作曲家として育ってゆく光の傍には、つねに鳥があることを仄めかす仕組みが働いている。
このように伊丹は、原作にあった森のフシギの音楽との関連には言及しないながら、大江が伝え聞いていた森の奥の村の物語と捨子の救済というイメージを、映画の中に、自然の風景とともに織り交ぜて差し出しているのである[8]。
空の怪物アグイーのイメージ
興味深いことに、大江の作品ではジンやイーヨーのように変奏される子供が、ときには、死児として、怪物として描かれて、さらにそこから逃げようとする主人公の姿も見え隠れする。
先に見た『個人的な体験』は、脳に腫瘍をもった子供が生まれ、父親となった大江自身を強く反映する物語である。と同時に、脳ヘルニアと診断された赤ん坊について、主人公の鳥が「赤んぼうの怪物から逃げきらねばならないぞ」[9]と言っていたように、子供は「怪物」に喩えられている。しかし、最終的に主人公は、逃げるというのは欺瞞であるとする。そして、欺瞞なしの方法として、自分で赤ん坊を殺すか、育てるか、の二択を見出す。
ある種、逃げることができない鳥として登場人物の人間が描かれはじめてから、地上の怪物として赤ん坊が、ときに亡霊的に、死んだものとして、姿を表すようになっているのだ。
このことは短篇「空の怪物アグイー」(1964年1月初出)にもよくあらわれている。ストーリーは、主人公「ぼく」が、いまは右目がほとんど見えないことを語る場面から始まる。彼は18歳のときに、伯父の紹介で知り合った銀行家から、彼の息子である、怪物にとりつかれた作曲家Dの外出の付き添いのアルバイトを依頼される。
はじめて「ぼく」がDの部屋を訪れると、そこではテープレコーダーから回転数をあげて音量を高くした犀(さい)の声が響き渡っていた。そして「ぼく」はDの付き添いを始めるのだが、やがて、Dには空を浮遊する《あれ》が見え、それが降りてくると話す癖があることがわかる。
「ぼく」は、Dの症状をよくしる初老の看護師に《あれ》について尋ねた。彼女は、《あれ》がカンガルーほどの大きさの、「木綿地の白い肌着をきた肥りすぎの赤ん坊」で、アグイーと言う名前なのだと教えてくれる[10]。その後、「ぼく」はDの離婚した妻にも同じことを尋ねる。すると彼女は、それが自分たちの死んだ赤ん坊の幽霊で、「なぜアグイーと言うのかといえば、その赤んぼうは生れてから死ぬまでに、いちどだけアグイーといったからなのよ」[11]と伝えるのである。
さらに、Dの情人の映画女優(Dは離婚した後に彼女と結婚する約束を反故にされていた)にも話を聞きに行くと、彼女は、「それで、わたし思うんだけど、Dちゃんは、赤んぼうの死んだ瞬間から、もう自分も死んだ人間のように新しい思い出はつくるまいとして、この現実の《時間》を積極的に生きなくなったんじゃない? それから赤んぼうのお化けにはどんどん新しい思い出をつくらせようとして、東京じゅうのいろんな場所で地上に呼びおろしているのじゃない?」[12]という仮説を述べる。
やがてD本人も、「空は死児等の亡霊にみち まばたきぬ」という詩句が含まれる中原中也の詩《含羞》の2節目とともに、空中の人間が描かれたウィリアム・ブレイクの絵が、アグイーの世界に通じていることを「ぼく」に教えてくれる。
しかし、その年のクリスマス・イヴの日、銀座から東京港に向かって「ぼく」とDの二人で歌舞伎座の前を歩いているとき、Dのもとにアグイーが降りてきた。それから、車道に、信号が変わってトラックたちがやってくる瞬間、Dは不意にそこに飛び出して烈しく跳ねられ、雪の中で無惨にも、「恐慌におそわれた鳩さながら数かずのジングル・ベルが飛びか」[13]うなか、血まみれになり、救急車に運ばれるが、あっけなく死ぬのである。彼がどうして突然飛び出して行ったのかは、わからない。それが自殺だったのかも判然とはしない。
それから10年後「ぼく」は子供に石を投げられる。石つぶてが右目に当たって、膝をつき、彼は、失明を感じる。まさにその最中、はじめて、「カンガルーほどの大きさの懐かしいひとつの存在が、まだ冬の生硬さをのこす涙ぐましいブルーの空にむかってとびたつのを感じ、ぼくは思いがけなく、さようならアグイーと心のなかでいったのである」[14]。
これまで散々、空を浮遊し、時に地上に降りることが語られつつも、「ぼく」には認知できないものであった、死児の霊としての怪物的存在アグイー。そのアグイーは、このように「無償の犠牲」をはらうことによってはじめて、わずかに一瞬、感じ取られるようなものとして、描かれている。
短篇「空の怪物アグイー」では、大江の息子、光と折り重なっているとはいえ、まったく別の、脳ヘルニアで死んだ子供のイメージが、動物ではなく、怪物として立ち現れる。それは、絶えず子を失った父親のもとを訪れ、身体的に激しい喪失をすることで、他者にも共有されうる幻想的な性格のものであるとわかる。
『個人的な体験』の鳥も徹底して海外に飛び立てないでいたが、大江の作品においては、飛翔してゆくのは、むしろこのような怪物的なイメージであって、あくまでも鳥は日常で地に足をつけたまま接触するものとして描かれている。
森のフシギの音楽とのシンクロニシティ
大江において、自分自身の家族の物語と重なるテーマは、とりわけ生まれ直しの主題とともに、『静かな生活』の中でも言及されていた長篇『M/Tと森のフシギの物語』(1986)で深められている。これは、大江を思わせる主人公が、四国の森の中で育つ中、祖母によって、谷間の村の昔話を聞かされてゆく物語である。大昔の歴史を語り聞かせるにあたって、祖母は、呪文のように、昔のことなればなかった事もあったことにして聴かねばならぬ、と繰り返し言い、そのたびに、主人公は「うん!」と元気よく答える。
この作品でも、「息子のなにより秀れた能力は、記憶にあります。幼児の頃、かれは五十種を超える日本の野鳥の声を覚えていたのでした」[15]と書かれている。ポイントとなるのは、光さんと呼ばれる主人公の息子が作曲した《Kowasuhito》というタイトルの曲が、森の奥に存在するという「森のフシギ」を体現しているのだと、主人公の祖母に体感されることである。
作品の現在時に光が作曲した音楽は、「森のフシギ」がならしているリンリン音楽を、まるで昔の子供が大怪音を楽しく聞いたように聴き取っていたのだと解釈される。彼が昔の子供たちと重ねられるのである。そして、それを聞くことは、「僕」にとっては魂を磨くために重要になるとされている。
この『M/Tと森のフシギの物語』では、殺されてもすぐに生んであげる、と言われていた亀井銘助の生まれ変わりとされた「僕」が、神話のような昔話と歴史をよりそわせながら物語ることを使命として引き受けていくことが、執拗に書かれている。それはそのまま、作家自身の生の使命に重なっている部分があると言える。
だとすれば、なんどもなんども、脳に腫瘍をもつ異常児が、生きたり、死んだりする物語がつむぎ直されていることもまた、そのような語り直しの使命に通じているだろう。しかし、そのように語り直される子は、あくまでも、実の子である光の存在の変奏になっているのである。
鳥として描かれる主人公の姿を、事後的に説明するかのように新しく言葉を紡いでゆくもう一人の別の子は、別の物語を紡いだとしても、決して訪れない。それはどうしてなのだろうか。似ているけれど、そのたびごとに違っている知的障害の子どもは、しかし、決定的に異なる存在ではないように思われるのである。
たとえば、先に見た『洪水はわが魂に及び』の主人公は、息子のジンが、いつも鳥の声のテープの後にその名を告げるように、世界の終わりが訪れたときに、世界の終わり、ですよ、と述べることを夢想しているシーンがあった。しかし、彼がそのように言う瞬間は決して訪れなかった……。
もちろん、諸作品に描かれていたように、その後、ゆるやかに、光をモデルとした子供たちは、十全ではないとはいえ、次第に言葉を使えるように成長はしてゆく。いくぶんかの違和感を湛えながらも、それこそ『静かな生活』では、イーヨーはたしかに会話をしている。しかし、そのように脳に大きな腫瘍を持って生まれた子供のモチーフが変奏されるなかで、きわめて特異的かつ重要に思われるのは、鳥の鳴き声を息子と共に聞く父が、その鳥の鳴き声のあとで、自分のその子供が声を発するのを待機する、待っている、その祈るような時間の尊さが根底にあることだと思うのである。
*
これまで、鳥に着目して、大江健三郎のいくつかの作品を読み解いてきた。そこから、ささやかながら垣間見えるのは、自然豊かな緑の森のなかで、鳥たちが囀るさまざまな音風景だった。しかし、種名を書き分けながら鳥が描かれるとき、さらにはその鳴き声にともに耳を傾けてゆくとき、そこに透けるように浮かび上がってくるのは、聴覚の鋭敏なイーヨーそのひとだけでなく、イーヨーにさまざまな鳥の声の録音を聴かせ続け、共に途方もない時間、鳥の声を聴き続けたであろう作家の生である。
浴びせるように鳥の声を聞かせる時間を積み重ねた末に、母親の言葉にも反応しなかった子供から生まれでた、はじめての自発的な言葉が鳥の名であった驚異は、たまさかの偶然の瞬間とも、作為による結果であるとも言い難い。ただ、この出来事からは、長きに渡る待機そのものが、祈りの時間であったことをまざまざと感じさせられ、そのプロセスが、事後的に認識されるものであるとはいえ、祈りの時間を積み重ねていた作家の生をすでに示しているように思われるのである。
そして、イーヨーに寄り添ってみることで、結果としては、大江の描き出す「森のフシギ」という非言語のなにか異界めいたモチーフが、具体的な地に足をつけた営為としての音楽の創作によっては、じゅうぶんに時を隔ててしまっても、それでもなお、迫りうるものであることが、静かにそっと差し出されていると気づかされるのである。
時を超えて異なる世代の人間が交換され、生まれ直してゆくSF的なイメージが介在しつつも、そのような奇跡的とも思われるときの訪れは、鳥の声を聴き続ける態度に支えられて、書き継がれ、描き直されている……。
そのように、イーヨーと共に、謎めいた森のフシギに迫ってゆこうとすると、読者であるわたしたちもまた、もしかすると、祈るように鳥たちの声を聞くことを、はじめられるようにさえ思われるのである。
[1] ほかに『不満足』(1962)で、語り手の友人が鳥という名前をあたえられている。また、『万延元年のフットボール』(1967)では、主人公の弟の名前が鷹四と鳥にちなんだ漢字を入れられている。大江の作品自体で生き物としての鳥そのものが主題になっているものとしては、たとえば初期短篇「鳩」(1958)や「鳥」(1958)が挙げられる。
[2] 大江健三郎『個人的な体験』新潮文庫、1981年、139頁。
[3] 同上、110頁。
[4] 同上、111頁。
[5] クイナは水鶏と書かれるように、水辺の近くに住まっている。軽井沢に現れるクイナについては、寺田寅彦のエッセイ「軽井沢」(1933)に、至るところでウグイスが鳴くだけでなく、池や蘆原、山裾でクイナが鳴く様子が描かれている。
[6] 大江健三郎「火をめぐらす鳥」、『大江健三郎自選短篇』岩波文庫、2014年、820頁。
[7] 大江健三郎『静かな生活』講談社文芸文庫、1995年、216頁。
[8] 伊丹は文庫版の解説である「「静かな生活 映画化について」のなかで、高校時代、選択クラスで一緒だった大江と連歌をつくったりしたエピソードを明かしながら、「その頃大江君が作った詩の中に「森は暗い輝きに満ち」という一行があって、その強いイメージ喚起力にひどく感嘆したことを覚えています。森のテーマはその頃から彼の中に芽生えていたわけです」と語っている。同上、292頁。
[9] 同上、117頁。
[10] 大江健三郎『空の怪物アグイー』新潮文庫、1972年、186頁。
[11] 同上、191頁。
[12] 同上、199頁。
[13] 同上、211頁。
[14] 同上、216-217頁。
[15] 大江健三郎『M/Tと森のフシギの物語』岩波文庫、2014年、380-381頁。