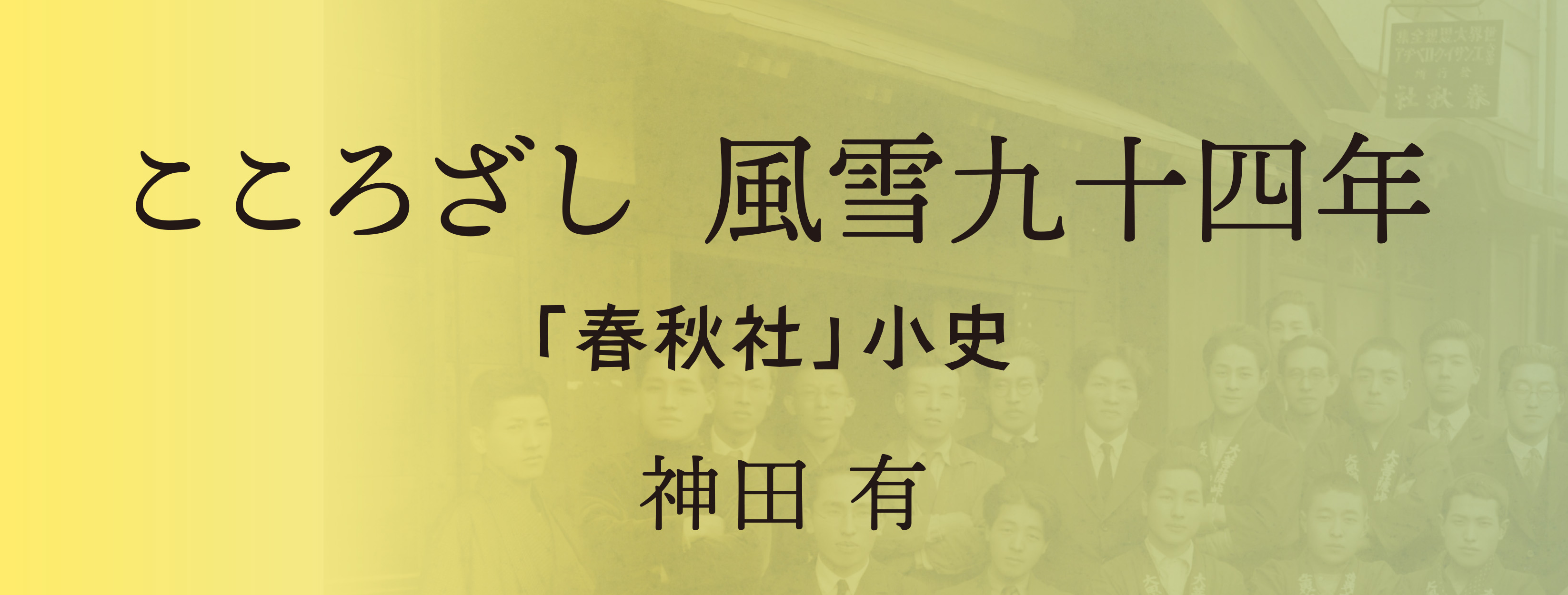「春秋社」小史3
NHK総合テレビ「ファミリーヒストリー」(2020年4月27日放送)にて明かされた、いま最も注目される講談師・神田伯山(本名・古舘克彦)氏と小社との意外な関係。創業者の神田豊穂を祖父にもつ小社現社長・神田明と、同じく豊穂の孫である神田有氏(この連載の執筆者)も番組内に登場。神田豊穂が伯山氏の曽祖父にあたる古館清太郎を誘って春秋社を立ち上げたことが語られましたーー
この記事は、2012年にPR誌『春秋』にて連載された、春秋社の歴史をふりかえるエッセイに加筆修正をしたものです。2018年に創業百年を迎えた小社の草創のときを今あらためて振り返ります。
(六)“十五年戦争”と春秋社
日中戦争以後、思想統制は公然化していく。昭和十二年(一九三七)八月「国民精神総動員実施要項」が閣議決定される等、日本はにわかに暗い時代に突入するのだった。
当時、江戸川乱歩はこう書いている――。
昭和十四年にはいってからだが、戦時統 制による出版物検閲が実にきびしくなり、 毎巻むやみやたらに書き替えを命ぜられた。当時は事前検閲の制度があって、内務省だ ったか警視庁だったかに、原稿又はゲラ刷 りを提出すること、風紀上面白くない個所 に赤線を引いて返される。出版者はそれを作者に届けて、その個所の書き替えを頼むという慣わしであった。
ところが私の場合は一行や二行ではない。一頁二頁にわたって全文書き替えを命じら れる。その検閲は既に組版を終ったゲラ刷 りで受けていたものだから、赤線の個所を 削除すると、そのあとを全部組み替えなけ ればならないので、赤線の行数に合わせて、別の文章を書かなければならない。それで、一応は元の意味と似た文章を書いて渡すの だが、二、三日するとまた戻ってくる。全 く別な意味のさしさわりのない文章にしてくれ。“今日はお天気がいい”という様な無意味な文章にしてくれというのである。
それでは前後が続かないので、そんな無茶なことを注文されるなら、選集の続刊をよしてしまおうと、私は怒ったが、出版社が、「まあまあ」というので、仕方なくまるで前後のつづかない文章を書いて、やっと検閲を通過したことが、殆ど毎巻であった。石川達三の『生きている兵隊』が発禁になったし、心ある作者達は中野重治の言葉を借りるなら、奴隷の言葉で書くしかなかったのである。
文学や思想の刊行物ばかりではない。昭和十六年(一九四一)八月、文部省は、学生・生徒の映画・演劇は土曜・日曜に限ると「厳達」したし、九月には講談落語協会は、艶笑物、博徒物・毒婦物・白浪物の公演を禁止した。
こうした状況は当然、春秋社の出版物にも影響してくる。
昭和十三年(一九三八)以降の出版物を見ると、原四郎編、『思いでの戦場――戦傷将兵の手記』、石丸藤太『共産ロシア抹殺論――支那事変後の世界』、沢田謙『叙伝 汪兆銘』、宿利重一『旅順戦と乃木将軍』等が見られる。
ここで特記すべきは、昭和十六年に出版された『東辺道』で、これは稀覯本である。著者の森崎實は、当時、満州新聞社の編集局次長兼政経部長で、記者としての技量、特に堅実な経済論説には平素から定評があった。
「東辺道」とは、中国、東北地方南部、鴨緑 江の北側、通化を中心とした広大な地域である。大日本帝国にとって、この地域に存在する膨大 な地下資源は垂涎の的であった。このため、国策会社、東辺道開発株式会社を設立。その開発調査に当って来たが、森崎は「東辺道」の沿革 から説き始め、自ら「東辺道資源調査班」を組織し、現場・現物主義でこの作品を書き上げている。
当然、当局の評価は高く、関東軍報道班長の長谷川宇一、国務院弘報所長の武藤富男が序文を寄せている。
私は、少年時代の数年を東辺道通化県で過ごした。東辺道通化県に連なる山々からは連日、ダイナマイトによる発破音が鳴り響き、石炭鉄鉱石を満載した貨物列車が日本本土を向け出発していくのを見送ったこともあり、本書はたいへん懐かしいものがある……。
戦況の悪化に伴い国民の疲弊はますます募っていくが、それでも出版人たちの思いは熱かった。ところが、意欲的な活動を展開しようと思うものの、肝心の用紙が入手できなくなってしまう。各社はなんとか、用紙を調達しようとするが、戦争末期にはいよいよ配給制度という事態に直面するのであった。
春秋社は、豊穂が昭和十六年(一九四一)八月に逝去。龍一、澄二、貢の三人の息子は全員応召され、留守居をおく状態で、前述したように、東京大空襲によって社屋等、出版に関わるすべての財が灰燼に帰してしまった。
中国戦線から復員した龍一社長は、社屋を日本橋から現在地(千代田区外神田二丁目十六番地)に移し、戦友の四、五人を入社させ、出版活動を開始した。
そのなかに一橋大学出身で、教授陣と昵懇の者がおり、一橋大学の経済学などのテキストを春秋社が一手に引き受けることになる。戦後、またたくまに経済・経営・会計の出版社として一時期をなした。一橋大学のOB(現在は八十代)たちからは「そういえば経済学のテキストはほとんどが春秋社だったなあ」との回想の声しきり。
かくて、経済部門と戦前からの仏教・哲学・思想書を中心として、やがて、井口基成校訂の
「世界音楽全集 ピアノ編」などが加わって充実の様相を呈していくのであった。
(七)再び、祖父・豊穂のこと
豊穂は、明治十七年(一八八四)三月四日、 茨城県麻生町で神田民衛の三男として生まれた。民衛は麻生藩の家老職を勤めた。
麻生藩は潮来(いたこ)からほど近いところにあり、一万石の小藩、最後の殿様は新庄直敬(なおのり)で、後、子爵となる。
明治維新の「廃藩置県」「藩籍奉還」により、武士階級の生活は大きく変わる。豊穂の父、民衛は文才があり、維新後上京し、著述劇作をもって生計を立てていたが、病弱のこともあり、早世する。なお、その著作は昭和初期まで、古本屋の店頭に並んでいたという。
長兄吉哉も父民衛と同じく早世し、次男は神田家を離れ、海事に従ったため、豊穂は母親と共に親戚の家に居候して過ごし、生活は困窮を極めたらしい。
豊穂は、これでは先行きが立たぬと一大決心して上京。横浜で丁稚奉公をし、苦学の末、麻生中学を卒業。「わんや」で出版業を身につけ、春秋社を創業した。
豊穂は読書を好み、小中学校のころから、ひそかに文学をもって世に出ようとしたこともあった。当時、神田石秋、神田一路、神田意智楼などの名で「文芸倶楽部」や「新潮」などに文章を発表したこともあったが、〝文才無し〞と自覚したのか、以後は筆を捨て、出版事業活動に専念する。
豊穂は昭和六、七年頃から、社長職を長男の龍一に委せ、みずからは会長のような形で、社屋の四階に陣取った。社員は混乱を避けるため、豊穂のことを“大神田さん”と呼んだ。
私の母によると、豊穂の一日は次のようにして始まる――。
お茶を飲んだ後、新聞を読み出す。当然のことながら、まず出版広告欄に目をやる。
「講談社から○○が出ています」「新潮社から△△が出ています」……
そんな社員の声もよそに、他社の新刊動向をしっかり見据える。そして、政治面、経済面、社会面へと目を転じるのだが、記事のおかしな表現に気づくと、「うん? この文章はおかしいな、ちょっと調べてみろ」と。さっそく辞書で調べてみると、まさに指摘通り、豊穂が正しいこともたびたびだったという。
こうした日課のあと、著者との打合せや編集者とのやりとりが続く――「うんそうか、よし、わかった。それでは葛生(くずう)君、印刷屋へ電話だ。それから久米(くめ)君ちょっと……」。
こうして滞りなくスムーズに事が運ぶ。
ある社員の回想によると――「とにかくズバリと会話の脈絡を継ぎ、次の段階へ飛躍して、もう他の何ごとかを思案・計画している。こういう瞬間の連続が、私の接近し得た大神田さんの日常であった……」。
当時、『一茶の種々相』を著した川島つゆは、社内で仕事をする豊穂の姿をこう描いている。
上衣を脱ぎワイシャツの袖をまくり上げて、若い者と一緒に書物をいじっていられた。「私が神田です」と云われた時には、ガシッと大岩に直面した感じであった。身長も二倍も大きく感じられた。次には大島の着流しでドカッと椅子に座っていたが、両肩に盛上がる肉の隆起と、にらみつけられるようなこわい眼付は、突然闘える大蟇(おおがま)を彷彿とせしめた。そして、頭から「俳人とクリスチャンくらい本を読まないものはありませんね」と吐出すようにいう人であった。(読まない奴と云いたかったに相違ない)。眼付のこわかったのは、当時既に視力が鈍っていたのを、無理に見ようとするためであったと思われる。
各界からの来客も多く、母によるとアナーキストとして名高い石川三四郎とはウマが合ったらしく、時折、石川が来社しては懇談していたという。
また豊穂は「すごく頭の切れる人だったが、超ワンマン」ゆえに仕事上の対立甚だしく、社を去った人は数知れなかった。結局、最後まで親しくしていたのは謡曲の関係を除けば、温厚な柳田泉先生と鷲尾雨工のお二人くらいだったのではないだろうか。
豊穂は昭和十六年(一九四一)八月、糖尿病が悪化、帰らぬ人となる。五十七歳であった。(了)
(『春秋』2012年7月号)