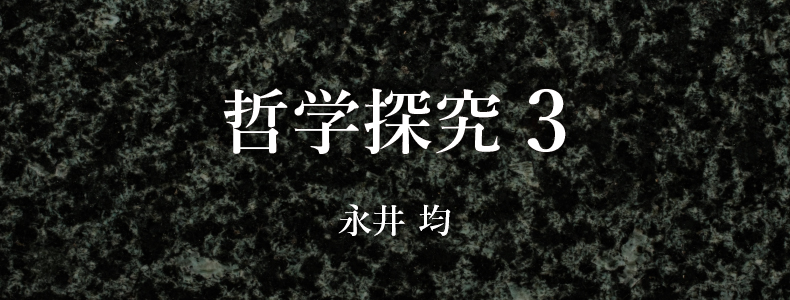第1回
この連載は書籍化されました。→永井均 著『独在性の矛は超越論的構成の盾を貫きうるか 哲学探究3』
はじめに
哲学探究3の連載を始めるにあたってまず、今回の連載がこれまでとどう違うかを述べてみる。
今回も主題は前二回とまったく同じである。まったく同じ問題を、またまた最初の第一歩から、新たに考え直すのである。私はこの問いを、少なくとも五十年以上、捉え方によってはすでに六十年以上も考えてきたのだが、ここでまた新たに最初から考え直さねばならない。だれも気づいていないように思われるが、この問いは恐ろしく奥が深い。これまでも今回も、私がその首根っこをつかまえることに成功しているかどうか、それは心もとない。この問いに、私がつかまえ損ねているさらに奥があることは疑う余地がない、と私は感じる。しかし私自身は、私がかろうじてつかまえているかぎりで、この問いをさらに深く探るほかには何もできない。
この問題に関して、私としては毎回、まったく新たな見地を切り開いているつもりなのだが、横から見ている人には、毎回ほとんど同じことを言っているように見えるらしい、ということに最近気づいた。考えてみれば、それは当然のことだろう。刻苦勉励の果てにたどり着いた見地であっても、もしその見地がそれ以前からすでに存在していた見地との自然な繋がりのうちに位置づけられていたなら、そこで生成した変化は外からはほとんど見えないはずだからだ。同じことを繰り返しているように見えても、その同じさはじつは今回新たに生成した新しい同じさなのだが、その新しさはすでにして一つの同じさの内に組み込まれて見えなくなっているはずなのだ。私のこれまでの議論も、そのようにして徐々に生成してきたと思う。これから毎回、これまで言っていなかったことを言うつもりなのだが、多くの継続的読者には、ほとんど同じことを言っていると感じられるであろう。
哲学探究の1と2は、連載時にほぼ完成形が実現することを目指して書かれていた。今回はこれとは異なり、かなり覚え書きに近いことが、順不同に書かれる箇所が出て来るはずである。したがって、正式に出版される時には、連載時とは異なる秩序のもとに、新たな形で再編成されることになると思われる。連載中にそういう組み換えが必要になる場合の便益を考慮して、今回は章わけ(や節わけ)のほかに、段落番号を振っていくことにした。
Ⅰ いかにして心や意識は他の諸々の存在者と同種の並列的存在者となりうるのか
1 人間が人間から生まれてくる。そのことに不思議はない。それは生物学的理由による。どうしてそうなっているのかも不思議だ、と感じることは可能だが、もしそれを不思議とみなすなら、その種の不思議さは森羅万象に及ぶことになるだろう。どのような法則によって説明されても、なぜそうなっているのかはやはり謎であり、かりにより基礎的な物理法則によって説明可能であっても、基礎的な物理法則がそうなっていることには、最終的にはもはや理由はない。事実そうなっているというだけである。それを不思議なことといえばいえる。
2 もし、そこに不思議を感じるなら、そもそも法則性というものがあるということに不思議を感じてもよいだろう。なぜ世界には一般的な法則性というものがあり、ものごとはすべてそれに服するのだろうか。いや、それどころか、ものそれ自体が、一般的な法則に服して、はじめて可能になる。たとえば、土とか石とか鳥とか雨とか風とか…。そういう一般的な種類というものがあって、あらゆるものはその一例である。さらにそれらに、丸いとか冷たいとか白いとか…一般的な属性があって、さらに動くとか縮まるとかぶつかるとか…一般的なことをする。ここでもまた、一般的な種類がまずあって、あらゆることはその一例なのである。森羅万象がそういう構造を体現しているとしたら、それはたしかに不思議なことだ。なぜ、世界はそのように出来ているのであろうか。
3 さらに、それらのもののうちのある種類のものには、心とか意識とか呼ばれるものがそなわっている。この点はどうだろうか。これがとりわけ不思議だと言う人も多い。しかし、ある種のものには必ず心や意識があるなら、それはこれまで述べてきたふつうの不思議さと同じだろう。なぜそうなっているのかはわからないとしても、その点についてなら、究極的にはすべてのものごとがそうなのだから。
4 しかし、それらのもののうちある種類のものには心とか意識とか呼ばれるものがそなわっている、とはそもそもどういうことなのだろうか。それはたとえば、すべてのカラスは黒いといったような仕方で、ある種類のすべてのものにそなわっているのだろうか。そうではないだろう。心や意識のそなわり方はそのような備わり方とは違う特徴を持つであろう。すべてのカラスが黒いことは、カラス(黒さとは別の特徴によってカラスと分類されるもの)たちを見ていくことによってそうだと(そうでない場合はそうでないと)わかる。しかし、心や意識は違う。そのように見ていっても、外から観察するだけではどんなによく観察しても、心や意識が本当にあるかどうかはわからない。そのうえ、内にもぐる方法はそもそも存在しない。
5 外から観察するだけでは本当にあるかどうかはわからないというのは、その逆に、内側から完璧にわかってしまう事例が一つだけ存在しており、あくまでもそれとの対比においていわれることである。それ以外の意味においてなら、必ずしもわからないとはいえない。そして、完璧にわかってしまう事例が一つだけ存在しているとは、つまり、自分というものが存在しているということである。自分が存在するとは、つまりそういうものが存在するということであって、それ以外のことではありえないだろう。心や意識という存在の意味を理解するには、この事実を避けて通ることができない*。
*その点で、心や意識はそもそも他の存在者と異なる存在の仕方をしており、していざるをえない、ということにここで注目していただきたい。
6 だから、問題をいま論じてきたのとは逆方向から、すなわち自分とはそもそも何かという問いの方向から考えてきた場合にも、それもやはりここで捉えたこの事実によって答えられるほかはないはずだ。なぜか現に一つだけ、むきだしの心が、むきだしの意識が、存在しており、それがすなわち自分なのだ、と。そして、なんと実のところは、すべては、すなわち森羅万象は、その一つだけの例外的にむきだしになっているその心から始まっているほかはない。その心以外のすべてのものごとも、だからたとえば他人の心は見えない(けれど自分と同じように存在するだろう)といったようなことも、それによって観察され、理解され、確認される*ほかはない。むきだしの心とは、同時に、すべての出発点であるような心でもあり、もしそれがなければすべてはないのと同じことであるような、特殊な心である。
*とはいえ、むきだしの心、むきだしの意識のむきだし性を際立たせる典型例は、観察するとか理解するとか思考するとか……ではなく、むしろそこはかとなく感じられる感じや気分や情緒のようなものであるだろうが……。
7 しかしそのように、なぜか一つだけむきだしの意識が存在していて、それが心や意識の典型例なのだとすると、むきだしでないほうの意識はどのようなしかたで存在できるのだろうか。いや、それ以前にそもそも、実のところはそのむきだしの意識にほかならないほうの人も、その逆にその心は徹頭徹尾隠されていて見えないほうの人も、ともに人という同じ種類にくくられ、ともに心や意識という同じ種類のものを持つとされるのはどうしてなのであろうか。ここでは、一般的な種類がまずあって、すべてはその一例である、というあり方が最初から成り立ってはいないのだ。だとすれば、どのようにしてこれほどにも違うものが同じ一つの種類にまとめられ、ここにもまた「一般的な種類がまずあって、すべてはその一例である」というあり方が成立するに至ったのであろうか。
8 この問いに答えようとするまえに、ひょっとするとこれこそが答えになるのかもしれないのだが、まずはこの問いそのものに二つの理解の仕方がある、という点を指摘しておかねばならない。問いに二つの理解の仕方があるというより、そこに含まれている「自分」に二種類の意味がある、といったほうが適切かもしれないのだが*。ともあれ、問いに答えることよりも問いそのものの持つこの二重性を明晰に理解することのほうがはるかに重要である。これまでなぜ多くの哲学者たちがこの点を明晰に議論してこなかったのかはただ不思議というほかはない。
*もしかすると段落7を読んだときに、その分類の仕方がすでにして理解不可能だと感じた方がいるかもしれない。「そのむきだしの意識にほかならないほうの人」と「その逆にその心は徹頭徹尾隠されていて見えないほうの人」という分類が実体的に存在するわけではなく、どの人もみな自分にとっては前者であり、他人にとっては後者であるだけではないか、と。その問題についてはこれからすぐに論じられていくことになるが、そのように感じた方にとっては、「ともに人という同じ種類にくくられ、ともに心や意識を持つ」という事態は、すでに問いの理解の前提として働いていたことになる。いま問われようとしているのは、そういう理解の仕方の成立の仕組みそのものなのである。
9 いま出されている問いは、「なぜか一つだけむきだしの意識が存在していて、それが心や意識の典型例なのだとすると、むきだしでないほうの意識はどのようなしかたで存在できるのだろうか」という問いと、「そのむきだしの意識にほかならないほうの人も、その逆に意識は徹頭徹尾隠されていて見えないほうの人も、ともに人という同じ種類にくくられ、ともに心や意識を持つとされるのはどうしてなのか」という問いである。こうした問いを提出する以上、書き手である私はこの問いをその読み手と共有できるものとして提出していることになる。この問いは、そう解された時にも、十分に有意味な問いとして理解されうるだろう。その場合、この問いの中の「むきだしの意識」とは、「なぜか一つだけ」と言われているにもかかわらず、私と読者の方々のそれぞれの「むきだしの意識」であることになる。少なくとも問いが伝達されるその現場においてはそうであらざるをえない。とすると、「なぜか一つだけ」とは、それぞれの人にとって一つだけという意味になり、そうである以上、じつのところは一つだけではない、ということがすでに認められていることになる。ここで重要な点は、そういう意味に取られてもこの問いは問題なく成立する、ということである*。
*このことは不思議なことのように思われるかもしれないが、いやたしかに不思議なことではあるのだが、ごく普通に起こっていることでもある。もしそうでなければ、たとえばデカルトが語った「我あり」の真理性・確実性を、『方法序説』や『省察』の読者が受け入れることは(それどころか意味を理解することも)できなかったはずだからだ。デカルトは森羅万象を疑って、最後に、いかにしても疑うことができないこととして、いま疑っている(限りでの)私の存在の確実性に到達した。だから、その「私」とはもちろん、そのとき森羅万象懐疑を実践していたその「私」だけであるはずだった。そのことを強調するために,『方法序説』において彼はわざわざ自叙伝的な叙法を採用もした。しかし、当然のことながら、彼の実践が哲学的(に意味のある)議論として理解されるには、それはだれにでも当てはまる一般的な自己意識的自我についての議論として理解されるほかはなく、実際そう理解されてきた。驚くべきは、この移行はごく自然になされた、ということである。そこに移行が介在すること自体がとくに問題とされることさえなかった。このデカルト的「我あり」の伝達という特殊な場面で起こったことは、われわれの日常的言語的伝達の前提となっていることなのである。これはやはり驚くべきことと言わざるをえない。
10 なぜ問題なく成立するのだろうか。それは、それぞれの人にとって「なぜか一つだけむきだしの意識が存在している」と考えられている*からだろう。意識というものは(意識というものの側からいえば)そのような仕方でしか存在できない**からだろう。「それが心や意識の典型例なのだとすると、むきだしでないほうの意識はどのようなしかたで存在できるのだろうか」という問いも、「そのむきだしの意識にほかならないほうの人も、その逆に意識は徹頭徹尾隠されていて見えないほうの人も、ともに人という同じ種類にくくられ、ともに心や意識を持つとされるのはどうしてなのか」という問いも、この水準で問題なく成立する。不思議なことではあるが、それがわれわれが生きている世界の実情なのである。
*「それぞれの人にとってなぜか一つだけ……」という表現がすでにある種の矛盾を含んでいることに注目してほしい。じつは矛盾ではないとすれば、ここには二つの異なる階層で成立する事象が合体しているのではないか、と疑ってもらってもよい。
**なぜそのような仕方でしか存在できないのか、そのことの不思議さをここで感じていただきたい。それを前注で提示した問題と繋げていただけたらなおよい。
11 しかし、いうまでもないことではあるのだが、初発には、字面はまったく同じでも、これとはまったく異なる問いが存在していたはずだ。重要なのはそのこと、すなわち、じつはここには異なる二種類の問いが重なって存在している、ということである。そのことは、いまそう解釈されたような問いの水準においても、そこに内在する矛盾として、すでに表れていた。なぜか一つだけ例外的にむきだしの意識が存在しているという事実が現に与えられているとき、それは、それぞれの人にとってそうであるという意味であることはありえない。もし本当に、なぜか一つだけ例外的にむきだしの意識が存在しているという事実が与えられている! という驚嘆(タウマゼイン)を感じたのであれば、それは、どうしたって、それぞれの人にとってそうであるという意味であることこそを断固拒否していなければならないはずだからだ。そうでなければ、そもそも「なぜか一つだけ……」などと思えるはずがないだろう*。
*だから課せられた困難な課題は、この事実を完全に保持したまま、そのこと自体を一般化して、「それぞれ」の視点へとそのまま拡張することである。(驚くべきことに、デカルト的「我あり」に関連させて述べたように、われわれはこのとても不可能そうに見える課題の達成にすでにして成功してしまっているのだ。)
12 その見地に立ってみよう。この見地はどのような見地であろうか。最も重要な事実は、この見地の成立にとっては、おそらく他の人々も皆それぞれにおいては「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしているはずだ、とか、もしかしたら他の人々もじつは皆「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方で存在している(あるいはしていない)のかもしれない、とか、その種のことを考慮してみる*余地は少しもない、ということである。他の人々もまたそういうあり方で存在するという可能性はまったくない、一〇〇パーセントない、のだ。理由はきわめて簡単で、事実としてそうでないということが、その事実だけが、ここで問題にされていることだからである。事態はすでにして完全にあからさまになっており、結論はもう出てしまっている。その意味では、これから調べてみるべきことは何もなく、「おそらく」とか「もしかしたら」といった考慮はそもそも働かせる余地がない。そういう考慮をはたらかせるべき問題もまた別にあるかもしれないが、それが問題ではないということこそが、この見地を成立させている。ここでブレないように注意しなければならない**。
*その種のことを考えることは、「他我問題」と名づけられた哲学界公認の問題設定であった。他我問題は、他人はもしかしたら意識のないゾンビかもしれない(そうであったとしてもわからない)という懐疑論的問題意識から出発して、他人にも自分と同じように意識があるといえるための根拠を探っていく、という問題設定に立つ。この段階ではまだ、それはそれで意味のある問題設定だと考えていてよいのだが、ともあれそれとは(一見似て見えても)まったく違う問題があることをここで見て取ることが肝心である。
** このことは、『世界の独在論的存在構造』の第7章では、「中心性と現実性の分離」問題として説明されている。同書の第2章で導入されている、関与(寄与)成分と無関与(無寄与)成分の対比も、本質的にはこれと同じ問題である。そこでの用語を使って表現するなら、なぜか現実にただ一つだけ存在しているむきだしの心は、そのむきだし性は、世界の実在的なあり方には少しも関与(寄与)していない、すなわち実在していない、ということになる。(なぜか現実にただ一つだけ存在しているなどという事実はだれにも認めてもらえない――どころかそんな事実は本当に(リアリー)存在しない――ことからもこのことは明らかだろう。)
13 実はまた別の問題なのではあるが、現象(appearance)と実在(reality)とを区別して前者の特異性を際立たせる際に強調される事柄が、そのある側面において、ここで論じられている問題に似ている。たとえば、ある壁が黄色く見えたなら、その壁がじつは(in reality)は白かろうと青かろうと、だからといってじつは黄色く見えていないなどということにはならない。現象としての黄色さにはその種の「じつは性」がそもそもない(そのことを現象と呼んだのだから)から、黄色く見えれば黄色で、それがじつは何色に見えているかなどという問題は存在しない。ある物を口に入れてなめたら甘く感じられたなら、それがじつは辛いものであろうと苦いものであろうと、だからといってじつは甘く感じられていないことにはならない。甘く感じられれば甘いのであり、それで終わりである。
14 ここで論じている問題は、いま(直前の段落13で)説明した客観側で成立する現象性問題の主観側バージョンであると見ることもできるものだ。その見方に立った場合、これもまた徹頭徹尾現象性の問題なのだから、壁がなぜか現に黄色く、味がなぜか現に甘いのと同様に、こいつ一人だけがなぜか現に「一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」なのである。その水準で起こっていることそのものを、そのまま捉えることが重要である。この水準においては、実は他の人々も……という問題はそもそも存在しない。ある壁は実は白かろうと青かろうと黄色く見えればもう黄色く、ある食べ物は実は辛かろうと苦かろうと甘く感じられればもう甘いのと同様の意味において、実のところは他の人々も「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしていようと実のところもしていなかろうと(そういう問題もまた存在しているとしても)、その種の「実は(リアリ)」性(ティ)の水準の問題とは関係なく、現に「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしているのはもうすでにその一人だけなのである。繰り返すが、この水準で成立している事実をそれ自体として取り出すことが重要だ。なぜなら、たくさんの人間たちの中に私である(という通常とは違うあり方をした)人間が存在しているという事実は、この水準で成立する事実でしかありえないからである。多くの哲学書がなぜかそうしてきたように、この水準を取り逃がして早々に別の水準に問題を移してしまえば、おそらくわれわれにとって最も重要な問題の存在が見逃されてしまうことになるだろう。
15 ここで、多少先走りの感もなくはないが、ある重要な指摘をしておきたい。現に黄色く見えれば黄色く、現に甘く感じられれば甘い、という問題と、現に「なぜか一つだけ存在するむきだしの意識」であれば現にそうなのだ、という問題を同型と見る場合、どちらにも潜在的に他のあり方との比較が介在している、という点にまずは注目してもらいたい。前二者の場合は、他の諸々の色ではなく黄色い、他の諸々の味でなく甘い、であり、後者の場合は、他の人々ではなくこの人だ、である。どちらにおいても、ただ単に、とにかくこれだ、と言っているのではなく、あらかじめ可能性の領域を提示したうえで、これら(が可能なのだが)ではなく現実にはこれだ、と言っている。つまり、可能性の空間を前提として、そのうちのこれが現実だとされているのである。
16 ということはつまり、前者においては、現実に見えるのがもし黄色ではなく茶色であればそれが端的な現実となり、現実に感じられるのがもし甘さではなく酸っぱさであればそれが端的な現実となる、ということはすでに前提されており、後者においては、現実になぜかむきだしの心として存在するのが永井均の心ではなく安部晋三のそれであれば、それが端的な現実となるということがすでに前提されているということである。そうしたことは前提されたうえで、それはそうなのだが、本当の現実は、つまり現実の現実は、なぜか黄色く、甘く、永井均である、というように。
17 ここには「現実」の二層性が現れている。現にこれだ、現にこれであることは端的に与えられた事実そのものだから(そういうものとしては)否定しようがないのだ、と言っているにもかかわらず、しかしもしこれではなくあれであったなら、もしそちらが現実であったならば、その時はそちらが否定しようがないことになるだろう、ということも同時に言われていることになるからだ。しかし、もしそうだとすると、この否定しようのなさの根拠はどちらにあるのか。ここには根拠の二重性が生じている*。
* この根拠の二重性にかんしては、『世界の独在論的存在構造』第4章のルイス・キャロルのパラドクスにおけるアキレスと亀の対立を思い出していただきたい。これはつまり、端的な現実性は言語で表現されるかぎりどこまでも「可能な「端的な現実性」」として累進していかざるをえない、という問題なのである。
18 しかし、注意せよ。その問題のもつ意味は色や味に関する前者の場合と〈私〉に関する後者の場合とでは根底的に異なっている、ということに。前者の場合、ここは現に黄色く見えそこは現に茶色く見える、あるいは、こちらは現に甘く感じられそちらは現に酸っぱく感じられる、といった複数の事実の共在が問題なく可能である。のに反して、後者の場合、なぜかただ一つむきだしの心が存在しており、それが現に永井均のそれであれば、それがすべてでそれで終わりである。その事実と並んで、もうひとつの現実にむきだしの心が存在することはもうできない。他の人々もまたその人自身にとってはそれぞれ現実にむきだしの心であるはずだという話は、まさに前段落で示した二重性を使わなければ成り立たない話なのである。その種の並列性はこの二重性(多重性)を使って作り出すほかには作り出す方法がない。この根底的な異なりとその平準化こそがこの問題のキモである*。
*もしここで、たしかに後者はそのようにしてしか同じ平面での複数化ができないという点は認められるが、それはじつは前二者のような問題にかんしても言えることなのであって、前二者のような問題もまたじつは後者の問題の一部分でしかありえないのではなかろうか、と問われるなら、それはその通りである。ここは現に黄色く見えそこは現に茶色く見えるとか、こちらは現に甘く感じられそちらは現に酸っぱく感じられるといったことは、実のところは、なぜかただ一つ存在するむきだしの意識においてのみ言えることだからだ。そのことがすべての人々の心に一般化されるのは、この場合もやはり、ここで提示された二重性(多重性)が発動することによってであり、それ以外ではありえない。そういう意味では、あるいはそういう仕方で、この二つの問題は重なっており、それなしには段落13で論じたような現象の確実性も成立しえない。
19 しかし、われわれはこの二重性(多重性)に基づく並列的世界像を、そうとは気づかぬほどに自明のこととして前提して、通常の生活を営んでいる。哲学上の他我問題のような極端に懐疑論的な問題設定がなされる場合でさえ、この二重性(多重性)に基づいた並列的世界像は(なぜかそこは懐疑されずに!)前提され、一般的な自我と一般的な他我とのあいだに介在する認識論的問題(他我認識あるいは他我構成という一般的な問題)が論じられるのが常である。しかし、なぜそんなことを前提してよいのだろうか。また、なぜそんなことを前提することができるのだろうか。
20 この問いに現在のわれわれが――すなわち現在のわれわれの世界像の内部で――答えようとするなら、それが事実だからだ、と答えるほかはない。すなわち、そんな問いはそもそも存在しない、と。これは存在してはならない問いなのである。われわれの言語的世界像は、初発にこの構成が成立することによって成り立っており、その成り立ちの仕組みそのものを問うことは、たとえば「形而上学の排除」の名のもとに、いわばイデオロギー的に禁じられているのである。
21 だが、言語的世界像とは何か。それは、この二重性(多重性)を平準化して一重と見なし、そこに感覚(色や味のような)や感情(悲しみや怒りのような)や物体(石のような)や出来事(雨のような)のもつ並列的な在り方と同じ種類の並列的な在り方を仮構することによって成り立つ、きわめて独特の世界像である。主として様相、人称、時制の三つのカテゴリーが、この平準化を成立させており、われわれの知りうるすべての事象はその上に構築されている。われわれは例外なく、それに依拠して森羅万象を理解し、ものごと一般を処理している。これは端的な事実に反して構築された、いわば作り物の世界像なのではあるが、われわれは言葉を使用するかぎり様相、人称、時制に依拠せざるをえないのであるから、そのことを言語的に表現する方法を持たない。
22 この世界像の内部では、なぜかただ一つだけむきだしの意識が存在しているという端的な現実性が否定されるのではなく、最初から「可能な「端的な現実」」として理解されることになるのだ。同じ一つの現実世界の内部で理解されるとはいえ、だれかの語るその種の端的な現実性は、もし他者に理解されたなら、最初から一つの「可能な「端的な現実」」であるほかはなく、それゆえに翻ってまた、それを語る者自身も、そのように変換されて理解されることを最初から知っていなければならないからである。言葉が理解されるとはそういう仕組みが働くということなのであり*、われわれは自分自身にかんする思考でさえもそのように言語的に理解することを教えられたのである。言葉は、本質的に他者とともに理解し合うものであり、世界の、他者によってもまた理解可能な側面を切り取って成立するものだからである。他者ではない、言葉を発する側の主体も、そのようにいわばむきだしの直接性を取り除いて、事態を平板化して(つまり亀的に)も理解できるのでなければ、言葉を操ることはできない。
* 現に今、私はここで、読者に対してこの問題そのものを実践している。ここでふたたび、ルイス・キャロルのパラドクスにおけるアキレスと亀の対立を思い出していただけるとありがたい。そこでアキレスに対して亀は言語的世界像の平板化の側面を戯画的に強調して見せる役回りを演じているが、アキレスと亀が二者に分割して演じて見せている矛盾それ自体は、実際にはつねに一者に内在する矛盾として存在する。(それゆえ登場人物たるアキレスと亀自身にも、じつはふたたびこの矛盾が内在することになる。)いまここで論じている人称の問題以外にも、それぞれそれに特殊な問題がふくまれるとはいえ、時制にも様相にも、このことはそのまま当てはまるだろう。
23 だから、言葉を操る主体は、必然的に矛盾を生きなければならないことになる。自己自身を、それが自己であるという事実を、空前絶後の、他に例のないまったく特別の事態であると捉えると同時に、他者(他の発話主体)にも成立する一般的な事実のたんなる一例であるとも捉えていなければならないからだ。段落17の最後の「根拠の二重性」もこの矛盾の現われである。
24 なぜかただ一つだけむきだしの意識が存在しているという端的な現実が「可能な「端的な現実」」として理解されるようになるといわれるとき、「なぜかただ一つだけ…」というその端的な突出構造が否定されて、すべてが平板に並列されるような世界像に取って代わられる、というわけではない。むしろ、この突出構造は完全に維持されたまま、その突出構造がそのまま並列化されるのである。だから、前段落の「たんなる一例である」とは、色や味や、物体や出来事や、並列的に外から眺められた場合の心や意識や…が、つまりそういう同種のものが、同じ資格で並列的に存在する場合の、その一例とは意味が違う。そういうものたちのように、世界の中で同列に並んで存在するもののうちの一つ、という意味での一例ではなく、世界そのものが端的にそこから開けている唯一的な突出構造それ自体が同列に並んでいる、そのうちの一つ、という意味での一例なのである。自分はまったく例外的な存在者で、すべてはその内部にあるにすぎないという超越的・超越論的突出構造が、いわばメタレベルで一般化されるわけである。だからここでは、この一般化された突出構造と端的に現実に存在している突出構造の二重性が避けがたいものとなる。しかもこの二重性は最終的に存在する第一段階だけに生じるのではなく、それ自体が概念化されて、すべての段階に累進的に存在することになるのだ*。
*この点の直観的理解には、何度も繰り返し描いてきた「累進構造図」を参照されたい。
25 段落18で「前者」と呼ばれていた色や味のようなものに「クオリア」と呼ばれる独特の存在性格が与えられるのも、とりわけその段落の注*で述べたように、実のところはこの二重性によってであった*。それゆえ、人間という生き物からクオリア成分を取り除くとゾンビという生き物になる、といった捉え方はじつは誤りである。そのように捉えられれば、そこで取り除かれるべきクオリアという成分は、実在しないからだ。クオリアを取り除くとは、その究極的な意味においては、累進の原点にあるただ一つのむきだしの心からそのただ一つのむき出しという性質を、これまで使ってきた表現法で表現するなら〈私〉である人からその〈 〉性を、取り除くという意味でしかありえない。そのこと自体が累進的に一般化されることによって、人々(あるいは生き物)が一般的に持つ実在的なクオリアという発想が生じたのである**。
*もちろん、クオリアではなく意識でも同じことである。
**だから、クオリアは無関与成分かという問いも、的はずれである。無関与的であるのは〈私〉の〈 〉性であり、クオリア概念はその概念の一部にその無関与的なあり方に由来するものを密輸入して暗に取り入れているにすぎない。
26 ここで、段落11に戻って同じ問題を辿り直してみよう。そこではこう言われていた、「このステップには矛盾が内在している。もし本当に、なぜか一つだけ例外的にむきだしの意識が存在しているという事実が与えられている! という驚嘆(タウマゼイン)を感じたのであれば、それは、どうしたって、それぞれの人にとってそうであるという意味であることを断固拒否して(も)いなければならないはずだからだ」と。続く段落12ではこう言われていた、「そのとき最も重要なことは、おそらく他の人々も皆それぞれにおいては「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしているはずだ、とか、もしかしたら他の人々もじつは皆「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方で存在している(あるいはしていない)のかもしれない、とか、その種のことを考える余地は少しもない、ということである」と。この議論は「それぞれの人にとってそうであるという意味であることを断固拒否し」た場合にどうなるか、を論じている文脈上にあった。そうである以上、そんな断固拒否などしない場合、すなわち「それぞれの人にとってそうであるという意味であること」を受け入れた場合には、そうは(=段落12でまとめたようには=段落11で主張されたようには)ならない、と言われているようにこの文脈を読むことは自然なことだろう。
27 だが、文脈の理解という観点を離れて、事柄に即して考えてみた場合、そうはいえまい。「それぞれの人にとってそうである」と考える人は(と考える場合は)、段落11で主張されたようなことを、認めないことになるのだろうか。すなわち、おそらく他の人々も皆それぞれにおいては「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしているはずだ、とか、もしかしたら他の人々もじつは皆「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方で存在している(あるいはしていない)のかもしれない、とか、その種のことを考える余地がある、と考えることになるのだろうか。
28 なるほど、「それぞれの人にとってそうである」と考える人は(と考える場合は)、なぜか一人の人だけが端的に例外的な(すなわちむきだしの)あり方をしているという捉え方にはもはや固執してはおらず、すでにして一般的にそれぞれの人の視点に立つことを受け入れているのだから、それぞれの人々が皆じつは「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしている、ということをすでにして認めているように思われるかもしれない。しかし、そうではないのだ。「それぞれ」の視点へのこの移行を認めることは、だれもが「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしているということを、それらを眺めわたして、一括して認めることではないからである。それはむしろ逆に、そういうことは不可能なのだと認めることであり、そのことの一般化なのだ。すなわち、世界は現実にはその「それぞれ」のどれかの視点から開けるほかはなく、その視点に立てば、それ自身が「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしているほかはない、と認めることなのである。その視点に立てばそれ自身が「なぜか一つだけ例外的に存在するむきだしの意識」というあり方をしているほかはないと認めるとはすなわち、自身以外は決して――探究や検討の余地なく事実として現に――そういうあり方をしてはいないと認めることなのである。
29 ここには、本当にそうであるのか、といった問題は存在していない。「本当に」の水準でそれが成立するか否かを調べる方法は原理的に存在しないからだ*。しかし、この見地には独特の矛盾が内在することをふたたび確認しておかねばならない。この矛盾は前段落の「探究や検討の余地なく事実として現に」といった表現に象徴的に現れている。なぜなら、「現に」であるのは現にこの一つだけであり、だれにとってもそれぞれ、これと同じ「現に」が成り立つと見なすのは、実のところは現に与えられた事実からの逸脱であり、まさにそうではないということこそが問題になっているその当のことをそうだと主張することにほかならないからである。しかし、われわれは現にそれをしている! ここで「われわれ」というのは、この文章を書いている私と読んでいる読者諸賢のことであると同時に、一般にすべての(言葉を操る)人々のことである。われわれはみなこれをしている。というより、これをすることによって「われわれ」になっている、というべきなのではあるが。
*脳の働き具合を調べてみるといった見当はずれなこと以外に、何かなしうることがあろうか。その原理的ななさこそが他者の存在を定義している。
30 もう一つ、ここで確認しておかねばならない重大な事実がある。それは、このようにだれにとってもそれぞれこの「現に」が成り立つと見なすことは、通常の意味での他我問題に対する一つの立場を取ることではない、ということである。なぜなら、それは、段落13で論じたように、現に成立している所与の事実(いわば現象的事実)を語っているだけで、それを超えた真実がどうであるかはそもそも問題になっていないからである。このことは、この構造をそのまま「それぞれ」の水準に移行させても、そのまま維持されるのである。
31 しかし、逆説的ながら、これこそが他我問題への唯一の真の答えだ、とはいえる。これを超えた真実はそもそも存在しないからである。通常の意味での他我問題とは、この構造を、段落2で描写されたような個と類(個物と一般者)から成り立つ平板な世界のあり方に無理に移して(映して)*捉えたものであろう。だから、その問いに答えられるはずはない。答えられるはずのないあり方をしたもののことを他者と呼ぶのだから。
*『世界の独在論的存在構造-哲学探究2』第7章で導入した考え方で表現すれば、「ものごとの理解の基本形式」に従って(従わせて)、といえる。
(続)