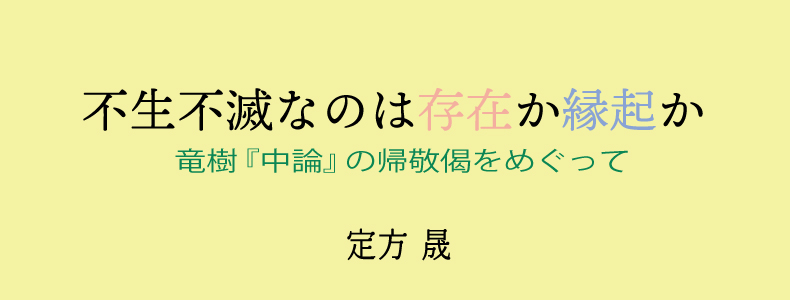不生不滅なのは存在か縁起か――竜樹『中論』の帰敬偈をめぐって
仏教哲学に、「不生不滅の縁起」という言葉は何を意味するかという議論がある。本稿はこの議論について述べるものであるが、仏教哲学に不馴れなひとのために、あらかじめ言っておくと、これは次のような議論に似ている。
「永遠の思想」という言葉は次のいずれを意味するか。
(1)「永遠に関する思想」を意味する。この場合、思想の内容は述べられている。だが、その思想が永遠に存続するか否かは述べられていない。
(2)「永遠に変わらない思想」を意味する。この場合、思想そのものはどのような思想なのかは述べられていない。
竜樹の『中論』の冒頭に帰敬偈と呼ばれるものがある。それをサンスクリット原文と羅什の漢訳で示せば、次のようになる。
anirodham anutpādam anucchedam aśāśvatam/
anekārtham anānārtham anāgamam anirgamam/
yaḥ pratītyasamutpādaṃ prapañcopaśamaṃ śivam/
deśayāmāsa sambuddhas taṃ vande vadatāṃ varam/
不生亦不滅 不常亦不断
不一亦不異 不来亦不去
能説是因縁 善滅諸戯論
我稽首礼仏 諸説中第一
羅什訳を書きくだせば、つぎのようになる。
生ずることなく滅することなく、常ならず断ならず、
一ならず異ならず、来ることなく去ることなし。
よくこの因縁を説き、善くもろもろの戯論を滅したる、
説者中の第一人者たるブッダに我は稽首す。
さて、問題は、最初の2行の言葉(否定辞an-[=「不」]が8つあるので「八不」と呼ばれる)と3行目のpratītyasamutpādaṃ(「縁起」と訳される、羅什訳では「因縁」)という言葉の関わりである。以下、サンスクリット語の語形に忠実な訳語「縁起」(「縁によって生じる」を意味する)という言葉を用いることにしよう。「八不」は「縁起」という術語の内容をいっているのか、「縁起」という術語に掛る形容詞なのか、という問題である。
この問題を論じるのに、いちいち「不生亦不滅 不常亦不断 不一亦不異 不来亦不去」という言葉を繰り返すのは煩瑣なので、簡略化して、「不生不滅」と言うことにしよう。すると、解釈は次の2つになる。
(1)「不生不滅の縁起」とは「すべての存在は不生不滅である」ことを教える言葉である。
(2)「不生不滅の縁起」とは「縁起の思想は永遠に変わらない」ことを教える言葉である。
*(1)の場合には「すべての存在」という言葉が補われていることに注意。この補足により、最初の2行だけで1つの文が完結している。(2)の場合は、初めの2行は3行目の「縁起(因縁)」という言葉につながっている。
中国や日本では(1)の解釈が用いられてきた。ところが現代になってサンスクリットの原文が学者たちに知られるようになると、(2)の解釈が現れるようになった。
サンスクリット原文によると、「八不」の句すべてが m で終わっている。そして3行目の「縁起」(pratītyasamutpādaṃ)がṃ(=m)で終わっている。pratītyasamutpādaṃは文脈から目的格であることは明らかなので、「八不」の句のほうをも目的格とみて、文法重視の学者は「八不」を「縁起」にかかる形容詞と見たがるのである。
羽渓了諦氏は『中論』の邦訳で「八不」について次のように注している。(『国訳一切経』中観部一、大東出版社、1930)
「不生不滅なる……不来不去なる」は梵文によれば形容詞であって、「縁起」の語を規定する。それは存在が生滅去来するものであるに対し、縁起そのものは不生不滅なる法であることを意味する。
また英訳者ロビンソンも同様の解釈をして訳している。
I offer salutation to the best of preachers,the Buddha, who has taught that dependent co-arising has no ceasing, no arising, no nullification, no eternity, no unity, no plurality, no arriving, and no depariting, that it is quiescent of all fictions, that it is blissful.
同様の解釈はインドの中観論者であるバーヴァヴィヴェーカにも見られる。かれは、縁起が不生であるということは自己矛盾ではないかという指摘に対して、縁起は世俗としては生起であるが、勝義としては不生なのだということなのだから損減にならないという。(Prajñāpradīpa,p.6,l.19-p.7,l.8 丹治照義『実在と認識』p.83による。)
「自己矛盾」という説明は漢訳文からは分かりにくいだろう。サンスクリット語で考えると分かりやすい。「縁起」のサンスクリット語はpratītyasamutpādaṃであり、「不生」のそれはanutpādamである。すなわち前者の中のutpādaṃ(「生起」)と後者のanutpādam(an- utpādaṃ, anは否定辞)は語形から矛盾することが明瞭である。
上記の二つの解釈法を
(1)「不生不滅の存在」派
(2)「不生不滅の縁起」派
と呼び分けることにしよう。前者は哲学者の派、後者は文法学者の派といえる。後者は文法に捉われて、中論の肝腎の哲学を理解しそこなっている。
この2種類の訳をめぐってかつて三枝充悳氏と立川武蔵氏のあいだで行われたちょっとしたやりとりが興味深い。三枝氏は「不生不滅の存在」派であり、立川氏は(表現に関するかぎり)「不生不滅の縁起」派である。
三枝氏はいう。
「縁起は生を持たない」といっても、「縁起は生を持つ」といっても、どのように考えても、私には「縁起そのものが生ずる・生じない」という命題が理解できない。ここにはどうしても「何か或るもの」を挿入せざるを得ない。それをいちおうbhāva(またはその複数)すなわち「存在(するもの)」(羅什は「法」「諸法」と訳す)としよう。すなわち「八不の縁起」とは「存在(するもの)(法・諸法)が八不である縁起」と解すべきであろう。その理由はたとえば第一品第一偈が、「bhāvāḥ(諸法)の四不生」を説いているところにも明らかである。(「中論研究序論」『理想』388号、1965年9月)
三枝氏は「第一品第一偈が」といっているが、これは帰敬偈のあと、第一偈の前にある、注釈者・青目の文をいっているのであろうか。そこに「仏は……因縁の相を説きたもう。いわゆる一切法は不生不滅、不一不異等、畢竟空にして無所有となり。」とある。
立川氏は三枝氏の考えを批判した。三枝氏が「八不」は「縁起の内容」を指すと考えるのに対し、立川氏は「八不」は「縁起」を修飾する形容詞だとするのである。立川氏はいう。
「滅することなく」から「行くことなき」までの八つの句は、それぞれ否定詞を含んでおり、「戯論の止滅した、吉祥なる」という表現と同様、「縁起」を修飾している。
立川氏が8つの句を「縁起」を修飾するものと考える理由は、8つの句(サンスクリット語)の語尾がmで終わっていることが、「縁起」(pratītyasamutpādaṃ)の語尾と一致することであろう。
立川氏も8つの句が本来は「縁起」の内容を表わすものであることを認めている。それにもかかわらず、なぜ「不生不滅の縁起」派の考えを採るのか。その理由を説明するのが氏の論文である
氏はサンスクリット文法の「有財釈」(または「多財釈」、現代語では「所有複合語」)の説明から始める。「所有複合語」は2つの語(正確にいうと2つの語幹)が結合してできる新しい1つの語であって、形容詞の働きをする(「……の」とか「……を持っている」とか訳す。)
たとえば「多い」+「財産」はふつうは「多い財産」を意味するが、所有複合語となった場合には「多くの財産を持っている」という形容詞になる。「八不」の場合、たとえば「不-生」(an-utpāda-)はふつうは「不生」を意味するが、所有複合語となった場合には「不生の」という形容詞になる。立川氏はこれに基づき、「八不」(八つの語はいずれも複合語になっている)は所有複合語だとして、「縁起」という術語を修飾する形容詞だとしたのである。
ところが、――と立川氏は続ける――竜樹を含むインドの仏教学者は所有複合語と他の複合語を文法的に区別することにルーズであった。竜樹は文法の上では「八不」を所有複合語として用いながら(だから「八不」の語尾と「縁起」の語尾を一致させている)、意味の上ではそれをふつう一般の複合語として用いた(だから「八不」と「縁起」は内容上、名詞―形容詞の関係にない)。これは、竜樹が、例えば「無明に縁って行が生じ」という教義における「項」(「無明」や「行」)と「関係」(「~に縁って~が生じ」)を厳密に区別しなかったことを示すと考えてよいだろう。
こうして立川氏も結局は、帰敬偈の意味としては「不生不滅の存在」派の考えに与するのである。(立川「『中論』における縁起」『名古屋大学文学部三十周年記念論集』、1979)
三枝氏は立川氏の批判に対し、先の自説を守った。(三枝「竜樹の帰敬偈について」『竜樹・親鸞ノート』法蔵館、1983)
三枝氏ら「不生不滅の存在」派の立場は「存在」(bhāva-)という言葉を補うことを前提としている。三枝氏はその語を文脈上bhāvāḥ(複数・主格)とした。これにより、氏の場合、「不生不滅の存在」は「諸存在は不生不滅である……」という、1つの独立した命題を説く文となる。立川氏も「存在」という言葉を補う場合を考えたが、氏が考えたのはbhāvānām(複数、所有格)である。これにより「諸存在の不生不滅」という言葉ができるが、ここからも上記と同様、「諸存在は不生不滅である」という命題が導かれる。
三枝氏の解釈の場合、帰敬偈は「諸存在は不生である……」といっているというのだから、「諸存在」(諸法)は主格で表わされなければならない。すなわち、bhāva-という語を複数・主格の形bhāvāḥとしなければならない。単数・主格の形ならbhāvaḥとしなければならない。いずれにしても、語尾がḥで終わっているのだから、述語anutpādamがmという語尾で終わっていることと矛盾する。anutpādamは、単数の場合でいえば、anutpādaḥとあるべきであるのに、そうなっていない。ここに立川氏が批判を挿む理由がある。
私は主語として、bhāvaḥの代りに、sarvam(「一切」)を補ったらどうかと思う。これは中性名詞であるので、単数・主格(「一切は」の意)でも語尾はmとなる。そうすれば、主語と述語はともに語尾mの形で主格となって一致する。「八不」のほうはみな男性名詞であるので、主格であるなら語尾をḥとしなければならないが、mとしてあるのは、sarvamに形を合わせたのだ、と考えることにしよう。このように考えれば、帰敬偈の最初の2行はこれだけで完結した文となり、この2行を形容詞として3行目の「縁起」につなげる必要はなくなる。
最初の2行に主語を補うことを恣意的と見るひとがいよう。しかし、私は、竜樹が主語を省いたと考えるので、補う。この省略はかれ自身の哲学に合致するものである。かれは『中論』「観去来品」で、「行く者は行く」の主語「行く者」は蛇足だといっているではないか。[注]
私のこの解釈には依然として疑いが残るだろう。しかし、いずれにしても、『中論』の哲学を洞察する者は、たとえ文法を無視してでも、(1)「不生不滅の存在」派の解釈を採らねばならないことを知るだろう。帰敬偈は「よくこの因縁を説き」といっている。『中論』が縁起の解説を主眼としていることは明らかである。「縁起」の内容を説かずして、いくら「縁起は不滅の真理だ」といっても、意味はない。羽渓氏は「それは存在が生滅去来するものであるに対し」といっているが、これは竜樹の考えに反する。
以上の私の考えは三枝氏の2番目の論文を読んだときに生まれたものであるが、それを発表する機会を逸してしまった。その後、三枝・立川論争に関する論評が現れたかも知れない、決着がついたかも知れないと思いながら、それを知る余裕がなかったので、発表を控えていた。
丹治照義氏の著『実在と認識』に「八不の縁起」への言及がある。しかし、氏はこの言葉を繰り返すだけで、その意味が「不生不滅の存在」派のものか、「不生不滅の縁起」派のものか、明かにしていない。氏の近著『中論上』(大蔵出版、2019)にも説明がない。三枝・立川論争への言及がなく、参考文献欄には立川氏の論文があげられていない。私はこの問題に対する大方の関心を促すために筆をとった次第である。
注:カントが同じことをいっている。拙稿「『私』をめぐるカントとインドの哲学」、「Webはるとあき」、2019.07.08