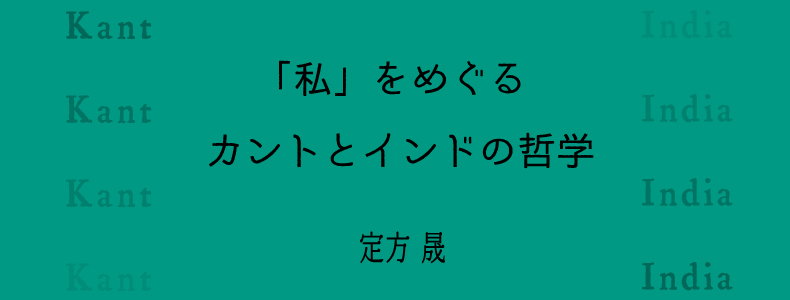「私」をめぐるカントとインドの哲学
私はインドの哲学を専攻しているが、最近カントの『純粋理性批判』を読んで、カントの考えにインドの哲学と共通するものが幾つもあることを知って驚いている。私はすでにこれに関連した論文を春秋社Web「はるとあき」に2つ発表したが(1)、さらに1つ加えたい。今回は同書の「誤謬推理(Paralogism)」の議論をインドの哲学思想と比較してみよう。
『純粋理性批判』の「純粋理性の誤謬推理について」の章は「私とはなにか」を論じている。「私」とは実に不思議な存在である。われわれはふだん「これほど自明な存在はない」と考えているが、改めてそれを考えようとすると、とたんに分からなくなる。いま私は「ふだん考えている」といった。これは訂正しなければならない。われわれはふだんそんなことは考えていない。考えていないからこそ、分かったつもりになっていたのである。
以下、拙論中のカントの文について二つのことを断っておきたい。(1)『純粋理性批判』の和訳は多いが、私が引用するのは私がたまたま大学の図書館から借り出した宇都宮芳明監訳、上(以文社、2004)からである。(2)カントの文は難解である。1つのセンテンスに、専門用語を含む多くの修飾句あるいは従属節が挿入され、また1つのセンテンスが終わるまでに論理的な紆余曲折が幾度となく現れることがその原因である。そこで、私はカントの文を、論旨を損なわないと思われる程度に縮約して示すことにする。なお、引用文のあとの( )の中は和訳とドイツ語原書のページを示す。
「誤謬推理」の1つが「私(魂)は実体である」である。実体とは不変かつ独立の存在をさす。カントは、この推理が誤りなることを示すために、「私は思考する」(Ich denke)という命題から出発する(2)。
「私は思考する」という概念(判断)はすべての概念の乗り物(Vehikel)であり、それゆえ、それらの概念とつねに一体である。(p.426,A341)
これは重要な指摘である。われわれは「猫が歩く」とか「空は青い」とか考えたり、言ったりするが、それは厳密にいうと、「『猫が歩く』と私は思考する」、「『空は青い』と私は思考する」ということである。(「考える」と「言う」は音声にするかしないかの違いで、概念としては同じである。以下、「思考する」で両概念を代表させることにする)。「猫が歩く」や「空は青い」に限らず、すべての概念が「……と私は思考する」という概念に支えられている。この事実を指してカントは「私は思考する」という概念をすべての概念の「乗り物」と称したのである(3)。
われわれはこのことを意識していなかったが、いわれてみれば、そのとおりである。じつにわれわれホモ・サピエンスにとって「私は思考する」は精神生活の基本中の基本である。あまりに基本的すぎて、われわれはそれを忘れていたのである。デカルトも確実な存在の探求を「私は思考する」(cogito)から始めた。
「猫が歩く」や「空は青い」の場合、これに「……と私は思考する」をつけてもつけなくても、さしたる問題は生じない。しかし、「私は歩く」や「私は賢い」の場合には、問題が生じる。これらの句に「……と私は思考する」をつけた場合、たとえば「『私は歩く』と私は思考する」といった場合、ここには2つの私が現れる。この2つの私を『私』と「私」で区別することにする。ここに生じる問題は『私』と「私」は同一か否か、ということである。言葉が同じであるので同一であるように見える。しかし、さきの「『猫が歩く』と私は思考する」の場合、『猫』と「私」は別である。したがって「『私は歩く』と私は思考する」の『私』と「私」もじつは別であるかも知れない、という疑いが生じる。
一般人は言葉が同じである以上、同じだと考えるであろう。しかし、同じであると考えると、つぎのような矛盾が生じる。『私は歩く』の反対概念は『私は歩かない』である。この2つの概念を同時に抱いた場合、どちらかが偽であるということで話が済むが、これに「……と私は思考する」をつけると、そうはいかない。片や「『私は歩く』と私は思考する」、片や「『私は歩かない』と私は思考する」となり、1つの「私」が「『私』は歩く」と「『私』は歩かない」とを同時に思考することになり、矛盾が生じる。
では『私』と「私」をつぎのように区別したらどうか。『私』を「思考される私」にし、「私」を「思考する私」にするのである。しかしこの場合には循環論法が生じる。「『私は歩く』と私は思考する」といった場合、『私』が「思考される私」であることにはだれでもすぐ気がつくが、「私」もまた「思考される私」であることには気がつきにくい。「……と私は思考する」といっているのは誰か。その誰かこそ「思考する私」であり、「……と私は思考する」の「私」はもはや「思考される私」であるに過ぎない。では、“「『私は歩く』と私は思考する」と私は思考する”といえば、その誰かを言い当てたことになるか。読者はすでにお気づきの通り、言い当てられたと思われた私もまたすでに「思考される私」に転じている。こうしてわれわれは最終的な私には決してたどり着くことができない(4)。
カントは循環について言っている。
われわれは、この主観をめぐってつねに循環(Zirkel)に陥っている。すなわち、この主観について何らかの判断を得ようとすれば、われわれはいつでもつねにこの主観の表象(Vorstellung)を用いなければならないからである。(p.429, A346)
客観を認識する為に前提しなければならないものを、それ自身客観として認識することはできない。また、規定する自己(思考)〔認識する自己〕は規定可能な自己(思考する主観)〔認識される自己〕から、認識が対象から区別されるように、区別される。こうしたことはごく明らかなことである。ところが、〔両者を区別せず〕思考の総合における統一を、この思考の主観における知覚された統一と見なす仮象(Schein)〔認識する自己を認識される自己と同一視する思い込み〕ほど、もっともらしく見え、人を誤らせるものはない。われわれはこの仮象を、実体化された意識のすり替えと呼ぶことができるであろう。(p.469, A402)
カントのこれらの言葉は「認識者を認識することはできない」ことを意味している(5)。私はインドのウパニシャッドの哲人ヤージュニャヴァルキヤ(前8世紀)の言葉を思い出す。一部省略して示す。
いわば相対の存在するとき、そこに一は他を見、そこに一は他を聞き、そこに一は他を嗅ぎ、そこに一は他に語り、そこに一は他を認識す。
されどその人にとりて一切が我となりしとき、そこに彼は何によって何者を見得べき。そこに彼は何によって何者を聞き得べき。そこに彼は何によって何者を嗅ぎ得べき。そこに彼は何によって何者に語り得べき。そこに彼は何によって何者を認識し得べき。それによってこの一切を認識するところのもの、そを何によって認識し得べき。
この我は、ただ「非也、非也」と説き得べきのみ。彼は不可捉なり、なんとなれば彼は捕捉せられざればなり。彼は不可壊なり、なんとなれば彼は破壊せられざればなり。彼は束縛せられずして動揺せず、毀損せられず。
ああ、認識者を何によって認識し得べけんや。
御身はすでにかく指教を受けられたり、マイトレーイーよ。ああ、不死とは実にかくのごとし。(ブリハド・アーラニヤカ・ウパニシャッド、4-5-15)。(辻直四郎著『インド文明の曙』岩波新書、pp.174-175)
ヤージュニャヴァルキヤの「相対の存在するとき」とは、「認識されるもの」(『私』)(6)と「認識するもの」(「私」)が存在するとき、という意味である。本来1つであるべき「私」を2つに分けて考えることは迷いだというのである。
このように「私」は認識不可能であるにもかかわらず、われわれは日常「私」という言葉を何の疑問もなく使っている。これはどういうことか。私が思うに、「言説は主語と述語から成る。主語がないと言説が成り立たないので形式的にでも主語を立てるのだ」ということである。
カントは言っている。
それ自体では完全に内容を欠いた「私」という表象(p.429, A345)
思考するこの私によっては思考の超越的主観=X以外の何物も表象されない。この主観(Subjekt)は、その述語である思考によってのみ認識されるのであって、主観を述語から切り離しては、われわれは決していささかの概念もそれについて持つことはできない。(p.429, A346)
すなわち、「私」によっては何も表象されない。ただ「私」に述語(「思考する」)が付くことによって、「私」は「思考するもの」という内容を持つものになる。こうなると、「私は思考する」という文(概念、判断)は「思考するものは思考する」ということと同じになる。これは同語反復である。これほどにははっきりしない同語反復もある。カントはデカルトの「われ思う、故にわれ在り」(cogito,ergo sum.)は推理ではなく(「故に」には意味がない)、同語反復(tautologisch)であると言い、cogito をsum cogitans(「われ思いつつ在り」)と言い変えている(p.436,A355)。「第二誤謬推理」の議論では、「思う」と「在る」という述語がともに「われ」という主語に属することを意味しているにすぎない、といっている。同語反復の例として私は「神は偉大なり」を付け加えよう。われわれは「偉大なるもの」を「神」と名づけるのである。したがって「神は偉大なり」は「偉大なるものは偉大なり」を意味することになる。「神」という言葉はそれ自体では「内容を欠いている」のである。
ひとは「思考するものは思考する」という表現はおかしいとは思っても、「私は思考する」という表現はおかしいとは思わない。ひとはそう表現することによって、内容のないもの(「私」)を内容のあるもの(実体)と思いこむことになる。言葉はじつに人をまやかすものである。
カントはいう。
われわれは「私」についてのこうした論理的意味以外には……いかなる知識も持っていない(p.433, A350)
この「私」は、……意識のたんなる形式にすぎない(p.455, A382)
すなわち、「私」は論理上の(=文法上の)必要から文頭に置かれるのであり、内容を持たず、意識の形式にすぎない、というのである。ここには言葉(情報の伝達)というものの秘密がある。いったん分けて、分けたものを結合するという手続きを取る以外に、伝達は不可能なのである。
「純粋心理学の第一誤謬推理(「私」〔魂〕を実体とする誤謬推理)に対する批判」を要約してみよう。
カントによれば、感性によって直観される多様な内容を悟性がカテゴリーによって整理する。統率者が被統率者たちを統一するようにである。形式が内容をまとめる、といってもよい。
われわれは日常、
私は歩く
私は歌う
私は……
といった思考をおこなっている。「私」は主語で、「歩く」等は述語である。これを「形式と内容」に当てはめれば、主語は形式で、「歩く」等は内容である。つまり「私」は形式に過ぎないのである。
ところがひとは形式に過ぎない「私」を実体(不変独立の存在)と考える。たぶん「私」が繰り返し現れるのでそう思うのであろう。だが、これら繰り返される「私」が同一であるという保証はない。また「私」という言葉をいくら眺めても常住不変性をそこから引き出すことができない。このような批判によって、形式に過ぎない主語を実在的な主体と見る誤謬が明らかにされる。実在的な主体(物自体)はわれわれには全く知られないのである。
さて仏教が説く無我の思想をみてみよう。無我の説明は難しい。小乗仏教では次のように説明する。ひとは「車」「車」というが、そこから輪、台、長柄などを取り除いたら、「車」と呼べるものは何もない。「私」についても同様である。「私」「私」というが、そこから身体、感覚器官、認識器官などを取り除いたら、「私」と呼べるものは何もない、と。
この説明は幼稚である。ばらばらに存在する輪、台、長柄などと、まとまって存在するそれらを区別していないからである。このまとまりこそカントのいう統一ないし形式である。その意味では「私」は存在するのである。無我を説くには別の方法が必要である。
大乗仏教は言葉の批判から入る。「私」とか「世界」とかいう言葉は、ひとが生活の便宜のために仮に設定したものにすぎない。それを絶対視してはならない、と。
インドの仏教哲学者ナーガールジュナ(3世紀)の『中論』第Ⅱ章の「行く者は行かない」(サンスクリット語 “gantā na gacchati”、英訳 “A goer does not go.”)はカントの「私は思考する」の議論に似ている。ナーガールジュナの議論を分りやすく紹介しよう。
かれは「行く者は行く」という表現をとりあげ、この表現はおかしいという。なぜなら、主語(「者」)は1つしかないのに、述語(「行く」)が2つある。だからむしろ「行く者は行かない」といったほうがよい、と。
「行く者は行く」という表現はカントの「思考する者は思考する」と軌を一にし、同語反復であり、たしかにおかしい。だが、ひとはいうであろう。われわれは「行く者は行く」という不自然な表現はしない。ナーガールジュナは「かれ」あるいは「太郎」というべき言葉を「行く者」という言葉にすり替えて自分に都合よい議論をしているのである、と。そこで私は「行く者」を「太郎」に替えて説明しよう。
ひとが「太郎は行く」と発話するとき、その「太郎」の中にはすでに「行く」が含まれている。なぜなら、ひとが「太郎」というとき、ひとは「行く太郎」を目にしている、あるいは頭に描いているからである。この「太郎」は「行く」から切り離せない(7)。だが、ひとは言葉によって「太郎」と「行く」を切り離す。ここに問題がある。現象は不可分で一なるものである。言葉はその不可分なものを分節する。分節された「太郎」は「行く」と関係なく独り歩きし始める。
現象においては「行く」から切り離された「太郎」は存在しない。だから、ひとがいう「太郎は行く」は「行く太郎は行く」というに等しい。「行く太郎は行く」という表現は「行く」が重複していて誰もが不自然と感じるが、「太郎は行く」といえば不自然さが消える。これこそ言葉のすり替えである。「太郎」は依然として「行く太郎」であることに変わりはないのである。ひとはすり替えによって不自然さを回避する習慣を身につけたのである。
カントの言葉に「あらゆる思考がその内に属している共通の主語」(p.432,A350)がある。このことを具体的な例文で示すと、つぎのようになる。(共通の主語を太字の「私」で示す。)
猫が歩くと私は思考する。
空は青いと私は思考する。
彼女は私を愛していると私は思考する。
……と私は思考する。(8)
カントはまたいう。
この表象(私)があらゆる思考において繰り返し繰り返し現れることは知覚できるが、この表象が常住不変の直観であることは知覚できない。(p.433,A350)
上掲の4つの例文に「私」が繰り返し現れている。ひとはこのことをもって「私」を不変の実在であると思い込む。反復出現は不変性や永続性を証明するには十分ではないのであるが、一般のひとには十分なのである。
私はこれに類似することをナーガールジュナ哲学の解説において何度もいってきた(9)。つぎのようにである。
われわれの言語生活は、つぎのような表現から成っている。
太郎は行く
太郎はころぶ
太郎は笑う
太郎は……
われわれは上記の一連の表現のなかから、太郎という不変の存在を抽出してくる。太郎はつねに、行く太郎か、ころぶ太郎か、笑う太郎か、……する太郎か、いずれかの太郎であるはずなのに、どの動作とも無関係の「太郎」を抽出してくる。そのような抽象的な「太郎」はけっして存在しない。それにもかかわらず、われわれはあたかもそのような「太郎」が存在するかのようにして「太郎」という。
われわれの言語活動は基本的に「主語+述語」の形式をとり、ひとは主語の位置にいとも安易にさまざまな言葉をはめ込み、そのことを通じて、それらの言葉が自明なものであると思い込む傾向がある。論理学に虚偽(過誤)の一つとして論点先取(assumptio non probata)と呼ばれるものがある。あることを証明するためにいまだ証明されていないことを前提として立てることである。ひとが主語として立てる言葉はすべて論点先取されたものである。このことを示すために、中観哲学はひとが「自明な存在」と思い込むものをsvabhāva(英語にするとself-being,漢訳では自性)と呼び、そのようなものは存在しないと説くのである。
上掲の「太郎は云々」の解説は私の創作であるが、ナーガールジュナの議論から当然生じるものである。こうしてカントもナーガールジュナも同様の結論に至る。「私という言葉が繰り返し現れることから、ひとはなにか私という不変な存在(実体、不死の魂)があるように思ってしまうが、それは誤りである」と。
このようにカントとナーガールジュナには共通点があるが、一方では重要な違いがある。カントの場合は、繰り返し現れるのは第一人称の「私」であり、それのみである。ナーガールジュナの場合は、第三人称の「太郎」であり、しかも「太郎」の代りに人称に関係なく主語の位置にどんな言葉を持ってきてもよい。
また、実体の観念を否定する場合、カントはそれを、表象(主観が抱く表象)を物自体と誤認することから生じるもの、とするのに対し、ナーガールジュナはそれを、便法に過ぎない言説を絶対視することから生じるもの、とする。カントの議論は認識論的であり、ナーガールジュナのそれは言語論的である。
〈注〉
(1)web春秋・はるとあき「般若経典の論理とカント」2018.08.10.「カントの『弁証』と仏教の『分別』」2019.05.25.
(2)カントは命題「魂は実体である」の「実体」を現実的なものとして捉えること(たとえば「魂は死後も生きつづける」とすること)は非とするが、理念(Idee)を示すものとしては非としない。(p.433, A351)
(3)カントの「私は思考する」は経験から独立して成り立つものであり、デカルトのそれが経験的な知覚(「われ在り」)に結びつくのとは異なる。(p.430, A347)
(4)ナーガールジュナ(後出)はその著『中論』の第Ⅶ章で「無窮(むぐう)」(anavasthā)という言葉を使っている。これは循環論法に相当しよう。あるひとが「すべての事象に生、住(持続)、滅の三つの相がある」といった。ナーガールジュナは「生、住、滅は互いに異なるから、生が住になることも、住が滅になることもできない」といった。相手は「生の中にすでに生、住、滅があるとすればどうか」といった。ナーガールジュナは「それでは無窮になる。すなわち生の中の生に生、住、滅があり、生の中の生の中の生に生、住、滅があるということになり、終わりがない、と。
(5)「私は思考する」という意識がわれわれに存在することは否定できない。過ちはこの「私」を「認識者としての私」として捉えることである。この「私」を「認識されている私」と正しく捉えている限り問題はない。そうした意味の「私」の存在までをも否定するのはもう1つの過ちである。
(6)( )中に「世界」を加えてもよいが、いまは「私とはなにか」に議論を集中するために加えないでおく。
(7)上記したカントの言葉「主観を述語から切り離しては、云々」参照。
(8)カントは事あるごとに「経験に依存する」と「経験から独立している」の違いに言及する。この考えによると、「猫が歩く」「空は青い」等は「経験に依存する」に属し、「……と私は思考する」は「経験から独立している」に属する。
(9)たとえば、「『去る者は去らず』の意味」『春秋』2012年6月号、pp.5-8