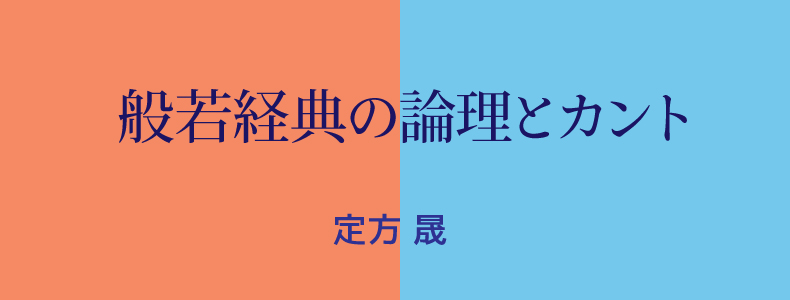般若経典の論理とカント 定方晟
般若経典には「xはAにあらず、非Aにあらず」といった類の表現が頻出する。ふつうに考えれば、Aにあらざれば非Aであるはずである。Aでも非Aでもなければ、何なのか。
私は最近、カントの『純粋理性批判』でアンチノミー(二律背反)に関する議論を読む機会を得た。アンチノミーとは、二つの相反する命題(定立、反定立)のいずれが真であるか決められない状態をいう。これは人間理性の能力の限界を示すものだという。私はこの議論を参考にして、般若経典の句を考えてみる。
二つの主張が相対立する場合、その対立(対当)の仕方にいろいろあるが、カントがあげる「匂い」の例によれば次のようである(1)。
〈弁証論的対当〉
(定)どの物体も良い匂いがする (反)どの物体も良くない匂いがする
〈分析的対当〉
(定)どの物体も良い匂いがする (反)どの物体も良い匂いがするということはない
両対当は反定立を異にするが、前者の場合、反定立は定立の部分否定であり(定立の「良い」を否定するだけで、「する」を否定していない)、後者の場合、定立の丸ごと否定である。
この結果、前者の場合には、第一命題(定立)と第二命題(反定立)のほかに、第三の命題「どの物体も全く匂いがしない」が生じ、第一命題、第二命題がともに偽であるということが起こり得る。これに対し、後者の場合には、その第二命題(反定立)がすでに「どの物体も全く匂いがしない」を包摂しており、第三の命題が生じる余地がない。また後者の場合、二命題のあいだに「一方が真であれば他方は偽、一方が偽であれば他方は真」という関係が必ず成立し、二命題のほかに「余計なもの」が生じる余地がない。すなわち排中律が成立する。これは数学の集合論でいうAとĀの関係に相当する。
この違いは何に由来するか。私は言葉に、と考える。後者の場合、(反)は(定)の形式的な否定であり、命題の意味内容には立ち入らない。したがって、命題の対立のほかには何も生じない。前者の場合、賓辞(良い匂い、良くない匂い)が異なるために命題の対比を無意味ならしめないための、両賓辞を結合する上位概念(匂い)を、ひとは無意識のうちに前提するのである。
カントは弁証論的対当の例として「世界は空間・時間的に有限である」「世界は空間・時間的に無限である」をあげている。ここでは世界(宇宙)に「大きさ」があることが前提されている。したがって、第三命題「世界に大きさはない」が生じる。
こうしてカントはアンチノミーが生じるのは弁証論的対当の場合であることを明らかにした。ひとは弁証論的対当において第三の命題が存在することに気づかず、第一命題と第二命題しかないと思いこみ、そのどちらかが真だと思って論争するのである。
般若経に次の句がある。
観色若常、若無常、是為戯論(羅什訳『摩訶般若波羅蜜経』大正蔵8、380c。玄奘訳『大般若波羅蜜多経』大正蔵6、890b。)
訳せば「色(=もの)をもしくは常とみる、もしくは無常とみる、これは戯論(=偽)である」となろう。すなわち、「色は常である」と考えるのも、「無常である」と考えるのも、ともに誤りである、というのである。「若常、若無常」は梵文では nityam iti vā anityam iti vā である(木村高尉校訂『梵文二万五千頌般若経』Ⅵ~Ⅷ, p.23, ll.26-27)。すなわち、「常」はnityam の訳であり、「無常」は anityamの訳である。この梵句は「観」や「戯論」に当たる梵語を欠くが、羅什や玄奘が見た梵典にはsamanupaśyati や prapañca という語があったのだろう。
注意すべき点は、「無常」の「無」にあたる否定辞が梵文ではa であることである。これは単語一つを否定するだけの部分否定を示す。もしna を用いて、例えば rūpaṃ nityaṃ na samanupaśyati (不観色常)とすれば、全文否定になる(2)。部分否定、全文否定の両者の関係をカントの「匂い」の例に倣って整理すれば次のようになろう。
〈弁証論的対当〉
(定)ものは常であるとみる 〈反〉ものは無常であるとみる
〈分析的対当〉
(定)ものは常であるとみる (反)ものは常であるとはみない
すなわち般若経のいう「観色若常、若無常」は弁証論的対当である。そしてそこに生じる「余計なもの」は「変化」である。だから、ここに第三命題「変化というものはない」が生じ、アンチノミーが生まれる。般若経が問題視するのはこの弁証論的対当であろう。
カントはかれ独自の概念「物自体」に関係させて弁証論的対当を説明する。かれは現象と物自体を区別する。われわれが知り得るのは(経験しうるのは)現象の世界である。物自体は現象を存在せしめる契機となるものであるが、それはわれわれには知られない(われわれの思惟がその存在を要請するだけである。)しかるに、ひとは現象について考えることを物自体について考えることと同一視する。ひとは空間や時間について大きさを云々するが、それはあくまでも現象についてであるにすぎないのに、物自体のことであると思い込む。物自体としての空間や時間に大きさがあるかどうかをわれわれは知ることがない。従って、それらが有限であるか無限であるかも知ることがない。
カントのいう弁証論的対当(dialektische Opposition)の「弁証論的」(dialektische)という言葉はアンチノミーの本質を理解するのに役立つ。 dia の語源をたどれば「2」(duo)に結びつき、 lektische のそれは「言葉」(logos)に結びつく。つまり弁証論的対当とは「言葉による二つの立場の対立」ということである。
言葉で二つの立場を対立させる場合、上述したように、必ず両者をまとめるその上位概念が必要となる。有限・無限の対立の場合、「大きさ」がそれである。般若経には「観地界若浄、若不浄、是為戯論」(大正蔵6、891c)もあるが、この場合は「清さ」がそれである。ひとは無意識のうちに上位概念を立て、立てたことに気づかずに議論している。カントがいう「余計なもの」とはこの種の概念のことである。上位概念を立てておきながら、それをそっちのけで議論しているから、問題が解決しないのである。
上のことに関連していうと、言葉はみな種(下位概念)と類(上位概念)を含意する。「猫」は犬や象ではないこと(種)、しかし哺乳類としては犬や象と同じであること(類)を含意する。ひとはこうした言葉を立てることによって自己の行動の焦点を絞ることができるのであるが、このとき類(上位概念)のほうはひとの意識に上りにくいのである。要するに「xはAにあらざれば非Aである」と言えるのは、Aが数学的記号の場合であって、Aが言葉の場合には言えないのである。
つぎに『金剛般若経』の論理についてであるが、これにはカント論理学は一部しか適用できない。この経につぎの文がある。梵原文と和訳を(順序を逆にして)示す。
如来によって般若波羅蜜と説かれたもの、それは如来によって非・(般若)(3)波羅蜜と説かれた。それゆえ般若波羅蜜といわれる。
梵原文(Vajracchedikā,Conze,ed.13a)ではyaiva prajñāpāramitā tathāgatena bhāṣitā saiva-a-pāramitā tathāgatena bhāṣitā. tenocyate prajñāpāramiteti.
上の句の「般若波羅蜜」と「非般若波羅蜜」に関してカントのいう弁証論的対当をつくると、「仏説は般若波羅蜜である」か「仏説は非般若波羅蜜である」か、のいずれかであるという主張が成立する。この場合、第三の命題「般若波羅蜜というものはない」が生じ、第一、第二命題がともに偽となりうるので、第一、第二命題のいずれをも真として選ぶことができない。一方、『金剛般若経』の主張は「仏説は般若波羅蜜でもあり、非・般若波羅蜜でもある」であるが、この場合も一方のみを真として選ぶことができない。
従って、選ぶことができないことを言えさえすればよいのなら、「……般若波羅蜜である、……非般若波羅蜜である、のいずれでもない」と言うより、「……般若波羅蜜でもあり、……非般若波羅蜜でもある(=……般若波羅蜜とも説かれた、……非般若波羅蜜とも説かれた)」と言うほうが分かりやすくてよい。こうして『金剛般若経』の上掲の句の前半が成立する。
後半「それゆえ般若波羅蜜といわれる」がまた難解である。「それゆえ」の意義が分からない。「それにも拘わらず」ではないかとさえ思いたくなる。
これについては私はこう考える。「それゆえ」でよい。「仏説は般若波羅蜜でもあり、非・般若波羅蜜でもある」が許されるなら、「般若波羅蜜」と「非・般若波羅蜜」は同じことになる。したがってどちらか一方をいえばよい。それならば分かりやすいほうの「仏説は般若波羅蜜である」がよい。
この私の説明は詭弁のようにみえるだろう。しかしこれは言葉の限界、言葉の本質によるものである。言葉は人間が生活の便宜のために編み出したもので、真理を述べるためのものではない。『維摩経』によると、菩薩たちが「不二」(宇宙は有限でもない無限でもない、等)について言葉を駆使して説明しあった。それを受けた文殊菩薩は「言葉を離れることが不二である」といい、残る維摩居士に説明を求めた。維摩は沈黙したままであった。それを見た文殊は「すばらしい、あなたが最もよく不二を説明した」と称えた。
ここで注意すべき点は、ただの沈黙は白痴の沈黙と変わらないということである。維摩の沈黙が生きているのは、沈黙の前に菩薩たちの言葉による説明があったからである。
やはり言葉は必要である。ナーガールジュナは『中論』でいっている。「世俗(vyavahāra)に依らずしては真理を伝えることができない。真理に至らずしては涅槃に至ることができない。」(観四諦品・第10偈)。注釈者ピンガラは、羅什訳によれば、「世俗とは言説のことである」といっている。
真理というものは分かたれ得るものではない。しかし真理を言葉で説明しようとすると、どうしてもそこにいったん分ける作業が必要になる。それからまとめる作業が必要になる。両作業のあいだにカントのいう「余計なもの」が入ってくるのである。このことに気づいているかいないかが、真理を捉え得るか得ないかの分れ目となる。仏陀は言葉のこのような本性を弁えた上でならよいと考えて言葉(「般若波羅蜜」)を用いたのである。これが「それゆえ」の意味である。
維摩経の「二」が示唆するように、言葉の本質は世界を二分することである。人間は己のとるべき行動を選択し易くするために、世界を二分することを覚えた。例えば「りんご」という言葉で世界を「りんご」と「りんごならざるもの」に分ける。そしてりんごを採るか採らぬかを決める。「分けて見る」というこの行為はあくまでも人間の営為にすぎず、物自体の与り知らぬことである。
西洋論理学(アリストテレスの伝統を受けつぐ論理学)は『金剛般若経』の論理は論理でないというだろう。しかし、『金剛般若経』はでたらめをいっていない。言葉について考えるひとにとっては筋が通っている。
では西洋の論理と『金剛般若経』の論理はどこが違うのか。論理とは言葉の規則である。西洋論理学は言葉の結合の仕方を考えるだけで、言葉そのものを考えること(4)がない。『金剛般若経』はそれを考え、言葉に潜む罠に気づいている。したがって、その言葉づかいは異色のものとなる。それは言葉の否定を含むが、これも論理のうちである。両論理の違いを示すために鈴木大拙は後者を「即非の論理」と呼んだ。
〈注〉
(1)このくだり、既存の邦訳ではほとんど理解できない。これについては『東海大学名誉教授会年報』2018に発表予定の拙稿を参照されたい。
(2)a- と na の違いの重要性を立川武蔵氏が説明している。阿部慈園編『金剛般若経の思想的研究』春秋社、所収、「『金剛般若経』に見られる「即非の論理」批判」p.108
(3)和訳には梵原文にない「般若」を補う。そうでないと逆説の形式にならないからである。
(4)カントはそこに限りなく近づいている。かれのいう「アンチノミー」は仏教の「戯論」に相当しよう。ウィトゲンシュタインへの私の言及については『年報』2010参照。