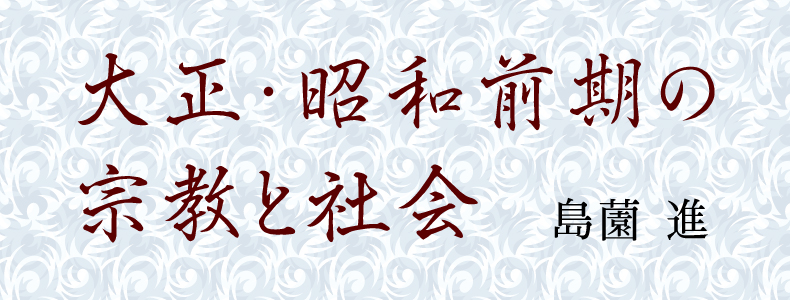第1回 明治天皇崩御と国家神道の新たな展開
「ある新しい宗教の発明」(1912年)
近代日本の宗教史を研究してきたが、大正時代から昭和前期、つまり敗戦までの時期をどう捉えるかが難問である。1912年から45年までの33年ほどの間だが、変化が激しかった。日本社会の都市化が進み、社会構造が複雑化していく時代だから、多面的に捉えざるをえないのは当然だ。たとえば、新宗教の発展は顕著だった。他方で伝統的な宗教行事は行われなくなっていくものも増えた。また、高等教育を受けた者の中には、キリスト教や親鸞の思想に親しむ者が少なくなかった。
神道、伝統仏教、キリスト教、新宗教、民俗宗教と分けて、それぞれについて見ていくと、それなりにどのような変化が生じたのかが分かる。それらについては、まとまった叙述がなされてきた。だが、それらを関連づけながら、日本の宗教に全体としてどのような変化があったのかと問われると、答え方が難しい。たとえば、この時期に日本社会の世俗化が進んだのかという問いに対する答えは多様にならざるをえない。
全体像が描きにくい理由はいろいろあるだろうが、最大のものは天皇崇敬や「国体」思想の評価という問題だろう。この天皇に関わる思想や実践のシステムを宗教として捉えなくては、大正・昭和前期の日本の宗教を理解することは困難である。これが私の立場だ。そこで、まずは大正期の天皇崇敬について見ていきたい。そこで時間を遡って、明治から大正への転換の年、1912年に目を止めてみたい。
明治時代の38年間、日本に滞在した日本研究者、バジル・ホール・チェンバレン(Basil Hall Chamberlain, 1850〜1935年)は、明治から大正への転換の年、1912年に「ある新しい宗教の発明」(The Invention of a NewReligion)という論文を公刊した。ここで新宗教とよばれているものは、神道の資源を引き継ぎながら新たに作り上げられた天皇崇敬のシステムを指している。1983年にエリック・ホブズボウムとテレンス・レンジャーが刊行した『創られた伝統』(紀伊国屋書店、1992年)は、近代の国民国家の儀礼を取り上げて「伝統の発明」(invention of tradition)の語を広めたが、チェンバレンの「ある新しい宗教の発明」はそれを先取りするような捉え方だ。
チェンバレンは新たに形成されてきた「ミカド崇拝」や「日本崇拝」があたかも古代に由来するものであるかのように装っていることに注目している。この捉え方の先駆性を指摘するタカシ・フジタニは、『天皇のページェント――近代日本の歴史民族誌から』(日本放送出版協会、1994年)にチェンバレンの論の一節を抜き書きしている(4ページ)。
いかなる製品もその材料を、また、いかなる現在もその過去を、それぞれ前提としてもっている。しかし忠誠・愛国という二〇世紀の日本の宗教はまったく新しい。というのも、その宗教のなかで以前から存在する考えがふるいにかけられたり、変形されたり、新規に組み合わされたり、違った用途に使用されたり、新しい重心を見出したりしたからである。新しいばかりか、未完成でもある。それはまだ政府の指導者たちの手によって、彼らの、さらには国民全体の利益となるべく、意識的もしくは半意識的に作り上げられる過程にある。
フジタニは明治時代の後期にこの「新しい宗教」が形を整えていく過程について、興味深い考察を行った。だが、今、私が関心を向けようとしているのは、その後の展開である。明治天皇の生涯という作品が完成されたとき、この「新しい宗教」は新たな段階に入ることになる。
1912年の集合的沸騰と「聖徳」
この年の7月30日に明治天皇は崩御するが、その葬儀の日、9月14日に乃木希典夫妻は自らその命を絶った。その年の11月には、宗教学者の加藤玄智が『神人乃木将軍』(菊地屋書店)という書物を刊行している。その末尾の一節は以下のとおりだ。
既に誠と云ふことが、明治天皇陛下の治国安民の根本的御精神であつて、其の御精神通りに、誠の権化、誠の化身とも謂ふべき乃木将軍を御養成遊ばすに至つた 明治天皇の御盛徳は如何に高大でありましたか、実に申すも可畏次第であります。 先帝陛下にして斯の如き御盛徳のありました為めに、将軍の如き、至誠の化身権化とも謂ふべき人が出たことと思ふのであります。将軍が忠義の死に依つて 先帝陛下の御盛徳を敬慕し奉ることのよすがが益々鮮明になり多くなつたことを有難く思ひまして、此の点からも将軍の死に無限の感謝をささげる次第であります。此点より見ましても将軍の死や是れ尋常一様の自殺殉死でなくして、真に耶蘇十字架の磔刑と同じく、義死であり、忠死であり、献身的犠牲的の死であると云はなければなりませぬ。(204―205ページ)
大正元年に「神人」を讃え、また「神人」が誠を捧げた天皇を讃えるこのような書物が刊行されたことは、宗教言説の歴史という面からも興味深い。チェンバレンは明治天皇の死と乃木希典の殉死をめぐる日本の国民の「集合的沸騰」(エミール・デュルケム『宗教生活の原初形態』岩波書店、原著、1912年)を知る前に「新宗教の発明」について語っていた。だが、チェンバレンが注目した「新しい宗教」と、加藤玄智が注目した乃木の「誠の化身」の宗教性がともに天皇崇敬を基軸としたものであることはまちがいない。
加藤玄智の『神人乃木将軍』の発行日は1912年11月1日となっているが、その直後の11月3日「明治聖帝天長の大節」に、加藤の尽力によって明治聖徳記念学会が設立されている。戦後は休会となったが、1975年「加藤玄智博士記念学会」が立ち上がり、1988年にそれを継承して再発足している。そのオフィスは明治神宮内にあり、現在、研究例会を行い、『明治聖徳記念学会紀要』を刊行している。再発足以前は、『神道研究紀要』と題されていたものである。
この明治聖徳記念学会の設立趣意書には、次のように記されている。
時偶々 明治聖帝の登遐に遇ひ奉り全国民を挙げて中々の至情禁ずる能はざるものあり、貴賤老少各その分に応じて争ひて、哀悼の赤誠を捧ぐ、是れ我等亦聖帝洪恩の万一に酬い奉らんとする微衷、こゝに新に明治聖徳記念学会なるものを組織し、内に在りては、深く日本の精神的文明を研究して能くその科学的の精緻透徹を致さんと期すると同時に、外に向ひては、その研究結果を内外文の紀要に公表して、彼れ外人をして我日本の真相を会得せしむるに至るの一助たらしめんことを切望して已まざる所以なり
「登遐」は「遠い天に登る」という意味で天子の崩御を指す言葉だが、滅多に用いられないこうした言葉を用いることで亡くなった天皇の神聖さがことさらに強調されている。「聖帝」、「聖徳」の語も天皇の神聖さを印象づける用語である。先に引いた『神人乃木将軍』では、「御盛徳」となっていたが、これは講演筆記のために「盛」の字が用いられたもので、加藤玄智は「聖徳」を意味していたと思われる。
天皇の聖徳論の由来
「聖徳」という言葉は現代日本人にはやや縁遠くなってしまっている。「しょうとく」と読んで聖徳太子を思い起こす人は多いと思うが、明治天皇と結びつけて考える人は少ない。だが、明治神宮外苑に親しみのある人なら、そこに「聖徳記念絵画館」があるのを知っていることだろう。これは明治天皇の生誕から崩御までの出来事を、「画題」の年代順に前半を日本画40枚、後半を洋画40枚の壁画で展示したもので、明治神宮の造営に連動して企画され、1926年にできあがったものだ。
大正天皇や昭和天皇について「聖徳」という語を付して語ることはあまりない。ということは、天皇の聖徳を讃える文化は明治天皇と皇后に対してとくに起こったユニークな現象ということになる。そういえば明治神宮は造営されたが、大正神宮や昭和神宮は造営されていない。おそらく平成神宮の造営もないだろう。ならば、明治天皇は特別に尊い天皇であり、神宮が造営されたほどだから「聖徳」が讃えられたのも不思議ではないかもしれない。
では、明治天皇の聖徳についての語りは、いつ頃始まり、どのように広められていったものなのだろうか。明治期から大正期にかけて生じた「新宗教の発明」の経過を知るためには、この問いへの答えが大いに役立つだろう。
佐藤一伯氏の『明治聖徳論の研究――明治神宮の神学』(国書刊行会、2010年)は、まさにこの問いに答えてくれる重厚な研究書である。佐藤氏によると、ある時期から「聖徳録」やそれに類する題を冠した書物や雑誌特集などが刊行されるようになり、次第に数が増えていく。天皇だけではなく皇后についても似たようなことが起こる。「聖徳」「至誠」「聖恩」「叡聖文武」(皇后は「慈愛荘婉」)「宸襟を悩ます」「一視同仁」などの語で天皇皇后の徳を讃える例はそれ以前からあったが、「聖徳録」とよべるようなまとまりをもった叙述の最初の例は、1891年11月の『萩の戸の月』である。これは新聞『日本』の附録として刊行されたもので、16ページの特集だった。
「萩の戸の月」というのは、1890年の御製(天皇の和歌)に「萩の戸の露に宿れる月かげはしづか垣根もへだてざるらむ」とあるのに拠ったものだ。「萩の戸」は清涼殿にある御局の名で、広く宮中の庭の意で用いられている。この歌の意義を、「一視同仁の御心、いともかしこし」と紹介されている。明治天皇は「萩の戸の月」の静かな光が「へだてがない」というところに、民の生活の安らかなことを願う、あるべき天皇の姿を見たのだろう。『萩の戸の月』の書き手は、その歌を明治天皇の仁慈への意思(大御心)を表すものとして受け止めている。
『萩の戸の月』は1890年の天長節を奉祝するための附録として企画されたもので、10日ほど前から掲載されていた予告には「此の附録は畏くも 今上陛下の乾徳に関する御事の一斑を記し奉りたるもの、世人と共に永く記臆して聖明の代に生れたるの幸福を祝せんとの微意に出づ」と述べられていた。明治天皇崩御のおよそ22年前のことである。
『春秋』2016年10月号