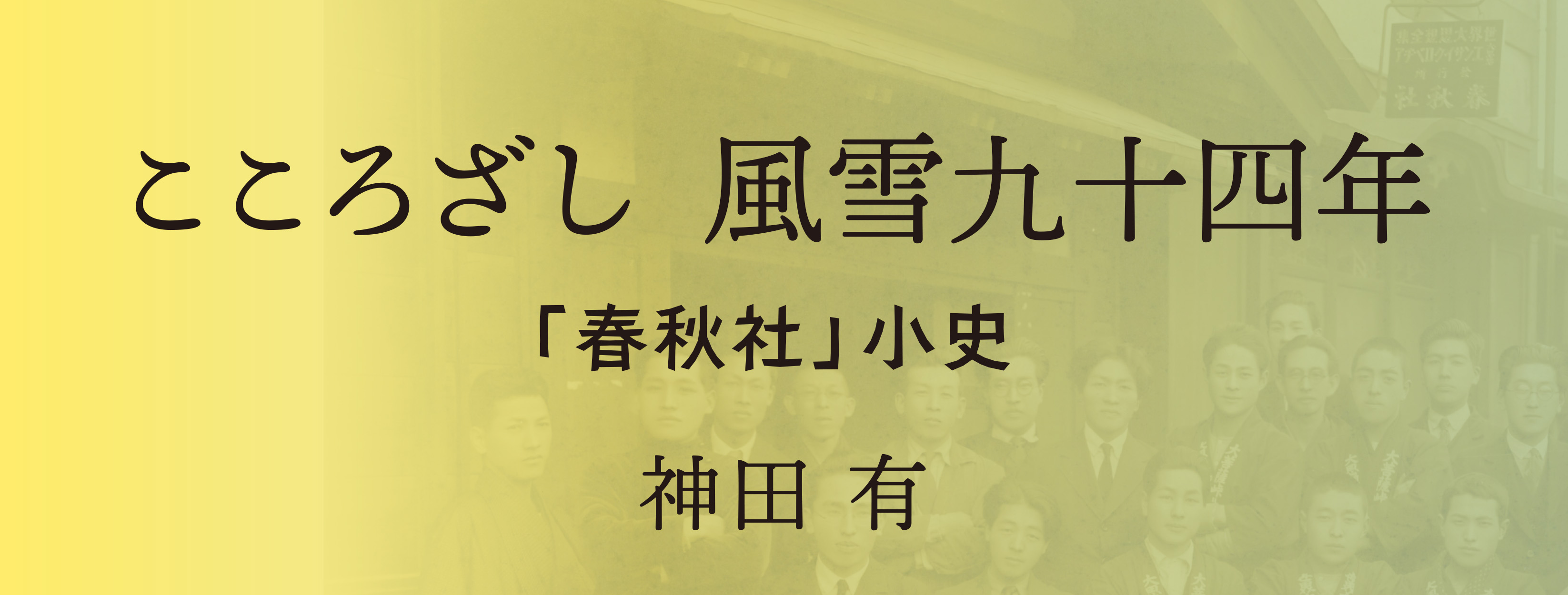「春秋社」小史1
NHK総合テレビ「ファミリーヒストリー」(2020年4月27日放送)にて明かされた、いま最も注目される講談師・神田伯山(本名・古舘克彦)氏と小社との意外な関係。創業者の神田豊穂を祖父にもつ小社現社長・神田明と、同じく豊穂の孫である神田有氏(この連載の執筆者)も番組内に登場。神田豊穂が伯山氏の曽祖父にあたる古館清太郎を誘って春秋社を立ち上げたことが語られましたーー
この記事は、2012年にPR誌『春秋』にて連載された、春秋社の歴史をふりかえるエッセイに加筆修正をしたものです。2018年に創業百年を迎えた小社の草創のときを今あらためて振り返ります。
はじめに
根っからの本好きな私は、暇さえあれば書店巡りをしている。各店の書棚を見て驚くのは、中小出版社から刊行された書籍の多さである。果たして今後、この中で何社が生き残れるか。そう考えるたびに、前途はかなり厳しいことが予想される。
出版業界に少しでも関心がある方ならお分りと思うが、こうした厳しい出版状況の下、典型的な中小出版社である「春秋社」が今年「創業九十四年」を迎えるということは、なんとも喜ばしいことである。
本来なら、立派な小史が出されてもよいはずだが、それが叶わないのは主に二つの大きな理由による。一つには、昭和二十年(一九四五)三月十日のB29による東京大空襲によって、社屋、在庫はおろか、貴重な印刷原版(紙型)や重要書類のことごとくが灰燼に帰してしまったこと。二つには、呉服橋時代の春秋社を知る人は、神田明現社長と私を除き、全員が鬼籍に入られたことである。
今後、本格的に『春秋社史』がまとめられるにあたって、少しでもお役に立てるのではないかと思い、当時を知る関係者の貴重な証言を蒐集しつつ、資料の読み直しをおこなってみた。幸運なことに、私はかつて春秋社の顧問であった柳田泉先生の知遇を得(先生宅と拙宅が隣どうし)、五十年近く公私共にお世話になった。明治大正文学史、特に島崎藤村についてご指導を賜り、また春秋社創設当時のことについても何かとお話をいただいていたのである。また、私の母は、昭和七年(一九三二)に日本女子大学国文科を卒業後、春秋社に入社。私が生まれるまで春秋社の仕事をしていたこともある。さらに、春秋社の創業事情については、木村毅や直木三十五らが断片的に言及している資料も併せて参考にした。
(一)創業のころ
春秋社の図書目録やホームページの社史沿革欄には、「当社は大正七年(一九一八)八月二 十二日、神田豊穂(筆者の「祖父」、以下、豊穂と記す)、加藤一夫、植村宗一(直木三十五、以下、直木と記す)らによって創業された」とあるが、これは法的な登記上のことにすぎない。実質的には「春秋社は神田豊穂と古館清太郎によって創設された」と記すべきと思われる。
古館は早稲田大学を卒業後、謡曲の本を出していた「わんや」に『謡曲界』の編集助手として採用され、当時、総編集長をしていた豊穂の片腕として仕事を共にした。文学青年どうしとしてウマがあい、よく文学談義を交わしていたという。
大正七年の夏のある日、豊穂が真剣な顔で。
「古館君、僕は出版業をやろうと思うのだが」と切り出した。古館は「いいですね、僕もお手伝いしますよ」と即答。豊穂の背中を追す形となり、ここに創業が決意されたという次第である。
古館は早速、「わんや」に辞表を提出、退職金は総て春秋社の出資金に回し、すぐさま同志集めを開始した。まず同郷の先輩でトルストイアンの加藤一夫を呼び込み、ついで直木も加わった。直木を誘う加藤の言がまた面白い――
「俺の早稲田の同級に、直木といって稀代の多智多策の奴がいるから、そいつを仲間に引っ張ってこよう。卒業していないのに卒業したといって親をだました奴だから用心せねばならぬが、きっといい案を出す」と。さらに「わんや」に資金を提供していた中尾文次郎も加わり、メンバーが揃った。
そこでまず、事務所を借りようということになり、日本橋区本材木町一丁目の土蔵造りの家の三階(六畳二間ほど)に社を構えた。組織としては、社長は豊穂、会計担当専務は中尾、編集担当専務は古館であった。
会社としての体裁が整ったところで、「第一に出版物は何にしようか」との議論になった。すかさず直木が『トルストイ全集』を提案。トルストイの心酔者だった豊穂はもとより、元々トルストイアンの加藤も賛同し、処女出版として『トルストイ全集』に挑むこととなった。
「全集」を出す以上、監修者と翻訳者を揃えねばならない。全員が走り回り、監修者として内田魚庵、片山伸、昇曙夢の三人に依頼し、相当数の翻訳者も確保した。作業は進み、いよいよ発刊の時を迎えることに。
こうして『トルストイ全集』の新聞広告が東京日々新聞の朝刊を飾った(大正八年九月十二日付)。大胆にも「予約会員募集」という乾坤一擲の賭けに出たのである。
広告が出てから、二、三日間、春秋社の社員は息を殺し、様子を窺っていた。すると三日くらいして事務所に予約申し込みが殺到、てんやわんやの騒ぎとなった。賭けは大吉と出たのである。
反響は想像を絶し、当時の出版物は初刷五百部というのが常識だったから、三千部を越す申込みは、社内の誰もが信じられぬ思いであったという。予約金は上製本が三円、並製本が二円だから、約八、九千円の売上を確保したことになり、幸先よいスタートを切った。
ところで、春秋社の創設当時の資本金はいくらぐらいだったのだろうか。公式なデータは全くないが、豊穂がこつこつと貯めた資金と「わんや」の退職金。プラス古館の退職金。そして、当時「わんや」に資金を出していた第一銀行常 務の中尾文次郎や、「わんや」の主人、村山金 吾も出資者の一人になろうと約束してくれた。 さらに、豊穂の中学時代の同級生、渡瀬雅太郎と謡曲の弟子で金融業の井岡友造らも出資者となる。
つまるところ出資金は、柳田泉先生によると「二千なんぼ」、後に春秋社の編集長になる木村毅によれば「どうやら五千円くらい」とのことだから、五千円前後と考えて間違いないようだ。新聞広告を数回打てば消えてしまうほどの過少資金だけれども。
ともあれ、『トルストイ全集』は当たりを勝ちえ、予約者はさらに増え、合計で五千部を越したのではないだろうか。
この全集が、なぜかくも多数の支持を得たか。ひとつには、外的な状況(時代背景)がある。NHKテレビ・ドラマでもお馴染みの司馬遼太郎の『坂の上の雲』を読むと良く分かるのだが、明治維新以来、日本人のロシアに対する関心は非常に高かった。日露戦争は日本の勝利に終わるが、大正六年(一九一七)十月のロシア革命とその余波(シベリア出兵等)へと人々の好奇のまなざしが続いていたのである。『トルストイ全集』の異常な売れ行きも、こうした社会情勢とけっして無縁ではないように思われる。時代状況と読書欲の関わりはいつの時代でも同じなのであろう。
しかしなにより注目すべきは、トルストイ文学の絶大な影響力に根ざしていると言ってよいだろう。その文学的価値は言うまでもなく、そこに込められた思想や人間観がわかりやすい形で広く庶民の心を捉えることもあった。
時代は遡るが、大正三年(一九一四)、帝国劇場で、島村抱月の率いる芸術座によってトルストイの『復活』が上演された。このときカチューシャに扮した松井須磨子がうたった劇中歌「カチューシャの唄」が全都の人気を呼び、やがて全国に拡がった。
「カチューシャかわいや、わかれのつらさ、せめて淡雪とけぬ間に、神に願いをララかけましょか……」(島村抱月・相馬御風作詞、中山晋平作曲)。
この歌は、「流行歌」としてステージで歌われた最初であり、須磨子は歌う女優の第一号であった。
当時の出版界では、新潮社が『トルストイ全集』を企画しており、手はじめに中・小編ものを二、三冊出版していた。そのうえ『トルストイ研究』という小冊子までも出して、トルスト イ作品の翻訳出版のPRを始めていたのだった。他社は、同業者の仁義(?)として当全集には手を出さなかった。
そこへ、新参者の春秋社が強引に割り込んできたのだから、「新潮社はとんびに油揚げをさ らわれた」と業界人の間でささやかれたという。
(二)豊穂と直木の確執
『トルストイ全集』の大成功でいちやく出版界を賑わした春秋社だが、出版の志はひとつにまとまっていくことなく、さまざまな確執・離反を生むことになる。
まず豊穂の第一のパートナーだった古館清太郎が春秋社を去る。理由は、出版社運営の方向性をめぐる見解の相違だった。古館は、「少ない資本金で始めたのだから、思い切って派手にやろう」と主張。それに対し、豊穂は「駄目だ、状況はそう甘くはない、手堅くやろう」と反論したのである。
ついで加藤一夫が去る。加藤は自分を春秋社に呼んでくれた古館が退社したので居づらくなったのであろうか。かくして春秋社は豊穂と直木の二本立てで、業務を進めることになった。ちなみに、事務所は本材木町から麹町三番地に移転。
さて、豊穂と直木の二頭立ては長続きするわけがなく、ほどなくして二人は大きな分岐点を迎えることになる。原因は直木の遊蕩である。直木は酒はあまり嗜まなかったが、芸者遊びにうつつを抜かし、しばしば人力車を春秋社の入口に付けては歓楽街に出かけた。
当時の出版業界と言えば、日販、トーハンといった取次店はなく、本屋に直接集金に出かけるというシステムだったから、社員にとってそれは重要な仕事であった。直木は関西方面に出かけると、必ず京都で派手な芸者遊びをし、挙げ句の果て、豆枝(まめし)という芸者とただならぬ仲になり、東京に呼び寄せるという滅茶滅茶な有様だった。
一方、豊穂と言えば幼いころから丁稚奉公をし、苦学のすえ麻生中学を卒業、「わんや」に入社。一途に出版業を身に付けてきたという刻苦勉励の士であり、直木の遊蕩には腹の虫が治まらなかったのである。
二人は大喧嘩の末、口も利かなくなった。その後、豊穂は「直木には金を貸さない」と断言。そこで、直木は冬夏社を興すことになる。一つの事務所に二つの出版社が存在するという異常な事態となり、春秋社の社員は右側の入口を使い、冬夏社の社員は左側の入口を使用するといった変則状態が続く。
冬夏社は、鷲尾雨工が全額出資して作った出版社だが、当時鷲尾は平尾賛平商店に勤めており、取り敢えず直木を専務に据え、様子をみていたわけである。直木が豊穂と決裂後、本格的に出版業務を行うことになったので、鷲尾は平尾賛平商店を退社し、冬夏社の仕事に専念することとなった。
直木は性懲りもなく、ここでも勝手気ままな生活を続ける。二、三冊の本を出すが、いずれも失敗に終わる。
豊穂は新しい事務所に移転することを決め、鷲尾にこう伝えた。
「直木とは一緒にやってゆけんから別れる。 君はぜひ僕の方に来てもらいたい。直木なんぞのそばにいたら、君はとんでもない目に遭うぞ。君のためを思って言っているのだ。あいつを追い払ってしまっちゃえ。どうだ、一緒にがっちりやって行こうじゃないか……」
鷲尾にとって豊穂の忠告はありがたかったが、当時の鷲尾はとてもその気になれなかったようだ。豊穂と行動を共にするには直木と絶縁しなければならない。直木を冬夏社から追うことは事務的には何の苦もなしである。しかし……。
「早稲田以来の長い友誼を考えると、僕には絶対に出来なかった」と、鷲尾は述べている。
ところが、事態は豊穂の予想した通りになってしまう。
鷲尾の直木に対する思いが覚める時が来る。鷲尾は『人間直木の美醜』という著作の中で直木に対する憤懣をぶちまけている。
僕はいつかは、僕のために彼の誠意をみせて、彼に対する僕の払った犠牲に報いてくれるに相違ないと、長い夢を見続けて、まだ覚めやらずにいたのであった。
だが、さすがに長い夢もついに覚める時が来た。直木は「人間社」という名で「人間」という雑誌を出すことになった。社中に社を作るのに社長の僕には諒解なしに冬夏社の金でやり出したのだ。(中略)もうその時は、冬夏社に金はほとんどなかったから、立ちゆく筈がない僕は慄然とした。
やがて冬夏社は倒産、鷲尾は膨大な負債を抱え、鷲尾家の財産を食い潰してしまい、牛込矢来町で、「江戸屋」というおでん屋を母や妻と営みながら、こつこつと文筆作業を続けるのであった。
(『春秋』2012年4月号)